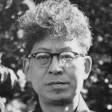精選版 日本国語大辞典 「中野重治」の意味・読み・例文・類語
なかの‐しげはる【中野重治】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「中野重治」の意味・わかりやすい解説
中野重治
なかのしげはる
(1902―1979)
詩人、評論家、小説家。福井県坂井郡高椋(たかぼこ)村(現坂井市丸岡町地区)の農家に明治35年1月25日生まれる。金沢の旧制四高で窪川(くぼかわ)鶴次郎らと詩作を始める。そのころ室生犀星(むろうさいせい)を知り、以後親しむ。1924年(大正13)東京帝国大学独文科に入学。翌年同人誌『裸像』を中平解(なかひらさとる)らと、26年からは『驢馬(ろば)』を窪川、堀辰雄(たつお)らと刊行するが、一方、25年夏には林房雄らを通して新人会に入会、翌年マルクス主義文芸研究会(マル芸)結成、しだいに左傾を深める。『裸像』『驢馬』に書いた詩が『中野重治詩集』(1931)の中心であるが、それらは、「お前は赤ままの花やとんぼの羽根を歌うな」と、自分の内部にあるものを深くみつめると同時にそれを激しく否定したところに成立した。
1927年(昭和2)東大卒業。その前年の1926年11月、日本プロレタリア芸術連盟(プロ芸)にマル芸の全員が参加、中野は中央委員に選ばれるが、福本イズムに影響された中野らのラディカリズムが原因で、1927年6月、青野季吉(すえきち)、葉山嘉樹(よしき)、林、蔵原惟人(これひと)らはプロ芸を脱退。うち林、蔵原ら共産党支持派は1928年3月、プロ芸とふたたび合体して全日本無産者芸術連盟(ナップ)を結成、論議はナップ内の中野対蔵原の芸術大衆化論争に持ち越された。「大衆の求めているのは芸術の芸術、諸王の王なのだ」と書いて中野は蔵原の二元論に対立する。これら『芸術に関する走り書的覚え書』(1929)に収められた評論群がこの期の代表作である。1931年共産党入党。1932年コップ(日本プロレタリア文化連盟)大弾圧で検挙投獄され、1934年に執行猶予で出所。以後敗戦までの中野の文学的闘いは、「転向」した自己を見据え、戦争につれて流されてゆく現実のなかで、動かない「もの」と人間精神とのかかわりを追究することにあった。こうした緊張の所産が『村の家』(1935)、『汽車の罐焚(かまた)き』(1937)、『歌のわかれ』(1939)、『空想家とシナリオ』(1939)の中編・短編であり、『斎藤茂吉ノオト』(1940~42)、『「暗夜行路」雑談』(1944)であった。
敗戦後まもなくの1945年(昭和20)11月共産党に再入党。新日本文学会を創設して中心的な働き手となる。1947~50年参議院議員として活躍。共産党の「50年分裂」の際は「国際派」の側にあり、政治主義に対して文学運動を守り抜く。1964年、党運営の官僚化を批判して除名される。『朝鮮の細菌戦について』(1952)をはじめとする透徹した多くの評論、『五勺の酒』(1947)などの現実を鋭くえぐった短編、『むらぎも』(1954)、『梨(なし)の花』(1957~58)、『甲乙丙丁』(1965~69)の豊かな長編世界が戦後の仕事。昭和54年8月24日没、郷里の「太閤(たいこう)ざんまい」の土に帰る。1983年(昭和58)丸岡町にその蔵書を収めた中野重治記念文庫ができ、毎夏、東京で記念集会が行われる。
[満田郁夫]
『『中野重治全集』全28巻(1976~79・筑摩書房)』▽『杉野要吉著『中野重治の研究 戦前・戦中篇』(1979・笠間書院)』▽『木村幸雄著『中野重治論』2冊(1979・桜楓社)』▽『桶谷秀昭著『中野重治 自責の文学』(1981・文芸春秋)』▽『満田郁夫著『増訂 中野重治論』(1981・八木書店)』▽『満田郁夫著『中野重治の茂吉ノオト』(1984・童牛社)』
百科事典マイペディア 「中野重治」の意味・わかりやすい解説
中野重治【なかのしげはる】
→関連項目荒正人|臼井吉見|亀井勝一郎|蔵原惟人|佐多稲子|戦旗|転向文学
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
改訂新版 世界大百科事典 「中野重治」の意味・わかりやすい解説
中野重治 (なかのしげはる)
生没年:1902-79(明治35-昭和54)
詩人,評論家,小説家。福井県坂井郡高椋(たかぼこ)村の自作農兼小地主の家に生まれる。金沢の四高で窪川鶴次郎らと知り,短歌,詩,小説の習作を始める。そのころ室生犀星を知り,以後親しむ。1924年,東大独文科に入学。翌年同人誌《裸像》を中平解らと出し,26年からは《驢馬》を窪川,堀辰雄らと刊行するが,一方,25年には林房雄らを通して新人会に入会,翌年マルクス主義文芸研究会(マル芸)結成としだいに左傾を深める。《裸像》《驢馬》に書いた詩が《中野重治詩集》の中心である。27年東大卒業。その前年,日本プロレタリア芸術連盟(プロ芸)にマル芸の全員が参加し,彼は中央委員に選ばれるが,福本イズムに影響された中野らのラディカリズムが原因で,27年,青野季吉,葉山嘉樹,林,蔵原惟人らはプロ芸を脱退。うち林,蔵原ら共産党支持派は28年,プロ芸と合体して全日本無産者芸術連盟(ナップ)を結成。論議はナップ内部の中野対蔵原の〈芸術大衆化論争〉(芸術大衆化論)に持ち越される。中野はプロ芸,ナップの指導者として,評論を多く書いたほか,《春さきの風》(1928)などの小説を書いている。31年,共産党に入党。32年,日本プロレタリア文化連盟(コップ)大弾圧で検挙,投獄され,34年に執行猶予の判決で出所。以後敗戦までの彼の文学的戦いは,〈転向〉した自己を見据え,戦争につれて流されて行く現実の中で,動かない〈もの〉と人間精神とのかかわりを追究することにあった。こうした緊張の所産が《村の家》(1935),《汽車の缶焚き(かまたき)》(1937),《歌のわかれ》《空想家とシナリオ》(ともに1939),《斎藤茂吉ノオト》(1942)であった。敗戦後間もなく共産党に再入党。新日本文学会を創設して中心的な働き手となる。47-50年,参議院議員として活躍。共産党の〈50年分裂〉の際は〈国際派〉の側にあり,政治主義に対して文学運動を守り抜く。64年,党運営の官僚化を批判して除名される。《朝鮮の細菌戦について》をはじめとする多くの透徹した評論,《五勺の酒》(1947)などの現実を鋭くえぐった短編,《むらぎも》(1954),《梨の花》(1957-58),《甲乙丙丁》(1965-69)の豊かな長編世界が戦後の仕事としてある。
執筆者:満田 郁夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
新訂 政治家人名事典 明治~昭和 「中野重治」の解説
中野 重治
ナカノ シゲハル*
- 肩書
- 参院議員(共産党)
- 別名
- 筆名=日下部 鉄(クサカベ テツ)
- 生年月日
- 明治35年1月25日
- 出生地
- 福井県坂井郡高椋村(現・丸岡町)
- 学歴
- 東京帝国大学独文科〔昭和2年〕卒
- 経歴
- 四高時代から創作活動をし、東大入学後は大正14年「裸像」を創刊。東大新人会に参加し、林房雄らと社会文芸研究会を結成、翌15年マルクス主義芸術研究会に発展した。この年「驢馬」を創刊し「夜明け前のさよなら」「機関車」などの詩を発表。昭和2年「プロレタリア芸術」を創刊、3年蔵原惟人らと全日本無産者芸術連盟(ナップ)を結成し、プロレタリア文学運動の中心人物となる。6年日本共産党に入党。7年弾圧で逮捕され、2年余りの獄中生活をする。転向出所後は「村の家」「汽車の罐焚き」「歌のわかれ」「空想家とシナリオ」などを発表。戦後は新日本文学会の結成に参加し、荒正人らと“政治と文学論争”を展開。また22年日本共産党から立候補して3年間参院議員として活躍。25年党を除名され、のち復党したが、39年別派を結成、再び除名された。22年「五勺の酒」を発表した後も小説、評論の部門で活躍し、30年「むらぎも」で毎日出版文化賞を、34年「梨の花」で読売文学賞を、44年「甲乙丙丁」で野間文芸賞を受賞。ほかに「中野重治詩集」「斎藤茂吉ノオト」「愛しき者へ」(書簡集 上下)「中野重治全集」(全28巻 筑摩書房)などがある。
- 受賞
- 毎日出版文化賞(第9回)〔昭和30年〕「むらぎも」 読売文学賞(第11回)〔昭和34年〕「梨の花」 野間文芸賞(第22回)〔昭和44年〕「甲乙丙丁」 朝日賞〔昭和52年〕「中野重治全集・全28巻」
- 没年月日
- 昭和54年8月24日
- 家族
- 妻=原 泉(女優) 妹=中野 鈴子(詩人)
出典 日外アソシエーツ「新訂 政治家人名事典 明治~昭和」(2003年刊)新訂 政治家人名事典 明治~昭和について 情報
20世紀日本人名事典 「中野重治」の解説
中野 重治
ナカノ シゲハル
昭和期の詩人,小説家,評論家 参院議員(共産党)。
- 生年
- 明治35(1902)年1月25日
- 没年
- 昭和54(1979)年8月24日
- 出生地
- 福井県坂井郡高椋村(現・丸岡町)
- 別名
- 筆名=日下部 鉄(クサカベ テツ)
- 学歴〔年〕
- 東京帝国大学独文科〔昭和2年〕卒
- 主な受賞名〔年〕
- 毎日出版文化賞(第9回)〔昭和30年〕「むらぎも」,読売文学賞(第11回)〔昭和34年〕「梨の花」,野間文芸賞(第22回)〔昭和44年〕「甲乙丙丁」,朝日賞〔昭和52年〕「中野重治全集・全28巻」
- 経歴
- 四高時代から創作活動をし、東大入学後は大正14年「裸像」を創刊。東大新人会に参加し、林房雄らと社会文芸研究会を結成、翌15年マルクス主義芸術研究会に発展した。この年「驢馬」を創刊し「夜明け前のさよなら」「機関車」などの詩を発表。昭和2年「プロレタリア芸術」を創刊、3年蔵原惟人らと全日本無産者芸術連盟(ナップ)を結成し、プロレタリア文学運動の中心人物となる。6年日本共産党に入党。7年弾圧で逮捕され、2年余りの獄中生活をする。転向出所後は「村の家」「汽車の罐焚き」「歌のわかれ」「空想家とシナリオ」などを発表。戦後は新日本文学会の結成に参加し、荒正人らと“政治と文学論争”を展開。また22年日本共産党から立候補して3年間参院議員として活躍。25年党を除名され、のち復党したが、39年別派を結成、再び除名された。22年「五勺の酒」を発表した後も小説、評論の部門で活躍し、30年「むらぎも」で毎日出版文化賞を、34年「梨の花」で読売文学賞を、44年「甲乙丙丁」で野間文芸賞を受賞。ほかに「中野重治詩集」「斎藤茂吉ノオト」「愛しき者へ」(書簡集 上下)「中野重治全集」(全28巻 筑摩書房)などがある。
出典 日外アソシエーツ「20世紀日本人名事典」(2004年刊)20世紀日本人名事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中野重治」の意味・わかりやすい解説
中野重治
なかのしげはる
[没]1979.8.24. 東京
小説家,評論家,詩人。第四高等学校を経て 1927年東京大学独文科卒業。在学中から室生犀星の影響を受けて短歌や詩への関心を深め,また,林房雄らとの交友によりマルクス主義に近づいた。 26年堀辰雄,窪川鶴次郎らと詩誌『驢馬 (ろば) 』を創刊,『夜明け前のさよなら』 (1926) ,『歌』 (26) などを発表。 28年ナップに参加,検挙投獄,転向,執筆禁止などを経て,第2次世界大戦後は民主主義文学者の結集に努力,新日本文学会の発起人となった。 47~50年日本共産党の参議院議員。 64年党の方針と対立して除名された。『中野重治詩集』 (35) ,小説『歌のわかれ』 (39) ,『むらぎも』 (54) ,『甲乙丙丁』 (65~69) ,評論『斎藤茂吉ノオト』 (40~41) がある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「中野重治」の解説
中野重治 なかの-しげはる
明治35年1月25日生まれ。大正15年堀辰雄らと「驢馬(ろば)」を創刊。日本プロレタリア芸術連盟やナップにくわわる。昭和6年共産党にはいるが,のち転向。10年の「村の家」は転向文学の代表的作品。戦後,蔵原惟人(これひと)らと新日本文学会を結成。20年再入党して22年参議院議員。同年の「五勺の酒」で天皇制と天皇の問題をえがく。39年党を除名された。44年野間文芸賞の「甲乙丙丁」は政治と文学の問題を追究した大作。昭和54年8月24日死去。77歳。福井県出身。東京帝大卒。作品はほかに「むらぎも」「梨の花」など。
【格言など】未練が老醜のはじまりではないだろうか(「五勺の酒」)
367日誕生日大事典 「中野重治」の解説
中野 重治 (なかの しげはる)
昭和時代の詩人;小説家。参議院議員
1979年没
出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の中野重治の言及
【芸術大衆化論】より
…28年にはこれをめぐって〈芸術大衆化論争〉が,その運動の主要な雑誌の一つたる《戦旗》誌上で,約半年にわたって行われた。中野重治はその6月号に〈いはゆる芸術の大衆化論の誤りについて〉を書き,通俗化・迎合・水うめ等によってプロレタリア芸術の大衆化をはかる傾向をはげしく論難し,芸術家としての頑固な進み方で大衆の真実に迫ることを要求した。これに対して,蔵原惟人がただちに批判して〈大衆の直接的アジ・プロの為の芸術運動〉も必要だとした。…
【甲乙丙丁】より
…中野重治晩年の長編小説。1965‐69年,《群像》に連載。…
【戦旗】より
…全41冊。28年3月の三・一五事件に抗するため,蔵原惟人らの前衛芸術家同盟と中野重治らのプロレタリア芸術連盟がその月のうちに合同し,結成したナップ(全日本無産者芸術連盟)の機関誌。それまでの蔵原らの機関誌《前衛》と中野らの機関誌《プロレタリア芸術》との合体であり,《文芸戦線》の社会民主主義的傾向に対して,共産主義芸術運動の展開をめざした。…
【ドイツ文学】より
…ヘルダーリンに心酔した伊東静雄を含め,日本浪曼派はドイツ文学から深い影響をうけているが,その一方,生田春月の訳編になる《ハイネ詩集》(1917)の意義も特筆に値しよう。中野重治や舟木重信のハイネ研究に受け継がれて,革命詩人としてのハイネのイメージが早くから築かれたからである。自由民権思想との関連でレッシングの劇作品や宗教論なども早くから翻訳紹介され,ドイツ文学の啓蒙主義的系譜もかなり日本に導入されていたが,国家主義的イデオロギーが強まるにつれて,それらは圧殺されていった。…
【中野重治詩集】より
…中野重治の全詩集。1931年ナップ出版部より刊行されるが発禁。…
【プロレタリア文学】より
…革命運動内の政治党派のせめぎ合いも激しくなり,青野たちは山川均を中心とする労農派支持に進み,蔵原たちはこれと対立した共産党の側に立った。当時共産党は非合法下の最前衛の党派で,三・一五事件などの大弾圧のなかでそれに屈せず活動していたので,本来,美的にも徹底的なものを追求する文学者は,中野重治をはじめとして多くの部分が共産党支持に向かい,三・一五事件直後にその弾圧に抗するようにして結成された全日本無産者芸術連盟(のち〈連盟〉が〈協議会〉に変わるが,略称はともにナップ。中野たちの日本プロレタリア芸術連盟(略称,プロ芸)と蔵原たちの前衛芸術家同盟(略称,前芸)との合体を中心に成立。…
【村の家】より
…中野重治の短編小説。1935年《経済往来》に発表。…
※「中野重治」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...