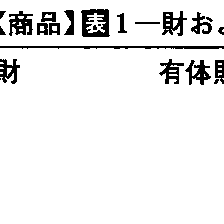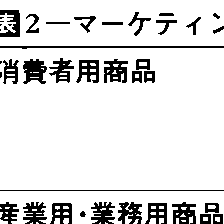商品(読み)ショウヒン(その他表記)commodity
精選版 日本国語大辞典 「商品」の意味・読み・例文・類語
しょう‐ひんシャウ‥【商品】
- 〘 名詞 〙 商売で売る品物。売買を目的とした財貨。あきないもの。
- [初出の実例]「且巨艦と雖とも岸上より直に商品を積ことを得べし」(出典:西洋聞見録(1869‐71)〈村田文夫〉前)
- 「生産者、卸売商人及び小売商人が売却したる産物及び商品の代価」(出典:民法(明治二九年)(1896)一七三条)
改訂新版 世界大百科事典 「商品」の意味・わかりやすい解説
商品 (しょうひん)
commodity
merchandise
Waren[ドイツ]
経済学上の商品
市場で交換されるもの,つまり売り買いの対象になっているものが商品である。今日の社会では,さまざまのものが商品として取引(商品化)されている。食料・衣料などの消費財,原料・機械などの生産財という形あるものはもちろん,運輸・保管,金融・保険,労働・娯楽などのサービス,さらには空気・水,知識・情報,土地,資本(株式)といったものにまで価格がつき売り買いされている。
しかし,このような社会でもすべてのものが商品になれるわけではない。たとえば,人身売買(人間の商品化)や売春(性の商品化),戸籍や国籍の売買(法的身分・資格の商品化)などは禁じられている(もっとも,法の目を盗んでこれらの売買が行われることはまれではない)。これらが商品化を禁じられているのは,社会の公序良俗を乱して社会生活の基盤をゆるがすことになるからである。しかし,ある社会の公序良俗の基準がどこにあるかは,その社会の伝統,慣習,道徳,価値意識,政治・経済状況などに依存する。したがって,種々の財・サービスのどこまでが実際に商品として売買されるかは,それぞれの社会によって異なるのである。たとえば,19世紀の半ばまでアメリカでは奴隷売買は正当な商品取引であった。また,社会主義経済では消費財は売買されるが,生産財はふつう売買の対象にはなっていない。あるものが商品となるかならないかは,当の社会のありようと深くかかわっているのであり,もともとからして商品であるというものはない。商品であることは,もの本来の性質によるのではなく,社会の中での取扱われ方による。つまり,商品は社会的な形態にほかならない。
産業社会と商品
産業社会が成立する以前においては,一社会の経済の中で商品経済の占める位置は部分的であった。つまり,財・サービスの多くのものは商品として売買はされなかった。なかでも,土地と労働は社会的・政治的な強い規制のもとにおかれており,一般に商品化されることはなかった。産業化以前の共同体的な社会では,土地と労働は政治・社会秩序の中心的要素をなしており,商品として売買されることは社会の体制を根本的にゆるがすことになったからである。土地と労働の商品化が法律的にも自由化されたのは,西ヨーロッパでも18世紀から19世紀にかけてのことにすぎない。商品経済は産業革命を経て経済社会の中心的システムとなり,現代へ通じる市場社会(資本主義社会)が成立した。ここでは,財・サービスの生産が商品として販売するために行われる一方,生産に必要な諸要素も商品として購入・調達される(商品による商品の生産)。このような生産様式は,土地と労働さえもが生産要素の一つとして商品化されることによってはじめて可能となった。労働者は労働力の対価である賃金を支払われて雇用され(労働力の商品化),その賃金で商品としての生活資料を購入することになる。市場社会は,このように生産的活動も消費的生活も商品によって成り立っている点に特徴があり,商品の法則・論理が大きな影響力・作用力をもつ社会である。
商品の論理
では商品の論理とは何か。商品には価値と使用価値の二つの要因がある。使用価値とは,商品となっているものの物理的な属性に基づく有用性のことであり,食物は空腹を満たし,衣服は身体を寒暑から保護し,住宅は雨露をしのがせるなどである。価値とは,それに対し,ものが商品という社会的形態をとることによってもつ商品としての価値のことであり,貨幣によって測られ価格という形で表されるものである。需要と供給によって変動する商品の価格が究極には何によって決定されるのか,つまり商品の価値が何によって規定されるのかという問題に関しては,古典派やK.マルクスのように生産に要する労働量にそれを求める労働価値説・客観的価値論と,C.メンガー,W.S.ジェボンズらにおけるように効用という心理学的事象から説明する効用学説・主観的価値論の系譜がある。今日では,労働時間や効用という特定の生理学的・心理学的実体に価値・価格を結びつけるのではなく,需要と供給からなる市場のシステマティックな相互作用によって価格が決定されるという均衡論的説明が一般的である。
しかし,商品の価値は,たんに物理的属性からくる使用上の価値でない以上,結局のところ,ものがその社会の中で与えられている社会的価値の一つの形態にほかならない。そのような価値は,慣習,伝統,生活様式,ものに付された社会的イメージなどからなるその社会の価値観念(価値体系)に従っており,このことは市場社会でも変わらない。商品の消費・生産,需要・供給の活動,企業の競争,政府の規制も実際には社会の価値観念に支えられ方向づけられて行われているのであり,だとすれば価格の形成もたんに需要と供給のメカニズムによるというのではなく,社会の価値観念に枠づけられ体系づけられている。たとえば,ブランド商品はブランド・イメージに商品としてのおもな価値があり,それが商品の品質を決め価格をも決めさせている。また賃金・所得の差異は現実には職種・職業や組織内での地位に対する社会的評価の差異に基づいているのである。
商品の物神性
商品経済においては,商品は生産者にとって利得の源であり,消費者にとって幸福の源である。マルクスのいうように商品はまさしく〈富の原基形態〉になっている。商品の種類や商品の価格は人々の最大の関心事であり,その変化が人々のさまざまの活動・心理をよび起こす。マルクスによれば,商品経済においては,社会的分業を形づくる労働と労働,人間と人間という本来の関係が物と物,商品と商品の関係によって覆い隠されてしまい,後者があたかも本質的関係であるかのように錯覚され,人々は商品の論理につかれたように行動する。彼は商品のこの魔力にも似た作用を商品の物神性(フェティシズム)と呼んだ(〈物神崇拝〉の項参照)。商品化がますます広がり深まっている現代の市場社会では,この傾向はなおさらといえる。ボードリヤールは,マルクスの考えを受けながらも,いまや商品の物神性は労働や使用価値といった実体をもち,それを隠すといったものではなく,イメージ・記号の差異のみからつくり出される商品の体系そのものの物神性であるとした。商品化が労働の生産物にとどまらず,あらゆる領域に広がることによって,商品の世界は分業や労働を覆い隠すというよりも,そうした過程とは実質的に無関係に独自の価値秩序を形づくり,人々を巻き込み動かすに至っているということである。
執筆者:杉村 芳美
商品学上の商品
本来の字義は〈商う品物〉という意味だが,今日ではそれよりも広い意味で使われている。商は章と冏(けい)の合字で,物事が明らかなこと。これが〈あきなう〉と同義になったのは,竇(あきなう。貨幣をさす貝に字義がある)の仮借として商が使われ, の字がすたれてしまったためである。商うとは,商人が営利を目的として行う売買行為をいうのであるから,この場合,商品とは,商人が行う商業活動の客体(目的物ないし営利活動の手段)である,ということになる。このような古典的な商品概念は,現在でも,人々の観念,経済とりわけ商業と貿易の諸制度,および関連の法律などに色濃く残っている。しかしながら,現実にそれよりもはるかに広い意味で商品という言葉が使われていることも事実である。この現代的な商品概念においては,主体の前提は必要条件ではない。すなわち,商品とは,この場合,市場において売買されるいっさいの財およびサービスをさす,ということになるだろう。以上のような商品概念の変遷は,昔時の商業優位の時代から今日の工業優位の時代への転換を背景としている。その転換期がいわゆる産業革命だったことは確かである。かつて商人は,諸国の〈物産〉を危険を冒して遠隔地から運んでくることで,それを商品化することができた。だが現代では,商品化過程が大きく変化するとともに,そのプロセスの主役は,多くは生産者(製造業者)であり,それと結びついた販売業者であるが,しかしときには消費者(たとえば生活協同組合)だったりするというわけで,商品を商人の活動とだけ結びつけて考えることはできなくなった。商品供給者の戦略上の組織的展開は製品計画とか商品計画(マーチャンダイジング)とか呼ばれるが,それらの戦略展開において大部分を占める商品は,物産的な商品というよりは,むしろ工業的な〈製品〉であることが多い。新しい情報産業やサービス産業においては,それぞれの無形の販売対象を〈商品〉と呼ぶ事例がふえている。したがって,今日では,最広義の商品概念が支配的になりつつあるといえる。
の字がすたれてしまったためである。商うとは,商人が営利を目的として行う売買行為をいうのであるから,この場合,商品とは,商人が行う商業活動の客体(目的物ないし営利活動の手段)である,ということになる。このような古典的な商品概念は,現在でも,人々の観念,経済とりわけ商業と貿易の諸制度,および関連の法律などに色濃く残っている。しかしながら,現実にそれよりもはるかに広い意味で商品という言葉が使われていることも事実である。この現代的な商品概念においては,主体の前提は必要条件ではない。すなわち,商品とは,この場合,市場において売買されるいっさいの財およびサービスをさす,ということになるだろう。以上のような商品概念の変遷は,昔時の商業優位の時代から今日の工業優位の時代への転換を背景としている。その転換期がいわゆる産業革命だったことは確かである。かつて商人は,諸国の〈物産〉を危険を冒して遠隔地から運んでくることで,それを商品化することができた。だが現代では,商品化過程が大きく変化するとともに,そのプロセスの主役は,多くは生産者(製造業者)であり,それと結びついた販売業者であるが,しかしときには消費者(たとえば生活協同組合)だったりするというわけで,商品を商人の活動とだけ結びつけて考えることはできなくなった。商品供給者の戦略上の組織的展開は製品計画とか商品計画(マーチャンダイジング)とか呼ばれるが,それらの戦略展開において大部分を占める商品は,物産的な商品というよりは,むしろ工業的な〈製品〉であることが多い。新しい情報産業やサービス産業においては,それぞれの無形の販売対象を〈商品〉と呼ぶ事例がふえている。したがって,今日では,最広義の商品概念が支配的になりつつあるといえる。
現代商品の動向
日本では,第2次大戦前から戦後の高度成長期へかけて,エネルギー革命が進行し,また真空管,トランジスター,半導体の利用による家庭電化の促進,そして,モータリゼーションの加速などがあって,さまざまな技術革新型の新製品が開発され,その普及がめざましかった。これらはいわゆるシーズ(アイデア)からニーズへの開発パターンのものであった。この時期,貿易立国の日本は,カメラ,オートバイ,トランジスターラジオ,テープレコーダー,時計,合成繊維織物などの輸出で優位に立った。しかし,1973年の石油危機以後,経済環境が著しく変化し,技術革新が一段落したこともあって,省資源・省エネルギー,安全性,消費者のライフスタイル,さまざまな生活欲求,社会的要求などのニーズからシーズへの開発パターンをたどる商品が多くなった。豊饒(ほうじよう)の時代を反映し,それらの商品はファッション化が著しい。こうした傾向のなかで,技術革新型のシーズとして最も重要な意味をもつ変化は,半導体から集積回路(IC)へ,そしてさらに超LSIへのコンピューター素子の発展であった。すなわち,このエレクトロニクス化の進展によって,多くの精密機械商品が小型化し,あるいは複合化した。電卓,VTR,マイコン(パソコン)などが人気商品となり,各種OA機器の開発や自動車の電子化も進行した。そして,電子処理技術の通信,放送,印刷,出版などへの応用により,情報化がいっそう促進されることになった。各種コンピューターの普及はパッケージ化されたソフトウェアが独立の商品となることを可能にしたし,さまざまな情報誌の激増は情報型商品の存在を誇示しているようにみえる。現代における広範な商品化の波は,いまやサービスの分野においても実にさまざまな商品形態を生み出しており,〈サービス経済化〉の傾向が著しい。サービスの商品化ないし市場化は,表面的には,なるほどと思われるような新しい商売ないしビジネスの出現として感知される。しかしその底流を探ってみると,製造企業や流通企業などの経営に必要なソフト部門の外部化,および家計サービスの外部化という2面があることがわかる。生産と消費におけるこのような潜在需要の存在がニーズ密着型のソフト専門業やサービス提供業を成立させているのである。このようにして新しく出現しつつあるソフト商品やサービス商品の特徴は,価値の重点が物質そのものから離れた情報価値や,より便利なサービス価値にあることだが,近年,金融,保険,運輸,通信,出版,卸・小売,外食,教育・教養,レジャー,スポーツなどにあいついで現れた新手のサービス商品にみられる共通の側面は,広域的なかつ情報的なシステム化ということであり,その場合には,価値の重点はシステムの質そのものにあるということになるだろう。
商品の分類
商品分類法には,大別すると,(1)概念的分類,(2)実務的分類,(3)制度的分類の3種がある。(1)は,商品の概念的な整序のための分類で,分類区分を生物学に準じて異と同の2面から二名法の原理によって行う体系的なものと,単一基準によって2ないしそれ以上に商品のカテゴリーを分けたものとがある。前者の参考例としては,表1の分類が考えられる。古典的な商品概念は可動財のみを考えており,現代的な商品概念は表の全商品群を包含している。なお,マーケティングにおいては,A.コープランドが提唱した方法に従い,財商品について表2のような分類法が採用されてきた。消費者用商品については,消費者の愛顧動機と購買慣習によって分けられており,産業用・業務用商品の亜分類とは異なった概念的分類となっている。このうち最寄品は最寄りの商店で購買される商品で,タバコ,新聞・雑誌,食料品,薬・化粧品などである。買回り品は購入・選択の過程で品質・価格・適応性などを比較検討して各店を買い回るような商品で,衣料,装身具,靴などをいう。専門品は消費者が商標など価格以外の要素に特別の魅力を感じて,特別な購買努力をするもので,高級家具・衣料,自動車,ピアノなどがこれにあたる。次に(2)は,産業の各分野において,慣習的かつ実際的に行われているもので,体系上は多少の難点を含んでいる場合が多い。現実には複数の分類基準を実務的見地から適宜組み合わせる必要があるからである。また(3)は,主として統計調査と貿易制度に関して,国際的ならびに国内的に整合性を与えるために制定されているもので,いくつかの分類基準の組合せからなる多桁の網羅的な大型分類である。これには,国際分類として,SITC(標準国際貿易分類),CCCN(関税協力理事会品目表)があり,後者は,HSN(harmonized system nomenclature)として,コーディング・システム(harmonized commodity description and coding system)を備えたものに改訂される方向にある(1983現在)。以上のほか,サービスを包含したものとして,ICGS(国際標準金財貨サービス分類)が近く制定される見通しである。また,国内的には,独自の日本標準商品分類が制定されているが,国際的にみると,孤立的な性格のものになっている。
商品性
商品性は商品の売買契約において,黙示の担保implied warrantyを構成する要件であって,市場で売買されるのに適する不可欠の属性をいう。銘柄売買や見本売買においては,現物が平均的商品average goodsであることが必要だが,それにより商品性merchantabilityがあるとされる。なお,欠陥商品の判定に関して,アメリカの不法行為法では,不特定多数の買手に販売された場合を要件とし,それを商品性の一要素としている。
商品学
商品に関する研究は,大なり小なり,さまざまな分野で行われている。しかしそれを〈商品学〉の名称のもとで行ってきた歴史は,世界のある地域に限られている。率直にいって,それはドイツ語圏と日本とである。すなわち,ドイツ語圏では,数百に分断されていた18世紀初期の領邦国家の時代に,主邦プロイセンを中心に,商人学Kaufmannswissenschaftが興され,その重要な一つの分科として,Waarenkundeという名称の学問がスタートしたのである。もっとも,その先駆的業績としては,アラブの商人ディマシュキーAbū al-Faḍl al-Dimashqīの書《商業の美徳》(11世紀ころ),地中海商業時代のイタリア人の記録(15~16世紀),その後のフランス人の書(17~18世紀)をあげることができる。なかでもフランスのサバリJaques Savaryの書《完全なる商人》(1675)と彼の息子ブリュスロンJ.Savary des Brûslonsが編集した《一般商業辞典》(1723)は,ドイツ人に大きな影響を及ぼした。ドイツで商人学を興したのはマールペルガーP.J.Marpergerであるが,18世紀半ばに,この時代の商学的商品学を純粋な形で体系化したのはルードビッチCarl Grünther Ludoviciである。すなわち彼は,傑作の評価が高い《商人大学(商人辞典)》(1752-56)の別巻〈概説商人体系〉(1756)において,みずからの体系を示した。それは一般商品学Allgemeine Waarenkundeと個別商品学Besondere Waarenkundeの2体系をもち,前者が後者の叙述基準をなすというものであった。この総論-各論型の叙述スタイルは20世紀にまで受け継がれてきたが,他面において,アルファベット式に商品を配列した商品辞典もかなり刊行されてきた。要するに,こうしてWaarenkundeは個々の商品についての商品知識の集成を任務としてきたのである。その結果,商品理論の開発が立ち遅れることとなった。これは商業理論についても同様であり,商人学から発展した商取引学Handlungswissenschaftの体系も未熟なものであった。そこで大胆に商学体系の再編を試みたのはロイクスJ.M.Leuchsである。彼は《商業の体系》(1804)において,商学を商業学Handelswissenschaftと商業誌Handelskundeの2体系に組み直し,前者を理論部門,後者を実際部門とした。その体系の中で,商品学も商品論Waarenlehreと商品誌Waarenkundeの2体系で考えるべきだとした。しかし,彼のあと1世紀余もこのWaarenlehreの語は忘れられたままであった。その間にドイツ商品学は,ベックマンJ.Beckmannが18世紀末ころ創始した技術学Technologieの影響と,のちにオーストリアのウィースナーJulius von Wiesnerが開拓した原材料学Rohstofflehreの刺激によって,その内容が著しく技術学的かつ応用自然科学的なものとなり,商学的商品学は衰滅してしまったからである。その推移は明らかに重商主義時代から産業資本主義時代への転換を背景としている。技術学をライフワークとしたベックマンが《商品学予論》(1793-1800)を著した動機は,当時のWaarenkundeと称した書の内容があまりにも浅薄だったためである。それから約70年後,《植物界原料品》(1873)の大著によって商品学を蘇生させたウィースナーも,ベックマンと同様のことをいっている。こうしてウィースナーの影響を強く受けたWarenkunde(現代語)は,顕微鏡をおもな武器とする商品鑑定Warenprüfungを最も重要な領域とするに至った。ウィースナーとその一派の学者たちはオーストリア学派と呼ばれている。かくして,19世紀末期には,ドイツ語圏の商品学は技術学(ウィースナーの原材料学はこの一分科だった)としっかり手をつなぐことになった。現在,ドイツとオーストリアの学会はそれぞれDGWT,ÖGWTと称し,Warenkunde und Technologieの学会を名のっている。
1884年ころ日本では高等商業教育が本格的にスタートしたが,そのカリキュラムはベルギーのアントワープ高等商業学校を模したもので,その中に〈商品工芸誌〉がおかれていた。そこで,ドイツ商品学がベルギーを経て日本に移入されたとみることができる。明治末期から大正期,昭和初期へかけて全国に高等商業学校が設けられたが,そこでは商品学は主要科目の一つだった。私立大学も含めると,商品学の講座はかなりの数にのぼった。そのなかで,小原亀太郎(1886-1945)はオーストリア学派と交流してみずから応用自然科としての商品鑑定学を樹立し,学界に多大の影響を与えた。そうしたなかで,ひとり商学的商品学の復興を主張し,小原と論争したのは上坂酉三(こうさかとりぞう)(1888-1976)だった。なお,上坂は小原の没後(戦後)に,商品のアメリカ的研究であるマーチャンダイジングとドイツ的研究であるバーレンクンデとの融合を考えた〈第三商品学〉の構想を提示した。以上のような商品学の発展はそれなりに意味のある事実であったが,商品学者が視野においた商品の概念は最狭義のものであり,そのために,方法論の立遅れを招いた。この反省から,意欲的な学者たちによって,方法論の模索が続けられており,商品に関する現代的な諸問題への積極的な取組みのための理論構築の努力が続けられている。
執筆者:吉田 富義
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「商品」の意味・わかりやすい解説
商品
しょうひん
commodity 英語
Waren ドイツ語
経済学上の商品
商品とは、本来物質的生産において生産された欲望の対象である労働生産物が、交換関係にある場合に初めてとる形態である。この形態をとるには、一定の社会的・歴史的条件が必要である。その条件とは、社会的分業の存在と生産手段が私的・分散的に所有されていることである。すなわち、社会的分業のもとでは、自分が生産する労働生産物の種類は制限されるから、他人の労働生産物を利用しなければならない。また、社会的所有に対立する私的・分散的所有のもとでは、自己所有の労働生産物を提供してしか他人所有のものを手に入れられない。したがって、この条件のもとでは、交換を通じてしか他人所有の労働生産物を入手しえないことになる。
[海道勝稔]
商品の価値
このように商品は、一方で労働生産物としてなんらかの欲望を充足させる有用性をもつとともに、他方では交換されるものである。すなわち、交換価値をもつ。欲望充足の対象としては、商品ごとにその種類を構成する物理的・化学的・幾何学的性質や形状の違いとなるが、この違いは使用価値である。ところが、これと明確に区別されるものとして商品は交換されるものとしてある。互いに交換されるには、商品どうしの間に一定の共通なものがなければならない。この共通なものとは、それぞれの商品を区別している形状や物理的・化学的・幾何学的性質の諸属性、つまり使用価値ではない。そこでこれらを取り去ってみると、共通なものは互いに人間労働の生産物だという社会的面のみである。この人間労働の生産物というのは、それぞれの商品を生産するそれぞれの具体的有用労働の生産物ということではない。具体的有用な面を消失した無区別な一般的人間労働、質的に共通で量的にのみ比較される人間の精神的・肉体的労働能力の生産的支出一般としての抽象的人間労働、したがって普通の人間ならだれしも行える単純労働を尺度単位とし、複雑労働は社会的過程においてこれに換算される抽象的人間労働、これが商品どうしの共通な社会的実体をなし、それに基づいて商品どうしが比較される。このように抽象的人間労働が商品に対象化され結晶しているものを商品の価値という。先の交換価値はこの価値の現象形態である。この場合、抽象的人間労働は価値の実体である。そして商品の価値量はそのなかに結晶している先の労働の量であるから、それは労働の時間的継続で計られる。この労働時間は、生産物における個別的なものでなく、社会的に必要な労働時間、つまり社会のその時々の正常な生産条件と社会的に平均的な労働の熟練と強度で生産するのに必要な労働時間によって決まるのである。これは価値が社会的なものだからである。
商品はこのように、一面では商品全体が人間の欲望を満たす使用価値であり、他面では商品全体が抽象的人間労働の結晶としての価値である。すなわち、商品はそのなかに使用価値と価値の2要因をもった統一物である。
この2要因は、商品を生産する労働そのものの二重性に起因する。労働は、一面では、特定の目的・作業様式・対象・手段にかなった生産的活動であり、特定の使用価値を生む。これを具体的有用労働という。したがって具体的有用労働は個々に異なり、個々的に使用価値は違ったものとなる。使用価値はこの具体的有用労働と自然素材を源泉とする。他面では、労働はその支出の形態にかかわりのない生理学的意味での脳髄(のうずい)・筋肉・神経・手などの人間の労働力の支出である。これを抽象的人間労働といい、この同等な人間労働または抽象的人間労働が価値を形成するのである。
[海道勝稔]
交換における価値
ところが、生産物の交換形態である商品の交換において、この商品の2要因である使用価値と価値とは相矛盾しあう。
商品所有者は、彼には自己所有の商品が自己の使用価値をもたず、消費しないから交換に提供しようとする。商品の使用価値は他人のための使用価値であり、商品所有者にはその使用価値は交換価値の担い手にすぎない。交換手段という使用価値をもつことになる。すべての商品は、その所有者には非使用価値であり、非所有者には使用価値であるから、全面的交換となるのである。しかし、交換は価値として連関することであるから、使用価値として実現する前に価値としての実を示さなければならない。
他方、商品は価値として実現する前に使用価値たる実を示さなければならない。なぜなら、使用価値あるものしか交換されないから、そこに支出された人間労働は、他人にとって有用な形態で支出されていなければならない。ところが、他人に有用か否かは、商品の交換のみが証明するからである。
このように商品の2要因である使用価値と価値は、相互に前提しあうとともに相互に排除しあう。商品の所有者には価値を有する他人のための使用価値である。さらに商品は、他の商品と交換されて初めて価値として他の商品との同等性が実現され、使用価値として役だつものとなるが、しかし交換されてしまえばもはや商品でなく、買い手にとっての単なる使用価値になってしまう。商品は経過的なものである。
商品は、交換の形態をとる経済関係の矛盾のもっとも簡単なものである。ところが、資本主義社会は、この交換関係が日常的で大量に幾十億通りにも繰り返される関係として存在する。そのことから、商品形態は貨幣形態・資本形態へと運動を展開して資本主義の全矛盾を解き明かすことになるから、商品は、有機体を構成し、かつそれを解明する最小単位の細胞と同じく、まさに経済上の細胞形態である。
商品は、資本主義のもとでは、人間の肉体の属性である労働力や労働生産物でないもの(たとえば土地・名誉など)にまで及び、さらに利子生み資本においては資本を「商品」として擬似化さえするに至る。
[海道勝稔]
商品学上の商品
伝統的商品観による「広義の商品」である経済財は有形・無形財に分けられ、さらに有形財は可動・不動財、可動財は実質・形式財に分けられるが、この実質財は「狭義の商品」と称され、通常のモノとしての商品である。
商品学上の商品は、このモノとしての商品を(1)人間の物質的欲望を満たしうる実質的価値を有するもの、(2)通貨を用いての交換により所有を一方から他方へ転換でき、同時に運送や保管の機能により移動しうるもの、(3)市場を対象に見込み生産されているもの、(4)そのものが現実かつ直接に商環境や流通過程に置かれ、商的取扱いを受けているもの、としている。これは、何らかの実質的価値を有する有体動産のうち、現に商いの環境に置かれているものである。したがって注文生産品や、実質的価値をもっていても骨董品(こっとうひん)などのような使用価値そのものを目的としない取引対象物としての商品はこの範疇(はんちゅう)に入らない。
[青木弘明・大竹英雄]
商品の分類
市場に流通する商品は多種多様なものが数限りなく存在するので一定の基準を設けて分類・整理する必要がある。分類基準自体にも種々あるが、一般に用いられているのは、(1)商品の物理的もしくは化学的性質による分類、(2)商品の生産様式もしくは産出源による分類、(3)商品の消費様式もしくは用途による分類、(4)商品の流通様式による分類などである。
(1)の分類では、腐敗損傷性の有無による非耐久製品(生鮮商品など)と耐久性商品、価値集中の程度による従量品と従価品、単位形態の性状によって液体、気体、固体、粉体、粘体、粒状商品などの区別がある。これらのうち従量品とは、綿花、鉄鋼、米穀など重量・容積に比して価値集約度が低いものをいい、従価品とは宝石、精密機器のように価値集約度が高く、重量や容積は問題にならないものをいう。
(2)の分類では、産業の業態によって農産品、水産品、林産品、鉱産品、工産品に分け、工産品はさらに醸造工業品、繊維工業品、化学工業品、機械工業品、電子工業品、窯業品などに細分類される。また、加工度の精粗によって原料(粗製品)、半成品(半製品ともいう。仕掛品)、完成品(精製品)に分けられる。
(3)の分類は、商品が生産(産業)的消費に充当されるか、消費者による最終的消費に充当されるかによる区分であり、もっとも広く用いられる分類である。生産的消費に充当される商品は生産財とよばれ、これはさらに原料品、材料品、部分品、補助品、設備品などに分けられる。このうち原料品は化学的加工が、材料品は物理的(機械的)加工が施されて新しい財になるものをいう。この分類は生産対消費という概念から使われてきたことばであり、具体的なモノの生産活動ではない各種サービスの事業者や官公庁が使う商品は、最終消費財のような商品であっても生産財であり、これを産業財とよぶことも多い。
また真偽や混合などによって真正品(しんせいひん)(本物)、偽交品、偽称品、模造品、人工品などに分けられる。偽交品は似たものを混合したもので、バターとマーガリンのブレンド、繊維の混紡や交織などがある。しかし現代では家庭用品品質表示法、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、食品衛生法などの表示制度があらゆる商品の表示を強制しているため、原材料名を偽る事例は少なくなり、原材料やその割合など、商品の正確な状態をそのままうたうことで、かえってブランド化に利用している。たとえばマーガリン類のブランド名では、コーン油を主原料とすること、ブレンドしているバターが半分であること、サフラワー油(べにばな油)を使用していること、発酵バターを含むことなど、それぞれ原料名やその割合を組み込む事例も多い。また涼しい素材感を打ち出す夏物の被服の場合、組成表示以外に販売促進として「麻綿混」などとうたっているものも普通にみられる。このように現代では、想定された使用環境において必要とされる機能をもたせるなど、適合性の高いものを製造するために複数の素材を使い、その機能を説明している被服品も多い。したがって複数素材を混用していても粗悪品を意味しないが、第二次世界大戦後の原料が不足していた時期には、複数素材を混用した粗悪品が、本物と偽って販売された事例が多かった。食品の場合、現代でも食品添加物による見た目の質的な偽交は多くの商品にみられる。また増量偽交では、冷凍むきエビの乾燥や酸化防止のために使用される表面の氷の膜(グレーズglazeという)を厚くしたもの、上白糖へ水分を含ませて増量したものなどの事例がある(なお、むきエビの表示重量は計量法によってグレーズを除いたものとされている)。偽称品は模造品や偽交品を真正品と偽った商品で、消費者を欺瞞(ぎまん)する目的で製造加工を施すものであり、ブランドや産地を偽ったものもこの一種である。
最終的消費に充当される商品は消費財とよばれ、これはさらに必需品と奢侈品(しゃしひん)、消耗品と耐久品、用途によって食料品、衣料品、住宅品、教養・娯楽品など多様に分類される。
(4)の分類では、需要者の購買慣習によって最寄品(もよりひん)、買回り品、専門品、規格品と特別意匠品、有標品と無標品(ノーブランド商品)、冷凍品・冷蔵品・常温品などに分類される。最寄品は需要者がもっとも近い店で適宜入手するもの、買回り品は購買に際して各店を回り、品質、価格、デザインなどを比較選択する商品をいう。また専門品は、専門的に取り扱う店で購入する高級品、耐久品などをさしている。
以上の商品分類は標準的なもので、流通や商店経営などの問題を考える場合には、いくつかの分類基準を混合した別な分類方式がとられることが多い。また商品分類は商品統計表の作成、関税の課税、貿易取引などに不可欠であり、このため取引されるすべての商品を分類するために作成された日本標準商品分類や、各国の関税率表を統一し、国際貿易の円滑化のためにHS条約として制定された国際統一商品分類(Harmonized Commodity Description and Coding System。HSと略す)などが利用されている。
[青木弘明・大竹英雄]
商品の売買・流通経路
商品の売買にあたっては、商品の品質、種類、数量、価格、引渡し場所、引渡し時期、代金決済方法などについて契約しなければならない。これらを商品の売買条件という。
商品の品質を決める方法としては、現品、見本、銘柄、標準品、仕様書など商品に応じた方法がとられる。銘柄とは、特定商品の品質を表示するものとして慣習上広く認められている名称で、産地名、等級、規格、商標、商号などで表される。標準品による方法は、あらかじめ売り手と買い手が品質の標準的なものを定めておき、これを基準として売買する。
商品の数量については、商品の種類に応じて用いる基準が異なり、流通段階によっても、また売買単位が異なるのが普通である。
商品の価格は、建(たて)とよばれる一定の数量を基準にして表示され、この価格を建値といい、運賃、保険料、保管料などの負担方法によって価格が異なる。
引渡しの時期にも、即時渡し、直(じき)渡し、延(のべ)渡しの別がある。
代金決済の方法には、現金払い、後(あと)払い(掛(かけ)払い、手形払い、賦(ふ)払いなど)、前払いなどの別がある。国内取引ではメーカーが流通段階のマージン(利幅)を組み込んだメーカー希望小売価格を決める建値制がとられていたが、建値制を維持できずに安売りが常態化したこと、加えて公正取引委員会により「不当景品類及び不当表示防止法」の二重価格表示に抵触する可能性を指摘され、オープン価格制がとられる商品も増えている。なお貿易取引の建値にはFOB価格(本船渡し価格)、CIF価格(運賃保険料込み渡し価格)などがある。
[青木弘明・大竹英雄]
商品と資源・環境問題
1970年代まで、商品はその生産から消費までの経済活動の範囲でとらえられてきた。しかし、地球規模の環境破壊や資源問題に直面し、また人類の経済活動の規模拡大や人口増加などによって相対的に地球が矮小(わいしょう)化したため、人々の地球観は自浄能力や無限性を有する地球から有限な地球へと変化した。したがって1970年代以降、商品の開発や流通および廃棄は資源・環境問題を前提にしてとらえられるようになり、地球本来の姿を取り戻して後世に残すために、人々は、資源・環境に対し低負荷性をもつ生産・消費活動と循環型の経済システムを命題として経済活動を修正してきた。商品の生産・流通・消費の際に、ごみの発生を抑制(リデュースReduce)させる商品およびその製造と包装の実現や、包装や本体を再使用(リユースReuse)し、さらには再資源化(リサイクルRecycle)してマテリアルリサイクルによる再生利用や、エネルギーなどに変換するサーマルリサイクルが行われている。資源を循環させるための静脈流通とよばれるリサイクリングには、廃棄物収集過程、再生加工、再生資源流通過程などが必要となった。しかしリサイクルによる再生原料の使用が強制されなければ、再生原料はバージン原料価格と同価格またはそれ以下でなければ流通しない。したがってリサイクルにおいても、生産の効率性を高めなければ消費生活のコストを低下させることができない。同時に商品の企画や設計の時点において低リサイクルコストですむ方法の開発が要求される。よって商品の適性には、これまで考えられてきた商品の消費・使用の際の使用適性や市場に対する適性だけでなく、資源・環境に対する低負荷性やリサイクル適性などの「社会(適)性」も含まれ、個装を含む商品形成の過程でこれらを組み込むことが前提となっている。1991年(平成3)には循環型社会のために「再生資源の利用の促進に関する法律」(通称「リサイクル法」)が制定され、2000年(平成12)に現行の「資源の有効な利用の促進に関する法律」に改正された(2001年施行)。また同時に循環型社会の基本的枠組みを「循環型社会形成推進基本法」(2000年制定)によって定め、「容器包装リサイクル法」(1995年制定)、「家電リサイクル法」(1998年制定)、「食品リサイクル法」「建設リサイクル法」(2000年制定)、「自動車リサイクル法」(2002年制定)などが改正あるいは制定され、1999年には「ダイオキシン類対策特別措置法」も制定されている。このような考え方から、金属、プラスチック、紙、ガラス、食品のリサイクルはもとより、希少資源であるレア・アース(希土類元素)を含むレアメタル(希金属)のリサイクルも行われている。大都市では電子機器などからの資源回収量が多いことから、「都市鉱山」ということばも使われている。レアメタルの場合、リサイクルが国際取引価格を低下させる方向で機能し始めており、主要先端産業の資源確保に役だっている。
[大竹英雄]
世界大百科事典(旧版)内の商品の言及
【フェティシズム】より
…
[経済学]
K.マルクスは,ド・ブロス,A.スミス,コント,L.A.フォイエルバハに通底する,以上のような人間の自然的感情を前提とした原始宗教論に疑問符を付し,フェティシズムの成立を社会的関係性,歴史性から解明しようとした。彼が《資本論》において展開したフェティシズムの対象は,資本制下において商品となった生産物である。宗教的世界で〈人間の頭の産物がそれ自身の生命を与えられ,それら自身のあいだでもまた人間との間でも関係を結ぶ独立した姿に見える〉ように,〈商品世界でも人間の手による生産物が,同じような様相を呈している〉からであった。…
※「商品」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...