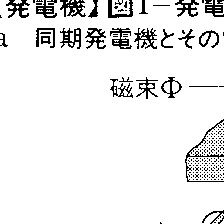翻訳|generator
精選版 日本国語大辞典 「発電機」の意味・読み・例文・類語
はつでん‐き【発電機】
- 〘 名詞 〙 機械的な動力から電力を発生させる回転機械の総称。磁界内でコイルを回転させ、誘導電流を得る装置で、直流発電機と交流発電機とがある。ダイナモ。
改訂新版 世界大百科事典 「発電機」の意味・わかりやすい解説
発電機 (はつでんき)
generator
ダイナモdynamoともいう。機械的エネルギーを電磁作用により電気エネルギーに変換し,電力を得る電気機械。直流を得るには直流発電機,交流を得るには同期発電機,誘導発電機が用いられる。このうち,同期発電機がもっとも一般に用いられ,電力会社の発電所用100万kVAを超える大容量機から,工事用や病院などの非常電源用の数kVAまで,各種各様のものが作られている。
発電機の原理と特性
磁束を横切って運動する導体には,フレミングの右手の法則により,電圧が誘起される。この原理を用い,発電機が作られている。
同期発電機
図1のように磁極によりΦウェーバーの磁束が作られている場の中で,電機子コイルABをω(rad/s)の速度で回転させると,コイルと鎖交する磁束をφ,コイル巻数をnとして電機子コイルには電磁誘導作用により,
の起電力が発生する。時刻t=0においてコイルが磁束と垂直な面内にあったとすれば,時刻tではωt(rad)だけ回転した位置にあるから,tでの鎖交磁束φ(t)は,
φ(t)=Φcosωt ……(2)
と表される。(2)と(1)から,一定磁界中でコイルを角速度ωで回転させると,コイル端子AB間には,
e(t)=nωΦsinωt ……(3)
で与えられる正弦波状の交流起電力が発生する。同期発電機では電気出力の周波数が機械的な回転速度で決まり,この回転速度を同期速度という。図1で磁極の数Pを増加させていけばコイルの1回転で発生する鎖交磁束の変化速度はP/2倍されるから,出力周波数f(Hz)が指定されている場合に回転速度を毎分回転数Nで表すと,
N=120f/P ……(4)
の同期速度で発電機は回転しなければならない。原理図では界磁が固定し,電機子コイルが回転する回転電機子形であるが,実際のものは逆に界磁が回転する回転界磁形である。界磁には電磁石を用いて,三相電圧を誘起するのが一般である。図2にその原理図を示す。三つのコイルを空間的に120度の間隔で配置し,図2のbのように結線すれば,端子U,V,Wに図2のcのような三相電圧が得られる。なお界磁コイルは回転しているので,図1の原理図に記載のスリップリングを使い外部より直流電流で励磁する。
直流発電機
原理は図1のとおりで,電機子コイルに発生する電圧は交流であるが,整流子を通じ,交流を一定方向の電圧として取り出せば,脈動はあるが直流が得られる。電機子コイルと整流子の片の数を増せば,電圧の高いところのみを使用することになり,脈動の少ない直流が得られる。直流発電機も,界磁には電磁石が用いられるが,その励磁の仕方で,他励,自励があり,自励にはさらに直巻発電機,分巻発電機,複巻発電機などがある。直巻発電機は単独の発電用として使用されることはほとんどなく,回路に直列に入れ,負荷の変動に対し,電圧の変化を少なくする補償用の増減圧機として用いられる。分巻,複巻発電機は負荷の増減に対し端子電圧の変動が少ないので,一般の発電機として用いられる(図3)。
誘導発電機
誘導電動機は同期速度より2~3%低い速度で回転子が回転し,固定子の作る回転磁界を横切って誘導電流を流して,電動機のトルクを発生しているが,回転子を同期速度以上で回転すると,逆に発電機として動作する。籠形の誘導電動機は構造が簡単で,励磁電流も電源側より供給されるので,特別の励磁装置を必要とせず,保守のための人手をほとんど要しない。一方,電源側より励磁電流の供給を必要とすることは,単独運転ができない,同期発電機に比して効率が劣る,などの欠点になる。このような長短を活かし,無人の小水力発電所などに用いられる。
原動機による発電機の差異
発電機の構造は,同じ同期発電機であっても原動機の種類や特性によっても変化する。事業用の発電所では水車,蒸気タービン,内燃機関などが原動機として用いられる。
水車発電機は水力発電所で水車によって駆動される発電機で,毎分100~500回転程度の比較的低速で運転されるために極数が多く,急激な電気負荷の変動が水車に極端な速度変化を与えないように,はずみ車効果を大きくしてある。最近の揚水発電所用発電機では,揚水時には発電機を電動機として動作させ,その動力で水車をポンプとして使用して下池の水をくみ上げ,発電時には上池の水を下池に落とし,水車,発電機として動作させている。火力発電所や原子力発電所で用いられるタービン発電機は,50Hzまたは60Hz用によりそれぞれ毎分3000または1500回転,3600または1800回転という高速で回転するために,遠心力に耐えるよう長くて比較的直径が小さく界磁巻線を埋め込んだ円筒形回転子を用いている。往復動型の内燃機関で駆動される発電機は,トルクの変化に対しても安定に動作するように,大きなはずみ車が付加される。
いずれの方式においても発電機は電気機械であると同時に機械的回転体であるから,軸たわみ,ねじれなどの機械振動の固有振動数が電気回路側から励振されることのないような配慮が必要である。
発電機の誘起電圧は界磁の磁束密度に比例するので,高い磁束密度が得られる超電導電磁石を用いた超電導発電機の開発が進められている。
執筆者:山本 充義
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「発電機」の意味・わかりやすい解説
発電機
はつでんき
generator
運動エネルギー(回転運動)を電気エネルギーに変換するエネルギー変換機器の総称。回転電気機器は電動機動作と発電機動作が可能であるが、とくに発電を目的として設計されたものを発電機とよんでいる。直流発電機、同期発電機、誘導発電機などの形式がある。
[森本雅之]
初期の発電機
発電機はM・ファラデーの電磁誘導の発見に続き、電動機と同時期につくられている。初期のものは永久磁石の回転を利用していた。1832年にピクシーHippolyte Pixii(1808―1835)が回転する永久磁石をコイルの近くを通過させて、「波打った電気」を製造することに成功した。これが現在の交流発電機の原型である。その後、1869年のZ・T・グラムは電気ブラシとコイルを使った直流発電機を発明した。その後、1881年にはE・W・ジーメンスが実用的な交流発電機を製造した。またこのころは送電を直流にすべきか、交流にすべきかの議論もあり、エジソンダイナモなどの直流発電機も種々開発された。
[森本雅之]
原理
磁界中に直線導体を置き、導体を磁界と直角の方向に運動させると、導体にはE=Blv(単位はボルトV)で表される起電力を生ずる。ここにBは磁界の磁束密度(テスラ)、lは磁界中にある導体の長さ(メートル)、vは導体の速度(メートル毎秒)である。起電力の向きはフレミングの右手の法則によって示される。
磁界に対する導体の運動は相対的であればよく、導体を静止させたままとし、磁界を上方へ速度vで動かしても導体に生ずる起電力の大きさと向きは、導体を下方に速度vで運動させた場合と同じになる。実際の発電機では、磁極か導体のいずれかを回転させて相対運動をさせる。
[磯部直吉・森本雅之]
発電機の種類
発電機は原理的には電動機と同一の構造である。したがって発電機も電動機と同様に、端子電圧の形態(直流電力を発電するか交流電力か)および回転速度と発電電力の周波数が比例する(同期する)かにより分類される。したがって直流機、誘導機などの電動機と発電機をあわせた呼び方で以下に示すような分類が行われる。
〔1〕直流機
(1)自励 直巻(ちょくまき)直流機、分巻(ぶんまき)直流機、複巻直流機。
(2)他励 他励直流機、永久磁石直流機。
〔2〕交流機
(1)同期機 巻線形同期機、永久磁石同期機、リラクタンス機(リラクタンスモーター)。
(2)誘導機(非同期機) かご形誘導機、巻線形誘導機、単相誘導機。
(3)交流整流子機(ユニバーサルモーター)。
一方、発電機は原理的な分類のほかに、駆動する原動機によっても分類される。
(1)タービン発電機 ガスタービン、蒸気タービンで駆動される高速の発電機。
(2)水車発電機 水車で駆動される低速の発電機。
(3)エンジン発電機 ディーゼルエンジンや各種のエンジンを原動機にもつ同期発電機。
(4)風力発電機 風車で駆動される超低速の発電機。
(5)その他の発電機 マグネト発電機、オルタネータ、エジソンダイナモ、電動発電機。
[森本雅之]
『電気学会編・刊『電気工学ハンドブック』第7版(2013)』
百科事典マイペディア 「発電機」の意味・わかりやすい解説
発電機【はつでんき】
→関連項目火力発電|水力発電|整流子|動力|励磁機
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「発電機」の意味・わかりやすい解説
発電機
はつでんき
generator
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の発電機の言及
【水力発電】より
…河川,湖沼などを利用して水を高い位置から急速に流下させ,その水の力で水車を動かし,これを動力として発電機を回転して電気を発生すること。すなわち水の位置エネルギーを水車によって機械エネルギーに変換し,これにより発電機を駆動して電気エネルギーを発生するものである。…
※「発電機」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...