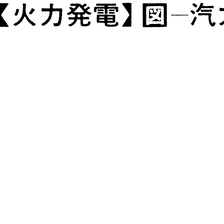共同通信ニュース用語解説 「火力発電」の解説
火力発電
火力発電は原発の停止が長引き、電力供給の柱となっている。特に石炭火力はコストが低く、安い料金で電力を供給できる。一方で、石炭は天然ガスに比べて二酸化炭素(C〓(Oの横に小文字の2))の排出量が多く、新設計画に懸念が指摘されている。経済産業省は電力会社やプラントメーカー、研究者らを集めた産官学による協議会を開催し、高性能な火力発電の技術開発を支援している。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
精選版 日本国語大辞典 「火力発電」の意味・読み・例文・類語
かりょく‐はつでんクヮリョク‥【火力発電】
- 〘 名詞 〙 発電方式の一つ。石油、ガスなどの火力で作った蒸気を利用して発電機を回し、電力を発生させるもの。
- [初出の実例]「火力発電に依存することの大きい西日本」(出典:経済実相報告書(1947)二)
改訂新版 世界大百科事典 「火力発電」の意味・わかりやすい解説
火力発電 (かりょくはつでん)
thermal power generation
石油,石炭,ガスなど燃料のもつ熱エネルギーを,原動機により機械エネルギーに変え,発電機を回転させて電力を発生させることをいう。火力発電は原動機の種類によりボイラーと蒸気タービンを用いる汽力発電,ディーゼルエンジンなどの内燃機関を用いる内燃力発電,ガスタービンを用いるガスタービン発電,ガスタービンと蒸気タービンの組合せによるコンバインドサイクル発電などに分類される。このうち汽力発電は,熱効率が高く大出力に適するため,事業用火力発電などにもっとも一般的に用いられている。
電力供給を目的とした火力発電の始まりは,1882年T.エジソンが創設したエジソン電気会社が発電機をニューヨーク市に設置し,一般への電気供給を行ったこととされる。日本は87年に東京電灯会社が日本橋茅場町に25kWの発電所を設けたことに始まり,これは日本初の水力発電所である京都市の蹴上(けあげ)発電所の完成に先立つこと5年であった。初期の火力発電は往復蒸気機関を用いるものであったが,1904年には東京市街鉄道会社が深川発電所に500kWカーチスタービン2台を設置し,06年には東京電灯会社が千住発電所に1000kWパーソンズタービン4台を設置し,それぞれ蒸気タービンによる火力発電を開始した。
明治の末からは水力資源の調査と開発が積極的に進められ,しだいに火力発電は渇水期の補給用として位置づけられるようになったが,引き続きかなりの火力発電所が建設され,昭和20年代には単機出力は最大5万5000kWに達した。
この水主火従の時代は第2次世界大戦後まで続いたが,30年代に入って産業の急速な発展に伴う電力需要の増大に対処するため,単機出力の拡大ならびに蒸気温度,圧力の上昇が図られて,単機出力は最大37万5000kW,蒸気条件は566℃,169kgf/cm2(ゲージ圧)に向上した。こうしてキロワット当り建設費の低減,熱効率の向上に加え燃料価格の安定による経済的な優位性と建設工期が短いことなどの特徴から,この間多数の火力発電所が建設され火主水従時代を迎えた。そして40年代には単機出力は100万kWに増大し,蒸気圧力も246kgf/cm2に達し,熱効率は40%を超えるに至った。
汽力発電
燃料を燃焼して得られる熱エネルギーをボイラーで水に伝え,高温,高圧の蒸気に変える。この蒸気は蒸気タービンに導かれ,その内部で膨張しながらタービンの羽根車(動翼)に回転力を与え,熱エネルギーは機械エネルギーに変換される。蒸気は膨張の後,低温,低圧となり,タービンを出て復水器の中で水に凝縮される。凝縮した水は復水と呼ばれるが,ポンプで高圧に加圧され,再びボイラーに送られる。こうして水はボイラーとタービンの間を循環し熱の吸収と放出を行う熱サイクルを構成する。このように加熱,膨張,凝縮,昇圧を行う熱サイクルをランキンサイクルという。上述のサイクルに用いられるタービンを復水タービンという。このほかに自家用発電などで蒸気を凝縮させないで膨張を中途でとどめ,タービンから出た排気を工業プロセスの加熱源などに使用するものがあり,このようなタービンを背圧タービンという。ランキンサイクルではタービンに入る蒸気温度,圧力が高いほど熱効率は高い。そのため,ふつう蒸気温度は飽和蒸気温度以上に加熱された過熱蒸気が用いられる。またタービンで膨張の途中の蒸気をいったんボイラーに戻し,再び高温に加熱してタービンで膨張させる再熱方式も一般に採用される。再熱は一度だけ行われる場合が多いが,再熱を2度行う場合もあり,それを2段再熱方式という。蒸気圧力は,大型の汽力発電所ではいわゆる臨界圧力(ゲージ圧225.6kgf/cm2)を超えた超臨界圧力の蒸気が用いられる。またタービンで膨張の途中で一部だけ外部に取り出した蒸気を抽気というが,これでボイラーの給水を加熱する再生方式も一般に採用される。再生方式では復水器で蒸気が凝縮する際に循環水に奪われる熱を抽気の分だけ減少させることができ,サイクル効率を高める効果がある。
ボイラー
発電用ボイラーには火炉の周囲に水管を配したいわゆる水管ボイラーが広く用いられる。ボイラーの給水はこの水管内を上昇しながら加熱され蒸気になる。蒸気圧力が低い,いわゆる亜臨界圧力(ゲージ圧225.6kgf/cm2以下)の場合は,ボイラー上部にある火炉水壁管の出口に大型円筒状のドラムを置き,ここで蒸気と水は分離され水は再び水壁管の下部に導かれる循環式が用いられる。蒸気圧力が高い超臨界圧力(ゲージ圧225.6kgf/cm2以上)の場合は,液体と気体の間に相の変化がなく,蒸気と水を分離することができないため,水が水壁管を流れる間に蒸気となる貫流式が用いられる。貫流式ボイラーには二つの方式がある。一つは水壁管をいくつかの垂直なブロックに分け,給水はそれらを順番に流れるようにしたもので,ブロック間は降水管と呼ばれる管でつながれる。もう一つはボイラーの水壁管が斜めに配列され,水が火炉の周囲をらせん状(スパイラル)に回りながら上昇し,加熱され蒸発するようにしたボイラーである。前の方式の貫流式ボイラーは,蒸気(給水)圧力を下げて亜臨界圧で運転すると蒸気と水の比重差を生ずるため,降水管が円滑に機能しなくなるので一定圧力運転を行う必要がある。これに対し後者では圧力が変化して,水管での蒸発域が変動しても流れに支障を生じないので超臨界圧設計でも亜臨界圧運転が可能であり,出力によって圧力を変化させて運転するいわゆる変圧運転を行うことができる。最近の事業用火力では負荷変動能力が強く要請されるので,このボイラーが多く採用される傾向にある。いずれの種類のボイラーでも,このようにして気化した水は過熱器に入り必要な温度にまで昇温され過熱蒸気となる。過熱器は火炉の上方,あるいは後方の燃焼ガスの通路の中に設けられ,垂直または水平の高温材の管群から構成される。タービンから戻された蒸気を再び過熱域まで昇温する再熱器も,過熱器と同じ構造である。燃焼ガスは火炉および過熱器,再熱器を通ってしだいに温度が下がり,ボイラーのガス通路の最下流に設けられた節炭器において,燃焼ガスの残りの熱が火炉水管に入る前の給水に回収される。さらにボイラーを出た燃焼ガス中の余熱は,空気予熱器において燃焼用空気を予熱することにより,さらに熱回収が行われる。この空気予熱器には多くの場合,再生式熱交換器と呼ばれる形式のものが用いられる。ボイラーの通風方式には主として加圧通風(圧力通風ともいう)方式と平衡通風方式とがある。前者は火炉に燃焼用空気を送り込む押込通風機のみで通風を行うもので,火炉の圧力は大気圧より高くなる。後者は押込通風機と,ボイラー出口で燃焼ガスを吸い出し煙突に送る誘引通風機を用いるもので,火炉の圧力は大気圧よりやや低くすることができる。石炭燃焼の場合には,ボイラーから周辺に灰などの粉塵が漏出することを避けるため平衡通風方式が採用される。石油およびガス燃焼の場合にはこのような心配がないため,設備の簡単な加圧通風方式が採用される。そのほかおもな通風機としてはガス再循環通風機とガス混合通風機がある。ガス再循環通風機は,節炭器出口で燃焼ガスの一部を取り出し火炉の下部に戻し再循環させる。この再循環ガス量を変化させることにより,ボイラー内を通過するガスの温度と流量を変化させ各部の水,蒸気への収熱量のバランスを調節して蒸気温度を制御することができる。また,ガス混合通風機は,燃焼ガスの一部を空気に加え,燃焼用空気の酸素濃度を下げ燃焼温度を下げて窒素酸化物の生成を抑制する。また同じような目的で燃焼用空気の一部を火炉の上部から加える2段燃焼法も用いられる。油や石炭を使用するボイラーでは,燃焼ガス中に含まれる灰や未燃分を除去するため電気式,または機械式の集塵器が設置される。
蒸気タービン
蒸気タービンは円周状に配列した動翼の列を何段にも並べた回転体の車軸(ローター)と,車軸を囲んで密閉するとともに動翼と対になる静翼を取り付けた静止部の車室,回転する車軸を支える軸受などから構成される。蒸気は静翼と動翼の間を交互に通りながら膨張し車軸に回転力を与える。膨張に伴って蒸気の体積は大きくなるので,タービンの翼も低圧段になるにつれて長くなり,回転によって生ずる遠心力も大きくなる。このため蒸気の流れを後段で分割する方法がとられる。さらに車室も圧力や温度に応じて分割し,それぞれを最適な設計とした多車室形がとられる。これらのタービンを一つの軸心上にくし形に配列したものをタンデムコンパウンドといい,二つの軸に分けて配列したものをクロスコンパウンドという。汽力発電所の出力の調整は,蒸気タービンに入る蒸気流量を増減することによって行われる。この調節を行う方法には,タービン入口の弁(加減弁)の開度を変える絞り調節方式と,加減弁は一定開度のままでボイラーの蒸気圧力を変える変圧運転方式とがある。変圧運転方式では部分負荷,すなわち最大出力よりも低い出力において蒸気の絞り損失をなくすることができ,またボイラーへ供給する給水圧力を下げることもでき,ポンプ駆動動力を減少させることができるので,熱効率の面でも有利である。タービンの排気は復水器で凝縮されるが,その潜熱を奪うための冷却水としては海水,河川水,湖水など自然界の水を用いるものと大気を用いる冷却塔など人工的なものがあるが,日本では海水が主として利用される。この冷却水を復水器に送り込むポンプを循環水ポンプという。復水器は冷却水を通した多数の細管の表面に蒸気が接触し,冷却され凝縮するしくみ(表面冷却式)のものが広く用いられる。復水器にはサイクルの低圧部分で大気から漏れ込んだ空気などが混入するため,真空ポンプを用いて排出し真空を維持する。復水は復水ポンプにより送り出され,再生サイクルの場合,タービンの抽気で加熱や脱気が行われたのち,給水ポンプで再びボイラーに送り込まれる。この給水加熱は数段に分けて行われ,それぞれ最適のタービン段落からの抽気が用いられる。給水加熱器には主として表面加熱式のものが用いられるが,脱気器には通常,給水に直接加熱蒸気を接触させる混合加熱式が使用される。これによりボイラーの腐食の原因となる給水中に溶解している酸素などを熱的・機械的作用によって分離する。給水ポンプは,給水の圧力をボイラー出口の蒸気圧力まで高めてボイラーへ供給するポンプで,大容量火力では主タービンの抽気を蒸気源とする小型の蒸気タービンで駆動させる。
発電機
蒸気タービン中において蒸気は高速で流れるため,タービンの速度も高速となる。このため蒸気タービンに直結される発電機(タービン発電機という)も50Hz系では毎分3000回転,60Hz系では毎分3600回転のいわゆる二極機がおもに用いられるが,クロスコンパウンド機の低圧タービン側には,その1/2の速度の毎分1500回転機や,1800回転機,すなわち四極機が用いられることもある。タービン発電機の回転軸(これを回転子という)は遠心力に耐えるため横置の細長い円筒形が採用される。タービン発電機では材料の強度的な制限とたわみの問題から大きさが限られるので,大出力とするためには冷却が重要となる。当初は空気冷却式であったが,上述の理由から日本では昭和20年代の終りから冷却効果の高い水素冷却式が使用され始めた。その後タービン発電機をいっそう大容量化するため冷却をさらに効果的にする必要が生じ,導体の中に直接水素ガスを通す直接冷却式や水を用いる水冷却式が採用されることとなった。
計測制御装置
電力需要の変動に応じて火力発電所の出力の調整を行うため,タービンへ流れ込む蒸気流量とボイラーへ供給される燃料量,空気量,給水量などを調節して,各部の温度や圧力を所定の値に保つ自動制御装置が設けられる。また各部の温度,圧力やタービンの振動などを監視し,異常があった場合警報を発する監視装置や記録装置が設けられる。さらに故障があった場合その種類に応じてただちに発電機を送電系統から遮断したり,タービンへの蒸気を閉止したり,あるいはボイラーへの燃料を閉止して停止するなどの保護装置が設けられる。また大容量火力発電所では省力化および信頼性向上の目的から,コンピューターを用いてプラントの状態監視や複雑な起動停止操作を行わせている。
燃料
日本の火力発電の燃料は1965年ごろまでは国産の石炭が中心であった。石炭は固体であることから取扱いが不便で,また大量の灰を発生するので,埋立てや灰処理のための特別な用地を必要とする問題があった。そのため大気汚染が問題となるに従って,価格面で有利で,輸送,貯蔵にも便利な石油に逐次転換された。また環境問題が深刻化してからは硫黄分の少ない燃料として原油やナフサも使用されるようになった。しかし,70年代に入り石油に対して供給の不安が高まり,価格の高騰が続いたため石油から石炭やガスへの転換が進められた。石炭は燃焼の際に硫黄酸化物や窒素酸化物を比較的多く発生する欠点もあるが,世界的に資源量が豊富であることから,排煙処理装置の進歩により,日本でも石油に代わる火力発電用燃料として輸入が拡大されている。ガス燃料では天然ガスが代表的なものであり,硫黄分や灰分を含まないもっとも清浄な燃料である。しかし,海で囲まれた日本まで大量かつ長距離の輸送を行うため,極低温(約-162℃)の液化天然ガス(LNG)やプロパン(約-43℃),ブタン(約-7℃)など低温の液化石油ガス(LPG)とする必要があり,このため生産地には液化設備,輸送には特殊な低温タンカー,消費地には気化設備をそれぞれ必要とし,多額の設備投資を伴う。
ガスタービン発電
燃焼によって得られた高温のガスを用いてタービンを回転させる方式。この目的に用いるタービンをガスタービンという。その動作はガスタービンに直結した空気圧縮機によって吸い込まれた空気を10kgf/cm2前後の高圧力に圧縮し燃焼器に供給する。燃焼器中において燃料を燃焼させて発生した高温のガスは,ガスタービンの中で膨張し動翼に回転力を与える。ガスタービンの熱サイクルは圧縮,加熱,膨張,放熱の過程から構成される。このような熱サイクルを一般にブレイトンサイクルと呼ぶ。ブレイトンサイクルには,外気をサイクル内に取り入れ排気を大気中に放出する開放サイクルと,ガスがサイクル内を循環する密閉サイクルの2種類に大別されるが,発電用に主として用いられるのは開放サイクルである。その中でも大型ガスタービンでは単純サイクルと呼ばれる構成の簡単なものが用いられる。ほかに開放サイクルに属するものとしては,熱交換器を用いて排気の余熱を回収する再生サイクル,タービンで膨張の途中のガスを加熱する再熱サイクルやこれらを組み合わせた熱サイクルがある。ガスタービンの出力は数千kWから10万kW程度までである。構造は汽力発電に比べ簡単で補機が少なく復水器冷却水を必要とせず,建設工期も短く,始動停止が容易で急速な負荷変化にも応じられるなどの特徴を有するので,ピーク負荷用や汽力発電所の自力始動用非常電源として用いられた。しかし,排ガスの温度が300~600℃と高く熱損失が大きいため,熱効率が25~30%と低いこと,またガスタービンの高温腐食を防止するためには灯油,軽油,天然ガスなどの良質燃料を使用することが必要とされることから,1973年のいわゆる第1次石油ショック以降は,単独で発電用として計画される例は少なくなった。
コンバインドサイクル発電
ガスタービンと蒸気サイクルを組み合わせ高い熱効率を得るもので複合サイクル発電ともいう。汽力発電の場合はボイラーなどの高温高圧部の材料の温度限界から蒸気温度が制限される。これに対してコンバインドサイクルでは,高温側に作動温度の高いガスタービンを利用し,低温側にガスタービンの排気の余熱を用いる蒸気タービンを使用することによって,熱サイクル全体の作動温度の範囲を広げ熱効率を向上することが可能となる。この組合せにはガスタービンの排気を直接,排熱回収ボイラーに導き蒸気を発生させる排熱回収式,ガスタービンの排気にさらに燃料を加え排ガスの温度を高めてボイラーに導く排気助燃式,ガスタービンの排気をボイラーの燃焼用空気として利用する排気再燃式がある。ガスタービンの入口温度が低い場合には排気温度も低くなるので,ボイラーとしては排気再燃式が主として用いられたが,ガスタービンの高温化が進められた結果,排熱回収式の熱効率がむしろよくなったこと,それに加え設備の構成が簡単なことから排熱回収式が一般的となっている。ガスタービンは入口ガス温度の高温化によってそれ自体の性能のみならず,コンバインドサイクルとしての性能が向上する。そのため燃焼器やタービン初段とその近くの高温部に,ニッケルやコバルトを主体とした耐熱性にとくに優れた材料を適用するとともに翼の内部に多数の冷却通路を設けるなど,冷却効果を高めた設計が採用されている。その結果,入口ガス温度として1100℃級が使用されており,さらに1500℃級を目標とする研究も行われている。コンバインドサイクルとしての熱効率は1100℃級の場合で43%に達し,1500℃級では50%以上になる。排熱回収ボイラーは火炉をもたない点が汽力発電用と比べて異なる点であるが,そのほかにガス温度が600℃程度と低いので熱回収を効果的に行うためフィン付きチューブを使用したり,給水を高圧,低圧の2種類の圧力で供給し,効率的な熱吸収,蒸発を行わせる混圧式蒸気サイクルを採用するなどのくふうをしている。またコンバインドサイクル発電の始動停止は所要時間が汽力より短く損失も少ないので,多数台設置される場合,運転台数を増減することにより発電所全体として軽負荷時にも全負荷に近い熱効率を維持することができる。コンバインドサイクル発電のそのほかの特徴としては,蒸気タービンの出力分担が汽力発電所より少ないので,復水器より冷却水へ放出される放熱量が少ないことがある。一方,ガスタービンの燃焼過程において大量の冷却空気を混入させることから,コンバインドサイクル発電では排ガス量が汽力発電より多く,窒素酸化物の排出量が多くなる傾向があるので,燃焼器への蒸気噴射や水噴射,あるいは脱硝などの対策がとられる。このほか,地域暖冷房または工場などで,総合熱経済の向上を図るため,動力と発電設備を組み合わせた熱併給発電も行われている。
→内燃力発電
執筆者:宮原 茂悦
火力発電所の公害
火力発電所は大量の燃料を燃焼させるため,大気汚染源の主要なものの一つであり,多くの事件を引き起こしてきた。歴史的にみると,すでに1890年ごろまでに日本で最初の電力会社である東京電灯会社と大阪電灯会社の火力発電所が市民の苦情を受けており,ことに煙の都とまで呼ばれるようになった大阪では第2次大戦前を通じて問題が絶えなかった。とくに1917年から20年にかけて大阪電灯の安治川東発電所と春日出発電所によって引き起こされた降灰事件は当時の一大事件であり,大阪電灯は被害に対する慰謝金として4万円を住民に支払うとともに,徹底したばい煙防止設備の設置を約束させられた。また,30年代に微粉炭燃焼法が採用されると,火力発電所からのばい塵の発生は飛躍的に増大した。これらはいずれも石炭を燃料とするもので,不完全燃焼によるすすや灰分が飛散したものであるが,石油への燃料転換とともに硫黄酸化物が主要な汚染物質となり,さらに窒素酸化物が問題となってきた。
硫黄酸化物は燃料中の硫黄分の燃焼によって発生するため,低硫黄燃料の使用が抜本的な対策となる。日本でこれが問題となったのは,石油-石油化学-電力のコンビナートが建設され稼動し始めた60年代であり,72年の四日市公害裁判が対策を進行させる転機となった。窒素酸化物は70年の光化学スモッグ事件をきっかけとして注目されるようになったが,その発生には,燃料中に含まれる窒素分の燃焼からと,燃焼による高温下で空気中の窒素が酸化されるものがあり,前者は燃料の高級化により改善されるが,後者は燃焼法の改善や排煙脱硝法などの多面的な対策が必要である。また,火力発電設備の巨大化により,液体燃料中にも含まれる各種の重金属などのばい塵としての発生量も無視できない量となってきている。
なお,蒸気タービンを回した後の蒸気の冷却に際して,主として海水を利用し,これを再び海域に放出する貫流方式がとられているため,温排水の海洋生物への影響も問題になっている。
執筆者:加藤 邦興
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「火力発電」の意味・わかりやすい解説
火力発電
かりょくはつでん
石炭、石油、天然ガスなどの燃焼による熱エネルギーを、タービンなどの原動機によって回転する機械エネルギーに変え、さらに発電機を働かせて電気エネルギーに変換させること。火力発電のなかでとくに水蒸気を介して発電する場合を汽力発電と狭くよぶこともある。ガスタービン発電は燃焼ガスで直接タービンを回すが、熱源はガスなど火力発電と同じであるので火力発電に分類する場合もある。ディーゼルエンジンなど内燃力発電は一般には火力発電には入れない。また、燃料の種類により、石炭を燃料とする石炭火力発電、重油など石油を燃料とする石油火力発電、天然ガス(石油ガス)を燃料とするガス火力発電に分けられる。原子力発電も熱で水蒸気をつくり、その水蒸気でタービンを回転させて発電するので原理的には火力発電と同様であるが、熱源が異なるので火力発電としては分類されない。
ガスタービン発電は日本においては1965年(昭和40)ころから各所に設置され、自家用をはじめ電気事業用としても多く使われている。また火力発電の熱効率の向上を目的に、ガスタービンと排熱回収ボイラーを組み合わせた複合サイクル発電(コンバインドサイクル発電)、アドバンストコンバインドサイクル(ACC:Advanced Combined Cycle)発電が全盛となっている。日本では、火力発電はその機動性の高さからピーク負荷対応がおもな役目になっている。
日本で最初に建設された火力発電所は、1887年(明治20)11月に東京・日本橋南茅場(かやば)町に設置されたもので、出力25キロワットの直流発電機(原動機は蒸気機関)によるものであった。これは、琵琶湖(びわこ)疎水利用による日本最初の水力発電所に先だつこと5年であった。第二次世界大戦前の火力発電所は、水力発電所が渇水期に減少する出力の補給用として建設された。昭和の初めまでは、ボイラーおよびタービンはほとんど欧米からの輸入品であったが、1930年(昭和5)当時の鉄道省川崎発電所(神奈川)に国産の2万5000キロワット機が据え付けられ、順調な運転を行った。続いて当時としてはもっとも高い圧力であった飾磨(しかま)港発電所(兵庫)の圧力46気圧、出力3万5000キロワットのタービンおよびボイラーが国産化された。その後さらに国産化が進み、3600回転機としては当時の世界的記録をもつ1万8000キロワットの宇部発電所(山口)、3万キロワットの坂発電所(三重)が建設された。第二次世界大戦後の1952年(昭和27)に圧力60気圧、出力3万5000キロワットの築上(ちくじょう)発電所(福岡県)が建設され、これを契機として、1号機外国技術導入、2号機以降国産化方式による高温・高圧の大容量・高効率の火力発電所がつくられていった。その後は続々と建設され、1957年に千葉火力発電所12万5000キロワット機、1960年に横須賀火力発電所26万5000キロワット機、1967年に姉崎火力発電所(千葉)60万キロワット機、1974年に鹿島(かしま)火力発電所(茨城)100万キロワット機など、大容量のものがつくられた。
日本が高度成長期を迎えた1960年代、旺盛(おうせい)な電力需要にこたえるために大型火力発電所が次々に建設され、1973年の第一次オイル・ショック前には石油火力発電が総電力量の80%にも達した。しかし、1974年、1979年の二度のオイル・ショックを経て、電源の多様化、新エネルギーの開発、原子力発電の進展により、1985年ごろから石油火力発電の割合は50%を切るようになり、燃料としては二酸化炭素CO2、窒素酸化物NOx、硫黄(いおう)酸化物SOx削減の観点から石炭火力、石油火力より環境負荷の小さい液化天然ガス(LNG)発電に中心が移りつつある。
石炭火力発電については、オイル・ショックの経験と脱硫・脱硝(硫黄酸化物や窒素酸化物を除去すること)など環境対策技術が進歩したこと、石炭の埋蔵量が豊富で供給が安定し安価であることなどから、その可能性が見直されてきている。世界的にみると主力の発電は石炭火力発電である。
[嶋田隆一]
火力発電所
火力発電所は主として汽力発電を大容量に行う設備である。ボイラー、タービン、発電機が基本となり、これにいろいろな補助設備(補機)や付属設備が設けられている発電プラントである。燃料にはLNG、重油、石炭があるが、一部には液化石油ガス(LPG)、高炉ガスや原油を用いるものもある。燃料の燃焼によってボイラーで水を加熱し、高圧200気圧付近、高温500℃程度の蒸気をつくり、これを蒸気タービンに送る。蒸気タービンでは、高温・高圧の蒸気でタービンを回し、蒸気タービンに直結されたタービン用(横軸2極機、または4極機)発電機を回転させて、電気を発生する。発電機の回転速度は、大部分が高速で小型な2極機で、東日本の50ヘルツ地域では毎分3000回転、西日本の60ヘルツ地域では毎分3600回転のものが採用されている。大容量の発電機出力は60万~100万キロワットで、水素ガスで満たして冷却する大容量の横軸高速回転機械による発電である。小容量の自家用発電でも1万キロワット以上で、発電機電圧は11キロ~24キロボルトである。この電圧は、発電所構内または発電所に接近した変電所で66キロ~500キロボルトに高められ、送電線を経て需要地域に送られる。タービンを通った蒸気は復水器に送られ、冷却されふたたび水に戻される。復水器でこの蒸気を水にするためには、大量の冷却水が必要であり、大部分は海水が用いられる。復水器から出た水は、ふたたび蒸気タービンの途中から取り出した蒸気(抽気)によって加熱され、ボイラーに送り戻される。ボイラーで燃焼した燃料の排気ガスは、煙道を通って煙突へ送られるが、煙突からの排気ガスのなかに有害な塵(ちり)を含まないようにする電気集塵(しゅうじん)機や脱硫・脱硝装置なども煙道に設置している。
火力発電所が設置される地点は、周辺に及ぼす環境面での影響が少ないように配慮するとともに、送電線に要する経費が少ないこと、燃料・資材の搬入に便利であること、とくに石炭火力発電所の場合、燃料ばかりでなく灰の搬出も必要であることから、普通は海岸に建設される。
[嶋田隆一]
百科事典マイペディア 「火力発電」の意味・わかりやすい解説
火力発電【かりょくはつでん】
→関連項目産業公害|蒸気原動所|タービン発電機|超臨界圧ボイラー|電源三法|発電
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「火力発電」の意味・わかりやすい解説
火力発電
かりょくはつでん
thermal power generation
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...