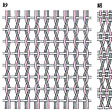精選版 日本国語大辞典 「紗」の意味・読み・例文・類語
しゃ【紗】
普及版 字通 「紗」の読み・字形・画数・意味
紗
人名用漢字 10画
[字訓] うすぎぬ
[字形] 形声
声符は少(しょう)。少に沙・砂(さ)の声がある。少は沙模様のような状態のものをいい、紗はちぢみのような絹の紗
 、またうすぎぬをいう。
、またうすぎぬをいう。[訓義]
1. うすぎぬ。
2. つむぎ。
3. かすか。
[古辞書の訓]
〔和名抄〕紗 俗に射(しゃ)と云ふ 〔名義抄〕紗 シヤ・ウスモノ・カトリ 〔字鏡集〕紗 ウスモノ・カトリ・コメ・キヌ
[熟語]
紗帷▶・紗巾▶・紗袴▶・紗
 ▶・紗紗▶・紗糸▶・紗
▶・紗紗▶・紗糸▶・紗 ▶・紗
▶・紗 ▶・紗帯▶・紗
▶・紗帯▶・紗 ▶・紗帳▶・紗灯▶・紗
▶・紗帳▶・紗灯▶・紗 ▶・紗布▶・紗帽▶・紗幕▶・紗幔▶・紗羅▶・紗籠▶
▶・紗布▶・紗帽▶・紗幕▶・紗幔▶・紗羅▶・紗籠▶[下接語]
烏紗・浣紗・巾紗・金紗・錦紗・軽紗・紅紗・絳紗・素紗・窓紗・白紗・薄紗・
 紗・氷紗・風紗・袱紗・平紗・碧紗・紋紗・羅紗・籠紗
紗・氷紗・風紗・袱紗・平紗・碧紗・紋紗・羅紗・籠紗出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「紗」の意味・わかりやすい解説
紗 (しゃ)
綟り織(もじりおり)の一種。経糸2本を組織単位とし,その一方が搦み経(からみだて)となって,他の一方の地経(じだて)の左右に搦みながら組織される織物。一般に経緯に生糸を用い,強い糊を施して織り上げ,製織後に精練,染色,仕上げを行う。紗は羅と同様に,中国においてきわめて古い歴史をもつと考えられるが,羅より一層耐久性に乏しいためか,漢から隋・唐にかけて出土する羅ほど多くの例をみない。日本では平安以降〈うすもの〉と称して,装束類の夏衣料に広く活用されてきた。無紋の紗を〈素紗〉,文様を織り出したものを〈紋紗〉といい,さらに紋紗は地を紗織とし文様を平組織とした〈顕紋紗〉と,地を平組織として文様を紗織とした〈透紋紗〉とに分けられる。また金襴の製織とともに日本でも近世以降,紗地に金糸を織り入れた〈紗金〉(金紗ともいう),多色の絵緯(えぬき)を織り入れた〈繡紗〉などが作られた。特に京都竹屋町で織製された金紗は〈竹屋町金紗〉の名で知られる。
執筆者:小笠原 小枝
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「紗」の意味・わかりやすい解説
紗
しゃ
からみ織の一種で、経糸(たていと)2本が絡むごとに緯糸(よこいと)一越(ひとこし)が交錯したもっとも簡単なからみ織組織である。一般に綜絖(そうこう)2枚と、からみ綜絖1枚を使って製織する。この紗を地として、紋を平(ひら)、綾(あや)などの組織で表した紋紗、金糸を織り込んだ金紗(京都竹屋町で織られたので竹屋町(まち)ともいう)などがある。
紗は古代に少なく、正倉院にも数点が遺存するだけであるが、時代が下るにしたがって増加し、近世初頭には中国の明(みん)の技術が移入され、堺(さかい)では金紗が生産されるようになった。紗にあたるゴーズGauzeは、小アジアの一都市名で、ここで創始されヨーロッパへ発展したという。また日本でも東北地方の「あせはじき」などの農民服に紗がみられ、プレ・インカ裂(ぎれ)にも多くみられるので、織技(しょくぎ)の発展過程で、いずれの地域でも生み出される組織であったとみられる。わが国では、盛夏の着尺地、羽織地、袈裟(けさ)地、篩絹(ふるいぎぬ)などに使われる。
[角山幸洋]
百科事典マイペディア 「紗」の意味・わかりやすい解説
紗【しゃ】
→関連項目織物|絹織物|古代裂
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「紗」の意味・わかりやすい解説
紗
しゃ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル大辞泉プラス 「紗」の解説
紗
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...

 〈サ〉薄い
〈サ〉薄い 〈シャ〉
〈シャ〉