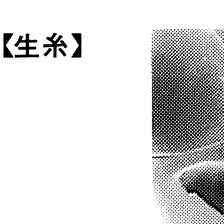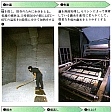精選版 日本国語大辞典 「生糸」の意味・読み・例文・類語
き‐いと【生糸】
- 〘 名詞 〙 蚕の繭をときほぐしたままの繭糸を数条合わせて糸にしたもの。
- [初出の実例]「壱口料稲壱束弐把 生糸一分二銖直」(出典:正倉院文書‐天平六年(734)尾張国正税帳)
改訂新版 世界大百科事典 「生糸」の意味・わかりやすい解説
生糸 (きいと)
raw silk
カイコ(蚕)の作る繭層から繭糸を解離し,数本以上の繭糸を抱合させつつ繰糸して得た連続する1本の糸で,撚糸(ねんし)や精練などの加工をしないものをいう。玉繭を繰った糸を玉糸というが,広義の生糸には玉糸を含めるが狭義の場合には含めない。
種類
生糸は原料の繭色によって白繭糸(白糸ともいう)と黄繭糸(黄糸ともいう)に大別されるが,現在一般に飼育されている蚕品種の繭色は白であり,大部分の生糸は白繭糸である。黄繭糸は東南アジア地域でわずかに生産されているのみである。生糸は太さ(生糸繊度という。単位デニール,略符号d)によって(1)細糸(18d以下),(2)太糸(19~33d),(3)特太糸(34d以上)に分類される。現在もっとも多く生産されているのは27dで,次いで31d,21dの順である。1個の繭から繰りとることができる繭糸の長さは,蚕品種などにより異なるが大体1000~1500m,太さ(繭糸繊度という)は2.5~3.5dである。玉糸の繊度は60d以上のものが多いが,200dをこえるものもある。生糸は繰糸方法により,器械糸,座繰(ざぐり)糸に分類されるが,現在は自動繰糸機で作られる器械糸が大部分である。また生産国により,日本糸,中国糸,韓国糸などに分類される。
構造および性質
繭糸は近似三角形の断面をもつ2本のフィブロイン繊維をセリシンが被覆する形状をなす。繭糸の主成分はセリシン(20~30%),フィブロイン(70~80%)でほぼ95%以上を占め,ほかに蠟,炭水化物などの二次成分を含む。セリシン,フィブロインともに約20種類のアミノ酸からなる高分子タンパク質である。セリシンは熱水やアルカリ水溶液に溶けるが,フィブロインは不溶性である。この相違はセリシンを構成するアミノ酸側鎖には極性基が多いのに対し,フィブロインは比較的短い側鎖からなるアミノ酸から構成されていることに由来するといわれる。生糸の触感がやや粗硬なのは,表面がセリシンによって覆われているからで,生糸をセッケンや弱アルカリ水溶液で精練するとセリシンは溶解してフィブロイン繊維のみとなる。生糸は精練により表面が平滑となり,絹特有の柔軟さ,優美な光沢,絹鳴りなどを生じる。製糸や絹加工は,前に述べた繭糸の二重構造とセリシンの熱水溶解性を巧みに利用して行われ,さまざまな絹織物が作られる。
生糸のおもな物性は次のとおりである。(1)比重は1.34~1.38で,天然繊維では羊毛とほぼ同じで,木綿より軽い。合成繊維とくらべるとナイロンより重く,ポリエステルより軽い。(2)乾強度は3.0~4.0g/d,湿強度は2.1~2.8g/dで,水にぬれると強度は低下する。また衝撃切断強度は他繊維より著しく強いが,屈曲強度や摩擦強度は劣る。(3)乾伸度は15~25%,湿伸度は27~33%で水にぬらしたときのほうが伸びが大きい。(4)ヤング率は700~1000kg/mmで衣料繊維素材としては最適な値といわれる。(5)吸湿性は20%前後で,吸放湿性能は優れている。(6)熱の不良導体で保温性に富む。(7)電気の不良導体で電気絶縁性に富むが,乾燥時には摩擦によって帯電する。(8)耐光性は弱く,とくに紫外線の影響を受けてもろくなりやすい。
検査
生糸および玉糸は蚕糸業法に基づき,農林水産省令で定められた生糸検査規則にしたがい,国の農林規格検査所,あるいは農林水産大臣が指定する検査所で検査を受けるか,農林水産大臣が指定する工場において生糸の製造者がみずから行う検査をしたものでなければ,売買取引はできないこととなっている。生糸の検査は,品位と正量について荷口ごとに行うが,品位検査は総荷および料糸検査からなる。総荷検査は生糸の総荷について荷ぞろいの状態ならびに整理欠点の有無および程度について検査され,料糸検査は総荷から抽出した料糸について,再繰切断,繊度,糸むら,強力および伸度の検査が行われ,これらの検査成績を総合し格付けされる。格付けの等級は上位から5A,4A,3A,2A,A,B,C,Dの8等級に分けられている。正量検査は荷口から所定の検査試料を採取し,これを乾燥して無水量を求め検査試料の原量に対する水分率を算出し,これを荷口の水分率とする。検査荷口の原量に水分率を乗じた積をその原量から引いて,その荷口の無水量を算出し,これにその100分の11(公定水分率)を加算したものをその荷口の正量とする。生糸の取引は,品位検査により格付けされた等級と正量検査によって得られた正量によって行われる。
執筆者:小河原 貞二
日本の蚕糸業の歴史
蚕糸業は養蚕業と製糸業(繭から生糸を生産する産業)とからなる。日本では古代以来養蚕が行われ諸国で絹が生産されたが,室町以後西陣で機業が盛んになると,その原料はほとんど中国から輸入する白糸(しろいと)に頼っていた。しかし1685年(貞享2)に江戸幕府が輸入超過を防ぐために白糸(中国産生糸)の輸入を制限したことが契機となって,衰退ぎみであった国内の生糸生産が再び発展しはじめた。とくに岩代,上野,信濃などの東山道諸国では養蚕・製糸業が勃興し,多量の為登糸(のぼせいと)を京都の和糸問屋を通じて西陣機業へ送るようになった。18世紀に入ると諸藩の国産奨励政策にも支えられて生糸生産はさらに各地へ普及し,西陣機業や地方機業へ原料糸を供給した。当時の繰糸技術は胴取や手挽(てびき)と呼ばれたごく簡単なものであったが,19世紀に入るころ糸枠の回転を歯車やベルトによって加速する座繰が発明された。生糸生産はおもに農家の副業として行われ,糸師ないし糸元師と呼ばれる商人が生糸を買い集めたが,彼らのなかには原料繭を買い集めて農家へ配り賃挽をさせる前貸問屋制を営む者もあった。
1859年(安政6)の開港は輸出向け生糸生産を激増させた。当時ヨーロッパの養蚕業が微粒子病の流行で大打撃を受けていたことも日本生糸の輸出を促進したが,L.パスツールが微粒子病を駆逐してからも安価な日本生糸の対ヨーロッパ輸出は伸び続け,さらに1884年からは新興絹織物業国たるアメリカが最大の輸出先となった。もっとも日本生糸は当初イタリア・フランス生糸に比べて品質が劣り,絹織物の横糸にしか用いられなかった。しかし明治政府は,輸出産物として最も重要な生糸の輸出検査のために生糸改所を江戸に設けたり(1868),生糸の粗製乱造を規制するために,各産地に生糸改会社を設けた(1873)。また96年には生糸輸出の拡大に伴い,農商務省のもとに横浜,神戸に生糸検査所を設け,生糸の正量,品質検査を行った。これらの結果,1900年代には縦糸用の優良な生糸もしだいに生産されるようになった。こうして日本の生糸輸出量は05年にイタリアの生糸生産量を,09年には中国の生糸輸出量をそれぞれ上回り,世界最大の輸出国としての地位を確定した。日本国内で生産される生糸の3分の2ないし4分の3が年々輸出されたが,23年の関東大震災で神戸港の生糸輸出が本格化するまでは,ほとんどの輸出生糸は横浜港経由であった。横浜には,原,茂木,渋沢,小野などの生糸売込問屋が店を構え,荷主から委託された生糸を輸出商(1910年ころから邦商取扱量が外商のそれを凌駕(りようが))へ売り込むとともに荷主に対して資金を融通した。
開港直後の生産増大は,座繰技術が岩代,上野から各地へ普及したことと,生糸生産者の増加によってもたらされた。例えば信州諏訪地方へは1860年(万延1)に上州座繰器が導入され,従来の手挽に比して労働生産性は約2倍となり,端緒的なマニュファクチュア(工場制手工業)も現れた。その後72年(明治5)開業の官営富岡製糸場や73年開業の小野組二本松製糸場などの影響を受けて,長野・山梨・岐阜3県を中心に多数の器械製糸場が設立され,79年にはその数は666に及んだ。その多くは10~30人繰の小規模マニュファクチュアで,簡易化された安価な繰糸器械を備えつけており,おもに豪農や中農によって設立された。器械製糸による生産量は94年に座繰製糸のそれを凌駕するが,座繰製糸のほうも組合製糸などの形で仕上工程を集中しつつ存続しており,その衰退は1910年代以降のことである。器械製糸場では各地の小作貧農層から出稼ぎに来た未婚の女工たちが長時間労働を強いられており,《職工事情》によれば1901年当時の諏訪地方の労働時間は〈決シテ十三四時間ヲ降ルコトナク長キハ十七八時間ニ達セル〉ありさまであった。彼女らは寄宿舎で全生活を管理され,平均繰糸成績を得た者に標準日給を与え,成績の上下によって日給に大きな格差をつけるという等級賃金制によって,長時間緊張した労働を余儀なくされた。器械製糸家は生産費の8割前後を占める原料繭の購入価格の引下げにも力を注ぎ,共同購繭を行った。こうして横浜生糸売込問屋に多額の手数料や利子をとられ,浮沈を繰り返しながらもしだいに経営を拡大する者が現れ,09年には片倉組,岡谷合資,小口組,山十組,山一林組,尾沢組の六大製糸(いずれも諏訪地方)の横浜出荷量は全体の12.6%を占め,片倉組の釜数=繰糸女工数は4282に達した。
第1次大戦を画期に日本の生糸輸出はアメリカ向けを中心に急増し,29年には約58万俵(60kg俵)と大戦前の3倍以上の水準に達し,中国その他を大きく引き離した。だが生糸価格は20年代とくにその後半にはレーヨン糸との競争も加わって低落ぎみであり,29年の大恐慌によって暴落し,34年には輸出額の首座を綿織物に奪われるに至った。この間片倉製糸(1920年片倉組を改組。現,片倉工業)や郡是製糸(1896創立。現,グンゼ)などは生糸売込問屋への依存から脱却しつつ,養蚕組合への蚕種配布による特約取引を通じて優良繭を確保して高級格生糸を生産し,大恐慌後は多条繰糸機を率先して採用することにより,靴下用の高級格生糸を独占的に供給した。こうして片倉・郡是二大資本が1920年代以降独占的な高利益を得た反面,山十組,小口組などの大資本を含む2000以上の製糸家の多くは20年代以降損失が重なり,借入先の生糸売込問屋と共倒れ的状況に陥っていく。女工の労働条件は1916年の工場法施行後もあまり改善されなかったため第1次大戦後は争議が多発し,27年には山一林組の大争議が起こった。この争議は労働者側の敗北に終わったが,同地方の女工の待遇改善の契機となった。しかし,まもなく世界的な大恐慌が襲来して倒産製糸家の賃金不払問題が新たに発生している。
執筆者:石井 寛治
現代の生糸生産
1934年には75万俵に達した日本の生糸生産は,その後第2次世界大戦などのため減少した。戦後,食糧輸入の見返物資とするため蚕糸業の復興対策がとられた結果再び増加し,70年には35万俵を超えるまで回復した。しかしその後は養蚕農家の減少により繭生産量が減少したため,95年には5万俵の生産量に落ちた。日本の生糸の需給動向は,1940年以前は生糸生産量の約70~80%が輸出,20~30%が内需にむけられており,生糸輸出が日本の経済に大きな貢献をした。しかし,第2次大戦で途絶した輸出は戦後再開されたが,かつて最大の輸出先であったアメリカにおいてナイロンが本格的な生産に入っており,生糸の主たる使途であった婦人用靴下がナイロンに取って代わられつつあったため,輸出量は期待されたほど伸びず,戦後最高の輸出量は59年の9万俵にとどまった。一方,日本経済が高度成長期に入るころから,生糸の内需が拡大しはじめ,生糸消費の過半は国内の着尺織物市場にむけられるようになり,72年には国内の絹需要量は50万俵に達するようになった。生糸消費量が国内生産量を上回るようになったことや,生糸が貿易の自由化品目となったことなどから,1963年にはじめて海外産の生糸の輸入があり,その後,輸入量は需要の増大に伴って増加し,72年には15万俵を超えるに至り,日本は世界における最大の輸入国となった。しかし,73年の第1次石油ショック以降,日本経済が低成長期に入るとともに,絹消費は大幅に減少した。政府は国内の蚕糸絹業保護の立場から,繭糸価安定法により,海外からの生糸輸入を3万俵前後に規制して需給の均衡を図りつつある。
なお世界における生糸生産量の推移をみると,戦前は1935年が最高で90万俵であったが,第2次大戦中に大幅に減少し,45年には十数万俵前後となった。しかし,その後は増加を続け,82年には100万俵を超え,95年には187万俵となった。主要生産国は中国,インド,朝鮮民主主義人民共和国,ブラジル,日本で,ほか二十数ヵ国において生産されている。
執筆者:小河原 貞二
中国の生糸
中国における生糸の歴史はきわめて古い。1926年に山西省夏県西陰村の新石器時代遺跡から繭殻が発見されているし,1958年には浙江省呉興県銭山漾の新石器時代遺跡から絹片,絹糸などが出土している。初期は野蚕を利用したものであろうが,家蚕の利用も殷代には始まっていたようである。甲骨文には〈桑〉〈蚕〉〈糸〉などの文字が見えている。周代は養蚕製糸の地域が広まったようで,《詩経》の鄘(よう)風,衛風,鄭風,魏風,曹風,豳(ひん)風などに桑,糸のことが見えるが,今日の河南・山西・山東・陝西地方にあたる。漢代に入ると,養蚕製糸の地域はさらに広まるが,《史記》貨殖列伝や《塩鉄論》本議篇によると兗(えん),豫(よ)つまり今日の山東・河北・河南地方が生糸の特産地として伝えられている。後漢から魏晋南北朝にかけては新たに四川や南方の江蘇,浙江などの地域における養蚕製糸業が発展する。唐代は生糸や絹織物が貢賦の対象とされたが,それらを負担する州郡が《大唐六典》《新唐書》地理志などに見えており,それらによると河南,河北,山南,剣南,江南の諸道が多い。ただし江南道とくに越州(銭塘江南岸の紹興などの地方)は開元年間(713-741)以降,製糸織物の技術が急速に進展したようである。
宋代には南方の生糸,絹織物の生産は北方のそれを凌駕することになる。《宋会要輯稿》に各路が負担する租税および上供の糸綿,絹織物の数量が見えているが,糸綿は租税,上供とも両浙路(今日の江蘇省南部と浙江省)が第1位である。両浙路でもとくに長江(揚子江)下流域の太湖地区が蚕糸業の中心となっている。明・清時代以後,綿花の栽培が普及するとともに,蚕糸業は地域的に限られるようになる。当時の生糸の産地として浙江・江蘇・四川・山東・河北地方があげられるが,とくに浙江の湖州,嘉興,杭州が有名である。明代繭には黄繭と白繭があり,黄繭から取った糸を黄糸,白繭から取った糸を白糸といい,白糸の方が貴ばれた。湖州,嘉興のものは白糸で,その他の地方のものは黄糸が多かった。清代は広州も白糸の産地として知られるようになる。蚕糸業は古代から清代まで,農村副業が主であった。農家は養蚕でえた繭をみずから製糸し,みずから織物としたが,唐・宋以後は製糸だけを行い,貢税を負担したり,商人に売り渡したりするようになる。
製糸には繅車(そうしや)(日本でいう座繰)を用いるが,古くは手で回転する繅車であったが,宋代には足踏式のものも現れ,生産も高まったようである。元代は足踏式の繅車も南と北で異なり,王禎《農書》に南繅車,北繅車が図説されている。清代は湖州を中心とする太湖南岸の農家は依然繅車製糸を行っているが,清代の末期には上海や広東には外商系や民族資本系の製糸工場がおこり,器械製糸が行われることになり,生糸の生産が急増するが,それとともに繭の売買も盛んになる。またとくにアヘン戦争以後,生糸は輸出品の代表的なものとなるが,輸出港は上海,広東,輸出先はイギリス,フランス,アメリカなどである。
執筆者:佐藤 武敏
ヨーロッパの生糸
古くから中国の主要な輸出品であった絹の生産方法は中国人によって厳重な秘密とされ,そのためローマの著述家の中には絹の原料を植物と考えたものさえいた。ヨーロッパに初めて持ち込まれた蚕卵は,552年にネストリウス派の僧侶が長い竹のつえの中に隠して運んだといわれる。それ以後養蚕・製糸業はビザンティン帝国からギリシアへ伝わり,イスラム教徒の手でさらに西方に伝播(でんぱ)して,10世紀ころにはスペインのアンダルシア地方がヨーロッパ随一の中心となった。しかし最大の蚕糸業国として栄えたのはイタリアであり,ピエモンテ,ロンバルディア両地方産の生糸,撚糸が名声を博した。フランスへは13世紀中ごろに移入され,16世紀末以降農学者O.deセールらの努力で大きな進歩をとげ,ローヌ川流域を中軸とした南東部一帯で生糸の生産が飛躍的発展をみた。1825-53年には全国的な養蚕ブームが展開されたが,54年以降の激しい蚕病の流行によって,フランスのみならずイタリア,スペインなどの養蚕業は大打撃を被った。日本からの蚕種輸出が重要性をもったのは,この間の66-80年ころにかけてであった。蚕病流行を境として,ヨーロッパではアジア産の生糸が大量に流入し始め,その国際的取引市場として1869年のスエズ運河開通以前にはロンドン,それ以後はリヨン,19世紀末以降はリヨンと並んでミラノが重要な役割を果たした。
ヨーロッパにおける製糸法は,18世紀までは直火で加熱される煮繭,繰糸釜と,1台の繰糸装置を用いて行う家内座繰法が一般的であった。19世紀初頭にはリヨンのジャンスールによって煮繭,繰糸釜の熱源として蒸気が利用され始め,後には綛揚(かせあげ)機の駆動などに蒸気機関も適用され,均質で上質の生糸の機械制工場生産が本格化した。より掛け装置はフランス式(シャンボン式)からしだいにイタリア式(タブレット式)に変わり,打繭・接緒作業の自動化も進んだ。撚糸工程では,13世紀にイタリアのボルゲサノの発明した水力利用のボローニャ式撚糸機,すなわち円形撚糸機が長く用いられていたが,18世紀には,フランスで改良された楕円形撚糸機が登場した。
→絹織物 →養蚕
執筆者:松原 建彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「生糸」の意味・わかりやすい解説
生糸
きいと
繭(まゆ)から繰糸したままの長い糸で、精練処理や撚合(ねんごう)などの加工をしていないものをいう。ときには2匹以上のカイコがつくった繭から繰糸した玉糸や、精練を施したものを生糸に含めることがある。この生糸は、屋内で飼育されるカイコからとれる家蚕(かさん)糸と、サクサン・天蚕・エリサンなどからとれる野蚕(やさん)糸に分けられるが、一般には家蚕糸が使われる。カイコは、鱗翅(りんし)目カイコガ科カイコガの幼虫で、桑の葉を食べて、卵・幼虫・蛹(さなぎ)・成虫の変態を繰り返し成長する。幼虫の間、4回の休眠(脱皮)を経て、繭をつくり蛹になるが、ここで熱気を当てて、蛹を殺す。
繭から生糸にする作業を製糸とよび、その工程は、乾繭(かんけん)(繭を長期にわたって保存するため、乾燥して繭中の蛹を殺す)、煮繭(繭から繭糸がよく解けるように繭を煮る)、繰糸(繭糸を数本引きそろえて糸にする)からなり、不良繭を除去後、繭糸を引きやすくするため熱湯中で煮繭し、目的に応じた糸の太さに従って繭の個数を決め、糸口を集めて1本の生糸にする。これを繰枠に巻き取ったのち、大枠に巻き返して綛(かせ)に仕上げ束装(そくそう)する。
この束装は、輸出生糸の増加とともに統一されてきたが、生糸市場においては、1綛約70グラムの綛を捻造(ひねりづくり)にし、30綛を1括(くく)りとして紙装したのち、内地向けには、約18括を1梱(こり)(10貫=37.5キログラム)として莚(むしろ)包みにする。輸出向けには、約29括を1俵(16貫=60キログラム)に洋装する。これが標準の梱包(こんぽう)方法であったが、現在では国内生産が減少して、輸入生糸に依存しているために、過去のものを示した。
製糸は、初め釜(かま)などで繭を煮ながら枠に巻き取る手挽(てび)き法によったが、巻き取りに歯車などを使った座繰(ざぐり)機が江戸後期に現れ、明治初期にはイタリア・フランスから製糸機械が輸入され、官立富岡製糸場が設置されて、生産は家内工業から工場生産へ移っていった。現在では、能率的な多条繰糸機が一般的に用いられ、また糸質の均一化を図るため、自動繰糸機も一部で使われている。
わが国における明治以後の生糸生産は、殖産興業政策による輸出産業として、東北地方から中部地方にかけて、盛んに地場産業として育成されたが、外国の生糸市場における価格の変動に、国内の製糸産業は影響を受けた。そのため購入繭価格の安定化、製糸工程の合理化、製糸労働者の確保、等級別賃金の設定などの経営合理化を進めることにより、生産原価の低廉化と生糸価格の維持を図り、外国生糸に対抗することにした。そのため第二次世界大戦前には、生糸生産高は世界一を誇ることになるが、これらは主としてアメリカに輸出され、婦人用靴下に加工された。
繰糸したままの繊維は、空気中で酸化されると表面が膠質(こうしつ)(セリシン)に包まれるため、光沢がなく、粗硬である。そのため、せっけん液などで精練し、これを除去すると、フィブロインが残り、絹独特の光沢と柔軟さが生まれるので、練糸(ねりいと)としてもっぱら使用される。
生糸は、2本の繊維を構成するフィブロインと称するタンパク質と、膠質としてフィブロインを含むセリシンというタンパク質とからなる。フィブロイン、セリシンの生糸全体に対する比は、前者70~80%、後者20~30%で、そのほか、わずかに脂肪質、無機質、色素を含んでいる。アルカリで処理するとセリシンは除かれ、2本の練絹(ねりぎぬ)となるが、この工程を生糸の精練、あるいは単に「練り」とよんでいる。繭糸の繊度は、2~4デニールで、1個の繭から製糸される長さは、短いもので600~800メートル、長いのは1200~1500メートルの連続繊維である。多数の繭を組み合わせ、繊度がそろった所定繊度の生糸を繰糸するのは、かなりの熟練を要する。生糸の繊度は、14、21、28デニールのものが多いが、要求に応じて、各種の太さのものがつくられる。
生糸の取引には、正量検査、品位検査を受ける。品位検査は、糸条斑(むら)、繊度斑、強伸度、抱合状態、肉眼光沢、手ざわり、色相などについて行う。生糸の抗張力は1デニール当りだいたい3~4グラム、伸びは20%前後、ヤング率毎平方ミリメートル当り800~1200キログラム、比重1.35、公定水分率は11%。弾性に優れ、耐熱性が大きく、発火点以後の燃焼速度はいろいろな繊維のなかでとくに小さいことが注目されるが、高価で、紫外線に弱いのが欠点である。その反面、水中に置いたとき、低温時でも性質があまり変わらないので、用途は広い。
絹織物の原糸として使用するのがもっとも多いのは当然であるが、そのほかに絹靴下などの編物や、組紐(くみひも)などの組物、琴糸や三味線糸などにも使われている。
[角山幸洋]
百科事典マイペディア 「生糸」の意味・わかりやすい解説
生糸【きいと】
→関連項目糸荷廻船|絹一揆|座繰|信達騒動|玉糸
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「生糸」の意味・わかりやすい解説
生糸
きいと
raw silk
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「生糸」の解説
生糸
きいと
蚕繭(さんけん)の繭糸(まゆいと)を数本抱き合わせて1本の糸にしたもの。ふつう撚(よ)りを加えたり,精練して膠質のセリシンを除去する前のものをいう。ただし古代には真綿を紡いだ紬糸(つむぎいと)や玉糸類が多かったようである。「延喜式」によれば全国的に生産されていたが,近世期以降は東日本が中心となった。また近世前期には絹の消費拡大を背景に京都の西陣(にしじん)などの絹織物産地が発展し,長崎や対馬などをへて中国や東南アジア産の生糸が大量に輸入された。しかしその後国内で蚕糸業が発展し,幕末開港を契機に生糸が欧米へ大量に輸出されるようになった。以後昭和戦前期まで生糸は重要な外貨獲得商品となった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「生糸」の解説
生糸
きいと
古代から絹織物の原料として生産。中国産生糸が上質とされ,室町時代以後も西陣織などは輸入生糸を使用し,常に輸入品の首位を占め16・17世紀には激増。江戸幕府は糸割符 (いとわつぷ) 制により輸入統制を行い,江戸中期以後幕府や諸藩の奨励で国内生産が増大し,地方機業も発展した。養蚕から発達して品質も向上し,幕末開港後輸出品の第1となる。明治時代以後,政府の保護で産額増大し,輸出品の主力となったが,近年化学繊維の進出で盛時は去った。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
普及版 字通 「生糸」の読み・字形・画数・意味
【生糸】せいし
字通「生」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典(旧版)内の生糸の言及
【織物】より
…勘合船は足利義政の時代に1船団3隻に制限されたが,それ以前は4,5隻から10隻という船団で,応仁の乱以前に渡明した船数は58隻に及んでいる。したがって貿易貨物も莫大な数量にのぼり,銅銭,陶磁器,香薬,染料などさまざまなものがもたらされたが,各時代を通じて大きな額を占めたのは絹織物と生糸である。《庭訓往来》は当時都をにぎわした輸入染織品として素羅,青香羅(せばら),三法紗,顕紋紗,花香羅,黄草布,上品細美(さよみ),素紗,桃花などの名をあげている。…
【五品江戸廻令】より
…この法令では,公布の理由として,諸商人が輸出品を開港場へ直送するために,江戸へ入る荷物が減少し,価格が騰貴して江戸の市民が難渋していると述べ,また,これは貿易仕法を改めるのではなく,商人が江戸問屋から荷物を買い取って貿易を行うことはさしつかえない,とも記している。しかし,主要な輸出品である生糸が五品の中に含まれていることから考えると,この法令公布の幕府の意図は,江戸問屋を中心とする旧来の流通機構が,貿易によって崩れるのを防ぐとともに,江戸問屋に価格の決定権をもたせて,貿易利潤を独占させようとした点にあったといえる。この法令を実行に移すため,江戸糸問屋は横浜に出店を設け,横浜へ入りこむ荷物を改めて,江戸からの送り状のない荷物はすべて返送させる計画をたてた。…
【鎖国】より
…それはポルトガル国王の名の下に軍事,行政,経済の全権を握る司令官(カピタン=モール)が指揮する大船によって行われる一種の官営貿易であり,1570年(元亀1)からマカオ~長崎間をもその航路の欠くことのできない一部として含みこむことになった。16世紀の30年代ごろから急激に台頭した日本産銀と中国産生糸の交易が大きな利潤を上げ始めており,それへの対応であった。イエズス会の布教資金もここから捻出された。…
【日本資本主義】より
…このような不均等発展は,産業諸部門が相互に社会的関連をほとんどもたないで他律的に発展したことによるが,それはまた大工業にとっての国内市場を狭隘(きようあい)にし,さらなる対外進出に駆りたてるものであった。日本の貿易は,(1)重化学工業製品輸入のため入超を続ける対ヨーロッパ貿易,(2)多額の生糸輸出により巨額の出超を示す対アメリカ貿易,(3)綿花,米等の工業原料,食料品の巨額の輸入のため赤字を続ける対東南アジア貿易,(4)綿製品の輸出により黒字を増大させる対東北アジア(中国,朝鮮)貿易の四つの主要局面から構成され,これを世界貿易体系との関連で要約すれば,(1)(2)の対欧米貿易では繊維原料を輸出して重化学工業製品を輸入する後進国型貿易関係をもち,(3)(4)の対アジア貿易では工業原料を輸入し綿製品を輸出する先進国型貿易関係をもつという二面性をもっていた。第1次大戦前には重化学工業の未成熟のため欧米からの輸入が増大し,また東南アジアへの工業製品輸出には大きな制約があったため,日本の貿易は絶えざる入超に悩まされた。…
【為登糸】より
…江戸時代に諸地方から京都へ送られた生糸。古代,中世にも生糸は生産されていたが,中世末には製糸業が衰え,中国産の生糸(白糸)が多量に輸入されるようになった。…
【紡績】より
…中国における材料として,絹,葛,麻,木綿,毛などがあげられよう。そのうち生糸にする技術は古くから発達したものである。 繭から生糸をとるにはまず,釜,鍋で水を沸騰させ,膠質を取り除くため繭を煮立てる。…
【和糸問屋】より
…江戸時代,京都で国産生糸を取り扱った荷受問屋。当時白糸(唐糸,輸入生糸)に対し国産生糸を和糸といった。…
※「生糸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...