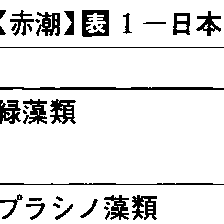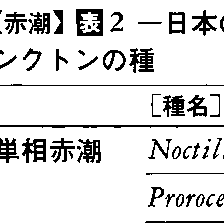赤潮(読み)アカシオ(その他表記)red tide
共同通信ニュース用語解説 「赤潮」の解説
赤潮
プランクトンが大量発生し、海水が赤褐色や茶褐色になる現象。増殖に伴い海中の酸素が不足したり、プランクトンが出す物質で魚のえらの細胞が壊されたりして呼吸困難となり大量死を引き起こすとされる。北海道の太平洋沿岸で今秋発生した赤潮は、低水温でも増殖する「カレニア・セリフォルミス」を中心に形成された。昨年10月にはロシア・カムチャツカ半島周辺で同種の赤潮が発生しており、日本では初めて確認された。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
精選版 日本国語大辞典 「赤潮」の意味・読み・例文・類語
あか‐しお‥しほ【赤潮】
- 〘 名詞 〙 プランクトンの異常繁殖によって海水が赤褐色や桃色に変色する現象。また、その海面。内湾などで多く発生し、魚介類に大きな被害を与える。三陸沖の厄水(やくみず)、東京湾の青潮、大阪湾の苦潮(にがしお)なども同様の現象。〔新しき用語の泉(1921)〕
改訂新版 世界大百科事典 「赤潮」の意味・わかりやすい解説
赤潮 (あかしお)
red tide
akashiwo
ある特定のプランクトンが短時日のうちに大増殖して,海域(主に内湾と沿岸部)や湖沼の水が色づいて見える現象。急速な大増殖blooming(bloom)は一般に異常増殖と言われることが多い。その色は赤潮を構成するプランクトンの種(しゆ)に固有の色素や生理状態によって赤褐色,褐色,緑色,黄緑色,青緑色などさまざまである。海域ではふつう赤潮と呼ばれるが,厄水(やくみず),青潮(あおしお),白潮(しろしお),苦潮(にがしお)などと呼ばれる場合もある。湖沼では水の華と呼ばれている。苦潮については,プランクトンの大増殖と関連していると考えられる極度の低酸素ないし無酸素の水塊のことをさし,赤潮とは区別したほうがよいとする見方もある。たとえば大村湾などで苦潮と呼ばれているのは,海の表層ではプランクトンの大増殖が視覚的には認められないにもかかわらず,底魚類などの斃死(へいし)や逃避現象を招くような極度の低酸素ないしは無酸素の水塊であり,三重県の真珠養殖場では,赤潮が出現する以前に低酸素の水塊が出現してアコヤガイの斃死を招くことが知られている。
赤潮などの変色現象については古くから注目されてきたが,水域の富栄養化・汚染と関連して近年とくに研究が進められている。厳密な定義はないが,細胞が比較的大型のプランクトン(たとえばオリスソディスクス,ゴニオラックスなど)の場合には100~200細胞/mlの密度で海面がやや変色したように見え,1000細胞/ml程度になると明らかに色づいて赤潮と呼ばれる状態になる。大型のプランクトン(たとえばヤコウチュウ)では103~104細胞/ml,小型のプランクトン(たとえばギムノディニウム,プロロセントルムなど)では105~106細胞/mlの密度に及ぶ場合がある。赤潮を構成する種の多くは細胞内にクロロフィルを含んでいるので,プランクトンの量を水中のクロロフィルaの量で表すと,およそ50mg/m3以上のとき赤潮と呼ばれることが多い。水中のクロロフィルa量は100mg/m3をこえて200~500mg/m3にもなることがある。
構成種
赤潮や水の華の構成種のほとんどは,光合成色素であるクロロフィルをもち光照射下で光合成を行うので分類学上は植物プランクトンとして扱われることが多い。しかし中には鞭毛をそなえてかなりの運動能力を持ち,原生動物として動物の分類表にも載っているものが相当数ある。日本の赤潮にみられる主なプランクトンの属は表1のとおりである。安達六郎(1972)は,赤潮の総細胞数の95%以上を1種類のプランクトンが占める場合を単相赤潮,その他を複相赤潮としている。日本の海域で出現頻度の高い種は表2のとおりである。湖沼の水の華を構成する代表的な属は,ミクロシスティス,アナベナ,セネデスムス,アンキストロデスムスなどである。
記録
赤潮発生に関する記録で最も古いのは,ギリシアのピュテアスPytheasによるアイスランド近海での報告(前325)であろうと言われる。旧約聖書の《出エジプト記》にはナイル川の水の赤変で魚が大量に死んだことが書かれている。日本では731年(天平3)に現在の和歌山県沿岸で海水の赤変現象が見られ,5日間も続いたことが《続日本紀》に記されている。また875年(貞観17)や1312年(正和1)の古文書にも川や海の水の赤変に関する記録が残されている。これらはいずれも赤潮に関する記録と考えられる。C.ダーウィンはビーグル号航海(1831-36)でチリおよびブラジルの沖合でラン藻トリコデスミウムなどによる海水の赤変を観察している。日本では,1890年代に静岡県海域や伊豆江の浦でのヤコウチュウの赤潮に関する論文がある。1910年前後には三重県などの真珠養殖場で赤潮によるアコヤガイの被害が問題になり,プランクトンの異常増殖が原因であるとされた。東京湾でも1907年以来赤潮の発生が報告され,湾奥部では渦鞭毛藻やケイ藻による赤潮のため魚が浮上したり斃死した記録があり,51年にはハマグリやアサリの大量死による大きな赤潮被害があった。徳山湾では1950年代後半から鞭毛藻の赤潮がほぼ恒常的に発生し,漁業被害を伴うので注目されるようになり,燧灘(ひうちなだ)では66年にミドリムシ類による赤潮が初めて発生したと報告されている。やがて赤潮の規模もだんだん大きくなり,各地で赤潮による被害が年々増加してきた。特に瀬戸内海西部では70年と72年に赤潮による養殖ハマチのきわめて大きな被害があった。
現在,赤潮の発生が毎年みられるのは東京湾,三河湾,伊勢湾,五ヶ所湾,的矢湾,英虞(あご)湾,大阪湾,瀬戸内海,大村湾などであり,内浦湾(噴火湾)のように近年になって赤潮がみられるようになった所もある。また東京湾のように冬季でも赤潮が認められる場合がある。典型的な水の華は諏訪湖,霞ヶ浦,琵琶湖などで毎年夏季にみられる。
害作用の原因
魚介類に対する赤潮の害作用の原因については,(1)窒息死,(2)中毒死,(3)その他,に分けて検討されている。窒息死については(a)水中溶存酸素の低下(赤潮プランクトンの呼吸による酸素消費,魚介類の代謝亢進による酸素不足,赤潮プランクトンの死後腐敗による酸素消費などによる),(b)水中の炭酸増加による呼吸阻害,(c)赤潮プランクトンの付着によるえら閉塞性呼吸阻害,(d)低酸素水塊からの逃避力不足,などの原因があげられるが,決定的原因とすることは困難である。中毒死については,赤潮プランクトンによる毒素産生,赤潮プランクトン死後の腐敗毒生成,赤潮発生時に繁殖する細菌の毒力などが原因とされる。毒素産生のめいりょうな報告は少ないが,ギムノディニウムからは強力な毒物質が分離され,プリムネシウム・パルブムからは魚毒イクチオトキシンと溶血作用を示すヘモリジンが,ペリディニウム・ポロニクムからは毒物質グレノジニンが報告されている。人畜に対し赤潮が直接毒作用を示して大きな問題となった例はないが,赤潮プランクトンを大量に捕食した貝類などが毒化して,それを食べた人が中毒を起こした例はある。
発生機構
赤潮の発生機構についてはいくつかの提案がなされているが,まだ完全にまとまった発生機構論は出されていない。一般に,淡水の流入する内湾や沿岸部で春から秋に発生することが多く,河川を通じて流入する都市排水と工業排水の増大に伴う水域の富栄養化(栄養塩などの増加)が基礎となり,日射,水温,塩分などの諸条件が好適となるのに加えて,ビタミン類(B12,チアミン,ビオチンなど)をはじめとする微量栄養物質や生長促進物質の効果もあって,プランクトンのきわめて急速な増殖が行われるものと推定される。大村湾などで降雨性赤潮と呼ばれているものでは,6月の降雨によって供給された多量の各種栄養物質が適度に希釈され,その他の条件が好適であれば,プランクトンの急激な大増殖が行われると考えられている。また無酸素化関連赤潮と呼ばれるものは9月に発生が認められ,底層の低酸素水ないしは無酸素水を通して海底から増殖促進物質が供給されることによりプランクトンが好適条件をそなえた亜表層で急速に増殖し,表層に集積するという機構が提案されている。
防除対策
現在のところ赤潮に対する有効な防除法はないが,基本的には水域の富栄養化をもたらす栄養塩,微量栄養物質,生長促進物質などの供給を少なくすることが必要不可欠である。そのため公害対策基本法(1967),海洋汚染防止法(1970),瀬戸内海環境保全臨時措置法(1973)などによって排水基準が示され,富栄養化防止,汚染防止のための法的措置がとられた。また県条例によって,富栄養化の原因となるリンの供給を少なくするためリンを含む洗剤の使用などを禁止している場合もある。
→プランクトン
執筆者:有賀 祐勝
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「赤潮」の意味・わかりやすい解説
赤潮
あかしお
red tide
海水中で浮遊生活している生物(プランクトン)の大量繁殖や集積によって、海水の色が平常時と異なって着色する現象。湖沼に生じる同様の現象は淡水赤潮とよばれる。呈色状態は、生物の種、活性、密度によって多様であり、色合いの違いから、白潮(しろしお)、青潮(あおしお)、緑潮(みどりしお)とよばれることもある。また、赤潮が水産業に大きな被害を与えるところから、厄水(やくみず)、薬水(やくみず)、くされ潮、苦潮(にがしお)などともいわれ、地方固有の呼び方も多い。ただし、苦潮などは生物そのものによって生じたというよりも、海底近くにあった貧酸素水塊が海面近くに湧出(ゆうしゅつ)したものである。外国でも同じ意味の名称がつけられている。赤潮は昔からおきており、その現象は人々に強い印象を与えたと考えられ、「海が血に染まった」といった類の伝説はこれをさしていることが多い。
[佐野 昭・高橋正征]
原因と生成
赤潮の原因となる生物は以下のように三つに大別できる。
(1)珪藻(けいそう)・藍藻(らんそう) これらは葉緑素をもち光合成によって無機物を有機物化する純粋の光合成独立栄養生物で、これらによる被害は少ない。しかし、羽状珪藻や藍藻のなかに毒物を含むものが知られるようになり、人間、家畜、魚貝類に被害が出ている。
(2)鞭毛藻(べんもうそう)・鞭毛虫類 鞭毛藻は光合成を行うが、溶存有機物を必要としたり、鞭毛を用いて運動し、動物的な生態をあわせもつ光合成生物である。鞭毛虫類は分類学上は鞭毛藻に含まれるものが多いがクロロフィルをもたず光合成は行わない。毒性をもっていたり、魚のえらをふさいだりして、魚貝類に直接被害を与える赤潮の原因となることが多い。
(3)原生動物・甲殻類など これらによる赤潮は被害をおこすことはほとんどなく、むしろ食物連鎖の過程で有用な位置を占めている。
赤潮の原因となる生物、とくに光合成を行う種が大増殖するには、水塊が成層していて上下の対流が少なく、真光層に栄養塩類が豊富で、光の強さと波長、水温、塩分がその種にとって適度であることが必要である。温帯地方では春から初夏にかけての海がこれに該当する。とくに梅雨後に晴天が続くと赤潮が発生しやすい。これは、陸地から栄養塩類が補給されるとともに、増殖条件が強化されるためである。増殖した生物が海流、潮汐(ちょうせき)流や風の影響で集積したり、走光性など生物自体の運動で集合すると赤潮現象は顕著になる。
赤潮は条件が整えば自然に発生するが、近年では内湾や沿岸で多発している。その背景にはその海域の富栄養化がある。常時栄養塩類が補給されるため植物プランクトンが継続して増殖し、ある種の金属類や有機物の補給は鞭毛藻や鞭毛虫類の増殖を促す。また富栄養化という環境変化に伴って生物相が変わり、従来は認められなかった生物が赤潮化して猛威を振るうこともある。1972年(昭和47)、1977年、1978年に瀬戸内海播磨灘(はりまなだ)で養殖ハマチに大被害を与えたシャトネラ(通称ホルネリア)赤潮はその例である。1980年代ごろから国内外で発生する赤潮には、オイルタンカーのバラスト水などとともに海外から持ち込まれて起こる外来性赤潮の可能性が指摘されている。
[佐野 昭・高橋正征]
被害と対策
赤潮の発生はさまざまな被害をもたらす。鞭毛藻には有毒種が多く、魚類を斃死(へいし)させ、また有毒化した魚貝類を食べた人間が中毒したりする。人間の粘膜を刺激するガスを発生し、熱病の原因となる種もある。無害種でも魚貝類のえらに付着して窒息死させることがある。赤潮生物が急激に大量死すると、有毒細菌が繁殖したり、酸化分解のために水中の酸素が欠乏して魚貝類を斃死または逃避させる。
播磨灘のシャトネラ赤潮による被害額は1972年が70億円以上、1977年、1978年がともに20億円以上に上った。1984年には熊野灘にギムノジニウムによる赤潮が発生し46億円相当の被害を与えた。1988年以降はシャトネラ赤潮は減少し、ギムノジニウム赤潮の発生が目だっているが、赤潮全般の被害は減少の傾向にある。
赤潮対策として、薬品散布による死滅、粘土を用いる強制沈殿、ポンプによる回収などの方法がある。発生の予測や監視によって養殖魚を退避させることもある。しかし、抜本的には、過剰な栄養塩類、有機物、金属などの補給を防ぐことが必要であり、現在では、法律とそれに基づく自治体の条例によって規制され、廃水処理の技術も向上しつつある。また、交易の活発化に伴い、生物の伝播(でんぱ)も活発化して、赤潮の広域拡大が問題となっている。とくに、有毒物質を含む赤潮では問題が深刻である。
[佐野 昭・高橋正征]
『岡市友利編『赤潮の科学(第2版)』(1997・恒星社厚生閣)』▽『日本水産学会編『赤潮――発生機構と対策』(2007・恒星社厚生閣)』▽『今井一郎著『シャットネラ赤潮の生物学』(2012・生物研究社)』
百科事典マイペディア 「赤潮」の意味・わかりやすい解説
赤潮【あかしお】
→関連項目ウズオビムシ|大発生|苦潮|水汚染|ヤコウチュウ(夜光虫)
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「赤潮」の意味・わかりやすい解説
赤潮
あかしお
red tide
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
ダイビング用語集 「赤潮」の解説
赤潮
出典 ダイビング情報ポータルサイト『ダイブネット』ダイビング用語集について 情報
海の事典 「赤潮」の解説
赤潮
出典 (財)日本水路協会 海洋情報研究センター海の事典について 情報
サーフィン用語集 「赤潮」の解説
あかしお 【赤潮 Red Tide】
出典 (株)デジサーフ、(株)セキノレーシングスポーツサーフィン用語集について 情報
栄養・生化学辞典 「赤潮」の解説
赤潮
世界大百科事典(旧版)内の赤潮の言及
【藻類】より
…プランクトン性の藻類や定着性の微細な藻類は稚魚貝や動物プランクトンなどの餌料として食物連鎖のうえで重要な位置を占める。ところで,ラン藻,ケイ藻,渦鞭毛藻などのプランクトン性藻類は環境が変化すると突然異常に大発生して,海では赤潮を,湖や池では水の華と呼ぶ現象を起こすことがある。赤潮や水の華は,水界の物理化学的性質をさらに急変させ,魚貝類を死滅させるなど,しばしば大きな被害をもたらす。…
【大発生】より
… 魚の大発生は豊漁と呼ばれることもあり,その結果,時には大量死亡も起こりうる。赤潮は,海や湖,沼や池などの水域に植物または動物プランクトンが大発生した場合の総称で,水の華とか,色によっては青潮またはアオコとも呼ばれる。この現象は,その水域の富栄養化によって起こり,ひどい場合には魚や貝の大量死亡をまねくこともある。…
【プランクトン】より
…鉛直移動の結果として,表層で生産された有機物が短時日のうちに深層に輸送されることになり,海洋の物質循環に大きな役割を果たしている。
[赤潮]
沿岸域の富栄養化した海域では,しばしばプランクトンが大増殖し,そのために海水が着色することがある。これを赤潮と呼ぶ。…
【水の華】より
…また季節的にも夏から秋にかけてみられることが多い。植物プランクトンが異常発生すると,水面近くは溶存酸素が過飽和となり,深いところでは酸素が欠乏してくるので,生息している魚類などに影響を起こし,この点では海に赤潮が発生するのとよく似ている。局地的に発生することが多く,大きな川のよどみになったところや小さな湖水や池などによく見られ,日本では平地の淡水に見られるのが普通である。…
※「赤潮」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...