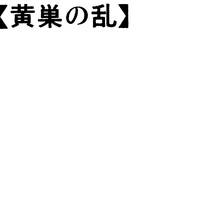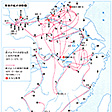精選版 日本国語大辞典 「黄巣の乱」の意味・読み・例文・類語
こうそう【黄巣】 の 乱(らん)
改訂新版 世界大百科事典 「黄巣の乱」の意味・わかりやすい解説
黄巣の乱 (こうそうのらん)
中国,唐末の民衆反乱。黄河流域から広東に至る広大な地域を舞台として戦われ,唐朝滅亡の原因となっただけでなく,中国史上大きな画期をもたらした。
3世紀以来発達をとげてきた貴族政治は,8世紀半ばの安史の乱を契機に大きく様相を変えた。傭兵部隊を基礎とする節度使権力の出現,両税法・専売法など新税制の導入,またそれらの背景となった交換経済の発展等々が時代の変化を特徴づける。唐朝は江淮(こうわい)地方を主要な財源地帯として国運の維持を図ったので,9世紀になると政治矛盾はこの地方に集中するようになった。黄河・淮河・長江(揚子江)と大運河とが交わる地域は,専売品である茶・塩の密売人や亡命軍人など反政府勢力が暗躍し,浙江の裘甫(きゆうほ)の乱,徐州の龐勛(ほうくん)の乱などの地域的反乱をひき起こした。こうした情勢が全国的な暴動と化したのが,黄巣の乱である。
指導者黄巣は塩の密売を生業とする俠客で,科挙試験に失敗して腐敗した唐朝への反逆の意志を強めたといわれる。874年王仙芝に呼応して挙兵,山東・河南一帯の州県を襲い,その勢力は日を追って拡大した。最初洛陽占拠をねらったが果たさず,南下作戦をとってついに福建から広州に入った。ここで軍を整えたのち,数十万の勢力をもって北上,880年(広明1)洛陽を占領し,同年長安に入城して黄巣を皇帝として大斉国を建てた。唐の僖宗は一時成都に避難したが,勝利に酔う反乱軍が無秩序におちいったところを唐側の包囲反撃にあい,黄巣は長安を放棄して河南方面に脱出,884年(中和4)追いつめられて郷里山東で自決した。こうして11年にわたる乱は終わったが,唐側の成功は黄巣から離反した朱温(全忠)や唐朝が投入した沙陀(さだ)族(トルコ系)の李克用らの力に負うところが大きく,乱後はこれらの勢力や乱を契機に自立した各地の新興勢力が互いに覇を争い,五代十国時代に移行した。貴族政治はここに最後的な終末を迎える。黄巣の乱の特徴は縦横に転攻して相手の弱点をつく流動作戦にあり,その後のいわゆる流賊の源流をなす。その理念に平均思想が見られることも注目される。
執筆者:谷川 道雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「黄巣の乱」の意味・わかりやすい解説
黄巣の乱
こうそうのらん
中国、唐末約10年(875~884)にわたる農民大反乱。唐朝は9世紀以後、牛・李(り)両派の党争でその官僚支配を弱め、宦官(かんがん)層がこの党争を利して軍事力を背景に実権を握り、地方藩鎮(はんちん)は中央勢力を動かして自立に努めた。憲宗の武力による対藩鎮強硬策から、歳入不足は恒常化し、賦税や塩、茶の専売による収奪が激しくなり、富商や土豪は土地を集積し、政府の特権商人や藩鎮の将校、軍人、下級役人になって国家の収奪を免れた。他方、中小の農民は窮乏し、新興の地主層の下で小作人、農業労働者となり、また流民化して群盗となった。とくに専売税の増加で塩、茶が高価になると、塩賊、茶賊とよばれた闇の塩、茶の商人団が現れ、なかでも揚子江(ようすこう)を挟んで南北に活動した江賊がもっとも大規模であった。
王仙芝(おうせんし)、黄巣はいずれも山東の塩賊で、黄巣は読書人でしばしば進士にあげられたが及第できず、貴族官僚支配に反感をもっていたという。裘甫(きゅうほ)、龐勛(ほうくん)の乱が相次ぎ、年少の僖宗(きそう)が宦官に擁立されて世情が動揺し、さらに飢饉(ききん)で窮迫した農民が群盗化して各地に蜂起(ほうき)した。この情勢下に反乱した王仙芝、黄巣らは、争って参加する民衆とともに流賊化してたちまち山東10余州を寇掠(こうりゃく)し、強大な下克上的風潮を醸成した。王仙芝の死後、一時、唐朝軍に敗れて福建から広州に退き、ここから風土病を避けて北上し、黄巣は自ら天補平均(均平)大将軍と称したというから、均平な小農民の世界を理想としていたのであろう。彼は王仙芝の残党をもあわせて880年洛陽(らくよう)、長安両都を陥れ、国を建てて大斉と号し、年号を金統と称したが、財政基盤を欠き、統治の能力、経験も乏しかった。地主層による郷村防衛軍や、唐朝の召用した突厥(とっけつ)沙陀(さだ)族の李克用(りこくよう)の精鋭な騎馬軍の攻撃に敗れ、有力部将朱温の寝返りもあり、長安から退却、東走して山東の泰山付近で敗死した。黄巣の乱は唐の滅亡、中国の貴族官僚支配の崩壊の最大の契機となった。唐朝に降った朱温はただちに黄巣討滅に活躍し、全忠の名を賜り、直接唐を滅ぼして五代の最初の王朝である後梁(こうりょう)を創建した。
[松井秀一]
『堀敏一「黄巣の叛乱――唐末変革期の一考察」(『東洋文化研究所紀要』第13冊所収・1957・東洋文化研究所)』▽『松井秀一著『唐末の民衆叛乱と五代の形勢』(『岩波講座 世界歴史6 古代6』所収・1971・岩波書店)』▽『谷川道雄・森正夫編『中国民衆叛乱史1 秦~唐』(平凡社・東洋文庫)』
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「黄巣の乱」の意味・わかりやすい解説
黄巣の乱
こうそうのらん
Huang-chao zhi luan; Huang-ch`ao chih luan
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「黄巣の乱」の解説
黄巣の乱(こうそうのらん)
Huang Chao
唐末の875~884年に起こった農民反乱。黄巣はその指導者で,科挙の落第生,富裕な塩の闇商人で,多数の侠客(きょうかく)を養っていた。当時塩,茶の闇商人は政府の弾圧に抗して武装しており,政府の重税,特権商人の圧迫で没落する農民の反抗と結びつくことが多かった。反乱は仲間の王仙芝(おうせんし)の挙兵に始まり,黄巣がこれに応じ,各地の群盗,農民を結集して大きくなった。初め山東,河南を荒らしまわったが,王仙芝が投降を試みたので黄巣はこれと分かれ,王仙芝が殺されてから江南,福建をへて広州を陥れた。それより北上して荊州(けいしゅう)から長江にそって下流に出,淮河(わいが)を渡り,天補平均大将軍と称して洛陽,長安を陥れた。帝位について国を大斉(だいせい)と号したが,補給を絶たれて分裂が起こり,長安を撤退して河南に出たが,李克用(りこくよう)の軍に敗れて泰山で自殺した。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
百科事典マイペディア 「黄巣の乱」の意味・わかりやすい解説
黄巣の乱【こうそうのらん】
→関連項目朱全忠|西夏|節度使|タングート|唐
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「黄巣の乱」の解説
黄巣の乱
こうそうのらん
黄巣(?〜884)は山東の塩密売人で,875年王仙芝 (おうせんし) の乱に呼応して挙兵。王の敗死で残党を集めて大勢力となり,四川以外の全中国を荒らした。880年洛陽・長安を陥れて帝位につき,大斉国と号したが,官軍の反攻を受けて敗走中,部下に殺されて乱は平定された。この乱で唐の統一は解体し,乱の鎮定に活躍した藩鎮勢力が強大となり,黄巣の部下で唐に寝返った朱全忠が唐を滅ぼし,中国は五代十国という分裂の時代をむかえた。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の黄巣の乱の言及
【五代十国】より
…五代十国期の〈武人支配〉は,この〈唐宋変革〉の過渡期としての性格を示す一指標である。この時期の〈武人支配〉は,直接的には唐末の黄巣の乱に起因する。唐を滅ぼし五代最初の後梁朝をたてた朱全忠は,黄巣軍の中心的部将であり,唐側に投降してその恩賞として節度使に任ぜられた。…
【唐】より
…これが唐の高祖であり,ここに唐王朝が成立した。唐朝は,黄巣の乱後に黄巣の部下であった朱全忠に禅譲させられるまで,およそ290年の命脈を保ったが,8世紀半ばに起こった安史の乱ごろを境として,前半期と後半期とではあらゆる局面で性格を異にする。前半期は隋に引き続き律令体制の社会であった。…
※「黄巣の乱」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...