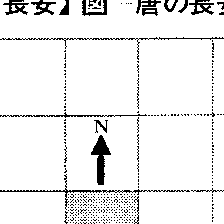精選版 日本国語大辞典 「長安」の意味・読み・例文・類語
ちょうあんチャウアン【長安】
- [ 一 ] 中国、陝西省西安市の古名。漢・隋・唐など、多くの王朝の都となり、特に唐の盛時には東西九・七キロメートル、南北八・六キロメートルの城郭の内に都市が計画的に建設され、人口一〇〇万を擁する世界最大の都市として繁栄した。東都洛陽に対して、西都あるいは上都とも呼ばれた。
- [ 二 ] ( 中国、唐代の首都長安を模して造られたところから ) 平安京の称。
- [初出の実例]「長安城の遠樹を望めば、百千万茎の薺青し〈源順〉」(出典:和漢朗詠集(1018頃)下)
- [ 三 ] 平安京の朱雀大路から西側、右京の称。
- [初出の実例]「朋旧誰来破二閑寂一、乱山西尽是長安」(出典:六如庵詩鈔‐二編(1797)一)
改訂新版 世界大百科事典 「長安」の意味・わかりやすい解説
長安 (ちょうあん)
Cháng ān
西安の旧名で,中国の代表的な古都の一つ。陝西省渭河平原の中部に位置し,北は渭河に臨み,南には秦嶺がつらなり,西には灃水(ほうすい)が流れ,東には滻河と灞河がある。前漢が初めて城を築いて都とし,その後,前趙,前秦,後秦,西魏,北周,隋,唐の諸王朝いずれもここに都した。ただし前漢から北周までの長安城は今日の西安市の北西約10kmのあたりに,隋・唐の長安城(隋は大興城という)は西安市のあたりにあった。
西安市の周辺は早くから開発されたところで,今日,仰韶(ぎようしよう)文化や竜山文化に属する新石器時代の遺跡がかなりの数発見されている。とくに有名なのは西安市の東郊滻河東岸の台地上にある半坡(はんぱ)の仰韶文化の遺跡で,西安半坡博物館には村落のあとや出土の石器,骨器,陶器などが展示されている。歴史時代に入ると,周は西安市の西の豊や鎬に都しているし,秦は西安市の北の咸陽(今日の咸陽市の北東)に都している。前漢は高祖の5年(前202),婁敬(ろうけい)の上奏にしたがって長安に都することに決定,長楽宮,未央(びおう)宮などの工事を進め,次の恵帝のとき城牆(じようしよう),城門を設け,恵帝の5年(前190)完成している。
漢の長安城の全体の形は不整形で,東が5940m,南が6250m,西が4550m,北が5950mである。東が真直であるほか,すべて曲折がある。城門は1面3門,4面で12門あったが,各城門は3道になっていた。城内の大道は八街九陌(きゆうはく)と呼ばれ,これらの大道も3道に分かれていた。3道の中央部分が馳道つまり皇帝の車馬の専用道路である。城内は里に区画され,《三輔黄図》によると160あったという。里もそれぞれ牆垣でかこまれ,その内部は巷で区切られていた。長安城の主要部分は宮殿であるが,南東部に長楽宮,南西部に未央宮があり,建築物は未央宮の方が多かった。官庁は未央宮の内外に点在していたようである。城内の人口は10余万くらいと思われるが,長安城とその周辺は三輔と呼ばれ,首都圏をなし,三輔全体では人口もかなり多かったようである。経済の中心である市場は《三輔黄図》では9市あったとしているが,それらはほとんど城外にあったようである。
隋の文帝開皇2年(582),漢城とは別の地点に新しい都城を営むことになり,その年6月工事に着工,翌3年3月皇帝は新しい都城つまり大興城に入っている。工事期間が短いが,隋から唐にかけていくたびか改修工事を行っている。大興城は東西18里115歩,南北15里175歩の大きさで,城牆の高さは1丈8尺,城内に110坊あったという。唐の長安城はこれをうけついだものである。その形は東西が南北よりやや長い長方形をなしている。実測の結果を見てみると,東西は9721m,南北は8651.7mである。まわりを囲む城壁は版築でつくった土牆である。高さはまちまちであるが,一般的に0.7mから1.5mである。城壁の各面には城門が設けられ,東,南,西面にはそれぞれ3門,北面は中央部に宮城などがあるため9門あったようである。
隋・唐長安城の設計で一つの大きな特色は,それまでの都城と相違して宮城,皇城が中央北辺に位置している点にある。宮城は太極宮,東宮,掖庭(えきてい)宮の総称で,その大きさは東西が2820.3m,南北が1492.1mとなっている。太極宮は宮中の正殿で皇帝の居住する宮,東宮は皇太子の居住する宮,掖庭宮は皇妃,宮女などの居住する宮である。ただ高宗のときから皇帝は城の北東の大明宮に居住するようになったため,太極宮は西内,大明宮は東内と呼ばれ,玄宗のときに興慶坊につくられた興慶宮の南内とあわせて三大内と呼ばれた。太極宮は南面中央に承天門があり,この門で詔令を発布したり赦宥(しやゆう)を行ったりするので前朝と称されたが,この門の次に嘉徳門があり,つづいて太極殿に達する。ここは皇帝が政治をみるところである。その近くには門下省,中書省などの官庁も設けられている。
宮城の南に横街をはさんで皇城の地域がある。その形は長方形で,東西は宮城と同じく2820.3m,南北は1843.8mである。皇城内には東西に走る街が7条,南北に走る街が5条あり,こうした街に沿って官庁が並んでいた。宮城,皇城が漢城と同様主要部分をなし,長安は政治的都市であるといえる。それ以外が官吏,商工業者その他が住む地域である。街道が縦横に規則正しく走り,南北11条,東西14条となっている。とくに北は皇城の朱雀門から南は外郭城の明徳門まで南北に走る幹線道路が朱雀街(別に天街という)で,150mから155mの道幅があり,これを境として東が万年県,西が長安県に属していた。城内の都市区画は坊と呼ばれ,記録によって坊数が異なるが,たとえば《大唐六豊》では皇城の南は東西10坊,南北9坊,皇城の東西は各12坊となっている。ほかに東西の両市が4坊の地を占めている。これらの坊には塀がめぐらされ,塀には門が設けられていた。そして坊門は夜間閉められ,一般の交通はできなくなっていた。なお長安城の南東部は土地が高く,住むのに不便であるところから,曲江池や芙蓉園などが設けられていた。
長安城の人口は,時期により変動はあるが,だいたい100万あるいはそれ以上と考えられている。ただ東の万年県が西の長安県より人口が少なかったと思われる。というのは,万年県には公卿以下勲貴のものが多く住み,長安県には一般庶民が多く住んでいたからである。地形も南東部が高く,北西部がしだいに低くなっている。人口が最も密集していたのは万年・長安両県を通じて市に近い地域である。長安城は政治的都市といっても経済的機能も有し,市がその中心的役割を果たしていた。東西の両市が主要な市で,東市は隋の都会市,西市は隋の利人市をうけついだものである。調査の結果によると,東市の大きさは南北1000余m,東西924mで,四面は牆に囲まれ,内部は東西,南北にそれぞれ二つの街道が走り,井字形をつくる。西市の大きさは南北1031m,東西927m,東市と同様牆に囲まれ,内部は井字形をなす。つまり東市西市とも九つの長方形から成り立ち,中央の区画には市を管理する市署,平準署などが設けられていた。
他の長方形の区画にはさらに巷道があり,それに沿って肆(し)が設けられた。肆は商品の種類ごとに列をなしていた。また同業者は行(こう)という団体を結成していた。たとえば東市には肉行,鉄行,西市には絹行,薬行などが見えている。こうした行肆(こうし)と並んで経済的に重要な役割を果たしたのは邸店である。これは市の四壁に沿い,市をつつむ形で配置されていた。邸店の機能は旅宿,飲食,倉庫などで,遠距離通商を担当する客商,任地往復の官吏たちによって利用された。
長安の市には胡商と呼ばれる外国商人も多く集まった。太宗の貞観5年(631),突厥(とつくつ)を平定したとき,中書令温彦博の議にしたがい,突厥人を河南,朔方などにうつしたが,長安にも万家近くがやってきたとされ,代宗の大暦14年(779),ウイグル人の長安にとどまるもの1000人におよんだとされている。その他の国の人たちも長安にやってきているが,多くは商人で,とくに西市に住んで肆を営むものもあらわれた。文献には珠宝商や高利貸をしていた胡人が見えるし,胡商によってもたらされたと思われるペルシアのササン朝の銀貨,東ローマ帝国の金貨が西安の近郊から出土している。飲食店を営む胡人もおり,唐代,饆饠,焼餅,胡餅などの胡食が中国に伝えられた。また西域の酒,たとえば高昌のブドウ酒,ペルシアの三勒漿,竜膏酒などが喜ばれ,長安にはこうした酒を取り扱う胡人の肆があり,胡姫つまりイラン系の女子がサービスをしていたことは李白の〈少年行〉の詩などによって知られる。
長安はまた当時,世界における文化の中心地の一つでもあった。宗教についていうと,長安の城中にはいたるところ寺院が点在していた。《両京新記》によると,僧寺61,尼寺27,道士観10,女観6となっており,他に波斯寺2,胡祆祠(こけんし)4があったという。玄宗の天宝年間(742-755)以後はさらに増置されたようである。こうした寺院の中にはきわめて大規模なものもあり,大興善寺は靖善坊の地全部を占め,大薦福寺は開化坊の南半分を占めていた。これら寺院の創設や維持の主体になったのは皇族や貴族たちであったが,唐代,経師,覆講師,邑師,説法師,遊行僧などがあらわれ,民衆の教化,救貧,救病などの社会事業にのり出した。また唐代,景教(ネストリウス派),祆教(ゾロアスター教),摩尼(マニ)教なども入り,それら三つの宗教の寺院は三夷寺と称された。これらは仏寺や道観に比べると少なかったが,長安の国際色を物語るものであった。
娯楽施設としては太常寺,梨園,教坊,妓館,戯場などが著名である。太常寺,梨園,教坊は宮廷の楽舞施設であり,妓館,戯場は民衆の娯楽施設である。妓館の中心をなしたのは東市の近くの平康坊にあった北里である。戯場は大慈恩寺,青竜寺,大薦福寺,永寿寺など大きい寺院の境内や門前を利用したもので,ここでは呑刀,吐火,弄丸,舞剣の諸技をはじめとして縄(綱渡り),竿技(長竿の頂上で軽業を演ずるもの)など西域の特技で西域風の濃いものが演ぜられたりした。
このように長安は隋・唐の都城であっただけでなく,経済や文化の中心地でもあり,各国から多くの人たちが集まった。長安の都市形態,政治制度,経済,文化はとりわけ周辺諸国に大きな影響を与えた。しかし安史の乱後,長安はしだいに衰微し,とくに唐末,朱全忠によって長安城内のおもな建築物がほとんど破壊された。昭宗の天祐元年(904),韓建が新城を築いたが,皇城を中心とした小規模なもので,その後明の洪武のはじめ都督の濮英が長安城を増修し,今日残っている城牆は当時のものである。
執筆者:佐藤 武敏
漢唐長安の遺跡
前漢代の大型墓は帝陵とともに渭河北岸にある。そのうち長陵陪葬の楊家湾4・5号墓には貴族邸宅を模したと考えられる大型木造墓室があり,隋葬坑からは2500体にのぼる騎兵,歩兵軍団俑が発見された。茂陵陪塚の1号無名墳の1号隋葬坑には〈陽信家〉(武帝の姉,陽信長公主家)銘をもつ多数の豪華な器物があった。長陵付近発見の〈皇后之璽〉玉印や茂陵,渭陵付近発見の玉彫品などとともに前漢代貴族社会の豪華な生活をしのばせる。西安周辺では高窰村から〈上林〉〈南宮〉などの宮殿銘をもつ多数の青銅容器が発見され,武帝経営の上林苑の一端を示す。苑内には鉄農具の窖蔵(こうぞう)もあった。長安県洪慶村出土の鉄歯車,西安東郊灞橋前漢墓発見の世界最古の紙などは前漢代科学技術の様子を示している。南北朝時代,長安はたびたび北朝の都となったが,その間の資料はわずかに夏の真興6年(424)銘の石馬と石仏像のみである。隋・唐時代,長安は再び全国統一王朝の帝都として繁栄した。隋・唐代の墓地は西安市の東西郊外で多数発見されている。なかでも精巧な家形石棺と豪華な金,銀,ガラス器をもった隋文帝の曾孫李静訓墓(608・大業4),高松塚古墳と同笵の海獣葡萄鏡をもつ独孤思貞墓(698・聖暦1),多数の精美な唐三彩俑を出土した鮮于庭誨墓(723・開元11)などは紀年が明確で豊富な副葬品をもった高級貴族墓である。西安市何家村の窖蔵からは多数の金銀器とともに和同開珎,ビザンティン,ササン金銀貨が発見され,世界都市長安の様相をしのばせる。また長安城中には多数の仏寺が栄えたが,日本の空海らも学んだ青竜寺址が発掘され,東西に並んだ塔と金堂址が発見されている。安国寺址窖蔵出土の白大理石仏像もあわせ盛時をしのぶことができる。
執筆者:秋山 進午
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「長安」の意味・わかりやすい解説
長安
ちょうあん
西周、秦(しん)、前漢、新、前趙(ぜんちょう)、前秦、後(こう)秦、西魏(せいぎ)、北周、隋(ずい)、唐の11王朝が都した中国第一の古都。現在の陝西(せんせい)省西安(せいあん)。漢、唐代にもっとも繁栄したが、唐代には東都洛陽(らくよう)に対して西都(せいと)または上都とよばれた。中国西北地方にある関中平野のほぼ中央部に位置する。
西周の都鎬京(こうけい)の遺址(いし)は、現西安市南西郊に位置する。また、秦の咸陽(かんよう)宮址は北西方の渭河(いが)北岸にあり、阿房(あぼう)宮址は西郊に現存する。前漢の長安城は、市の北西郊、渭河の南に位置し、宮殿の基壇や版築(はんちく)の城壁の一部は、現在、地上にその姿をとどめている。周囲に城壁を巡らし、12の城門をもつ城内には、長楽宮、未央宮(びおうきゅう)などの宮殿が造営され、市(いち)や居住区が設けられた。総面積36平方キロメートルに及ぶ漢長安城は、武帝の時代にほぼ完成をみた。この都城は王莽(おうもう)時代の農民反乱によって破壊されたが、その後、五胡(こ)十六国および北朝の諸王朝はいずれも漢長安城の位置に宮都を構えた。なお、前漢の帝王陵は、渭河の北に広がる渭北丘陵と、西安市南東の白鹿原(はくろくげん)上に造営された。
582年、隋の文帝は宇文愷(うぶんかい)らに勅して、漢城南東の竜首原(りゅうしゅげん)に新都を造営し、これを大興城(だいこうじょう)と名づけた。唐長安城はこの大興城を修築したもので、都城の基本的構成に大きな変化はなかった。その規模は東西9.7キロメートル、南北8.6キロメートルの横に長い方形で、北辺中央に宮城、皇城を配し、城内中央を南北に幅150メートルの大路があり、この大路を中心に大小の道路が東西・南北に走って碁盤目状の街区を構成していた。長安城外北東には太宗・高宗の大明宮が、また玄宗(げんそう)は城内に興慶宮を造営した。さらに南東隅の曲江池は遊宴の地として知られていた。城内は109の坊に分かれ、坊内には住宅のほかに仏寺、道観、イスラム寺院などが点在していた。また、東西両市には各種商店や旅宿、飲食店などが軒を連ね、各地の商人や旅人たちで大いににぎわった。当時長安は、東アジアのみならず世界各地の国々との交流の中心地であり、西域の隊商や周辺諸国の人々が頻繁に往来した。日本からも遣唐使や留学生、留学僧がしばしばこの地を訪ねた。唐都長安は玄宗時代に最盛期を迎え、人口100万人を擁する国際色豊かな文化都市となったが、その後、唐朝の衰微とともに凋落(ちょうらく)の道をたどった。
唐朝滅亡以後、長安はふたたび国都となることはなく、長く一地方都市にすぎない存在であったが、新中国の誕生によって復興し、陝西省都の西安として、政治、経済、文化の中心となっている。
[田辺昭三]
『佐藤武敏著『長安』(1974・近藤出版社)』▽『田辺昭三著『西安案内』(1979・平凡社)』▽『西嶋定生編『奈良・平安の都と長安』(1983・小学館)』
百科事典マイペディア 「長安」の意味・わかりやすい解説
長安【ちょうあん】
→関連項目開元の治|漢|関中|周|条坊制|隋|都市|洛陽
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「長安」の解説
長安
ちょうあん
渭水盆地の中心都市で,早くから要害の地として知られ,前漢の首都となってのち,五胡十六国時代の前趙 (ぜんちよう) ・前秦 (ぜんしん) ・後秦 (こうしん) ,南北朝時代の西魏 (せいぎ) ・北周・隋・唐がここに都を置いた。特に栄えたのは前漢・唐の時代で,前漢時代は周囲が約28㎞,城の内外に9つの市があった。唐の長安は,隋の文帝楊堅が造った大興城に手を加えた東西約10㎞,南北約8㎞の大規模なもので,宮城・皇城(官庁所在地)・市・住宅地をもつ計画都市であった。最盛期は玄宗 (げんそう) のころ(8世紀前半)で,人口は100万に達し,渤海 (ぼつかい) ・新羅 (しんら) ・日本・ペルシア・アラビア・インド・トルキスタンから人が集まる国際的な文化都市であった。日本の平城京・平安京,渤海の上京はこれをまねて造られた。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「長安」の解説
長安(ちょうあん)
Chang'an
中国陝西(せんせい)省西安の古名。周の鎬京(こうけい),秦の咸陽(かんよう)もこの付近であったが,前漢がここに都を定めて以来,晋,西魏,北周,隋,唐の都となった。隋は漢以来の長安城の南東に,都市計画によって新しい都市をつくり大興城と名づけた。唐がこれをついで完成し,玄宗の時期には100万の人口があったとされ,世界的な都市となった。唐末の乱で破壊されたが,その後皇城を中心に復活した。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「長安」の解説
長安
ちょうあん
漢・隋・唐などの首都として栄え,特に唐代には人口100万人に達した。平城京・平安京は長安を手本にしてつくられた。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「長安」の意味・わかりやすい解説
長安
ちょうあん
「シーアン(西安)特別市」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の長安の言及
【市】より
…秦・漢から唐にかけての時代には,国都はもとより,州県城などの地方の政治的都市にも,城郭内の一区画を限って市に指定し,店舗を設けて商業を営むことを許した。たとえば漢代の長安では,城内に東市と西市があり,すべて国家の監督のもとに運営され,市令以下の官吏がおかれ,市場の流通秩序の維持にあたって,市租あるいは市籍租とよぶ一種の営業税を徴収した。市の内部では同業者が店舗を並べて肆(し)あるいは列とよぶまとまりをなしていたが,その活動はだいたいにおいて個別的であり,相互扶助の機能を有する団体の結成は見られない。…
【商業】より
…商業区域である市の営業時間には制限が加えられ,唐代では正午に鼓を打って市を開き,日没前に再び鼓を打って閉じる規定であった。漢都長安の東市,西市,呉市,燕市,唐都長安の東市,西市,洛陽の南市,北市などが,その代表例である。市の商店は同種同業のものが集まって,一つの町をつくるのが原則であった。…
【隋唐美術】より
…遊牧民族と深いつながりの中にその政治文化を標榜した北朝に南朝が統合され,華北と江南とが漢以来再び一つの政治体制のもとに動きはじめたのが隋代である。隋代38年ののちこれを受けた軍閥貴族集団である唐は,北の政治,南の経済を長安・洛陽に集合し,対外的にも北方・西方の遊牧民族に対処しつつ,トゥルファン(吐魯番)以西パミール以東の異域に勢力を及ぼし,西域の確保と同時にその高次の文化を吸収していった。 隋・唐の文化は南北合一に基盤があるが,支配者層の嗜好を反映していちじるしく外向的かつ華美であり,規模の点では南朝のような抑制された性格とは異なり,壮大かつ数量的であり,質の点で粗大であったといえる。…
【都城】より
…都城とはもともと城郭に囲まれた都市をさすが,一般には特に国の首都ないし副都となった都市をさすことが多い。中国で最初の統一王朝を建国した秦の始皇帝は,長安(現,西安)の北西にあたる咸陽城を拡張して統一帝国の首都にふさわしい大都城としたが,秦の滅亡の際にすっかり焼き払われた。前漢は長安に,後漢は洛陽にそれぞれ都城をおいて以後,これら長安と洛陽は,しばしば後の王朝の首都あるいは副都となった。…
※「長安」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...