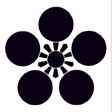精選版 日本国語大辞典 「前田綱紀」の意味・読み・例文・類語
まえだ‐つなのり【前田綱紀】
百科事典マイペディア 「前田綱紀」の意味・わかりやすい解説
前田綱紀【まえだつなのり】
→関連項目稲生若水|東寺百合文書|東寺文書
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「前田綱紀」の意味・わかりやすい解説
前田綱紀
まえだつなのり
(1643―1724)
加賀藩第5代藩主。幼名犬千代、初名綱利(つなとし)。1645年(正保2)父4代光高(みつたか)の急死により、3歳にして家督を相続。祖父利常(としつね)(3代藩主)の後見を、利常の死後は夫人の父保科正之(ほしなまさゆき)の後見を受けた。利常は改作法と称する農政大改革を施行し、綱紀はそれを継承・整備して藩政を確立した。新田開発の推進、非人小屋の創設、職制の改正など、目覚ましい治績を残したが、学者文人の招聘(しょうへい)、図書の収集・刊行の奨励、演芸・美術工芸の振興など、元禄(げんろく)・正徳(しょうとく)期(1688~1716)のいわゆる文治主義に対応して、すばらしい成果をあげた。1723年(享保8)81歳をもって退老、翌年5月9日、江戸邸にて病死した。その諡(おくりな)によって「松雲公」と称し、この時代を藩政の最盛期とする。しかし、次の吉徳(よしのり)の停滞期に入ると、緊縮政治が要請され、いわゆる加賀騒動が誘発されたのである。
[若林喜三郎]
『若林喜三郎著『前田綱紀』(1961・吉川弘文館)』
改訂新版 世界大百科事典 「前田綱紀」の意味・わかりやすい解説
前田綱紀 (まえだつなのり)
生没年:1643-1724(寛永20-享保9)
加賀藩5代藩主。幼名犬千代。1645年(正保2)3歳で襲封,54年(承応3)正四位権少将兼加賀守,58年(万治1)権中将となり,84年(貞享1)綱紀と改める。93年(元禄6)参議,1706年(宝永3)従三位となり,23年(享保8)隠居し,肥前守と改めた。その治政は79年に及び,藩制確立期にあたって番方・役方の職制を整え,農商政策では改作法の祖法化,1683年(天和3)の問屋立て,93年の切高仕法などを行い,また盗賊改方,藩営の〈非人小屋(御救小屋)〉の設置など治安救恤(きゆうじゆつ)にも意を用いて,名君とうたわれた。趣味は文事の諸方面にわたり,とくに書物奉行を置いて古今の書を捜求した。《東寺百合文書》,三条西家蔵書の整理などもその一環である。また木下順庵,室鳩巣,稲生若水らの学者・文人を招禄し,みずからも《桑華字苑》《秘笈叢書》などを編纂した。金沢城内に細工所を設けて工芸に励ませ,能は宝生流を招いた。法号松雲院。
執筆者:高沢 裕一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「前田綱紀」の意味・わかりやすい解説
前田綱紀
まえだつなのり
[没]享保9(1724).5.9. 江戸
江戸時代中期の加賀藩五代藩主。光高の子。母は水戸中納言頼房の娘。幼名は犬千代。初め綱利と称した。号は顧軒,梅 墩,香雪,松雲軒。正保2 (1645) 年光高没後3歳で襲封。祖父利常の後見,のちは岳父保科正之の援助によって藩政にあたった。改作法と呼ぶ農政の確立,防火制度,城下町の市政など,藩政,民政全般にわたる成果をあげた。しかし,他方では財政に苦しみ,藩の借銀がふえたりした。また学問を好み,林鳳岡,室鳩巣,木下順庵とも交わり,古文書の収集保存にも深い関心を寄せた。その蔵書によって尊経閣文庫の基をつくり,東寺伝来の古文書『百合文書 (ひゃくごうもんじょ) 』の保存に尽力した。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「前田綱紀」の解説
前田綱紀 まえだ-つなのり
寛永20年11月16日生まれ。前田光高(みつたか)の長男。正保(しょうほ)2年3歳で加賀金沢藩主前田家5代となる。はじめ祖父利常(としつね)が後見。改作法(農政改革)や藩職制・軍制などの諸制度を整備,また加賀象眼・蒔絵(まきえ)などの産業を振興。木下順庵,稲生若水(いのう-じゃくすい)らを招致し,和漢古典の収集につとめ,「歴代叢書」「庶物類纂」などを刊行。享保(きょうほう)9年5月9日死去。82歳。初名は綱利(つなとし)。号は顧軒,松雲など。
【格言など】国の安危は,政(まつりごと)の得失にあり。山河の険,恃(たの)むに足らず(黒部川架橋に,家臣が国の要害を失うと反対したことに対して)
山川 日本史小辞典 改訂新版 「前田綱紀」の解説
前田綱紀
まえだつなのり
1643.11.16~1724.5.9
江戸前期の大名。加賀国金沢藩主。光高の長男。1645年(正保2)3歳で家督相続し藩主となる。祖父利常,舅保科正之の後見をうける。61年(寛文元)金沢へはじめて入国。藩政では利常の改作仕法を引き継ぐとともに,十村(とむら)制度の整備,切高仕法の導入などを行った。好学の大名として知られ,木下順庵・室鳩巣(むろきゅうそう)・稲生若水(いのうじゃくすい)ら多くの学者を招くとともに,書物の収集,東寺・三条西家などの古文書の整理・補修を行った。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「前田綱紀」の解説
前田綱紀
まえだつなのり
江戸中期の加賀(石川県)藩主
1645年,3歳で家督を継いだ。義父の会津藩主保科正之の援助を得て改作法の実施・貧民救済などを行い,民政に尽力し「中興の英主」といわれた。また学問を奨励し,木下順庵・室鳩巣 (むろきゆうそう) らを招き,古書・古文書の収集保存・刊行を行い,学問の発達にも貢献。名君の一人として有名。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
367日誕生日大事典 「前田綱紀」の解説
前田綱紀 (まえだつなのり)
江戸時代前期;中期の大名
1724年没
出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報
関連語をあわせて調べる
2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...