精選版 日本国語大辞典 「郷土玩具」の意味・読み・例文・類語
きょうど‐がんぐキャウドグヮング【郷土玩具】
- 〘 名詞 〙 その土地特産の材料を用い、あるいはその土地の風俗、慣習、伝説に基づいて作られた、地方色豊かな玩具。
改訂新版 世界大百科事典 「郷土玩具」の意味・わかりやすい解説
郷土玩具 (きょうどがんぐ)
日本全国それぞれの土地で古くから自給自足的につくられ,主として子どもたちの遊び道具として親しまれてきた伝承的な人形玩具類。そのほとんどが江戸時代から明治期にかけて生まれたもので,いずれもその土地の生活風俗などに結びついている。旧藩当時の各城下町などを中心に発生発達したものが多く,郷土色ゆたかな特徴をもち合わせていることからこの名称がつけられた。
発生,移り変り
日本の玩具が出そろってきたのは江戸時代からのことである。それ以前は,古くから中国などの海外文化を受け入れ,渡来玩具をたくみに日本化してきたが,江戸時代に入ると,鎖国下の泰平時代を迎えてさまざまな生活文化が開花した。人形や玩具もこの時期に商品化が盛んになり,日本独特の人形玩具類が数多く登場してくるようになった。元禄(1688-1704)ころの市井風俗を描いた井原西鶴の《男色大鑑》は,大坂盛場の手遊び屋(玩具店)に子ども向きの張子細工などの,いずれも郷土玩具の祖型をおもわせる新考案玩具類がすでに売られている模様を伝えている。さらに1773年(安永2)刊の玩具絵本《江都二色(えどにしき)》(北尾重政)には,当時流行した88種の江戸玩具が描かれている。そのなかには鶯笛(うぐいすぶえ),振り鼓(つづみ),犬張子など現在も郷土玩具として残され各地に散在しているものが数多く収録されている。またこの時代には,近世から発達した各地の城下町とその周辺の集落を基盤にして,郷土の生活習俗を反映する諸玩具が生み出された。ときには藩主の参勤交代の旅などに付随して,江戸や京,大坂などの大都市から人形玩具の新しい製作技法や着想が伝えられ,これらがまた一つの製作母体となったり,藩主が領内の経済力を高めるために,それらの生産を奨励したこともある。例えば江戸城内大奥で始まったという千代紙細工や糸まりづくりが,やがて各地の城下町にももたらされ,そのつくり方が伝えられた。また京の伏見産の土人形(伏見人形)も西日本一帯から日本海沿岸地方にまで伝えられ,それぞれの地方の土人形づくりの原型に応用された。こうした製作技法の交流と郷土文化の開発とによって,全国各地のおもに盆地の中心に位置する城下町周辺に,さまざまな人形玩具が生まれてきた。
収集,観賞と研究の歴史
日本の各地に発生した固有の玩具類に興味を寄せて,子どもたちの遊びとは別に,成人の立場からこれらを収集,観賞して楽しむ趣味は,すでに江戸時代にも存在した。江戸中期をすぎると,江戸などの大都市をはじめ全国各地の城下町を中心とする都市文化はその範囲をしだいに拡大し,それに従って古くから伝承されてきた田舎(いなか)の生活風俗などは,城下町文化からとり残された周辺の村落とか,はるか遠く離れた地域にしかみられなくなる。こうした生活の移り変りから,古い習俗をかえって珍しく感じて,それに一種の郷愁をおぼえる傾向も生まれ,自己の日常生活の周辺からもそれに似たものを見いだして考える気風を生じた。そして全国各地に散在する手遊びおもちゃ類を通して古俗を学ぼうとする傾向も強まった。
明治時代に入ると〈文明開化〉の波に乗って,欧米先進国の近代玩具が海外からもたらされ,やがて国内でもそれにならって量産化が始まった。一般市場に新しい国産玩具が広く出回ってゆくようになると,従来の地域的にも限られた旧型玩具は商業的にもしだいに圧倒されて落伍の運命をたどる。また各家庭で求める玩具の性格も,新たに〈教育〉に役だつことが目標とされてきて,信仰やまじない,縁起などにちなんだものの多い古風な伝承的玩具類は後退し,子どもの遊び道具としての存在を失う傾向をみせた。ところがこれとは逆に,日本古来のこの種の玩具にかえって郷愁と魅力とを感じとる趣味人,好事家たちの間には,これまでの子どもに代わって,今度は成人の趣味玩具としてこれらを収集,愛玩する機運が生じてきた。それを推進する指導的立場にあったのが東京神田の玩具研究家清水晴風(仁兵衛)である。彼は全国各地に散在するこの種の伝承玩具人形類を採集してそれらを描いた画集《うなゐの友》を1891年に発行し,1913年まで6編を刊行した。彼の死後は日本画家西沢笛畝が継いで24年10編まで担当,初編以来前後33年間を費やして完結した。これが始まりで東京,京阪,名古屋方面を中心に明治末期から大正期にかけて伝承玩具人形類の愛好趣味が全国的に広まった。当時は〈土俗玩具〉〈地方玩具〉あるいは〈大供(おおども)玩具〉〈諸国玩具〉などまちまちの名称で呼ばれていた。また,玩具趣味家たちの間には,さまざまな〈おもちゃ番付〉も出現した。日本各地の郷土臭の強い人形玩具類を相撲番付式にならべ,収集上の人気,優劣などを一覧させるものである。1916年発行の〈大供用玩具二百撰〉が最初のものとされ,収集手引きとして役だった。〈郷土玩具〉の名は,23年発行の《郷土趣味》に同誌主宰者田中緑紅(俊次)が〈郷土玩具の話〉を連載し始めたのが記録のうえでは最初とされる。
しかし,社会生活の近代化によって古い型の玩具はしだいに衰退し,有毒色素取締法などで製作上の制限も加わったりして,製作者の転廃業が相次いだ。関東大震災で古い東京の姿が消失したが,江戸玩具の衰退と廃絶はかえって愛玩趣味家たちの間に収集運動の復活をもたらし,震災後の大正末期から昭和戦前期にかけて全国的な流行をみるようになった。各地に郷土玩具を愛好する趣味団体が生まれ,これまでの各界名士など特殊な階層の趣味家を越えて,一般家庭や若いサラリーマン,学生層にまで愛好熱が広まった。なかには洋画家山本鼎(かなえ)を指導者とする農民美術派の作品や郷土玩具研究家有坂与太郎(正輔)の提唱する創生玩具など新型の郷土玩具も登場し,大都会には各地の郷土玩具を販売する専門店も出現した。またこれまでまちまちであった玩具の名称も,35年前後に〈郷土玩具〉に統一され現在に至っている。
第2次世界大戦後は各地に研究,趣味団体が誕生して復活ぶりをみせ,54年午(うま)年の年賀切手図案に郷土玩具の三春駒(福島)が登場したのが始まりで,毎年各地の郷土玩具が採用され,郷土玩具切手シリーズとして人気がある。このように収集趣味が普及している半面で,商業主義の進出や流通,交通の発達などから玩具のもつ郷土性が失われてゆく傾向をみせている。また戦後新たに考案された民芸調玩具,あるいは旧型を模した観光みやげ玩具も同じく郷土玩具を名のっている例が多い。新旧二つの郷土玩具をどのように区別するかで混乱も生じている。これらを総合的に系列化し,あるいは比較分類して研究の道を開いてゆくことも今後の課題とされている。
特徴
材料には土,木,竹,わら,紙,布,糸など明治以前から国内で日常生活の周辺で比較的たやすく,安価に入手できるものが用いられる。その点で近代玩具とは材質的にも異なる。製作は手づくりで,伝統的な技法と着想がみられる。素朴な材料の性格を生かした多種多様なものがあり,各地ごとに民芸品としての個性が認められる。製作地域は全国にわたっているが,紙や土などを材料にしたものはおもに城下町など都市およびその周辺に多く産出される。和紙が多く消費され,そのほご紙類が玩具材料に廃物利用できるからである。またこれらの地域では瓦の生産が盛んにみられ,瓦焼に伴って土人形類も生まれてきた。さらに山間部の森林地帯には木製の作品が生まれた。土人形が盛んにつくられていた江戸末期には,全国で100ヵ所以上の産地があった。現在は日本の民族玩具として海外にも広く紹介され,優れたものとして高く評価されている。
内容的には,子ども向きの遊び道具のほかに民間信仰やその土地の年中行事などの生活習俗に結びついたものが多い。清水晴風は郷土玩具を,(1)信仰的につくったもの,(2)記念的なもの,(3)子どもに与えるもの,の三つに分類しているが,郷土玩具のほとんどは(1)の神仏への民間信仰と強く結びついているところに特徴がある。この種の玩具の市場は寺社の縁日祭礼や門前市であり,いずれも安産,子育て,開運厄よけ,病難よけ,商売繁盛,豊作祈願など縁起物もしくはマスコット的な性格をもった作品が多い。なかには神社から授与される護符的な色彩の濃い,玩具らしくないものまで含まれている。したがって子どもの遊び道具にはふさわしくないものも見受けられるが,これらの玩具の成立ちには,子どもの健康と多幸とを神仏に祈る親の愛情がくみとれる。民俗学的には〈みやげ〉という言葉は宮笥つまり〈神々に供える祭具器物〉の意味から発しており,古い型の玩具が信仰を母体にして生まれてきたことを示している。また作品の多くに赤い色が用いられているのは,古くから赤い色が魔よけのまじないとされる民間信仰と結びついているからである。こうした信仰玩具が発達したのは,江戸時代に病苦や天災地変の厄からのがれるため神仏の加護にすがろうとする祈りと,それを目的とする神社詣や寺参りが盛んになり,信心がてらの物見遊山が流行したことが複合された結果でもある。さらに3月,5月の節供祭が盛んになったことや,あるいは土地の祭礼など年中行事にちなんだものが多く生まれ,季節感に富んでいる。ことに節供行事に付随してさまざまな人形類が各地で産出され,郷土玩具の中核ともなっている。
種類
郷土玩具は,子どもの遊び道具的なものから,成人層の愛好趣味の対象となるものまで多種多様である。昭和戦前期に郷土玩具研究の指導的立場にあった有坂与太郎は郷土玩具の種類を,(1)風俗ならびに慣習的関係に基づく玩具,(2)児童の遊戯の対象物としての玩具,に大別している。さらに(1)を3種に分けて,〈史的関係より生じた玩具〉として蘇民将来(そみんしようらい),鹿児島神社の鯛車,三春駒,ねぷた提灯(ちようちん),笹野の削掛け,古賀のあちゃさん,高岡の鶉(うずら)車,長野のわら人形,応神天皇の起上り,矢口の矢守,水戸の農人形をあげ,〈地的関係より生じた玩具〉として新潟の木牛,大阪,四国の浄瑠璃(じようるり)人形,東北地方の牛,馬玩具,海辺地方の船玩具などを例にし,〈迷信ならびに信仰的関係より生じた玩具〉として静岡地方の虫よけ首人形,奈良法華寺の安産犬守,東京地方のざる被り犬張子などをあげている。(2)の項のものとしては,〈日常生活より生じた玩具〉として凧(たこ),こま,羽子板,姉様などを,〈祭礼関係より生じた玩具〉として祭礼の山車(だし),神輿(みこし)を模した玩具などをあげている。
また材質的に分けると,土製(各地土人形,土鈴など),木製(こけし,木地玩具など),紙製(張子人形,面,姉様など),布,糸製(糸まり,押絵雛(おしえびな)など),竹製(はじき猿,鳥笛など),わら製(わら馬,わら細工など),練物製(人形,起上りだるまなど),貝製(貝人形,貝笛など),およびこれらの材料を複数取り合わせているものがある。すでに廃絶したものも少なくないが,いまも全国各地に現存するものの総数は数千点の種類にのぼると推定される。
→玩具 →人形
執筆者:斎藤 良輔
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「郷土玩具」の意味・わかりやすい解説
郷土玩具
きょうどがんぐ
日本各地で古くから手作りでつくられ、それぞれの土地で親しまれてきた玩具。ほとんどが江戸時代から、明治期にかけて発生したもので、その土地の生活風俗など郷土色を反映している。多くは旧藩当時の習俗を残す城下町などを中心に発達した古い型の伝承玩具群で、明治期以後の新しい材料と機械的な製作技法による近代玩具とは区別される。近代玩具に圧倒されて廃絶したものも少なくないが、現在全国に散在している数は約3000種といわれる。
[斎藤良輔]
特徴
材料は土、木、竹、藁(わら)、紙、布、糸など、明治期以前から存在し、生活周辺から比較的たやすく入手できる安価なものが用いられる。製作は手作りで、伝統的な技術と着想とがみられ、民芸品としての個性がある。内容的には子供向きの遊び道具的なもののほかに、民間信仰やその土地の生活習俗と結び付いたものが多い。神社や寺院の祭礼縁日、門前市などで売られるものが目だち、いずれも安産、子育て、悪病災難除(よ)け、開運出世、招福長寿、商売繁盛、豊作祈願などの縁起物や、マスコット的性格をもったものが多い。なかには神社から授与される護符的色彩がことに強く、玩具らしくないものまで含まれている。また3月、5月の節供飾りや、四季の年中行事にちなんだものがみられ、季節感に富んでいる。ことに節供行事に付随してさまざまな人形類が生まれ、質量ともに郷土玩具の中核となっている。
紙、土製のものは、おもに城下町やその周辺に多く産出される。なぜなら、そういう地域では和紙が多く使われ、反故(ほご)紙類が玩具材料として廃物利用できることや、また町作りの瓦(かわら)焼の影響などがあげられる。土人形製作が全盛期を迎えた江戸末期には、その産地だけでも全国で100か所余りに上った。それらは鎖国300年の太平が生んだ産物でもあった。木製のものは、多く山間部で発達した。いずれも手作り独特の美があり、種類も豊富で、造形にも各地で変化がある。素朴な材料を巧みに用いてつくる、技術と着想が生んだこれらの作品は、日本の伝承的な民族玩具として海外にも紹介され、高く評価されている。
[斎藤良輔]
歴史
日常生活や流通機構が、地域的に限定されていた封建時代には、玩具もそのほとんどが各地の城下町を中心とした地方色を帯び、いわば郷土玩具そのものであった。江戸中期を過ぎると、古い習俗に興味をもち、各地にみられる伝承的な手遊びおもちゃ類を通し、古俗を学ぼうとする関心も生まれてきた。『骨董集(こっとうしゅう)』(山東京伝著)、『嬉遊笑覧(きゆうしょうらん)』(喜多村信節(きたむらのぶよ)著)、『守貞漫稿(もりさだまんこう)』(喜田川(きたがわ)守貞著)などの考証随筆類が登場してきたのも、その表れである。
明治期に入ると、この種の玩具類は近代玩具の進歩に押されてしだいに後退し、子供の遊び道具としての生命を失っていくが、それと入れ替わりに、成人層による趣味愛好運動が台頭してきた。これは当時の欧米心酔主義に反発して、日本古来の伝承玩具に郷愁を感じることからおこった。その指導的役割を務めた代表者の一人が、東京の玩具研究家、清水晴風(しみずせいふう)(仁兵衛)である。彼は1891年(明治24)全国各地の人形玩具を採集して描いた玩具画集『うなゐの友』を発行したのをはじめ、明治末期から大正時代にかけて愛玩趣味を広めた。
大正期から東京、大阪などに趣味家相手の郷土玩具の専門店も登場した。郷土玩具は「土俗玩具」「地方玩具」「大供玩具」「諸国玩具」などとよばれたが、1935年(昭和10)ごろ「郷土玩具」の名称に統一された。第二次世界大戦後は観光ブーム、民芸調の流行などから収集趣味も普及している。また伝統的製品を模倣した観光土産(みやげ)の新興郷土玩具類も多く出現している。
[斎藤良輔]
『清水晴風著『うなゐの友』(1891・芸艸堂)』▽『武井武雄著『日本郷土玩具』(1930・地平社書房)』▽『斎藤良輔編『郷土玩具辞典』(1971・東京堂出版)』

鷽

北原人形

鯨舟・鯨車

古賀人形

木の葉猿

笹野彫り

田面船

堤人形

遠刈田こけし

鳴子こけし

博多人形

弾き猿

鳩車

鳩笛

肘折こけし

松江の姉様

三春駒

三春張子

虫切り鈴

撫養の首でこ

弥治郎こけし

八幡馬

犬張り子の製作

今戸人形の絵付け

うずら車の絵付け

古賀人形の絵付け

堤人形の絵付け

博多人形の絵付け

『守貞漫稿』に記された玩具
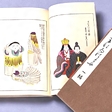
『うなゐの友』

大入道

黄鮒

金魚提灯

米喰い鼠

佐世保こま

三角達磨

鳥取の張り子玩具

大社のじょうき

ちんちん馬

津軽のずぐりごま

津山の土天神

能古見の土人形
百科事典マイペディア 「郷土玩具」の意味・わかりやすい解説
郷土玩具【きょうどがんぐ】
→関連項目姉様
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「郷土玩具」の意味・わかりやすい解説
郷土玩具
きょうどがんぐ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の郷土玩具の言及
【独楽】より
…しかし,第2次世界大戦を境に急速に衰退し,現在ではその遊事生命をあやぶまれている。その一方,おとなの趣味として,多くの郷土玩具のこまが市販され,新しい創作ごまが作られるなど,こまの種類はかつてないほど多くなった。
[種類]
(1)木の実ごま 木の実に心棒をさし,指でひねってまわすこま。…
※「郷土玩具」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...


