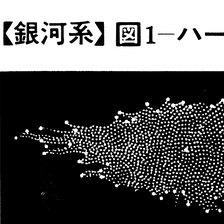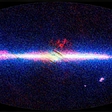銀河系(読み)ギンガケイ(その他表記)Galaxy
精選版 日本国語大辞典 「銀河系」の意味・読み・例文・類語
ぎんが‐けい【銀河系】
- 〘 名詞 〙 太陽系が属する島宇宙。凸レンズ型をした円板状の渦状星雲で、地球からは全天をめぐる帯状に見える。有効直径一〇万光年、中核部の厚さ一・五万光年、太陽付近の厚さ〇・五万光年の大きさをもち、自転運動を行なっている。銀河の中心は、射手(いて)座方向にあり、銀河座標の原点となっている。
- [初出の実例]「燦爛たるカペラ・シスチナの壁画は人間神性の銀河系」(出典:つゆの夜ふけに(1939)〈高村光太郎〉)
改訂新版 世界大百科事典 「銀河系」の意味・わかりやすい解説
銀河系 (ぎんがけい)
Galaxy
Milky Way Galaxy
太陽系のまわりに分布している星々や星間物質は,一つのまとまった集団体系を構成して,宇宙空間の一隅を占めている。この体系を銀河系といい,アンドロメダ銀河などと同様な渦巻銀河の一つである。私たちの地球が所属する太陽系は,そのほんの一部分である。
銀河系の光学像
天の川が無数の微光星の集積であることは,17世紀の初め,自作の望遠鏡を夜空に向けたガリレイによって発見された。この天の川は,北半球の夏空に見えるはくちょう座などの部分と,冬空に見えるオリオン座などの部分が,南天のみなみじゅうじ座で接続しており,天球を一周している。天の川の中心線は天球上の一つの大円をなしていて,この大円を銀河赤道,銀河赤道の作る面を銀河面と呼んでいる。天の川はいて座の部分でもっとも明るく幅も広い。そして全天の星の分布を見ると,天の川に近いところほど星の数が多いことがわかる。
18世紀後半,W.ハーシェルは,当時としては最大の口径46cmの反射望遠鏡を使い,全天から選択したいくつかの一定面積の天域ごとに,何等までの星が何個あるかという星数統計を行った。当時はまだ恒星の距離を求める方法が知られていなかったので,ハーシェルは,星の実光度がどれも等しいものと仮定し,暗い星ほど距離が遠いという関係を使って,恒星の空間分布を推定した。その結果として得られたのが,1785年に発表されたいわゆるハーシェル宇宙(図1)である。それによれば,われわれのまわりの星々は,扁平な形の一つの有限な体系を構成し,天の川の方向に長くのびた形をもっていて,これは目で見た印象をはっきり裏づけている。さらに,いて座を中心とした天の川の広角写真を,近赤外光で撮影した写真で見ると,星の大多数がいて座の部分で膨らんだ凸レンズの形の範囲に存在していることがわかる。その凸レンズを二分するように中央を横切る暗黒帯は,星の光が星間塵のために遮られることによって生じたものである。星間塵と星間ガスからなる星間物質は,星以上に銀河面に沈殿して分布するため,このように銀河面に沿った暗黒帯が見られるわけである。
凸レンズの形に分布する星の種類を調べた結果,次のようなことがわかった。すなわち,中央の膨らんだ部分(これをバルジbulgeという)には,K型,M型の赤色低温度星が多く,ほかに,球状星団,こと座RR星型変光星,惑星状星雲といった天体が混在している。これらはいずれも老齢の星で,種族Ⅱと呼ばれているものである。一方,バルジの両側の扁平な部分(これを円盤部diskという)には,O型,B型の青色高温星,ケフェウス型変光星,散開星団などが主として分布する。これらは年齢の若い星で,種族Ⅰと呼ばれるものである。なお,星間物質もまたこの円盤部に含まれている。このように,銀河系の中央部を占める扁球状のバルジと,それを取り巻く円盤部は,構成成分を異にし,凸レンズ状の銀河系主体はそれらの合成であるということができる。なお,種族Ⅱの天体の一部は,この銀河系主体の周辺の,やや扁平な球状の範囲にも希薄ながら分布しており,この部分をハローhaloと称している。以上が銀河系の構成であるが,最近は,銀河系の範囲が,上記のハローの部分のずっと外側にまで広がっているという説が有力となり,目には見えないこの広がりの部分を,コロナcoronaと呼ぶ例も目につくようになった。
アンドロメダ銀河をはじめとする多くの渦巻銀河に見られる渦巻模様が,わが銀河系にも存在することは,1951年に初めて明らかにされた。銀河円盤部に分布する明るい天体であるO型,B型の星の配列から,3本の渦巻の腕(オリオンの腕,ペルセウスの腕,いての腕)が見つかったのである。光学的に明るい天体としては,ほかに電離水素領域があり,その分布からも渦巻の腕の跡づけがなされている。
電波による観測
渦巻の腕はどれも銀河系の円盤部にあり,そこはまた,星間物質がまんべんなく分布している場所でもあるので,その中の星間塵の吸収によって,光学的観測の射程は,比較的近距離に制限される。ところが光に比べて波長のずっと長い電波は,星間塵による吸収遮断が少なく,遠距離にまで到達する利点がある。1950年代後半には,星間物質中の中性水素が放射する波長21cmの電波を受信して,中性水素の量や分布を求める観測が成功し,その結果,銀河系円盤部全般にわたって,渦巻構造が見られることがわかった(図2)。70年代には一酸化炭素の分子が放射する波長2.6mmの,いわゆるミリ波帯電波の観測も盛んに行われるようになり,星間物質の違った様相が明らかになりつつある。一酸化炭素は水素分子との衝突によって励起されるので,その分布は取りも直さず水素分子の分布を示すわけである(水素分子そのものは,探知できるほどの放射を出さない)。さて,一酸化炭素の観測結果によれば,中性水素とはかなり分布の様子が違っている。図3に示すように,一酸化炭素は,銀河系中心からの距離が約2万光年のところにピークをもち,太陽系のある3万光年の距離よりずっと内側の領域を占めるリング状の範囲に分布するのに対し,中性水素は,銀河中心からの距離が1万光年から4万光年の幅広い範囲に広がって分布している。さらに細かく調べると,一酸化炭素は,直径十数光年程度のかたまりに分かれていることもわかった。したがって,水素分子も,銀河系内のこのような範囲に,直径十数光年の雲という形で分布していることになる。これは光でも見える太陽系付近の暗黒星雲の大きさに近い。そして,水素分子雲は,中性水素原子のガス雲に比べて低温高密度で,暗黒星雲同様に,恒星誕生の母胎とみなされるものである。太陽系の内側に位置する一酸化炭素のリングは,また,このような水素分子雲のリングでもあり,銀河系内の恒星誕生の揺りかごとでもいうべき地域なのである。なお,電離水素の顕著な分布帯も,また,この2万光年リングに一致することが知られている。電離水素領域は,大質量の星が生まれると,その高温の放射で水素が電離されることによってできることを考えれば,水素分子雲が若い大質量星と密接に関連していると想像してよいであろう。
銀河系中心部の構造
銀河系の中心部は,暗黒帯のまっただなかにあり,星間塵による光の吸収は,実に30等にも及ぶとされている。上に述べた近赤外写真の波長は約1μmであるが,これよりもっと長波長の2.4μmの赤外線で観測すると,星間塵による吸収はずっと少なくなり,図4のように,中心核部の構造がかなりよく見えるようになる。さらに波長の長い電波では,もっと見通しがよくなり,例えば波長3.75cmで観測した場合の電波強度分布は,図5に見るとおりである。中心に,いて座Aと呼ばれる電波点源があり,これがすなわち,わが銀河系の中心核であるとみなされている。そのまわりにもいくつかの電波源が分布していることは図に見られるとおりである。
さて,中性水素の波長21cmの電波で銀河系の中心部を観測したところ,中心核のまわり2000光年の範囲で,非常に速く回転する水素ガス雲の存在が認められた。その厚さは200光年程度の,薄い円盤状で,これを中心核円盤と呼んでおり,回転速度は円盤外縁部で約200km/sである。また銀河系中心から約1万光年(3キロパーセク)のところには,リングの一部または渦巻の腕のように見える構造があり(図6),約150km/sの速度で銀河系中心のまわりを回転しながら,50km/sの速度で外側へ膨張していることもわかった。これを3キロパーセク腕と呼んでいる。なお,いて座A付近を細かく観測すると,この電波源は東西二つに分かれ,その西側のほうは高温ガスが放出する熱電波源で,赤外線強度のピークもここに一致することが認められた。この事実から,ここには多数の高温で大質量の星が,星間塵とともに集中しているものと想像されている。おそらく直径数光年の,このいて座A(西)の部分には,100万ないし200万個もの若い星があり,密度はきわめて高い。ちなみに,太陽付近の星の平均密度は,これと同じ体積内に1個の程度にすぎない。このような銀河系中心核をブラックホールと考える説も提出されている。
銀河系の形態型
光学観測および電波観測によって知られた銀河系の渦巻模様の状況から,銀河系をハッブルの銀河分類型にあてはめると,SbないしSbcというところに落ち着く。また,銀河系の近赤外写真などに見られるバルジの大きさ,すなわち明るさの中央集中の程度から判断して,銀河系はヤーキス分類型のgk型に相当するとされている。ちなみにアンドロメダ銀河M31は,ハッブル分類でSb型,ヤーキス分類ではk型であるから,銀河系はM31に比べ,渦巻腕のまきこみ方がやや開いており,またバルジがやや小さいということになるわけである。NGC3147とNGC7331およびNGC891の各渦巻銀河は,いずれもヤーキス分類のgk型であり,ハッブル分類では前の二つがSb,NGC891はSbcであるから,どれもわが銀河系によく似た銀河であるといえよう。つまり銀河系を外側から見たとして,正面向きに見るとNGC3147に,やや斜めから見るとNGC7331に,真横から見るとNGC891に似た姿に見えるであろう。
銀河系の大きさ
銀河系の大きさを知るには,系内の星々までの距離がわかればよい。しかし一般恒星の距離決定は,遠いものまで十分に行うことがむずかしく,とくに種族Ⅰの星は,星間塵と混在しているため,その吸収の影響で,観測可能な範囲が著しく狭められる。ところが種族Ⅱの球状星団は,多数の星の集団で明るい天体であるうえに,銀河面から離れたバルジやハローの領域に大部分が分布しているので,星間吸収の影響が少ない。そこで遠くにあるものまで観測することができ,しかも球状星団には,絶対等級が一定なこと座RR星型変光星を含むものが多いので,距離決定に好つごうである。各球状星団の距離が決まると,それらの空間分布図が得られ,この図から銀河系の輪郭やその大きさがわかり,また銀河系内の太陽の位置もわかるわけである。この方法で銀河系の大きさを決める試みを初めて行ったのはシャプリーH.Shapleyで,1910年代末から約10年間にかけてのことである。彼が,当時知られていた93個の球状星団の空間分布図から求めた結果は,銀河系が楕円体で表され,その三つの軸の直径が23万光年,16万光年および13万光年というものであった。また太陽は銀河面上にあって,銀河系の中心から5.2万光年の距離にあることも導かれた。ところがシャプリーのこの解析には,星間塵による星の光の吸収が考慮されていない。球状星団でも,とくに銀河系中心に近い方向にあるものについては,かなりの星間吸収が存在するのである。30年,トランプラーR.J.Trumplerが吸収の事実を明らかにし,ステビンズJ.StebbinsとウィットフォードA.E.Whitfordが36年にこれを球状星団の距離決定にも適用した結果,銀河系の大きさは16万光年×13万光年×11万光年に,また太陽の銀河系中心からの距離は3.3万光年と大幅に修正された。なお球状星団の距離決定に使われること座RR星型変光星の絶対等級の値についても,諸種の議論があり,初期のころは0.0等(写真絶対等級)という値が採用されていたのが,80年代初期現在では,0.6等(実視絶対等級)という値が標準値とされている。また球状星団の発見数もかなり増加して,80年代初期現在では,114個の球状星団について,図7に示すような空間分布図が得られている。これから導かれる太陽の銀河系中心からの距離は2.9万光年という結果になった。
太陽と銀河系中心間の距離を求めるのに,銀河系のバルジ中に分布すること座RR星型変光星を使う方法もある。太陽から見たバルジ方向,すなわち銀河系中心方向には星間塵が多く,暗黒帯が広がっているが,部分的に星間塵が少なくてかなり遠くまで見通しのきく“窓”と呼ばれる個所がある。その一つに球状星団NGC6522付近の領域があるが,1944年,W.バーデはこの方向に観測される35個のこと座RR星型変光星が,写真等級mpg=17.5等にピークをもち,その両側にすそを引いた等級頻度分布をもつことを見いだした(図8)。この事実は,バルジ中のこと座RR星型変光星が,銀河系中心のまわりに対称に分布していることによるというのが彼の解釈である。この型の変光星の写真絶対等級Mpgとしては,当時0.0等という値が採用されていたので,mpg-Mpg=17.5等は,銀河系中心と太陽間の距離R0を示す距離指数に当たる。実際は,これからNGC6522方向の星間吸収量Aを差し引いた値mpg-Mpg-Aが,吸収を補正したR0の距離指数になる。バーデはA=2.8等を採用して,R0=8.7キロパーセク=2.8万光年という値を得た。その後,銀河系中心方向にあること座RR星型変光星の数が増え,またその絶対等級Mpgや,星間吸収量Aの値も改良された結果,この方法から導かれるR0の値もいくぶん改訂されている。
以上のほかに,諸種の銀経方向でのO型星,B型星のスペクトル観測から得られる視線速度,または波長21cmの電波スペクトルのずれから得られる中性水素の視線速度をもとに,運動学的解析を行って,R0を求める方法もある。これらの諸方法で求めた80年代初期現在でのR0の値は,約3万光年である。
銀河系の回転
銀河系の円盤部を構成している恒星や星間物質が,銀河系の重力で中心に向かってつぶれてしまうことなく,一定のまとまりを保っているのは,中心のまわりの回転,いわゆる銀河回転によって生ずる遠心力が重力とつり合っているためである。星々の銀河回転の状況は,それらの視線速度や固有運動の観測値から明らかにされてきた。光学的観測の対象としては,O型,B型の星や,電離水素領域など,明るくて遠くのものまで距離がきめやすいうえ,顕著なスペクトル線があって視線速度が求めやすいものが選ばれることはいうまでもない。最近では電離水素領域について,太陽より外側約2万光年の範囲まで,銀河系中心からの距離と回転速度の関係を示すいわゆる回転速度曲線が得られている。波長21cmの電波による観測からは,銀河系中心付近から太陽の距離までの回転速度曲線が早くから求められており,最近では一酸化炭素の2.6mmの電波による観測結果もまとめられている。
これらの結果を総合して描いた銀河系の回転速度曲線は,図9に示したとおりである。中心からの距離Rが2000光年までの中核部では,回転速度VがRに比例する,いわゆる剛体回転が見られ,これは上述の中心核円盤の回転に相当するものである。R>2000光年でVはいったん減少したあと,Rがほぼ1万光年あたりからふたたび増加し,Rがほぼ2.8万光年で第2のピークを示す。以前はその後,RとともにVは減少していくものと考えられていたが,1970年代末ころに行われた一酸化炭素の電波観測の結果によれば,Rがほぼ3.5万光年以降Vはみたび増加し,Rがほぼ4.5万光年から先は,Vは280km/sという値が続きそうなようすである。このように,回転速度曲線が,Rの大きいほうで一定の値を保つ傾向は,他の多くの渦巻銀河でも観測されていて,後述するような議論を呼んでいる。
さて銀河系内の太陽の距離R0がほぼ3万光年では,銀河回転速度が約250km/sであり,太陽が銀河中心のまわりを一周するには,約2.5億年かかる計算になる。なお,上記の回転速度曲線は,銀河系円盤部にある種族Ⅰの天体についてのもので,それらの運動は平均的に見ると,銀河面内の円運動で近似される。一方,種族Ⅱの天体は,一般に銀河面に対して傾いた面内の楕円軌道をとる。したがって種族Ⅰの天体に比べて,銀河面内の運動成分は小さいが,銀河面に直角な方向の成分は大きい。太陽系から見た場合の諸天体の相対速度は,太陽と似た運動をしている種族Ⅰでは小さくて平均20km/sくらいである一方,太陽とかけ離れた運動をしている種族Ⅱでは,大きくなるわけである。高速度星と呼ばれる速度約60km/s以上の星の大部分は,種族Ⅱの星である。それらの銀河系中心のまわりの軌道は,銀河面に対して傾いているとともに離心率も小さくなく,かなり細長い楕円形をしている。このことは,それらの星が銀河系中心の近くを近点とするケプラー運動をしており,そこでの滞在時間が長いことを意味している。すなわち,それらは本来銀河系のバルジ領域に属する星であるが,その細長い軌道上の運動の途中,現在たまたま種族Ⅰの領域である太陽付近を通りかかったものにほかならない。なお,これら高速度星をはじめとする種族Ⅱの星々は,太陽から見た場合の運動方向が,種族Ⅰの星々の銀河回転とは逆の銀経270°の方向に強い偏りを示すことがよく知られている。これは,種族Ⅰの星々の銀河回転方向の速度成分が,太陽付近で平均約250km/sであるのに対し,種族Ⅱの星々の同方向の成分はずっと小さいので,太陽から見ると,回転の後ろにとり残されるように見えるためと解釈される。
銀河系の質量
ある力学系の質量分布とその回転のようすは密接に関係する。質量分布によって決まる重力と,回転によって生ずる遠心力の間につり合いが成り立っているからである。例えば剛体の円盤ないし密度一様な回転楕円体は,回転速度Vが中心からの距離Rに比例して増えるし,質量が中心に集中した太陽系のような力学系では,ケプラーの法則が示すような回転(VはRの-1/2乗に比例)をする。また質量が距離Rに比例して増加する場合,VはRによらず一定となることがわかっている。さて銀河系の回転速度曲線を見ると,Rの小さい中心部ではVがRに比例して増加しており,この部分は剛体回転とみなされる。R>2000光年では,速度曲線は複雑な形をとるが,例えば銀河系を,Rとともに密度が変わっていく回転楕円体と考えて,その質量分布と回転速度の間の力学的関係を導いたうえ,観測される回転速度曲線にもっともよく合うような質量分布を採用するといった方法で,この部分の質量を決めることができる。回転速度曲線として,R>2.5万光年でVがしだいに減少していくような形が考えられていたころは,上記のような方法で求めた銀河系の総質量は,太陽質量の約2000億倍,すなわち4×1044gという値であり,そのうちの約60%が,太陽系のあるRがほぼ3万光年より内側の範囲にあるという結果であった。ところが1970年代末ごろから,R>3万光年でVがふたたび増大し,R>5万光年ではVが一定値をとるような,新しい速度曲線が導入されたので,銀河系の質量も計算しなおされた。この回転速度曲線の解析から求めた,R<5万光年までの質量は,太陽質量の3000億倍となる。さらに,R>5万光年での回転速度が一定値をとるのがもし事実ならば,上述のように,銀河系の質量はRに比例してどこまでも増えていくことになる。ところがRが5万光年より外側,すなわちハローより外側のコロナの領域には,実は目に見える天体がない。光で見えないだけでなく,水素や一酸化炭素のようなガス雲の存在を示す電波スペクトルも検出されていない。おそらくは,コロナの中に天体があるとすれば,それらは主として進化が進んだ老齢の星からできていて,質量のわりに放射の乏しい種類のものであろう。ただしこの見えない物質が,いままでの天体の概念とはまったく違うものであるかもしれないという考えもあり,目下の一つのなぞとなっている。
→銀河
執筆者:高瀬 文志郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「銀河系」の意味・わかりやすい解説
銀河系
ぎんがけい
the Galaxy
our Galaxy
Milky Way Galaxy
太陽が属する銀河。宇宙に多数ある銀河galaxyの一つであるが、われわれの太陽が属する銀河ということで、他と区別して英語ではgalaxyのgを大文字で書き、theやourをその前につける。これに対応して、日本語では銀河ではなく「銀河系」とよぶことにしている。英語のMilky Way Galaxyに対応する「天の川銀河」とよばれることもある。銀河には楕円(だえん)銀河、レンズ状銀河(S0(エスゼロ)銀河)、渦巻銀河、不規則銀河などさまざまな形態のものがあるが、銀河系は渦巻銀河で、そのなかでも中心部に棒状構造をもつ棒渦巻銀河に分類される。銀河系を外から見ると、アンドロメダ銀河(M31)にかなりよく似ていると推定される。
[岡村定矩]
銀河系と銀河の発見史
1609年から1610年にかけて望遠鏡で空を詳しく観察したガリレイは、暗い夜空に淡い光の帯のように見える天の川が、実は微光星の集まりであることを発見した。この天の川を形づくる恒星集団の分布する空間が宇宙であり、それは太陽系を越えてはるか遠方に広がっていることが想像された。
体系的な観測から宇宙の形と大きさを決めようとした最初の人はF・W・ハーシェルである。1785年に発表された「ハーシェルの宇宙」は直径が約6000光年、厚みが約1100光年の円盤形で、太陽はほぼ中心にあった。
星までの距離決定技術が進み、観測データも蓄積された1922年に、オランダのカプタインが新しい宇宙モデルを発表した。円盤状で、太陽が中心近くにあることはハーシェルの宇宙と同じだが、直径は約5万光年、厚みが約1万光年であった。同じころ、アメリカのシャプリーは、球状星団の分布する範囲が宇宙と思えば、その大きさは約30万光年にもなり、しかも太陽は中心からはずれた端の方に位置することに気がついた。また当時、天球上で天の川を避けて分布する渦巻星雲の正体が何かについても天文学者の間で異なる解釈がなされていた。
1920年に、宇宙の大きさと渦巻星雲の正体について、当時の二つの考え方の代表者であるシャプリーとカーチスHeber D. Curtis(1872―1942)が、アメリカ国立科学院でそれぞれの主張を戦わせる公開討論会が行われた。シャプリーは、「宇宙の大きさは30万光年程度で、渦巻星雲は星が生まれようとしているガスの雲」という主張であった。一方カーチスは、「宇宙の大きさは3万光年程度、渦巻星雲はばく大な数の恒星の集団で、昔カントの主張した島宇宙である」という主張であった。これは後に、The Great Debate(大論争)とよばれるようになったが、この論争で決着はつかなかった。
1923年にハッブルが渦巻星雲(M31)にセファイドとよばれる変光星を発見して論争は決着した。セファイドが見つかると距離を測ることができ、その結果、M31は天の川の恒星集団のはるか外にある島宇宙であることがわかった。結局、それまで宇宙と考えられていた天の川恒星集団は、宇宙に散在する同規模の多数の恒星集団(銀河)の一つであることがわかったのである。渦巻星雲の正体についてはカーチスの主張が正しかったが、宇宙(銀河系)の大きさに関しては彼はかなり過小評価しており、シャプリーの推定のほうが現実に近かった。
[岡村定矩]
銀河系の基本構造
1000億個の桁(けた)の恒星と星間物質からなる銀河系は、パンケーキ状の薄い円盤(ディスク)とそれを包み込むようなほぼ球状のハローから成っている。ディスクの中心部分には膨らんだ楕円体状の構造があり、バルジとよばれている。太陽はディスク中にあり、中心から約2万5000光年の位置にある。天の川は、ディスクを内側から真横(エッジオン)に見た姿である。
ディスクは中心近くほど質量密度が高く、外側にいくにつれて密度は指数関数的に減少する。最外縁部は半径で約6万光年くらいまで広がっている。星と星間物質の大部分はディスクにあり、星が約9割、星間物質が約1割の質量を占める。星間物質はディスクの赤道面に濃く凝集している。そこでは星間ダストによる吸収も強いので、天の川が中央の暗い帯(ダークレーン)で二分されているように見える。ディスク中の星と星間物質は銀河系中心のまわりを回転している。太陽の位置での回転速度は毎秒約220キロメートル(回転周期約2億年)であるが、広い半径にわたって回転速度はほぼ一定である。ディスクでは、星生成活動が現在でも起きており、散開星団、発光星雲、暗黒星雲などが見られる。ディスクにある星を種族Ⅰという。
正面向き(フェイスオン)に見えている銀河の渦巻構造は容易に観測できるが、銀河系では太陽がディスク内にあることと、星間吸収が強いために、銀河系ディスクの渦巻構造を可視光で見ることはできない。中性水素原子が放つ波長21センチメートルの電波輝線が観測できるようになって、1958年にオールトらがディスク内の中性水素ガスの密度分布を描き出すことに成功した。電波は星間ダストに吸収されることがなく、銀河系全体を見通すことができるからである。この研究によって初めて、銀河系が渦巻腕構造をもつことが実証された。ハローは年齢の古い種族Ⅱの星から成るが、その密度はディスクに比べるとはるかに低い。太陽近傍で見ると、ハローに属する星の密度は、ディスクに属する星の密度の約1000分の1である。ハローには球状星団が点在しており、これまでに約150個が知られている。ハローの星や球状星団は、銀河中心のまわりを回ってはいるが、ディスクのようにそろった回転ではなく、それぞれがほとんど無秩序にさまざまな軌道で回転運動をしている。
バルジは中心ほど密度が高いラグビーボールのような回転楕円体で、銀河系の棒状構造を形づくっており、およそ100億個の恒星があると推定されている。星間吸収が強いため、バルジの詳しい観測はむずかしい。
[岡村定矩]
基本的観測量
銀河系は、個々の星の成分と運動を詳しく調べることができるほぼ唯一の銀河である。星の位置と運動を調べるには、(銀経、銀緯)からなる銀河座標系を用いることが多い。銀河系のディスクの中心面(銀河面)と天球面の交線を銀緯0度とする。この線は天球上で天の川の中心線とほぼ一致する。この線に垂直方向に南にマイナス90度、北にプラス90度まで銀緯をとる。一方、銀経は銀緯0度の線に沿って測る。銀河系の中心方向を銀経0度と定め、0度から東向きに360度までとる(天の赤道と銀河面は大きく傾いているので、ここでいう東西南北は単に方向を示すために便宜上用いていることに注意)。
多くの恒星に対してその位置と速度、および金属量などの組成を知ることは銀河系研究の基本である。三次元空間での星の位置と速度は次のようにして求める。
銀経と銀緯によって天球上の星の位置が決まる。さらに、距離を決めれば、銀河系の中での三次元的な星の位置が決まる。星の距離は、年周視差法をはじめとしてさまざまな方法で測る。星の速度は、視線方向とそれに垂直な方向に分けて測定される。視線方向の速度成分(天球面に垂直な成分)は、星のスペクトルを観測し、ドップラー効果によるスペクトル線の偏移量から求める。視線方向に垂直な接線方向の速度成分(天球面内の成分)は、星の固有運動と距離から求める。固有運動とは、年周視差と年周光行差以外の経年的な星の天球上での位置ずれのことで、一定の時間間隔をおいて撮影された写真から測定される。通常は、角度秒/年という単位で表す。距離がわかっている星の方向が、天球上で1年で何秒ずれるか(固有運動)を測定すれば、接線方向の速度がキロメートル/秒の単位で計算できる。恒星の位置、固有運動、年周視差(距離)の観測は、1993年に打ち上げられた位置天文衛星ヒッパルコスHIPPARCOSによって飛躍的な進歩を遂げた。1ミリ秒角を切る高精度で約12万星のデータを掲げたヒッパルコス星表と、0.03秒角の精度で約100万星のデータを掲げたタイコTycho星表が1997年に公開された。
星の金属量は、その星をつくるもとになった星間ガス中でどのくらいの星生成活動が起きたかを知る目安となる。ビッグ・バンでは炭素より軽い元素しか合成されなかったので、炭素およびそれより重い元素(天文学では金属とよぶ)は、星の中心核で合成されたか、超新星爆発のときにつくられたものである。宇宙で最初にできた星では金属量はゼロであったはずである。このような星は種族Ⅲの星とよばれており、探査が続いているが、2010年現在ではまだ見つかっていない。超新星爆発により、金属を含む星の外層が吹き飛ばされて周辺の星間ガスに混じり、そこからまた星が生まれて超新星爆発を起こす。時間がたつにつれて、星からガスへ、ガスから星への星生成のサイクルが何度もまわり、星間ガス中の金属量が増加する。簡単にいえば、星の金属量はいつごろその星ができたのかを示す時計のかわりに使えるのである。ハローにある星はディスクにある星よりも金属量が少ないので、それらは銀河系形成の初期にできたと考えられている。これらの星は種族Ⅱとよばれる。これに対して、より後にできたディスクにある星は種族Ⅰとよばれる。
金属量の少ない星ほど銀河系形成のより初期段階の情報を保持している。種族Ⅲの星の探査が精力的に行われているのはこの理由からである。星の金属量を精密に測定するには、分光観測によって高分散のスペクトルを撮影することが必要だが、測光観測による簡易法もある。多くの金属の吸収線は紫外線領域にあるので、金属量が多い星ほど可視域の明るさに比べて、紫外域での明るさが吸収によって暗くなる。逆にいえば、金属量の少ない星ほど紫外域で明るい「紫外超過」を示すことになる。U(紫外)、B(青)、V(黄)の三つのバンドの測光データのなかで、Uバンドで明るい星は金属量の少ない星の候補となる。これらの星を詳しい分光観測の対象にして、低金属量星を探査する手法が広く用いられている。
[岡村定矩]
銀河系形成の描像
エゲンOlin J. Eggen(1919―1998)たちは1962年に、太陽近傍の221個の星の運動と金属量の関係を調べて、銀河系が次のようにしてできたと推論した。銀河系を生むもとになったほぼ球状の巨大なガス塊が約100億年昔に中心に向かって重力崩壊をはじめ、わずか1~2億年の間に扁平なパンケーキ型に縮まって現在の銀河系の骨格ができた。ハローの星と球状星団はこの重力崩壊過程で生まれ、その後、円盤状に降り積もったガスの中で第二次の星生成が起きてディスクの星ができた。彼らの主張する重力収縮期間1~2億年は宇宙年齢(100億年の桁(けた))と比べるとあっという間である。これは後にRapid Contraction(急激な収縮)説とよばれた。ところが、太陽近傍では金属量の非常に少ない星が、この説の予想ほど見つからないという「G型矮星(わいせい)問題」が顕在化し、また、球状星団の年齢にも、1~2億年を超える相当の幅があることがわかり、銀河系の重力収縮は10億年以上の時間をかけてゆっくりと起こったとするSlow Contraction説がジンRobert J. Zinnらによって1980年ごろに提唱された。
急激な収縮かゆっくりとした収縮かの論争はその後長く続いた。しかし、急激な収縮だけでは説明できない現象が次第に見つかり、1998年には吉井譲(ゆずる)と千葉柾司(まさし)が、エゲンらが論拠としたデータは、対象とした星の選択に偏りがあることを示した。
銀河系の周辺には数十個の矮小(わいしょう)銀河があるが、その一つ(いて座矮小銀河)が現在銀河系ハローに飲み込まれつつあることが1994年にわかった。また、CCDによる広域観測を行った、スローン・ディジタル・スカイサーベイ(SDSS)から、銀河系ハロー中に、矮小銀河が飲み込まれたことを示す痕跡(こんせき)が多数見つかった。銀河系ハローはまだ形成途上にあるともいえる(矮小銀河が大きな銀河のハローに飲み込まれていく現象は最近アンドロメダ銀河でも見つかった)。
これらのことから、急激な収縮で短い間に一挙に銀河系ができたのではないと現在では考えられている。銀河系のハロー、ディスク、バルジがどのようにして現在の姿になったのかは、現在最先端の研究課題の一つである。
[岡村定矩]
ダークマター(暗黒物質)
宇宙にあるすべての銀河には、電磁波では検出できない多量のダークマターが付随していることがわかっている。銀河系においてこの問題が明らかになったのは、1960年代初頭のオールトによる指摘からである。彼は、太陽近傍にあるK型星について、ディスクに垂直な方向の分布と運動を詳しく調べた。これらの星が、重力と運動が釣り合った静水圧平衡の状態にあるとすると、多数の星に対してディスクに垂直な方向の運動速度を観測すれば、それと釣り合うべきディスク中心面(銀河面)での質量密度がわかる。これを重力質量密度という。オールトが求めた重力質量密度は、1パーセク立方(約35立方光年)あたり太陽質量の約0.15倍であった。一方、観測されていた星の密度と星間物質の密度を合わせた値は太陽質量の0.09倍であった。これは、K型星がディスクの上下に飛び散ってしまわないために必要な重力質量密度の6割でしかない。つまり、見えていない質量が太陽近傍の空間にあることになる。この正体不明の物質は「ミッシングマス(行方不明の質量)」と名付けられた。
その後1980年代になって、銀河系と同じ多数の渦巻銀河の回転曲線の観測から、それらがすべて、重力は及ぼすが光では見えない正体不明の物質からなるハローに包まれていること、また楕円銀河のX線観測から、楕円銀河でも同様であることがわかった。重力作用は及ぼすが電磁波では観測できないこの物質は、正体は不明だが、宇宙に普遍的に存在することがわかった。それはもはやミッシングマスではなく、より普遍的な名前としてダークマターとよばれるようになった。銀河はダークマターハローに包み込まれているのである。
銀河系のダークマターハローは、白色矮星、中性子星、褐色矮星などきわめて暗い星、あるいは小質量のブラック・ホールからできている可能性もある。これらの天体はマッチョ(MACHO:Massive Compact Halo Object)とよばれる。1986年にパチンスキーBohdan Paczynski(1940―2007)は、銀河系ハローにMACHOがあれば、たまたまそれが星の手前を通過するときに、マイクロレンズ現象という重力レンズ効果で背景の星が明るく見えるはずだという予測を行った。いくつかのグループがMACHO探しのプロジェクトを開始し、1993年に二つのグループが、予測されたマイクロレンズ現象を発見した。しかし2000年頃までには、MACHOは銀河系のダークマターハローの質量の20%程度でしかないことがわかった。ダークマターの正体は2010年現在まだ不明である。
[岡村定矩]
銀河系中心
銀河系の中心は、濃いダストの吸収によって可視光ではまったく見えないといってよい。電波による観測から、中心部に非熱的放射をだすコンパクトな電波源Sgr A*(いて座エー・スター)が見つかり、これが銀河系の中心核と考えられている。
赤外線の観測技術が進み、また、大気のゆらぎを補正して地上でも高い分解能を実現する補償光学の技術が実用化され、Sgr A*のごく近傍の恒星の運動を長年にわたって調べることができるようになった。その結果、銀河系の中心核には、太陽質量の400万倍の質量をもつブラック・ホールがあることが確実視されている。
ブラック・ホールを含む活動銀河核は通常強いX線を出すが、Sgr A*はX線ではそれほど明るくない。過去に活発な活動をした時期があるが、現在は何らかの理由で静穏な状態にあると考えられている。
[岡村定矩]
『岡村定矩著『銀河系と銀河宇宙』(1999・東京大学出版会)』▽『祖父江義明他編『シリーズ現代の天文学 第5巻 銀河2――銀河系』(2007・日本評論社)』▽『『ニュートンムック よくわかる天の川銀河系――「我が銀河」の真の姿は?』(2008・ニュートンプレス)』
百科事典マイペディア 「銀河系」の意味・わかりやすい解説
銀河系【ぎんがけい】
→関連項目アンドロメダ銀河|渦巻銀河|銀河|マゼラン銀河
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「銀河系」の意味・わかりやすい解説
銀河系
ぎんがけい
Milky Way Galaxy
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
最新 地学事典 「銀河系」の解説
ぎんがけい
銀河系
Galaxy
太陽系が所属している銀河。太陽質量の約2,000億倍の恒星と星間物質などからなり,中央部が膨らんだ,直径約10万光年の円盤形をした渦巻型銀河である。円盤部を包むハロー(halo)には百数十個の球状星団が分布する。太陽系は銀河中心から2.8万光年離れた円盤部にあり,220km/sで公転している。中央部の球状の部分はバルジ(bulge)と呼ばれ,厚みは約1.5万光年,円盤部の厚みは太陽近傍で約5,000光年。円盤部には恒星やガス・塵が集中しており,恒星の平均分布密度は10光年立方当り3個程度,ガス・塵などの星間物質は銀河系全質量の10%程度である。円盤部では年齢の若い種族Ⅰの星が多く,バルジやハローには老齢の種族Ⅱの星が多い。球状星団やマゼラン雲の運動から,銀河系の可視部分を包む太陽質量の約2,000億倍の暗黒物質(dark matter)が存在すると考えられるが,実態は明らかではない。
執筆者:黒田 武彦
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の銀河系の言及
【宇宙】より
…この憶測はF.W.ベッセルその他によって恒星の視差(距離)が測定されて(1838)証明され,19世紀後半には,太陽や恒星を対象とする天体物理学が分光学など実験室における物理学の発展に伴って急速に発展することになった。 一方,太陽系を取り巻く恒星集団(銀河系)についての認識も進んだ。すでにガリレイは銀河が無数の恒星の集りであることを望遠鏡による初めての天体観測(1609)で見つけたが,その後イギリスのライトT.Wright(1711‐86)や哲学者I.カントは,われわれのまわりの恒星が太陽を中心とする凸レンズ状の孤立した系をつくっていると説いた(1750‐55)。…
※「銀河系」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...