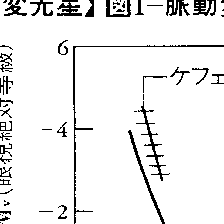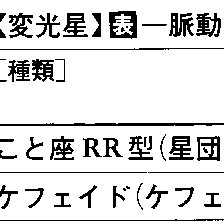精選版 日本国語大辞典 「変光星」の意味・読み・例文・類語
へんこう‐せいヘンクヮウ‥【変光星】
- 〘 名詞 〙 明るさの変化する恒星。
- [初出の実例]「変光星の光度の週期的変化の説明」(出典:ルクレチウスと科学(1929)〈寺田寅彦〉五)
日本大百科全書(ニッポニカ) 「変光星」の意味・わかりやすい解説
変光星
へんこうせい
variable star
時間とともに明るさや性質を変える恒星。
発見・観測史
恒星はその名のとおり昔は不変のものと考えられていた。だから、突然、天空に輝き始める「新星」は古代の人には大きな驚きであった。そのため多くの記録も残っている。紀元前134年にヒッパルコスは明るい新星を発見し、恒星表作製の契機とした。日本でも藤原定家(ていか)は『明月記(めいげつき)』のなかで「客星(かくせい)」の出現(1054)を記録している。この客星は銀河系に現れた超新星の一つで、その残骸(ざんがい)はいまも「かに星雲」として知られている。光度変化の科学的な測定は、ティコ・ブラーエが1572年に新星(実は超新星)を観測し、ファブリキウスが1596年にくじら座ο(オミクロン)星(ミラ)に周期的変光を発見したころから始まる。
当初は眼視観測だったので光度測定の精度も低く、発見される変光星の数も少なかったが、19世紀末葉から天体写真が実用化されるようになって精度も発見頻度も著しく向上した。当時の写真は青い色に敏感で測定精度は約0.1等級であった。20世紀に入ると、1940年代には光電測光法が導入され、同じ青色領域で精度が1桁(けた)増したが、1980年代に導入されたCCD(電荷結合素子)によってとくに赤色域を中心に感度が写真の100倍近く上昇した。測光精度が0.001等級とすると星の表面の0.09%の変光を測定することになるが、その精度で星を見ると太陽を含めたほとんどの星が変光を示すことになり、変光星との区別がますます困難になる。とはいえ、大規模な変光を示す星はなお限られており、ロシア科学アカデミー出版の『変光星総合カタログ』に記載されている変光星は1992年の時点で2万8450個に達し、その種類も20種を超えている。
また、20世紀に入ると光を波長に分解する分光観測が進展し、変光現象の物理的過程の解明に大きく貢献しているが、1950年代以降は電波、赤外線観測や大気圏外からの紫外線、X線、γ(ガンマ)線観測が急速に発展して、世界的な望遠鏡群による同時観測や地上と衛星を結ぶ共同観測など、観測法もますます多様化している。
[小暮智一]
分類
変光星の明るさの変化は光度曲線として表され、それによって変化の周期性、変光幅、増光減光のようすなどが解析される。また、分光観測によって光の波長分布、吸収線、輝線などの情報が得られれば、さらに詳しい解析ができる。
星には見かけの変光星と物理的な変光星とがある。前者は二つの離れた星が連星として共通重心の周りを公転しているのを、たまたま軌道面に近い方向から見るために食現象がおこって変光するという場合である。後者には一つの星自体に原因をもつ場合と、近接連星として相互作用で変光をおこす場合がある。
物理的変光星はさらに変光周期によって短周期、長周期、不規則に分類できる。短周期変光星にはケフェウス座δ(デルタ)星、こと座RR星などがある(周期1日から数十日)。星自体の不安定性による膨張収縮運動(脈動)が基本的な変光の原因となっているので脈動変光星という。長周期変光星は赤色巨星に集中しており、周期は150日から400日くらい、やはり脈動型の変光である。一方、不規則変光星には誕生期の変光と爆発型の変光とがある。変光の原因は星の周辺または表層部における突発的なエネルギー解放によるもの、近接連星におけるガス流と星または星を取り巻く円盤との衝突によるものなど、原因は多様である。
変光星はかつては通常の星とは別種の特別の星と考えられていたが、1950年代以降に発展した星の進化論によって、星の変光が進化の道程と深い関係をもつことが明らかになった。どの星も進化のある段階でその段階に特有の変光星になると考えられている。
[小暮智一]
星の進化と変光星
恒星は星間空間の冷たい塵(ちり)(星間物質)の雲の重力による凝集によって誕生する。雲の凝縮は密度、温度の高い中心部が先行し、中心核に原子核反応によるエネルギー生産が始まると一人前の星となる。初期に雲の周辺にあった塵はゆっくりと下降して星に取り込まれ複雑な変光現象を生じる。自分の重力で収縮中の星を前主系列星、水素核反応で輝く星を主系列星とよんでいる。主系列星はきわめて安定した星なのでほとんど顕著な変光をおこさず、短くて数千万年(青い星)から数百億年(赤い星)まで安定した光を放つ。核反応によって水素が枯渇すると星は主系列を離れ、不安定期に入り、最後に星の中心部での核反応が終結すると星は爆発するか、自分の重力でつぶれてしまう。それを「星の死」とよんでいる。このような星の一生に関連して変光星は次のように区分けできる。なお、(1)~(3)は単独の星の進化に関係する。
(1)誕生期(前主系列)の変光星
(2)不安定期(主系列星以後のおもに脈動変光星)
(3)星の最後(死)に伴う変光星
(4)連星系の進化に伴う変光星
[小暮智一]
誕生期の変光星
代表的な星はおうし座T型星である。星本体もまだ収縮中で中心核反応がおこっていないので中心温度も低く、表面近くでは大規模な対流運動が発達している。対流層からは太陽の彩層やコロナのようなガスの噴出と爆発が続き不安定な変光を生じる。また遅れて降り積もった塵のガスもそれに巻き込まれて毎秒数百キロメートルの高速ガスを流出させたりガスどうしの衝突で紫外線やX線を放射したりするなど活発な運動が繰り返されている。おうし座T型星はおうし座やオリオン座などの若いガス星雲や冷たい塵の雲の近傍に群をなして存在し、星の生まれつつある領域の代表的天体である。
星は誕生期を経て主系列星へと進むと一般には安定になるが、低温のM型星では閃光星(せんこうせい)(フレア星)とよばれる星があり、活発な彩層活動で爆発的増光を繰り返す。これは太陽表面のフレア現象が大規模になったものと考えられる。光で見ると数秒間で急激に増光し、数分から数時間でしだいに減光する。X線ではさらに急激な立ち上がりを示すが、電波では逆に緩やかな増光減光を示す。これらは太陽フレアともよく似ており、太陽フレアと同じように星の表面に強い磁場を伴った領域が存在することを示唆している。
[小暮智一]
脈動変光星
主系列星の中心部で水素が消費されヘリウムが蓄積してくると、星は主系列を離れ、中心核の密度、温度を増加させながら星の外層部は逆に膨張し、巨星から赤色巨星へと向かう。その道程で星は二つの顕著な脈動不安定帯を通過する。第一の不安定帯はケフェウス型変光星で短周期の脈動星である。第二は低質量星の進化した赤色巨星の領域に現れ、長周期変光星(ミラ型変光星)とよばれる。
一般に脈動変光星は脈動運動とともにその明るさを変えるが、明るさの極大・極小は星の半径の極小・極大の時期より遅れて現れる。これは、星内部の脈動が波となって表面に達するまでに時間がかかることを示している。また、変光の周期は星の平均密度と関係があり、平均密度の大きい星ほど短い周期で脈動する。ケフェウス型不安定帯の底部にあたる、たて座δ星では変光周期はわずかに2時間程度である。脈動変光星のうちケフェウス型と周期1日程度の星団型変光星では、平均の明るさと脈動周期との間に周期光度関係とよばれる関係があり、周期の長い星ほど光度が高い。この関係を利用すると変光周期の観測から星の絶対光度が求められ、見かけの明るさとの比較からその星までの距離が推定できる。数十日以上の長い周期のケフェウス型変光星は超巨星なので遠方からも発見されやすい。そのため、この方法は遠方の星団や系外銀河までの距離を測定する有力な方法である。宇宙の構造を探るうえで脈動変光星は重要な役割を担っている。
[小暮智一]
星の最後(死)の時期の変光星
星の中心部で核反応をおこす元素は進化とともに水素、ヘリウム、炭素など軽い元素からしだいに重い元素へと移っていくが、反応をおこすもっとも重い元素は鉄である。鉄まで反応をおこすのは質量が太陽の30倍以上の重い星である。鉄まで反応すると、重い星は最後を迎え、超新星爆発をおこして質量の大部分を吹き飛ばす。その後に残るのは中性子星か、ブラック・ホールである。鉄まで反応できない質量の小さい星は赤色超巨星となり、やがて核燃料を使い尽くすと熱源がなくなるので、星は自分の重力のためにつぶれる。その際、星の表皮を大きく飛び散らせ、美しい惑星状星雲を形成する。あたかも天空の花火に似た現象である。それが質量の小さい星の最後である。星がつぶれると白色矮星(わいせい)とよばれる超高密度星となる。たとえば太陽は約50億年後につぶれ、半径が地球ほどの白色矮星になる。つまり、地球がそのまま30倍の太陽質量になるわけであるから、白色矮星は平均密度が1立方センチメートルあたり1トン程度という高い密度である。
[小暮智一]
連星系の進化に伴う変光星
星の仲間には連星が多い。星全体の50%以上が連星ではないかと推測されている。連星系では二つの主系列星から同時に進化を始めても、星は質量が大きいほど進化が早いから、主星(連星を構成する星のうち、光度の明るいほうの星)が大質量星なら先に中性子星かブラック・ホールになるし、中小質量星であれば白色矮星になる。どれも超高密度星である。連星の相手が中性子星であるとパルサーとして観測されることがある。これは中性子星が非常に強い磁場をもち、また回転周期が数秒から1000分の数秒といった高速自転をしているので、その周期にあった電波、光、X線などをパルスとして放射するからである。連星の相手が白色矮星であると大質量星とは異なった変光星となり、とくに重要なのは激変星とよばれる星である。
[小暮智一]
激変星と新星の仲間
激変星とは爆発的に明るくなってしだいに減光する変光星の仲間で、歴史的に1回の爆発記録のあるものが新星、数十年をおいて爆発を繰り返す星が回帰新星、それより増光の規模が小さく爆発の間隔も数十日と狭い星を矮新星、また、爆発的な現象は示さないが新星に似た性質を示す星を新星類似星とよんでいる。激変星とはこれらの総称である。いずれも連星系で、先に進化した星はすでに星としての生涯を終えた白色矮星になっており、それに続く伴星(連星を構成する星のうち、光度の暗いほうの星)もかなり進化が進んで肥大化した暗い赤色星が多い。激変星にも静穏期と活動期(爆発時)があるのは、伴星が間欠的に多量のガスを主星に送り込み、その一部は主星に衝突し、一部は主星を回る回転ガス円盤に衝突爆発するためである。こうして間欠的に流れ込んだガスが星の表面または回転円盤に衝突して爆発すると種々の新星になるが、どのタイプになるかは主星と伴星の質量、相互距離、間欠の期間、流れ込むガス量などによって決まる。
[小暮智一]
『北村正利著『星の物理』(1974・東京大学出版会)』▽『下保茂著『変光星の探求』(1980・恒星社厚生閣)』▽『ディヴィド・H・クラーク著、岡村浩訳『超新星』(1987・海鳴社)』▽『桜井邦朋著『星々の宇宙――その現代的入門』(1987・共立出版)』▽『尾崎洋二著『宇宙科学入門』(1996・東京大学出版会)』▽『尾崎洋二著『星はなぜ輝くのか』(2002・朝日出版社)』▽『伊藤直紀著『宇宙の時、人間の時』(朝日選書)』
改訂新版 世界大百科事典 「変光星」の意味・わかりやすい解説
変光星 (へんこうせい)
variable star
明るさが時間とともに変化する星。変光星の発見は,16世紀末ドイツの天文学者D.ファブリチウスによるくじら座のミラの発見に始まる。ファブリチウスは,1596年の8月くじら座にある2等星がだんだん暗くなっていき,その年の10月には肉眼ではまったく見えなくなってしまったことに気がついた。当時は,恒星はすべて位置も明るさも変わらないものと考えられていたので,非常に不思議なことと思われ,この星にラテン語で“驚き”という意味のミラという名がつけられた。ミラは,11ヵ月の周期で2等から10等まで変光する長周期変光星と呼ばれる星の代表である。実は,ミラの発見以前に新星現象は知られていた。新星現象とは,夜空の一角に突如として新しい星が輝きだし,数日のうちに1等星もしのぐほどの明るさになるが,その後まただんだん暗くなり,ついには消えてしまう現象である。新星は,実は新しい星が生まれたのではなく,ふだんは肉眼で見えないような暗い星が,突然数千倍あるいは数万倍も明るくなり,また元の明るさに戻るもので,変光星の一種である。ミラの発見以後17,18世紀には,アルゴルの名で知られる食変光星,ペルセウス座β星の変光の発見,ケフェイド変光星の代表であるケフェウス座δ星の変光の発見などあるにはあったが,この間変光星の数はほとんど増えなかった。19世紀に入ると,天体望遠鏡を使って暗い星まで系統的に変光星を探す試みがなされるようになり,変光星の数は急速に増加した。さらに19世紀末から20世紀にかけて,写真術の発明により天体写真を使う方法が開発され,変光星の数は飛躍的に増大した。そして20世紀に入ると,光電管を使って星の明るさを精密に測る天体測光法が確立され,変光星の探索と観測技術は格段に進歩した。現在,変光星としてカタログに載っている星の数は2万5000個以上あり,しかも毎年いくつも新しい変光星が見つかっている。また,現在では,可視光以外の電磁波であるX線,紫外線,赤外線,電波などでも恒星が観測されるようになったが,これらの波長域の場合,星はむしろ時間的に変動があるのがふつうといってもよいくらいである。また,光ではあまり顕著な変光は認められないが,スペクトルが時間的に変化するという星もあり,分光変光星と呼んでいる。
変光星の命名法
変光星の名前のつけ方であるが,すでにギリシア文字やアルファベットなどで名前がついている星はそのままにして(例えばペルセウス座β星),新しく発見された変光星の場合は,各星座ごとに発見の順にRからZまでの名をまずつける(例えばおとめ座W星)。次からはRR,RS,……,RZ,SS,……,SZ,TT,……,ZZまで続く。ZZは54番目である。55番目からは,AAに戻って,AA,AB,……,AZ,BB,……,BZ,……,QQ,……,QZと続けられる。ただしJの字はIの字とまぎらわしいので一度も使われない。QZが334番目で,335番目からは,ローマ字V(variable starの頭文字)を頭につけV335,V336,……と続けられる。
変光星の分類
変光星は,大別するとその変光原因によって外因的変光星と内因的変光星の二つに分類される。
(1)外因的変光星は,幾何学的変光星とも呼ばれ,星本体の明るさは変化していないのだが,星の幾何学的位置関係が観測者に相対的に変化するために,見かけの明るさが変化して観測される星である。幾何学的変光星の代表は食変光星である。食変光星は,二つの星が連星系を作っていて,その共通重心のまわりに軌道運動しているのだが,たまたま軌道面が観測者の視線に近い方向を向いている場合,ちょうど日食のとき月が太陽を隠すように二つの星が交互に相手の星を隠す食現象によって,周期的に明るさが変わる星である。そのほか,磁変星も幾何学的変光星の仲間に入れることができよう。磁変星は磁場が観測されていて,磁場の強さが周期的に変化する星である。この現象は,星の自転軸と磁軸が傾いていて,星の自転により磁極が観測者側に現れたり消えたりするため,磁場の強さが変化して観測される,いわゆる“斜回転モデル”で説明される。パルス状電波を出すパルサーも,中性子星の斜回転モデルによって説明される一種の幾何学的変光星といえよう。
(2)内因的変光星は,物理的変光星とも呼ばれ,恒星内部の物理状態が時間的に変化するために,実際に明るさが変化する星である。物理的変光星の代表は脈動変光星である。脈動変光星は,星自身が膨張と収縮を繰り返すために明るさが変化する星である。物理的変光星としてはそのほかに,新星に代表される突然明るさを大きく変える新星型変光星(激変星ともいう),新星より規模が大きく星全体の大爆発である超新星,太陽フレア(太陽面爆発現象)を大規模にしたようなフレアが観測されているフレア星などがある。また星間雲の中から生まれたばかりの星おうし座T型星は,誕生の際の余波で不規則な変光をする物理的変光星である。
脈動変光星
すでに述べたように,脈動変光星は,星自身が規則的に膨張と収縮を繰り返しているために明るさが変わる星で,現在,銀河系の中だけで1万8000個以上知られている。
脈動変光星の分類
脈動変光星は,その変光の周期と特徴,スペクトル型,銀河系内での分布や運動により,いくつかのタイプに分類される。このように分類された脈動変光星の種類と特徴を表に示す。また,図1はこれら脈動変光星のHR図上の位置を示したものである。以下では代表的脈動変光星についてその特徴を見てみよう。
(1)こと座RR型星 この型の変光星は,最初,球状星団の中で多く発見されたため,星団型変光星と呼ばれていた。その後,球状星団以外でもたくさん見つかるようになり,もっとも明るく代表的な星の名をとり,こと座RR型変光星と呼ぶようになった。この型の星の脈動周期は,1.5時間から24時間にわたり,代表的周期として約半日である。こと座RR型星は,球状星団や高速度星の中で多く発見される種族Ⅱを代表する脈動変光星である。またスペクトル型はA2からF6で,絶対等級は+1等級から0等級くらいの狭い範囲に限られている。この型の変光星の明るさが星によらずほとんど同じで,絶対等級が0等であるという性質を使って,シャプレーが銀河系内に分布する球状星団までの距離を求め,現在知られている銀河系の大きさを決めた話は有名である。図2は,こと座RR型星の三つの代表的光度曲線を示す。光度曲線というのは,光度を縦軸に,時間を横軸にとって,変光星,新星などの光度変化のようすを示す図である。
(2)ケフェイド変光星 ケフェウス座δ星を代表とする脈動変光星で,ケフェウス座δ型変光星,またはケフェイド,セファイドなどともいう。この型の星の脈動周期は1日から50日,変光範囲は0.2等から1.5等で,ケフェウス座δ星自身の場合,周期5.366日,変光の振幅約1等である。ケフェイドは,若い天体の集りである種族Iの天体で銀河面内に集中している。現在,この型の変光星はわれわれの銀河系中に700個ほど見つかっている。またわれわれのお隣りの銀河である大マゼラン銀河,小マゼラン銀河の中にもたくさんのケフェイド変光星が発見されている。HR図上で,ケフェイド変光星は斜め右上から左下にかけて細長い帯状の領域に分布しており,これをケフェイド不安定帯と呼んでいる。ケフェイド変光星は,すでに中心で水素を燃え尽くし,現在,中心でヘリウム燃焼段階にある星と考えられている。ケフェイド変光星が天文学上果たしたもっとも重要な役割は,宇宙のものさしとしての役割である。ケフェイド変光星の場合,周期光度関係といって,脈動周期と星の平均絶対光度との間に一定の関係があり,周期の長い星ほどその絶対光度が明るくなっている。今かりに,ある銀河系外星雲の中にケフェイド変光星が見つかり,その脈動周期がわかったとすると,周期からその星の絶対光度がわかり,それと見かけの明るさを比較することにより距離が求められることになる。アンドロメダ銀河などわれわれの銀河系近傍にある銀河までの距離は,現在この方法によって決められている。
(3)長周期変光星 最初に述べたミラを代表とする赤色巨星,あるいは超巨星の脈動変光星で,その脈動周期が100~1000日とたいへん長い星である。また,これらの変光星のうち,変光の振幅が2.5等以上のものをミラ型変光星,2.5等以下のものを単に長周期変光星ということもある。さらに,これらの星に比べて,変光の振幅も小さく,また変光の規則性も悪い赤色半規則星,不規則変光星と呼ばれる星があるが,これらも含めて長周期変光星と総称することが多い。ミラ型変光星の中には,変光の振幅が8等から9等と極端に大きな星がある。しかし,これは可視域での明るさの変化の話であり,すべての波長域にわたる全放射光度を考えれば,これらの星の変光も1等ないし2等にすぎない。ミラ型のスペクトルでは顕著な輝線が現れるのが大きな特徴で,これは脈動により衝撃波が発生し,星の大気中を伝播(でんぱ)するために生じたものと解釈される。長周期変光星は,恒星の中でもっとも半径の大きく,表面温度の低い星である。
(4)おとめ座W型星とおうし座RV型星 ケフェイドは典型的種族Ⅰの星であるが,球状星団などの種族Ⅱの天体中にも,周期が1日よりも長い脈動変光星があり,種族Ⅱのケフェイド,あるいはおとめ座W型星と呼んでいる。種族Ⅱのケフェイドの場合,光度曲線で極大の山の後に“肩”と呼ばれる膨らみがあるのが特徴である。種族Ⅱのケフェイドにも周期光度関係があるが,同じ周期の種族Ⅰのケフェイドに比べて1.5等ほど暗い。おうし座RV型変光星はおとめ座W型星を長周期側に延長したところにある脈動変光星で,この型の星の変光の特徴は光度曲線が不規則なことで,光度極小の谷が交互に深くなったり浅くなったりする。
(5)たて座δ型星 この型の変光星は,HR図上でケフェイド不安定帯を光度の低い側に延長して主系列と交わる付近にある脈動変光星である。脈動周期は1時間から4時間,変光の振幅は一般に小さく0.3等以下である。光度曲線は一般に複雑で,いくつかの振動が重なった多重周期の星が多い。
(6)ケフェウス座β型星 脈動変光星は一般に表面温度の低い晩期型星が多いが,ケフェウス座β型変光星は例外でスペクトル型がB1~B2と早期型星である。この型の変光星は,脈動周期3~6時間,一般に変光の振幅が非常に小さく,発見がむずかしい。この型の変光星の約半数に,光度曲線に“うなり”の現象が観測されている。うなりというのは,振動の振幅が規則的に大きくなったり小さくなったりする現象で,ケフェウス座β型星の場合,うなりの周期は7~50日である。
(7)くじら座ZZ型星 この型の星は,白色矮星(わいせい)の脈動変光星で,現在十数個見つかっている。脈動周期は100~1000秒程度,変光範囲は0.01~0.3等である。一般に光度曲線は複雑で,多重周期のものが多い。図3は,このグループでいちばん変光範囲の大きいおうし座HL-76という星の光度曲線である。くじら座ZZ型は,DA型といって水素の吸収線のみが強く出ている白色矮星のスペクトルをもち,色指数から求めた星の表面温度が1万Kから1万3000Kと,狭い範囲に限られているのが特徴である。この星の脈動は,のちほど述べる非動径振動と呼ばれる振動であると考えられている。
脈動現象
それでは,脈動変光星の脈動とはどんな現象であろうか。恒星は,内部が高温高圧のガス球で,自分自身が作りだす重力と内部の圧力がバランスして一定の大きさに保たれている。今かりに,このような星をほんのわずかだけ膨張,または収縮させて手を放したとしよう。すると星は元の平衡の大きさに戻ろうとして振動を始める。これは星の自由振動,あるいは固有振動と呼ばれるものである。脈動変光星の脈動は,基本的にはこのような星の固有振動なのである。星の固有振動には動径振動と非動径振動の2種類がある。動径振動というのは,星が球形を保ったまま膨張と収縮を繰り返す振動である。それに対して,非動径振動は星の形状が球形からずれるような振動である。ケフェイド,こと座RR型など大部分の脈動変光星の脈動は動径振動と考えられている。しかし,白色矮星の変光星くじら座ZZ型星の脈動,太陽の5分振動などいくつかの現象は,星の非動径振動と考えられている。星の動径振動は,その復元力がガスの圧縮性によるもので,一種の“音波”の定在波振動である。定在波振動で,動かない場所を振動の“節”といい,いちばん大きく振れる場所を“腹”という。星の固有振動の場合も,弦の振動と同じように,内部に節の一つもない基準振動,節が一つの第1倍振動,……がある。ケフェイドなど脈動変光星の脈動は,大部分基準振動であろうと考えられている。しかし,こと座RR型のうちベイリーのc型と呼ばれる光度曲線をもつ星の場合のように,第1倍振動の脈動が考えられている例もある。また,動径振動が音波の定在波振動であるということを使うと,星の脈動周期は星の平均密度の平方根に逆比例するという関係を得る。星の内部の平均密度が低い巨星の脈動変光星の周期は長く,平均密度の高い白色矮星の脈動周期は短いという相似則を,この関係は表している。また,ケフェイド変光星に周期光度関係があるのも,この周期平均密度関係という相似則のためである。
脈動励起機構
脈動変光星の脈動は星の固有振動であると述べた。しかし,星の振動も弦の振動と同じように粘性や熱により振動エネルギーが散逸してしまうので,ほうっておけばやがて減衰する。しかし,脈動変光星の場合,脈動はいつまでも減衰せず一定の振幅を維持している。これは,脈動変光星の内部に特別な脈動を維持する機構が働いていて,そのために脈動が減衰しないのである。この特別な機構を脈動励起機構,あるいは脈動維持機構という。脈動変光星の脈動維持機構についてはいろいろ研究されており,ケフェイドやこと座RR型など代表的脈動星の脈動維持機構は現在ではよくわかっている。これらの星の場合,星の表面から少し内部に入ったところに,水素およびヘリウムが部分電離の状態にある層がある。これらの層は,ちょうど自動車のエンジンのように,星の熱エネルギーを振動の運動エネルギーに転換する熱機関の働きをして脈動を維持している。
執筆者:尾崎 洋二
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「変光星」の意味・わかりやすい解説
変光星【へんこうせい】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「変光星」の意味・わかりやすい解説
変光星
へんこうせい
variable star
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...