デジタル大辞泉 「銀河」の意味・読み・例文・類語
ぎん‐が【銀河】
2 銀河系と同等の規模をもつ無数の恒星や星間物質からなる集合体。形から、渦巻き銀河・棒渦巻き銀河・楕円銀河・不規則銀河などに分類される。銀河系外星雲。系外銀河。小宇宙。島宇宙。
[類語]天の川・銀漢・星・スター・恒星・惑星・星座・綺羅星・星辰・星屑・星雲・星団・首星・流星・流れ星・彗星・箒星・一番星・一等星・新星・超新星・変光星・ブラックホール・連星・主星・伴星・遊星・小惑星・衛星・α星
翻訳|galaxy
星が数百億から数千億集まった集団。138億年前、宇宙が誕生した後、約38万年後に水素やヘリウムなどの元素ができ、これらの元素を材料に星が形成された。130億年前には、銀河が既に宇宙にあったことが、観測で分かっている。宇宙には銀河がたくさん集まっている場所とそうでもない場所があり、場所によって渦巻きや
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
数千億個の星とガス星雲、暗黒星雲とからなる大集団で、宇宙を構成しているユニットの天体である。アンドロメダ銀河はその代表例。銀河は、かつては銀河系外星雲、島宇宙、小宇宙などとよばれていたが、いずれも同じものである。近年では「銀河」とよぶことが多い。太陽が属する銀河系も銀河の一つであり、他と区別するために英語では銀河系の場合、頭文字を大文字にしてthe Galaxyと記される。
[若松謙一]
18世紀後半につくられたメシエの星雲カタログ(『メシエ・カタログ』)には100個あまりの星雲がリストされており、そこには渦状(かじょう)星雲や楕円(だえん)星雲などの銀河が、オリオン星雲やヘラクレス座の球状星団とともに区別なく記載されている。1888年ドライヤーによって出版された『NGC星表』には、リストされた星雲数が7840個にも及んだ。そして奇妙なことに、他の星雲が天の川に沿って多く発見されるのに対して、渦状星雲や楕円星雲は天球上、天の川を避けて分布しているのである。一方、19世紀中ごろから分光学が天体観測にも利用され始め、その結果、星雲にはガスからできているものと、星からできているものとがあることがわかってきた。1864年イギリスのW・ハギンズは、渦状および楕円星雲が太陽のような吸収線スペクトルを示すことを発見、それらが「星の集団」であることをつきとめた。しかし渦状や楕円構造をもつ星雲状天体が銀河系に属する小規模の天体なのか、あるいは銀河系外にあって、わが銀河系と同規模の天体なのかは、20世紀初頭の天文学における大きな論争点であった。この論争に決着を与えたのは、これらの天体までの距離の決定である。
1912年、アメリカの女性天文学者リービットは、小マゼラン星雲中のケフェウス型変光星について周期‐光度関係を発見した。つまり変光周期を観測するだけで星の真の明るさが推定できるのである。距離が未知の星について、その変光周期を観測することにより、星からどれほど遠ざかれば、観測される等級にまで暗く見えるかが計算でき、したがって星までの距離が測定できることになる。この方法は現在でも距離決定の基本的方法の一つである。1923年ハッブルは、当時建設されたばかりのウィルソン山天文台の2.5メートル望遠鏡を用いて、アンドロメダ銀河および数個の明るい星雲中にケフェウス型変光星を発見し、数百万光年という遠方の距離測定に成功して論争に終止符を打った。これによって、渦状星雲や楕円星雲は、わが銀河系と対等な独立した宇宙であり、星やガスを含む一大システムであるという理解が確立した。星雲の分類がハッブルによって提案されたのは1926年である。
1929年ハッブルは、多くの銀河がわれわれからの距離に比例する速さで遠ざかって運動していることを発見し、宇宙が膨張していることをつきとめた(ハッブルの法則)。この発見によって、宇宙全体の構造や進化を調べる宇宙論の研究がいっそう発展することとなった。1943年バーデは、アンドロメダ銀河の星を観測し、恒星には年齢の若い星と古い星とがあることを発見、前者を種族Ⅰ、後者を種族Ⅱと分類した。
1950年代になると、ある種の銀河から強い電波が発せられていることが発見され、銀河中心核の激しい活動にその原因があることがわかってきた。1963年シュミットMaarten Schmidt(1929―2022)によって奇妙な天体クエーサーが発見された。その後も電波による低温の水素ガス雲や分子雲の観測、X線による数億度のガスの検出、赤外線による誕生直前の原始星の発見などが相次いで行われている。観測の多面化によって銀河の構造、進化および宇宙論の研究は著しい進歩をみせている。
[若松謙一]
ハッブルの分類では、銀河をその形態によって、楕円銀河(E)、渦状銀河(S)、棒渦状銀河(SB)および不規則型銀河(Irr)の四つに大別する(括弧(かっこ)内はその記号)。
[若松謙一]
楕円体状の外観を示し、中心から周辺にかけて緩やかに暗くなる。見かけの扁平(へんぺい)率によって、E0, E1,……, E7と細分する。ここで添え数字は、銀河の長径をa、短径をbとするとき、10×(a-b)/aを表す。E0は球形の銀河、E7はもっとも扁平率の高い銀河を表し、添え数字が8、9となるような扁平率の進んだ楕円銀河は存在しない。楕円銀河は一般に明るさのむらや吸収物質による内部構造を欠き、表情に乏しい。これは、楕円銀河を構成する天体が年齢の古い種族Ⅱの恒星に限られ、青白色巨星、星間ガス、宇宙塵(じん)などの種族Ⅰの若い天体が欠如するためである。楕円銀河の質量は、その全質量が太陽の1兆倍を超す巨大なものから、100万倍以下の小さなものまでさまざまである。
[若松謙一]
一般に中心部の球状のバルジ部と、それを取り巻く扁平な円盤部とから成り立ち、渦状構造はバルジ部の縁(ふち)から始まって、円盤部の外縁で消える。円盤部に対するバルジ部の大きさと渦状構造の発達度および渦巻の巻き方の弛緩(しかん)度により、Sa、Sb、Sc型に細分される。Sa型は大きなバルジ部の周りに比較的小さい円盤部をもち、その上に渦状構造がようやく認められる程度である。SbからScと進むにしたがい、バルジ部が相対的に小さくなり、渦状構造が発達してくると同時に、渦状腕は間隔が開いて弛緩した状態になる。バルジ部が種族Ⅱの古い星からなるのに対し、円盤部、とくに渦状腕に沿って青白色巨星を含む種族Ⅰの若い星、HⅡ領域(ガス星雲)、暗黒星雲などが複雑に分布し、不規則な模様を示す。アンドロメダ銀河は典型的なSb型銀河であり、わが銀河系もSb型と考えられている。
[若松謙一]
バルジ部から対称に棒状構造が伸び、その先端から渦状腕が始まる。S型と同様にSBa、SBb、SBcに細分される。SBaからSBcへと渦状腕はしだいに弛緩状態になり、バルジ部も小さくなっていく。また、青白色巨星、HⅡ領域、暗黒星雲の分布もS型とほぼ同様にSBaからSBcにかけて顕著になる。棒状構造に沿って顕著な暗黒星雲の列が見られることが多い。
[若松謙一]
ハッブルの形態分類で、E7からSa、SBaへの分岐点にたつ銀河として、1936年ハッブル自身によって追加された中間型の銀河である。扁平率がS型と同程度に進んでいること、バルジ部と円盤部との二つの成分が認められることなどはS型に属する性質であるが、円盤部の渦状構造は見られない。種族Ⅱの星ばかりからなり、中性水素ガスや暗黒星雲がほとんどない点などはむしろE型銀河に近い。巨大銀河団のなかによくみいだされることから、S型銀河のガス成分が銀河どうしの衝突によってはぎ取られたものとする説もある。
[若松謙一]
明瞭(めいりょう)に区別される二つの型に細分される。IrrⅠ型はハッブル系列のScやSBcからの続きとして、明るいO型星、B型星やHⅡ領域に富み、中性水素ガスも多量に存在する。しかし形態は回転軸対称を示さず、渦状構造にも欠けている。大・小マゼラン星雲がその代表例。IrrⅡ型は基本的にはE型やS0型の構造であるが、糸状の暗黒星雲が銀河全面にわたって不規則に分布する。M82銀河はその代表例。
[若松謙一]
数千億個に及ぶ星の集団である銀河は、星どうしが万有引力で互いに引き合っているため、そのままでは銀河はつぶれてしまう。その形を保つためには個々の星は激しく運動している必要がある。楕円銀河は非等方的な動径方向の乱雑運動によってその膨らんだ構造を保っている(後述)。渦状銀河は回転運動によって円盤の形を維持している。渦状銀河の回転運動は、1912年スライファーが初めて検出した。わが銀河系の回転運動も1927年オールト、リンドブラッドBertil Lindblad(1895―1965)による星の固有運動と視線速度の解析から理論が打ち立てられ、銀河回転のようすが明らかになった。
銀河回転のようすを描いた曲線は「回転曲線」とよばれ、近年、大型の光学望遠鏡によるHⅡ領域の観測や、電波望遠鏡による中性水素ガス、CO分子雲などの観測によって詳しく調べられている。回転の中心に対して、われわれ観測者に近づくように運動している側では、ドップラー効果のためにHⅡ領域やCO分子雲から発した輝線はその波長が短いほうにずれ、反対に遠ざかるように運動している側では長い波長側にずれることになる。銀河内の各場所ごとの波長のずれの大きさを測定することにより回転曲線が得られる。
銀河の中心部では、回転スピードは中心からの距離に比例して大きくなっているのに対して、ある距離より外側では一定の回転スピードのままである。その結果、中心部分の星やガスは銀河内を速く一周しているのに対し、周辺部ではゆっくり一周することになる。このような回転運動は微分回転とよばれている。最大回転スピードは一般に、大きな銀河ほど大きく、秒速300~350キロメートルにも達している。しかし銀河は、直径が10万光年以上にも達する巨大なシステムであるために、1回転するのに周辺部では2億年もかかっている。銀河の年齢が135億年程度と推定されているので、銀河の誕生以来、その回転はまだ中心部で数百回転、周辺部で数十回転しかしていないことになる。
[若松謙一]
銀河の質量は、渦状銀河ではその回転運動の大きさ、楕円銀河では乱雑運動の大きさを測定することによって求められる。銀河が力学的平衡状態を保っていることにより、星やガスの運動は銀河内の万有引力の強さ、したがって物質分布のようすを表していることとなり、銀河の総質量が求められる。
回転曲線から求めた渦状銀河の質量は、太陽の質量(2.0×1030キログラム)の1010~1012倍程度である。楕円銀河では太陽の質量の106倍の非常に小さなものから1013倍にも達する巨大なものまである。不規則型銀河では106~1011倍といろいろな質量の銀河が存在する。回転曲線から求めた渦状銀河の質量分布は、銀河の表面の明るさから推測されるよりもはるかに広がっていて、銀河周辺部に多量の物質が隠れて分布していることがわかった。この検出されていない物質を「ミッシング・マス」(見えない物質)または「ダークマター」とよんでいる。その量は「見えている」物質の数倍にも達している。この物質を求めて多種多様な観測が試みられている。たとえば、電波望遠鏡による低温度(~100K)の中性水素ガスや分子雲のサーベイ、紫外線やX線による高温度(10万~数千万K)の電離ガスの検出、赤外線による低温度星や星間塵(じん)の検出、重力レンズ現象を利用したマッチョとよばれる惑星規模の小天体の検出などである。しかし、現在においてもいまだ検出されていない。
渦状銀河の周辺に多量のミッシング・マスが存在することは、1973年、オーストライカーJeremiah Paul Ostriker(1937―2025)とピーブルスによって、棒渦状銀河の力学からも論じられている。つまり、多量の物質が銀河を球状に包み込んでいない限り、渦状銀河は力学的不安定性のために、すべて棒渦状銀河に変形されてしまうというのである。楕円銀河の周辺部のミッシング・マスについては後述する。
[若松謙一]
渦状銀河が微分回転していることは、渦巻構造の本質を理解するうえで深刻な問題となった。もし、円盤上の星やガスが渦状構造をもちながら運動しているとすれば、中心部が速く回転し周辺部がゆっくり回転する、いわゆる微分回転であるために、この渦巻構造はたちまち、その中心部に強く巻き込んでしまい、その結果として、ぐるぐると強く巻き込んだ渦巻銀河となっているはずである。銀河が誕生して以来、中心部はすでに数百回も回転しているのであるから、宇宙には強く巻き込んだ渦巻をもつ銀河が数多く発見されても不思議ではない。ところが、多くの銀河は強く巻き込んでいるどころか、むしろほんのわずかしか巻き込んでいない銀河のほうが多い。渦状構造は、絶えずできては消え、消えてはできる一時的な現象である、ともかつては考えられていた。
1964年、中国系アメリカ人の天文学者リンChia-Chiao Lin(1916―2013)とシューFrank Shu(1943―2023)とは、リンドブラッドの理論を発展させ、渦状構造の密度波理論を提唱した。それによると、円盤上では星の密度の渦状の濃淡パターンができ、それが波となって伝わっている、というのである。この波は、星の密度の濃淡によって生じた引力と、銀河の微分回転とが互いにうまく調節しあって自分自身で円盤上を伝搬しうるもので、現在も広く受け入れられている理論である。
渦状銀河の写真をよく見ると、渦状構造に沿ってその内側には暗黒星雲が、外側には青い若い星やガス星雲が明るく輝いて並んでいるのに気づく。現在でも渦状部ではガスから多量の星が生まれており、このことが渦状構造をよりいっそう際だたせている。1966年、日本の天文学者藤本光昭(みつあき)(1932―2013)は、渦状銀河内の星の形成について、銀河衝撃波理論を提案した。円盤上を回転しているガスが星の密度の高い渦状腕部に近づくと、その強い重力場によってガスが加速され、超音速で渦状腕部へ突入し、衝撃波が発生する。このときガスは強く圧縮され、ガス内に含まれていた暗黒物質の濃度が増して暗黒星雲の列となり、またこのガスの圧縮によって原始星が収縮して星となって輝くというのである。
この理論は、渦状銀河内の中性水素ガス雲の運動や非熱的電波の強度分布などの観測によって検証されている。しかし、最近、超新星の爆発によって生じた衝撃波が星間ガスを強く圧縮し、そこで星が形成され、それが銀河の微分回転によって渦巻状に伝搬していく、との説も提案されている。
[若松謙一]
楕円銀河の形状は、球を押しつぶした形をしているのが普通であり、その原因として、銀河回転による遠心力が考えられていた。しかし1977年、銀河周辺部の回転スピードを観測した結果、その速さはせいぜい秒速100キロメートルと小さいことがわかった。楕円銀河の形状は、個々の星の乱雑運動の非等方性に支配されて決まっていることになる。球を押しつぶしたような楕円銀河の真の形状は、回転軸方向に伸びている、いわゆるプロレート型回転楕円体(フットボール型)であるのか、縮んでいるオブレート型回転楕円体(円盤型)であるのか、もしくは三軸不等の楕円体であるのかは、銀河の形成プロセスと関係して興味深い問題であるが、まだ解決をみていない。
楕円銀河にもミッシング・マスが存在していることが、X線の観測からわかってきた。1980年、「アインシュタイン」と名づけられた人工衛星が、おとめ座の巨大楕円銀河M87の周辺から強いX線が放出されていることを発見。そのスペクトルから、このX線は数億Kにも達する超高温の希薄なガスから発しているものであることがわかった。この高温ガスを銀河の周囲に強く結び付けておくためには、光で見えている物質だけでは不十分で、その10倍ものミッシング・マスが存在していなければならない。その正体が何であるのかは、これからの研究にまたなければならない。
[若松謙一]
広大な宇宙空間を漂っている銀河も、ときには互いに衝突しあっていることがはっきりしてきた。パロマ山天文台のシュミット・カメラで撮られた天体写真を詳しく調べていたソ連の天文学者ボロンツォフ・ベリヤミノフは、1959年、互いに非常に接近している二つの銀河間に淡くかすかな「橋」が架かっている例を多くみいだした。その後、トゥームレAlar Toomre(1937― )は、コンピュータでのシミュレーションで、このような「橋」が銀河どうしの衝突で形成されうることを示した。銀河どうしが非常に接近すると、銀河周辺部にある星やガスは互いに相手の銀河の引力(いわゆる潮汐(ちょうせき)力)によって引きずり出され、二つの銀河を結ぶ細い「橋」が形成されるというのである。
指輪(リング)の形をした銀河も最近多く発見されている。初め、銀河中心の爆発説も考えられたが、渦状銀河の円盤部に対し、もう一つの銀河が垂直に横切って衝突するときに形成されることが、1976年トゥームレらによって示され、多くの観測事実とよく一致することが確認されている。
銀河どうしの衝突によって生じた奇妙な形をした銀河(特異銀河とよばれている)の例としては、鋭い球殻(シェル)がいくつも重なり合っているように見えるシェル状楕円銀河、銀河円盤に対して直交するもう一つの円盤が回転しているポーラー・リング銀河などがある。
[若松謙一]
1954年バーデとミンコフスキーRudolph Leo Minkowski(1895―1976)は、正確な位置がつきとめられた電波源おとめ座Aやペルセウス座Aの方向に、パロマ山天文台の5メートル望遠鏡を向けて観測したところ、そこに奇妙な形をした銀河を発見した。
おとめ座Aは、M87とよばれる巨大楕円銀河で、その明るい中心核から直線状のジェットが噴出しているのをみいだした。このジェットは色がきわめて青くかつ強く偏光していることから、シンクロトロン放射によるものと考えられた。シンクロトロン放射光とは超高エネルギーの電子が磁場中を運動するときに発する光であり、このことは、銀河の中心核で高エネルギー粒子をつくりだす激しい現象がおこっていることを物語っている。
一方、ペルセウス座Aは、ペルセウス座銀河団の楕円銀河であって、そのスペクトル観測から、中心核ではいろいろな電離段階にあるガスが、秒速1万5000キロメートルにも達する速さで激しく動いていることがわかった。中心核は数日ないし数か月の単位で明るさが大きく変光している。これらの激しい活動は、太陽系よりわずかに大きい数光日の大きさの領域でおこっていると推測されている。その原因として、銀河中心には太陽の質量の108倍にも達する巨大なブラック・ホールがあって、その周りにガスが激しく落下しているとの説が有力である。
銀河中心の核活動は、光だけでなく、電波、赤外線、紫外線、X線の各波長域でも検出されており、その活動の規模や形態によって、セイファート銀河、電波銀河、とかげ座BL天体、クエーサーなどとよばれている。
[若松謙一]
1950年以降、星の構造や進化についての観測や理論が著しく進歩し、現在、銀河の進化に関する理解がかなり進んでいる。太陽より小さな質量で生まれた星は、その寿命が150億年以上と非常に長いため、銀河の誕生以来これまで輝き続けている。それに対して、太陽質量の10倍以上もある重い星は、その寿命が数百万年から数千万年と短く、現在、観測されているこれらの星は、「最近」誕生したばかりであるということになる。このように、銀河はいろいろな質量をもったいろいろの年齢の星の集合体なのである。
生まれたばかりの青白色巨星は、おもにガスを多量に含む渦状銀河の渦状腕部に多いことなどから、星は星間ガスから生まれてくると考えられている。一方、重い質量の星は、星の中心部で核融合反応をおこし、次々と元素合成を行って進化し、最後に超新星となって大爆発をおこし、ふたたび星間ガスへ戻ってゆく。このとき、星のなかでつくられたヘリウム(He)や窒素(N)などの元素が星間空間へとまき散らされる。このようにガスから星へ、星からガスへのサイクルを繰り返しながら、銀河はしだいに進化していくことが、1970年代に銀河内のHe、N、O、Sなどの元素分布を調べることによって解明されてきた。すなわち銀河内の星やガス星雲のこれらの元素は時間の経過(宇宙の進化)とともに増加していくのである。
このような観点にたつと、楕円銀河は、ガスがすっかり星に変わってしまって、もはや新しい星を生み出すガスが残存していない銀河で、したがって年齢の古い種族Ⅱの星だけから構成されているといえる。一方、渦状銀河や不規則型銀河には、まだ多量のガスが残存しており、いまでも活発に星の生成が行われている。したがって種族Ⅰの星やHⅡ領域などのガス星雲が多数存在している。
ハッブルの形態分類は銀河の進化系列を表すと、かつては考えられていたが、以上みてきたように、
①楕円銀河は渦状銀河に比べて、はるかに質量の大きなものも小さなものも存在している、
②銀河を構成している個々の星の運動状態が乱雑運動と回転運動とで大きく異なっており、したがって銀河の全角運動量が互いに大きく違っている、
などの理由から、この考え方はとられなくなっている。ハッブルの系列は、時間的進化系列と考えるよりは、むしろ銀河が生まれたときの原始銀河雲の物理的状態、たとえば原始雲の角運動量、質量、密度、乱流速度などの違いによるものとする考えが有力である。
[若松謙一]
銀河は、宇宙空間の中で単独で存在しているよりは、むしろ集団をつくっているのが普通である。数十個の集団を銀河群group of galaxies、数百から数千個の集団を銀河団cluster of galaxiesとよんでいる。銀河団内での銀河分布に明確な中心があって、個数密度の高い、いわゆる規則型銀河団(例、かみのけ座銀河団、平均後退速度は秒速6900キロメートル)では、楕円やS0型銀河が多いのに対し、銀河が散漫に散らばって分布している不規則型銀河団(例、ヘラクレス座銀河団、平均後退速度は秒速1万1000キロメートル)では、渦状銀河や不規則型銀河が多い。規則型銀河団の中心部には、ひときわ巨大な楕円銀河が1~2個存在していることが多く、cD型銀河とよばれている。この銀河はときには強い電波源となっている。銀河団のタイプとその構成銀河の種類との間に相関関係がみられるが、その理由はまだ解明されていない。
1970年代後半になると、銀河団から強いX線が出ていることがわかってきた。X線が銀河団の広い部分から発していることやX線スペクトルの解析から、このX線は温度が数億Kにも達する高温ガスからの熱放出であることがわかった。最近、6.7キロ電子ボルトのエネルギーのところに鉄の輝線スペクトルが検出されている。その強度から、このガスに含まれる鉄の元素量比は太陽に含まれる比の数分の1程度と推定された。宇宙では、鉄は星の内部でしかつくられないことから、これらのガスは、銀河の内部にたまっていたガスが、なにかのメカニズムで銀河から吹き飛ばされてしまい、銀河団中にたまったものと考えられている。
[若松謙一]
ハッブルの宇宙膨張の発見以来、銀河は宇宙の構造を調べるための灯台の役割を果たしている。銀河系をすこし遠く離れてしまうと、もはや個々の星は大望遠鏡を用いても観測できなくなり、星の大集団である銀河だけが検出できる天体となる。遠方の銀河を観測すると、それだけ過去の銀河の様態、宇宙の様態が見えてくる。遠方の銀河の構造や色を観測して、近くの銀河と比べてみる試みが近年始められている。詳しい観測はこれからの研究にまたなければならないが、最近の観測によると、楕円銀河では過去数十億年間ほとんど際だった色の変化(したがって銀河を構成している星の種類の変化)はなかったことがわかっている。遠方の銀河の後退速度を測定して、宇宙膨張のスピードが過去100億年の間にどのように減少してきたかを調べ、宇宙全体の構造や進化を研究する分野も盛んになってきている。
[若松謙一]
ある一定以上の明るさをもつすべての銀河の赤方偏移を測定して、銀河の宇宙空間における分布を調べる研究が、1990年代に入ると急速に進展した。その研究の結果、銀河は集団をつくって単に銀河団を形成しているだけでなく、その銀河団がまた数個集まって超銀河団(スーパー・クラスター)を形づくっていることがわかってきた。代表例は、かみのけ座超銀河団や、強いX線源でもある、へびつかい座超銀河団などである。
これらの超銀河団は、長さ数億光年にも及ぶ銀河の「ついたて状の連なり」で結ばれていることがハーバード大学の研究チームにより発見され、その連なりはウォールとよばれている。ウォールの手前や後ろは銀河がほとんどない空間となっており、ボイド(空隙)と名づけられている。どのようなメカニズムで数億光年規模の巨大構造が形成されたのかは今後の銀河研究の大きな課題である。
[若松謙一]
1990年に打ち上げられたハッブル宇宙望遠鏡(以下HSTと略す)は、上空500キロメートルの軌道上を回るスペース望遠鏡で、口径2.4メートルの光学望遠鏡を搭載している。地球大気外にあるため、解像度が0.1秒と地上望遠鏡に比べ10倍も優れており、これまで見えなかった天体の微細構造や、検出できなかった暗い天体を観測できるようになった。以下に、これまで得られた代表的な成果を要約する。
①240万光年離れたアンドロメダ銀河は、これまではきわめて明るい超巨星しか見えていなかった。HSTでは29等星という、きわめて暗い星までも一つ一つに分解されて検出できるようになった。また散開星団のHR図(色-等級図)を調べることにより、恒星進化の詳細が研究されている。
②ケフェウス型変光星の周期-光度関係を用いて直接測れる銀河の距離は、従来はせいぜいM81銀河までの約1000万光年であった。HSTでは、おとめ座銀河団のM100銀河についてもケフェウス型変光星の検出に成功し、この銀河団が5600万光年であることをつきとめ、宇宙膨張の速度(69±10km/秒/Mpc)や宇宙年齢(135±15億年)について、いっそう精度の高い値が得られている。
③多くの楕円銀河周辺で、これまで検出できなかった球状星団が発見されている。これら球状星団の空間分布や元素量の分析により、楕円銀河の形成機構や進化過程の解明がいっそう進展している。また、球状星団は楕円銀河の距離指標としても役だつことがわかり、数千万光年の空間でのハッブル定数の決定に重要な役割を果たしている。
④銀河中心核の微細構造がしだいに解明されている。たとえば、おとめ座銀河団の一員である楕円銀河M87では、長さ5000光年にも及ぶ長大なジェットが中心核から飛び出している。その根元に直径500光年の回転円盤が発見され、秒速550キロメートルの速度で回転していることが観測された。その結果、太陽質量の30億個分に相当する巨大ブラック・ホールの存在が力学的に明らかになった。
⑤周りに十字架型に並んだ四つの点状構造のある暗い点状の天体がHSTで多く発見されている。これは点状に見えるきわめて遠方の銀河に、その背後のクエーサーが偶然一直線状に重なってしまった天体で、アインシュタイン・クロスとよばれている。ときにはリング状に見えるので、アインシュタイン・リングともよばれる。クエーサーの光が銀河の近くを通過するとき、銀河の重力場であたかも凸レンズのように光の進路が曲げられ、四つの点像が結ばれたものであり、「重力レンズ天体」ともよばれている。その像の解析により、手前の銀河の重力場を調べることができ、銀河のダークマターの分布構造を調べるには格好の天体である。
⑥HSTはCCDとよばれる検出器で撮像している。このため、同一天域の多数の映像をコンピュータ上で重ね合わせて1枚とし、100時間にも及ぶ長時間露出の画像を作り出すことができる。この手法で北斗七星の一角を撮影した画像はハッブル・ディープ・フィールドとよばれ、地上望遠鏡では写らなかった、きわめて多数の銀河が映し出されている。これにより、渦状銀河が楕円銀河に比べ多く存在することがわかり、また銀河間衝突のため変形した特異銀河なども多数発見されている。これらの銀河の赤方偏移は測定中であるが、現在のところ、一番遠方のものは赤方偏移が5.2の銀河である。今後、いっそう遠方の銀河が検出されてくるものと期待されている。
[若松謙一]
口径8~10メートルクラスの巨大地上望遠鏡は能動光学という手法により、HSTに匹敵する鮮明な解像力をもっているうえ、集光力はHSTより20倍も大きく、観測の成果に大きな期待が寄せられている。日本の「すばる望遠鏡」を始め、これらの望遠鏡が一斉に本格的に稼働し始める21世紀初頭において、期待される「銀河」関連の研究テーマを以下に概観する。
①銀河の進化 銀河における星形成や元素組成が、宇宙の年齢とともにどのように変化してきたかは、近距離の銀河から、きわめて遠方の銀河へとさかのぼって観測することにより調べることができる。しかし、遠方の銀河は赤方偏移のため、可視光域が近赤外線域へと大きくシフトしてしまうため、赤外域での観測が必要となる。「すばる望遠鏡」は近赤外線域での観測に優れた性能をもっており、また広い写野をもつので、この種の研究には一番適した望遠鏡である。
数十万個にも及ぶ銀河を一つ一つ観測することで、楕円銀河や渦状銀河内での星の生成率がどのように変化してきたのかが、いっそう明確になる。銀河が宇宙を構成している最小単位であることに思いいたすと、この研究が宇宙論研究の出発点であることが理解できよう。
②銀河の形態の起源 銀河の個数密度や、楕円銀河、渦状銀河、棒渦状銀河などの頻度分布が宇宙膨張とともにどのように変化してきたのか、また銀河団の中心部と周辺部とでの違い、超銀河団内とウォールでの違いなどを「すばる望遠鏡」の広い視野を利用して観測できる。銀河がどのようなメカニズムで多様な形態に分岐したのか、なぜ巨大銀河と矮小(わいしょう)銀河とに分離したのか、ハッブルの研究以来のこれらの基本問題について重要な鍵(かぎ)がみつかるであろう。
③宇宙の膨張速度の時間変化 近年、光ファイバーを用いたいわゆる多天体分光器の開発が進み、600個もの天体のスペクトルを同時に観測できるようになってきた。この装置を大型望遠鏡に装着すると、きわめて暗い多数の銀河の赤方偏移を効率よく測定できる。一方、近年著しく進歩した超新星による銀河の距離測定法を利用すると、宇宙膨張の速度が銀河形成期の赤方偏移6の時代から現在に至るまでどのように変化してきたか、いわゆる宇宙膨張の減速パラメータの値を精密に測定できる。インフレーション宇宙の検証のためにも重要なテーマである。
④宇宙における構造形成 前述のように、銀河は単独に存在しているのではなく、銀河団、超銀河団、ウォール、ボイドなどの数億光年にも達する巨大な構造(天体)の一員として、ビルディングのブロックのような役目を果たしている。赤方偏移5を超える遠方の空間から、銀河系のすぐ近くの空間まで調べれば、これらの巨大構造の時間的な進化を追いかけていくことが可能になる。このような研究は、一度に広い視野の観測ができる「すばる望遠鏡」のもっとも得意とする分野である。また巨大構造の研究は、多数の銀河のスペクトルを赤外域で一度に観測できる多天体分光器が開発されたことによって、いっそうの進展が期待できる。やがて、これら巨大構造の形成過程、進化過程が明らかになるであろう。
⑤クエーサーの進化とブラック・ホール形成 クエーサーとは、きわめて遠方にある激しく活動する銀河中心核であり、周辺部からブラック・ホールへガスが落ち込んでいる現象と解釈されている。クエーサーは見かけ上は星と区別できないものの、特異な色をしているため、その色を測って候補天体を絞り込めば比較的容易に探し出せる天体である。きわめて暗い候補天体のスペクトルを「すばる望遠鏡」などで観測すれば、赤方偏移5以上のクエーサーが多数発見できると期待されている。
また、クエーサーの個数密度や物理状態が赤方偏移とともにどのように変化するか調べることにより、クエーサーの進化過程、とりわけブラック・ホールの形成メカニズムについて、新しい知見が得られるであろう。
[若松謙一]
最近の研究によると、銀河は誕生直後から巨大な星の形成がきわめて盛んで、そのために生まれたての銀河(原始銀河)は宇宙塵にすっぽりと覆われて遠赤外線でしか検出できないだろうと予測されている。1999年、赤外線人工衛星ISOでの日本のグループによる観測では、多くの赤外線天体が200ミクロン帯で検出されている。しかし、望遠鏡が小さく映像の解像力が不足しているため、手前の星なのか広がった天体として写る遠方の原始銀河なのか、はたまた「シラス」とよばれる銀河系内の塵の雲なのか最終結論が得にくい段階である。
2010年までに、日本をはじめ各国がきそって大型の赤外線望遠鏡を人工衛星として打ち上げる予定である。これらの望遠鏡での観測が進めば赤外線源の形状もわかり、また連続光スペクトルや輝線スペクトルも得られ、原始銀河の検出に成功し、銀河形成史や宇宙論に大きな展開が期待されている。
[若松謙一]
銀河は、星と異なって像が広がっているうえ、非常に暗い天体なので、空の澄み渡った季節に都会からすこし離れた観測条件のよい場所で観測するのが望ましい。観察には注意力と忍耐力を必要とする。
肉眼で見える銀河は、北半球ではアンドロメダ銀河、南半球では大・小マゼラン星雲だけである。『メシエ・カタログ』にある銀河は、口径10~15センチメートル以上の小型望遠鏡で見えるので、明るく見えやすい銀河M104(おとめ座)、M51(りょうけん座)、M81(おおぐま座)などから始めて、しだいに暗い銀河に進むのがよい。
渦状構造や暗黒星雲などの観測には写真撮影が必要である。近くの明るい銀河でさえ視直径が10分角(満月の約3分の1の大きさ)程度しかないため、500ミリメートル以上の焦点距離のレンズが必要である。暗い天体であるので、F5~7の大口径の明るいレンズが望ましく、露出時間も10分以上かかるため、赤道儀で追尾する必要がある。
[若松謙一]
『T・フェリス著、堀源一郎監修『銀河宇宙の神秘』(1981・旺文社)』▽『若松謙一・渡部潤一著『みんなで見ようガリレオの宇宙』(1996・岩波ジュニア新書)』▽『野本陽代、R・ウィリアムズ著『ハッブル望遠鏡が見た宇宙』(1997・岩波新書)』

ハッブルの銀河の分類
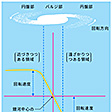
渦状銀河の回転
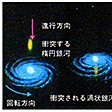
銀河の衝突(リング銀河の形成)

アンドロメダ銀河

おとめ座A

かみのけ座銀河団

黒眼銀河

子持ち銀河

マゼラン星雲

しし座A

葉巻銀河

M63銀河

M81銀河

M100銀河

M101銀河

NGC1300銀河

レンズ状銀河

シェル状銀河

ポーラー・リング銀河

アンテナ銀河
少年少女雑誌。1946年(昭和21)10月創刊、49年8月終刊。新潮社発行。編集には、滑川(なめかわ)道夫、石川光男、高橋健二、吉田甲子太郎(きねたろう)らがかかわった。石川によれば、「正しい世界観をやしない、つよく美しい人間性の確立を目ざした高学年児童のための総合雑誌」を編集方針とした。当初、誌面は横組みで片仮名表記を多く用いたが、のちに縦組みに変更した。読者に作品批評を求めるなどユニークな試みもなされた。おもな寄稿作家に平塚武二(たけじ)、岡本良雄、壺井(つぼい)栄、椋鳩十(むくはとじゅう)らがいる。ほかに吉野源三郎、中野好夫らの名もみえる。
[大藤幹夫]
天の川の意味にも使われるが,天文学の分野においては天の川に象徴されるわれわれの銀河系と同じ形態の恒星の大集団をいう。一般に直径数千光年から数十万光年の大きさの空間内に,100万個から1兆個にも及ぶ恒星と星間物質が密集しているものを指す。その多くは我々の銀河系の外側,はるか遠方にあるために,比較的近距離のマゼラン銀河やアンドロメダ銀河でも,肉眼や小望遠鏡に淡い雲のようにしか映らない。かつてはその見かけによって〈星雲nebula〉として一括されていたが,1925年にE.ハッブルによって〈アンドロメダ星雲〉を含む3個の〈星雲〉にセファイド型変光星が同定され,その距離が推算されるに及んで,星雲の一部がわれわれの太陽系を包む巨大な恒星の集りである銀河系の外にあって,銀河系と同等の規模をもつことが明らかになった。このため,銀河系外星雲extragalactic nebulaと呼んで輝線星雲,散光星雲,惑星状星雲などの銀河系内星雲と区別される。また,その大規模に密集した恒星系のようすを表して,島宇宙とか小宇宙と呼んだこともある。天の川,つまり銀河がわれわれの銀河系の全体構造を反映していることと,夜空での見かけが淡い乳色状の塊であることから,銀河またはギャラクシーgalaxyの名が与えられるようになった。したがって,20世紀初頭における銀河の発見は,人類を宿した太陽系を包む巨大な恒星系が,宇宙に無数に存在する銀河のうちの平凡な1個に過ぎないことを教えた。
1771年にC.メシエがまとめたメシエ星表(M番号)に38個が登録されたのをはじめとして,1888年のNGC星表や1895-1908年のIC星表などの恒星でない天体,すなわち星雲や星団をいっしょに記載した天体表に収録されてきたが,32年にはH.シャプリーと,エームズA.Amesによって,約13等より明るい1249個の銀河だけを選んでその特性を記した銀河カタログ《Shapley-Ames Catalogue》が出版された。現在ではド・ボークルールde Vaucouleurs夫妻らによってまとめられた《Third Reference Catalogue of Bright Galaxies》(1991)がもっとも広く用いられ,2万3024個の銀河を収録している。収録数の多いものとしては,ツビッキーF.Zwickyらによる銀河と銀河団のカタログ(1961-68)があり,3万1350個の銀河と9700の銀河団を収めている。アンドロメダ銀河はM31またはNGC224のカタログ番号で表記されるが,このようなカタログ番号の与えられていない暗い銀河は,無名銀河anonymous galaxyとして文字AまたはAnを冠し,その赤経,赤緯座標を付記してA16 38-30 58のように表記されることが多い。
銀河の分類は,1926年にハッブルによって提唱された形態分類が基本となっているが,銀河の明るさの中央集中度に基づいたヤーキス分類などもある。ハッブルの分類ではその見かけの形によって,楕円銀河(E),渦巻銀河(S),棒渦巻銀河(SB),不規則銀河(Ir)に大別される。楕円銀河は滑らかな輝度分布をもち,際だった内部構造を示さない。その見かけの扁平率は円形に近いものから,軸比が10:4程度に平らなものまであるが,それよりも扁平なものは知られていない。渦巻銀河は,若い青い星々の集積や星間塵による暗条によって形どられる渦巻状の腕(渦状腕)の存在によって特徴づけられる。一般に,中央にある楕円体状のバルジbulgeと呼ばれる部分と,それに重なる円盤状の部分からなり,渦巻構造はこの円盤内の副構造である。棒渦巻銀河では,中央の楕円体部分が細長く棒状に近い構造を示し,その両端から渦巻状の腕が伸びている。棒状に細長くなっている度合にはさまざまなものがあり,S型とSB型は連続的につながっている。大ざっぱに分類すると,両者はほぼ同数となる。S型とSB型をまとめて円盤銀河(D),あるいは渦巻銀河(S)と総称することもある。中央の楕円体部分と円盤部分の勢力比は,円盤部分のかろうじて認められるもの(S0/a)から,ほとんど円盤部分だけのもの(Sm)まであり,渦巻の巻込みの度合も,S0/a型からSm型にかけて緩くなっていく。S0/a型に近いものを早期型渦巻銀河,Sm型に近いものを晩期型渦巻銀河と呼び習わしているが,進化の系列とはまったく関係がない。早期型から晩期型になるに従い,渦状腕は滑らかなものから,多くの塊を含む副構造に富んだものへと移り変わる。その極限として,円盤全体にそのような副構造が卓越し,不規則な見かけを与えるようなものが,不規則銀河(I。ハッブル分類のIrにあたる)である。楕円銀河と渦巻銀河の中間の型としてハッブルはS0型を導入した。これは円盤部分を備えてはいるが,渦巻構造の見えない銀河で,大部分は構造的にE型とS型の中間に当たると思われるが,なかにはS型の構造をもちながら,その円盤部分に渦巻状の副構造の発生しないものもあると思われている。その原因としては,若い星を生む原材料となる星間物質の欠如があげられている。最近では形態分類がさらに細分化され,円盤部のリング状の副構造の顕著さやその位置,または中央部のレンズ状副構造の有無などが分類基準に加えられている。
見かけ上もっとも明るい銀河は,積算実視等級が0等の大マゼラン銀河(I)で,次いで2等級の小マゼラン銀河(SBm),4等級のアンドロメダ銀河(Sb)であるが,両マゼラン雲が約16万光年のところにあるのに対して,アンドロメダ銀河は,210万光年の遠方にあり,後者は前2者に比べて桁違いに勢力の大きな銀河であることがわかる。このように比較的近い銀河では,個々の恒星に分解して観測できるので,よく調べられている恒星の特性を利用して,その絶対光度と見かけの明るさの比較から距離を決定する。とくに脈動型変光星の変光周期と絶対光度の関係が適用されるが,変光星の理論に改訂があると,宇宙の距離尺度も改訂される。20世紀中ごろには,このような理由から宇宙の尺度が約2倍にも伸びた。もはや個々の星が観測できないほど遠方にある銀河については,星団や巨大な電離水素領域の見かけの大きさや明るさ,その中に出現した超新星の最大光度などを利用して距離を決定する。また内部の速度場を反映するスペクトル線の広がりと絶対等級との間の経験的な相関法則も用いられている。ハッブルは,1929年に,このようにして決めた距離と,その銀河のスペクトル線の赤方偏移が示す後退速度との間に,よい比例関係の成り立つことを発見した。このハッブルの法則を逆用して,スペクトルを撮ることによって,さらに遠方の銀河の距離を決定している。距離が知れると,各銀河の絶対的な勢力,すなわち幾何学的な大きさや絶対光度を知ることができる。楕円銀河や早期型の渦巻銀河は一般的に大きく,その直径は数十万光年,絶対等級は-22等にも及ぶ。一方,不規則銀河や,矮小楕円銀河と呼ばれる銀河では,直径が数千光年,絶対等級が-16等程度の勢力かそれ以下のものも多い。これらは伴銀河として大型銀河に付随するものも多く,小規模なものでは,孤立した巨大な電離水素領域や広がった球状星団といってもよさそうなものまでがある。直接写真に比べて,スペクトルを撮るのが困難なために,見かけの形態だけから絶対光度を推定するくふうもされている。渦巻銀河については,渦状腕の発達度や円盤部分の表面輝度を判定基準として,ⅠからⅤの5段階にわたる〈光度階級〉が導入され,Sa-Smの各分類型ごとに,絶対等級と対応づけられている。最近の統計的研究によれば,この対応づけは,各光度階級の明るい部類の銀河についてはほぼ正しいが,暗いものまでを含めていくと必ずしも対応関係がよくないといわれている。楕円銀河のうちには,とりわけ明るいcD型と呼ばれるものがあって,その形状の周縁部分が異常に遠方まで裾を引いて広がっていることで見分けられる。この種の銀河は,銀河団の中心付近に多く,絶対等級が-23等ないし-24等にも達するので,遠い宇宙空間での基準灯台のような役割を果たすことができる。一方,暗い矮小楕円銀河は,表面輝度の低いものがほとんどで,近いものしか発見されていない。
近年の大型望遠鏡の発達や高性能検出器の開発,それに大型コンピューターと連動して用いられる高速測定器などに関する技術的発展によって,銀河についての複雑な情報を数量的に処理することも可能となってきた。その結果,従来の写真判定は,表面輝度分布の定量的な表現やそのパラメーター表示へと移行しつつある。楕円銀河の表面輝度分布は,見かけの中心からの距離をrとすると,exp{-αr1/4}に比例する関数によってよく近似できる。また早期型の渦巻銀河の円盤部の表面輝度分布は,exp{-βr}に比例する関数でよく近似される。ここでαとβは距離尺度を決めるパラメーターで,楕円銀河の場合には,αは比較的共通である。したがって標準的な楕円銀河では,その全光度を与えると,扁平率を除いた分布のようすは一意的に定まってしまう。それに対して渦巻銀河では,r1/4法則にほぼ従う中央の楕円体状部分と,単純な指数法則にほぼ従う円盤部分とがあるために,その両者の光度の比が形態を定量的に分類するためのよいパラメーターとなっている。しかし,渦巻銀河の場合には,このほかにも総光度を表すパラメーターが必要となるために,本質的に二次元的な分類が必要とされている。
天球上での銀河の見かけの分布は一様ではない。天の川を挟む約40度幅の帯の中では,その外側に比べて,見える銀河の数は格段に少ないが,これは,われわれの銀河系の天の川を含む面,つまり円盤部分の中心面付近に,多量の星間塵があって,外界からの光を吸収しているからである。吸収をあまり受けない赤外線を用いた探査から,天の川の中にも,マッフェイ1,マッフェイ2などの銀河が見つかっている。比較的明るい銀河に限ると,おとめ座からおおくま座に連なる帯状の領域に集中が見られ,さらにたどっていくと,この帯は全天を巡って環状に伸びている。これは,おとめ座銀河団を中心に,われわれの銀河系とアンドロメダ銀河を含む局部銀河群をもその一部とする,扁平な銀河の大集合を見ているのであって,超銀河系と呼ばれている。銀河は,明るいものが数個に暗いものがたくさん加わって,銀河群を形成したり,数百から数千の明るいものが集まって銀河団を形成している。さらに,複数の銀河団がその間に帯状に分布する銀河によってつながって,超銀河団を形成している場合もある。稠密(ちゆうみつ)な銀河団の構成銀河には,楕円型やSo型が多く,渦巻型は少ない。反対に,散在銀河には渦巻型が比較的多い。平均してみると,比較的見かけの明るい銀河にあっては,渦巻銀河が全体の約半数を占め,残りの半分のまた半分をSo型が,3割を楕円銀河が占めている。不規則銀河は全体の1割程度である。このような見かけの頻度比率を絶対数の比率に直すには,各種の銀河の絶対光度に関する分布を知らなくてはならない。その補正を行うと,不規則銀河が圧倒的に多くなるとされている。カタログに記載されている銀河のうち,絶対写真等級が-17.5等よりも明るいものを数えると,その平均空間密度は,1000万光年立方につき約1個ということになる。したがって,狭い空間領域に複数個の銀河がまったく偶然に存在する確率は極端に小さい。現実には,数個の銀河が隣接しているものも少なくない。銀河団の外部に見られる多重銀河は,その発生起源と関係があるのではないかとも考えられている。
渦巻銀河の構造は,われわれの銀河系を内から見たり,隣のアンドロメダ銀河を外から観察することで,詳しく調べられている。中央の楕円体状の部分と円盤部分は一体となって,いわゆるレンズ状の星系を構成している。太陽もこのレンズ状星系の一員であって,その銀河系内の空間運動特性や化学組成,年齢は,円盤種族と呼ばれるこの星系の代表的なものである。すなわち,円盤種族は100億年近い年齢と重元素に富んだ組成をもち,銀河中心を巡ってほぼ回転運動をしている。この回転運動の角速度は外縁部ではほぼ一定値にとどまり,その結果隣接する円環領域はお互いにずれていく。中央の膨らんだ部分では円盤面に直交する方向の運動成分も顕著で,重元素の量比は,中央に近づくにつれて円盤周縁部の数倍に増大する。円盤部分の中心面近くにはガスやちりなどの星間物質が数百光年の厚さの薄い層をなして分布し,その中の濃密領域で恒星が誕生しつつある。これらの若い星々は種族Ⅰの星系と呼ばれ,ほとんどが円盤中心面内を運動し,円盤種族に近い化学組成をもっている。星間物質の濃密領域や若い星々の集団(散開星団や電離水素領域など)は連なって分布し,渦巻状の模様をなしている。銀河の恒星生成活動は,中央の楕円体状部分が円盤部分に移り変わるあたりでもっとも激しく,そこから外向きに渦状腕に沿って広がっているが,それより内側では星間物質はかえって少ない。はっきりと観測されるこのレンズ状星系を包んでハロー種族,または種族Ⅱと呼ばれる希薄な星系が広がっている。この星系は球に近い楕円体状に広がっていて重元素比は円盤種族のものの1/10~1/10000と低い。球状星団は代表的なハロー種族の構成員であり,年齢は100億年程度か,もしくはそれよりも古い。ほぼ等方的に分布し,銀河の中心を巡る軌道運動をしていて,なかには離心率の大きな運動を示すものもある。
渦巻銀河に見られる渦状構造は,銀河の発見以来多くの注目を集めてきた。円盤状の構造から回転していることは容易に推定できるが,かつて想像されたように,渦状腕がひとつながりの帯の回転によって生じたものだとすれば,時間がたつにつれてきつく巻き込んでしまうであろう。しかし,実際には一体の帯ではなく,青い若い星の集りが帯状に並んでいるのであって,これらの大質量星の寿命が数百万年の程度であることを考えれば,数億年で1回転する銀河円盤にあっては,時が移るにつれて異なる星を見ていることになる。大質量星が隣接する場所に次の大質量星の誕生を誘起するならば,回転との相乗効果で,渦巻模様が発生する。しかし,星間物質の高密度領域も渦状腕に沿っているので,現在では,渦状構造は銀河円盤部に生じた疎密波であるとする考え方が主流を占めている。密度の高い領域では星間物質が圧縮されて若い星が誕生し,渦状に際だって見えるとするもので,分類型によって違う渦巻模様の特徴も説明できそうである。この説では,物質は渦巻模様を巻き込む向きに追い越していくのが妥当とされているが,観測的には円盤部の回転の向きと渦の巻込みの向きの関係は確立されていない。というのも,見かけの模様のどちらが手前かという判定がつけがたい場合があるからである。しかし,星間物質による吸収のようすなどから判定してわかっているものについては,回転の向きは巻込みの向きと一致している。楕円銀河内の星の運動は,渦巻銀河のハロー種族のものに近く,扁平な楕円銀河の場合でも,その形状は回転運動よりも異等方無秩序運動によって規定されている。渦巻銀河に残存する星間物質の割合は,晩期型のものほど多いが,特殊なものを除くと不規則型でも総質量の20%を超えない。また,若い青い星の生成率が残存星間物質の量に依存するため,晩期型の銀河ほど青く見える。
渦巻銀河の円盤部の星の表面や星間物質の化学組成は,ほぼわれわれの太陽のものに近いが,中央部に向かうに従って鉄などの重元素の量比が数倍に増加するとともに,窒素,酸素などの特定の軽元素の量比が1桁近くも増える。楕円銀河の中心部では,さらにこの傾向が強いようである。逆にハロー部分では重元素は少ない。このような観測的状況証拠に基づいて,原初銀河が重元素を増しつつ収縮したとする銀河形成過程が推測されている。すなわち,ハロー種族の星が,核融合によって重元素を作っては超新星として爆発を繰り返すうちに星間物質の部分がしだいに自己重力によって収縮し,ある時点からは遠心力が効き始め,回転軸方向だけの収縮が進んで円盤種族が形成され,そのなごりの星間物質が現在種族Ⅰの星々を生みつつある。楕円銀河の場合には,初期収縮の段階で活発な恒星生成活動があり,回転運動の少ないことも手伝って円盤は形成されず,星間物質もほとんど残っていない。
銀河を構成する星やガスが,その運動と相互の万有引力とのつり合いによって,ほぼその形状を保っていると考えると銀河の総質量を求めることができる。とくに渦巻銀河の場合には,円盤部分の回転速度曲線が総質量を求めるためのよい手がかりとなる。このようにして求まる力学的な質量は,観測される星の明るさから推算される光学的質量よりも大きく,場合によっては1桁以上も大きい。円盤部分の回転速度は早期型ほど速くて,数百km/sにも達するが,観測できるかぎりの外縁部でも速度の下がらないものが多く,ハロー種族のように広がった領域に大量の見えない物質が存在するとする作業仮設も提唱されている。われわれの銀河系やアンドロメダ銀河は,大型の銀河に属し,その明るい部分の質量はほぼ太陽質量の1011~1012倍(約1045g)と見積もられている。
銀河の中には,強いX線,紫外線,赤外線,電波などの大量の高エネルギー粒子や,高温プラズマに起因すると思われる放射線を放っているものがある。電波銀河,セイファート銀河,マルカリアン銀河,クエーサー,BL Lac天体などと呼ばれるものがそれである。可視域では一般に青紫色光の過剰を示し,活動的な銀河中心核,あるいは活動的な中心部分をもっているものが多い。これらが銀河の進化の特殊な時代に見られるかなり普遍的な現象なのか,特殊な条件のもとに生まれた銀河だけに見られる不安定性に起因する現象なのか,まだ明らかではない。宇宙全体の膨張や収縮の影響を考えないならば,自己の重力だけでまとまって孤立している恒星系としての銀河は,しだいにエネルギーを失って中心部に密集していく星からなる核部分と,エネルギーを得て外縁部分に広がっていく星からなるハロー部分に分離発達していくものと推察される。このようにして生じる濃密な中央の核部分が,上記のような活動的現象を引き起こすものと思われる。見かけの大きさが小さいのに表面輝度が異常に高い,コンパクト銀河と呼ばれるものの一部は,まさにこのような構造をもっていると推定されている。クエーサーやBL Lac天体もコンパクト銀河の極端な例で,中心に巨大なブラックホールがあり,それにガスや星が引き込まれて重力エネルギーが解放されると考えられている。この種の特異銀河のうちには,中心核から〈ジェット〉と呼ばれる物質噴射を思わせる突起形状を示して高エネルギー放射を行っている。また活動性の影響が銀河全体に及んで,爆発を思わせる不規則な形状を示すものもある。これも不規則銀河の一種ではあるが,不規則型のⅡとして区別されている。多重銀河の多くは,お互いの重力作用によって,形状を乱されているが,これらのうち正確な分類が困難なものも,特異銀河の範疇(はんちゆう)に入れられる。
太陽のような恒星の平均密度が約1g/cm3なのに対して,われわれの銀河系のような銀河の明るい部分の平均密度は,実にその1/1025にすぎない。銀河の物質はそれほど緩やかにしか重力によって束縛されていないので,複数個の銀河が遭遇すると,その影響は非常に大きい。渦巻銀河の場合には太い渦状腕を発達させたり,恒星生成活動を活発化し,相互の間に橋状の連なりのできることもある。また特殊な条件を満たす遭遇では,2個の銀河が合体して,より大きな1個の銀河になってしまうことさえありうる。銀河団の中心付近に見られるcD銀河は,このような合体によって,次々に近づく銀河をのみ込んで巨大化したのではないかと思われている。このように,重力的束縛の緩やかな銀河は,一般に環境の影響を受けやすく,銀河の形成や構造進化を考えるうえで,環境効果も見逃してはならない。銀河の進化を実証的に明らかにするには,遠方の,したがって遠い昔の銀河の世界を観測するのがいちばん直接的である。異常を示さないふつうの銀河で観測にかかっているもっとも遠方のものは,約50億光年程度のかなたのものであるが,特異銀河の一種とみなされているクエーサーでは,z=3.53,つまり150億光年ほどもの遠方のものまでが観測されている。
銀河の観測には,口径の割合に焦点距離の短い,いわゆる口径比の小さい明るい望遠鏡を用い,低倍率で見るのが適している。したがって,双眼鏡はこの目的に向いている。これは銀河が遠方にあって,個々の星としてよりも,その集合として,淡く白っぽく光る広がった塊として目に映るからである。ふつうの銀河の表面輝度は,明るい部分でも1秒角四方の中に19等星とか18等星が1個あるのに匹敵する程度なので,夜空の暗いところで見ることが肝心である。専門的観測の場合には,遠方にある見かけの小さな銀河も対象とし,焦点面に置いた乾板や光電検出器により直接に撮像するので,焦点距離の長いことも望遠鏡の条件となる。地球大気の揺ぎのために生じる解像限界の0.5秒角までを分解するには,10mないし20mの焦点距離の望遠鏡が要る。しかも,なるたけ口径比を小さくしようとすれば,必然的に大型望遠鏡となってしまう。現在では,口径4mないし6mの大型望遠鏡が銀河観測に活躍していて,その多くは,f/2.7ないしf/3.5の直接焦点と,f/7.5ないしf/10程度のカセグレン焦点を備えている。赤方偏移や内部速度場,化学組成を決めるためのスペクトル観測にも,明るい分光器を必要とする。最近では光電効果を利用した電子的な検出器が活用され,それぞれの位置に到達する光子の数を積算する方式が広く用いられ始めている。しかしながら掃天探査を目的とするような場合には,広い天域を一度に撮影しなければならず,撮影面積も大きくなるために情報量は膨大なものとなる。探査目的には,明るくて写野の広いシュミットカメラが引き続き活躍している。20世紀後半に入ってからの銀河天文学の急速な発展を反映して,1970年代には,チリのアンデス山脈やハワイのマウナ・ケア山などの世界的な天文観測適地に,続々と大型光学・赤外望遠鏡が建造された。91年にスペースシャトルによって打ち上げられた口径2.4mのスペーステレスコープは,空気の揺ぎのないことを生かしてf/24という大口径比で,逆に銀河を個々の星に解像してしまうことをねらっている。
ふつうの銀河中の星間ガスや分子雲,また高エネルギー粒子からのシンクロトロン放射の観測には,電波望遠鏡が活躍するほか,特異銀河については,大気圏外からのX線,紫外線領域の望遠鏡,さらにはγ線望遠鏡も重要な情報を提供する。
銀河の理論的研究では,新しい手法として,コンピューターによるシミュレーションが大幅に取り入れられている。とくに銀河をたくさんの質点の集りとみなして,その万有引力による相互作用で,どのように構造が変わっていくかを追跡するのに利用され,質点の数は数千から数十万点に及ぶ。さらに,星間物質も加えて,星と星間物質の間のやりとりも組み込むことによって,銀河の形成や進化のシミュレーションも行われている。このような計算で,現在いちばん不確実な要素は,銀河の中での星の生成率である。
→銀河系
執筆者:小平 桂一
児童雑誌。1946年10月~49年8月,新潮社発行。第2次世界大戦後,山本有三を編集顧問に創刊。有三執筆の創刊のことば〈銀河のはじめに〉には,敗戦の中から立ちあがる新生日本の子どもたちに向けて,宇宙の悠久と,真理に生きることの尊さが熱意をこめて語られていた。滑川道夫,高橋健二,吉田甲子太郎らが編集長を務めた。国語国字問題に熱心な有三の主張から,初めは2段横組みを用いたが,読者の支持が得られず,後半は縦組みに改められた。北畠八穂《ジロー・ブーチン日記》,壺井栄《あばらやの星》,椋鳩十《動物スケッチ》,平塚武二《ウイザード博士》,坪田譲治《ゆめ》,岡本良雄《ラクダイ横丁》,国分一太郎《雨ごいの村》,塚原健二郎《犬のものがたり》など多くの作品を生んだ。同じ時期の《赤とんぼ》(1946年4月~48年10月),《子供の広場》(1946年4月~50年5月),《少国民世界》(1946年7月~48年10月?),《少年少女》(1948年2月~51年12月)などとともに戦後の良心的児童雑誌として評価されたが,これらの雑誌は1950年代初めまでにすべて廃刊となり,大衆的な娯楽誌に席を譲った。
執筆者:冨田 博之
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
字通「銀」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…雲のように見える天体ということで星雲と呼ばれたが,星雲の中には,われわれの銀河系内の星間物質が光り輝いているものと,銀河系のはるか外側にあって,数十億個から数兆個の恒星の大集団であるものとの二つがあり,前者を銀河系内星雲,後者を銀河系外星雲と呼んでいた。現在では,これを区別して,銀河系内星雲を単に星雲,銀河系外星雲を銀河galaxyと呼んでいる。…
… 昭和初期には,プロレタリア児童誌《少年戦旗》(1929)が生まれたが,すぐ廃刊になり,1937年の日中戦争を境にして児童雑誌も徐々に統制され,44年には《日本ノコドモ》《良い子の友》《少国民の友》《少年俱楽部》《少女俱楽部》の5誌だけになった。 第2次世界大戦後は,《赤とんぼ》《子どもの広場》《銀河》(1946),《少年少女》(1948)などの文芸的に質の高い良心的雑誌がせきを切ったように創刊されたが,50年までにはみな廃刊となり,かわって《おもしろブック》《少年》《少女》《漫画少年》など一連の新しい大衆娯楽雑誌がつぎつぎに登場した。そしてテレビの発達とともに,〈読む〉雑誌から〈見る〉雑誌へ,月刊から週刊へと移りかわり,現在では,児童雑誌といえば学年別月刊誌以外はほとんどが週刊劇画雑誌で,年齢を問わず,幅広く読まれている。…
※「銀河」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...