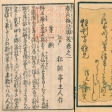精選版 日本国語大辞典 「人情本」の意味・読み・例文・類語
にんじょう‐ぼんニンジャウ‥【人情本】
改訂新版 世界大百科事典 「人情本」の意味・わかりやすい解説
人情本 (にんじょうぼん)
幕末から明治初年にかけて流行した近世小説の一ジャンル。人情本の源流の一つは,式亭三馬,梅暮里谷峨(うめぼりこくが)らが,寛政の改革以降に著した物語性に富む連作洒落本(しやれぼん)に求められるが,それとともに読本(よみほん)を通俗化し,講釈などの話芸をとりいれた中型読本と呼ばれる大衆読み物からの転化が考えられる。前者の系譜を引くのは《娼妓美談(けいせいびだん) 籬の花(まがきのはな)》(1817)など,末期洒落本作者として出発した鼻山人であり,後者の中型読本から市井の男女の情話を描く人情本様式への転回を告げたのは,新内の名作《明烏(あけがらす)》の後日談として書かれた,2世南仙笑楚満人(なんせんしようそまひと)(為永春水)・滝亭鯉丈(りゆうていりじよう)合作《明烏後正夢(のちのまさゆめ)》(1819-24)と素人作者の写本《江戸紫》を粉本とした十返舎一九の《清談峯初花(せいだんみねのはつはな)》(1819-21)であった。
《明烏後正夢》で戯作(げさく)文壇に登場した2世楚満人は,その後,狂言作者2世瀬川如皐(じよこう)や筆耕松亭金水(しようていきんすい)らの助力を得て,二十数部の人情本を出版するが,いずれも未熟な習作で世評もかんばしくなかった。しかし,2世楚満人の戯号を改めた為永春水が,1832年(天保3)《春色梅児誉美(しゆんしよくうめごよみ)》を発表するに及んで,その凄艶な恋愛描写と洗練された〈いき〉の美学が少なからぬ反響を呼び,風俗小説としての人情本のジャンルが確立することになった。みずから〈東都人情本の元祖〉と名のった春水は,《春色梅児誉美》にひきつづいて,深川芸者の意気地と張りを描いた《春色辰巳園(たつみのその)》(1833-35),富裕な商家の若旦那と小間使の恋をつづった《春告鳥(はるつげどり)》(1836)などの佳作を発表するが,殺到する注文に応ずるために門弟を動員した合作体制をとった37年以降の作品には見るべきものが乏しい。人情本作者としては春水のほかに,《閑情末摘花(かんじようすえつむはな)》(1839-41)の松亭金水,《仮名文章娘節用(かなまじりむすめせつよう)》(1831-34)の曲山人らがあげられるが,天保の改革の際に風俗を乱すものとして春水が処罰されてからは,ジャンルとしての生命を失っていく。なお,町人の日常生活を写実的に描いた人情本の作風と,会話と地の文とを分けて書く形式とは,明治の文学に少なからぬ影響を与えた。
執筆者:前田 愛
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「人情本」の意味・わかりやすい解説
人情本
にんじょうぼん
江戸後期の小説の一ジャンル。洒落本(しゃれぼん)の後を受け、洒落本と違っておもに婦女子を読者とし、文政(ぶんせい)初年(1818)から明治初年(1868)にかけて江戸で流行した、写実的な恋愛小説の名称である。市井の青年男女を主人公に、多くは1人の男性に配するに2人ないし3人の女性をもってし、三角関係、またそれ以上にわたる情痴的恋愛の種々相を描くものである。背景となる江戸市井の風俗の的確な描写に加えて、会話と地の文を対等に扱う近代的な表現様式も樹立し、明治の風俗小説、硯友(けんゆう)社の文学を生む役割をも果たしている。ただ、以上のように定義づけられるのは、天保(てんぽう)(1830~44)に入って為永春水(ためながしゅんすい)が人情本をリードするようになってからの作品で、それ以前の文政期の人情本は、音曲、演劇、講釈などに取材した未熟な伝奇小説であった。人情本の名称も、春水が『春色梅児誉美(しゅんしょくうめごよみ)』四編序で彼自身の作品を人情本(もの)と称してから一般化したもので、普通にはその書型から滑稽(こっけい)本とともに中本(ちゅうほん)とよばれ、本屋仲間の公的な称呼としては中型絵入読本(ちゅうがたえいりよみほん)、さらにその内容から初期においては泣本(なきほん)とも称されていた。
人情本は洒落本からテーマや表現技術を多く受け継ぎながら、なお書肆(しょし)の要求で婦女子を読者と予想することでそれにふさわしい題材や表現を加え、洒落本と違って遊里から離れ、中型絵入読本の名称が示すように、通俗的な世話読本として執筆されたところに成立する。一般にそれは、無名作者の草稿を十返舎一九(じっぺんしゃいっく)が校合して出版した『清談峯初花(せいだんみねのはつはな)』(1819)を最初とするが、2世南仙笑楚満人(なんせんしょうそまひと)(為永春水)や鼻山人(はなさんじん)らの作品によってしだいに現実主義的な傾向を強め、曲山人(きょくさんじん)の『仮名文章娘節用(かなまじりむすめせつよう)』(1831)を経て『春色梅児誉美』(1832~33)以下の春水の作品で、他の江戸小説に対して完全に独自性を主張する位置を確保した。鼻山人や松亭金水(しょうていきんすい)らも活躍するが、天保の改革の風俗取締りによって弾圧され、幕末になって復活するものの、そのまま維新開化の波にのみ込まれ、「続きもの」とよばれる明治の小新聞(こしんぶん)の風俗読み物へと解消していった。
[神保五彌]
『『人情本について』(『山口剛著作集4』所収・1972・中央公論社)』
百科事典マイペディア 「人情本」の意味・わかりやすい解説
人情本【にんじょうぼん】
→関連項目石橋思案|江戸文学|戯作|春色梅児誉美|条野採菊|田螺金魚|中本|帝国文庫|当世書生気質|文化文政時代
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「人情本」の意味・わかりやすい解説
人情本
にんじょうぼん
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「人情本」の解説
人情本
にんじょうぼん
近世小説の一様式。書型は中本。たんに中本・泣本(なきほん)などと称されていたが,この分野の代表的作者為永春水が自作に「人情本」の称を用いたところから,この名称が定着した。女性をおもな読者として想定し制作された恋愛小説であるところに,大きな特色がある。1819年(文政2)刊行の十返舎一九作「清談峰初花(みねのはつはな)」と滝亭鯉丈(りゅうていりじょう)作「明烏後正夢(あけがらすのちのまさゆめ)」の2作を嚆矢とする。32~33年(天保3~4)刊行の為永春水作「春色梅児誉美(うめごよみ)」の成功により完成したかたちをみるが,春水とその作品が天保の改革にともなう出版統制の処罰の対象となり,衰退していった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「人情本」の解説
人情本
にんじょうぼん
別名中本 (ちゆうほん) 。19世紀初期から明治初期まで続いた。風俗小説の洒落本から派生し,主として男女の情愛を写実的に描写した。代表作に為永春水の『春色梅児誉美 (しゆんしよくうめごよみ) 』など。天保の改革で風俗を乱すと処罰の対象とされた。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の人情本の言及
【仇∥婀娜】より
…江戸末期の美意識。浮気やいろっぽさを意味する〈仇〉に女性の姿態のしなやかさやたおやかさを表す漢語の〈婀娜〉を当てたのは,式亭三馬を嚆矢(こうし)とするが,この語はやがて為永春水の人情本で江戸下町の女性のやや頽(くず)れた官能美を表現する言葉として盛んに用いられる。〈いき〉の美学を支える〈意気地〉と〈張(はり)〉が弛緩しはじめたときに,〈あだ〉の美感があふれだすのである。…
【江戸文学】より
…中華趣味のまんえんによる中国俗語小説の日本化ともいうべきもので,上方では上田秋成などをその掉尾(とうび)とするが,その後これも江戸に移り,曲亭馬琴によって大成された。また読本の小説性と滑稽戯作の軽妙卑俗さとを兼ね合わせた試みが中本(ちゆうぼん)の世界で種々なされ,一つの型として定着したのが人情本であり,明治の写実小説へとつながる位置にある。以上はとくに俗文芸の立場での展望であるが,一方,江戸時代は漢詩文を中心とする伝統的雅文芸にリードされた時代でもある。…
【戯作】より
…江戸中期に知識人の余技として作られはじめた新しい俗文芸をいう。具体的には享保(1716‐36)以降に興った談義本,洒落本(しやれぼん)や読本,黄表紙,さらに寛政(1789‐1801)を過ぎて滑稽本(こつけいぼん),人情本,合巻(ごうかん)などを派生して盛行するそのすべてをいう。またその作者を戯作者と称する。…
※「人情本」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...