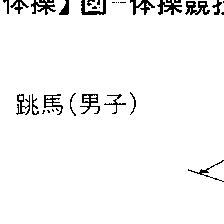翻訳|gymnastics
精選版 日本国語大辞典 「体操」の意味・読み・例文・類語
たい‐そう‥サウ【体操】
- 〘 名詞 〙
- ① 均整のとれた身体の発育、健康の増進、体力の鍛錬などを目的として行なう一定の規則正しい運動。徒手体操、器械体操などの別がある。
- [初出の実例]「必ずしも練兵体操を以て其主務と為すを要せず」(出典:明六雑誌‐一四号(1874)リボルチーノ説・続〈箕作麟祥〉)
- ② 学校の教科としての「体育」の旧称。
- [初出の実例]「理学本科第四級〈略〉月 自九時半至十時 体操」(出典:文部省雑誌‐明治六年(1873)七月二四日)
体操の語誌
明治初期に造られた訳語。原語は英語の Exercise または Gymnastics で、辞書では「英和双解字典」(一八八四)の Gymnasium の項に「体操所」、Gymnastics の項に「体操術ノ」とあるのが早い。→「たいいく(体育)」の語誌
改訂新版 世界大百科事典 「体操」の意味・わかりやすい解説
体操 (たいそう)
gymnastics
健康なからだの育成,むだのない経済的な動きの修得,スポーツや作業に適する基礎的な運動能力の養成を目的とする運動法。
沿革
英語のジムナスティックスgymnasticsの語源はギリシア語のギュムナスティケgymnastikēにさかのぼる。古代ギリシア人が裸体で競技をする習慣のあったところから,〈裸体の〉を意味するギュムノスgymnosから派生したことばで,前5世紀ころから使われている。したがって,古代ギリシア人にとって体操とは〈裸体で競技をすること〉を意味したのであるが,さらに積極的に〈睡眠,栄養,マッサージなどと関連して運動効果を科学的に検討し,運動を体系づける分野〉を意味するようになった。
近代に入って,ヨーロッパのヒューマニストたちも,体操ということばをほぼギリシアの用例に従って用いた。その代表的文献がグーツ・ムーツの《青年のための体操》(1793)である。ここで体操とは,健康で明るい市民生活を営む能力を身につけるために,いろいろな運動を体系づけ,方法化することであり,走・跳・投,レスリング,運搬,水浴など,あらゆる自然的な運動が体操の内容となった。この時点ではまだ徒手体操も器械体操も考えられておらず,視覚や聴覚などの感覚訓練をも含む広義の身体運動を体操と考えていた。今日の体操競技に発展した器械体操は,F.L.ヤーンによって考案されたものであるが,彼は体操ということばをギムナスティークGymnastikからトゥルネンTurnenに改め,統一ドイツ国家を建設するための青少年教育の意味で用いた。したがって,その内容には運動技術の習熟や意思の鍛錬を目的にした器械体操や行軍ばかりでなく,フォークダンスや政治討論集会なども含まれており,今日の体操の概念とはかなり異質なものを含んでいた。
近代の体操が,独自の運動形式のもとに理論的な体系を樹立したのはスウェーデン体操の父といわれるP.H.リング以後である。彼は健康を体操の直接目標として考え,身体的欠陥を除去し,健康の保持増進をはかる人為的運動法を考案した。そのための理論的根拠を医学に求め,生理学と解剖学を基礎とする合理的運動法の確立をめざした。彼はこの精神から,目的に従って体操を4部門に分けた。すなわち,教育体操,兵式体操,医療体操,美容体操である。彼が熱心に研究したのは教育体操と医療体操であり,兵式体操や美容体操は,それぞれの目的に応じて医学的原理と方法を応用する部門にすぎなかった。このように,体操を近代科学(生理学,解剖学など)に基づいて理論化し,方法化しようという傾向はデンマーク体操にも受け継がれ,その後の北欧体操の発展の方向を決定づけることになった。一方,ヤーンのトゥルネンは政治的な非合法活動であるとして,ときのプロイセン政府から弾圧(1820年,トゥルネン禁止令)され,政治色を抜きにした純粋な運動技術の習熟をめざすことになり,水平木棒(今日の鉄棒),平行棒,あん馬をはじめとする器械運動に活路を求めた。また,学校教育のなかに体操を導入しようとしたシュピースA.Spiess(1810-58)は身体運動を〈関節の可動性の原理〉に従って部分運動に分類し,やさしい運動からむずかしい運動を段階的に習得する徒手体操を体系化した。同様の発想はJ.H.ペスタロッチの《基本体操》(1807)のなかにも認められ,〈部分の総和が全体を構成する〉とする近代的な分業による生産システムの体操への応用が,当時の教育の考え方とも符合していた。その結果,シュピースの徒手体操はドイツの学校体育の主流を占めるにいたった。しかし,彼の後継者たちは徒手体操を集団秩序訓練体操へと発展させ,体操の鋳型化,形骸化を招き,強い批判を浴びることになった。
これらの批判は,20世紀初頭に多方面からなされ,一括して〈体操改革運動〉と呼ばれており,大きく四つの系譜が認められる。(1)リング以来の伝統に支えられた北欧体操の系譜。医学的合理主義をさらに推し進めた新しいスウェーデン体操とデンマーク体操の主張である。なかでも,肋木(ろくぼく),横木,階梯(かいてい)などの器具を用いての運動の効果や機能に着目し,世界各国の注目を集めた。(2)演劇的な発想から,人間感情の表出を重視する表現体操の系譜。デルサルトF.A.Delsarte(1811-71)にはじまり,カルマイヤーH.Kallmeyerによってその理論化と体系化がなされた。彼らは,体操は形式ではなく人間の感情表出に基づくべきもので,心の躍動を表現する運動法である,と主張した。とくに,運動創作の分野で独自の貢献をした。(3)音楽的な発想に起源をもつリズム体操の系譜。形式的で機械的なタクト(拍子)による体操ではなく,生命現象の基本にあるリズム原理に基づく体操の主張である。〈振動〉運動を中心とする運動の緊張と解緊のリズミカルな交替法則,経済性の法則,表出をともなう心身の相互作用の法則,などに大きな特色がある。(4)ダンス的発想に基づく芸術体操の系譜。古典バレエの固定図式を打破しようとしたI.ダンカンの主張は,同時に形骸化したシュピース体操への強烈な批判ともなった。以後,R.vonラバンやM.ウィグマンらによってダンスを基調にした芸術的な体づくりや運動づくりが探求された。これらの〈体操改革運動〉は,隘路におち込んでいた体操を蘇生させ,新しい体操への道を切り開くことになった。1922年ベルリンで開かれた〈芸術的な身体運動に関する会議〉は,それまで個別に展開されていた体操改革の諸主張を一堂に会して論議し,統合するための絶好のチャンスとなった。25年には〈ドイツ体操連盟〉が結成され,女性の体操分野で著しい発展がみられた。伝統的な棍棒や亜鈴(あれい)などの手具だけでなく,ボール,輪,縄,帯状布などの手具を用いた体操に新境地が開かれた。この方向は,東欧諸国で顕著な発展がみられ,これらの手具体操に床運動,アクロバティックダンス,バレエなどの諸要素を加味した,リズミカルで美しくしかも巧みさを競う体操がスポーツの分野に進出し,1950年以降〈新体操競技〉として独立し,今日の隆盛を迎えている。
現代は,体操がふたたび多様化の時代に入っている,と考えられる。リズムにのる楽しさを強調したジャズ体操,心肺機能を高める有酸素運動に着目したエアロビック体操(エアロビクス),筋肉の伸展をめざすストレッチ体操をはじめ,東洋の神秘主義的な心身一如の思想に支えられたインドのヨーガ,中国の按摩・導引体操や太極拳,さらに一種独特の直観理論に基づくシュタイナーのオイリュトミー体操にいたるまで,多種多彩である。このような現代の体操の多様化現象は,現代人の健康生活上の不安の反映にほかならないが,その解決法には二つの大きな傾向が認められる。一つは,心理学や生理学などの科学的な根拠に裏づけされた体操を求める近代的・合理主義的な解決法であり,いま一つは,ヨーガに代表されるように,体操を単なる運動法と考えるのではなく,その根本にある宗教的な信仰をも同時に体操の内容として受け入れようとする解決法である。インドや中国やギリシアで発展した古代の体操は,信仰と深く結びついた健康法であり,養生法であった。しかし,近代の体操は,古代の体操が内包していた宗教性を排除して,その形態だけを継承し,近代のナショナリズムに支えられながら,さらに,より少ない時間と空間でできる,合目的的で,より効果的な運動法の開発へと体操の合理化を推進していった。20世紀初頭に現れた体操改革運動は,近代文明のもたらした科学主義や主知主義に対する抵抗であり,知性と情緒を分断された近代人に対し,体操分野での情緒の復権を迫ったものである。その意味で,現代の体操にみられる二つの大きな傾向は暗示的である。すなわち,合理性と非合理性を同時に併せもつ存在としての人間にとって,真の体操とはなにかがいま問われているといえよう。
執筆者:稲垣 正浩
日本における体操
洋式体操が日本に入ったのは江戸時代末期であるが,学校教育で体操が実施されるようになったのは,1873年5月,改正小学教則で〈毎級体操ヲ置ク,体操ハ一日一,二時間ヲモツテ足レリトス,榭中体操図,東京師範学校板体操図等ノ書ニヨリテナスベシ〉と示されてからである。前者の体操図はドイツの原書から,後者の体操図はアメリカの原書から翻訳したもので,いずれも保健を目的とする体操であった。明治の初期は,このような簡単な図解をよりどころに行う,いわば直訳模倣の時代であり,指導者もほとんどおらず,実際には各学校で実施されたわけではなかった。78年文部省が体操教員の養成を目的とする体操伝習所を設立し,アメリカからG.A.リーランドを招聘(しょうへい)して体操の指導にあたらせ,また手引書を出すようになって,ようやく体操が全国的に普及しはじめた。その体操は〈軽体操〉と呼ばれ,後には〈普通体操〉と呼ばれるようになるが,内容はやはり保健的性格のものであった。
しかし,明治20年代になって体操の教育的意味は大きく変えられる。すなわち,86年に一連の学校令の制定により日本の近代学校制度の確立がはかられた際,それまでの〈遊戯〉〈普通体操〉のほかに,小学校では〈隊列運動〉(ただし男児のみ)が,中学校・師範学校では〈兵式体操〉が教材として加えられた。兵式体操とは,陸軍において兵士の訓練のために行う集団的行動の諸形式で,実戦能力の育成よりも,秩序を守る習慣や精神を養うことを主たる目的とするものであった。兵式体操の学校教育への導入を熱心に主張した文部大臣森有礼の意図もまた,国家が必要とする人物にふさわしい精神的資質の育成にあった。兵式体操の採用は普通体操にも影響を及ぼし,国家主義的教育の手段としての性格を強めることになり,その形式主義化が普通体操の低調を招く結果となった。1900年代の初め,医師川瀬元九郎,東京女子高等師範学校の井口あぐりがアメリカからスウェーデン体操を持ち帰ってその普及につとめ,13年制定の学校体操教授要目では,それまでの普通体操に代わってスウェーデン体操が中心となった。しかし,たび重なる戦争を経て,体育の国家主義化,さらには軍国主義化が進行し,日中戦争に入ってからは〈大日本国民体操〉〈皇国体操〉〈建国体操〉などといった体操が相ついでつくられるにいたった。
第2次世界大戦直後は,学校体育はスポーツ中心へと転換し,明治以来体育教材の首座にあった体操は,かろうじて準備体操,整理体操としての必要を認められる程度のものとなった。しかしその後,58年の学習指導要領では〈徒手体操〉としてその位置を回復し,さらに,体力向上を体育の目標として強調した68年の指導要領では〈体操〉と名称も改められた。それにともない,内容も従来の身体各部を人為的形式に従って動かすものから,歩く・走る・跳ぶなど全身的で律動的な自然運動へと変化し,保健と体力づくりに加えて動きの教育としての性格を強めた。そこには,20世紀初頭から,伝統的体操の形式主義を否定し,人間の心身の解放を唱えて台頭してきた新しい体操の影響をうかがうことができ,学校での体操も見直しの時代を迎えている。
→学校体育
執筆者:中森 孜郎
体操競技
体操競技は国際体操連盟(FIG)に帰属するスポーツ種目の一つで,男子6種目(ゆか,あん馬,つり輪,跳馬,平行棒,鉄棒),女子4種目(跳馬,段違い平行棒,平均台,ゆか)から成っている。体操競技においては男女とも,それぞれの器械種目で演技することによって団体総合,個人総合,種目別の別で競われる。この体操競技を成立させる諸ルールは,ほぼ4年に一度改訂されている。このほか,体操競技に似た競技種目として新体操,トランポリンtrampoline,スポーツ・アクロ体操,エアロビクスなどがある。
歴史
体操競技の原型となる器械体操は,19世紀初めヤーンによって考案された。彼は1811年ベルリン郊外に体操場をつくり,あん馬,鉄棒,平行棒などの器械を使う体操を行ったが,今日の高度なものと比べると,かなり原始的であった。また古い時代の体操は,陸上競技と同じような走・跳・投も加わった体を鍛えるための総合運動であった。19世紀後半になると,ヨーロッパ各国で次々に体操連盟がつくられ,活発な活動がはじまった。81年には現在の国際体操連盟Fédération internationale de gymnastique(FIG)の基となる国際会議が開かれ,はじめて国際協約がつくられた。こうして体操競技は,96年アテネで開催された第1回オリンピック大会から正式種目となっている。アテネ大会では,器械体操の母国ドイツが強く,つり輪で地元ギリシアのJ.ミトロプーロス,あん馬でスイスのL.ズッターが優勝したが,ドイツ勢は鉄棒でH.ワインゲルトナー,跳馬でK.シューマン,平行棒でA.フラトーが優勝したほか,団体戦でも地元ギリシアを押さえて優勝した。しかしヨーロッパが中心であった初期のオリンピック大会は現在とは試合方法も内容もかなり異なっていた。例えば,今では1チーム6選手と決まっているが,1908年のロンドン大会では団体優勝したスウェーデンは59人を動員し,2位ノルウェーは33人,3位フィンランドは26人であった。最低でも1チーム16人,最高は60人もの選手が出場していた。日本が初参加した32年のロサンゼルス大会でも,器械体操とは別個にクライミングロープclimbing ropeやタンブリングtumblingが種目に入っていた。1903年にアントワープで第1回大会が行われた世界選手権大会についても同様で,第2次大戦後最初の大会(1950年,バーゼル)にいたっても,〈総合運動としての体操〉という古い時代のなごりで,棒高跳びや走高跳び,100m競走が体操競技の種目のなかに入っていた。現在のような方式になったのは,旧ソ連が初登場し,日本が戦後初参加した52年のヘルシンキ・オリンピック大会以後である。
ヨーロッパで育った体操が日本に上陸したのは江戸時代末期で,幕府や藩が軍事訓練のため洋式体操を輸入したことにはじまる。器械を据えつけて公に器械体操をはじめたのは明治の初めで,1871年(明治4)の廃藩置県の際,近衛鎮台兵の兵営に鉄棒,棚,手摺(てすり),木馬などが設置された。体操競技が日本で組織的に行われるようになったのは明治の末期からである。1902年慶応義塾に器械体操部が正式に誕生,04年に紅白競技会が開かれ,06年には青山師範学校との間で鉄棒,横木,棚,木馬の4種目で競技会が行われた。日本体操協会の前身である全日本体操連盟が結成されたのは30年で,同年第1回全日本器械体操選手権大会が開催された。32年のロサンゼルス・オリンピック大会が初めての国際試合参加であったが,結果は団体成績で優勝したイタリアに約140点の大差をつけられ最下位であった。35年ブダペストで開かれた第6回国際学生競技大会で慶応義塾チームが2位となり,国際舞台で日本最初の入賞を記録した。オリンピック大会では,戦後初参加した52年のヘルシンキ大会で,上迫忠夫が種目別の床運動で2位,竹本正男が跳馬で2位,上迫と小野喬が3位となりはじめてメダルを獲得した。続く56年のメルボルン大会では,鉄棒で小野が初の金メダルを獲得した。一方,オリンピックの中間年に開催される世界選手権大会では,54年ローマで開催された第13回大会で男子の竹本(床運動)と女子の田中(のち池田)敬子(平均台)が初優勝した。日本の女子体操代表が国際舞台へ出たのはこの大会が最初であった。体操競技のメーンエベントともいえる団体総合で,日本の男子チームは60年のローマ・オリンピック大会で初優勝し,以後64年東京大会,68年メキシコ大会,72年ミュンヘン大会,76年モントリオール大会と5連勝するとともに,世界選手権大会も62年プラハ大会,66年ドルトムント大会,70年リュブリャナ大会,74年バルナ大会,78年ストラスブール大会と5連勝し,オリンピック・世界選手権10連勝という成績を残した。この間,個人戦でもしばしば上位に入賞し,68年のメキシコ・オリンピック大会の床運動で,金,銀,銅メダルを独占した。個人戦でのメーンエベントである個人総合でも,1964年東京オリンピック大会で遠藤幸雄が初めて優勝したのをはじめ,68年メキシコ大会,72年ミュンヘン大会で加藤沢男が2連勝,84年ロサンゼルス大会でも具志堅幸司が優勝した。その後,しばらく低迷期があったが,2004年アテネ大会の男子団体総合で優勝,08年の北京大会でも2位となった。
競技方法
男子は床運動,あん馬,つり輪,跳馬,平行棒,鉄棒の6種目,女子は床運動,跳馬,段違い平行棒,平均台の4種目で競技する。男女とも各種目の総合点で争う団体総合,個人総合の総合と,総合時の各種目上位者による種目別選手権(種目別決勝)とがある。演技方法は,各自の創意工夫で行う自由演技である。床運動は男女とも12m四方の演技面で転回,宙返り,跳躍などのダイナミックな技や平均技などの静止技を調和のとれたリズミカルな構成で演じる。女子は音楽の伴奏がつく。跳馬は踏切板を使ってジャンプし,馬背に手をついて転回するなどして着地にいたるまでの飛形を争う。男子は馬を縦に置き,女子は横に置いて跳ぶ違いがある。つり輪はつり下がった2本のロープの先の輪を持って懸垂,回転,倒立などの技を演じ,回転やひねりなどをして着地するまでの技を争う。あん馬は馬の上で腕立支持の姿勢で旋回,交差運動などを行う。男子の平行棒は2本の平行した棒の上や下での宙返り,方向転換,倒立などの技とひねり技を入れたり,宙返りなどして着地にいたる技を争う。これに対して女子の段違い平行棒は2本の平行したバーの高さが違い,この段違いの上下バーの間を移行しながら演技を行い,最後はひねり技や宙返りなどで着地にいたるまでを競う。鉄棒は各種の車輪,側方跳越しなどした後,やはりひねり技や宙返りなどして着地するまでを争う。平均台は高さ1m25cmにはり渡した幅10cmの細長いビームの上で平均姿勢などの各種ポーズやダイナミックな跳躍,回転,宙返りなどをして着地にいたるまでを競う。採点は以前は10点満点からの減点法であった。しかし現在は,演技の難度など構成内容を評価するA得点と,演技のできばえを評価するB得点の両方を加算して算出する。審判員はA審判2名(うち1名が主審),B審判6名の合計8名。A審判は演技の難度,技のグループをチェックしてA得点を算出,B審判は演技の実施減点を10点満点から引いてB得点を算出する。
執筆者:小野 泰男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「体操」の意味・わかりやすい解説
体操
たいそう
体操は、(1)身体の円満な発育、発達を助けて、健康を保持増進する、(2)筋力を増強し、柔軟性、巧緻(こうち)性を養成して運動能力を向上させる、(3)身体の欠陥を矯正して美しい体をつくる、(4)スポーツや作業後の疲労回復に役だつ、などの目的をもって行う科学的な身体運動である。したがって、体操の種類は多く、その目的や効果、使用する器具、実施する対象などによって、いろいろな名称でよばれている。準備体操、整理体操は目的による、美容体操、医療体操、矯正体操は効果による、徒手体操、手具(しゅぐ)体操、器械体操は使用する器具による、学校体操、青年体操、産業体操、職場体操は対象による、ラジオ体操、テレビ体操は利用するマス・メディアによる各名称である。また、デンマーク体操、スウェーデン体操、ドイツ体操は創始国名、ブックNiels Bukh(1880―1950)の体操、ボーデRudolf Bode(1881―1970)の体操は創始者名、ソコールSokolの体操は団体名で、その種類、名称、特徴は多種多様である。
[上迫忠夫]
歴史
体操は、英語でジムナスティックスgymnastics、ドイツ語でギムナスティークGymnastikというが、いずれもギリシア語の「裸体」を意味するギムノスgymnosからきたもので、ギリシア時代には走、跳、投、ボクシング、レスリングなど、いろいろな競技が裸で行われたことに由来している。ギリシア時代のギムナスティークは、闘争に関係をもつ技術動作が主であったが、当時においても身体の調和的発達の必要性を理解して、胴体の体操、身体を柔軟にするための運動、抵抗によって筋力を増強する運動なども開発されていた。また中国では紀元前2600年ころすでに「医療体操漢法」という、庶民の要求によって生まれた健康法が行われていたといわれ、それは道教の僧侶(そうりょ)によって広められたと伝えられている。今日の体操の運動形式が生まれたのは18世紀で、ドイツ体操、スウェーデン体操、デンマーク体操がよく知られている。いずれも強健な国民をつくることを目的としていた。
[上迫忠夫]
日本の体操
1872年(明治5)に公布された学制により、日本の青少年教育に体操が取り入れられた。初めは下級小学校に「体術」として設けられたが、まだ教授方式など明確ではなかった。翌1873年茨城、愛知、岐阜、敦賀(現、福井県)、京都の5府県が発行した『体操図』から、体操ということばが一般に使用されるようになった。1878年文部省布達により東京・神田一ツ橋に体操伝習所が設立され、アメリカのボストン体育師範学校長リーランドGeorge Adams Leland(1850―1924)を招いて、学校体操の選定と指導者養成を図った。このとき通訳を務めた坪井玄道(つぼいかねみち)が『新体操法』を著して近代式体操を紹介した。ついで1886年、学校令の制定により体操科教科課程が設けられ、リーランドの方式が採用された。内容は、普通体操(矯正術、徒手体操、亜鈴(あれい)体操など)と兵式体操(柔軟体操、器械体操、教練など)を中心とした。
1902年(明治35)スウェーデン体操が紹介され、1913年(大正2)学校体操教授要目制定以後は、この体操が学校体育の主流をなした。その後、日本の体操に指導的役割を果たしたのは、デンマークのブックの基本体操、オーストリアのガウルホーフェルKarl Gaulhofer(1885―1941)の自然体操、ドイツのボーデの表現体操であり、いずれも律動と音楽による自然運動を主体とする体操であった。日本が第一次、第二次世界大戦に突入してからは、学校教育全般が軍事目的志向となり、体操は国民鍛練方法の一つとして軍事教練とともに重視され、国民体操、産業体操の名のもとに盛んに行われた。第二次世界大戦後の一時期、体操は、戦時中のスポーツ軽視の風潮からなおざりにされたが、教育課程改訂により小学校から大学まで体育が必須(ひっす)課目となり、ふたたび重視された。ことにオリンピックをはじめ、スポーツの国際交流が盛んになるにつれ、低年齢層の体力開発と国民の基礎体力向上が叫ばれ、体操教室、健康教室、体力づくり教室などが全国各地に設けられ、家庭婦人の間にも普及した。
体操実施の留意点としては、(1)目的を明確にすること。単に身体を動かすだけでは体操とはいえない。疲労回復のためなのか、激しい作業またはスポーツの準備運動なのか、筋力増強、柔軟性養成のためなのか、単なる健康保持のためなのか、目的をはっきりさせる。(2)年齢、性別、健康度、体力などによる適性を考えること。以上の2点があり、運動の内容、強度、実施時間、実施方法はおのずから決定される。肝要なのは、個々の運動を正しく、根気強く、継続して行うことである。目的に適した体操教室に入会し、専門家の指導を受けることが望ましい。
[上迫忠夫]
百科事典マイペディア 「体操」の意味・わかりやすい解説
体操【たいそう】
→関連項目ブック|リング
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「体操」の意味・わかりやすい解説
体操
たいそう
gymnastics
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
普及版 字通 「体操」の読み・字形・画数・意味
【体操】たいそう
字通「体」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典(旧版)内の体操の言及
【学校体育】より
…学校の管理のもとでスポーツ,体操,遊戯,ダンスなどの身体運動を用いて,計画的に行われる教育活動をいう。教科,体育行事,特別教育活動の3領域からなる。…
【体育】より
…モンテーニュ,コメニウス,ロック,ルソーらがその線上にあり,実践的な活動が盛んになるのは18世紀後半に入ってからである。すなわち,J.B.バゼドーは汎愛学校ではじめて体育を授業に組み入れ,J.C.F.グーツムーツは学校体育を確立し,F.L.ヤーンはドイツ体操を創始し,P.H.リングはスウェーデン体操を考案した。こうして近代体育が軌道に乗り,19世紀を通じて世界各国へ普及,普通教育の教科の一つとしてとり上げられるようになった。…
※「体操」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...