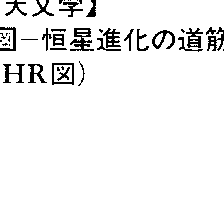天文学(読み)テンモンガク(その他表記)astronomy
精選版 日本国語大辞典 「天文学」の意味・読み・例文・類語
てんもん‐がく【天文学】
- 〘 名詞 〙 宇宙の構造や天体の運動、化学組成などを研究する学問。自然科学における最古の分野の一つで、現在では天体物理学・電波天文学・天体力学・天体分光学・位置天文学などに細分化している。天体学。星学。
- [初出の実例]「天文学三道あり、一は星学、二は暦算学、三は窮理学なり」(出典:和蘭天説(1795)凡例)
日本大百科全書(ニッポニカ) 「天文学」の意味・わかりやすい解説
天文学
てんもんがく
astronomy 英語
astronomie フランス語
Astronomie ドイツ語
天文学とは、ひとことでいえば「地球外の天体や物質を研究する学問」ということになる。近年の科学知識の普及により、天文学を天気予報と関係したものであると考える人は少なくなってきてはいるが、それでもなお、空でおこる現象はすべて天文現象であると誤解される場合も少なくない。
[磯部琇三 2015年5月19日]
天文学の対象
天文学は歴史的な発展の過程のなかで、対象を拡大し、内容を豊かにして、科学として成立してきた。天文学は4000年以上もの長い歴史をもつ医学とともに、もっとも古い学問の一つである。古代のメソポタミアやエジプトでは、農耕のための季節の移り変わりを知る必要から天球上の星の動きが観測された。水星、金星、火星、木星、土星などの明るく目だつ天体の動きが、天球上に散在する星々の日々の動きである日周運動とは異なっていることがみつけられ、古代人が住み着いた地域に大地を中心としたさまざまの宇宙観が形づくられた。
それらの宇宙観のうち古代ギリシアにおいては、ヒッパルコスによるより精度の高い天体の観測と、その300年後にギリシア天文学の最高峰を築いたプトレマイオスによる天動説によって、宇宙像はより確かなものとなった。この時代の天文学は、星々が天球上に張り付いた平面的な認識であり、しかも宇宙は変化してはならないという原則が根底にあった。ギリシア・ローマ時代、すでにハリー彗星(すいせい)の接近など天体現象の多様性を観測することができたが、彗星現象などは大気中におこる現象であるとされていた。これは、天体までの距離を測定する手段をもたなかったためである。
コペルニクスの地動説は、地球が動くか太陽が動くか、という天文学上の大きな問題を投げかけた。さらに地動説の登場によって太陽系の各天体間の距離が重要な問題となった。これに答えたのが、ティコ・ブラーエによる肉眼観測だけで得た精密で大量の位置観測データに基づいて求められたケプラーの法則であろう。これによって、地球と太陽の距離を単位(現在では1天文単位とよぶ)としてではあるが、太陽系内の各天体間の距離が明らかになった。
17世紀、大航海時代を迎えて、船の位置を正確に知るために天測が行われた。天測に使う星の位置を正確に示した星図や星表が出版された。これとヒッパルコスのカタログとの比較から、それまで変化しないと考えられていた星(恒星)が、日周運動以外に互いに位置を変える固有運動を示すことが発見された。天文学が太陽系空間から恒星空間に広がったといえる。
地球が太陽の周りを回っていれば観測されるはずであると考えられた恒星の視差測定は1838年になってようやく行われ、これによって恒星の世界を三次元的にとらえることが可能になった。それ以前にF・W・ハーシェルは、銀河系という太陽を含む星々の大きな集団の存在を指摘している。銀河系の大きさが3万光年にも及ぶ巨大なものであることが判明したのは20世紀に入ってからであり、さらに全体の構造が明らかになり始めたのは電波観測が行われてからである。
銀河系の外にある巨大な星の集団―銀河の研究も進み、100億光年余りの距離の天体まで調べられるようになった。宇宙は138億年前にビッグ・バンによって始まり、その中から銀河や星々が形成され、そしてそれらの天体が進化し、滅んでいくことも明らかになってきた。
天文学はそれらの巨大な宇宙の姿を取り扱っており、その中に存在するものは互いに密接な関係をもつようになった。宇宙のビッグ・バンの直後に放射された電磁波が3K放射として観測されており、そのころに形成された水素原子やヘリウム原子が特定の星の中に化石として残っている。一方、星の中で形成された元素が星間空間に放出され、それが次の星の誕生時に取り込まれたのが、地球上でみられるような多くの元素である。このように、地球を調べる場合でも、それらの元素の起源を尋ねる場合には天文学と関係をもたなければならなくなってきている。
今日の天文学はかつての天文学のように可視光だけによる観測ではすまなくなっている。可視光と同じ電磁波である電波、赤外線、紫外線、X線、γ(ガンマ)線などあらゆる手段が用いられ、対象とする天体の範囲は3Kから数億Kという多様な温度に拡大している。さらに太陽系空間では、人工飛翔(ひしょう)体(探査機)が現場まで飛び、その場で物質を化学的に調べることが可能になっている。
冒頭で天文学を大気の外の現象を研究する学問であると述べたが、天文学は長い歴史のなかでその対象を拡大し、現代にあっては単に天文学という一つの学問の範疇(はんちゅう)に収まりきれず、他の多くの学問との密接な協力を必要としてきている。星々の大気を調べる宇宙化学、そして高分子からもっと大きい生命の基となる物質を求める宇宙生物学などの分野も開けてきている。
[磯部琇三 2015年5月19日]
天文学の方法
肉眼による観測
天体観測のもっとも簡単な方法は肉眼で夜空を見上げることである。夜空に輝く星々を見ることが宇宙のさまざまな事象を考える一つの契機になっていることは確かである。古代の人々も夜空の星を見てそれぞれの宇宙像をつくりあげた。
肉眼で見える天体は、数千個(全体で6000個)の恒星と5個の惑星、月、太陽、それにときおり現れる彗星と新星(超新星)である。彗星や超新星は何年かに1回ぐらいしか現れないので、ほとんど決まった天体を見ていることになる。その結果、肉眼観測においてもっとも関心がもたれたのは星々の天球上の位置であり、天体の位置を測定するためにさまざまなくふうがなされた。水平線のような基準となる方向からの角距離を求める四分儀や六分儀(中国では渾天(こんてん)儀)などが発明された。とはいえ、人間の目はそのレンズの大きさや視細胞の大きさによって1分角より細かく分解して見ることはできず、熟練した観測者がこれらの装置を用いて観測しても、せいぜい0.1分角の精度の位置しか得られなかった。
肉眼による観測は、恒星のように相対位置に変化がみられない天体では新しい事象を明らかにすることはほとんどできなかったが、太陽、月、惑星のように天球上を動く天体に対しては有効な手段であった。メソポタミアや中国では惑星の周期ばかりでなく、日食や月食の予報もある程度行われていたし、また月の動きがより高い精度で求められ、太陰暦をつくる基礎となった。つまり長年月の肉眼による観測を記録し比較することによって正確な暦を作成したのである。
[磯部琇三 2015年5月19日]
望遠鏡の導入
1608年、オランダの眼鏡職人リッペルスハイHans Lippershey(1570―1619)が初めて望遠鏡をつくり、翌年ガリレイが天体観測に望遠鏡を用いて、天文学に大きな革命をもたらした。望遠鏡の使用が天文学に与えた影響には二つの側面がある。一つは、人間の目の瞳孔(どうこう)より大きい口径の対物レンズ(鏡)が、天体からの光を多く集めてより暗い天体をとらえることができるようになり、太陽系内では天王星や海王星、そして数々の小惑星が発見され、また彗星や新星の発見の数が肉眼観測に比べて著しく増大したばかりでなく、多くの星が明るさを変えていること、恒星はつねに変わらない天体であるという考え方が当てはまらないことなどが明らかになった。このように望遠鏡によって観測可能な天体が増えてくると、より多くの人々の協力が必要となり、それが多くのアマチュア天文家の誕生を促した。天文学は他の学問分野と異なって、アマチュア天文家が学問の一部を担うことができる例外的な学問である。
望遠鏡の使用によるもう一つの側面は、対物レンズ(鏡)の口径に反比例して角分解能が向上することである。ガリレイは木星の四つの衛星を発見したが、これは、望遠鏡により木星本体と衛星を分離して見ることができることによって可能となったのである。それまで連続的に輝いていると考えられていた天の川が、多数の星が重なり合っていることも明らかにされた。また20世紀に入り、アンドロメダ銀河が銀河系内の天体であるか系外の天体であるかを決める最大の鍵(かぎ)となったのは、星雲状の部分が個々の星に分解でき、その距離を測定することが可能になったためである。対物レンズ(鏡)の口径を大きくすることによる角分解能の改善(口径10センチメートルの角分解能は約1秒角、100センチメートルでは0.1秒角)は、多くの新しい発見を可能にしてきた。しかし地表に近い所では大気のゆらぎによって点像が1秒角以上に広がってしまい分解能が低下する。このため、近年は大気のゆらぎの少ない標高4000メートル級の高山に望遠鏡を設置し、その困難を除去する努力がなされている。また口径2.4メートルの望遠鏡をスペースシャトルに積み込んで大気圏外に持ち出したスペーステレスコープ(ハッブル宇宙望遠鏡)によって0.02秒角の分解能も可能となり、たとえばハリー彗星が遠日点に達した30等級の暗さでも観測することができる。つまり望遠鏡の口径の増大は、暗い天体の観測を可能にするばかりでなく、角直径の小さい星の観測にも有効である。
望遠鏡の導入は、天体の位置測定の精度を100倍以上に高め、高精度の観測によって得られたデータを説明するために、ニュートンの万有引力の法則が考えられた。そして太陽系の天体の動きはすべてこの法則に従っていることが示され、さらに恒星間空間や銀河間空間の説明にもこの法則が用いられていった。恒星の運動がニュートンの法則に従うか否かを調べるためには、その距離を求めなければならない。1838年暮れから1839年正月にかけて、ベッセル、ヘンダーソン、ストルーベらによって次々と恒星の年周視差が求められた。その測定には望遠鏡が用いられたとはいえ、肉眼による観測であり、個々の星の位置と他の恒星の位置を比較し決定するもので、非常な困難を伴った。
[磯部琇三 2015年5月19日]
写真術の応用
1839年写真術が発明され、翌年すでにドレーパーが月の写真を撮った。写真術の天体観測への応用も天文学を進める大きなステップとなった。写真の特徴は、天体からの光を蓄えられること、データとして保存できること、などである。人間の目は10分の1秒の光を蓄える能力をもつが、それより長時間見ていても暗い天体を観察することは不可能である。写真では1時間の露出をすれば1時間分の光を加え合わせた天体の撮影が可能であり、たとえば彗星や散光星雲などのように暗く広がった部分を撮るのに威力を発揮する。データ保存の機能を有する写真は、新星や変光星などの性質を調べるためには欠くことができない。最近発見されたγ線を突発的に放射する特異な天体が、80年前にハーバード大学天文台で撮られた写真のなかに写っていたという例もある。また半年の間隔を置いて撮られた2枚の乾板を比較して、数百光年より近い星の年周視差が求められたり、それらの星の光をプリズムを用いてスペクトルに分け、星の大気の状態が明らかにされている。
星の本来の明るさである絶対等級と星の表面温度を示す量であるスペクトル型の関係はヘルツシュプルングとH・N・ラッセルによって研究され、この関係を示した図はHR図とよばれるが、この図を用いて、年周視差の測定できない星々の距離が決定されている。さらにセファイド(ケフェウス)型変光星の変光周期は、その絶対等級との間に一定の関係が成立することがわかり、星のスペクトル写真を撮らなくても距離が求められるようになった。
写真撮影によって星のスペクトル線が写せるようになると、そのスペクトル線の本来の位置からのずれをも測定することができるようになった。ずれを引き起こすおもな原因は、天体と観測者との間の視線方向の動きによるドップラー効果である。星の固有運動と距離の値から横方向の速度が求められ、これによって三次元的な運動が明らかになった。ハッブルは、1917年にウィルソン山天文台に完成した口径257センチメートルの当時世界最大の望遠鏡を使って銀河のスペクトル写真を撮り、それらの視線速度を測定して観測される銀河までの距離に比例して後退速度が速くなるというハッブルの法則をみつけた。ハッブルの法則は、銀河の分布している宇宙は膨張しているという考えの基礎となった。
写真観測の欠点は、乾板に乳剤を塗布したものを使うために精度が悪く、0.1等級程度の誤差が生ずること、さらに露光後の結果がみられるまで現像時間があるため、刻々と変化する天体の観測に不利であることなどである。
[磯部琇三 2015年5月19日]
特殊観測装置の登場
1930年代から光電効果を使った受光器が用いられるようになり、さらに電子を増幅することにより0.002等級という飛躍的な精度で天体観測ができるようになった。セファイド型変光星のような規則的な変光を示すものばかりでなく、地球軌道より直径の大きいミラ型変光星の大気のゆらぎや、突然に爆発的に輝きだすフレア星の存在も明らかにされた。連星は、その軌道周期や光度変化を使って、それぞれの星の質量を決めることができる重要な天体である。二つの星が互いに隠し合う食現象の観測によって、個々の星が球形からどのように変形しているかを求めることができる。このためには高精度の等級決定が必要なのである。
光電子増倍管による観測では一時に一つの星しか観測できないため、多数の天体を同時に観測でき、しかも精度のよい受光器が求められた。1970年代、テレビ技術の急速な発展によってそれが可能になってきた。さらに電荷結像素子(CCD)を用いた装置が開発され、入射光の90%以上が有効に使える二次元画像受光器が可能になった。その結果、土星より外にあるハリー彗星のような24等級の天体を数十分の観測でとらえることができるようになった。望遠鏡の口径の増大とともに高精度の二次元画像受光器の採用は、これまで観測が困難であったクエーサーやパルサーの検出、星の誕生の場所の観測など多方面での新しい研究を開く要因となってきている。
[磯部琇三 2015年5月19日]
電波による観測
1930年、アメリカのジャンスキーによって銀河の中心から電波がくることが発見されたことが契機となって、電波天文学という新しい分野が開かれた。1944年、水素原子から放射される電波が波長21センチメートルの電波として受信できることが予言され、1951年、ユーインHarold Irving Ewen(1922―2015)とE・M・パーセルがその観測に成功し、星間空間には星の質量に匹敵するガスが存在することが示された。1970年代以降、急速な電波天文学の発達により、センチメートル波帯からミリメートル波帯へと新しい波長領域が開かれるにつれて、星間空間において簡単な分子から複雑なものまで多数の分子がみつけられた。このような分子を含むガス雲の密度は星間空間としては高く、太陽の質量の数十万倍の質量のガスを含む分子雲を形づくっている場合が多い。
可視光の場合と同様に、電波観測においてもより暗い天体をより詳しく観測する必要が大きくなっている。電波観測の最大の欠点は角分解能が悪いことで、たとえば可動式では世界最大のエッフェルスベルグ(ドイツ)の電波望遠鏡は口径100メートルであるが、波長1センチメートルでは0.5分角の分解能しかもたない。この欠点を補うために干渉計という技術が開発された。超長基線電波干渉計は0.001秒角の分解能をもち、遠距離のクエーサーが非常に小さな天体であることを明らかにしている。
[磯部琇三 2015年5月19日]
超高空・大気圏外からの観測
可視光より波長の長い赤外線の存在は19世紀にわかっていたが、それらの電磁波を受光する装置がなかったため赤外線天文学は進展しなかった。赤外線の観測が始められたのは1960年代である。赤外線観測では、大量の星間塵(じん)を含む分子雲内でガスが収縮して新しい星の誕生がおこると、星の光のエネルギーで温められた星間塵が赤外線を放射する姿をとらえることができる。また電波観測との協力によって星間雲から星への進化のシナリオを描くことが可能となってきている。地球の大気に遮られて地上に届かない波長100マイクロメートルの遠赤外線の観測には、望遠鏡を気球にのせて上空での観測が行われている。1983年にはIRASとよばれる赤外線用人工衛星が打ち上げられ、宇宙に散在する低温の天体を次々に発見、またベガのように通常の恒星の周りにも惑星系の元になるような塵(ちり)の円盤が存在することなどをみつけた。さらに1996年にはISOという赤外線用人工衛星が打ち上げられ、より大きな発展を示した。
紫外線、X線、γ線などの観測も大気圏内では不可能である。1946年に最初のX線観測のためのV2ロケットが打ち上げられた。1970年代以後、ロケットや人工衛星の技術の発達により、紫外線天文用としてコペルニクス衛星や国際天文紫外線衛星が、X線用として、はくちょう衛星、てんま衛星、アインシュタイン衛星などが打ち上げられた。それらは星間空間の観測ばかりでなく、星の周りにおける10万~1000万Kに及ぶ高温の領域が存在すること、太陽のコロナのように星の周りにもコロナが存在すること、超新星の爆発エネルギーにより分子雲のような低温のガスの近傍に数十万Kに達する高温ガスが隣り合わせに存在することなどをつきとめ、また、かに星雲の中心星が中性子星となって強力なX線を放射していることや、なかにはブラック・ホールと考えられる天体もみつけている。
新しい天文学は急速な発展をみせて、数多くのデータを蓄積するに至っている。天文学の方法はさまざまな観測手段の開発とその発達によって発展してきた。
[磯部琇三 2015年5月19日]
天文学の分野と他の自然科学
天文学は高等学校の教科では地学に組み込まれている。その理由の一つは、地学の手法と共通して多数の観測(観察)例を集めて、そのなかから法則性をみいだそうとする手法によっている。ヒッパルコスは多くの星の位置を精密に測定し、それらの星々を繰り返し観測してデータを整理することによって歳差とよばれる現象をみいだした。ハッブルは銀河の距離とドップラー効果による視線速度のデータを並べてハッブルの法則をみいだした。このように天文学ではさまざまな観測データを並べ、それらを洞察力をもった目でみることによって新しい法則性がみつけられる場合が多い。つまり、より多くの観測データを集めることが天文学にとっては重要な課題である。
17世紀初頭、ケプラーの法則が提出されて以後、天体の動きは統一された法則に従って取り扱われるようになった。ケプラーの法則は、ニュートンの万有引力の法則によって統一された。天体の軌道問題をニュートン力学の下で解くためには、微分・積分学の知識が必要である。数学における微積分学の展開は、惑星・小惑星ばかりでなく、彗星の軌道計算を可能にし、ニュートンの友人であるハリーはのちに彼の名が冠せられた大彗星の軌道を発見した。
天体力学の確立は太陽系内の天体の運動を正確に記述することを可能にした。このことが、物理定数のなかでもっとも重要な光速度の決定を可能にした。たとえばレーマーは、木星の衛星の食の周期の観測によって光の伝播(でんぱ)に時間のかかることを発見、光速度を求め、またブラッドリーは、光速が有限であるために地球の公転運動の速度に対応して、天球上の星の位置がずれる光行差の現象を発見した。
光速が有限であることは各方面に大きな影響を与えた。遠い天体ほど昔の姿をみせているという事実は宇宙の理解の仕方を変え、相対性理論のように時間と空間の等価性をもった理論へと発展していった。また宇宙のビッグ・バンモデルにおけるより遠くの天体を観測することによって、宇宙の始まりに近いところを調べることになるというのも光速の有限性からくるものである。光速有限性を使った新しい観測術も試みられている。地球からレーザー光線を放射して月あるいは人工衛星の表面に設置した鏡に反射させ、戻ってくる時間を測って距離を求める方法で、望遠鏡による位置の測定よりもはるかに精度が高く(誤差1センチメートル以下)、宇宙技術の進展に欠くことのできない観測技術である。
ニュートンは1666年に三角プリズムを使って太陽の光がスペクトルに分解できることを示したが、天体の光がスペクトルに分散できるというこの発見は、天体物理学の基礎として重要であり、天体力学における万有引力の発見に匹敵する。19世紀初頭、分光器の改良を進めていたフラウンホーファーは太陽スペクトルのなかに多くの暗線のあることを発見、1850年代、オングストレームとストークスが、それらの暗線のある位置が実験室で見られるナトリウムのスペクトル線の位置と一致していることをみつけた。この発見は、太陽さらには恒星の化学組成を明らかにする第一歩となった。ローランドは太陽スペクトルを詳しく調べ、地上でみられる36個の元素による吸収線をみつけ、またロッキャーらは太陽スペクトルから、それまで地上にみられない元素による吸収線を発見、ヘリウムと名づけた(のちにヘリウムは不活性ガスとして地上に存在することが明らかになった)。地上に存在しないと考えられた元素に、コロナの中にみつかったコロニウム(1870)、星雲中のネブリウム(1927)がある。コロニウムは100万Kもの高温で存在できる鉄原子が13回電離したものであり、ネブリウムは酸素原子などの電子軌道間の遷移のうち、量子力学によって禁止されているものであった。これらの発見は量子力学を形成するうえでも重要なものであった。1913年にボーアは原子モデルを発表して、水素原子のスペクトル線が原子核の周りの電子軌道の遷移で説明できることを示した。
原子核物理学が進み、1919年にはラザフォードが原子核の人工転換に成功した。その結果から、それまで説明困難であった太陽や恒星のエネルギー源が、水素原子からヘリウム原子に変わる核融合反応によるものであることが明らかになった。そして20世紀初頭に得られたHR図上の星々の分布は、さまざまな質量の星がその内部で原子核融合反応をしているその反応の各段階のようすを示していることもわかってきた。
天体物理学は、星の表面の性質やその内部の状態を明らかにするばかりでなく、星間空間にも物質があることをつきとめた。1905年、ハルトマンは、星間空間にカルシウムおよびナトリウムの元素による吸収線を発見した。ついで電離酸素やカリウム、鉄などの物質が発見され、化合物として炭化水素CH、シアンCNなどの分子の存在が確かめられた。さらに電波観測技術の発展により、1963年には水酸基OHがみつかり、それ以降、一酸化炭素CO、水蒸気H2O、硫化水素H2Sなど60個以上の分子の存在が確かめられている。新しくみつかった電波スペクトル線がどのような分子に対応するのかを調べるために、室内実験や理論計算によっていろいろの分子線の波長が決められ、複雑な分子までが研究対象になっている。
星間空間には、分子のほか1マイクロメートル以下の微粒子が存在する。これらの微粒子は光の波長よりも小さく、光を散乱する度合いが波長によって異なり、波長の短い光ほど強く散乱・吸収する。そのため遠い星の光が見かけ上すこし赤みがかって見え、これを星間赤化とよぶ。これらの微粒子の表面を触媒として星間分子の大部分は形成されている。今日では微粒子表面だけでなく、ガス状態の分子どうしの化学反応の研究も重要になっている。
固体微粒子の組成の研究も重要な課題となっている。太陽や星などでは各元素の存在の割合がほぼ一定の値であるが、星間ガスでは水素原子やヘリウム原子を除くと、その割合は太陽などに比べて少なくなっている。少なくなった元素の多くは固体微粒子の中に閉じ込められている。これらは星間塵とよばれ、酸素を主成分とする水、炭素のグラファイト、ケイ素の砂粒などがおもな成分である。星間塵は星を誕生させる分子雲の中に多量に存在し、周りの熱源に対応していろいろの温度の赤外線を放射している。星がどのように誕生するのか、またその周りに太陽系のように円盤状に物質が集まり惑星系がどのようにつくられるのかは、この星間塵の性質によって異なってくる。天体現象の説明には固体物理学の知識が必要になってきている。
星間分子の多くは星間塵の表面で形成され、しかも複雑な分子まで発見されているが、電波観測でそれらが発見されるためには、星間空間の視線上に1013個以上の同種類の分子がなければならないことを考慮すると、その数は少ないであろうが、より複雑な分子の存在が考えられる。そして星間塵の主成分が水や炭素原子であることを考え合わせると、生命の基になる有機物質が存在する可能性もある。このような状況と、星が誕生するときに惑星系を形成する可能性が強いことから、地球以外の宇宙に存在の可能性がある生命体についての研究がなされている。宇宙生物学が始められている。
原子どうしが密に結合して自由に動けなくなったのが固体である。一方、太陽程度の質量の星の進化の最後の段階にあたる白色矮星(わいせい)は、原子どうしの表面が接触するぐらいに詰まった天体である。太陽よりはるかに質量の大きい星の場合には、原子核の中に電子が押し込められてしまい、すべてが中性子でできた中性子星になる。1立方センチメートル当り106グラムの白色矮星と、1015グラムの中性子星の間には大きな隔たりがある。しかしこのような星は一種の固体として取り扱うことができる点において共通している。中性子星の多くは強いX線源である。そしてX線源として有名なはくちょう座X‐1やコンパス座X‐1には、中性子星よりも密度の高いブラック・ホールが存在している可能性が強い。中性子星では素粒子の核力によって互いにつぶれないように支えているが、1立方センチメートル当り1015グラム以上の密度になると核力では支えきれなくなって押しつぶされる。これがブラック・ホールである。ブラック・ホールからは光も物質も逃れ出すことはできず、したがってその存在を直接観測できないが、その周辺の星や空間からガスを吸い込む際に非常に大きなエネルギーが放出される。これがγ線、X線から電波までのあらゆる電磁波で観測される。
白色矮星や中性子星、ブラック・ホールのような天体は、地球上の実験室では実現できないような高密度・高温度の状態にあるので、極限の物理学を研究するうえで非常に重要である。
これまであげてきたさまざまな天体の現象は、観測の結果が物理学によって理論的に確立され、あるいはその逆に理論が観測によって証明されるものであった。その代表例はニュートンの法則にみることができる。理論的に存在が予想されたブラック・ホールも電磁波の観測によって明らかにされた。光速の90%もの速さで遠ざかるクエーサーがあり、これにハッブルの法則が適用されれば、その観測によって百数十億年も過去の状態を知ることができる。そのためにより遠くのクエーサーを探す努力が巨大な望遠鏡を使って行われている。それでは、あらゆる天体の現象について以上のような関係が成り立つかといえば、そうとはいいきれない。現代の天文学の理論の基礎となっているのは相対性理論と量子力学であり、その相対性理論は、たとえば太陽の近傍を通過する恒星の光が約1.8秒角曲げられる現象や、水星の近日点が1年に約0.43秒角余分に動く現象、あるいは、遠方のクエーサーが近傍の銀河とほぼ同じ方向にあると重力レンズがあるような形になってまったく同じ二つのクエーサーが見える現象などの観測によりその正しさが確かめられている。しかし、たとえばこれらの理論によるビッグ・バン宇宙について、理論的にはビッグ・バン後10-44秒、宇宙が1032Kであったころまで、その状態を明らかにすることができるが、今日の電磁波を使っての観測技術では、ビッグ・バン後10万年より以前の宇宙の姿を見ることはできない。それは、そのころの宇宙の物質密度があまりにも高く、電磁波は自由に空間を飛ぶことができなかったためである。
以上みてきたように、今日では、天文学は天文学のみで独立した学問ではありえなくなっている。物理学そのものであったり、物理学のいろいろな分野、化学、生物学、そして惑星学という意味での地球物理学などと密接な関係にある。気象学も太陽や木星の大気の取扱いにおいて関係をもち始めている。天文学はまさに総合科学であるというのにふさわしい時代を迎えているのである。
[磯部琇三 2015年5月19日]
天文学と他の分野
天文学と社会
人類はその誕生後、長い狩猟生活の期間を経て、しだいに農耕を行うようになった。種を播(ま)く時期を決めるために季節を知る必要性が出てきた。夜空の星を見、太陽の動きを観測することがその第一歩であった。古代エジプトではシリウスが日の出直前に東天に昇るころの一定時期にナイル川が氾濫(はんらん)し農業や生活に大きく影響を及ぼすところから、氾濫を予報するためにシリウスの日の出直前の出現を予知する必要が生じ、1年の長さを知った。このように天文学の始まりは農業から出ているといえる。そして農業がそれぞれの国の主要な産業となってくると、季節の変化を予報することが権力者である国王にとって重要なものとなった。季節の変化ばかりでなく、日月食などの天文現象を正確に予報することは権力者の威令を行き届かせ、人民を支配するうえで重要であった。そのため中国でもギリシア、ローマでも権力者は専門の天文官を置いて天体の観測を古くから行ってきた。このような伝統は今日にまで続き、暦の編纂(へんさん)は各国の政府直属の機関で行われることが多い。日本では国立天文台と海上保安庁水路部、アメリカではワシントンの海軍天文台が編纂している。
紀元後15~16世紀の大航海時代、広大な海原を航行する船の位置を正確に知るために星が使われ、そのために天球上での星の位置を正確に観測する努力がなされた。その一例が1675年のイギリスのグリニジ天文台の創設と、その前後に相次いでヨーロッパ各国が天文台を建設したことである。これにより恒星の固有運動や光行差など天文学上の大きな発見がなされた。現代では天文学は純粋科学の一つと考えられるようになってきた。しかしそれでも場合によっては政治的に利用される場合がある。軍事衛星を含む人工衛星の動きは天体力学を基礎に解析されているが、このような実際的なものばかりでなく、アポロ計画での月面への人間の送り込みと月探査が結果的に国威発揚に利用されるといった例もある。
現代の天文学の経済とのかかわりは古代の農耕時代のように直接的ではないし、深いものではない。太陽フレア現象の監視から、地球でのデリンジャー現象による電波障害の影響を予報するといった程度のものであろう。一方、天文学が物理学の進歩に役だっているという意味で、工業技術に貢献してきたといえる。さらに天文学の観測研究には最先端の工業技術が要求され、天文学を進めるために開発された製品が工業製品の水準を高めている側面もある。その代表的なものがスペーステレスコープに使われている高感度のCCD撮像素子であろう。
[磯部琇三 2015年5月19日]
天文学と哲学・宗教
天体現象の多くのことがわかってきた現代においても、夜空を眺めると宇宙の深遠さに心打たれる経験をもつ人は多いであろう。数千年も昔の人々は昼夜の変化ばかりでなく、日々に変わる星空に大いに興味を抱いたであろう。石器時代末期に数多くの星座などの彫刻が生まれるようになったのは、そのような人々の意識の表れであろう。古代では天文学は天体現象の予報という実際的な側面と、宇宙の構造に関する哲学的な側面との二つの方向に広がっていった。そして宇宙は土・水・風・火の4元素からなるとする原則を考え出す一方、宇宙は神によってつくられ、天体現象は神の意志の表れとする宗教的な側面にまで連なっていった。そのような時代にあっても、天体を観測するという点では科学的な態度が貫かれた。とくに紀元前6世紀、古代ギリシアのタレスをはじめとするイオニア学派は、宗教や神話から独立した科学的視点から天体現象の説明を試みている。しかしこのような流れも、ヨーロッパ中世を通じて、宇宙は神の創造物とする考え方に支配されて進展をみせなかった。中国や日本では金星よりも明るくなったと記録されている1054年の超新星爆発(現在かに星雲とよばれる)も、ヨーロッパでは、宇宙に存在するものは不変であるという考えの下に記録されなかったのであろう。コペルニクス、ガリレイが唱えた地動説がキリスト教界との間に引き起こした軋轢(あつれき)についてはよく知られている。1983年5月、ガリレイが宗教裁判で有罪となって350年を経て、法王ヨハネ・パウロ2世はガリレイへの判決が誤りであったことを公式に認めた。このことはある意味で一つの時代を画したといえるであろう。
ガリレイが主張した宇宙観は太陽系の中だけの話であった。しかし現在の宇宙論は、恒星界から銀河の世界、さらにはビッグ・バンという宇宙創生の時点にまで膨大に広がっている。ガリレイの時代、神のみぞ知るといった世界まで今日では科学のメスが入れられている。それでは、天文学や物理学は宗教的な側面をすべて消し去るほどに宇宙の事実を明らかにしたであろうか。また明らかにできるであろうか。天文学上の数多くの個々の問題はもとより、ビッグ・バン以前の宇宙について、あるいはブラック・ホールの中の状況について、宇宙の終わりについて、などという問題に答えが出せるであろうか。もし出せたとしても、それですべての問題が解決されたことになるのであろうか。技術的に考えても宇宙の全体像を明らかにするには、宇宙に存在する全原子数より多い計算機の記憶素子を使っても計算するのは不可能かもしれない。天文学は宇宙のどこかに生命体が存在する可能性の強いことを示し始めている。何十万光年のかなたに人類のような存在があるとなったとき、わたしたちは新しい宇宙像をどのように描けばよいのであろうか。宇宙の理解という意味で天文学は宗教や哲学とふたたび密接な関係をもち始めた時代ではないだろうか。
[磯部琇三 2015年5月19日]
現代天文学の動向とその将来
天文学はその手法の根底がそうであるように、より多くのデータの集積が重要である。星や銀河やクエーサーが刻々と各波長域での強度を変化させていることが判明してきた現在、必要なデータ量は膨大なものとなっている。そのため、より多くの望遠鏡で、精度の高い、能率よい観測は不可欠のものとなっている。多数の天体のなかから特徴ある天体現象をみつけるためにはアマチュア天文家による観測もますます必要である。
一方、種々の天体の詳しい研究は一段と進んでいる。電波やX線などによる観測が始まったころは、その波長で天空を観測したというだけで天文学的な大きな発見がなされた。しかし1980年代に入ってそのような時代も終わろうとしている。より暗い、より強度の弱い天体の観測が重要になってきた。電波望遠鏡では長野県野辺山(のべやま)宇宙電波観測所の45メートル、ドイツ、エッフェルスベルグの100メートルという大口径のものが建設されている。さらに角分解能をあげるためにアメリカ、ニュー・メキシコ州の大口径開口合成電波望遠鏡をはじめとする多くの干渉計により、地上での可視光の限界を超える観測がなされている。1997年(平成9)には日本の人工衛星「はるか」が打ち上げられ、人工衛星上のパラボラアンテナと地球上の電波望遠鏡の連携によって形成された巨大な干渉計による観測も始まっている。X線においても大口径・高角分解能のアインシュタイン衛星が、大半の星の周りにコロナが存在することなど新しい発見をしている。
電波やX線を放射する天体は一般に可視光では暗く、その観測のために超大口径の望遠鏡の建設が必要となっている。1948年パロマ山天文台の508センチメートル望遠鏡以後、しばらく下火にみえた大口径望遠鏡の建設も、1990年代には、日本をはじめ、アメリカ、ロシアなどで従来のものを大きく上回る規模で建設され、日本がハワイに設置した8.2メートル望遠鏡をはじめ、9台の大口径望遠鏡が次々と完成している。
これらの大装置の完成によって、大きな天文学的な発見がなされ始めていることは確かである。しかしガリレイが自分自身の資金と能力をもって製作した望遠鏡と異なり、その建設には数百億円という巨大な費用が必要となっている。天文学のこのような側面は、昔のように1人の人間の趣味で行える範囲を大きく超えている。天文学は人類の宇宙に対する限りない知的興味を基盤に発展し、現在も重要な課題に取り組んでいる。宇宙の実相を一つ一つ解明していくことが人類にとってどのような意味をもつのか、ということを改めて考えなければならないほどに天文学が巨大化したことも事実である。
現代の天文学の動向で重要な点の一つは、電磁波だけで観測するのではなく、現場において調べられるようになったことがある。人工探査機アポロによって月が調べられた。惑星探査機パイオニアやボイジャーによって木星をはじめとする惑星が探査された。これらは、調査しようとする天体の近傍に直接行って解析するものであり、非常に強力な手段である。この方法の問題点は、次々と探査機を送り続けることができないことと、この方法が使用できる範囲が現段階では、せいぜい太陽系内に限られていることである。
[磯部琇三 2015年5月19日]
天文学の歴史上の発見
天文学の発見の多くは長年のデータの積み重ねによって生まれる。ここでは、天文学の歴史上、重要な発見をあげておく。
日月食の予報に関して、太陽と月とが19年間でほぼ同じ位置に戻るサロス周期は紀元前7世紀にみつけられている。紀元前150年ごろにはヒッパルコスが約1000個もの星の位置のカタログをつくり、その結果、星々が歳差運動をしていることを示した。1543年のコペルニクスの地動説はそれまでの天動説を覆すものとしてよく知られるが、1596年にファブリキウスがくじら座ο(オミクロン)星(ミラ)の変光を発見したことは、それまで不変であると考えられていた恒星に対する考え方を大きく変えるものであった。ガリレイは望遠鏡によって太陽黒点、木星の四大衛星、土星の耳(環(わ))などをみつけたが、1610年にファブリキウスは太陽が自転していることを認識している。
1672年にカッシーニによって太陽視差が測られ、ケプラーの法則と組み合わせることにより、太陽系の惑星の分布が決められるようになった。そしてニュートンの万有引力の法則によって各天体の相互の位置が正確に予報できるようになり、それが、1675年の木星の衛星の食を使った光速度の決定へと続いた。
1781年のF・W・ハーシェルの天王星の発見、1801年のピアッツィによる小惑星ケレスの発見、1846年のアダムスの海王星の発見というように、太陽系天体の解析が次々と行われ、天体力学の有効性が明らかになった。
一方、恒星界についても、1718年にハリーによって恒星の固有運動がみいだされ、明るさの変化ばかりでなく空間的にも動いていることが明らかになり、太陽系自身も恒星の間を動いていることが知られた。キリスト教総本山のバチカン天文台のセッキは1866年に恒星のスペクトル分類を行い、HR図をつくるうえでの基礎的データを得ている。1868年にハギンズは恒星の視線速度の測定に成功し、恒星の三次元空間での動きが求められるようになった。地球が太陽の周りを回っているように星どうしが回り合う連星は1802年にF・W・ハーシェルが発見しているが、これはのちに連星の周期などを使ってそれぞれの星の質量を求める可能性を開き、1920年にはピースFrancis Gladhelm Pease(1881―1938)が干渉計により恒星の直径を測り、恒星自体の性質も明らかになった。
1908年のリービットによるセファイド(ケフェウス)型変光星の周期‐光度関係の発見は、アンドロメダ銀河が銀河系内の天体ではなく、約200万光年もの距離にある銀河の一つであることを明らかにすることになった。1927年オールトらは銀河系が秒速250キロメートルもの高速で回転していることをみつけ、銀河系内にも多様な天体があることがわかってきた。1925年エディントンは白色矮星という高密度の天体の存在を示し、それが1970年代のX線観測での中性子星、ブラック・ホール発見への足掛りとなった。1939年ごろワイツゼッカーとベーテは太陽の熱源が原子核融合反応によっていることを示し、星の進化のようすも明らかにされた。
1929年ハッブルは銀河の速度―距離関係を求め、宇宙は膨張していることを示し、この発見がビッグ・バン宇宙へと連なった。1963年に最初のものが発見されたクエーサーは光速に近い速さで遠ざかる天体で、宇宙の古い姿を見ていることになる。そして1965年にペンジアスらがみつけた3K放射は、ビッグ・バンの10万年後、宇宙が透明になったころに放射された電磁波の名残(なごり)のものであった。
このように天文学では次々と新しい発見が続いているが、それらはいずれも長年月のデータの積み重ねのうえになされたものである。現在もよりよいデータの蓄積は続いており、それらに基づく次の発見が期待される。
[磯部琇三 2015年5月19日]
『『現代天文学講座』15巻・別巻1巻(1979~1983・恒星社)』▽『広瀬秀雄著『天文学史の試み』(1981・誠文堂新光社)』▽『二見靖彦著『中性子星の世界』(1982・サイエンス社)』▽『P・C・W・デイヴィス著、戸田盛和訳『宇宙はなぜあるのか』(1985・岩波書店)』▽『磯部琇三著『宇宙のしくみ』(1993・日本実業出版社)』
改訂新版 世界大百科事典 「天文学」の意味・わかりやすい解説
天文学 (てんもんがく)
総論
天体現象を対象とした自然科学の一分野であり,最古の時代から発達した学問であった。古代人のもっていた知識は,主としてその実生活の必要と結びついて得られたものであり,天文学もその最初の段階は季節を正し,月のみちかけを知るという暦の問題から始まっている。こうした暦の知識は農業社会においてとくに必要なものであり,天文学の芽ばえは中国,バビロニア,エジプト,インドなどの農業国家において発生した。しかしこれらの古代国家においては,知識人と称するものは帝王を中心とする少数の支配階級であり,支配階級は暦の作製をもって多数の人民を支配する一手段と考えた。〈天文学は帝王の学問〉という古いことばはこうした古代国家において適切なものであった。古代国家に発生した天文学はいずれも低い段階にとどまっていて,たんに現象を記録するか,さらに一歩進んでも現象を簡単な数理によって整理する程度であって,いくつかの現象を結びつけて説明しようとするものではなかった。
ところがギリシア時代になると天動説が起こり,日月および惑星の運動を共通の機構によって数学的に説明しようとした。こうして学問としての天文学が,ここに初めて成立したのである。フランスのH.ポアンカレもいっているように,天文学は自然の中に法則が存在することを最初に教えたものであった。天文学が古くから高い段階の学問として成長したのは,それが民衆の生活に必要な知識を提供したばかりでなく,天体の運動にみられる整然さの中に人々が法則性をつかみとることができたからである。
近世における天文学はコペルニクスの地動説に始まり,ケプラー,ガリレイを経てニュートンに至って大きく進歩した。彼が発見した一般の力学法則および万有引力則に基づいて,18世紀には天体力学が著しく発達した。また17世紀初めに実用化された望遠鏡の使用によって天体観測の方面にも大きな変革が行われた。その後,新しい観測方法の改良とともに,他の関係学科,数学,物理学,化学などの発達に伴って,天文学の新しい分野が開かれていった。比較的古くから発達してきた球面天文学,位置天文学,実地天文学,天体力学などのほかに,統計的方法を適用した統計天文学,物理学を主要な武器とする天体物理学,太陽物理学,さらに電波天文学,X線天文学,赤外線天文学,宇宙論などの発展をみるに至った。
このように天文学自体としては諸種の分野がそれぞれにはなばなしい活躍を行っているが,天文学のもっとも先端的な部門は物理学の応用といえるであろう。したがって古代と比較すると,天文学の研究方法における独自性はいくぶん希薄になっている。しかしこうした傾向は他の諸学科にも認められるところである。同じ自然科学のなかで天文学は比較的非実用的な学問であると考えられがちである。しかし過去における天文学の発達をみると,農業のうえに,航海のために大きな貢献を行ってきた。また今日でも時刻測定の仕事は天文学者の重要な仕事である。さらに純学問的な立場からいえば,天体現象はすべての点で地上で実現しえない巨大な実験室を提供するものであり,こうした実験室から生まれた結果は,やがて他の学問に大きな影響をあたえることができる。
→暦 →天体物理学 →電波天文学
歴史
古代
中国では前14世紀の殷の時代から前5世紀ころまでは,もっぱら暦法を中心にして発達してきた。その初期から〈陰陽暦〉(われわれが〈旧暦〉と呼ぶもの)が使われており,2~3年ごとに挿入される閏(うるう)月は年末におかれ,それを〈13月〉と呼んだことがあった。のちには正しい閏月挿入法が考案され,ギリシアの〈メトンMetōn法〉(前5世紀)と同じく,19年間に7回の閏月を挿入することが,西方諸国よりも早く知られたようである。観測器械としては地面に垂直棒を立ててその影を測る簡単な〈ノーモン〉が用いられ,これによって1年の長さが正確に求められるようになった。また若干の星座をみて季節の推移を知ることもできた。時間の測定には主として水を利用した〈漏刻〉が使用されたが,それがいつの時代に始まるかはわかっていない。古い時代には日食や月食がよく注意されたが,これらは当時の支配者にとって凶兆と考えられたからである。前7世紀のころからは日食の日付を書いた記録があり,またすい星や流星にも注意するようになった。惑星運動に注意するのもこれからまもなくの時代であろう。惑星の中でもっとも光の強い木星は12年で天を1周することが知られ,したがって木星の位置によって〈歳〉をしるすという意味でこれが〈歳星〉とも呼ばれた。木星の位置によって国家や支配者の運命を占うことが行われているのは,西方の占星術の発生とまったく相似ている。こうした惑星や太陽および月などの天体の位置を指示するために〈十二次〉や〈二十八宿〉が考案されたのもほぼ同じ時代であろう。十二次は,バビロニアに始まる黄道十二宮と類似のもので,天体が動く天空を12等分したものである。二十八宿は天空を適宜に28分したものであり,この部分に散在する星座の名で呼ばれた。十二次は1年の月数と関係があり,二十八宿は恒星月の長さと関係がある。後者はインドにおいても早くから知られていた。こうして天体位置の観測が行われるにつれ,位置測定の規準となる恒星の位置にも関心がはらわれたに相違ない。現在〈石氏星経〉の名で呼ばれる星表には,赤道座標による星の位置があたえられており,しかもその位置は前4世紀ころに観測されたと考えられる。しかしこのような観測が行われたとすれば,相当な観測器械が必要であり,同時に日月および惑星に関する研究もかなり数量的になっていたはずであるが,現存の記録だけではこうした随伴的な事実を立証できない。
漢の時代になって,前2世紀の終りに完全な陰陽暦が制定され,それによって民衆の使用する暦が計算されるようになった。同時に惑星の公転周期や簡単な食周期が知られるようになり,これらによって惑星の位置や日・月食の予報が行われるようになった。もちろんこうした予報はきわめて粗雑なものであった。またこのころから〈渾天(こんてん)儀〉と呼ばれる観測器械が記録にあらわれてくる。これと類似なものは同時代のギリシアにおいても使用されており,いくつかの目盛をきざんだ円環を組み合わせ,望筒によって天体をみてその位置を測るのである。中国の暦はたんに日付を配当するだけでなく,日・月食や惑星位置なども書きこんだ。日・月食は著しい天体現象であるから,その予報についてはとくに苦心がはらわれた。そのために前2世紀末以後,多くの天文学者によって多くの暦法が考案され,こうした暦法の変遷がそのまま中国の天文学の発達史である。このほかには若干の宇宙論のようなものもあったが,あまり大きな発達をみなかった。
→中国天文学
バビロニアでは中国に比べて,天体位置についての記録が比較的古くから残っている。こうした観測はもっぱら占星術の必要と結びついたものであった。バビロニアやエジプト,インドなどでは,祭祀を主宰する神官階級が高い位置を占め,同時にそれらは知識階級でもあった。そのために農業に必要な暦法よりもむしろ神秘的な占星術が重要な天文学の領域を占めてきた。このために天体の位置を数量的に観測することは中国よりも早く行われる結果となった。バビロニアの黄道十二宮なども天体位置の測定規準として早く知られたのである。バビロニアの暦法は中国と同じく陰陽暦であり,19年に7回の閏月を挿入することは,ほぼ前6世紀に知られていた。バビロニアに比べて,エジプトの天文学は低い段階にあった。しかし〈太陽暦〉が古くから使用されたことは注目に価する。ナイル川の洪水に先だっておおいぬ座のシリウスが東天に現れた。このシリウスの観測によって1年の長さが知られ,またナイル川の洪水が農業に大きな影響をもったところから,エジプトは早くから〈365日〉をもって1年とする太陽暦が採用され,前1世紀には4年ごとに1日の閏日を挿入する方法が始められ,これがローマのユリウス・カエサルの手でローマの公暦となった。これがユリウス暦であり,1582年までヨーロッパにおいて使用された。
ギリシアの天文学がこうしてバビロニアとエジプトとの天文学を受けついで形成されていった。ギリシア天文学の素材は,この二つの先進国に負うところが多い。しかしギリシア人はまったく新しい精神をもって,ばらばらの素材のなかから学問としての天文学を組織していった。〈天動説〉はギリシア天文学を代表するものである。プラトンの門弟エウドクソス(前4世紀)は初めて数理的天文学を組織しようとした。主として日月および惑星の見かけの運動を説明するために,それぞれに対し3~4個の回転球を組み合わせ,その最内側の球に天体が固定していると考えた。こうしたエウドクソスの説はその後も若干の追随者が出たが,地球からみた天体の大きさの変化を説明することができなかった。前2世紀にはギリシア最大の天文学者ヒッパルコスが現れ,みずからも観測を行うと同時に,円運動の組合せとして天体の運動を説明した。地球を中心とする大円上を等速度で動く小円(周転円)があり,この小円上を太陽が等速度に動くとし,この2円の組合せにより太陽の運動,したがってその位置をかなり正確に予報することができた。彼は太陽および月の運動について大きな成功を収めたが,惑星の問題は未解決のままに残された。そのほか〈歳差〉の発見を行い,〈正弦表〉を作って〈三角法〉の創始者となり,球面上の問題を解くうえに大きな改良を加えた。天動説は地球を宇宙の中心と考えて,そのまわりに動く円運動の組合せによって,天体の運動を求めようとするものである。地球中心説はギリシアの支配的な説ではあるが,しかし〈地動説〉がまったく存在しなかったわけではない。なかでも前3世紀のサモスのアリスタルコスは地球その他の天体が太陽のまわりを動くことを唱えた学者として注目される。ヒッパルコスの天動説をいっそう完全なものとしたのは,2世紀にアレクサンドリアで活躍したプトレマイオスである。彼の著書《アルマゲスト》はギリシア天文学を集成した大著である。ここでは月の運動はヒッパルコス以上に詳細となっており,ヒッパルコスが手をつけずに残した惑星の運動も,一応数学的に求められる。
インドにおける天文学はバビロニアやエジプトと同じように占星術をその主流としている。5世紀の終りころからは,ヒッパルコス時代のギリシア天文学を基礎にして,やや進歩した天文学がみられるようになった。
→インド天文学
中世
西洋の中世前半においては,天文学のうえには見るべき業績はない。この時代に天文学を初め,ギリシアの学問の伝統を保持したのはアラビアを中心として興ったイスラム諸王朝であった。概観するとイスラムの天文学はギリシアの天文書の翻訳に始まり,それの修正を中心として行われた天文観測に著しい特色がある。ギリシア天文学の最高峰に位する《アルマゲスト》の名はもともとアラビア語に由来するのである。ギリシアの学問を保存し,これをヨーロッパに伝えたことは世界学術史におけるイスラムの偉大な功績である。ヨーロッパの文化的不振は10世紀にその底をつき,以後だんだんに上昇していった。最初は現在のスペイン領にあったイスラム王朝から,アラビア語に翻訳されていたギリシア科学書が伝わって,これがラテン語に翻訳された。こうした翻訳事業は12世紀ころから急速に流行するが,さらに15世紀にはビザンティン帝国の滅亡によってギリシア語文献がヨーロッパに伝わった。ヨーロッパの近世は,まずギリシアの学問の水準に到達することから始められなければならなかった。プトレマイオスの《アルマゲスト》がヨーロッパに完全に理解されるようになったのは,やっと15世紀のことである。ドイツ生れのプールバハGeorg Purbach(1423-61)やその門弟レギオモンタヌスは《アルマゲスト》を基礎にして天文表を作製した。
近世
コペルニクスが〈地動説〉を唱えたことは,天文学ばかりでなく一般の学問に大きな変革をもたらし,これまで絶対の真理として考えられていたギリシアの学問に根本的な反省を与えることになった。彼の大著《天球の回転について》は1543年(彼の死の直前)に出版された。彼は,太陽を宇宙の中心におく点ではまったく革新的ではあるが,天体の運動を説明するさいには,やはりプトレマイオスと同じように円運動の組合せを考えており,多くの点で従来の思考方法をそのままに残している。この点では,彼は中世から近世への過渡時代における学者とみるべきであろう。彼は観測家というよりもむしろ思索的な天文学者であった。これに対しデンマークのT.ブラーエは,16世紀最大の観測天文学者であった。この偉大な天文学者が行った火星の観測を整理することによって,ドイツのケプラーは有名な惑星運動の3法則を樹立した。円を完全な図形と考える思想から,ギリシア人は完全なものと考える天体の運動を円運動によって説明しようとした。こういう天動説にはその根底に独断が横たわっていた。しかしケプラーは純粋な観測材料を帰納し,そこから法則をつかみ出すという〈近代科学〉の方法を用い,惑星が太陽を焦点とする楕円を描くということに考え及んだのである。ケプラーと同時代にイタリアではガリレイが活躍していた。彼は落体の研究を行い,力学上の諸問題を解いたが,とくにコペルニクスの地動説を論証し支持したことは著名である。そのためローマ教皇の命で宗教裁判にかけられ,晩年は不遇のうちにすごしたが,学問の使徒としての彼の名は不滅である。そのほか彼は望遠鏡を天文学に使用した最初の1人として有名であり,これによって木星の衛星を発見し,太陽の黒点を発見した。太陽の黒点についてはドイツの天文学者C.シャイナーとの間に発見の前後について論争を生じたこともあった。
ガリレイに続いてイギリスにはニュートンが出た。彼の大著《プリンキピア》は1687年に刊行をみたが,これによって天文学はまったく新しい形をとるようになった。ある天文学史家はニュートン以前を〈幾何学的天文学の時代〉と呼び,ニュートン以後のある時期を〈力学的天文学の時代〉と呼んでいるが,〈二つの物体の間には距離の2乗に逆比例し質量の相乗積に比例する引力がはたらく〉という簡単な万有引力則が,遠く離れた天体の間に成立することが証明され,こうした万有引力則によって天体の運動や形状を論ずる学問が18世紀を通じて流行したのである。18世紀末から19世紀初めにかけてラプラスは5巻からなる《天体力学》を出し,この学問は一応の完成をみることになった。《天体力学》は主として太陽系の力学的諸問題を取り扱った。太陽系の惑星については1801年に小惑星の第1号ケレスがイタリアのG.ピアッツィによって発見され,以後その数は急速に増した。この小惑星の発見に伴って,C.F.ガウスによって〈軌道論〉が開拓された。またイギリスのW.ハーシェルは1781年に新しい大惑星天王星を発見した。その後の観測によって天王星の運動がニュートン力学によって説明しえない不規則さを示したため,さらにその外側に未知の惑星が存在するという予想のもとに,フランスのU.J.ルベリエとイギリスのJ.C.アダムズが万有引力則に基づいて未知惑星の位置を推算した。ルベリエの推算値に従ってドイツの天文学者J.G.ガレが海王星を発見した。これはニュートン力学の勝利を意味するものであったが,しかし万有引力則はけっして十分なものでなく,とくに水星の近日点移動を説明するために,20世紀にはいってA.アインシュタインの〈相対性理論〉が登場することになった。また1930年には惑星冥王星(2006年,定義変更により小惑星に分類された)がアメリカで発見された。小惑星は現在(1983)2880個以上発見され,いずれも火星と木星との間に散在する。ニュートンと同時代のE.ハリーは〈ハリーすい星〉の研究者として著名であるが,同時に星の〈固有運動〉を発見した。彼はまたJ.フラムスティードに次いでグリニジ天文台の第2代台長となった。グリニジ天文台の第3代台長となったJ.B.ブラッドリーは光行差を発見した。
こうして従来の天文学が主として太陽系の星々を対象としていたのに対し,17世紀の終りから天文学者の目はしだいに恒星の世界に向けられるようになった。恒星世界の研究者として最初に大きな業績をあげたのは天王星の発見者W.ハーシェルである。彼は自製の反射望遠鏡を用い,全天の星を数えるという労力をいとわなかった。恒星を全体として考えるとき,その本来的な明るさは同一であり,見かけの光度はもっぱら地球への距離によって大小が生ずると考え,恒星が空間の中にどのように配置されているかを決定しようとした。こうしてわれわれの宇宙は銀河面に沿って比較的扁平な集団であるということが立証された。現在の銀河宇宙は,こうしたW.ハーシェルの見解から発展したものである。銀河宇宙と同じように,太陽系の諸星は同一平面(すなわち黄道面)に近く散在している。この著しい事実から出発しカントは太陽系の生成を論じ,星雲の冷却に伴って惑星が生まれたと考えた。これを,いっそう厳密に論じたのはラプラスであって,ふつうに〈カント=ラプラスの星雲説〉と呼ばれている。W.ハーシェルはまた,太陽系が全体として空間中をヘルクレス座の方向に運動することを発見した。W.ハーシェルが宇宙構造を考えたときには恒星への距離についての正確な知識はなかった。恒星への距離が遠いために三角測量によるふつうの方法はひじょうに困難であったが,19世紀初めにドイツのF.W.ベッセルは精密な観測器械を使用し,はくちょう座61の視差測定に成功し,恒星距離を求める最初の成功を得た。
観測方法の発達
ガリレイが初めて用いた望遠鏡は屈折望遠鏡であったが,W.ハーシェルは大きな反射望遠鏡の作製に成功,多くの天文学上の業績をあげた。19世紀になると優秀なガラスの製造と光学理論の進歩に伴って,屈折望遠鏡にも大きなものが作られるようになった。1850年代には最大38cm口径であった屈折望遠鏡は,19世紀の終りには101cmのものが生まれた。これは現在もアメリカのヤーキス天文台にあるもので,世界最大を誇っている。W.ハーシェル時代の反射鏡は金属を研磨したものであったが,19世紀の半ばにドイツの学者によってガラス製の反射鏡が作られ,製作の容易なために屈折望遠鏡以上に大きなものが作られることになった。20世紀初めにはアメリカのヘールGeorge Ellery Hale(1868-1938)は257cmの反射望遠鏡をもつウィルソン山天文台を建設し,さらに,508cmの反射望遠鏡がパロマー天文台に設置され,現在では200cm以上の大望遠鏡は30基近い数となるに至った。
こうした望遠鏡の発達と並んで写真術が天文学にとり入れられた。その最初の天体写真は1840年ころに撮影され,それ以来写真術は天文観測の主要な武器となったが,現在では光電管や半導体素子の受光器の利用が盛んである。また分光学がとり入れられたのも顕著なできごとであった。19世紀初めにドイツのJ.vonフラウンホーファーは太陽スペクトルの中に数百の暗線を認めたが,やがてこれらの暗線が太陽上層部の特定物質によることが推定されるようになった。こうして分光学の助けによって太陽をはじめとする恒星の物理的性質を研究する道が開けたのであり,1850年代のころから天体物理学の分野が急速に発達するようになった。分光学はまた恒星の運動について新しい知識をあたえた。オーストリアのC.J.ドップラーは〈ドップラー効果〉の発見者として知られているが,この理論によって暗線の〈ずれ〉を観測して,星が観測者から遠ざかるか,あるいは近づくかを知ることができた。すなわち恒星の〈視線速度〉の発見である。現在では回折格子,干渉板,フーリエ分光装置などの分光器を望遠鏡につけて星の分光写真をとることによって,その物理的性質の研究が進められている。太陽面の観測には,1930年にコロナグラフを発明したフランスのB.F.リヨの考案した単色光フィルター,バブコックH.W.Babcockの創案になる磁場測定装置などが改良され,水素のHα線など任意の波長の単色像,磁場や視線方向の速度の分布図が得られる。
また,第2次世界大戦のころより発達した電波技術によって電波天文学の一分野が開かれ,波長,観測対象,用途によって各種の電波望遠鏡が作られた。なかでも,大陸間にまたがる超長基線干渉計(VLBI)では,0.″001程度の角度の分解能を得ることができる。光学望遠鏡による星像は大気のゆらぎのため瞬間ごとの像(スペックル)がおどって写真乾板上ではぼけてうつるが,スペックル干渉法が開発され,他の二,三の方法とともに近い超巨星の大きさを測るのに用いられる。大気の吸収で地上にとどかない波長域の観測や大気のゆらぎの影響をさけるため,気球,ロケットおよび人工衛星を用いる。さらにスペースシャトルを利用してスペース望遠鏡やスペース天文台を運営する時代になりつつある。
執筆者:藪内 清
最近の天文学
宇宙論
膨張宇宙は,遠い銀河ほど遠ざかる速度が比例的に増大するE.ハッブルの関係式が一様等方宇宙に対するアインシュタイン方程式のフリードマン解と一致することにより,観測的にも理論的にも多くの支持を得ていたが,1965年アメリカのペンジアスA.PenziasとウィルソンR.Wilsonとが3Kの宇宙背景放射を発見して,ビッグバンと称する超高温超高密度の宇宙初期の大爆発モデルが確立した感がある。ビッグバンの初期は素粒子の宇宙で,ほぼ等量ある物質,反物質は光速で宇宙が膨張するにつれて重い粒子から対消滅し,余剰が物質として残るが放射優勢の宇宙となる。宇宙膨張は速く,そのため重い元素はできず水素とヘリウムしかできないといってよい。膨張がさらに進んで温度が下がると,それまで電離していた水素が中性となり,放射とよく相互作用する自由電子が減少して物質と放射とが別の温度をとることができるようになる。宇宙は晴れて,その時期に物質を離れた放射が,ほとんど光速度で逃げるわれわれ観測者に達すると,ドップラー効果で赤方偏移して3Kという低温の宇宙背景放射になると考えられる。宇宙のエネルギー密度は断熱的な膨張による冷却のため放射優勢から物質優勢になり,銀河が形成されるようになるのはビッグバン開始以来数千万年ほど後と考えられている。
最近,素粒子論の大統一理論が宇宙論に応用されて,ビッグバン初期にインフレーション宇宙という概念が導入された。これによると,物質と反物質量の非対称性や宇宙黒体放射のきわめてよい等方性などの起源が議論できることになった。
銀河物理学
銀河は銀河団,超銀河団に多く集中し,これらはボイドと呼ばれる銀河の少ない泡と泡の間に網目状に存在している。銀河の形成は集団にしろ単体にしろもとになる宇宙初期の密度ゆらぎが1/100程度以上あって動的に凝縮する必要があるが,そのゆらぎをつくる原因については乱流説,ブラックホール説などあるがまだ定説はない。銀河には楕円銀河,渦巻銀河,棒渦巻銀河,不規則銀河があり,大きさも大小さまざまである。銀河系やアンドロメダ銀河は大きな渦巻銀河で太陽の(1~2)×1011倍ほどの質量といわれているが,暗くて見えない星,ブラックホールあるいはニュートリノといった見えない質量が見える質量の数倍銀河周辺あるいは銀河間空間にあるといわれている。銀河の形態や色は中にある星の進化の状態に関係があり,アンドロメダ銀河のバルジと呼ばれる中央部や楕円銀河の多くは種族Ⅱの進化して赤色巨星になった小質量星の寄与で赤みを帯び,円盤部は若い種族Ⅰの青い星や水素電離領域の影響で青みがかる。しかし,星団中の銀河の食い合い,星間雲からの突発的な恒星形成などがあって,銀河の分類もハッブルの形態分類だけでは不十分である。銀河系中心核は,赤外線,電波などの強い源であるが,セイファート銀河では中心核の活動はもっと激しく,もっとも激しい活動を示すのはクエーサーquasar(恒星状天体)である。クエーサーは稠密(ちゆうみつ)銀河核が中心のブラックホールへ降着円盤を作って物を流入させているものと考えられる。クエーサーは光でも電波でも明るく,波長が赤方偏移で3倍以上になっているような宇宙の遠いところにあるものまで見えるので,宇宙論的にもたいへん重要な天体である。渦巻銀河の腕は恒星形成の場所を示すもので,密度波理論では,原料となる星間ガスが自己励起的な密度波をなすためにできると考える。密度波理論以外にも,連鎖反応的な恒星形成と銀河の差動回転との組合せによって渦巻腕を作るという考えもある。
恒星進化論
渦巻腕の中に大きな星間雲ができ,凝縮が進んで濃い分子雲ができる。分子雲は,COなどの分子や星間塵(ダスト)に富み,10Kくらいの低温で密度も高いので,恒星形成の場をなす。原始星は,エネルギーを放射で外部へ放出して冷却し,やがて自由落下に近い収縮をするが,中心密度が十分高くなると落下をはねかえして主系列前の重力収縮星となる(図の1→2)。恒星は,水素をヘリウムにする一連の原子核反応を豊富なエネルギー源として,寿命の大半を主系列星としてすごす。ただし,太陽の1/20以下の質量の星は陽子-陽子反応を起こせるほど中心温度が上がらず,太陽の100倍以上の質量の星は脈動に対しきわめて不安定ですぐ質量を失ってしまう。主系列星の寿命は質量の2乗以上に逆比例し,太陽以下の暗い低温度矮星(わいせい)は100億年以上の寿命をもつが,明るいO,B型星は1000万年程度で主系列を離れ赤色巨星へと進化する。中心部の水素が消費され,ヘリウム中心核の周辺で殻状で水素を変換するようになると,中心核の密度は急激に増大し,逆に外側は急激に膨張して赤色巨星となる(図の2→3)。太陽程度の小質量のヘリウム核は電子縮退という状態にあって,やがてヘリウム3個から炭素を作る核反応が始まると,ヘリウムフラッシュという大爆発を起こして外包をふき飛ばし,水平分枝へ飛ぶ。さらに,再び赤色超巨星へいくが,質量を放出し,中心の核燃焼は止まって,惑星状星雲期を経て白色矮星に冷却していく(図の4→5)ものと考えられる。大質量星では,密度が低く電子縮退はおくれ,タマネギ状に外から水素殻,ヘリウム殻,炭素殻,酸素・ネオン・マグネシウム殻といった構造となるが,最終的に中心部に不安定性を生じて爆発し,超新星となる。中心部の不安定性は星の質量によって異なるが,高温の鉄が吸熱反応でヘリウムにこわれる反応などでつぶれ,重力エネルギーを大量に放出するタイプなどが考えられている。中性子量を残す場合と残さない場合とある。
元素の起源
水素からヘリウムまではビッグバンの際に形成されたといわれているが,それ以上の質量数の元素は星が作ったものとされる。C,N,O,Neなどは矮星進化に伴って内部に蓄積され,鉄より重い元素は超新星爆発の際に中性子を吸って重元素に成長する過程がおもなものである。しかし,もっとゆっくりした合成過程,高温の熱的な平衡過程などの調整過程も重要である。
恒星の活動
オリオン星雲中に,可視光では見えないが強い赤外線を出しているKL天体,BN天体などの赤外線星がある。このような星はできたての星で,ダストを多量に含んだ厚い包被にとりまかれている。はくちょう座X-1星は,ブラックホールに連星の相手方の星から出た質量が落ち込む過程で,円盤状になって回転する高温のガスからX線を出している系と考えられている。しかし,X線パルサーの大部分は,ブラックホールよりは中性子星が本体をなしており,X線バースターと呼ばれる種類もある。同様な構造でも本体が白色矮星になると,激変量や新星のモデルになると考えられる。銀河中心方向へかなり集中の見られるバルジX線源といわれるものに球状星団中心と一致するものが何個もあり注目される。かに星雲もX線源であるが,とくにその中心星は電波からX線に及ぶパルサーで,周期は0.033秒ときわめて短く,中性子星である。中性子星は太陽質量程度,半径は10kmくらいで,密度はきわめて大で,半径があと1/10くらいになればブラックホールになるほど重力は強大である。ケフェウス座δ星は脈動する変光星として著名であるが,脈動変光星には,ミラ型長周期変光星,たて座δ星型,こと座RR星型,ケフェウス座β星型などいろいろなタイプがある。高温超巨星および赤色超巨星では強い恒星風による質量流出が盛んで,104年以下で質量の半ばを失うような場合もある。広がった恒星風領域は,紫外線,CaのH,K線,COミリ波電波線などで観測される。フレア星は赤色矮星であるが,太陽フレアを大規模にしたような現象が見られる。A型特異星には磁変星があり,数千~数万ガウスに及ぶ磁場がある。
太陽物理学
デービスR.Davisらが太陽からのニュートリノを測り,理論モデルからの予測より何倍も低い測定値を得た。その後,測定の解釈やモデルの検討などでかなり差がちぢまったが,まだ問題を残している。太陽内部の探査には,周期5分程度のところにたくさんある固有振動を解析する陽震学が発達し,有力な手段となっている。黒点,白斑,スピキュール,紅炎,フレア,コロナなどの太陽面活動の根源は磁場であって,太陽磁場は,自転と対流を媒介とする磁場励起のダイナモ作用で作られ,約11年(磁場極性の反転を考慮すると22年)周期で変動する。フレアは磁場に蓄えられたエネルギーがコロナ中でプラズマ機構によって解放されて起こる現象で,電波,X線,水素Hα線などを強く放射するほか,強い太陽風や太陽宇宙線のバーストを起こし,地球にも電波じょう乱やオーロラなどをひき起こす。
太陽系起源論
カント=ラプラスの星雲説,ワイツゼッカーC.F.von Weizsäckerの乱流渦説などは基本的には正しいが具体性に欠けていた。ボエジャーなどによる惑星探査が盛んに行われ,太陽系の起源も実測値に基づいた考察が可能になってきた。原始太陽系星雲は中心に太陽を作ったが残りは周辺に円盤状をなして回転し,その中にダストが形成され,赤道面に沈殿してダスト円盤を作る。ダスト円盤は自己重力作用で分裂し,無数の微惑星を作った。火星より内側は,太陽熱の影響が大きく,ダストは鉄やシリケート(ケイ酸塩)を主成分とし,木星以遠では水やCO2などの氷が多く加わってできたであろう。微惑星は衝突集散して大きいのが雪だるまのようになり,原始惑星を作ったと考えられる。木星,土星などは大量のガス成分をとり込んで大質量となったものである。すい星,流星などは原始の微惑星のなごりをとどめているものと考えられている。
→宇宙 →銀河 →銀河系 →恒星 →太陽系
執筆者:海野 和三郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「天文学」の意味・わかりやすい解説
天文学
てんもんがく
astronomy
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
最新 地学事典 「天文学」の解説
てんもんがく
天文学
astronomy
宇宙にある天体を地球ないし地球近傍から観測することで調べる学問。現在では電波・赤外線・可視光・紫外線・X線・ガンマ線などあらゆる波長の電磁波に加え,重力波・ニュートリノなど他の信号も観測対象である。主として,太陽系外の天体が研究対象である。現代では観測やそのデータ処理に用いる技術開発も含む。人類の置かれた立場を理解するという哲学的意味も重要視されている。
執筆者:半田 利弘
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
百科事典マイペディア 「天文学」の意味・わかりやすい解説
天文学【てんもんがく】
→関連項目占星術
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の天文学の言及
【宇宙】より
…
【コスモスの発想】
カオスに対して,この世界を秩序正しい構成をもつものとしてとらえ,それをカオスなる原初形態から何らかの原理に基づいて編成されたとする考え方は,すでにヘシオドスにもあって,一種の宇宙開闢(かいびやく)説として,エロスを中心とする神話の世界もそこに重なるが,コスモスという語を意図的に用いて,宇宙全体の秩序ある様態を表現しようとしたのはピタゴラスが最初であるといわれる。 もちろん,このような考え方の背景には,バビロニアに発する天文学的な知識の伝承があり,天体の運行,季節変化など天象,気象に見られる秩序正しさへの認識が必須であったには違いないが,ピタゴラス,もしくは彼によって代表される当時のギリシアの一つの典型的な世界観,すなわち〈すべては数である〉という表現が象徴するような世界観を前提としていたことを見のがすべきではない。この世界観には,数の神秘的象徴主義から具体的な算術や幾何学に至るさまざまな要素が包摂されており,そこには弦や管の整数比分割が協和音を生み出すという音楽上の調和(ハーモニー)の問題も含まれていた。…
※「天文学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...