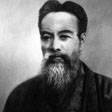精選版 日本国語大辞典 「山岡鉄舟」の意味・読み・例文・類語
やまおか‐てっしゅう【山岡鉄舟】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「山岡鉄舟」の意味・わかりやすい解説
山岡鉄舟
やまおかてっしゅう
(1836―1888)
幕末・明治前期の剣客、政治家。名は高歩(たかゆき)、通称鉄太郎、鉄舟は号。天保(てんぽう)7年6月10日旗本小野朝右衛門の長男として生まれ、1855年(安政2)槍(やり)の師である山岡家を継いだ。また千葉周作に剣を学び、のち無刀流を案出し春風館を開き門弟を教えた。1856年講武所剣術世話役。1862年(文久2)幕府が募集した浪士隊の取締役となる。1868年(慶応4)3月戊辰戦争(ぼしんせんそう)の際、勝海舟(かつかいしゅう)の使者として駿府(すんぷ)に行き、西郷隆盛(さいごうたかもり)と会見して、江戸開城についての勝・西郷会談の道を開いた。1869年(明治2)9月静岡藩権大参事(ごんだいさんじ)、1871年茨城県参事を経て、1872年6月侍従に就任。ついで宮内少丞(しょうじょう)・大丞と進み、1881年宮内少輔(しょうゆう)となった。子爵。書は一楽斎と号して有名である。勝海舟、高橋泥舟(たかはしでいしゅう)とともに幕末三舟と称せられる。明治21年7月19日没。墓は東京谷中の全生庵(ぜんしょうあん)にある。
[佐々木克]
『小島英熙著『山岡鉄舟』(2002・日本経済新聞出版社)』▽『大森曹玄著『山岡鉄舟』新版(2008・春秋社)』
改訂新版 世界大百科事典 「山岡鉄舟」の意味・わかりやすい解説
山岡鉄舟 (やまおかてっしゅう)
生没年:1836-88(天保7-明治21)
幕臣でその後明治天皇の侍従。一刀正伝無刀流剣術の開祖(無刀流)。旧姓小野,諱(いみな)は高歩(たかゆき),通称は鉄太郎,鉄舟は号。江戸本所大河端に生まれる。父は600石の旗本小野朝右衛門。10歳のとき飛驒の郡代となった父とともに飛驒高山に行き,17歳までそこで過ごした。その間,儒学,書,剣を学び成長した。若くして両親をなくした鉄舟は,苦労しながら幼弟5人を養育し,1855年(安政2)20歳で槍術の師山岡静山の家名を継ぐことになり,静山の妹英子(ふさこ)と結婚した。その後,講武所で剣術を学んだり,清川八郎らと浪士団を引率して上洛するなど,激動の時代のなかで活躍した。一方,禅の修行も積み,剣禅一致の境に達し,1880年剣の師浅利又七郎から一刀流の印可をうけ,一刀正伝無刀流をたてた。清純,誠実の人物で,明治維新のときには単身官軍の営所に乗り込み,西郷隆盛と会見して勝海舟との会談を周旋し,江戸を戦火から救った(江戸開城)。1869年(明治2)新政府に出仕し,静岡県権大参事,茨城県参事,伊万里県知事を歴任,また明治天皇に侍従として仕え,信任が厚かった。
執筆者:中林 信二
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
新訂 政治家人名事典 明治~昭和 「山岡鉄舟」の解説
山岡 鉄舟
ヤマオカ テッシュウ
- 肩書
- 明治天皇侍従,無刀流創始者
- 旧名・旧姓
- 旧姓=小野
- 別名
- 諱=高歩(タカユキ) 通称=鉄太郎
- 生年月日
- 天保7年(1836年)
- 出生地
- 江戸・本所大河端
- 経歴
- 幕臣小野朝右衛門の長男に生まれるが、早くに両親を失くし、弟妹養育の傍ら儒学や書を学ぶ。安政2年(1855年)槍の師である山岡家を継ぐ。禅の修業も積み、一刀流の印可を受ける。千葉周作にも師事し、一刀正伝無刀流道場・春風館を開設、多くの門下を育てた。のち幕府講武所剣術心得を経て、文久2年(1862)浪士取締役として治安につとめる。慶応4年(1868)勝海舟の使者として駿府に赴き、西郷・勝会談を周旋して江戸無血開城への道を開いた。維新後、静岡県権大参事、茨城県参事、伊万里県知事を歴任し、明治5年明治天皇の侍従となった。幕末の三舟の一人。
- 没年月日
- 明治21年7月
- 家族
- 父=小野 朝右衛門(旗本・飛弾郡代)
出典 日外アソシエーツ「新訂 政治家人名事典 明治~昭和」(2003年刊)新訂 政治家人名事典 明治~昭和について 情報
百科事典マイペディア 「山岡鉄舟」の意味・わかりやすい解説
山岡鉄舟【やまおかてっしゅう】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「山岡鉄舟」の解説
山岡鉄舟 やまおか-てっしゅう
天保(てんぽう)7年6月10日生まれ。山岡静山の妹と結婚,静山の跡をつぐ。剣を千葉周作の門にまなび,幕府講武所でおしえる。戊辰(ぼしん)戦争では勝海舟の使者として西郷隆盛にあい,江戸開城のための勝-西郷会談の道をひらく。維新後は静岡藩権大参事,茨城県参事,明治天皇の侍従などを歴任。明治13年一刀正伝無刀流をたてる。海舟,高橋泥舟とともに幕末三舟と称された。明治21年7月19日死去。53歳。江戸出身。本姓は小野。名は高歩(たかゆき)。字(あざな)は曠野,猛虎。通称は鉄太郎。別号に一楽斎。
【格言など】臨機応変の妙用は,無念無想の底より来る(西郷隆盛との会見についての述懐)
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「山岡鉄舟」の意味・わかりやすい解説
山岡鉄舟
やまおかてっしゅう
[没]1888.7.19. 東京
江戸時代末期の幕臣。通称は鉄太郎。刀槍に長じ,無刀流を編出して春風館道場を設立。講武所剣術世話役,浪士取締役をつとめた。慶応4 (1868) 年3月江戸開城に際しては,勝安房 (海舟) の使者として駿府の大総督府におもむき,東征軍参謀西郷隆盛と会見,徳川家存続に尽力した。明治2 (69) 年静岡県権大参事として旧幕臣の処遇斡旋に努め,次いで茨城県参事,伊万里県知事を歴任。のち明治天皇の侍従,宮内少輔。 1886年子爵,勲二等に叙せられた。禅機に達した人生観は剣の名声と相まって,剛毅武人型の模範として後世に名高い。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「山岡鉄舟」の解説
山岡鉄舟
やまおかてっしゅう
1836.6.10~88.7.19
幕末期の幕臣・剣術家,明治初期の侍従。諱は高歩(たかゆき)。飛騨郡代小野朝右衛門高福の子。山岡静山の婿養子。千葉周作に入門し,幕府講武所で剣術世話役となる。1863年(文久3)幕府の浪士募集に際し取締役。68年(明治元)精鋭隊歩兵頭格,大目付を兼ねる。東征軍の東下に対し,駿府で西郷隆盛らと会見,勝海舟と協力して江戸無血開城を実現させた。維新後静岡県ほかで参事・県令を勤めたのち,72年天皇側近となり,82年宮内少輔を辞任。無刀流の創始者。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「山岡鉄舟」の解説
山岡鉄舟
やまおかてっしゅう
幕末・明治初期の政治家
通称鉄太郎。幕臣。千葉周作門下の剣道の達人で無刀流を創始。戊辰 (ぼしん) 戦争で徳川慶喜 (よしのぶ) 東帰後,勝海舟と協力,静岡で西郷隆盛と会見し,江戸無血開城に奔走した。明治新政府では県知事などを歴任し,明治天皇の侍従となり,子爵を授けられた。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の山岡鉄舟の言及
【三遊亭円朝】より
…また,モーパッサンの《親殺し》を翻案した《名人長二》,同じくサルドゥーの《トスカ》を翻案した《錦の舞衣(まいぎぬ)》なども手がけた。中年以降は山岡鉄舟のもとで禅に傾倒し,その話芸は迫真軽妙の極に達して朝野の名士に愛され,落語家の社会的地位を向上させた。門下には円喬,円右,円左,小円朝,円馬,円遊などの名手がそろい,明治の落語黄金時代を成した。…
【無刀流】より
…正式には一刀正伝無刀流。開祖は明治維新に活躍した山岡鉄舟。鉄舟は一刀流を学ぶかたわら,禅や書に通じ,1880年悟るところがあり無刀流を立てた。…
※「山岡鉄舟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...