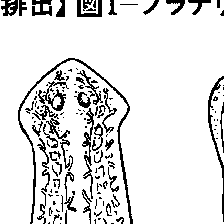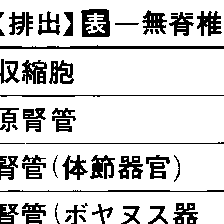翻訳|excretion
精選版 日本国語大辞典 「排出」の意味・読み・例文・類語
はい‐しゅつ【排出】
- 〘 名詞 〙
- ① 外におし出すこと。
- [初出の実例]「其中の水を排出して大気を送入するも」(出典:気海観瀾広義(1851‐58)七)
- ② 生物体が物質代謝の結果体内に生じた不用産物または有害物質を、体外または代謝系外に排除すること。排出機構は動物では特定な器官(腎臓・汗腺など)が発達しているが植物ではあまり発達していない。排泄。〔医語類聚(1872)〕
改訂新版 世界大百科事典 「排出」の意味・わかりやすい解説
排出 (はいしゅつ)
excretion
動物の体内で物質代謝の結果生じた不用物質,すなわち老廃物や有害な物質を体外に出すこと。排泄(はいせつ)ともいう。食物中に含まれる栄養素のうち炭水化物と脂肪は体内で完全に酸化すると水と二酸化炭素になる。タンパク質と核酸は分解すると水と二酸化炭素のほかに,窒素を含む最終代謝生成物,いわゆる窒素老廃物を生じる。呼吸によって体外に出される二酸化炭素は別として,窒素老廃物は種々の無機塩類イオンなどとともに水溶液の形の尿として,排出器官を通じて体外に出される。この過程が排出である。脊椎動物には排出器官として発達した腎臓があるが,無脊椎動物にも系統群によってそれぞれ特有の排出器官があり,排出器官では,原理的にはろ過,再吸収,分泌の三つの過程を経て尿が作られる。脊椎動物の腎臓を例にとると,まず第1段階として腎小体(マルピーギ小体)で,小動脈よりなる糸球体からそれを包むボーマン囊へ体液がろ過されるが,これは小動脈内血圧と外側の圧の差によって起こる限外ろ過であって,血球と大部分のタンパク質を除く血液成分がこし出される。つぎにこのろ液(原尿)が細尿管内を流れるあいだに,水,ブドウ糖,無機塩類などの必要な物質は再吸収されて血液中にもどり,余分な物質やろ過が不十分であった物質は,血液中から細尿管内に分泌され,最終的に尿ができる。再吸収と分泌の過程では,濃度こう配に逆らって濃度の低い側から高い側へ物質が輸送されることもある(能動輸送)。その結果,物質の種類によって血中濃度にたいする尿中濃度の比(U/P比)に大きな差を生じる。たとえばヒトではこの比はブドウ糖0,尿素70,クレアチニン50,ナトリウム1,カリウム8,リン酸17である。再吸収や分泌は脳下垂体後葉から出るバソプレシン,副腎皮質のコルチコイドなどのホルモンで制御されており,血液組成の恒常性の維持に重要な役割を演じている。
脊椎動物のなかでも魚類と両生類は,血液と等しいかあるいはそれより低い濃度の尿を出しているが,鳥類や哺乳類など陸生のものは血液よりはるかに濃い尿を排出する。尿の濃度と量はその動物が摂取する水の量と深い関係がある。水の乏しい乾燥した環境に住む動物は濃い尿を出す。すなわち腎臓の濃縮能力が高い。たとえばヒトでは尿の濃度が血液の約4倍,ビーバーでは2倍であるのにたいして,砂漠にすむネズミ類では15~25倍である。脊椎動物の血液の濃度は海水よりはるかに低いから,海にすむ動物は絶えず脱水の危険にさらされている。これらの動物では,水を補うために飲む海水や餌とともに摂取される多量の塩類は,腎臓以外の経路でも排出される。たとえば海産硬骨魚類ではえらにある塩類細胞から,また海産爬虫類と鳥類では眼窩(がんか)や鼻腔にある塩腺から塩化ナトリウムNaClが体外に分泌される。
尿中に出される窒素老廃物はアンモニア,尿素,尿酸などであるが,動物がこのうちどれをおもに排出するかは,その動物がすんでいる環境,とくに水の利用状態と密接な関係がある。タンパク質が分解してできたアミノ酸の脱アミノ反応によってアンモニアができるが,これは毒性が強いため速やかに体外に出さなければならない。水生の無脊椎動物や硬骨魚類は水に溶けやすいアンモニアを直接周囲の水に流し出すことができる(アンモニア排出動物)。アンモニアは腎臓以外からも出されることがある。たとえばコイやキンギョでは腎臓から排出される窒素の6~10倍量をえらから排出している。しかし十分に水を利用できない陸生動物では,毒性の低い尿素や尿酸にかえて排出する。両生類と哺乳類は尿素排出動物であって,尿素は肝臓で尿素回路(オルニチン回路)という代謝経路によってアンモニアと二酸化炭素から合成される。尿素は毒性は低いが水によく溶けるから,体内に高濃度に存在すると大きい浸透圧を生じ,そのために細胞が脱水されるおそれがある。とくに排出機能の発達していない胚の発生過程ではこの関係は重要である。哺乳類のような胎生動物では,胎児の老廃物は母親の腎臓を通じて排出されるが,それ以外の陸生動物,すなわち昆虫類,巻貝類,爬虫類,鳥類の卵は乾燥に備えて堅い殻をもち,胚発生中の老廃物は孵化(ふか)まで卵の中にたまったままである。これらの動物では窒素老廃物は水に難溶性の尿酸として排出される(尿酸排出動物)。
→腎臓 →尿
執筆者:佃 弘子
排出器官excretory organ
無脊椎動物の排出器官は収縮胞,原腎管,腎管の三つに大別され,その形態や構造はさまざまである(表)。排出器官は本来,代謝の結果生じた老廃物を排出するための器官であるが,それに伴う種々な働き,例えば浸透圧調節や体液中の各種のイオン濃度の調節などにも関係し,環形動物では生殖細胞の体外への放出にも利用されている。腔腸動物と棘皮(きよくひ)動物にはとくに排出器官と呼べるものはないし,他の動物でも排出器官があっても体表やえらから老廃物を排出している場合も多い。
収縮胞contractileは細胞器官の一つで,淡水産の原生動物でよく発達し,体内に浸入した水の排出に関係している。アメーバの収縮胞はふくろ状であるが,ゾウリムシの収縮胞は中央のふくろの周囲に放射状の導管を5~6本そなえている。周囲の細胞質から水分が集まり導管が膨大し,次いで中央のふくろが膨大して,ある大きさに達すると体外に内液を放出する。この働きが周期的にくり返されて細胞内の浸透圧が一定に保たれている。
典型的な原腎管protonephridiumは扁形動物のプラナリアに見られ,体の両側にある主管から複雑に網目状に分枝して,その先端に炎細胞がある(図1)。排出口は1対で体の中央両側に開く。炎細胞は鞭毛の束のあることから名づけられたが,鞭毛の束のある管腔はひだ状の薄い膜で構成され,代謝産物は周囲の組織からこの膜をとおしたろ過によって管腔に入る。淡水産の動物では原腎管の発達は著しい。
腎管nephridiumは環形動物,軟体動物,節足動物などに存在する排出器官で,動物によってその形態がひじょうに異なっている。環形動物の腎管は各体節に1対存在するところから体節器官と呼ばれる(図2)。先端は漏斗状に広がり繊毛をそなえ,一つ前方の体節体腔内に開口している。漏斗部から入った体腔液の成分のうち電解質などは,腎管上皮細胞で再吸収され薄い尿が排出される。陸生のある種のミミズ(貧毛類)では,全部の腎管が集合して共通の輸管を作り消化管に開口して,そこで水が再吸収されるので乾燥した環境にも適応できる。広い塩分濃度に適応できるゴカイ(多毛類)では複雑に曲がった長い腎管が発達しているほか,多くの種では腎管の先端は閉じ,原腎管の炎細胞に似た有管細胞をもつものが多い。
軟体動物のうち,二枚貝や巻貝では,ボヤヌス器Bojanus'organと呼ばれているのが腎管で,囲心腔に漏斗で開口し外部へは外套(がいとう)腔に開口する。イカ,タコの類では1~2対の腎囊をもち,やはり囲心腔と連絡している。
節足動物の甲殻類では1対の触角腺が排出器官で,第2触角の基部に開口する。触角腺は体腔囊・迷路・腎導管・膀胱からなり,淡水産の種では腎導管が長く,体液の浸透圧調節に関与して,体液より薄い尿を排出できる。クモ類は脚基腺が腎管由来の排出器官であるが,マルピーギ管をももつ。昆虫類には腎管由来の排出器官はなく,マルピーギ管が排出機能を営む。
原索動物に属するナメクジウオには咽頭部背側に体節的に腎管があり,その一端は囲鰓腔(いさいこう)に開口する。それぞれの腎管の先端には多毛類と同じ有管細胞があって,血管壁に接する。有管細胞の円筒部は10本の棒と膜で構成され,炎細胞の管腔部に似た構造で,老廃物はろ過により管腔に入り尿が生成される。このように無脊椎動物の排出器官でも多くのものが,脊椎動物と同様にろ過と再吸収といった過程で尿を生成しているのは興味のあることである。脊椎動物に共通の排出器官は腎管に由来する腎臓であるが,その構造と機能について詳しくは〈腎臓〉の項目を参照されたい。
執筆者:小川 瑞穂
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「排出」の意味・わかりやすい解説
排出
はいしゅつ
生体が物質代謝の結果生じた老廃物を体外に排除することで、排泄(はいせつ)ともいう。老廃物としては、動物では普通、含窒素老廃物のほか、塩分、水がある。したがって排出は同時に浸透調節という重要な役割を果たすことにもなる。呼吸の結果生じる二酸化炭素や、食物のかすであって物質代謝の産物ではない糞(ふん)は老廃物には含まない。含窒素老廃物の成分は動物の種類によって異なる。硬骨魚類ではその主成分はアンモニア、爬虫(はちゅう)類のヘビ・トカゲ類や鳥類では尿酸、両生類や哺乳(ほにゅう)類では尿素である。植物では物質代謝の結果生じた分解物を多くはそのまま体内に蓄える。葉、葉柄、茎などにみられる樹脂、タンニン、シュウ酸カルシウム、炭酸カルシウムなどがこれで、植物の老廃物といわれることもあるが、むしろ有意義な場合が多い。
[内堀雅行]
排出器官
排出を行うための器官として排出器官があるが、この器官は一般に浸透調節の主要器官も兼ねる。植物にはとくにないが、動物では種類によってさまざまな形態のものがある。普通、原生・海綿・腔腸(こうちょう)動物は排出器官をもたないが(淡水原生動物では収縮胞が排出作用をすると考えられている)、扁形(へんけい)・紐形(ひもがた)・輪形動物には原腎管(じんかん)というものがあり、その起部には繊毛束をもった炎(ほのお)細胞がある。環形動物にみられるのは各体節ごとに対(つい)をなして存在する腎管(体節器)で、体腔に開く腎口とそれに続く屈曲した細管よりなる。腎管の変形したものに軟体動物の腎嚢(じんのう)(二枚貝のものはとくにボヤヌス器という)や節足動物の甲殻類の触角腺(せん)がある。昆虫類や多足類にはマルピーギ管とよばれる盲管の排出器官があり、腸に開口する。脊椎(せきつい)動物は腎管の発達した腎臓を有する。たとえば哺乳類の腎臓は糸球体と糸球体嚢(ボーマン嚢)よりなる腎小体(マルピーギ小体)、それに続く尿細管やその集合管、腎盂(じんう)などからできている。脊椎動物の腎臓には個体発生上および系統発生上、前腎、中腎、後腎の区別がある。
[内堀雅行]
百科事典マイペディア 「排出」の意味・わかりやすい解説
排出【はいしゅつ】
→関連項目消化
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...