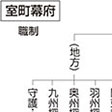精選版 日本国語大辞典 「将軍」の意味・読み・例文・類語
しょう‐ぐんシャウ‥【将軍】
- 〘 名詞 〙 ( 古く「しょうくん」とも )
- ① 一軍を統率し指揮する職。また、その職分の人。一軍の長。大将。将。
- ② 一軍を統率し指揮して出征する臨時の職。また、その職分の人。出征する方面によって、鎮東将軍、征夷将軍、征西将軍などと呼ばれた。
- [初出の実例]「忠文がみちのくにの将軍になりてくだりける時」(出典:大和物語(947‐957頃)六九)
- ③ 征夷大将軍の略。建久三年(一一九二)源頼朝が征夷大将軍に任ぜられてから、征夷の事実の有無にかかわらず、幕府の頭首が代々この職に就任する例となった。
- [初出の実例]「恩賞しきりに隴山の跡をつぎて将軍の召しを得たり」(出典:東関紀行(1242頃)鎌倉遊覧)
- ④ 一般に、将官、特に大将を敬っていう語。〔日誌字解(1869)〕
改訂新版 世界大百科事典 「将軍」の意味・わかりやすい解説
将軍 (しょうぐん)
日本古代においては天皇の命を受け,軍隊を統率して蝦夷(えみし),隼人(はやと)等を討ち,また海を渡って朝鮮半島に戦った軍人の称。《日本書紀》に崇神天皇が四方を征服せしめるために4人を将軍に任じたことが見え(四道将軍),また雄略天皇が紀小弓(きのおゆみ)ら4卿を将軍に任じ,欽明・推古朝に外征の大将軍,副将軍の任命されたことが散見するが,これらは後世の称号をもって追記したもので,当時はただイクサノキミとのみ言い,将軍の号はなかったものと思われる。ただ,《日本書紀》に将軍の肩書を持つ氏族を見ると,大伴・物部はもちろんのこと,蘇我・河辺・境部のいわゆる蘇我一族,それらとともに武内宿禰の裔と称する紀・角・巨勢・葛城・平群・波多の諸氏が目だち,そのほか上毛野・阿倍・吉備などの雄族,そして海人(あま)族である阿曇氏などが挙げられる。これらの氏々は,たとえ将軍の号を帯びたことはなくとも,古代における有力軍事氏族であったことは疑いのないところである。
701年(大宝1)の大宝律令制定に至って,軍事制度も軍防令に明記された。それによって将軍の制を見ると,まず征討を要することあれば兵を整え,その統領として将軍以下の指揮官を任命した。動員1万人以上ならば将軍1人,副将軍2人,軍監2人,軍曹(ぐんそう)4人,録事(ろくじ)4人,5000人以上ならば副将軍,軍監各1人,録事2人を減じ,3000人以上ならば,さらに軍曹2人を減じた。兵員に多少はあっても,以上を各1軍とし,3軍を統べるために大将軍1人が任命された。大将軍が出征するときには天皇から節刀(せつとう)が授けられるが,これは全権を委任したしるしであるから,実戦に際し命に従わないものは大将軍の裁量によって処断し,帰還の日に太政官に上申すればよいとされた。《続日本紀》によって奈良時代の実例を見ると,大将軍,将軍,副将軍には征討に直接関係のない場合も少なくない。また征夷将軍,征東将軍,征夷大将軍,征東大将軍,征狄(せいてき)将軍,征越後蝦夷将軍,陸奥鎮東将軍,陸奥鎮守将軍,鎮狄将軍,征西将軍,征隼人持節大将軍,鎮西将軍など,各種の将軍の任命されたことも知られる。さらに,将軍号こそないが,征夷大使,征東使,征東大使なども事実上の将軍,大将軍であった。これらの将軍は鎮守府,鎮西府のそれを除けばおおむね臨時の官であり,征討を終え凱旋すれば天皇に節刀を返上して自動的にその任を解かれた。なお以上のほかに,左将軍,右将軍,前騎兵大将軍,後騎兵大将軍,検校兵庫(けんぎようひようご)将軍など,征討のときではなく平時に置かれたものもあるなど,将軍の名称・種類は多かったが,要するに1軍の統領たる武官の称であった。
これら将軍のうち蝦夷征討に当たるものは奈良時代を経て平安時代に至り,諸将軍中最も重視された。光仁・桓武朝に征夷事業が再び活発化すると,791年(延暦10)大伴弟麻呂(おとまろ)を征東大使,坂上田村麻呂らを副使に任じたが,2年後に征夷大使・副使と改め,さらに翌年正月までには征夷大将軍,副将軍と改称した。後世の武門の棟梁の代名詞たる征夷大将軍の号はこの大伴弟麻呂に始まる。弟麻呂の後をうけて797年副将軍坂上田村麻呂が大将軍に昇格し,彼の後811年(弘仁2)文室綿麻呂(ふんやのわたまろ)が征夷大将軍となった。その後征夷の事業は一応終結し,鎮守府にゆだねて蝦夷を治めしめることとなり,以後征夷大将軍任命のことはなくなった。しかし平安時代末の1184年(元暦1)に至り,木曾義仲を征夷大将軍に任ずるに及んで370年ぶりにこれが復活した。ただ征蝦夷のこととは無関係であり,義仲が兵馬の権を掌握せんと意図した結果であったから,ここにおいて征夷大将軍の意義は一変した。やがて義仲は敗死するが,その後源頼朝は全国を平定し鎌倉に武家政権を樹立し,義仲に倣って征夷大将軍たらんことを朝廷に奏請し,後白河法皇没後ようやくこれを認められた。以来兵馬の権を握る者は皆この職に就いて天下に号令することとなり,征夷大将軍は武家最高の官職となった。このため鎮守府将軍任命のことも廃絶し,以後は将軍といえば征夷大将軍を指すこととなった。将軍職は鎌倉時代に源氏3代・摂家2代・皇族4代,室町時代に足利氏15代,江戸時代に徳川氏15代,計約700年継承されたが,1867年(慶応3)徳川慶喜が政権を天皇に返上し将軍職を辞することとなって消滅した。
→征夷大将軍
執筆者:黛 弘道
将軍 (しょうぐん)
jiàng jūn
中国の武官名。春秋時代ころより〈軍を将(ひき)いる〉意味から発生した名。戦に勝つためには強い権限が必要なので,任命に当たって王や皇帝は宗廟などで特別な儀式をし,賞罰二権をゆだねる意味で斧鉞(ふえつ)を授けた。そのため将軍は一度軍陣に臨めば王命すら聞かないことを認められた。漢代ではこのような権限を持つ官職は常置の官ではないとの建前をとり,必要に応じて任命し,前・後・左・右将軍のほか最上級の大将軍,車騎将軍,皇帝をまもる衛将軍などがあったが,武帝の対匈奴戦で霍去病(かくきよへい)が驃騎将軍として大将軍衛青とその功が並んだため驃騎将軍は大将軍と格を同じくする将軍号となり,さまざまな美称をつけた列将軍を指揮するようになった。霍光が大将軍として昭帝を補佐した例が,その後外戚の長が将軍として尚書のことにもあずかる風を開き,外戚の権力構造の基本となった。
後漢末の争乱期には再び多くの将軍号が生まれ,それらの将軍を指揮する上級の将軍には節が与えられてその権限を行使した。やがて将軍の格により,使持節,持節,仮節の3種に分かれ,権限に差をつけた。通常の将軍号はしだいに増加し,南朝梁の武帝にいたって125の将軍号を定めこれを24班に分類整理したので,従来の将軍号は明らかに格付けされ,唐代の武散官につながる。唐では左・右衛以下各衛の指揮官たる大将軍,将軍など実職の将軍号とは別に従一品驃騎大将軍以下,従五品下遊撃将軍までの武散官の将軍号があった。武散官の散官とは実職を伴わない位階のみを表す官称をいう。宋代には武散官の将軍号だけが残り,神宗時代(1068-85)にはそれも消滅したが,元代には武散官将軍号が復活して明・清に続いた。実職の将軍号は明代では総兵官に将軍号を加え,その下に副将,参将,遊撃将軍などの階級があり,清代には総兵の将軍号は消滅し,ただ漢人の緑営に副将以下が存続した。また駐防八旗兵を率いる将軍が置かれたほか,臨時に大将軍が任命されることがあった。なお漢では将軍の府を莫(幕)府とよび,この伝統が日本にも伝わった。
執筆者:大庭 脩
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
デジタル大辞泉プラス 「将軍」の解説
将軍
百科事典マイペディア 「将軍」の意味・わかりやすい解説
将軍【しょうぐん】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「将軍」の意味・わかりやすい解説
将軍
しょうぐん
旺文社日本史事典 三訂版 「将軍」の解説
将軍
しょうぐん
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「将軍」の意味・わかりやすい解説
将軍[古代ギリシア]
しょうぐん[こだいギリシア]
「ストラテゴス」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の将軍の言及
【江戸時代】より
…安土桃山時代に続く時代。徳川家康が征夷大将軍になった1603年(慶長8)から,15代将軍徳川慶喜が大政を奉還して将軍を辞した1867年(慶応3)までの265年間を指す。この間,権力の中枢である幕府が江戸に置かれたのでこの呼称があるが,徳川氏が権力を握っていたので徳川時代ともいう。…
【江戸幕府】より
…徳川家康が1603年(慶長8)2月12日征夷大将軍に任命されて江戸に開いた幕府。以後,1867年(慶応3)10月15日15代将軍徳川慶喜の大政奉還までの265年の間,対内的には全国を統治し,対外的には日本を代表する政府として機能した。…
【官位】より
…その叙任の方法は,4代家綱時代まではまず朝廷に奏上しその後に幕府が叙任する例であったが,5代綱吉時代以後は幕府が叙任しその後に朝廷の位記口宣を申請するというものであった。将軍および世子以下の官位昇進の次第は3代家光時代にその例規が定まり,将軍宣下とともに正二位内大臣となり,のち従一位左大臣に進み,正一位太政大臣を追贈され,世子は従二位権大納言となり右大将を兼ねるのを例とした。御三家,万石以上の大名の官位もその地位の高下,家格によって定まっていて,尾張・紀伊両家の従二位権大納言,水戸家,御三卿の従三位権中納言,加賀前田家の従三位参議を最高とし,以下従五位下まで数等に分かれ,城主格以上の大名は従五位下の国守に叙任されるのを例とした。…
【公方】より
…平安中期の《源氏物語》《枕草子》などにみられる〈おおやけかた〉と同義で,1181年(養和1)8月の後白河院庁公文所問注記集(《東大寺文書》)に〈公方済物〉,1256年(康元1)8月の感神院政所下文案(《八坂神社文書》)に〈公方に訴え申す〉などとあるように,〈私〉の対語として公家,朝廷の方面をさす語であった。この用法は中世を通じても見られるが,鎌倉中期の1283年(弘安6)将軍家御教書(みぎようしよ)を〈公方御教書〉といったのを早い例として,将軍をさす言葉として用いられるようになった。これは北条氏の幕府内部での勢力が強大になり,得宗およびその御内人(みうちびと)と御家人との摩擦が強まる過程で,得宗や〈御内〉と将軍とを区別する意図で,多少とも意識的に使われた形跡があり,おそらく安達泰盛の関与があったものと推定される。…
【大君】より
…江戸幕府が外交文書において将軍を表す語として用いた〈日本国大君〉の略称。3代将軍徳川家光のとき,朝鮮との国交修復に際し対馬藩主の宗氏が将軍の号を〈日本国王〉と改作した事件が起き,これを機に幕府は朝鮮に対し1636年(寛永13)来日の朝鮮通信使から〈日本国大君〉の称号を使用させた。…
【幕藩体制】より
…江戸時代の,将軍を頂点とした封建的政治体制をいう。
[規定と特質]
幕藩体制は,兵農分離制を階級支配の原則とした純粋封建体制の一形態であって,石高制(こくだかせい)を土地所有体系の基本とした封建領主が,士・農工商・賤民の政治的編成を基本とした経済外強制によって民衆支配を行い,その支配体制の総体を鎖国制という民族的枠組みによって維持,固定している政治体制である。…
【琉球使節】より
…江戸時代に琉球国王が襲封,将軍の代替りに際し,江戸に派遣した使節。1634年(寛永11)薩摩島津氏が琉球国王に徳川将軍の代替りを祝う慶賀使を派遣させたのに始まる。…
【兵法】より
…しかしまた戦争は避けることのできないもので,ときとして断固とした決戦が必要である。この場合,開戦前に政治的・経済的・自然的条件について彼我の状況をよく知り,味方を不敗の態勢におくことが大切であるが,特に国内の人心の和合と将軍の徳性が考慮される。将軍が任命されたからには君主でさえもはやみだりに口をはさむことは許されない。…
※「将軍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...