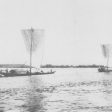精選版 日本国語大辞典 「米代川」の意味・読み・例文・類語
よねしろ‐がわ‥がは【米代川】
日本歴史地名大系 「米代川」の解説
米代川
よねしろがわ
- 秋田県:総論
- 米代川
奥羽山脈の岩手県
鹿角盆地では
上流では岩手県境の 后坂
后坂
米代川は河口の地名から
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「米代川」の意味・わかりやすい解説
米代川 (よねしろがわ)
秋田県北部を西流する川。奥羽山脈の岩手県八幡平市の旧安代(あしろ)町に源を発して秋田県に入り,花輪盆地,大館盆地,鷹巣(たかのす)盆地,出羽山地を貫流し,能代平野より日本海に流出する。河口近くでは能代川とも呼ばれる。幹川流路延長136km,全流域面積4100km2。上流の鹿角(かづの)市,中流の大館市,下流の能代市が中心都市である。奥羽山脈や出羽山地の横谷部は,先行性の流路をとり,上流部の湯瀬渓谷,中流部の徯后(きみまち)坂は景勝地として有名。上流より熊沢川,大湯川,犀(さい)川,長木川,下内川,岩瀬川,早口川,阿仁川,藤琴川,種梅川など多くの支流を合流するが,阿仁川が最大の支流である。流域は日本三大美林の一つと称された秋田杉の宝庫で,近年までいかだ流しが見られた。秋田藩は林政に力を注ぎ,用材の伐採・搬出の義務を負う材木郷を各地に置いて能代奉行が支配したが,各材木郷には戦国武士の系譜を引く大肝煎がいて各村々を統轄した。現在も河口の能代市はじめ,川沿いの北秋田市,大館市などは製材業,木工業が盛んである。流域はまた,日本屈指の非鉄金属鉱物の埋蔵地帯で,小坂鉱山,尾去沢鉱山(おさりざわ),花岡鉱山,松峰鉱山,釈迦内鉱山(しやかない),阿仁鉱山などの鉱山が開発された。
鉄道開通前は県北地方の物資輸送路としても重要で,能代を中心に,二ッ井・荷上場(能代市),鷹巣・米内沢(よないざわ)(北秋田市),扇田・大館・十二所(大館市)などに河港が発達し,扇田までは大船と呼ばれた200俵積みくらいの船が通行した。終航地は十二所であったが,明治初年の水利開発により,花輪(鹿角市)まで通船可能となった。下り荷は米,銅,硫黄など,上り荷は塩,魚,砂糖,日用品が主であった。1905年の奥羽本線開通後は水運はすたれ,河港は衰退した。流域の総人口は県人口の約2割を占める。流域は米産地帯であるが,随所にみられる河岸段丘は普通畑,リンゴ園に利用され,畜産もまた盛んである。なお二ッ井町より上流の町では,近世以来の伝統をもつ定期市が開設されている。
執筆者:北条 寿
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「米代川」の意味・わかりやすい解説
米代川【よねしろがわ】
→関連項目合川[町]|秋田[県]|鷹巣[町]|田代[町]|比内[町]|藤里[町]|二ッ井[町]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「米代川」の意味・わかりやすい解説
米代川
よねしろがわ
秋田県北部を西流して日本海に注ぐ川。一級河川。秋田県三大河川の一つ。延長136キロメートル(秋田県側で110キロメートル)、流域面積4100平方キロメートル。岩手県の奥羽山脈に発する兄(せ)川、根石川などの水を集め、秋田県に入ると花輪、大館(おおだて)、鷹巣(たかのす)の各盆地と能代(のしろ)平野を貫流して日本海に流入する。支流は31に及び、おもな支流に、鉱山地帯の小坂川、森林地帯の長木川・岩瀬川・早口(はやぐち)川、阿仁(あに)鉱山のある阿仁川などがある。奥羽山脈、出羽山地を横断する先行河川で平均勾配(こうばい)は670分の1、荷上場(にあげば)、早口、大滝、湯瀬(ゆぜ)付近は流路が階段状をなすため、河川交通時代にはかなりの制約を受けた。流域の鉱産物や秋田杉を日本海沿いの能代まで運ぶため江戸時代から舟運が利用されてきた。河口から荷上場(能代市)、鷹巣(北秋田市)、大館(おおだて)・扇田(おうぎだ)・十二所(じゅうにしょ)(大館市)などの河港が発達し、扇田までは200俵積みの大船が通った。終航地は普通は十二所で、風のよいときは沢尻(さわしり)(鹿角(かづの)市)まで上った。天保(てんぽう)年間(1830~1844)には上流から米、大豆、荏粕(えかす)、銅、硫黄(いおう)などを運び、能代港からは塩、松前物(水産物・水産加工物)、砂糖、繰綿(くりわた)、日用品を上流に荷揚げした。1905年(明治38)奥羽線が全通してから舟運は衰えた。
[宮崎禮次郎]
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「米代川」の意味・わかりやすい解説
米代川
よねしろがわ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...