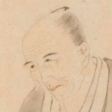精選版 日本国語大辞典 「佐藤一斎」の意味・読み・例文・類語
さとう‐いっさい【佐藤一斎】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「佐藤一斎」の意味・わかりやすい解説
佐藤一斎
さとういっさい
(1772―1859)
幕末期儒学思想界の大御所。名は信行、のちに坦。通称は幾久蔵(きくぞう)、のちに捨蔵。字(あざな)は大道。号は一斎、愛日楼(あいじつろう)、老吾軒、百之寮、風自寮。美濃(みの)国(岐阜県)岩村藩家老の二男に生まれ、藩主松平乗蘊(まつだいらのりもり)(1716―1783)の三男、後の林述斎(じゅつさい)と兄弟のごとくして育った。34歳で林家の塾頭となり、70歳で昌平黌(しょうへいこう)の儒官となる。一斎は若いときから陽明学の信奉者であったが、寛政(かんせい)異学の禁の波及効果の一つとして、藩籍を離脱して大坂に出て、中井竹山(なかいちくざん)に朱子学を学んだ。しかし、のちに林家の塾頭になったときでさえも、公人としては朱子学を講じはしたものの、個人的信念としてはあくまでも陽明学の信奉者であった。「陽朱陰王」などと陰口をたたかれもしたが、「公朱私王」とでもいいうべきものである。朱子学・陽明学を兼採した一斎の宋明(そうみん)性理学に関する学殖は当代随一であった。一斎門では天下の俊秀と講学できることも大きな魅力であった。幕末期の文教政策・人材養成の点で果たした一斎の功績はきわめて大きいものがあった。主著に『言志(げんし)四録』『愛日楼文詩』(1829)などがある。
[ 田公平 2016年5月19日]
田公平 2016年5月19日]
『相良亨・溝口雄三他校注『日本思想大系46 佐藤一斎・大塩中斎』(1980・岩波書店)』▽『宮城公子編・訳『日本の名著27 大塩中斎・佐藤一斎』(1984・中央公論社)』
百科事典マイペディア 「佐藤一斎」の意味・わかりやすい解説
佐藤一斎【さとういっさい】
→関連項目中村正直|松崎慊堂|山田方谷|渡辺崋山
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
改訂新版 世界大百科事典 「佐藤一斎」の意味・わかりやすい解説
佐藤一斎 (さとういっさい)
生没年:1772-1859(安永1-安政6)
江戸後期の儒者。名は坦,字は大道,通称は捨蔵。号は一斎のほか,愛日楼,老吾軒など。美濃岩村藩の家老職の家に生まれ,藩主の三男でのちの林述斎とともに儒学を学ぶ。また大坂の中井竹山にも学び,林家の門に入る。述斎が林家を継ぐとこれに師弟の礼をとり,1805年(文化2)には林家の塾長となって門生の教育に当たった。述斎没後の41年(天保12),幕府の儒官となり昌平黌で教えた。その学問は立場上表面は朱子学をとったが,陽明学の影響も強く受け,〈陽朱陰王〉と評された。気一元論,命数論,死生説などに特色がある。温厚篤実な性格で,その門下から安積艮斎,渡辺崋山,山田方谷,佐久間象山,横井小楠,大橋訥庵,中村正直らの多彩な俊秀を出した。著書に《言志四録》および《近思録》《伝習録》《論語》などの欄外書,《愛日楼文詩》《僑居日記》《俗簡焚余》《初学課業次第》などがある。
執筆者:衣笠 安喜
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「佐藤一斎」の意味・わかりやすい解説
佐藤一斎
さとういっさい
[没]安政6(1859).9.24. 江戸
江戸時代後期の儒学者。名は坦,字は大道,通称は捨蔵。別号は愛日楼。父は美濃,岩村藩家老信由。中井竹山,皆川淇園,林述斎に学び,文化2 (1805) 年林家の塾長,文政6 (26) 年岩村藩儒官,天保 12 (41) 年江戸幕府儒官となった。官学にあったため,朱子学を講じながらも内実は陽明学に傾いており,陽朱陰王といわれた。門人に安積艮斎 (あさかごんさい) ,渡辺崋山,佐久間象山,中村正直,横井小楠らが輩出した。著書『愛日楼文詩』 (29) ,『言志四録』『初学課業次第』。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「佐藤一斎」の解説
佐藤一斎 さとう-いっさい
明和9年10月20日生まれ。美濃(みの)(岐阜県)岩村藩家老佐藤文永の次男。藩主松平乗薀(のりもり)の子の林述斎(じゅっさい)とともにまなぶ。林家の塾頭をへて昌平黌(しょうへいこう)教授となる。朱子学と陽明学を折衷した学風で,門人に渡辺崋山(かざん),佐久間象山(しょうざん)らがいる。安政6年9月24日死去。88歳。名は信行,のち坦(たいら)。字(あざな)は大道。通称は幾久蔵,捨蔵。別号に愛日楼。著作に「言志四録」など。
【格言など】春風をもって人に接し,秋霜をもって自らつつしむ(「言志後録」)
山川 日本史小辞典 改訂新版 「佐藤一斎」の解説
佐藤一斎
さとういっさい
1772.10.20~1859.9.24
江戸後期の儒学者。父は美濃国岩村藩家老の佐藤信由(のぶより)。初名は信行のち坦(たいら),字は大道,通称捨蔵,号は一斎のほかに愛日楼・老吾軒。19歳で出仕。藩主松平乗蘊(のりもり)の子でのち林家を継ぐ林述斎と親交を結ぶ。20歳で致仕して学問に専念,22歳で林家に入門,述斎に師事し34歳で塾長。70歳で昌平黌儒官。陽明学に傾きながら寛政異学の禁後の林家塾長の立場から朱子学を掲げたため,陽朱陰王との誹(そし)りもうけた。門下から佐久間象山(しょうざん)・渡辺崋山(かざん)らを輩出。主著「言志四録」。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「佐藤一斎」の解説
佐藤一斎
さとういっさい
江戸後・末期の儒者
美濃(岐阜県)岩村藩士。中井竹山に師事し,林述斎の弟子となった。のち昌平坂学問所の儒官となり,立場上朱子学をとったが,陽明学の影響も濃い。門人に安積艮斎 (あさかごんさい) ・渡辺崋山・佐久間象山らを輩出。著書に『言志四録』『近思録』など。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
367日誕生日大事典 「佐藤一斎」の解説
佐藤一斎 (さとういっさい)
江戸時代後期の儒学者;林家塾頭;昌平坂学問所教官
1859年没
出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の佐藤一斎の言及
【武士道】より
…〈甲冑ハ辱ム可カラザルノ色ナリ。人ハ礼譲ヲ服シテ以テ甲冑ト為サバ誰カ敢テ之ヲ辱シメン〉という佐藤一斎の言葉は,近世武士社会における礼儀尊重の精神を語るものである。武士【相良 亨】。…
※「佐藤一斎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...