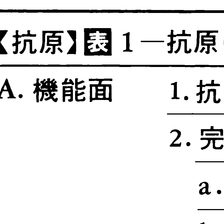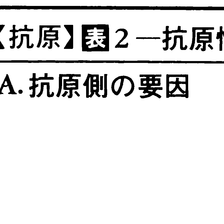翻訳|antigen
精選版 日本国語大辞典 「抗原」の意味・読み・例文・類語
こう‐げんカウ‥【抗原・抗元】
- 〘 名詞 〙 生体内に入ると抗体をつくらせる原因となる物質。一度抗体ができると、次に侵入した同じ原因物質と特異的に反応する。〔血液の科学(1944)〕
改訂新版 世界大百科事典 「抗原」の意味・わかりやすい解説
抗原 (こうげん)
antigen
1903年,ドイッチュL.Deutschが抗体をつくるきっかけとなり,それと反応するものという意味の語Antisomatogenを縮めてつくった語で,血清学,免疫学の分野を中心に多く使われている。抗原は次の2条件から定義される。
条件(1) 脊椎動物の体内に入って,それだけに反応性をもつ(これを特異性という)抗体や感作リンパ球をつくって,その個体に免疫を成立させるが,条件によってはそれに特異的な不反応性(免疫学的寛容)状態を成立させる能力,またはその潜在能力をもつ物質。
条件(2) できた抗体,または感作リンパ球と生体の内外で特異的に反応する(潜在)能力をもつ物質。
物質がもつ抗原としての性質は抗原性と呼ばれ,その能力の強弱は抗原性が高(強)い,低(弱)い等という。また,抗原を抗体産生を含む免疫の成立,免疫学的寛容やアレルギーを起こす能力に焦点をしぼって考えるとき,免疫原(イムノーゲンimmunogen),寛容原(トレローゲンtolerogen),アレルゲンallergenなどともいう。さらに,抗原を生体に与えて免疫状態等を成立させることを免疫(感作)するなどという。
分類と性質
抗原は性質,由来等から表1のように分類され,目的に応じて使い分けられる。また,どんな性質の物質が抗原性をもつかも重要なので,その各種の条件を表2にあげた。このなかで最も重要なものは自己・非自己(自分の体の構成成分,またはそうでない成分)の区別で,前者には原則として抗原性はないが,後者にはそれが認められる。しかし,これにも自己抗原のような例外があり,表中の多数の条件を満足していても抗原性をもたなかったり,その逆の場合も多い。多くの高分子有機物質にはなんらかの形で抗原性をもつと考えられるが,未検討の物質の抗原性の有無を確認するには,適当な種の動物の多数の個体を免疫してみる以外にない。この際,適当な免疫増強剤の併用,簡単な化合物なら,他の高分子物質に結合させると抗原性が新たに現れたり,強まることが多い。
抗原のこのような機能は抗原分子全体にあるのではなく,その限定された部位がもつ化学的・立体的構造との関連が深い。このような部分を決定群(基)またはエピトープepitopeと呼び,多くの場合,分子量500~1000で4×2×1nmくらいの大きさをもち,タンパク質抗原ではアミノ酸5~8個,多糖体抗原なら単糖5~6個くらいの大きさからなる。
抗原特異性とその基盤
特定の抗原の免疫で生体がつくった(または正常動物が少量もつ)抗体または感作リンパ球は,その抗原に特有な決定群とのみ反応する。これは抗原抗体反応の大きな特徴で,抗原のこのような性質を特異性といって医学その他の分野に広く応用されている。しかし,これにも例外があり,免疫抗原と類似の構造をもつ抗原(たとえばヒトのヘモグロビンを免疫抗原とすれば,サルのヘモグロビン)では対応しない抗体に対して反応することがある(交叉(こうさ)反応)。この際,構造の類似性が高いほど交叉反応は強く起こるが,免疫に用い,できた抗体と対応した抗原を主抗原,そうでなく交叉反応をする抗原を副抗原と呼ぶ。免疫血清を副抗原で吸収するとその中には主抗原と反応する抗体のみが残り,逆に主抗原では吸収後は全部の抗体が除去される。この現象をうまく利用すれば免疫血清中に主抗原だけと反応する抗体のみを残すことができる(抗血清の吸収操作)。特異性と抗原やその決定群の化学的構造の関係は,構造既知のハプテンによる人工抗原,アミノ酸等を重合させた合成抗原,さらに天然抗原の分解産物やその特定の構造部の化学的修飾等を用いてこまかく分析され,タンパク質抗原,多糖体(たとえばミオグロビン,デキストランや血液型抗原)抗原の中にはその構造が明らかにされているものもある。
→抗原抗体反応 →免疫
執筆者:木村 一郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「抗原」の意味・わかりやすい解説
抗原【こうげん】
→関連項目アレルギー|アレルゲン|オーストラリア抗原|感作|クローン|蛍光抗体法|血液型|抗毒素|ジフテリア血清|スネル|スーパー抗原|組織適合抗原|ツベルクリン反応|DNAワクチン|トキソイド|プロテウス菌|ペニシリン|溶血性連鎖球菌|ワクチン|ワッセルマン反応
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
化学辞典 第2版 「抗原」の解説
抗原
コウゲン
antigen
動物体内において抗体を産生させて,その抗体と特異的に反応する物質.異種のタンパク質,多糖,核酸,核タンパク質,リポタンパク質,および合成高分子が抗原となる.たとえば,ウシ血清アルブミンをウサギに非経口的に投与すれば,ウサギ血清中にウシ血清アルブミンに対する抗体が産生される.ウサギ血清アルブミンをウサギに投与しても抗体は産生されない.このように,抗原となる物質は免疫される動物の抗体産生細胞によって“異種”と認識される物質である.一般に,抗原は細菌,血球などの粒子,あるいはタンパク質などの複雑な高分子である.[別用語参照]ハプテン
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「抗原」の意味・わかりやすい解説
抗原
こうげん
antigen
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「抗原」の意味・わかりやすい解説
抗原
こうげん
antigen
生体に免疫応答を惹起(じゃっき)し(免疫原性)、その結果生じた特異的抗体または特異的リンパ球と反応しうる性質(反応原性)をもったものをいう。免疫原性をもつためには、通常異種で、分子量がある程度以上大である必要があり、タンパク質や多糖体は免疫原性が強い。小分子量(通常1000以下)のものは反応原性はあるが、高分子物質と結合しないと免疫原性はなく、ハプテンhaptenとよばれる。
免疫原となりうる基本構造を抗原決定基といい、多くの抗原は数多くの異なる抗原決定基をもつ複合体で、ハプテンはそれ自体抗原決定基となりうる。
[高橋昭三]
栄養・生化学辞典 「抗原」の解説
抗原
世界大百科事典(旧版)内の抗原の言及
【抗原認識】より
…抗原が生体に侵入すると,免疫系の中心をなす種々のリンパ球が刺激されて増殖し,種々の機能を現すようになり,免疫が成立する。抗原刺激に対するこのような免疫応答は,その抗原に特異的であり,ひとつひとつの抗原に対しては,それぞれきわめて限定された少数のリンパ球のみが反応する。…
【抗体】より
…生体にウイルス,細菌,その他の細胞や動植物の成分などの抗原が侵入すると,生体の免疫系が刺激され,やがてそれらの侵入物に特異的に結合できるタンパク質が合成されて,細胞表面,血清その他の体液中に出現する。このタンパク質が抗体である。…
【ハプテン】より
…K.ラントシュタイナーが1921年に人工抗原の研究に際して提唱した概念上の抗原決定基。ラントシュタイナーの定義によれば,独立では抗原性をもたないが,他のタンパク質(担体)と結合させて投与すれば,特異的な抗体をつくらせ,その抗体と結合する能力を有する低分子物質をさす。…
【免疫】より
…この物質はやがて,タンパク質であり,試験管内でさまざまな反応を起こし,生体内では感染防御に働く分子であることが明らかになり,のちに〈抗体〉と呼ばれるようになった。これに対し,この抗体産生を誘導する微生物由来の異物,さらには広く〈自己でないもの〉を〈抗原〉と呼ぶのである。抗原と抗体の試験管内および生体内での反応を〈抗原抗体反応〉と呼ぶが,これは免疫反応の重要な要素である。…
※「抗原」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...