精選版 日本国語大辞典 「椀」の意味・読み・例文・類語
わん【椀・碗・盌】
- [ 1 ] 〘 名詞 〙
- [ 2 ] 〘 接尾語 〙 椀に盛った飲食物を数えるのに用いる。
椀の補助注記
水を入れるための器としては、上代に「もひ」の語もあったが、一般には丸いものの義で「まり」と呼ばれた。従って、挙例の「法隆寺伽藍縁起并流記資財帳」の読みは明らかでないが、音読したものとして扱った。
もいもひ【椀・盌】
- 〘 名詞 〙 水を盛る食器。おわん。まり。
- [初出の実例]「止由気太神御前 御水四毛比 御飯二八具」(出典:止由気宮儀式帳(804))
改訂新版 世界大百科事典 「椀」の意味・わかりやすい解説
椀 (わん)
一般には飯,汁その他飲食物を盛る器をいう。椀のほか埦,鋺などとも書く。わん状の容器が日本で使いはじめられた時期は縄文時代までさかのぼりうるが,飲食器として一般化するようになる時期は,稲作が伝わり農耕が行われるようになった弥生時代が最有力である。そのよりどころは奈良県磯城郡田原本町の唐古遺跡から出土した2種類の木製椀で,その一つは高台のあるいわゆるわん形を呈し,当時すでにこの形が通用していたことがわかる。わんが,器物の名称として文献類に明記されるようになるのは奈良時代に入ってからで,埦,鋺,椀のほか垸,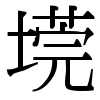 ,
, ,院,鋎,
,院,鋎,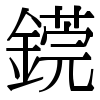 ,
, などとも記されている。土偏は土・焼物製,金偏は金属製,木偏は木製の意を表したのであろう。《和名抄》によれば,鋺はカナマリ,椀をマリ,モヒと訓むが,この訓みは正倉院文書にも〈水麻理〉〈加奈鋺〉〈毛比〉などの記載事例があって,奈良時代からの訓みであったことが知られる。しかし東京国立博物館の法隆寺献納宝物や正倉院宝物,あるいは平城京跡などの出土例を見るかぎり金属製鋺または木製黒漆塗椀の遺品は寺院や宮廷所用に限られており,わん類の主流をなしたのは当代はもちろんそれ以前から土師器(はじき),須恵器(すえき)などの土・陶製埦であった。それは多くの出土品によっても明らかである。それらの中には平城京跡出土の土師器のように〈弁垸勿他人者〉と墨書銘を記し,みずからの所有権を明らかにした珍しい例もあるが,この埦で同時に注目されるのは,〈弁垸〉と記しながら,口径19cmの大ぶりな容器であることであろう。したがって当時〈わん〉と称するものは,法量的にも大小広範囲にわたっていたことを示唆している。また奈良時代のわんの種類には片埦,鋺形,重鋺などがあった。片埦は口縁の一方に注口のついたいわゆる片口(かたくち)状の埦で,船橋遺跡出土のものがこれにあたる。鋺形は片埦よりも手間がかかるところから,糸底のある高台付きの金属製鋺とみられ,〈土鋺形〉と記されるものはこの器形をさらに写した土師製の埦であったと想定される。重鋺は入れ子状に組み入れることのできる大・小一具の鋺で,747年(天平19)の法隆寺資財帳や正倉院文書に見るかぎりでは五重または十重が通例だったようである。当時の遺品としては正倉院宝物中の加盤・加鋺と称する入れ子形重鋺や法隆寺献納宝物中の2組の八重鋺が相応する。いずれも佐波理(さはり)製と目されるものであり,組入れとするため当時は金属鋺が原則であったと考えられる。もちろん後世においては木製漆塗椀にも入れ子状のものの類例があり,三・四・五ツ椀などと呼ばれた。
などとも記されている。土偏は土・焼物製,金偏は金属製,木偏は木製の意を表したのであろう。《和名抄》によれば,鋺はカナマリ,椀をマリ,モヒと訓むが,この訓みは正倉院文書にも〈水麻理〉〈加奈鋺〉〈毛比〉などの記載事例があって,奈良時代からの訓みであったことが知られる。しかし東京国立博物館の法隆寺献納宝物や正倉院宝物,あるいは平城京跡などの出土例を見るかぎり金属製鋺または木製黒漆塗椀の遺品は寺院や宮廷所用に限られており,わん類の主流をなしたのは当代はもちろんそれ以前から土師器(はじき),須恵器(すえき)などの土・陶製埦であった。それは多くの出土品によっても明らかである。それらの中には平城京跡出土の土師器のように〈弁垸勿他人者〉と墨書銘を記し,みずからの所有権を明らかにした珍しい例もあるが,この埦で同時に注目されるのは,〈弁垸〉と記しながら,口径19cmの大ぶりな容器であることであろう。したがって当時〈わん〉と称するものは,法量的にも大小広範囲にわたっていたことを示唆している。また奈良時代のわんの種類には片埦,鋺形,重鋺などがあった。片埦は口縁の一方に注口のついたいわゆる片口(かたくち)状の埦で,船橋遺跡出土のものがこれにあたる。鋺形は片埦よりも手間がかかるところから,糸底のある高台付きの金属製鋺とみられ,〈土鋺形〉と記されるものはこの器形をさらに写した土師製の埦であったと想定される。重鋺は入れ子状に組み入れることのできる大・小一具の鋺で,747年(天平19)の法隆寺資財帳や正倉院文書に見るかぎりでは五重または十重が通例だったようである。当時の遺品としては正倉院宝物中の加盤・加鋺と称する入れ子形重鋺や法隆寺献納宝物中の2組の八重鋺が相応する。いずれも佐波理(さはり)製と目されるものであり,組入れとするため当時は金属鋺が原則であったと考えられる。もちろん後世においては木製漆塗椀にも入れ子状のものの類例があり,三・四・五ツ椀などと呼ばれた。
平安時代のわんは,《延喜式》記載のわんが基準となろう。名をとどめるのは朱漆椀,加椀,大椀,中椀,羹(あつもの)椀,飯椀の6例で,このほかに椀形というのがある。これらの椀にはそれぞれ寸法を併記しており,最大は朱漆椀の口径1尺1寸,深さ3寸5分と,加椀の径1尺1寸,深さ7寸で,最小は羹椀の径6寸である。朱漆椀,加椀の異例な大きさが注目されるが,それはこの時代にも椀自体が定形化されていなかったためであろうし,《延喜式》記載のわんであるため,あるいは儀式用具だったのかもしれない。
当時朱漆器を使用できる者の階層は烏漆(黒漆)器を使用する者よりも上位にあり,《延喜式》の〈大膳上〉には,親王以下三位以上が朱漆,四位以下五位以上が烏漆あるいは土器とされていた。ただ朱漆椀といっても全面朱漆塗か中半分を朱漆塗としたいわゆる内朱外黒のものであったかはつまびらかでない。加椀は正倉院に加鋺と称する佐波理の重鋺が伝わっていることによっても,幾重かの重椀であったと考えられる。飯椀は飯を盛る椀,羹椀は汁用の椀で,いずれも用途を表している。いずれにせよこのころから,後世見るような用途に応じた種々のわん形がしだいに形成されてきたことは確かである。しかしこの時代も主流は木製漆塗椀でなく土・陶製の埦であったと思われる。平安時代も後半に入ると近畿地方を中心に土師の表面を黒色にいぶしたいわゆる瓦器碗(がきわん)が多用されるようになるし,中世初頭までは須恵器質の山茶碗(やまちやわん)が実用性に富む食器として新興の武士や土豪層の間で盛んに利用されるようになる。
中世期のわんについては,伝世遺品が寥々たるものであり,なかでも木製漆塗椀は,この時代に比定される遺品はあっても確証のある事例は乏しい。その使用のさまはこれまで絵巻物などに描かれたわんが重要な参考資料とされてきた。しかし近年では中世の住居跡や武家の居館跡の大規模な発掘が各地で行われ,その出土品によってようやく実態が解明されつつある。これら発掘遺品によって考えられる中世期わんの特色は,中国との交易により頻繁にもたらされるようになった白磁や青磁など宋・元の焼物わんが,上層階級のみならず一般にまで波及してきたこと,また木製漆塗椀が予想以上に利用されていたことである。鎌倉市の諏訪東遺跡,千葉地遺跡,蔵屋敷東遺跡や福井県あわら市の旧金津町の桑原遺跡,朝倉氏居館跡の福井県一乗谷遺跡,広島県福山市の草戸千軒遺跡などからおびただしい数の漆塗椀が発見された。鎌倉時代から室町時代に至るこれらの出土椀に見られる特色は,そのほとんどが木製ろくろ挽きの素地に全面黒漆を塗布し,さらに朱漆による絵文様を施したいわゆる漆絵椀であること,また外面のみに意匠を施すのが通例である近世の漆絵椀と異なり,椀の内外に模様を描いているのが注目される。しかもそれらの意匠は千変万化で機知に富み,また平安時代以来の伝統を踏まえた日本的情趣を示すものが少なくない。器形の上では,おおむね器体の背丈や高台が低く作られ,ゆったりとした面と相まって安定感を示す。なお同形式の漆絵椀は黒地朱文様に限るわけではない。
また近年韓国全羅南道新安沖海底の沈没船からおびただしい数の宋・元の陶磁器とともに発見された漆絵椀には,片輪車,州浜,秋草などの意匠が見られ,これらが日本製であると推測されている。これは朱漆地に橙,緑,黒の色漆で意匠を表しており,この種の漆絵椀が14世紀前半期にはすでに製作されていたことを裏付ける貴重な資料となっている。一方,《慕帰(ぼき)絵詞》や《酒飯論絵詞》のような絵画によっても明らかなように,この時代には俗に根来(ねごろ)椀と称される朱漆塗椀もおもに寺院などの什器として多用された(根来)。現存する紀年銘椀としては奈良眉間(みけん)寺に伝来した明徳2年(1391)銘朱漆塗椀(東京国立博物館)が最古のものである。その器形は当時中国から盛んに請来された天目茶碗のそれを範としており,唐物尊重の時代の好尚を如実に物語っている。
飯椀,汁椀,平椀,坪(つぼ)など木製漆塗椀の膳具が,現在にも通じるような形式に整備されるようになるのは近世に入ってからである。近世椀の特色はその変化に富む形状もさることながら,表面に施す塗や加飾の手法に最も発揮された。伝統的な朱漆塗や漆絵が依然として主流であったが,新たに蒔絵(まきえ)椀や金・銀の箔押椀が出現し,漆絵がいっそう華麗さを加えることになる。蒔絵椀では秀吉・北政所の廟所である高台寺に,什器として調進された膳具(高台寺蒔絵)が名高いが,漆絵金箔押の装飾を施した秀衡椀や大内椀が盛行するようになるのも近世初頭ころからであろう。美しく豪華に膳具をしつらえることが,接客の具にふさわしかったからにほかならない。また幕藩体制が確立し,各藩の産業奨励策によって漆器生産が各地で行われるようになったことも塗物椀の流行を促した大きな理由といえよう。浄法寺(じようぼうじ)椀(岩手県浄法寺の産。南部椀ともいわれる),会津塗(福島県),輪島塗(石川県),若狭塗(福井県小浜市の産。変(かわり)塗の一種),吉野塗(奈良県吉野地方の産。吉野絵,吉野彫,吉野根来,吉野春慶など),黒江塗(和歌山県海南市の産),大内塗(山口県山口市の産。大内椀は毛利家に伝えられ,漆絵に金箔を施す),日野椀(滋賀県蒲生郡の産)などが良質な椀として知られている。熟練した木地師や塗師の手により,大量に作られたこれらの椀は,材料が吟味され,軽量でしかも堅牢に仕上げられ,機能的にもすぐれた器形をもっていた。
いまわれわれが常用しているような磁器製の飯茶碗が広く利用されるようになるのは,近世末期ころからであろう。伊万里などの磁器が菜物,焼物の皿や徳利といった日常の食器として一般化するようになり,量産により低廉化され,やがて膳椀にも盛んに利用されるようになったと考えられる。ただ汁椀のみ現在に至るまで木製漆塗椀である。これは高温の汁を盛って口もとにまで運ぶには磁器は不向きであり,また日本人の感覚にも温和な漆器が合っていたからである。
→茶碗 →椀貸伝説
執筆者:河田 貞
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
普及版 字通 「椀」の読み・字形・画数・意味

10画
(異体字)椀
人名用漢字 12画
[字訓] はち
[説文解字]

[金文]

[その他]

[字形] 形声
声符は
 (えん)。
(えん)。 は人が坐して、ひざをまるくしている形。そのまるくふくよかな形のものをいう。材質によって
は人が坐して、ひざをまるくしている形。そのまるくふくよかな形のものをいう。材質によって ・椀・
・椀・ ・鋺・碗というが、みなはち形のもの。殷・周の青銅器に盂(う)というものがあり、儀礼の際に用いるが、于(う)もゆるくまがるものの意で、盂は深い鉢の形。みな命名の法が似ている。
・鋺・碗というが、みなはち形のもの。殷・周の青銅器に盂(う)というものがあり、儀礼の際に用いるが、于(う)もゆるくまがるものの意で、盂は深い鉢の形。みな命名の法が似ている。[訓義]
1. わん、はち。大なるものを盂という。
2. 字はまた椀・
 に作る。
に作る。[古辞書の訓]
〔新
 字鏡〕椀 万利(まり)〔和名抄〕鋺 日本靈異記に云ふ、其の
字鏡〕椀 万利(まり)〔和名抄〕鋺 日本靈異記に云ふ、其の は皆鋺なりと。俗に加奈万利(かなまり)と云ふ。今案ずるに、鋺の字未だ詳らかならず。古語に椀を謂ひて末利(まり)と爲す。宜しく金椀の二字を用ふべし/
は皆鋺なりと。俗に加奈万利(かなまり)と云ふ。今案ずるに、鋺の字未だ詳らかならず。古語に椀を謂ひて末利(まり)と爲す。宜しく金椀の二字を用ふべし/ 辨色立
辨色立 に云ふ、末利(まり)。俗に毛比(もひ)と云ふ 〔名義抄〕
に云ふ、末利(まり)。俗に毛比(もひ)と云ふ 〔名義抄〕 マリ・モヒ/椀 イホテ・コロモハリ・マリ・モヒ
マリ・モヒ/椀 イホテ・コロモハリ・マリ・モヒ[語系]
 ・椀・
・椀・ ・
・ uanは同声。
uanは同声。 (わん)は椀のような形に器を刳(えぐ)り削って作ることをいう。
(わん)は椀のような形に器を刳(えぐ)り削って作ることをいう。 uyanや、また
uyanや、また nguanも、そのように削りとることをいう。
nguanも、そのように削りとることをいう。 は〔段注〕四下に「抉(えぐ)りて之れを取るなり」とする。
は〔段注〕四下に「抉(えぐ)りて之れを取るなり」とする。 ・宛iuanと于hiua、
・宛iuanと于hiua、 ・紆iuaと声義近く、ゆるくめぐるようなさまをいう語である。
・紆iuaと声義近く、ゆるくめぐるようなさまをいう語である。[熟語]
 子▶・
子▶・ 唇▶・
唇▶・ 遂▶・
遂▶・ 脱▶・
脱▶・ 注▶
注▶[下接語]
瓦
 ・玉
・玉 ・金
・金 ・銀
・銀 ・漆
・漆 ・酒
・酒 ・茶
・茶 ・斗
・斗 ・白
・白 ・浮
・浮 ・覆
・覆 ・
・

椀
人名用漢字 12画
(異体字)
10画
[字訓] はち
[字形] 形声
声符は宛(えん)。宛は人が
 中に坐する形で、ひざのまるくふくよかな形から、そのような状態のものをいう。中国では古く
中に坐する形で、ひざのまるくふくよかな形から、そのような状態のものをいう。中国では古く の字を用い、わが国では多く椀を用いる。陶器のものには碗、金属製のものには鋺を用いる。
の字を用い、わが国では多く椀を用いる。陶器のものには碗、金属製のものには鋺を用いる。 は皿形の形状よりいい、椀は木製のものをいう。これらの字の古訓については、
は皿形の形状よりいい、椀は木製のものをいう。これらの字の古訓については、 字条参照。
字条参照。[訓義]
1. わん、木のわん。
2. はち、小ばち。
 字条参照。
字条参照。[熟語]
椀盂▶・椀花▶・椀器▶・椀
 ▶・椀珠▶・椀脱▶・椀
▶・椀珠▶・椀脱▶・椀 ▶
▶[下接語]
玉椀・香椀・漆椀・汁椀・茶碗・籌椀・斗椀・灯椀・熱椀・氷椀・捧椀・鏤椀
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「椀」の意味・わかりやすい解説
椀
わん
汁や飯などを盛る食器で、陶磁器製のものは碗、木製のものは椀の字をあてたが、のちに、茶器から転用された飯用の陶磁器のものは茶碗とよばれるようになった。そのため、現在では椀といえば、木製の汁や飯を盛る食器のみに限定されている。歴史的には、土器の碗が始まりと考えられるが、木工の発達により、木をくりぬいて椀がつくられるようになった。加工を施さない椀は、かなり古くから用いられていたようであるが、使用上、限界があり、平安時代になると、漆塗りの技術が生まれ、木椀に漆加工が施されるようになった。そして、椀は、木製のものに漆塗りを施したものが中心となっていった。また、漆加工ができるようになると、椀の生地(きじ)の厚みも、薄く仕上げることが可能となり、さらに、模様などの加工も細かくなり、日常品であるとともに、芸術品としても発展することになった。
椀は、目的により、形態の異なるものが数多く存在する。汁椀では、みそ汁に使うもののほか、吸い物椀、汁粉椀など、また、汁の多い煮物などを盛る大ぶりの椀もある。
椀は、木製であるため、断熱性が高く、熱い汁物を入れても、口にもっていったとき、直接熱さを唇に感じさせない。したがって、熱いものを、熱さを楽しみながら味わうことができるとともに、中の料理、主として汁物などが冷めにくいという利点もある。
江戸時代の初めまでは、ほとんど木椀が料理の盛付けに用いられていたが、陶磁器による茶碗の発達とともに、木椀はだんだん少なくなり、汁椀や一部料理の盛付け程度に用いられているのが現状である。その理由は、漆塗りは手間と時間がかかるとともに、使用にあたって注意点があり、陶磁器のように簡便に使うと、はげたり、割れたりするといった点もあると思われる。それと、高価な点が、椀を少なくした理由とも考えられる。椀は漆塗りの産地ごとに特徴があり、独特の味わいを料理に与える利点がある。なお、近年は、プラスチック製のものや、木のかわりにプラスチックに漆を塗ったものなども出回っている。
[河野友美・大滝 緑]
『『和食器――盛り付け自由自在』(1997・同朋舎出版)』▽『神崎宣武著『図説 日本のうつわ――食事の文化を探る』(1998・河出書房新社)』
百科事典マイペディア 「椀」の意味・わかりやすい解説
椀【わん】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「椀」の意味・わかりやすい解説
椀
わん
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
食器・調理器具がわかる辞典 「椀」の解説
わん【椀】
世界大百科事典(旧版)内の椀の言及
【茶碗】より
…しかし当時,日本では磁器はつくられておらず,この場合の茶碗は中国から請来された磁器を意味していた。日本で焼かれた茶碗で早い時期のものといえば灰釉茶碗(坏(つき))や山茶碗(やまぢやわん)があげられるが,これらはむしろ飲食用の器であった。しかし日本では飲食用の器としては木製の椀(わん)が主流であり,そのために江戸時代に入るまで陶磁器の飲食用碗はあまりつくられていない。…
※「椀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...




