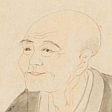精選版 日本国語大辞典 「武野紹鴎」の意味・読み・例文・類語
たけの‐じょうおう【武野紹鴎】
百科事典マイペディア 「武野紹鴎」の意味・わかりやすい解説
武野紹鴎【たけのじょうおう】
→関連項目今井宗久|京釜|信楽焼|草庵|茶道|西村道仁|備前焼
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「武野紹鴎」の意味・わかりやすい解説
武野紹鴎
たけのじょうおう
(1502―1555)
戦国時代の堺(さかい)の豪商、茶の湯名人。若狭(わかさ)守護武田氏の後裔(こうえい)で、父信久のとき堺に来住したと伝えるが、不詳。名は新五郎、仲材といい、居士(こじ)号を一閑(いっかん)と称す。舳松(へのまつ)町に住み皮革を家業とした。30歳までは連歌(れんが)師であったといい、その間1528年(大永8)3月以来、当代の代表的な文化人であった三条西実隆(さんじょうにしさねたか)に師事して古典を学び、『詠歌大概(えいがのたいがい)』(藤原定家(ていか)著、歌論書)の序の部分の講釈を受けていたとき、茶の湯について悟るところがあったという。京都では下京(しもぎょう)四条、夷堂(えびすどう)の隣に居を構え大黒庵と号した。連歌師心敬(しんけい)の説く枯淡の美を茶の湯に取り入れ、四畳半茶室を基本とする草庵茶の湯の発展に指導的な役割を果たしたが、名物道具を多数所持したことからもうかがわれるように、わび茶への過渡期に位置づけられる。女婿(じょせい)の今井宗久(そうきゅう)をはじめ、津田宗及(そうきゅう)、田中宗易(千利休(せんのりきゅう))らの師。和泉(いずみ)南宗寺の大林宗套(だいりんそうとう)に参禅し、これが茶人参禅の風を生む一方、茶禅一味(ちゃぜんいちみ)が説かれるようにもなった。天文(てんぶん)24年10月没。享年54。墓は南宗寺境内にある。
[村井康彦]
山川 日本史小辞典 改訂新版 「武野紹鴎」の解説
武野紹鴎
たけのじょうおう
1502~55.閏10.29
戦国期の茶人,堺の豪商。堺流茶の湯の開祖。名は仲材(なかき)。通称新五郎。武野氏は若狭国の守護武田氏の後裔で,父信久は諸国を流浪したのち堺に住み,姓を武野として,武具作製の皮革業を営んで財をなしたという。紹鴎は,歌道・連歌に堪能で,24歳で三条西実隆に和歌を学び,村田珠光(じゅこう)門下の藤田宗理や十四屋(じゅうしや)宗伍などに茶の湯を学んだという。実隆の「詠歌大概」(藤原定家)の序の講義をきいて茶道の極意を悟ったという。彼は和歌の心を茶の心に生かし,唐様趣味を和様に転化するなどの工夫を行った。晩年京都四条に草庵大黒庵を設け茶事に専念した。2畳・3畳の小間の茶室,竹の茶入や茶杓などを創案し,それまでの茶の湯の姿を大きく変化させた。弟子に嗣子の宗瓦(そうが),女婿の今井宗久をはじめ,津田宗及(そうぎゅう)・千利休・松永久秀など多数。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「武野紹鴎」の意味・わかりやすい解説
武野紹鴎
たけのじょうおう
[没]弘治1(1555).閏10.29. 京都
室町時代末期の茶人。若狭国守護の武田氏の子孫。父の代に堺に移住し姓を武野と改めた。名は仲村,通称新五郎。京都に出て三条西実隆に歌道を学び,連歌にも長じた。従五位下因幡守に叙任せられたという。次いで十四屋宗悟 (じゅうしやそうご) ,宗陳に茶道を習い,さらに実隆から藤原定家著『詠歌大概』の序巻の講義を受けて,茶道の極意を得たといわれる。享禄5 (1532) 年仏門に入って紹鴎と号した。晩年は京都四条に茶室大黒庵を設け茶会を開催。村田珠光によって始められた佗茶 (わびちゃ) をもって茶道の理想とし,4畳半座敷から3畳,2畳半の小座敷を考案。また多くの名物を秘蔵していたことでも有名。門人に今井宗久,津田宗及,千利休らがいる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「武野紹鴎」の解説
武野紹鴎 たけの-じょうおう
文亀(ぶんき)2年生まれ。父信久は堺の有力町衆。はじめ京都で三条西実隆に和歌,連歌を,のち茶の湯を村田珠光(じゅこう)の門人村田宗珠,十四屋(じゅうしや)宗伍らにまなぶ。珠光の侘茶(わびちゃ)をひろめ,門人に千利休,今井宗久,津田宗及らがいる。弘治(こうじ)元年閏(うるう)10月29日死去。54歳。名は仲材。通称は新五郎。号は一閑,大黒庵。
【格言など】正直に慎しみ深く,おごらぬさまを,侘びという(「石洲流秘事五箇条」)
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...