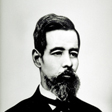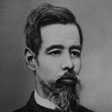精選版 日本国語大辞典 「陸奥宗光」の意味・読み・例文・類語
むつ‐むねみつ【陸奥宗光】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「陸奥宗光」の意味・わかりやすい解説
陸奥宗光
むつむねみつ
(1844―1897)
明治時代の外交官、政治家。天保(てんぽう)15年7月7日、和歌山藩士伊達宗広(千広)(だてむねひろ(ちひろ))の六男として生まれる。宗広が藩内の政争で失脚したため江戸に出て苦学、安井息軒(そくけん)などに師事。やがて尊王攘夷(じょうい)運動に身を投じて坂本龍馬(りょうま)を知り、1863年(文久3)ともに勝海舟(かつかいしゅう)の神戸海軍操練所に入った。同所が閉鎖されると龍馬に従って長崎で亀山(かめやま)社中を結成、海運・商業に従事、このころに陸奥陽之助(ようのすけ)と称した。1867年(慶応3)には龍馬の下で海援隊に入って活躍した。明治維新とともに外国事務局御用掛に登用され、兵庫県知事などを経て和歌山藩の藩政改革を担当。渡欧後、政府に復帰して神奈川県知事となり、1872年(明治5)には租税権頭(ごんのかみ)に任じられて地租改正を建議した。1875年元老院議官となる。1877年の西南戦争に呼応した土佐立志社の挙兵計画に加担し、1878年に拘引され、免官、下獄した。1882年出獄後外遊、1888年駐米公使となり、メキシコとの間の最初の対等条約締結に成功した。第一次山県有朋(やまがたありとも)内閣に農商務大臣として入閣、最初の議会で政党工作に努め、続く松方正義(まつかたまさよし)内閣にも留任したが、選挙干渉問題をめぐる政府の責任を追及して辞任した。枢密顧問官を経て第二次伊藤博文(ひろぶみ)内閣の外務大臣となり、イギリスとの間で条約改正交渉を進め、対外硬派による反対を抑えて1894年7月日英通商航海条約の調印にこぎ着け、治外法権の撤廃に成功した。さらに朝鮮で東学党の乱(甲午(こうご)農民戦争)が起こるとただちに出兵を決定、8月日清(にっしん)戦争に突入した。1895年伊藤首相とともに全権として講和条約に調印したが、三国干渉を受け、遼東(りょうとう)半島の還付を決断した。戦争中から持病の肺結核が進行し、1896年5月外務大臣を辞任した。この間1895年に伯爵となる。その後、竹越与三郎(たけごしよさぶろう)に雑誌『世界之日本』を編集させ、匿名で寄稿したが、明治30年8月24日没した。回顧録に『蹇蹇録(けんけんろく)』がある。
[宇野俊一]
『『蹇蹇録』(岩波文庫)』▽『陸奥広吉編『伯爵陸奥宗光遺稿』(1929・岩波書店)』▽『萩原延壽著『陸奥宗光』上下(2007~2008・朝日新聞出版)』
改訂新版 世界大百科事典 「陸奥宗光」の意味・わかりやすい解説
陸奥宗光 (むつむねみつ)
生没年:1844-97(弘化1-明治30)
明治の政治家,外交官。和歌山藩士伊達宗広の第6子として出生。宗広は和歌山藩大番頭格を務め,千広と号して《大勢三転考》を著す。宗光の幼名牛麿,江戸遊学ののち脱藩,陸奥陽之助と称し坂本竜馬のひきいる海援隊の一員として活躍。維新後政府に出仕,外国事務局御用掛から兵庫県知事,神奈川県知事をへて租税頭,大蔵少輔心得となるが,薩長の専制を憤って辞任,1875年元老院議官となる。78年立志社の政府転覆計画に荷担したとして投獄され,獄中にベンサムの《道徳および立法の諸原理》を《利学正宗》として翻訳。83年特赦により出獄すると外遊してL.vonシュタインに国家学を学び,帰国後外務省に出仕。88年駐米公使となりメキシコとの対等条約(日墨通商修好条約)とアメリカとの新条約調印を果たした。90年1月帰朝して第1次山県有朋内閣に入閣して農商務大臣となり,第1回総選挙(1890)に和歌山第1区から立候補し当選した。91年5月成立した松方正義内閣に留任し,内閣規約を提案,みずから政務部長となったが薩摩派との衝突で辞任した。11月後藤象二郎や大江卓,岡崎邦輔の協力をえて日刊新聞《寸鉄》を発刊して薩摩閥を攻撃し,みずからの列する松方内閣を批判,92年3月辞職して枢密顧問官となる。92年第2次伊藤博文内閣が成立すると迎えられて外務大臣となり,長年の懸案であった対等条約実現を期す。千島艦事件をめぐる領事裁判問題,防穀令事件をめぐる朝鮮との賠償交渉,議会における条約励行建議案にみられる排外気運の高揚などのなかでイギリスに新条約案を提示,条約改正会談を開始した。94年5月,朝鮮国に甲午農民戦争がはじまると清国の出兵に対抗して派兵し,7月16日日英通商航海条約の調印に成功した。一方,朝鮮では積極政策を展開し,23日朝鮮王宮占拠による親日政権の樹立,25日豊島沖海戦により日清戦争を開始した。この開戦外交はイギリスとの協調を維持しつつ,対清強硬路線をすすめる川上操六参謀次長の戦略と気脈を通じたもので〈陸奥外交〉の名を生んだ。日清戦争後薩摩派を中心とする膨張主義とそれに賛同した世論の圧力で下関条約で遼東半島を割取し,三国干渉を招いた。軍に制約された日清戦争の外交を詳記した《蹇蹇録(けんけんろく)》を持疾の肺患とたたかいつつ95年末脱稿したが,長く公刊を許されなかった。なお,試験採用による職業外交官の制度が確立したのは陸奥の外相時代である。
執筆者:藤村 道生
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「陸奥宗光」の意味・わかりやすい解説
陸奥宗光【むつむねみつ】
→関連項目海軍操練所|小村寿太郎|内地雑居問題|日米通商航海条約|日清戦争|原敬|星亨
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
新訂 政治家人名事典 明治~昭和 「陸奥宗光」の解説
陸奥 宗光
ムツ ムネミツ
- 肩書
- 外相,枢密顧問官,衆院議員(無所属)
- 別名
- 幼名=牛麿 通称=小次郎 陸奥源二郎 陽之助 号=福堂 士峰 六石
- 生年月日
- 天保15年7月7日(1844年)
- 出生地
- 紀伊国和歌山(和歌山県)
- 経歴
- 15歳で江戸に遊学3年。京都で勤王運動に参加、慶応3年脱藩し、坂本龍馬の海援隊に入った。鳥羽伏見の戦いが起こると岩倉具視に開国を説き、明治元年外国事務局御用掛となり、3年渡欧。神奈川県令を経て、5年大蔵省地租改正局長。7年薩長藩閥に抗して辞任。8年元老院議官に復帰、西南戦争に林有造らと反政府挙兵を企図したとして禁獄5年。16年赦され、17年渡欧。19年帰国して外務省に入り、21年駐米公使、23年山県内閣の農商務相、24年和歌山県から衆院議員当選。25年枢密顧問官、同年第2次伊藤内閣の外相となり、27年日英通商航海条約に調印して治外法権回収に成功した。日清戦争・三国干渉などの外交に従事、日清講和条約(下関条約)には伊藤とともに全権を務めた。28年伯爵。回顧録「蹇蹇録」がある。
- 没年月日
- 明治30年8月24日
- 家族
- 二男=古河 潤吉(古河財閥2代目当主)
出典 日外アソシエーツ「新訂 政治家人名事典 明治~昭和」(2003年刊)新訂 政治家人名事典 明治~昭和について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「陸奥宗光」の意味・わかりやすい解説
陸奥宗光
むつむねみつ
[没]1897.8.24. 東京
外交官,政治家。伯爵。和歌山藩士,本姓伊達。 15歳のとき江戸の安井息軒,水本成美に学ぶ。文久3 (1863) 年頃,坂本龍馬の知遇を得,のち海援隊に参加。慶応4 (68) 年1月外国事務局御用掛となり,イギリス公使 H.パークスの遭難事件など対外事件を処理。明治4 (71) 年廃藩置県による初の神奈川県知事,同5年地租改正局長,1875年元老院議官となったが,西南戦争に呼応して政府転覆計画に加担し,入獄。 83年出獄後欧米を巡り,88年駐米公使となり,在任中,初の平等条約である日墨通商修好条約に調印した。 90年山県内閣の農商務相,また衆議院議員となり,次いで松方内閣の農商務相,92年枢密顧問官。同年伊藤内閣の外相となり,対等条約の締結に尽力,94年イギリスとの条約改正交渉において,日英通商航海条約締結に成功。日清戦争ではイギリス,ロシアの中立化に成功し,下関講和会議には全権委員となり活躍。その高度な外交政策は日本外交の原点ともいわれ,当時の外交を語る著述『蹇蹇録 (けんけんろく) 』がある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「陸奥宗光」の解説
陸奥宗光
むつむねみつ
1844.7.7~97.8.24
幕末期の和歌山藩士,明治期の政治家。旧名伊達陽之助。幕末期に脱藩して坂本竜馬の知遇を得て海援隊に加わる。維新後,外務大丞・大蔵省租税頭・元老院議官などを歴任したが,西南戦争時に西郷軍に通謀した疑いで1878年(明治11)禁獄5年の刑をうけた。82年特赦されて欧米に渡り,88年駐米公使としてメキシコとの対等条約の締結に成功。90年第1次山県内閣の農商務相に起用され,第1次松方内閣にも残留,旧縁をいかして自由党・独立倶楽部に独自の影響力をもった。92年の選挙干渉問題で品川弥二郎内相と対立して辞任したが,第2次伊藤内閣の外相となり,治外法権の撤廃を内容とする条約改正を実現したほか,日清戦争の講和条約,三国干渉などの処理や議会対策に大きな成果を残した。伯爵。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「陸奥宗光」の解説
陸奥宗光 むつ-むねみつ
天保(てんぽう)15年7月7日生まれ。伊達宗広(むねひろ)の6男。坂本竜馬の海援隊に参加。維新後新政府につとめたが,明治10年の土佐立志社事件により5年の刑に服す。のち駐米公使,農商務相をへて,25年第2次伊藤内閣の外相。27年日英条約改正に成功し,同年の日清開戦から三国干渉にいたる難局に対処した。明治30年8月24日死去。54歳。紀伊(きい)和歌山出身。通称は陽之助。著作に「蹇蹇録(けんけんろく)」。
【格言など】他策なかりしを信ぜむと欲す(「蹇蹇録」)
旺文社日本史事典 三訂版 「陸奥宗光」の解説
陸奥宗光
むつむねみつ
明治時代の政治家・外交官
紀伊藩出身。海援隊に加わり,尊王攘夷運動に参加。1872年明治新政府の租税頭として地租改正の実施にあたり,初期議会では政党工作に腕をふるう。第2次伊藤博文内閣の外相として,'94年7月日英通商航海条約を締結し,領事裁判権の撤廃と税権の一部回復に成功。ひきつづき日清戦争前後の外交にあたり,下関講和会議に伊藤首相とともに全権として出席した。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
367日誕生日大事典 「陸奥宗光」の解説
陸奥 宗光 (むつ むねみつ)
明治時代の外交官。衆議院議員;伯爵
1897年没
出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の陸奥宗光の言及
【足尾鉱毒事件】より
…翌91年12月の第2議会で田中正造は鉱毒質問を行い,足尾鉱毒問題は全国に知れわたった。殖産興業政策の柱のひとつで重要な外貨獲得産業である産銅業の保護育成をはかっていた政府は,次男を古河の養嗣子にしていた陸奥宗光が農商務大臣だったこともあって鉱毒問題を重視し,その鎮静化のために被害民と古河との間に,わずかの補償とひき換えにいっさいの苦情を申し立てないことをうたった示談契約を締結させた。この示談工作と日清戦争の勃発により鉱毒反対運動は一時後退するが,96年9月未曾有の大洪水が発生し,鉱毒被害は栃木,群馬の2県から茨城,埼玉,さらには東京,千葉にも拡大したため,田中正造らは被害地の町村長や有志活動家を中心に鉱毒反対運動を再編強化し,〈対政府鉱業停止運動〉として確立させた。…
【皮∥革】より
…明治維新後,軍隊の洋式化が進み,多量の革製品が必要となった。最初の近代なめし技術の導入は,1869年(明治2)陸奥宗光によって,ドイツより技術者を招いて和歌山に製革伝習所を開設したのが始まりである。その後は急速に技術が進歩し,主として軍用品としての需要が増大し,皮革産業の発展をみるに至った。…
【蹇蹇録】より
…陸奥(むつ)宗光の著書。1895年10月,療養中の大磯で速記者に口述し,そののち推敲したものであるが,外務省の機密文書を引用した外交秘録であることから,当時一般に流布されることなく,秘密出版として![]() 少部数が作られた。…
少部数が作られた。…
【条約改正】より
…これまで改正交渉に消極的だったイギリスはロシアの極東進出を牽制するため,日本の好意を得ようと,交渉を受け入れる姿勢を示したが,大津事件(1891)で青木は引責辞任した。第2次伊藤博文内閣の外相陸奥宗光は議会の反対を防ぐため自由党と提携したが,改進党や国民協会は千島艦事件(1892)の責任追及のなかで対外強硬論をもりあげ,改正交渉を牽制した。陸奥は第5議会を解散して対外硬派を抑え,イギリスに外人排斥運動の取締りを保証した。…
※「陸奥宗光」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...