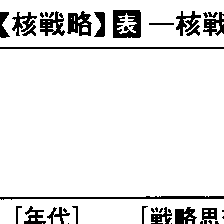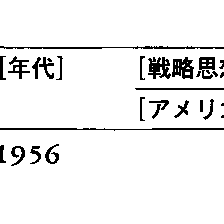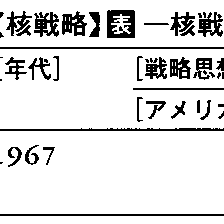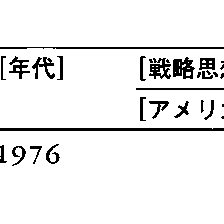改訂新版 世界大百科事典 「核戦略」の意味・わかりやすい解説
核戦略 (かくせんりゃく)
nuclear strategy
第2次世界大戦の終末期に広島,長崎で使用された核兵器は,在来の兵器に比べてけたはずれの破壊力を持つために,旧来の戦略思想を一変させた。核兵器はその巨大な破壊力のために〈究極兵器〉と呼ばれ,その使用は人類の破滅につながるので,戦争はできなくなったと見るものまでいた。しかし,第2次大戦後,核兵器は使用されなかったが,戦争は引き続いて発生してきた。核兵器は使用されなかったが,使用される可能性が存在し,核兵器によって国際政治は大きな影響を受けてきた。
核兵器の登場によって,平和と戦争の関係はあいまいなものとなった。過去において,軍事力は政治問題を解決する有効な手段であった。戦争の際,軍事力を行使して,相手の抵抗力を喪失させ,それによって自己の意思を実現することができた。現代では,核兵器は相手側の報復攻撃とその後の核の応酬へと発展しやすいため,その使用を避けねばならない。かつてのような軍事力の全面的使用はできなくなり,核兵器の使用可能性を示すことによって,相手の心理に働きかける手段となった。核兵器の登場とともに,在来型の軍事力にも核兵器と同じような性格が生じてきた。こうした状況のもとで,相手に対する働きかけは,軍事的手段だけでなく,政治・外交,経済,文化,心理など,他の手段も同時に使用されるようになった。
したがって核戦略とは,核兵器の構成,配備,運用などをめぐる軍事戦略というよりも,核兵器の存在を背景にした,国際政治に対する影響力の行使についての戦略といった性格が強まってきた。いまや核戦略とは,核をめぐる政策すべてを意味する言葉となり,単に軍事的な性格のものではなくなった。
国家戦略と核戦略
第2次大戦までの戦略論では,平和時において国家目標の実現をはかるための策略である政策(政略)と,戦争時において軍事力の有効な使用を図る戦略とに分けられて考えてきた。現在では,戦略とは,国家目標を実現するために国際間の諸問題をどのように解決していくかという政策(政略)の意味合いが強く,しかもそれは政治・外交,軍事,経済,文化など,国家の全機能を発揮する総合的方策と考えられている。これは〈国家戦略〉と呼ばれている。
現代の国家戦略は,国家目標を実現するため,あらゆる国力を動員する総合的政策の概念であるのとともに,軍事,経済,思想,文化などの国家機能について,その建設,維持,管理,運用などをめぐる部分的概念をも含んでいる。核戦略は,国家戦略の重要な部分を構成している。世界の軍備はすでに核兵器を組み込んだ体制になっており,冷戦下において米ソ両国はその圧倒的に優勢な核軍備によって世界を二分する支配力を確立してきた。米ソ両国はこの核軍備を背景にして国際政治に大きな影響力を行使してきており,両国にとっては核軍備の優位性の保持は国家戦略の重大な目標となっていた。米ソ両国が核軍備の優位性を求める戦略は,核軍備競争を激化させ,米ソ双方はもとより世界を破滅させるほどの核兵器を蓄積し,〈過剰殺戮(オーバーキル)〉と呼ばれるような状況を生んできたのである。
米ソの核戦略は,おのおのの同盟国の国家戦略にも複雑な影響を与えてきた。核時代に入って,東西の集団的安全保障体制が形成され,東西の同盟国はそれぞれ,その安全保障を米ソの核抑止力に依存してきた。同盟国は集団的安全保障による東西それぞれの結束を重視すればするほど,自国の独自性を放棄し,米ソそれぞれの世界戦略に協調することを余儀なくされてきた。米ソの圧倒的な核戦力のもとで,それぞれの同盟国はその主権の一部を放棄して米ソの戦略に協力し,その生存すら米ソにゆだねることを迫られていたともいえる。
抑止の思想
核戦略の基本となってきた思想は,米ソ両核超大国を含めて〈抑止deterrence〉である。核兵器は巨大な破壊力を持っており,この使用は人類の破滅につながる。したがって核兵器の使用は絶対に避けなければならない。しかし自国が核兵器を使わなくても,敵から核の先制攻撃を受ける可能性を否定できない。そこで核攻撃を受けた場合,敵に対して壊滅的な打撃を与える報復攻撃を行いうる態勢を整えることによって核戦争の発生を防止するというのが,抑止の思想である。抑止の思想は,1949年8月ソ連が原爆実験に成功,アメリカの核独占が終わり,米ソ間で核兵器競争の激化が見込まれ始めた1950年代に入って生まれた。抑止の思想は53年7月,まずイギリス総参謀長スレッサーJohn Slessor空軍元帥が採用,つづいてアメリカで国務長官ダレスが〈大量報復〉という形で導入した。それ以降,現在まで多くの核戦略理論が現れたが,すべてこの抑止の思想を中心に構築されてきている。
抑止とは〈相手が受け入れることのできないほどの有効な反撃が行われるという恐怖心を相手に起こさせ,その敵対行動を防ぐ措置〉(アメリカ統合参謀本部《軍事用語集》1979年版)と説明されている。そして,この抑止を成立させるためには〈能力,コスト,意図〉の三つの条件,すなわち(1)敵はわれわれがその行動をとる能力があることと納得し,(2)敵が得る利益よりもその行動をとることによる損害(コスト)の方が大きいことを知らせ,(3)われわれが主張したとおり行動する意思をもっていることの3点が重要とされている。
この抑止の思想に基づく戦略を〈核抑止戦略strategy of nuclear deterrence〉と呼び,核超大国の核報復力の強大さを示すことによって大規模戦争の発生を抑止するとともに,核超大国の相互間で核戦争を防ぎ,さらに小型の戦術核兵器で局地的な通常戦争の発生を抑止する戦略がとられている。抑止戦略は,こうした核兵器使用の脅威で戦争を抑止するとともに,戦争が発生した場合,最小限に被害を食いとめるための危機管理の政策も包含している。1970年代後半になって米ソ間の核戦力が均衡するのにともない,通常兵力による侵略の危険性がいわれ,この侵略に対抗して核兵器使用の危険性を低めるためには通常兵力の増強が必要だとする,〈通常兵力による抑止conventional deterrence〉の概念も提唱されるようになった。
核抑止論は,核兵器の巨大な破壊力と殺傷力によって相手を威嚇し,恐怖心を抱かせることによって,相手の行動を思いとどまらせる心理的ゲームである。威嚇や恐怖という心理状態はきわめてあいまいで,どの程度の質量の核兵器をもって威嚇すれば相手がどの程度の恐怖心を抱くかははっきりしない。恐怖心の量は,相手の心理状況や社会構造によっても大きく異なる。恐怖心には上限はないから,相手に与える恐怖をできるだけ大きくすることが必要になる。核兵器の増強によって相手の恐怖心を大きくしようとすればするほど,相手も同じように核兵器の増強を図っているに違いないという恐怖心が生まれ,それがいっそう核兵器の増強に走らせる。米ソ間の戦後の絶え間のない核軍拡競争はこうした心理状況を示していたといえる。
また核兵器は抑止のためで,実際には〈使われない兵器〉といわれてきた。しかし核兵器が〈使われない兵器〉となると,抑止の効果はあげられない。このために実際に使えるような戦略と核兵器が必要となる。限定的な核戦争の戦略がつくられ,核兵器も都市,工業地帯を攻撃して大量殺戮や大量破壊を行う戦略核のほか,局地的戦闘に使われる核砲弾,核地雷,核爆雷,短距離核ミサイルなどの戦術核兵器が開発されてきたのはこのためである。核抑止を強化しようとすればするほど,核兵器を現実に使える戦略と,核攻撃の被害を局限して現実に使用できる核兵器が必要となる。核抑止論は,核兵器は戦争の抑止のためで,現実に使用する兵器ではないと主張しながら,核兵器を現実に使用できるようにしなければ核抑止を強化できないという矛盾を内包していた。
各国の核戦略
アメリカの核戦略
アメリカの核兵器の独占は比較的に短期間で終わった。ソ連は1949年8月29日,原爆実験に成功,アメリカはこれに対抗して水爆(熱核兵器)と小型原爆(戦術原爆)の開発に着手,米ソ両国は核爆弾開発競争に入った。こうしたなかで,最初に登場した核戦略は,アイゼンハワー政権の〈ニュールック戦略new look strategy〉であった。この戦略では,戦略空軍を重視,侵略に対しては即座にかつ大量の核報復を行うというものだった。ダレス国務長官は54年1月,アメリカの戦略の基本を大量報復におくと宣言した。この戦略は〈大量報復戦略massive retaliation strategy〉と呼ばれ,その後のアメリカの核抑止戦略の原型となった。
1950年代後半になると,ソ連はアメリカ本土を直接爆撃可能な爆撃機を配備し,さらに中距離弾道ミサイル(IRBM)や大陸間弾道ミサイル(ICBM)の実験に成功,さらに57年10月には世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げ,核ミサイル時代に入った。アメリカの人工衛星計画バンガードは2度にわたって打上げに失敗,ソ連がミサイル技術で優位に立っているのではないかというミサイル・ギャップ論争も生まれた。ソ連の核戦力の増強に伴って,核による大量報復能力はアメリカの独占でなくなり,米ソいずれの側が先制攻撃を仕掛けても,相手側の核反撃を受けることを覚悟せざるをえなくなり,〈恐怖の均衡〉が認識され始めた。このために核による大量報復のおどしで局地戦争を抑止できないと見られるにいたった。そこで大量報復を修正して,小型核兵器を開発,限定的核戦争に備える態勢を重視した。これは〈ニュー・ニュールック戦略new new look strategy〉と呼ばれた。
1960年代に入って核戦力が整備されてくると,大量報復戦略への批判が表面化した。核兵器は破壊力が巨大で〈使えない兵器〉となっているので,局地戦争に対処するには在来の兵器で装備した通常兵力を重視すべきだという主張である。61年に登場したケネディ政権のマクナマラ国防長官は,全面核戦争から限定核戦争,通常兵力による局地戦争など,予想されるすべての戦争に対処することを考え,〈柔軟反応戦略flexible response strategy〉としてまとめあげた。この戦略は,脅威の性質に柔軟に対応する能力を持つことで,あらゆる種類の戦争を抑止することをねらっていたといえる。
この戦略において,マクナマラは核戦力については,敵の先制攻撃を受けても生き残れる非脆弱な核報復力を重視した。マクナマラは当初,敵の核戦力を攻撃する対兵力戦略counter-force strategyを重視していたが,ソ連の核戦力の非脆弱化にともなって都市・工業地帯を攻撃する対都市戦略counter-city strategy(対価値戦略counter-value strategy)を重視する方向に転じ,敵の核戦力を攻撃しアメリカの損害を限定するとともに,敵の奇襲攻撃を受けても生き残った核戦力で反撃して〈敵に受け入れられないほどの損害を与える能力〉を持つ必要があると考えた。これは〈確証破壊戦略assured destruction strategy〉といわれ,60年代以降の核戦略の基礎となった。
この確証破壊戦略に対しては当初から批判がでていた。この戦略のもとでは米ソ双方の都市・工業地帯を相手の核攻撃に対して脆弱にしておくことが核抑止を安定させることになるが,こうした政策は現実的でないとする批判や,一般市民の大量殺害に基礎をおいた政策で人道的でないばかりか,ソ連が軍事目標に対して限定的な核攻撃を行い,アメリカの一般市民の被害が限定されている場合,ソ連の都市・工業地帯への核攻撃を行って大量報復できるだろうか,などの疑問であった。こうした批判に対する核戦略の修正が1970年代以降に行われた。
確証破壊戦略の修正に着手したのは,1969年1月に登場したニクソン政権であった。ニクソン政権はニクソン・ドクトリンによって同盟国に対する防衛約束の縮小を図ったが,対ソ核戦力の均衡を重視して〈十分性戦略sufficiency strategy〉を提唱した。この戦略は,ソ連の都市・工業地帯に対する攻撃だけでなく,軍事目標攻撃をも考慮に入れたものであった。これはさらにニクソン政権の末期に国防長官となったシュレジンジャーによって発展をみた。シュレジンジャーは,戦略核攻撃のターゲッティング・ドクトリンtargeting doctrine(目標原則)の修正に着手,都市・工業地帯に対する核報復だけでなく,多種類の軍事施設を戦略核攻撃の目標とした。この戦略はのちに〈柔軟反応核戦略flexible strategic(nuclear)response〉と呼ばれている。この戦略の採用とともに,アメリカは対兵力戦略を重視し始め,なかでもコンクリートで防護されたミサイル・サイロ,指揮・管制中枢など硬化目標hard targetsの攻撃を重視した。
この政策は1977年1月に登場したカーター政権にも引きつがれ,戦略核攻撃の目標を核ミサイル,レーダー,潜水艦などの基地から指揮・管制中枢,核貯蔵施設まで広げた。同政権のブラウン国防長官は,ソ連の核戦力がミサイル数や破壊威力総計などで優位にあることを指摘して,〈ソ連の享受している戦力特質のどのような面も,アメリカが持つ他の有利な面で相殺することが必要だ〉と述べた。カーター大統領は1980年7月,核攻撃目標の変更を指令した大統領指令第59号(PD59)に署名し,この〈相殺戦略countervailing strategy〉の実施を確認した。
ニクソンの十分性戦略に始まり,シュレジンジャーの柔軟反応核戦略,ブラウンの相殺戦略まで一貫しているアメリカ核戦略の思想は,ソ連の核戦力の増強に対抗して,小規模・限定的な核攻撃から大規模な全面核戦争まで,予想されるいかなる態様の核攻撃に対しても対応できる選択肢を持ち,これによって核抑止を強化することを目ざしているといえよう。その核戦略理論は,核兵器体系の技術的進歩に対応したものといえるが,1966年以降の核ミサイルの多弾頭(MRV)化による運搬弾頭数の飛躍的増加や,誘導装置の改善による命中精度の向上などが,核ミサイル基地や指揮・管制中枢など,多数の軍事目標に対して正確な攻撃を行うことを可能にしたといえる。核兵器体系においては,戦略爆撃機,ICBM,潜水艦搭載弾道ミサイル(SLBM)の〈三本柱triad〉の均衡を重視している。
アメリカはその核戦略の変遷の背後で,核兵器技術開発の側面でソ連を絶えずリードしてきた。1950年代半ばに戦略爆撃機や原子力潜水艦を開発,1960年代初めに原子力空母,さらに1960年代末に多目標弾頭(MIRV)を開発し,ソ連はアメリカに5年から10年遅れて追随してきた。1980年代に入っても兵器開発の速度をゆるめず,レーガン大統領は81年10月,1980年代の核戦力増強計画を発表した。これは82-87年に2250億ドルを投じる計画で,新型弾道ミサイル(MX)トライデントII型SLBM,地上,空中,海上(中)発射巡航ミサイルの開発・配備を決めたものである。1983年末に戦略核兵器の弾頭数は約9000発の水準となったが,さらに増強を計画していた。戦略防衛の分野でも弾道ミサイル迎撃ミサイル(ABM)やレーザー兵器の開発が進められた。アメリカの新型核兵器の開発によって,目標攻撃の正確度はいちじるしく向上し,運搬核弾頭数も飛躍的に増加する。ソ連はこうしたアメリカの核戦力の増強を先制核攻撃能力の増加と見ており,米ソ間核軍拡競争の激化は避けられそうもない趨勢となっていた。
アメリカの核戦略のなかで注目しなければならないのは限定核戦争の重視である。レーガン大統領は1981年10月,ヨーロッパにおける限定核戦争の可能性を認め,83年11月から北大西洋条約機構(NATO)の決定に従って,西ドイツ,イギリス,イタリアへのIRBM(パーシングII型,地上発射巡航ミサイル)の配備を開始した。この措置はソ連のIRBM SS20配備への対抗措置であるとはいえ,当時ヨーロッパ各国はアメリカが限定核戦争を想定しているとの懸念を深めた。
アメリカの核戦力の増強の背後には,軍部と結んだ軍事産業の圧力があるといわれる。アメリカの主要軍事産業は約4000社で,1980会計年度の兵器調達費は830億ドルにのぼったが,このうち巨大兵器産業25社がその半額を受注した。軍産複合体は,軍事戦略,新兵器体系の開発,調達などに重大な影響を及ぼしており,核戦力の増強も新型核兵器の開発によって軍事産業の維持・拡大を図ろうとする巨大兵器産業界の意向が働いていたとの見方もできる。
核戦略のコラム・用語解説
【アメリカの核戦略用語】
- 大量報復戦略 massive retaliation strategy
- アイゼンハワー政権のダレス国務長官が1954年1月に発表した核戦略で,侵略が発生すれば侵略国に対して直ちに壊滅的打撃を与える報復攻撃を行うとの意図を明らかにし,それによって侵略を抑止しようというもの。アメリカ軍部でも朝鮮戦争休戦後の新しい戦略態勢の検討を行い,ダレス発言の前年の53年12月,ラドフォードArthur W.Radford統合参謀本部議長は,通常兵力を縮小して,核爆弾を搭載した戦略爆撃機を増強して,この報復力によってソ連の侵略を抑止することを提唱した。これは〈ニュールック戦略new look strategy〉と呼ばれたが,ダレス発言以後は大量報復戦略と呼ばれるようになった。この戦略は当時,アメリカ戦略空軍が圧倒的に優勢であったことを背景にしたものといえるが,50年代の後半にソ連の核戦力が増強されるのにともなって相互抑止の状態が生まれ,大量報復戦略による戦争の抑止がむずかしいと見られるにいたった。このために1957年ころから,ICBMやSLBMの開発と配備を進め,局地戦争の抑止のために戦術核兵器の開発と配備も行われた。この戦略は,戦略爆撃機を中心としたニュールック戦略を改めたものとして〈ニュー・ニュールック戦略new new look strategy〉あるいは〈ネオ・ニュールック戦略neo new look strategy〉と呼ばれた。
- 段階的抑止 graduated response
- 侵略に対して,直ちに全面的な核報復を行うのではなく,侵略の程度や態様に対応した適切な核使用を考えようという戦略で,こうした能力を持つことが核抑止の信頼性を高めるとした。この戦略では,戦略核兵器と戦術核兵器を区別し,戦略核を対ソ報復力として保持しながら,戦術核の局地的な核使用を段階的に行うことを考えた。ソ連の核戦力が増強され,相互抑止の状況が生まれた1957年,イギリスのアンソニー・バザード卿Sir Anthony Buzzardやアメリカのキッシンジャー(のちニクソン政権の国務長官)などによって提唱された。
- 柔軟反応戦略 flexible response strategy
- ケネディ政権が1961年に採用した戦略で,ゲリラ戦争から限定的核戦争,全面的核戦争にいたるまで,あらゆる段階の戦争に対処する能力を保有し,それによって戦争を抑止しようというもの。限定的な攻撃に対しても大量報復でしか対応できないというアイゼンハワー政権の大量報復戦略の硬直的姿勢では戦争を抑止できないとして,各種の戦争の形態に対応できる軍事力を保有することで,敵の出方によって対応できるような柔軟性の保持を狙ったものである。この戦略は段階抑止の思想と同じで,種々の異なった状況に対応できる能力を持つことを主眼としている。ケネディ政権以降,アメリカの戦略の中心的思想となっている。
- 損害限定 damage limitation
- 戦争が発生した場合,相手の核攻撃によって受ける損害を最小限に限定しようという戦略で,1964年1月27日,マクナマラ国防長官によって発表された。この戦略は,ソ連の核戦力が発射される前に攻撃を加えて破壊することが必要となるため,アメリカの核戦力を増強して攻撃目標をソ連の核戦力とすること,ソ連の核ミサイルや爆撃機の攻撃に対して防衛するためのABMや迎撃機,防空ミサイルを強化すること,一般市民の損害を限定するためにシェルター(退避壕)の整備を図ることなどをおもな骨子とした。マクナマラによってその翌年に発表された確証破壊戦略と表裏一体をなすもので,確証破壊戦略は攻勢的側面,損害限定戦略は防勢的側面についての戦略ということができる。
- 確証破壊戦略 assured destruction strategy
- 相手から組織的かつ大規模な核攻撃を受けても,その核攻撃から生き残った核戦力によって相手に対して壊滅的打撃を与える報復能力を持とうという戦略。この戦略は1965年2月18日,マクナマラ国防長官によって発表されて以来,アメリカの戦略核戦力の水準を決める基礎的な考え方となってきた。マクナマラは,アメリカがソ連の組織的かつ大規模な核攻撃を受けたのちでも,ソ連の人口の4分の1ないし3分の1,工業能力の3分の2を破壊する能力を保有することを提唱したが,67年にはその能力は人口の5分の1ないし4分の1,工業能力の半分ないし3分の2に縮小された。マクナマラはこうした確証破壊戦略をとる理由として,(1)この確証破壊の水準を超えた場合,アメリカの核戦力を増強してもソ連に与える損害は逓減する,(2)一方,この水準を下回ると,ソ連の指導者が無分別ないし自暴自棄となった場合,その行動を抑止するのに十分でないかも知れない,の2点をあげた。
- 十分性戦略 sufficiency strategy
- 1969年1月に発足したニクソン政権の核戦略で,米ソ間の核戦力がほぼ均衡し,相互抑止の状態が生まれているとの認識のもとに,軍事的には核戦争を抑止し,政治的にはアメリカと同盟国に対する威圧を防ぐのに十分な核戦力を維持しようというもの。ニクソンは71年2月25日に発表された外交教書のなかで,〈いかなる大統領であれ,一つの戦略的決定しかないということがあってはならない。特に敵の民間人,工業を大量に破壊することしか選択がないということでは困る〉と指摘,アメリカの戦略計画の策定にあたって対都市戦略だけではなく,軍事目標を攻撃する対兵力戦略をも考慮に入れることを提唱した。この意味で,十分性戦略は確証破壊戦略に基づく報復能力以上の核戦力を求めたものといえる。
- ターゲッティング・ドクトリン targeting doctrine
- ニクソン政権末期に国防長官に任命されたシュレジンジャーが1974年3月に発表した国防報告の中で明らかにした戦略核攻撃の目標選定についての原則。大量報復や確証破壊戦略では,ソ連の都市・工業地帯に壊滅的打撃を与えることが戦略の中心であったが,シュレジンジャーはこれを改め,都市・工業地帯を目標とするのとともに,ソ連の核ミサイル基地や指揮・管制中枢などの軍事目標をも選別的に攻撃する能力を持つ必要があるとした。つまり,こうした選別的に攻撃する能力を持たないと,ソ連がアメリカの都市・工業地帯への攻撃を避けて軍事目標に攻撃をしかけた場合,都市・工業地帯への大量報復で対応するのか,あるいは何もしないかの二者択一の選択しかないことになり,ソ連の限定的な核攻撃に対処できなくなるとした。このターゲッティング・ドクトリンに基づいて,アメリカは核攻撃の目標を迅速に転換するための指揮・管理体制の改善,ミサイルの目標攻撃の正確性の向上,弾頭威力の改善などを行った。シュレジンジャーのターゲッティング・ドクトリンは,敵の核攻撃に対して大量報復か否かといった硬直的な姿勢を改め,敵の出方によって柔軟に対応できる態勢をつくろうというもので,柔軟反応戦略を核戦略の分野に適用したものといえ,〈柔軟反応核戦略flexible strategic(nuclear)response〉とも呼ばれている。
- 相殺戦略 countervailing strategy
- カーター政権のブラウン国防長官が1978年1月に発表した国防報告の中で明らかにしたもので,〈ソ連が享受しているどのような戦力特質も,アメリカの他の有利な側面で相殺する〉戦略を指す。この戦略は主として,ソ連の核戦力が数量的に見てアメリカに対して優位であるのを,アメリカの質的優位で相殺することを意味している。この相殺戦略は,都市・工業地帯に対する確証破壊能力を保持しつつ,敵の核戦力,通常兵力,兵站(へいたん),戦争支援産業,航空基地,核貯蔵施設,指揮・管制中枢,ミサイル基地など,広範囲にわたる目標を選別的に攻撃できる能力を持つことを主眼としたもので,シュレジンジャーの提唱したターゲッティング・ドクトリンとほとんど変わらないものといえる。
- 大統領指令第59号 presidential directive 59
- PD59と略す。1980年7月25日,カーター大統領が署名した大統領指令で,アメリカの対ソ核攻撃の立案にあたって,ソ連の都市・工業中枢の破壊とともに軍事目標攻撃の有効性向上に重点をおくよう指示したもの。これはシュレジンジャーのターゲッティング・ドクトリンを正式に成文化したもので,都市・工業施設とともに通常軍事目標(飛行場,軍事基地,港湾,鉄道操車場など)のほか,指揮・管制中枢,ICBMのサイロ,地下掩体壕,レーダー施設,兵舎なども攻撃目標に加えられている。
- 対都市戦略 counter-city strategyと対兵力戦略 counter-force strategy
- 敵の都市や工業中枢を核報復の目標とし,敵の先制攻撃を受けた場合,主として都市・工業地帯に対して最大限の核攻撃を加える戦略を対都市戦略という。この戦略は,国としての存立に最も重要な価値を持つ人口や工業能力を攻撃目標としているために〈対価値戦略counter-value strategy〉とも呼ばれている。これに対して,敵の核戦力や通常戦力などの軍事能力を核攻撃の目標として,敵の攻撃を受けた場合,軍事目標に対して核攻撃を加えるのを対兵力戦略という。こうした戦略思想が生まれたのはマクナマラ国防長官時代で,マクナマラの核戦略は当初,対兵力戦略を重視した。マクナマラは敵の攻撃を受けてもアメリカの核戦力が破壊されにくく,敵の残存核攻撃力を破壊できるような非脆弱な第2撃(報復)能力の保有を考えた。しかし,ソ連の核ミサイルが堅固に防衛された地下サイロに収納されるなどの非脆弱化が進むにつれ,第2撃によって残存ミサイルを破壊することは不可能だと考え,確証破壊戦略を採用して対都市戦略を重視するようになった。しかしニクソン政権の十分性戦略やターゲッティング・ドクトリン,相殺戦略では,敵の軍事施設を選別的に破壊する対兵力戦略が重視されている。これは,ソ連が核戦力を増強してこうした能力を保有するにいたったので対抗措置をとる必要があると考えたのとともに,核兵器技術の進歩によってABMを突破するMRVや,個々の目標を正確に攻撃できるMIRVが開発され,核ミサイル基地を正確に攻撃する能力を持つにいたったことが大きく影響している。
- 第1撃能力 first strike capabilityと第2撃能力 second strike capability
- 先制核攻撃によって敵の戦略核戦力を無力化する能力を第1撃能力と呼び,敵の核による先制的な奇襲攻撃を受けても生き残った核戦力で敵に報復攻撃を行い,壊滅的打撃を与える能力を第2撃(報復)能力という。また,戦争が発生した場合,敵よりも先に核兵器を使用することを先制使用first useと呼び,先制核攻撃で敵の戦略核戦力を無力化する第1撃能力と区別している。アメリカの核戦略は伝統的に第2撃能力を重視し,敵の攻撃に非脆弱でかつ十分な第2撃能力を保有しないと,ソ連が第1撃によってアメリカの核戦力を破壊する誘惑にかられ,核抑止は不安定になると主張している。しかしニクソン政権以降,対兵力戦略を重視し,ソ連の核戦力に対して選別的に攻撃できる能力を強調しており,第2撃能力重視の政策の修正として論議を呼んでいる。
ソ連の核戦略
ソ連の核戦略は,アメリカのように明白な核抑止理論を打ちだしていないが,ほぼアメリカの核戦略を追っており,アメリカの第1撃から生き残り,しかもアメリカに耐えられないほどの報復を行える非脆弱な戦略核戦力の確保を目ざしていたと考えられる。1949年8月に最初の原爆,つづいて53年8月に水爆実験を行ったソ連は,57年8月には世界最初のICBMの実験を行い,次いで59年12月には戦略ロケット軍を創設した(上掲の表参照)。フルシチョフ第一書記兼首相は1960年1月の最高幹部会議の演説で,核ロケット第一主義を主張し,当時の総兵力362万人から120万人を削減することを決定した。しかし61年夏のベルリン危機とともに120万人削減を中止した。
64年10月,フルシチョフ失脚のあと登場したブレジネフ書記長は,フルシチョフの核ロケット第一主義をすて,通常軍備を重視する方向に転じた。これは1961年にアメリカでケネディ政権が登場し,柔軟反応核戦略に移行し通常兵力増強に重点がおかれたことに対応した措置と考えられよう。64年8月に廃止された地上軍総司令部が67年秋に復活,そのころから通常戦力重視の論文が多く見られるようになった。60年代に発表されたソコロフスキーVasilii Danilovich Sokolovskii元帥らの《軍事戦略》では,62年の初版,63年の第2版では〈現在の大量の軍事力の基幹は戦略ロケット軍になろう〉と述べていたが,第3版ではこの表現を訂正し,核戦力も通常戦力もともに重要との立場をとった。
ソ連は1960年代中ごろから急速な核戦力増強に乗りだした。66年4月の第23回党大会では,マリノフスキー国防相が〈あらゆる種類の核弾頭のストックを増大し,これを使用するための装備を用意した〉と報告,戦略ロケット軍の充実を誇示した。アメリカ側の資料によると,60年代末にはICBM数でアメリカを追いぬき,SLBM数でアメリカに迫るほどになった。こうした核戦力の均衡が69年11月からの第1次戦略兵器制限交渉(SALT Ⅰ)開始を可能にしたといえよう。
1972年にSALT Ⅰが妥結して,戦略兵器に数量的上限が設けられるのとともに,戦略兵器の近代化計画が急進展した。74年には4種類の新型ミサイルの実験を行い,翌75年にかけてSS17,18,19の作戦配備を開始,同年からMIRⅤ装備のミサイル配備が始まった。SLBMの分野でも1972年にデルタ級新型原子力潜水艦の配備を開始したのにつづいて,80年には排水量3万トンのタイフーン級原子力潜水艦の1号艦が進水,83年には作戦配備された。いずれも長射程のSSN8,同18などのミサイルを搭載する。アメリカに比べて遅れていた戦略爆撃機の分野でも,新型のブラックジャック(NATO呼称)の試験飛行が83年から行われた。このほか,戦略核兵器と戦術核兵器の中間の分野で新型兵器の開発が行われ,1975年から中距離爆撃機ツポレフTu26バックファイアの配備が始まり,77年からは射程5000kmで,MIRⅤ3発を装備した機動型のIRBM SS20の配備が始まり,1983年にはバックファイア180機,SS20は360基の水準に達した。
アメリカでは,ソ連の核戦力の増強とともに,ソ連の核戦略についての懸念が高まった。アメリカ側の懸念は,ソ連の核戦略は核兵器による戦争の抑止よりも,核兵器を戦争遂行の手段と見て,核戦争で勝つことを考えているのではないかという点であった。ソ連の核戦力の増強にともなってアメリカには,地上に固定配備しているICBMはソ連が先制核攻撃を加えた場合,その大部分は破壊される可能性が強まったという懸念が強く,アメリカが核軍拡を進める大きな理由になった。
イギリスの核戦略
イギリスは1952年10月,オーストラリアのモンテ・ベロ諸島で初の核爆発実験を行って以来,独自の核戦力保持の道を歩み始めた。核戦力は,液体燃料のIRBMブルーストリークの開発から,アメリカのスカイボルト・ミサイルの導入へと変わり,1962年にポラリス・ミサイル搭載原子力潜水艦の導入を決定した。80年代半ばの時点では,アメリカのポラリス・ミサイル(核弾頭はイギリス独自のもの)搭載の原子力潜水艦4隻(各16基のミサイル搭載)を基幹にしていたが,90年代には旧式化したポラリスにかえて,アメリカ製のトライデント・ミサイル搭載原子力潜水艦に更新する計画を進めた(97年現在,3隻の原潜に48基のトライデントを配備)。
イギリスが独自の核戦力を保有する理由について1980年のイギリス国防白書は,〈米ソ間の核戦力が均衡している現在,ソ連は,アメリカが自国への核攻撃を恐れて,ヨーロッパのために核使用する決意がぐらつくと考えるかもしれない。ヨーロッパが独自の核を持つことは,こうした誤った見方をしないようにさせる有力な保障となる〉と述べている。イギリスは独自の核戦力を持つことによって,ヨーロッパにおける核抑止に貢献するとともに,ヨーロッパに対するアメリカの核の保障を確実にすることを求めていたといえる。
イギリスの小規模な核戦力は最小限抑止minimum deterrenceの戦略に基礎をおいたもので,ソ連が西欧の主要都市に対して核攻撃を行った場合,イギリスがソ連に対して報復攻撃を行い,ソ連に対しても耐えがたい被害を与えることに主眼をおいている。ソ連の50都市を攻撃することによってソ連の人口の20%,工業能力の40%を破壊できる。こうした能力を持つことによって,ソ連の核攻撃は抑止できると考えたわけである。
フランスの核戦略
フランスの核戦力開発は,アメリカとの協力のもとで核軍備を進めたイギリスとは異なって,一貫して独自の道を歩んだ。特に1958年6月,ド・ゴール政権が成立したのちは,独自の核武装を求めた。1960年2月,サハラ砂漠で最初の核実験に成功,同年12月には核武装法の成立を見た。ド・ゴール大統領の国防方針は,〈フランスの防衛はフランス自身のものでなければならない。有事の際は,他の国々と同盟するだろうが,防衛はフランス自身のために,その責任と独自のやり方で防衛されねばならない〉というものであった。この方針を受けてアイエールCharles Aillere参謀総長は67年,ソ連だけを仮想敵国とする戦略を否定して,〈一つの方向だけでなく,あらゆる方向に対して介入できる能力を持たねばならない〉とする〈全方位戦略défense tour azimuts〉を提唱した。この戦略の背後には,フランス独自の核戦力保持の狙いがあった。
フランスの核戦力は,地下サイロから発射するIRBM SSBS18基,SLBM16基搭載の原子力潜水艦5隻,ミラージュⅣA型爆撃機34機などで構成されている。フランスの核戦略もイギリスと同じく最小限抑止戦略をとり,対都市攻撃に目標をおいている。フランスは独自の核武装を進めるなかで,1966年7月,NATOの軍事機構から脱退した(95年12月部分的に復帰。これについては〈NATO〉の項参照)。
中国の核戦略
中国は1964年10月,最初の核爆発実験に成功,米ソ英仏につづく5番目の核保有国となった。さらに67年6月には初の水爆実験を行い,70年4月には人工衛星を打ち上げ,80年5月には南太平洋へ向けてICBMの実験を行うなど,核戦力の整備につとめてきた。80年代半ばの中国の核戦力は4基のICBM T5,10基のIRBM T3,50基の同T2,50基のMRBM(準中距離弾道ミサイル)T1を中心に構成されていた。
中国は核保有国になったのちも人民戦争戦略を主張し,侵略に対しては人民の海の中でゲリラ戦を戦うというのが基本となっている。中国の核戦力を改善していくとしても,米ソに対抗できるようになるのはかなりの長期間を要する。そこで中国の核戦力は質量とも長期にわたって対ソ劣勢がつづくと予想しなければならない。この劣勢を補うのが人民戦争戦略である。
中国の核戦略は最小限抑止の戦略に基づいたものと見られる。当面の敵であるソ連が,その圧倒的に優勢な核戦力で攻撃すれば,中国の核戦力のかなりの部分は破壊される。しかし少数の核ミサイルでも生き残れば,ソ連の都市に攻撃をかけることができる。ソ連は,限定的にせよ中国の核報復による被害を予期しなければならないとすれば,中国に対する行動は慎重にならざるをえないとの見方に立つということである。中国はこうした最小限抑止の戦略に立って,ソ連の先制攻撃に対して核戦力の残存性を高めるため,SLBMの開発を進めた。
NATOの核戦略と西ドイツ
NATOに加盟した諸国のうち,米英仏3国のほかは核兵器を保有しておらず,また1992年に条約に参加したフランスを除く諸国は核不拡散条約に早く参加していた。NATOが49年4月に創設され51年初めに統一軍事機構が成立した当初の戦略は大量報復であった。ソ連の大規模な侵攻に対しては即座にアメリカの核戦力で壊滅的な打撃を与えることを基本とした。ソ連の核戦力の増強とともに大量報復戦略の見直しが始まり,57年12月にパリで開かれた首脳会談で,ヨーロッパにアメリカの核弾頭装着のIRBMを配備することを決定した。1960年代になって,英仏両国が独自の核武装をする動きを見せ,これを懸念したアメリカは,自国製核ミサイルを提供して他のNATO諸国が兵員,艦艇を供出してつくりあげる〈多角的核戦力multilateralnuclear force構想〉を打ちだしたが,英仏両国が消極的で結局,立消えとなった。
その後もヨーロッパにおける核戦力問題の検討がつづけられてきたが,1967年12月,NATOは柔軟反応戦略の採用を決定した。この戦略はNATOの戦力を通常兵力,戦術核,戦略核の3本柱で構成し,通常兵力による侵略に対しては通常兵力で対抗するが,それが持ちこたえられなくなった場合,戦術核,戦略核の使用へと段階的にエスカレーションさせるというものである。また通常兵力で優勢なワルシャワ条約軍(ソ連・東欧)に対抗するために核先制使用の可能性を否定していない。この柔軟反応戦略はその後もNATOの戦略の基礎となった。核戦略を検討するため,NATOは核防衛問題委員会と核計画グループを設けたが,このうち核計画グループは核戦略を計画するもので,アメリカ,イギリス,西ドイツ,イタリアの4ヵ国が常任,3ヵ国が非常任で他の加盟国から選ばれた。
NATO加盟国のなかで西ドイツは,東西対決の正面に位置するための自国の安全保障に深刻で,NATOの核戦略への参加を求めてきた。西ドイツはその再軍備にあたって,西側諸国との間で1954年10月にパリ条約を締結したが,同条約は西ドイツに対してABC(原子,生物,化学)兵器の生産・保有を禁止している。このため西ドイツは自国内にアメリカの核弾頭7000発(1980年に6000発に削減)と核運搬手段として戦闘爆撃機,パーシングⅠ型地対地ミサイルの配備を認め,アメリカの核保障を確実にする手段を講じた。
NATOは1979年12月,ソ連が最新型のIRBMSS20の配備を開始したのに対抗して,アメリカ製のパーシングII型108基,巡航ミサイル464基,合計572基を配備するとともに,米ソ間で中距離核戦力の削減交渉を行う〈二重路線〉を決定した。
中立国の核戦略
ヨーロッパで中立政策をとっているスイス,スウェーデン両国は,米ソいずれのブロックにも属さず,したがっていずれの核による保障も得ていない。また両国は1968年には核不拡散条約に調印,核兵器を保有・製造しない方針を明らかにしている。両国は〈総力防衛〉の防衛政策のもとで,侵略に対しては全国民を動員して国内で抵抗する防衛戦略をとり,核攻撃に対してはシェルター(退避壕)による民間防衛を重視する特殊な対抗策をとっている。
1960年代,スイス,スウェーデン両国で核兵器の保有をめぐる論争が行われた。両国とも,小規模な核報復力を持つことは周辺諸国を挑発することになるのでかえって危険であると考えた。しかし戦術核兵器の保有については意見が分かれた。保有論者は,戦術核の配備によって侵略者の侵略にともなう犠牲を大きくすることができるうえ,侵略者側の兵力集中をむずかしくし,核使用の危険性を低めることができると考えたのに対し,反対論者は核配備が侵略者側の核使用と先制核攻撃の危険を高めると反論した。スイスは1962年4月,核保有について国民投票を行ったが,核兵器保有を無条件で放棄する政府案は拒否された。
両国が力を注いだのは,核攻撃から市民を守るシェルター建設であった。スイス,スウェーデンとも,中立政策をとる両国に対して,どちらかのブロックを支持させるための核脅迫はあっても,全土を破壊するような核攻撃の起こる可能性は低いと見て,両ブロック間の核戦争が市民生活に影響する可能性を重視していた。スイスでは全国民の半数以上の350万人,スウェーデンでは70%の550万人を収容するシェルター建設など,核爆発や放射性物質から市民を保護する態勢のほか,燃料,食糧などについても国民生活を長期間まかなえる備蓄を推進した。
日本の非核政策
広島,長崎の原子爆弾による惨禍を経験した日本は,国民の核兵器に対する強い拒絶反応を背景とした〈核兵器を持たず,作らず,持ち込ませず〉の非核三原則を核政策の基本においている。NATOに加盟している西ドイツが,核兵器の保有・製造を放棄しながら自国内にアメリカの核兵器を配備することで安全を確保しようとしたのに対し,日本は日米安保体制のもとにおかれているが,核兵器の保有・製造はもとより,アメリカの核兵器の配備をも認めず,対照的な非核政策をとっている。
日本政府は戦後一貫して日本が核武装する意思のないことを表明し,アメリカの核兵器持込みも認めない方針をとってきた。この政策を〈非核三原則〉にまとめて提示したのは1967年12月11日,衆院予算委員会における佐藤栄作首相の答弁であった。この非核三原則は71年11月24日,沖縄返還協定の審議とからんで国会決議され,〈国是〉ともいえる位置を占めている。防衛政策の側面から見ると,1957年5月20日,国防会議(議長岸信介首相)が〈国防の基本方針〉を定め,侵略に対して〈米国との安全保障体制を基調としてこれに対処する〉とした。防衛力整備の上で核兵器との関連を明白にしたのは61年7月に決定された第2次防衛力整備計画で,同計画は防衛力整備の目標を〈日米安保体制のもとに,在来型兵器の使用による局地戦以下の侵略に対処する〉と定めた。政府は平和憲法の趣旨からいって,他国に脅威を与えるICBMや長距離爆撃機は保有できないとの立場をとっている。
日本の非核三原則の問題点は,米軍による核持込み問題のあいまい性である。1960年11月に調印された新安保条約では事前協議制が設けられ,在日米軍に関して,(1)配置の重要な変更,(2)装備の重要な変更,(3)戦闘作戦行動について,日米間で事前協議を必要とすると定めた。装備の重要な変更とは,核持込みを意味すると理解されている。米軍による核持込みについて疑惑が持たれてきたが,1981年5月,ライシャワーEdwin Oldfather Reischauer元駐日大使が〈核兵器を積んだアメリカの航空母艦と巡洋艦が日本に寄港したことがある〉と発言,波紋を広げた。同元大使は〈核持込みとは,日本領土内に陸揚げしたり,あるいは貯蔵することを指している〉と述べ,核搭載艦船の寄港や領海通過,同航空機の領空の通過は別問題とした。日本を基地としてきた米軍のなかでは,航空母艦ミッドウェーが核攻撃可能の航空機を搭載しているほか,水上艦艇にも核兵器搭載能力を持つものがある。また在日米軍基地には戦略爆撃機や原子力潜水艦に対する支援機能を持つものもあり,米軍基地を核と通常兵力用にはっきりと区別することはむずかしくなっている。
日本政府は日米安保体制のもとで,アメリカの〈核の傘〉の下に入っているので,日本に対する核脅迫や核攻撃をアメリカが抑止する責任を負っていると主張してきた。アメリカ政府もまた,日本に対する核保障を強調してきた。しかし米ソ両国の核戦力がほぼ均衡し〈相互確証破壊〉の状況が予想されるようになってから,日本など同盟国に対する核攻撃に対して,アメリカがはたして自国に対する核攻撃を覚悟して同盟国のために核報復するだろうかという疑問が生まれた。米ソ間で1973年6月,核戦争防止協定が締結され,核戦争の危険が生じたときには緊密に協議することが定められたが,これは同盟国に対する核保障を否定したものではないかという疑念を強めた。またソ連は1977年からIRBMのSS20の配備を開始,これに対抗してアメリカも83年末からヨーロッパにパーシングⅡ型などのIRBMを配備する対抗手段をとった。これは米ソ両核大国を聖域として核戦争から除外し,米ソの本土以外のヨーロッパなどの地域で核戦争を行おうとしているのではないかとの批判を呼んだ。このように米ソの核戦力が均衡し核兵器が使いにくくなればなるほど,米ソ両国が同盟国にさしかける〈核の傘〉は弱体化していった。
冷戦終結後の核戦略
冷戦の終結と核軍縮の進展
1990年代初頭には,第2次世界大戦後の戦略秩序の基盤となっていた〈米ソ超大国が支配する二極構造〉の崩壊がはっきりした。1989年後半には,ソ連が主導するワルシャワ条約(WTO)加盟の全6ヵ国では民衆の圧力によって民主化が進展し,社会主義政権は崩壊した。1990年10月3日には東西ドイツの統一が実現し,同年11月19日,東西両同盟の首脳がパリに集まり,〈ヨーロッパにおける対立と分断の時期は終了した〉と宣言した。翌91年8月,ソ連では保守派によるクーデタが失敗し,それがきっかけとなって同年12月,ソ連はロシアなど15共和国に解体された。
東西冷戦の終結とそれに続くソ連の解体によって,アメリカと旧ソ連(ロシア連邦)との間の核軍縮交渉は急速に進展した。1980年代初めからアメリカと旧ソ連との間で続けられてきた中距離核戦力(INF)交渉は1987年12月,レーガン大統領とゴルバチョフ書記長との米ソ首脳会談で長射程および短射程のINF(ミサイル数はアメリカ867発,ソ連1836発)の廃棄を決定した(INF全廃条約)。これは米ソ双方が保有していた核兵器の約5分の1に相当するものであったが,限定された射程の核ミサイルとはいえ,米ソ両国が核兵器の廃棄に合意したのはこれが初めてであった。
米ロ両国は1991年7月,戦略兵器削減条約(START Ⅰ)に署名し,同条約発効後7年以内に双方が戦略運搬手段数1600基機,核弾頭数6000発(うち弾道ミサイル弾頭数4900発)を上限とすることに合意した。これは米ロ両国が当時,保有していた戦略核弾頭数を約半数に削減しようというもので,史上初めての戦略核兵器の削減として画期的なものであった。
米ロ両国はこれに続く第2次戦略兵器削減条約(START Ⅱ)に取り組み,1993年1月には戦略弾頭数をSTART Ⅰ条約発効後7年間で総数3800~4250発に,さらに2003年1月までに3000~3500発に2段階に分けて削減することに合意した。START Ⅱは複数弾頭装備大陸間弾道弾(MIRVed ICBM)の全廃を含め,米ロ両国の戦略核弾頭数を冷戦終結時の約3分の1に削減しようというものである。(1994年12月発効)
START Ⅰ条約の発効にともない,アメリカは96年1月,START Ⅱ条約についても批准を完了したが,ロシア議会ではSTART II条約がロシアの核戦力の中心である複数弾頭装備ICBMの全廃など,ロシアに不利な条件となっているなどを不満として,97年末現在もなお批准を終えていない。このため,97年3月,ヘルシンキで開かれたクリントン,エリツィンの米ロ両大統領による首脳会談で,アメリカ側はロシアにSTART Ⅱ条約の早期批准を求め,同条約が発効すれば第3次戦略兵器削減交渉(START Ⅲ)を開始することを提案,ロシア側もこれに同意した。START Ⅲでは米ロの戦略核弾頭数を2007年までに2000~2500発に大幅に削減することをおもな内容としている。
→軍縮 →戦略兵器制限交渉
冷戦の終結と核戦略の変容
米ロ間の戦略核兵器を中心とした核軍縮の進展にともなって,米ロ両国の核戦略は大きく変容した。ソ連の解体後,米ロ両国の核戦略の力点は,冷戦期のように米ソ間で査察可能な措置を通じて核戦力の均衡を図ることではなくなり,大幅かつ一方的で,互恵的な核軍縮を行うこと,削減される兵器の安全・厳重な管理,ならびに第三世界を中心とした核・生物・化学兵器などの大量破壊兵器の拡散防止に重点が置かれるようになった。
戦略核兵器以外の戦術核兵器の分野でも,アメリカは1991年9月17日,戦術核兵器の全面的配備の変更を発表,旧ソ連(ロシア)もアメリカに見合う核軍縮を発表した。米ソ両国は地上に配備する短距離核ミサイル,核砲弾をすべて廃棄し,海洋配備の戦術核兵器の50%を廃棄し,残りの50%は地上に撤収すること,航空機搭載の核兵器も半分に削減するなどを発表した。イギリスも同様な措置を取り,フランスも戦術核ミサイルの近代化計画を縮小することを発表した。
戦略核兵器についても,米ソ両国は戦略爆撃機の24時間警戒態勢を解除し,大陸間弾道核ミサイル(ICBM),潜水艦搭載核ミサイル(SLBM)の一部も警戒態勢を解除することを発表した。また,米ソ両国は冷戦期,戦略核兵器の攻撃目標を相手国の都市・軍事目標に設定して即時に攻撃できる態勢をとってきたが,1994年1月,クリントン,エリツィン両大統領による米ロ首脳会談で,これを解除することに合意した。また中国・ロシア間で94年9月に核攻撃目標解除に合意し,その後,米中間でも同様の措置に合意した。
核保有国は米,英,仏,ロシア,中国の5ヵ国に限定されたが,これに加えてイスラエル,インド,パキスタンはすでに核兵器を取得もしくは生産する能力をもっており,リビア,イラン,イラク,北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)なども核兵器取得の動機のある国と見られている。第三世界のこれらの国々では核兵器のほかに生物・化学兵器や運搬手段として弾道ミサイルの拡散が懸念されている。
冷戦後の米ロの核戦略態勢
アメリカのクリントン政権は1994年9月,冷戦終結後の核戦略態勢についての検討の結果を〈核態勢の見直し〉として発表した。この報告では,アメリカの核戦略の基本を核軍縮の〈先導〉の役割と,ロシアの脅威の再燃に対する〈防止措置〉の役割の二つにおき,ロシアとの核軍縮の進展や国際情勢に対応して,核戦力の水準を定めるとの慎重な姿勢をとっている。
戦略防衛については,海外駐留米軍や同盟国を戦術・戦域弾道ミサイルから防衛するための戦域ミサイル防衛(TMD)を最優先で開発することにしている。またアメリカ本土を長射程の弾道ミサイルから防衛する国家ミサイル防衛(NMD)については,将来の脅威に備えて技術開発を継続することにしている。
ロシアは1993年11月,国防政策の基本理念として〈ロシア連邦軍事ドクトリンの主要規定〉を示した。同規定では,近い将来,世界的規模の戦争が発生する可能性は低下したが,局地戦争や武力紛争が世界の平和と安定に対する脅威となっているとの認識を示した。また,国防の目的を主権,領土,国民など,ロシアにとって死活的に重要な利益を擁護することであると規定し,これらの利益を擁護するために即応態勢と戦闘力を維持することを強調している。
戦略核戦力については,ロシアは戦略核ミサイルの削減を進めてはいるが,解体費用の不足などで解体が遅れ,アメリカよりも多くのICBM,SLBMを保有している。戦略爆撃機TU160(ブラックジャック)の生産は停止したと見られているが,旧式ICBMから単弾頭・移動式のICBMであるSS25への更新,改良型SS25の開発が進められている。
また,射程500kmから5500kmの中距離核戦力(INF)については,INF条約に基づき1991年までに廃棄を完了し,艦艇に配備した戦術核については92年11月に艦艇から撤去したが,短距離地対地ミサイル,中距離爆撃機,攻撃型原子力潜水艦,海上・空中発射巡航ミサイルなどの多様な核戦力を依然として保有している。
ロシア軍は通常戦力の削減が続き,即応態勢が低下しているために,安全保障上,核戦力を相対的に重視する傾向が強まっており,限られた財源を優先的に核戦力に投入して,核戦力の即応態勢の維持に当たっていると見られている。
→核兵器 →ミサイル
執筆者:阪中 友久
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「核戦略」の意味・わかりやすい解説
核戦略
かくせんりゃく
nuclear strategy
核兵器を使用する戦争のための軍事的および政治的基本方針。
[服部 学]
アメリカの核戦略
第二次世界大戦終了時に唯一の原爆保有国であったアメリカは、対ソ封じ込めの原爆外交政策をとった。いわば原子爆弾は核脅迫戦略の手段であった。1949年にソ連も原子爆弾を完成すると、アメリカは戦術核兵器と水素爆弾の開発に乗り出し、54年1月、ダレス国務長官は「自らの選ぶ方法と場所において即座に反撃できる」大量報復戦略(ニュールック戦略ともいう)を提唱した。57年ソ連がICBM(大陸間弾道ミサイル)の発射に成功すると、アイゼンハワー大統領はこれをネオ・ニュールック戦略に修正したが、その内容は、戦略核戦力を強化して対ソ優位を保とうとするものであった。一方このころから海外の基地に戦術核兵器を配備し、地域を限定した限定核戦争戦略が取り入れられた。60年代になって、ケネディ大統領は、核戦力と通常戦力のいずれをも強化する柔軟反応戦略を採用した。60年代後半にソ連の核戦力が増強されてくると、マクナマラ国防長官は相互確証破壊に基づく抑止戦略を掲げた。70年代にアメリカはミサイルのMIRV(マーブ)(多核弾頭誘導弾)化でソ連を大きく引き離し、先制核攻撃のカウンター・フォース(対軍事力)戦略が可能となってきた。70年代終わりのブラウン国防長官の相殺戦略の内容はカウンター・フォース戦略であった。80年8月カーター大統領の署名した大統領指令第59号は、アメリカの戦略核戦力の攻撃目標が都市や産業施設ばかりでなく軍事目標を含むことを明らかにしている。クリントン大統領は、97年11月、大統領指令第60号で、核攻撃の目標は従来のロシアなどから第三世界諸国中心に設定し、必要な場合には先制攻撃を行い、そのために使いやすい新型核兵器の開発を進めることを明らかにした。
現在は多種多様な核兵器体系が存在し、したがってこれらを使う核戦争にも、限定核戦争から長期大規模核戦争とよばれるものまで、多種多様の核戦略が考えられている。
[服部 学]
ソ連、ロシアの核戦略
ソ連は1949年に原子爆弾を手にしたが、十分な運搬手段がなく、また古典的軍事思想を固守したスターリンの軍事戦略は原子兵器とはなじまなかった。スターリン時代には核戦略とよべるものはなかった。マレンコフは水素爆弾と長距離爆撃機を手にしたことから、核兵器を抑止戦力とみなす政策を採用した。しかし量的にはアメリカのほうが優勢であり、これは一種の最小限抑止力論に基づくものであった。フルシチョフは、ロケット技術の進歩と大型水爆開発の自信過剰からか、アメリカに対する軍事的優位を得ようとして核軍拡に乗り出したが、この間アメリカはミサイルのMIRV化に全力を注いでいた。ソ連がようやくMIRV技術のもつ意味の重大さに気づき、その後を追い始めるには5年の遅れがあった。米ソの核兵器関連技術開発の足どりは、ほとんどの技術でアメリカが2年ないし5年先行し、ソ連の核戦略はアメリカの技術の進歩に振り回され、つねにその後を追うという状況が繰り返されてきた。ソ連解体後のロシアは、依然として大量の核兵器をもっているが、核戦略については核抑止以外とくに明らかにしていない。
[服部 学]
その他の国の核戦略
フランスはガロワ将軍の『中級国家の核武装論』に基づいた抑止戦略論を採用している。つまり、かつての米ソのような大規模な核戦力をもたなくとも、対都市戦略に基づく小規模の核戦力で抑止力となりうるという考え方である。またアメリカのNATO(ナトー)(北大西洋条約機構)に対する核の傘を信頼せず、アメリカも含めて全世界のあらゆる国に対する全方位戦略を主張している。
イギリスの核政策は、アメリカおよびNATOの戦略ときわめて密接な関係をもっており、独自の核戦略はもっていない。
中国は、最初に核兵器を使うことはないと宣言してきた。しかしどのような核戦略をもっているのかについては、なにも発表していない。とにかくあらゆる種類の核兵器をもつことに重点を置いているようにみえる。インドとパキスタンの核実験はカシミール紛争を理由にあげているが、明確な核戦略はまだないように思われる。事実上の核兵器国とされるイスラエルも対アラブ政策があると思われるが、核兵器の存在を明らかにしていない。
[服部 学]
『豊田利幸著『核戦略批判』『新・核戦略批判』(岩波新書)』▽『R・C・オルドリッジ著、服部学訳『核先制攻撃症候群』(岩波新書)』▽『中川八洋著『現代核戦略論』(1985・原書房)』▽『中川八洋著『ソ連核戦争戦略』(1984・原書房)』
百科事典マイペディア 「核戦略」の意味・わかりやすい解説
核戦略【かくせんりゃく】
→関連項目安全保障|水素爆弾|戦略兵器削減条約|戦略兵器制限交渉|臨界前核実験
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「核戦略」の意味・わかりやすい解説
核戦略
かくせんりゃく
nuclear strategy
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...