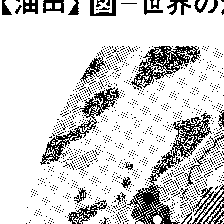翻訳|oil field
精選版 日本国語大辞典 「油田」の意味・読み・例文・類語
あぶら‐た【油田】
- 〘 名詞 〙 社寺で灯明の油料の資として定められた田。その田租などを油の料にあてがうもの。
- [初出の実例]「右田地者〈略〉任二親父遺言一、為二現当二世悉地円満一、寄二進石燈炉御油田一畢」(出典:高野山文書‐弘安二年(1279)正月二五日・光広御影堂燈炉油田寄進状)
ゆ‐でん【油田】
- 〘 名詞 〙 現在、石油を産出している地域。広義では、過去に石油を産出した地域や石油を含む地層がまとまって分布している地域をもいう。
- [初出の実例]「之れを総称して甲を東山油田とし」(出典:風俗画報‐二三三号(1901)人事門)
改訂新版 世界大百科事典 「油田」の意味・わかりやすい解説
油田 (ゆでん)
oil field
原油とガスが共存するのを常態とする地層を油層といい,単数または複数の油層が分布する一定区域が油田であり,原油およびガスを採収するのに必要な各種の生産施設も,この油田区域に含まれる。一方,ガスだけが遊離して存在するのを常態とする地層をガス層といい,単数または複数のガス層およびガスを採取するのに関連した生産施設を含む区域がガス田gas fieldである。ガス層は乾性(ドライ)ガス層とガス・コンデンセート層に分けられる。前者はガス層圧力が降下しても層内にはつねにガス相だけが存在するものであり,後者は層圧の降下過程で層内に液化が始まり,その液化量はしだいに増加して,ある層圧で最大となり,その後,液相は減少するものである。その他のガス田として水溶性ガス田があり,これはガスが水に溶解して存在するのを常態とするようなガス層より成るものである。この型のガスは日本においては貴重な資源であるが,世界的にはイタリアのポー川流域に分布する程度である。
石油に限らず,地下資源が地域的に偏在していることは広く知られており,しかも世界中に分布する約4万の油田(1986)のうちで,埋蔵量的に巨大油田が占めている比率はきわめて大きい。1995年現在,埋蔵量50億バレル以上の超巨大油田数は46で,全埋蔵量の約45%を占める。また10~50億バレルの極巨大油田179,5~10億バレルの巨大油田201を合計して,全埋蔵量の約32%を占める。したがって,5億バレル以上の巨大油田の埋蔵量が全体に対して占める割合は約77%である。天然ガスについても埋蔵量約8500億m3以上の超巨大ガス田は31で全埋蔵量の48%を占める。また約2800億m3以上の極巨大ガス田51,約850億m3以上の巨大ガス田193を合計して全埋蔵量の約31%を占める。埋蔵量約850億m3以上のすべての巨大ガス田の埋蔵量が全体に対して占める割合は約78%である。
油田成立の地質学的条件
石油は世界各地の堆積岩のなかに分散した状態で大量に分布する。しかし,石油が経済的に採取できるような油田が形成されるためには,数多くの石油地質学的条件が必要である。とくに良好な石油根源岩,油層岩(貯留岩)およびキャップロック(帽岩)の分布および適切なトラップの存在が不可欠である。
石油の貯留
石油の根源岩(母岩)として有力なのはケツ岩と石灰岩である。海底に沈積したこれらの堆積物の上位には次々に新しい堆積物が追加されていくため,しだいに地下深部に埋積される。地下へ向かっては,通常2~4.5℃/100mの割合で温度が増加する。石油の根源岩に含まれる有機物は,70~90℃以上の温度に達すると,熱作用によって分解され石油に変質する。この過程を熟成という。ここで生成された石油は,上位の堆積物の荷重によって圧密を受け,水分とともに根源岩から貯留岩へ搾り出されていく。この過程を一次移動という。次に貯留岩へ移動した油と水は,油のほうが水より軽いので,油は上方へ,水は下方へと分離する。この過程を二次移動という。貯留岩中を移動している油が,その移動を妨げるようななんらかの障害物,例えば断層や背斜構造(これをトラップと総称する)に到達すると,ここで移動がとまって石油が集積し,油田が形成される。
油田構造
最も一般的な油田構造は,褶曲運動によって形成された背斜トラップである。貯留岩のなかには比重の順に,上から下へガス,油,水が配列されている。それぞれの層の境界を油ガス界面,油水界面という。油層頂部のガスをキャップガスといい,また油層の下の縁の部分に分布する水層を端水,油層の底部に分布する水層を底水という。
層位トラップとは,岩質の変化によりまたは地層の不整合面の直下に油が集積したものである。このタイプの油田のなかにもいくつかの巨大なものはあるが,世界全体の油田数あるいは埋蔵量のなかで,層位トラップ油田が占める割合は10~15%にすぎず,またこのタイプの油田の探鉱は,石油地質学的にも地球物理学的にもきわめて難しい。
バーレントラップ
石油の探鉱を行う技術者は,対象地域の地理的・地質学的条件を考慮し,さまざまな手段を使って探鉱を行い,最善と考えられるロケーションの試掘を行う。しかし試掘によって商業規模の油・ガス田が発見される確率は依然として3~4%にしかすぎない。りっぱな背斜構造あるいはその他のトラップは存在するにもかかわらず,実際に試掘を行った結果,このトラップに油が集積していなかったようなケースはひじょうに多い。これを〈バーレントラップbarren trap〉という。その原因は数多くあると考えられるが,おもなものをまとめると次の通りである。(1)石油の根源物質(有機物)が存在しないか少ない,(2)石油が生成されるのに必要な地下温度が不十分,(3)石油がトラップに集積するのを妨げるような条件があった,(4)いったん集積した石油が造構造運動,浸食などによって破壊され,逸散してしまった,(5)トラップの形成時期が遅すぎて,堆積盆地における石油の移動,集積過程がすベて終わってしまってからトラップが形成された,などのためである。
油田評価
試掘の結果,新しい油田が発見されたら,油田の規模に応じて数坑の評価井(探掘井)を掘削し,第1にその埋蔵量を評価する。その結果に基づいて開発および生産計画を策定し,これに必要な生産設備などを設計する。さらにこの油田の開発に必要な費用を算出して生産収入とのバランスを考慮し,フィージビリティスタディfeasibility study(企業化経済評価)を行う。
油井
新油田開発の最初の問題は掘削する採油井の数をなん本にするかということである。これは坑井間隔,すなわちウェルスペーシングwell spacingをどのくらいにするかということでもある。かつては油井の数が多いほど,油層からの回収油量も多いと考えられていた。しかし現在の一般的技術コンセンサスとしては,ウェルスペーシングの大小は,ある程度の限度内においては最終的な油田からの回収量にあまり影響を与えないとされている。油井の数が少ないほど掘削費は安くてすむが,その油田からの年間生産量は少なくなるので,最終的な油の回収量はあまり変わらないとしても,生産収入が長期的に繰り延べられてしまう。したがってウェルスペーシングの大小は,技術的問題というよりも主として経済的問題である。最近の傾向としては,ウェルスペーシングはしだいに大きくなっている。開発費が安く,採油井の生産能力が高い場合にはウェルスペーシングはわりに狭くてもよいが,経済的・技術的条件に恵まれない油層の場合は,広いスペーシングのほうが有利である。
排油機構
油層のなかの油が地上まで採揚されるメカニズム(排油機構)は,いくつかの基本型式がある。おもなものは,溶解ガス押し型,ガスキャップ押し型,水押し型がある。しかし実際にはこれらのいくつかのメカニズムが組み合わされて油は地上まで押し上げられる。溶解ガス押し型の排油機構では,圧力の低下に伴って油中に溶存するガスが油層内で分離膨張することにより排油が行われる。この型の油層は生産を開始後まもなく,油の生産量,油層圧力ともに急激に減退するので,油の回収率(採収率)は一般に10~25%にとどまる。ガスキャップ押し型の排油機構は,油層の上方のキャップガスが油を採油井へ,次いで地上まで押し上げるメカニズムである。この型の油層は溶解ガス押し型の場合よりも生産量,油層圧力の減退が著しくないし,したがって油の回収率もやや高く,20~40%のものが期待できる。水押し型の排油機構は,油層の下方の水層の水が油を採油井へ,次いで地上へ押し上げるメカニズムである。十分な水押し機構が働くためには,油の容積の10倍から数十倍の容積の水が存在することが必要であるが,良好な水押し油層の場合には35~60%の回収率を期待することができる。
油層工学というのは流体力学の理論を油層の解析へ応用した技術であるが,その主要目的は最少費用で油の最大回収量を得ることである。近代石油生産業の誕生は一般に1859年ペンシルベニアでのE.L.ドレークによる石油の発見が端緒であるとされているが,これとほぼ同じころにフランスのダルシーH.P.G.Darcyは多孔質媒質を通過する水の流れに関する古典的な研究成果を公表している。しかし当時は地下深部で圧力を測定したり,高温,高圧の油層条件で油の性質を測定する方法がなかった。このような種類の測定が行われるようになったのは第1次大戦の直後であるが,これはごく限られた油田で行われただけで,世界的に広く実施されるようになったのは1920年代後半以降である。
二次回収法,増進回収法
油田の生産挙動(生産推移)は個々の油田において千差万別である。油層流体の流れを解析するためには,大型コンピューターを使って油層シミュレーションを行う。油層シミュレーションは将来における油田の生産挙動,油層圧力の挙動,最適生産計画などに関する予測を行うために実施される。シミュレーションの結果は,油田の技術的・経済的評価のための基礎となるものである。油層の圧力維持のためにガス(ガス圧入法)または水(水攻法)を層内へ圧入する二次回収作業(二次回収法,二次採油)は,一応20世紀のはじめから実施されてきた。これによって一般に回収率が5~30%向上することが期待される。二次回収法では,圧入した水やガスが油をうまく採油井へ押し出していくこと,すなわち油を水やガスで置換する効率を高めることが最大の技術的課題である。その一つの手段として〈ミシブル攻法〉がある。水による油の置換が不完全なのは,2種類の流体の界面における表面張力による抵抗のためである。液相プロパンのような軽質炭化水素を添加すると,これは原油とミシブルである(親和性がある)から油を効率的に置換する。ミシブル攻法のなかには,プロパンのスラグを高圧のガスで後押ししてやったり,高圧でガスだけを圧入する方法もあり,さらに炭酸ガスを圧入する方法もある。水および油の両者に対してミシブルな界面活性剤を使ってミシブルな流体フロントを作る方法も,実験室では置換効率の向上に関して注目すべき成果をあげている。
重質かつ粘性の高い油層に対して空気を圧入し,原油のごく一部を燃焼させることによって油の粘性を下げて移動しやすいようにし,回収率を高める手法(地下燃焼法)はすでに十数年前に実用化されたが,現在ではほとんど水蒸気圧入法に切り換えられている。カリフォルニア州の全石油生産量のうち約30%は水蒸気圧入によって生産されている。また二次回収のために圧入する水のなかに分子量の高いポリマーを溶解させて水の粘性を高め,易動度を改善することによって均一的な水攻効果を得ようとする改良型水攻法も一部で実用化されている。水攻法やガス圧入法を二次回収法と称するのに対して,さまざまなミシブル攻法,地下燃焼法,水蒸気圧入法のような熱回収法,あるいは界面活性剤やポリマーを使うケミカル攻法は,従来は三次回収法(増進回収法=EOR,Enhanced Oil Recovery)と呼ばれてきた。しかしこれらの方法は二次回収法とともに,油田開発の初期から適切な方法を選択して応用することが望ましいので,二次あるいは三次回収という区別をしないで,全般として改良型回収法(IOR,Improved Oil Recovery)という名称が広く使われるようになっている。
フィージビリティスタディ
油田評価が行われた対象油田に対する投資計画についてはフィージビリティスタディが行われ,プロジェクトを採択すべきか否かの意思決定が行われる。投資計画の経済性を判定するにはいくつかの指標がある。投資総額,実際の収益額,収益/投資比率,正味収益の現在価値,投資回収期間,割引正味現金収支収益率(DCFROR)などである。とくにDCFRORは石油鉱業界では広く使われている。この指標には時間に対する金の価値の割引の概念が含まれていることが有利であり,また市場の金利や会社の他のプロジェクトの平均収益率と当該プロジェクトとの優劣の比較ができる。しかし,ある対象油田に関する上記の指標がすべて問題なく優れていると判断されることはまれである。どの指標を基準としてプロジェクトを採択すべきかについての明確な根拠は存在しない。その選択は各会社の経営方針しだいである。例えば,ある会社がDCFRORが20%以上であることをプロジェクト採択の方針にしているならば,それに従えばよい。会社の資金量に厳しい制限があって,資金を早く回収したいならば,投資総額が少なく,回収期間が早いという指標が最も重要なものになる。
このような指標には本来リスクあるいは不確定性といった要素は含まれていない。しかし最終的な意思決定を行う前には,これらの要素についても考慮し,感度分析を行う場合もあるし,技術的・経済的要素についての確率分布モデルを作成するために,モンテカルロ・シミュレーション(モンテカルロ法)に基づく計算を行うこともある。油田評価の場合にこの方法がわりあいによく使われるのは容積法による埋蔵量計算の一手段としてである。集油面積,有効層厚,孔隙(こうげき)率,水飽和率,容積係数などのいくつかの値に適当な確率が与えられ,これに基づいて計算が行われ,期待される埋蔵量の確率分布が求められる。
→採油
世界の油田
世界中には約4万の油田があり,毎日約6200万バレルの原油が生産され,またそれらの油田には約9153億バレルの確認可採埋蔵量が残されている。産油国は日本のような小規模なものを含めて70国ある。1995年の生産実績で,最大はサウジアラビア(世界全体の12.7%)で,旧ソ連(11.2%),アメリカ(10.6%),イラン(5.9%),中国(4.8%),ノルウェー(4.5%),メキシコ(4.3%),ベネズエラ(4.2%),イギリス(4.1%),UAE(3.6%)がこれに次ぐ。これらの上位10ヵ国の生産量が世界全体の約65%を占める。
世界最大の油田はサウジアラビアのガワール油田(総可採埋蔵量1150億バレル)で,第2位はクウェートのブルガン油田(同600億バレル)である。北アメリカではアラスカのプルドー・ベイ油田(同126億バレル),旧ソ連では西シベリアのサモトロール油田(同274億バレル),アフリカではアルジェリアのハッシ・メサウド(ハージー・マスウード)油田(同91億バレル),南アメリカではベネズエラのボリーバル・コースタル油田(同380億バレル),アジアではインドネシアのミナス油田(同47億バレル),西ヨーロッパではノルウェー領(一部イギリス領)北海のスタットフィヨルドStatfjord油田(同39億バレル),オーストラリアではやや規模が小さいが,バス海峡のキングフィッシュKingfish油田(同12億バレル)がそれぞれの地域において最大である。
中東では次の28油田が50億バレル以上の総可採埋蔵量をもっている。すなわちガワール,サファニヤ,カティーフQatīf,アブカイクAbqaiq,アブ・サファAbu Safah,ベッリBerri,マニファManifa,クライスKhrais,シャイバShaybah,ズルフZuluf(以上サウジアラビア),ブルガン,ラウダテインRaudhatain,ザブリヤSabriya(以上クウェート),ザクム,ブ・ハサBu Hasa,バブBab,アサブAsab,ウンム・シャイフ(以上UAE),ルマイラ,キルクーク,マジュヌーンMajnoon,ウェスト・クルナWest Qurna,イースト・バグダードEast Baghsdad,ズベアZubair(以上イラク),マルンMarun,ガッチサーラーン,アフワーズ,アガジャリAgha Jari(以上イラン)。以上の油田だけで中東全体の埋蔵量の約70%を占めており,とくに重要である。サウジアラビアのガワール油田は延長200km以上に及ぶ超巨大油田で,地下約2200mのアラブ石灰岩油層(ジュラ紀)から同国全体の生産量の半分以上を生産している。クウェートのブルガン油田については詳細な生産統計が公表されていないが,累計生産量としては世界一の超巨大油田のようである。イラクでは北部のキルクークは古い油田で,南部のルマイラ油田は新しい油田であるが,この両油田が双へきである。イラン最大の油田は1963年に発見されたマルン油田である。ガッチサーラーン油田は同国で最も古い油田の一つであるが,現在でも主力油田の一つである。
北アメリカのうち,アメリカではテキサス州が最大の産油地帯で,北アメリカ全体の3分の1近い原油を生産する。アメリカの産油量は1970年の約960万バレル/日をピークとして漸減の傾向にある。カナダの産油量はアメリカの7分の1くらいで,やはり漸減している。メキシコは石油生産が最も急速に成長した国で,現在の産油量は270万バレル/日。アメリカにおいてはアラスカ北部のプルドー・ベイ油田が最大の生産量をあげている。この油田が発見されたのは1968年であるが,全長1200km,建設費90億ドルのアラスカ縦断パイプラインが完成し,生産が開始されたのは77年である。カナダの主要油田は西部のアルバータ州に分布する。ペンビナPembina,スワン・ヒルズSwan Hillsなどの大油田の発見が相次いだ1950~60年代以降目だった発見はあまりなく,今後はマッケンジー・デルタ,ボーフォート海,北極諸島を含む北極圏の探鉱とオイルサンドの本格的開発に期待が寄せられている。日本の北極石油(株)はカナダ資本のドーム社に協力して,カナダ側のボーフォート海で探鉱を行っている。メキシコはユカタン半島の付け根の地域で1972年に発見したレフォルマ油田群およびその沖合のカンペチェ湾油田群の開発が進んで,重要な輸出国になったが,全土にわたって広範な探鉱活動も行われている。
旧ソ連の石油生産の中心地はカスピ海に面したバクー地域から,ウラル山脈の西のボルガ・ウラル地域へ移り,さらに現在ではオビ川流域の西シベリア地域へ移った。西シベリアの油田地帯は極寒,無人の湿原地帯に分布する。この地域最大のサモトロール油田は面積300km2の巨大油田で,地下2200mの白亜紀砂岩油層から約85万バレル/日の生産を行っている。サハリン北部のオハOkha油田は古い歴史をもつ油田であるが,その沖合において日本のサハリン石油開発協力(株)が1975年以来探鉱を行い,すでにオドプトOdoptu,チャイボChaivoの両油・ガス田を発見した。東ヨーロッパの各国はそれぞれある程度の生産があるが,とくにルーマニアは古い歴史をもつ産油国で,高度の油田技術をもち31万バレル/日の生産を行っている。
アフリカでは1950年代後半以来次々に多くの油田が発見されている。とくにナイジェリア,アルジェリア,リビアが重要な産油国である。油田規模としては,アルジェリアのハッシ・メサウドとリビアのサリールSarirの両油田がとくに大きい。ナイジェリアには総可採埋蔵量が5億バレル程度の中級油田が多い。
南アメリカではベネズエラが南アメリカ全体の産油量の3分の2を占め,アメリカ,カナダなどへ大量の輸出が行われている。アルゼンチン,トリニダード・トバゴ,ペルー,ボリビアも古くからの産油国である。エクアドル,コロンビアでは1960年代に中型油田が発見され,ブラジルでも活発な探鉱活動によって次々に油田が発見されている。ベネズエラでは同国全体に油田が分散しているが,マラカイボ湖の湖中から東岸にかけて分布するボリバール・コースタル油田の総可採埋蔵量(380億バレル)は世界第3位である。オリノコ川の河口付近ではキリキレQuiriquire,オフィシナOficina油田が大きい。オリノコ川南方地域には約7000億バレルと推定される重質油が分布しており,その開発は今後の問題である。ペルー海岸のタララTalara油田と,コロンビアのジャングル地域のオリトOrito油田は,総可採埋蔵量が10億バレル級の大油田である。またリャノ堆積盆地の新規採鉱により,83年にカノ・ライモンCano Limon(11億バレル),92年にクシアナCusiana(16億バレル),93年にクピアグアCupiagua(5億バレル)が次々と発見され,現在までの総発見量は15油田,49億バレルにも増えた。アルゼンチンの油田は,アンデス山脈の東麓部とサン・ホルヘ湾に面したコモドロ・リバダビアに分布するが,最近同国最南端のフエゴ島で油・ガスが発見され,その延長がイギリス領フォークランド諸島(マルビナス諸島)まで広がっているとの推定も行われている。その領有権をめぐってアルゼンチンとイギリスが紛争を起こした。ブラジルのカンポス堆積盆地における大水深海域の探鉱の結果,1984年にアルバコラAlbacora(14億バレル),85年にマーリムMarlim(24億バレル),87年にマーリム・スルMarlim Sul(11.6億バレル),89年にバラクーダBarracuda(11億バレル)が次々と発見された。近年の総発見量は23油田,90.7億バレルで,産油国の仲間入りをした。しかし,アマゾン地域の古生代堆積盆地では大規模な出油は報告されていない。
東アジアおよび東南アジアでは,中国が最大の産油国である。1995年末現在,中国の原油累計生産量は210億バレルで,残存埋蔵量は310億バレルと報告されている。約299万バレル/日の生産を行っているが,93年から輸入国に転じた。インドネシアが中国に次ぐ。ブルネイと東マレーシアのサバ州,サラワク州も重要である。タイも1981年からガスの生産国になった。中国の油田の埋蔵量については諸説があるが,生産量からみると勝利,遼河,大港の順である。日本の日中石油開発(株)が渤海で発見した油田の規模はかなり小さく,期待はずれであった。インドネシアではミナス,ドゥリDuri両油田をもつ中部スマトラが最大の産油地帯である。北西ジャワ島沖で発見されたシンタCinta,キティKitty,アルジュナArdjunaなどの油田からの生産が開始され,日本のインドネシア石油(株)も出資しているカリマンタン・マハカム沖のハンディルHandil,アタカAttaka,ブカパイBekapaiなどの油田とともに,インドネシアでは海洋油田の生産量が急増している。西イリアン西部のワリオWalio,カシムKasimなども比較的新しい油田である。
オーストラリアでは1960年代に大型油田の発見がつづいた。北西部ではバロー島上のバロー油田,南東部ではバス海峡のキングフィッシュ,ハリブートHalibutなどの海洋油田があるが,まだ国内需要を満たすにはほど遠い。
西ヨーロッパの産油量は1950年から60年の間に約5倍に増加したが,その需要の10%を満たすにすぎず,大部分を輸入に頼ってきた。しかし1970年代以降の北海における大油田の相次ぐ発見によって,西ヨーロッパの石油情勢は大きく変わった。北海における最初の油田発見は,70年のノルウェー海域エコフィスクEkofisk油田で,72年に地下2800mの白亜紀のチョーク質油層から15万バレル/日の生産を行っている。同年イギリス領でもフォーティーズForties油田が発見され,75年に生産を開始した。北海の大油田としては,ノルウェー領のスタットフィヨルド(可採埋蔵量39億バレル,一部イギリス領),エコフィスク(同23億バレル),イギリス領のブレントBrent(同20億バレル),フォーティーズ(同26億バレル),ニニアンNinian(同12.6億バレル)などがある。
世界のガス田
天然ガスは従来輸送手段に問題があり,地域的に消費される資源で,国際的な商品としての価値は高くなかった。しかし近年,長距離,大口径の輸送用パイプライン敷設の技術が進歩し,また1959年以来天然ガスを極低温で液化し,LNGタンカーで輸送するプロジェクトが次々に実現した。このようないわゆるLNGプロジェクトは開発の初期投資は大きい。日本はアラスカ,ブルネイ,インドネシアから,アメリカ,イギリス,フランスはアルジェリアから,イタリア,スペインはリビアからの輸入を行っている。
世界の超巨大ガス田として,総可採埋蔵量が約8500億m3を超えるガス田が31存在するが,そのうち旧ソ連に属するものが14もある。おもなものは旧ソ連ではウレンゴイ(可採埋蔵量約10兆m3),ヤンブルグ(同約4.8兆m3),ザポリヤルノエ(同約3.4兆m3),アストラハン(同約2.7兆m3)などがある。その他の国では,オランダのフローニンゲン(同約2.1兆m3),カタルのノース・フィールド(同10兆m3),イランのカンガン(同2.8兆m3),ナール(同2.8兆m3),パザナン(同1.1兆m3),アメリカのヒューゴットン(同2.0兆m3),アルジェリアのハッシ・ル・メル(同3.0兆m3),中立地帯のドラ(同2.0兆m3),インドネシアのナツナ(同1.3兆m3)がある。
→天然ガス
日本の油・ガス田
日本では海陸を含めて60以上の油・ガス田が発見されているが,その規模は世界的基準からするとかなり小さい。しかし国内の油田は最も安定した供給源であることはいうまでもなく,また開発,生産にあたっての経済条件が海外における利権条件よりはるかに恵まれているので,たとえ油田規模がかなり小さくても経済的にフィージブルとなる場合が少なくない。日本の陸域および周辺海域ではある程度の規模の探鉱開発作業が継続的に実施されている。第2次大戦後の国内の石油開発は,1946年に石油資源開発促進委員会(略称PEAC,現在の石油審議会開発部会)の勧告に基づき,物理探査技術や深層掘削技術の発展がはかられ,これによって八橋(やばせ)油田深層や明治ガス田が発見された。54年にPEACの答申による〈第1次5ヵ年計画〉の推進母体として,55年に石油資源開発(株)が国策会社として設立された。その後数次にわたって5ヵ年計画が策定されている。帝国石油(株)も石油資源開発(株)と並行して着実な探鉱作業をつづけ,55年以降83年までに日本全体で海陸で47油・ガス田を発見した。海域においては国際石油会社との共同作業も行われ,エッソ,シェル,ガルフ,アモコの各社が参加した。83年まででこの共同作業が成功したのは,海洋石油資源開発(株)-出光石油開発(株)-アモコの阿賀沖油・ガス田,帝国石油(株)-エッソの磐城沖ガス田であるが,その他にも試掘の結果,ある程度良好な成果を得たところもある。
日本の油・ガス田の大部分は秋田・山形・新潟県を含む東北・日本海側地域とその沖合に分布する。北海道には天北・石狩・日高地域にいくつかの中小規模の油・ガス田が,長野県北部に二,三の小油田が,太平洋側には唯一の油田として相良油田(静岡県)が,また福島県のいわき市沖には磐城沖ガス田が分布する。水溶性ガス田は千葉,新潟両県のほか静岡県,宮崎県などでも採収されており,各地方の貴重なエネルギー源になっている。日本の油・ガス田のうち最大規模のものは,新潟県の吉井・東柏崎ガス田で1995年末までの累計生産量は154億m3,石油換算で約1540万kl(天然ガス1000m3を原油1klに換算)である。これに次ぐのが秋田県の八橋油田(約800万kl),新潟県の中条・新胎内ガス田(約700万kl)であり,500万klクラスの油・ガス田としては,阿賀沖油・ガス田(新潟市沖),東新潟・松崎ガス田(新潟県),頸城油・ガス田(新潟県)が,300万klクラスとしては西山油田,新津油田(ともに新潟県)が,200万klクラスとして南阿賀油田,見附油田,藤川・雲出ガス田(以上新潟県),申川(さるかわ)油田(秋田県)がつづく。磐城沖ガス田は500万klクラスのものといわれていたが,2007年に帝国石油が採掘を終了。
日本の油・ガス田のほとんどは背斜構造に集積したものである。このなかには山岳部における両翼が急傾斜な背斜構造(吉井・東柏崎,西山,新津など)と,平原部における緩やかな背斜構造(東新潟・松崎,頸城など)とがある。また余目,南阿賀両油田,紫雲寺・中条ガス田などは背斜+層位トラップの組合せによって成立したものである。日本の油・ガス層の層準は新第三系中上部および第四系下部に限られているが,いくつかの試掘井において古第三系,白亜系,ジュラ系においてもある程度の油・ガス徴を確認している。油・ガス層の岩質はほとんどが砂岩であるが,凝灰岩あるいはケツ岩が混在した凝灰質砂岩あるいはケツ岩質砂岩であることが多い。最近クローズアップされているのは緑色凝灰岩の油・ガス層で,見附油田,吉井・東柏崎ガス田および関原・片貝ガス田の深掘りによって,これが優れた油・ガス層であることが証明された。また秋田県の福米沢(ふくめざわ)油田は日本で唯一の苦灰岩油層より成る。
→石油
執筆者:加藤 正和
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「油田」の意味・わかりやすい解説
油田
ゆでん
地下から原油を採収している地域の呼称。秋田市八橋(やばせ)にある油田を八橋油田とよぶように、油田が存在する地名で名前がつけられることが多い。またイギリスとノルウェーの間にある北海では、多くの海洋油田が開発されているが、個々の油田に名前がつけられているほかに、これら油田群を総称して北海油田とよんでいる。このように一つの地域にある油田群を総称して名前をつけることもある。
[田中正三]
油田の開発
油田開発に先だって地質調査や物理探査が実施される。その結果油層の存在の可能性が推定されると試掘井が掘削される。油層の地質構造が背斜構造のときには、試掘井は背斜の頂部に掘られる。試掘井の掘削に成功し十分な石油の産出が確認されると、油田の埋蔵量を調べるため、油田の広がりを調査する坑井が掘られる。そのデータから開発に足る十分な埋蔵量があることがわかると、油田開発の計画がたてられ本格的な開発が始まる。
開発計画をたてるときまず考えることは、油田開発のため幾本の坑井を掘るかということである。海洋油田の場合など、1本の坑井を掘るのに莫大(ばくだい)な費用がかかるから、最少の坑井数で油田全体から十分な油を採収できるように計画がたてられる。坑井数を決める基本的な考え方は、各油井はそれぞれ特有な集油区域をもっているということである。1本の油井へ流入する油は、油層のどの部分から流れてくるかは明らかにすることはできないが、油層全体から集まってくるのではなく、その油井を中心とした一定の限定された油層部分から、すなわち集油区域から流入するという考え方である。中東の大油田のように油層岩石の浸透性がよい場合には、集油区域の面積は大きいと考えられるので、坑井数が少なくても油田全体から多量の油が採収できることになる。このため中東の大油田では各坑井の間隔は1マイル(1600メートル)という大きい間隔にとられることも多い。油層岩石の浸透性の小さい油田は、各油井の集油区域の面積が小さいから、坑井間隔は200メートル程度となり、数多くの坑井が掘られることになる。したがって、大油田は油井の数が多く、中小油田は油井の数が少ないというものでなく、その逆の場合が非常に多い。
[田中正三]
油田の埋蔵量
油田開発の基礎となるのは油田の埋蔵量である。埋蔵量は鉱量ともいう。埋蔵量はいろいろの観点から分類できる。まず総埋蔵量と可採埋蔵量に分けられる。油層中にある油は全部地表へ採収できるものではない。油層中の原油の総量を総埋蔵量といい、地表へ採収できる原油の量を可採埋蔵量という。油層の埋蔵量はいくらあるかというときは可採埋蔵量をいう。可採埋蔵量と総埋蔵量の比を採収率という。油層の平均採収率は25%から30%といわれている。一つの油田が発見されても、そこにある油の一部が採収されるだけで、総埋蔵量の70%以上が地下に残留してしまう。この残留した油を採収するために、二次採収、三次採収が実施される。石油採収の技術が進み採収率が大きくなれば、油田の埋蔵量は増大することになる。
埋蔵量はまた確認埋蔵量、推定埋蔵量および予想埋蔵量に分類される。確認埋蔵量とは、坑井を掘り、地層中の油の存在を確認してから求められた埋蔵量である。推定埋蔵量は、油の存在が確認された地層において、地質学的にみて油が確実にあるだろうと推定された区域の原油の埋蔵量である。予想埋蔵量は、石油の確認はまだなくても、地質学的に石油の存在が考えられる地域の埋蔵量である。試掘井が成功すると、その油田の確認埋蔵量と推定埋蔵量が求められるが、油田開発の進展に伴い坑井数が増加をすると、いままで推定埋蔵量とされていたものが確認埋蔵量に算入されることになる。石油鉱業の歴史はつねに石油の産出しない地域への探査拡大の歴史である。石油の存在が地質学的にみて考えられる地域において、試掘井が成功すれば、予想埋蔵量が確認埋蔵量に書き換えられることになる。油田から産出し消費される石油は再生することはないから、石油の埋蔵量は全体としては減少していくが、その存在が確認された石油の量すなわち確認埋蔵量は、石油の消費にもかかわらず、減少しなかったり、ときとしては増加をすることさえもおこる。1940年代から50年代は石油埋蔵量が急激に増加し、石油の時代が出現したが、70年代になってからは石油埋蔵量は横ばいである。
[田中正三]
R/Pと石油の寿命
石油はあと何年もつか、石油資源の寿命はあと幾年かということがよく問題となる。この問題はむずかしい問題で、だれも正しい答えの出ない問題であるかもしれない。しかしこの問題を考えるときの目安としてR/Pが用いられることがある。Rは石油の埋蔵量を、Pは毎年の生産量を意味する。油層を油の倉庫と考えれば、Rは在庫量でPは出荷量であるから、R/Pは、倉庫にある石油がなくなるまでの年数ともいえる。たとえば1976年のR/Pは30年であったが、この値から世界の石油は30年後になくなってしまうとも解釈される。しかしR/Pは石油の埋蔵量を生産量で割るのであるから、生産量が倍になればR/Pは2分の1に、生産量が2分の1になれば、その値は倍になる。したがってR/Pの数字は絶対的な値ではない。R/Pが30年といっても、30年後に石油が一滴もなくなることは、技術的にありえないことであるし、前に説明したように確認埋蔵量は、石油の産出にかかわらず、一定の値を保つ可能性もあり、増加する可能性があるから、R/Pは石油の寿命を表すものでないことは明らかである。1976年の時点でR/Pが30年であっても、30年後依然としてR/Pが30年であることもありうることである。以上のようにR/Pは石油の寿命を表すものでないが、一面、石油資源の有限性を示すものであるとはいえる。油田の寿命についてもR/Pの考え方が用いられることがあり、油田管理上の一つの目安として役だっている。
[田中正三]
巨大油田
世界中にある油田の数は2万とも3万ともいわれている。これら油田のうち大きな位置を占めているのが、巨大油田とよばれる大油田である。巨大油田は埋蔵量が5億バレル以上の油田である。巨大油田のうち埋蔵量が50億バレル以上の油田を超巨大油田という。世界最大のサウジアラビアのガワール油田は、埋蔵量が600億バレル以上といわれる超巨大油田である。これら巨大油田は中東に多く存在し、昭和20年代から30年代にかけて次々に発見され、現在の石油時代を出現させた。巨大油田の数は約250、超巨大油田の数は約30あるといわれている。これら約300の油田の埋蔵量は、世界の埋蔵量の75%を占めているという。日本の原油輸入先の国は中東の国々が多く、1981年では中東よりの輸入量は、全原油輸入量の約69%を占め、中東の巨大油田群の影響の大きさを示している。今後石油埋蔵量が増加し、安定した石油の供給ができるか否かは、巨大油田の発見にかかっている。
[田中正三]
世界の油田開発
石油鉱業は1859年のアメリカ、ペンシルベニア州のドレーク井の成功より始まった。石油の存在は古くより知られていたが、石油採収を目的として井戸を掘ったのはドレークが最初の人である。石油鉱業はアメリカでテキサス州やカリフォルニア州に広がっていき、大小の油田が数多く発見された。現在でも油田が活発に開発されているが、1968年アラスカの北極圏内のノース・スロープで発見されたプルドー・ベイ油田は巨大油田で、アメリカの石油供給に重要な役割を果たしているが、同油田から原油を送るアラスカ縦断パイプラインは、自然保護か石油資源開発かをめぐって注目を集めた。
1870年代には早くもインドネシアの油田開発が始まり、現在も多量の原油を産出している。スマトラのミナス油田は東南アジア最大の油田で、日本へも多量の原油を輸出した。カスピ海に面したバクー油田は早くから開発され、1900年代の初めにはロシアは世界第一の産油国になった。1960年代には西シベリアの油田が開発され、同地域にあるサモトロール油田は世界屈指の大油田である。旧ソ連地域は現在も世界最大の産油地帯である。
中東の油田開発も1900年代初めより始まり、1908年イランのマスジェデ・ソレイマーン油田の発見より、油田開発は急速に進んでいった。サウジアラビアのガワール油田、クウェートのブルガン油田は世界最大級の油田で、両油田の埋蔵量合計は全世界の石油埋蔵量の15%ともいわれている。北アフリカでもリビアのサリル油田、アルジェリアのハッシ・メサウド油田などの大油田が発見された。中国では1957年東北地方で大慶油田が発見され、以後、山東省で勝利油田、河北省で大港油田、任邱油田などが発見された。中国は石油の大生産国となった。ヨーロッパの北海では1960年代から70年代にかけて次々に大油田が発見され、イギリスは石油の輸出国となった。メキシコは、南部のタバスコ州でレフォルマ油田が開発されており、そのほか多くの油田が発見され、豊富な石油資源の将来が注目されている。
このような大油田の発見により石油時代が到来したが、石油の需要の急速な伸びを満たすことが困難となり、1973年の第四次中東戦争のときの石油ショックから、省エネルギーが叫ばれるようになった。
[田中正三]
日本の油田
日本の油田開発は早くより行われ、明治時代には新潟県で東山油田、西山油田、新津油田などの開発が行われている。大正時代になると秋田県の黒川油田、豊川(とよかわ)油田などが開発され、石油の生産量は飛躍的に増大した。昭和になると秋田市の八橋(やばせ)油田が開発され、日本最大の油田となった。北海道では札幌市の近くの石狩油田が早くより開発された。日本の石油鉱業の歴史は、世界の石油鉱業の歴史とほぼ同時代に始まったが、中東のような大油田の発見はなく、現在は新潟市沖合いにある阿賀(あが)沖油・ガス田、新潟県陸上部にある南阿賀油田、頸城(くびき)油・ガス田、山形県の余目(あまるめ)油田、秋田県の申川(さるかわ)油田、八橋油田などがあるにすぎない。現在も油田の探査が続けられているが、油田よりもガス田が多く発見されている。
[田中正三]
日本の石油開発企業の海外での油田開発
石油開発技術は高度化しているため、産油国の油田開発への協力と日本の石油資源確保のため、日本企業は中東やインドネシアなどで油田開発を行っている。中東ではサウジアラビアとクウェートの中間の沖合いにあるカフジ油田、アブダビ沖のザクム油田、ウムシャイフ油田、ムバラス油田、エルブンドク油田の開発を行っている。インドネシアではアタカ油田、ブカパイ油田、ハンディル油田、アフリカではガボン沖合いのバリステ油田、コンゴ民主共和国(旧ザイール)沖合いのGCO油田などで石油を生産している。また中国の渤海(ぼっかい)湾、サハリン沖合いなど世界各地で石油資源の探査を進めている。
[田中正三]
百科事典マイペディア 「油田」の意味・わかりやすい解説
油田【ゆでん】
→関連項目鉱山|採油|石油|油層
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
最新 地学事典 「油田」の解説
ゆでん
油田
oil field
狭義には一つの貯留層の直上に当たる地表の区域を指すが,地下の貯留層や油井などの産油施設まで含めて,しばしば曖昧に用いられる。ある地質条件下に近接して多くの油田が存在するときは油田群(oil fields)という。さらに産油区域に確認区域(proved area)・推定区域(probable area)・予想区域(possible area)を含め,類似あるいは関連地質条件下で多くの油・ガス田が存在する所を石油地域(province)という。これらも単に油田と呼ばれる。
執筆者:木下 浩二・公文 富士夫
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「油田」の意味・わかりやすい解説
油田
ゆでん
oil field
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...