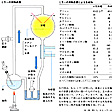精選版 日本国語大辞典 「生命」の意味・読み・例文・類語
せい‐めい【生命】
- 〘 名詞 〙
- ① 人間や動物、植物などが生物でありつづける根源。いのち。寿命。性命。しょうみょう。
- [初出の実例]「千金方云、自レ古名賢治レ病、多用二生命一、以済二交急一」(出典:政事要略(1002頃)九五)
- 「かずならぬ身なりともといひつつ、せいめいにまつりかへられければ、明王、命にかはりて」(出典:とはずがたり(14C前)五)
- 「元気は生命の本也。飲食は生命の養也」(出典:養生訓(1713)三)
- [その他の文献]〔戦国策‐秦策・昭王〕
- ② その方面、分野で活動、存在し続けることができる根源。
- [初出の実例]「政治的生命は絶えたと、世間の評判は喧ましかったぢゃらう」(出典:社会百面相(1902)〈内田魯庵〉電影)
- ③ 唯一のよりどころ。いのち。
- [初出の実例]「恋を生命とし、恋の為に半生を犠牲にした」(出典:春潮(1903)〈田山花袋〉一)
- ④ そのもの独特のよさ。神髄。また、一番大切なところ。いのち。
- [初出の実例]「詩の生命(セイメイ)は節奏なりと曰ひしが」(出典:詩辨(1891)〈内田魯庵〉)
- ⑤ 他の存在から区別する生物固有の特性。哲学で、この特性を、無機世界の原理に還元できるとする機械論の考え方と、無機世界とは違った独自の原理と見る生気論の考え方に分けられ、後者には、一生物の全体は部分の総和以上の原理があると見る全体論が属している。
しょう‐みょうシャウミャウ【生命】
- 〘 名詞 〙 ( 「しょう」「みょう」は、それぞれ「生」「命」の呉音 ) いのち。寿命。せいめい。しょうめい。
- [初出の実例]「此の人、性(ひととなり)、本より畋猟(かり)を好むで、朝暮に生命(しゃうみゃう)を
 すを
すを (やく)とす」(出典:今昔物語集(1120頃か)九)
(やく)とす」(出典:今昔物語集(1120頃か)九)
- [初出の実例]「此の人、性(ひととなり)、本より畋猟(かり)を好むで、朝暮に生命(しゃうみゃう)を
日本大百科全書(ニッポニカ) 「生命」の意味・わかりやすい解説
生命
せいめい
生命とは人間を含めた生物一般の基本的な属性である。しかし生命を科学的に規定することはなかなかむずかしい。生の否定である死の定義が医療の現場の問題としても議論の的である現状からも、生命の定義のむずかしさがうかがえる。かりに脳の活動停止を個体死と規定しても、機能を維持している器官や組織が存在している。個体をつくっているすべての細胞が活動を停止すれば、生物学的には完全に死であるが、これも難問を含んでいる。なぜなら、細胞が死んだというためには、「細胞が生きている」ということが規定されていなければならない。その完全な規定はまだなされていないのである。このような現状のもとで、「生命とは何か」という問いに対してすべてを満足させる定義を与えることはできないといえよう。では現代の生物学は生命をどのようにみているか、また、生物と無生物を隔てるものは何か、について述べる。次に生命に対する見方が歴史的にどのような変遷を経てきたか(生命論または生命観の歴史)の概略を記し、最後に生命の起源について述べる。
[川島誠一郎]
生命現象
生命について得られた生物学上の知見は莫大(ばくだい)な量に達しており、生物の特性としてあげられてきたものには、生物体の有機物質を主とした構成と有機物質の生産、代謝、刺激反応性、ホメオスタシス維持の能力、自己複製と生殖、遺伝と変異などいろいろある。いずれも生物学的に重要なものであるが、「生命」の必要十分条件を規定するのはむずかしい。
[川島誠一郎]
代謝
ウイルスを例外として、生物の体は細胞からなっている。したがって細胞が営む物質代謝(簡単に代謝とよぶ)は生命の重要な特性の一つである。生物は絶えず外界から物質を吸収し、また外界へ排出している。これが代謝の外見である。細胞内では環境から吸収した物質によって絶えず物質の更新が行われている。これは生命維持に不可欠で、代謝の停止は生物の死を意味する。代謝が進行していても、一般的には細胞や生物体の形態の急激な変化はおこらない。これは代謝が合目的的に調節されていることを意味している。
生物体を構成している物質を原子のレベルにまで分けると、無生物の世界を構成している原子と同じである。代謝も素反応(種々の反応の構成要素となる基本的反応)に分けると、無生物界でおこっている化学反応と違いはない。このことから、生命の特性としての代謝は素反応の組合せ方に特徴があるということになる。分子のレベルにおいては生命に特徴的な性質がみられる。生物体を構成する物質には、水と無機塩類のほかに、有機物質であるタンパク質、核酸、炭水化物、脂質などがある。これら有機物質は、基本的には生物のつくりだす物質である。なかでもタンパク質はたいせつな物質で、生物体の形をつくり、酵素作用を営む。タンパク質には構造の異なる多数の種類があり、このために酵素作用を営むタンパク質に特異性が生じる。たとえば脂質を分解する酵素が糖を分解しないというように、ある反応を触媒する酵素は他の反応を触媒できない。
どの種類の酵素タンパク質をどのくらいもっているかによって、生物の種による代謝の型の違いを生じるが、基本的な代謝はバクテリアから人間に至るまで共通性がある。たとえば動物が運動する際の筋収縮のエネルギーも、養分を吸収する際の腸絨毛(じゅうもう)の用いるエネルギーも、ホタルの発光のエネルギーも、すべて高エネルギーリン酸化合物(ATPなど)の分解によってまかなわれている。生体内にはさまざまな代謝があるが、各個の代謝はかってな速度で進行しているのではなく、全体として、生命維持の目的を損なわないように制御されている。この制御は、(1)酵素活性に対する直接的制御、(2)酵素自体も代謝の反応生成物であるから、酵素生成量を変え、その結果として代謝を制御する、の二通りがある。
生物と環境とは不可分の関係にあり、環境のある程度の変化に対して生物は適応する。この性質によって、形態や機能の安定が保たれている。その基盤に代謝各反応の制御がある。多細胞生物では、細胞内の酵素反応の制御だけでなく、細胞と細胞の間、各組織間、各器官間に個体全体として調和を保つような調節がなされている。
[川島誠一郎]
自己複製と遺伝
すべての生物に普遍的な特性は、自らときわめてよく似た子孫を再生産する能力をもっていることである。この自己複製の過程は遺伝とよばれ、生命の基本的特性としてあげられる。
遺伝学はショウジョウバエやトウモロコシなどの高等動植物を用いて研究が行われてきたが、その後バクテリアやウイルスなどが研究材料として利用され始めるに及んで、急速な進歩を遂げ、遺伝子の実体も明らかになってきた。その知見をもとに高等動植物の遺伝子の物質的実体の解明も進んでいる。
遺伝形質を支配する情報はDNA(デオキシリボ核酸)に含まれている。ウイルスではRNA(リボ核酸)のこともある。バクテリアに寄生するウイルスのバクテリオファージが菌体に寄生するとき、菌体内に入るのはDNAだけであることから、バクテリオファージの増殖に必要なのは、それを構成するタンパク質と核酸のうち、核酸であることが明らかとなった。DNAの複製にはDNAポリメラーゼという酵素が働く。核酸のもっている遺伝情報が発現する際、すべての情報が等しく発現するのではない。このことは、1個の受精卵から性質や形態の異なる多様な組織や器官が分化してくる現象が示している。これは、遺伝情報が発現するときのタンパク質合成の制御として説明される。ある種のタンパク質を合成する情報があってもその合成がおこらないのは、伝令(メッセンジャー)RNAへの遺伝情報の暗号の転写がおこらないのがおもな理由である。情報が発現するのは、常時抑制されていた転写過程の抑制が解除されることによる。
この過程は、F・ジャコブとJ・L・モノーが提出した(1961)タンパク質合成の調節機構に関する学説(オペロン説)では次のように説明される。遺伝子は構造遺伝子と調節遺伝子の二者に分けられ、タンパク質の遺伝的調節にはこの二者が異なる機能を発揮している。構造遺伝子はタンパク質の構造を決定し、調節遺伝子は構造遺伝子によるタンパク質の生産量を調節する。数個の構造遺伝子の並んだ一単位をオペロンとよぶ。これと隣接する位置にありオペロンを特異的に調節するオペレーターにより、暗号の転写が制御されている。調節遺伝子はリプレッサー、アポリプレッサーなどの調節物質をつくる遺伝子である。リプレッサーはその系のオペレーターを識別し、それと結合することでオペレーターへ連なる遺伝子、すなわちオペロンの働きを抑制する(負の調節)。負の調節が行われている間は、オペロンの伝令RNAへの転写はおこらない。実際には負の調節機構だけでなく、正の調節の例も知られている。また、転写レベルだけでなく翻訳レベルでの調節も発見されている。
遺伝は、生物が自己と似た子孫をつくることであり、分子遺伝学によれば究極的には細胞核内のDNAの自己複製の問題であるが、生物は安定した遺伝性とともに、自己とすこし異なる子孫を再生産する変異性をもつ。もし遺伝による再生産がまったく変化しないものであれば生物の進化はおこりえない。生物の変異と進化は生命現象として特筆に値することである。生命のこの特性は、DNAは安定した分子ではあるが絶対的な安定性はもっていないことに基づいている。
放射線や変異原性をもったある種の薬品を作用させると、突然変異といってDNAまたは染色体に変化がおこる。DNA分子構造の変化としては、あるヌクレオチドの欠損や他のヌクレオチドによる置換、新たなヌクレオチドの付加や挿入などがある。場合によってはヌクレオチドの切断がおこる。こうした変化がDNAにおこると、リボゾームで合成されるタンパク質の配列に変化が生じ、タンパク質の一次構造が変わる。放射線や薬品によってDNAの構造の一部に変化が生じた場合、その障害がわずかであれば、細胞はこれを修復する特殊な酵素をもっている。しかし障害が大きければ修復できずに、その生物は生存できないか、元の生物と異なる突然変異体を生じる。突然変異体は自然選択を受け、適者が生存することによって進化がおこる、と一般的に考えられている。地球上の環境は一定不変ではないのであるから、変異体を生じる可能性は、新しい環境によりよく適合する子孫を残す確率を高めることに通じる。DNAの自己複製とそれに基づく個体の増殖に加えて、DNA分子の一定の不安定性、および先に述べた物質代謝とその調節は、生命の重要な基本的特性であることは、揺るぎのない事実である。
[川島誠一郎]
生物と無生物
「生命とは何か」の解答に接近する方法の一つは、生命現象をもったもっとも単純な有機体を調べることである。前述したように、バクテリオファージはバクテリアを宿主として増殖するウイルスであるから、自己の写しをつくるという生物共通の属性を備えている。親から生まれた子がふたたび親になるまでには、環境に向かって開放された物質系としての生体が、絶えずエネルギーを消費しながら生命活動を続けながらも、その形態と機能の同一性を維持するために自動的に調節された代謝系がなければならない。この自己増殖と代謝の二つを生命の共通項として認めた場合、バクテリアからアメーバ、ヒトに至るまでこの規定は完全に通用する。それではウイルスでは代謝はどうなっているのであろうか。
W・M・スタンリーは当時のタンパク質化学の進歩を背景にタバコモザイク病のウイルスを結晶化した(1935)。約4000万という巨大な分子量をもった核タンパク分子がタバコモザイクウイルスにほかならない。彼の用いた純化の方法は他の多くのウイルスの分離には応用できない手荒な方法であった。しかし超遠心機ができ、インフルエンザ、ポリオ、牛痘その他の動物ウイルスの純化がなされた。動物ウイルスのあるものはRNA、あるものはDNAをもち、それとタンパク質とで構成されていて、ものによってはかなりの量の脂質や多糖類を含んでいる。わずかの例外を除くとウイルスには、生物に不可欠と考えられエネルギー調達にあずかる呼吸酵素系をまったく欠いている。この酵素系がないため、ウイルス粒子は無生物的培地では増殖できない。この問題はまずバクテリオファージで解決された。バクテリオファージは、デレルF. H. d'Hérelleが1917年、トウォートF. W. Twortが1915年に独立に発見し、デレルにより「バクテリアを食う生物」という意味で命名された。彼らの研究は、赤痢患者の腸内容を濾過(ろか)して微生物を除去した濾液中に赤痢菌を溶かす働きが証明され、そのうえ、代を重ねることができた、という観察からなっている。つまり、ウイルスは自立した生物ではないが、生物界だけにしか認められない働きをすることのできる有機体である。ウイルスは他の生物体が存在しなければその全貌(ぜんぼう)を現すことがない。このように、ウイルスは生物としての体制または全一性をもっていないことから、それを生物とみるか無生物とみなすかは人により見解を異にする。しかし問題を広げると、生物の属性と考えられるすべてを備えていない生物の例はいくらもある。
ウイルスはどのように発生したのであろうか。現存するウイルスはすべて、宿主の細胞なしでは生存できない存在であるから、その起源は細胞の出現以後だと考えるのが論理的であろう。生命の原型として核酸とエネルギー調達能力のある酵素タンパク質とをもつもの、と仮定しても、ウイルスは後者の能力を失った存在と考えれば矛盾はないと思われる。ウイルスは(1)元来細胞の中にあった遺伝子が抜け出したものか、または(2)寄生性の微生物が宿主体内での甘えた生活を代々続けている間に、リケッチアやオウム病群病原体(DNAとRNAをもつリケッチアに近いもの)にその中間段階が示されているような生化学的退化、さらにエネルギー調達系の退化を続けて最終的には代謝機能をまったく喪失するに至ったものか、どちらかであろうと考えられているが、いずれにしても生命の歴史のうえでは細胞出現以降のいわば有史時代のできごとであろう。ウイルスは石ころのような無生物とは違い、自己増殖という生命の特性をりっぱに備えている。しかし、現生ウイルスの諸性質は、細胞出現以前の生命がウイルスのような存在であったことを証明するものではない。
[川島誠一郎]
生命観の変遷
古代の生命観
古代において生命の源と考えられた精霊は、地中、水中、大気中など至る所に潜んでいるとされた。しかしギリシアの医学者ヒポクラテスは病気の原因を精霊の乱れや神業に帰することなく、自然的原因によるものであることを主張した。これはひいては全生命現象への科学的見方の基本である。彼の唱えた、体には4種類の体液があり、その不調和が病気をもたらすという体液説は、近代の病理学に至るまで長く医学を支配してきた。プラトンに学んだアリストテレスは動物学の父であり、彼は、動物界と植物界をあわせた生物界が体制の移り変わりによって系列的に配置されると考え、「自然は、無生物から生物ではあるが動物ではないものを経て動物に至るまで、連続的に移り変わっている」(動物部分論)と述べた。しかし各器官はそれぞれ特徴的な霊魂をもち、自然はその目的のためにあるとする目的論者であった。アリストテレスが開拓した博物学の知識は、顕微鏡の発明により、微小生物の世界へと拡大していった。ローマの医学者ガレノスの説は次のようである。腸で消化された食物が門脈を通って肝臓に運ばれ、そこで食物から血液がつくられる。血液は心臓に運ばれ、一部は肺に送られる。肺から左心室に精気(プネウマ)を取り込むと鮮紅色の血液となり、動脈で全身に送られる。肝臓、心臓、脳を体の3個の主要器官とし、静脈、動脈、神経を脈管三型として、3種類の精気をそれぞれに対応させた。外界から取り入れた精気は肝臓で成長の原理となり、心臓では生命精気となり運動の原理に、動脈の一部は脳に達し精神精気となる。つまり成長、運動、思考という主要な生命作用の区分はアリストテレスの唱えた3種類の霊魂の説に結合している。古代における生命論は超人間的な生気が支配すると考えるもので、生命論を生気論と機械論に分けるなら生気論の一種である。
[川島誠一郎]
近世の生命観
ルネサンスの芸術家のアトリエに近代科学の源泉がある、といわれるのは、芸術家の写実的精神が自然の科学的探究を促したからである。レオナルド・ダ・ビンチは動物体と人体の解剖を行った。ベサリウスは1543年に『人体の構造について(ファブリカ)』を刊行した。ハーベーは著作『動物の心臓ならびに血液の運動に関する解剖学的研究』(1628)で、血液循環の経路を明らかにした。また簡単ながら実験によって仮説を確かめた。これらにより旧来の盲信が打破された。アリストテレスの目的論にかわり、因果関係を重要視したデカルトの生命機械論により、思考の合理性が尊重され、疑いの残らない明快な生命観が追究されるようになってきた。この時代には科学的化学が錬金術師の作業場から脱し、近代力学の体系が成立した。それは自然観の基本理念として浸透し、生命をもつ存在にも及ぼされた。生命現象に超自然的な原理が介入することを拒否し、生命を物質的現象と考えるのが生命機械論である。デカルトは生命機械論から人間を除外したが、ラ・メトリは機械論を人間にまで拡大した。生命現象の科学的研究が進むにつれて機械論は広まるが、機械論の内容に変化がおこり、新しいものになっていく。一方で生気論的生命観も命脈を保ち、時代とともに新しい形態のものが現れている。筋繊維の被刺激性と神経の興奮性の概念は、生命観の歴史で重要である。A・von・ハラーはこの問題を機械論の枠組みのなかで考えたのであるが、被刺激性、興奮性の概念が力学では説明しきれない生命原理の存在を印象づけた。このため、生気論的生命観の傾向が18世紀なかばからまた濃くなってきた。
[川島誠一郎]
19世紀の生命観
19世紀の初めに「生物学」という用語ができた。これは統一的な生命の科学的研究が成立していく気運を示す。1830年代末の細胞説の確立は、動物と植物が共通した存在であるという認識を深める基盤として重要であった。シュライデンによれば、細胞はそれ自身が独立の生命を有する個体で、構造的・機能的単位である。シュワンも同様に考えた。生体の構成物質に関する研究が生化学へと成長し、記載的段階にあった形態学、発生学が実験的科学へと進み、遺伝の実験的研究が生物学の重要課題として前面に押し出されてきた。次に19世紀の生命論の代表的な例をあげる。(1)俗流唯物論 K・フォークト、F・K・C・L・ビュヒナー、J・モレスコットによる。フォークトは、思想の脳に対する関係は、胆汁の肝臓に対する、尿の腎臓(じんぞう)に対する関係と同じであるという。議論が単純すぎるために俗流唯物論とよばれる。(2)エンゲルスの生命論 19世紀後半の弁証法的唯物論の立場からの生命論で、エンゲルスの『反デューリング論』と『自然弁証法』での議論をさす。生命はタンパク質の存在様式であるとした規定は、その哲学の枠を超えて有名となった。タンパク質は単に存在するだけでなく、他の生体物質との関連で機能している。それが生命であると説いている。(3)ドリーシュの生命論 H・ドリーシュの実験発生学は前成説への挑戦であった。ウニ胚(はい)の二細胞期や四細胞期の割球をばらばらに分離すると、各割球から小形ながら完全なプルテウス幼生が発生した。この結果は後成説的であり、各割球は正常発生において形成するよりも多くの部分をつくる調節能力をもっていることを示す。このような調節能力をもち、個々の割球の発生運命はその部分の全体に対する関係によって決定されると考えられる胚に関して、調和等能系という概念をたてた。彼は調和等能系を成立させる原理として、アリストテレスが用いたエンテレケイアentelecheiaを転用してエンテレヒーentelechie説という超自然的な考え方(個々の生体部分が、発生運命の決定に関して、あらかじめ目的を自らのなかに含む自律的因子としてエンテレヒーをもつという説)を提唱した。このため、ドリーシュの生命観は新生気論とよばれる。発生学の歴史では、シュペーマンの形成体の誘導作用という大仕事が成し遂げられた。形成体中の誘導物質として多くの種類のタンパク質が報告され、生命現象の化学的解明が推し進められるようになった。
[川島誠一郎]
20世紀前半の生命観
実験生物学の急速な発展に伴い生命現象を物質現象と考えることが普及したが、実際にはあらゆる研究者がこの立場にたったのではない。ドリーシュの調和等能系の概念は、生命現象における全体性の概念につながるものであり、さまざまに異なる全体論があった。生理学でのホメオスタシス(恒常性。生物体などが安定な形態・生理的状態を保つ性質)や統合(生体活動の安定性や統一性を保証する中枢神経系の機能)の概念や、環境と生体とを切り離せないものと認識する立場は、全体性の概念へ接近しやすいものである。オーストリアのベルタランフィは、発生現象の考察から出発し、有機体論(生体論ともいう)を唱えた。生気論に陥らずに機械論の単純さを超えることが意識されており、生命現象の段階的発展(階層性)と、生物体は開放系であるから流動平衡(動的平衡)をもつこととが生命の本質であると説いている。
[川島誠一郎]
分子生物学の台頭と生命観
第二次世界大戦の終了時、物理学の到達度と比較し生物学は未開拓であった。物理学者が生物学の問題解明に向かうことにより、生物物理学が興隆してきた。分子生物学はアメリカ合衆国、イギリス、フランスを中心におこり、生体高分子物質、とくに核酸およびタンパク質の構造と機能、それらを中心に据えた生命現象の統一的理解を目的とした。分子生物学は初期において分子遺伝学と同義語であったが、その後、分子生物学の対象は、脳を含めての生理学、発生学、生態学にまで拡大した。分子遺伝学の成立に寄与した情報理論またはシステム論も、その適用範囲は生物学の多くの分野に及んでいる。つまり分子生物学の成立で全生物学が新しい光のもとにさらされたといえる。分子生物学の対象のなかで、高度の物理学的概念や技術を必要とするものは生物物理学の課題となる。結局、次のような課題は生物学、分子生物学、生物物理学に共通のものになっている。すなわち、運動生理、エネルギー代謝、放射線生物学、細胞の分化と増殖の制御機構、免疫における抗体産生、脳と神経の生理、遺伝、分子進化の機構などである。このように生命の本質を、従来の諸科学分野の枠を乗り越えて理解しようとする生命科学をライフサイエンスとよぶ。
分子生物学の初期の研究はほとんどがウイルスとバクテリアを材料とした。これらの材料で通用することは高等生物にも通用するというのが、その際の一般的観念であった。遺伝の生化学的実験がバクテリオファージとバクテリアについて、20世紀に入って広く研究された。そしてDNAが遺伝物質である確かな証拠が得られた。J・D・ワトソンとF・H・C・クリックが共同研究によってDNAの構造について二重螺旋(らせん)モデルの仮説を提唱した業績は、生物学の革命であった。X線回折像に基づき、DNAは一定の幅をもった2本の長い鎖であることを推定し、それが安定を保って複製すること、一方ではDNAが担う遺伝情報がいかにしてRNAに転写され、さらにタンパク質に翻訳されるかが、この仮説で説明された。
原子物理学者のガモフは、DNAの遺伝情報、つまりDNAに書かれた暗号がいかに解読されるかについて、連続する3個のヌクレオチドで1個のアミノ酸が指定されるという説をたてた。最初につきとめられたのは、RNAのUUU(DNAではAAA)がフェニルアラニンを指定するという発見であった。これがアミノ酸を指定する他のすべての遺伝暗号(コドン)を解明する手掛りとなった。そして1966年までに、すべての暗号が解読された。DNAとRNAの実体がわかったため、人工的に遺伝子をつくり、それを細胞内に注入して働かせたり、異種生物間で遺伝子を組み換える可能性などが考えられるようになった。遺伝子組換え実験の過程でおこるかもしれない危険を避けるための実験指針も各国でつくられた。この指針に沿って、大腸菌にヒトのインスリン遺伝子を入れインスリンをつくらせるなどのことが広く企業化され始めた。これを遺伝子工学とかバイオテクノロジーとよぶ。臓器移植、クローン生物、遺伝子組換え、試験管ベビーなどの生命操作が急激に進んでいくことは、科学的生命観だけでなく、哲学的生命観に大きな影響を与えずにはおかないであろう。
現代生物学における生命観の基本は、生体を自動制御系としてみていくことであるといえる。生命観の大きな種別でいうと機械論であるこの見方は、1948年アメリカのN・ウィーナーによりサイバネティックスの名を与えられ「動物と機械における制御と通信の理論」と定義された科学に出発点がある。生命機械論の発展を大きく段階づけると、17~18世紀のデカルト‐ラ・メトリ的機械論が第一段階、19世紀から20世紀にかけての還元論的機械論が第二段階、これらの段階を踏まえた自動制御系としての生体という見方を中心にした現代の機械論を第三段階とすることができる。
[川島誠一郎]
生命の起源
生命はいつどのように地球に出現したか。この問題は哲学や神学の課題ともなっているが、生物学上の仮説は次の三型に分けられる。(1)生命は現在でも無生物から容易に自然発生する。(2)生命は遠い過去から宇宙に存在するもので、地球の誕生直後に落下した。(3)地球の歴史のある時期に、一連の化学反応が積み重ねられ、無生物的な有機物質が合成された。その後の物質の進化の過程で生命とよぶにふさわしい有機体が形成された。
[川島誠一郎]
自然発生をめぐる問題
生物の自然発生は古代から広く普及していた観念であるが、17世紀になって疑問が抱かれるようになったのは、発生の観察が盛んになったことに原因がある。17世紀後半にイタリア人のレーディは、生肉を瓶に入れ、それをガーゼで覆っておくとウジがわかず、覆わないでおくとウジが発生するという観察から、ウジはハエの卵から発生することを明らかにした。しかし、生物の自然発生の一般的否定までに至らず、ヒトの寄生虫などは自然発生すると考えた。その後の研究によって、寄生虫も含め、肉眼的に複雑な構造をもつ生物の自然発生は、18世紀までに考えられなくなった。18世紀後半以降論争の的になったのは微小な生物の自然発生であった。肉汁の腐敗やブドウ汁の発酵をめぐって、同じフランスのプーシェF. A. Pouchetとの論争を含んで研究を進めたパスツールは自然発生の否定に成功した。彼は、肉汁のような有機物を含む液を滅菌してから空気に触れさせても、空気中の微生物や胞子を適当な方法で除けば「自然発生」はおこらないことを巧みな実験で証明した。なかでも「スワン首のフラスコ」を用いた実験は有名で、論争解決の鍵(かぎ)となった。彼の『自然発生説の検討』は1861年に書かれた。
[川島誠一郎]
生命宇宙起源説
1860年前後の、生命観にかかわるもう一つの画期的な事件は、C・ダーウィンの『種の起原』の刊行(1859)であった。生物進化の過程を逆にたどれば、地球上におけるもっとも原始的な生物に行き着くことになる。ではこのもっとも原始的な生命体はどのようにして生じたのであろうか。生命には起源があるはずであるという論理的結論と、生物の自然発生はないという実験結果との間の矛盾を解決するため、生命の胚(はい)種が他の天体から地球にやってきて発展したのであるという説が現れた。ドイツのH・T・リヒターが1865年に、イギリスのW・T・ケルビンが1871年に、生命の胚種をつけた固形粒子が宇宙空間に飛び出したり、天体どうしの衝突で生物の付着している破片が宇宙空間に飛散して地球に落下したのであろうと述べた。スウェーデンの物理学者アレニウスは、原始生命は宇宙から光圧にのって到来したという可能性を理論的に示した(1903、1908)。現在この説は否定されているが、その最大の理由は、宇宙空間に存在する種々の高エネルギーの放射線に耐えられる生命体は考えられないからである。宇宙起源説は、地球における生命の起源の問題が他の天体における生命の起源の問題に転嫁されているので、たとえその説が正しいとしても真の解決とはならないことに注意しなければならない。
[川島誠一郎]
物質進化の帰結としての生命
生命の自然発生や宇宙起源説にかわり、現在では、地球上の生命は地球上における有機物の進化の結果として生じた、という考えが一般に信じられている。ソ連の生化学者オパーリンやイギリスのJ・B・S・ホールデンは、天文学や地球化学などの資料を広く集めて原始地球の状態を想定し、原始的生命体を構成する有機物がどのような過程で無機物から生じてきたかについて考え、生命起源説をたてた(1922)。オパーリンは著作『生命の起源』(1936)ではタンパク質の生成に重点を置いているが、のちに核酸とタンパク質とがまとまった系として生成するという観点を重要視した。
アメリカのミラーS. L. Millerは、オパーリンやホールデンの想定した原始地球の物理学的・化学的環境を模倣した条件でのモデル実験によって、有機物の合成が可能なことを証明した。地球が形成されたのは46億年前で、やがて原始海と原始気圏ができた。原始気圏は遊離窒素を含まない還元性のものであったと考えられている。そこでミラーは、原始気圏の仮想的成分であるメタン、アンモニア、水、水素の混合気体を、電極を入れたガラス管内に封入した。この管の中で数週間にわたって放電したところ、さまざまの単純な有機分子が気体相から分離し、ガラス管の底にたまった。この中には数種類のアミノ酸が含まれていた。
これらの生成物のかなりの種類が、月の石や隕石(いんせき)から検出されている。これは間接的ながら、生命誕生に必要な成分が無生物的に原始地球で生成されたとする仮説を支持するものである。生成された有機物は原始海底に蓄積し、やがて物質代謝や自己複製能力をもった細胞構造、すなわち生命が誕生した、と考えるのである。しかし、有機物から原始生命への発展の経路は一般に信じられている考えであるが、実験的証明はない。オパーリンは原始生命のモデルとして、コロイド状のコアセルベート(液滴)を用い、この中に酵素を封入し、細胞に似た代謝反応を行わせる実験を報告した。
オパーリンやホールデンの仮説によっては、生成物は広大な水域中に拡散し、生命誕生に必要な濃度にまで達したとは考えにくい。これを解決する仮説をJ・D・バナールが提唱した(1967)。最初の生命は酸化白土性粘土粒の中に生じたという仮説で、詳しくは次のようである。淡水や海水中で細かい粘土の沈殿物に吸着された小さな有機分子はでたらめにじっとくっついているのではなく、粘土分子との間および相互間に一定の位置をとる。これは、吸着された分子が互いに作用しあうことができ、とくにエネルギーが光の形で供給されうる場合にはいっそう複雑な化合物を形成することができるような位置である。以上のようにバナールは有機高分子の出現における粘土の役割を述べている。この粘土をイギリスのカーンス‐スミスA. G. Cairns-Smithは原始遺伝子と考えた。その素材の濃縮促進作用のある原始遺伝子の担う情報解読は、現存の核酸パターンの解読より、さらに直接的な物理化学的反応である。原始遺伝子、つまり粘土結晶による支配が、粘土結晶のパターンに従って生成した有機高分子(たとえば核酸)による遺伝的支配に移行したのが、生命の起源にかかわる重要段階であると考えた。しかし、DNA分子が存在しても、酵素DNAポリメラーゼとATPからのエネルギー供給系がなければ、現在の生物では自己複製はおこらない。この過程の実験的証拠はないが、すべての既知の生物がDNA(またはRNA)を含んでいるという事実から、最初に出現した自己複製体がDNA(またはRNA)を含んでいたと考えるのは妥当な論理的帰結であろう。
イギリスのアンブロースE. J. Anbroseは、種々の生命の原始形態があったとした場合、特定のものだけが自然選択の結果残ったとは考えられないと主張している(1982)。なぜなら、原始的な生命形態は、地球の表面は広いので、必要とする物質を求めて競争する生物的環境にさらされていなかった。また塩基をDNAの中に規則正しく、偶然に並べる確率は非常に小さく、分子のランダムな組合せから多くの種類の原始生命が同時に生じたとは考えられない、生命の起源はただ一度のできごとであったに違いない、と述べている。
[川島誠一郎]
環境と原始生命の進化
生物発生以前の地球には遊離の酸素は存在していなかったから、初めて出現した生物は無酸素的に有機物を分解しエネルギーを獲得する発酵型の微生物であったとされる。発酵により二酸化炭素が増加すると、次に、この二酸化炭素を利用し光のエネルギーで有機物を合成(光合成)することのできる「植物」が出現する。ここで初めて酸素が発生する。次に酸素による酸化をエネルギー獲得手段とする「動物」が発生した、と考えられている。いわば環境の変化が生物を変化させ、逆に生物が環境を変化させる(環境の生物化)という、両者の密接な相互作用がみられる。生物と外なる自然とをあわせて生態系というが、生物はこの構造のなかでのみ生存できる。また、この構造の発展とともに生物はより高次の生物に進化した。
生命現象の分子レベルでの解明がさらに進み、生命の起源に関する問題点が宇宙生物学やモデル実験による寄与などにより解決されたとき、生命の定義は再検討されなければならない。
[川島誠一郎]
『スミス著、八杉龍一訳『生命観の歴史』全2冊(1981・岩波書店)』▽『八杉龍一著『生物学の歴史』全2冊(1984・日本放送出版協会)』▽『アンブロース著、石川統訳『生命のシンフォニー』(1984・紀伊國屋書店)』▽『坂田昌一・近藤洋逸編『岩波講座 哲学Ⅵ 自然の哲学』(1971・岩波書店)』▽『木村資生・近藤宗平編『岩波講座 現代生物科学7 生命の起源と分子進化』(1976・岩波書店)』▽『バナール著、山口清三郎・鎮目恭夫訳『生命の起原』(岩波新書)』▽『シュレーディンガー著、岡小天・鎮目恭夫訳『生命とは何か』(岩波新書)』▽『オパーリン著、江上不二夫編『生命の起原と生化学』(岩波新書)』▽『パストゥール著、山口清三郎訳『自然発生説の検討』(岩波文庫)』
改訂新版 世界大百科事典 「生命」の意味・わかりやすい解説
生命 (せいめい)
命(いのち)ともいう。〈生物の本質的属性〉と定義することが多いが,この定義はあいまいであり,生命,生物の両概念に関して循環論法的でもある。また肉体つまり物質と区別される非物質的原理を前提とする感じも与える(英語のlifeは生活,生命の両方を指し,生物organismとほぼ同義の場合もあり,日本語でいう生命だけを指すことばではない)。それでもわれわれは〈生命現象〉〈生命の起源〉などの語を普通に用い,それで意味は通じるのだからそれでよいともいえるが,生命の厳密な定義をいかに下すかによって,それぞれの生命観があらわれるのでもある。
生命観とその問題
生命観あるいは生命論はしばしば目的論的なものと機械論的なものとに大別される。生気論と生命機械論の区別がほぼこれに該当する。生気論(活力論ともいう)はつまるところ生物に非物質的な生命力が存在して無機物とは異なった現象をあらわさせると説くものであり,結局は目的論的原理を認めることになる。一方,生命機械論は生物の現象を終局的に物質現象として理解する立場だが,それにいくつかのちがった考え方があることは後述する。なお新生気論,全体論,生体論(有機体論)などといった生命論の提唱もあり,実際には単純に割り切ることはできない。
生命をどう考えるかは生体の構造と機能の解釈に依存することであり,科学の発展によって異なってくる。その際とくに問題になることが三つある。(1)生命の起源について,つまり無機物からの生命の発生が可能か,(2)個体発生は前成,後成いずれの過程で起こるか,(3)生物の種は新たに生ずることはないか,それとも進化によって生じるかであり,これを三大問題という。個体発生の前成説と種の不変は聖書にもとづく観念と結合し,キリスト教徒にとってとくに重大な問題だが,生命の観念一般としても問題になることである。
古代,中世の生命観
宗教や迷信,あるいは神話や伝承にもとづく生命観は別として,科学的知識を基盤とした生命観の最初は,古代ギリシアの自然哲学にもとめられる。アリストテレスはその頂点に立つものであり,しかも後世にながく影響を及ぼした。かれは生命現象を,可能態である質料(ヒュレ)が現実態である形相(エイドス)として実現される過程として理解し,それは3種類の霊魂によって営まれるとした。植物には栄養作用の霊魂があり,動物にはその上に感覚作用の霊魂があり,そして人間にはさらに思惟作用の霊魂がある。またアリストテレスの4原因における目的因は生命現象においてとくに重要である。こうした点でかれの生命観は生気論的であり目的論的だが,しかし当時としては空疎な思弁を脱して現実の観察に相応させたものであった。
古代にあっても原子論者たとえばエピクロスやルクレティウスにおいては,霊魂も原子の運動にほかならなかったから,生命の唯物論的理解が少なくとも萌芽として存在する。他方,血液の働きを中心とした生命現象の説明には精気(プネウマpneuma)の観念が導入され,生命精気,霊魂精気,自然精気という3種類の精気の説は近代に至るまでもち続けられた。中世にはイスラム圏の学問で若干の生物研究は見られるが,生命観に関しては,アリストテレス的生命観や精気の説がもち続けられ,独特の神秘主義につらぬかれた錬金術や占星術ともいろいろの形で結合したが,生命の科学的解釈への道がとくに開かれることはなかった。
生命機械論の成立
ガリレイが血液循環の発見者W.ハーベーに直接影響を及ぼしたかどうかは不明だが,ハーベー自身はアリストテレス主義者であったにもかかわらず,かれの研究にはガリレイ的方法があらわれていた。また筋運動の力学的理解を基礎づけたG.A.ボレリはガリレイの弟子であった。17世紀において生命の機械論が提起される機は熟しつつあり,デカルトがそこにあらわれたのである。かれこそ生命現象の因果的理解の観念を科学の中に据え,近代生命科学を出発点につかせた学者であった。デカルトの生命機械論は《方法叙説》や《人間論》に述べられている。かれは動物を〈ゼンマイをまいた自動機械〉であるとし,つまり中世末期以来発達してきたゼンマイ時計と比較している。ただデカルトは人間だけには霊魂の存在を認めた。これに対し次の18世紀のラ・メトリーは,《人間機械論》(1747)において人間の霊魂をも否定し,生命機械論を徹底させた。かれもまたゼンマイ時計を比較の対象とした。そうした点でデカルトおよびラ・メトリーの生命機械論は機械との直接の比較の上に立つものであった。いうまでもなく当時において生命機械論は少数意見であり,反キリスト教の危険思想でもありえた。
→人間機械論
還元主義的機械論
18世紀後半から19世紀にかけて,生命機械論はその第2段階,すなわち還元主義的機械論になった。これは生命現象は究極において,物理学的および化学的現象あるいは法則に帰着ないし還元されるという観念であり,したがって特殊な生命力は認めない。A.L.ラボアジエが,呼吸の本質を燃焼に帰せしめたことは,その道を準備するものであった。19世紀前半にF.ウェーラーは尿素を(1828),A.W.H.コルベは酢酸を(1845)無機化合物から合成し,生体を構成する有機物質の合成に生命力は必要でないとする見解に論拠を与えた。しかし生命力あるいはそれに準じる観念は根強く存続し,19世紀前半では大生理学者J.P.ミュラーがそれを代表している。19世紀後半になって生理学および生化学の研究は急速に進み,生命現象の物理化学的解明の成果は累積し,世紀末には生理学的実験的方法を生物学の広範な分野に適用する実験生物学の成立がうながされた。哲学的には,思想も脳の分泌物であるという観念であらわされる生理学的唯物論が,K.フォークト,J.モーレスコット,L.ビュヒナーらによって唱えられた。他方,デュ・ボア・レーモンは,機械論的見解を推し進めつつも宇宙の究極には不可知の問題が残るとして,素朴な唯物論的理解を批判した。
三大問題の展開と生命観
時代をさかのぼり18世紀後半を見ると,カントの哲学と生命観とのかかわりが問題として浮かび上がる。動力因と質料因でどこまで説明できるかを論究しつつ,目的論的生命観をその座に据えたかれの哲学が多くの生物学者に理解されたとはいえないが,アリストテレスの哲学と同様に,後代の生命哲学に対して重大な論題を与えるものとなった。生物学の問題はおもに《判断力批判》(1790)で論じられており,それに進化の観念のあらわれがあることもいわれている。これと並び18世紀後半から19世紀前半にかけ,ドイツ観念論を基礎として生まれた自然哲学(いわゆるドイツ自然哲学)は,この世界を〈絶対理念〉の発現とみるなどの思想によって生物学に大きな影響を与えた。荒唐無稽の考えも多くあるが,細胞説の予見に近づいているとか,そのほか積極的意義を取りあげている歴史家もある。この自然哲学者の列に加えられるC.F.ウォルフは,18世紀後半,植物および動物の発生に関する後成説を唱え,その論拠となる観察事実を示した。かれはそれを含め,生命現象を生命力的な概念によって説明した。後成説は19世紀前半になりK.E.vonベーアの動物学的研究で確立された。ついで1860年ころは他の二大問題にとって重大な時期となった。ダーウィンは《種の起原》(1859)によって進化論を確立した。しかし生命の起源に関しては明確な記述はしなかった。L.パスツールは1860年代の初年,微生物の自然発生を否定する実験をし,生命の起源の問題に一時期を画した。ただし,かれは進化論には関心をもたなかった。そのパスツールは発酵の微生物説をもってリービヒの化学説と対立し,両者の意見の相違には生命力の問題がからんでいると一般には受けとられた。生命の起源に関してはその後いろいろの説がだされてきたが,1920年代よりオパーリンによって科学的研究の基礎づけがなされた。〈生命の起源〉に関して詳しくは〈生物〉の項を参照されたい。
新たな生命観へ
19世紀後半には,弁証法的唯物論の立場での生命観がエンゲルスによって論じられ,20世紀の唯物論者に引きつがれている。それは広い意味での生命機械論ではあるが,上位の現象(全体)を下位の現象(部分)に解消されないものとみる点で,全体論的生命観に所属させる論者もある。20世紀初年より提唱されたH.ドリーシュの新生気論は,動物が調和した全体として発生する現象に注目し,それを成り立たせる超物質的原理が存在するとし,アリストテレスの語(エンテレケイア)を借りてその原理をエンテレヒー(エンテレキー)と名づけた。これも全体論的生命観の一種とみることができる。20世紀にはそのほかいろいろの種類の全体論が,主として発生学と生理学の成果を土台として提起された。全体論holismの語を提案(1926)したJ.C.スマッツのほか,J.S.ホールデン,B.デュルケンはおもな論者である。J.S.ホールデンは生体と環境を一個の全体とする見方を述べた。つぎにベルタランフィは,流動平衡と階層構造を生命現象の特質とする生体論(有機体論)を提唱し(《理論生物学》1932),有力な生命観として普及したが,これにも全体論の要素があると考えられる。
現代生物学の実際の研究では,生体を物理化学的な系として解析を進めており,その点で見れば19世紀からの還元主義的生命機械論が中心に座しているわけである。20世紀にはいり,生物学には情報理論が広範に適用されるようになり,それは生体を自動制御系とし自動制御機械と類比する見方に通じている。そのことを重視すれば,20世紀には生命機械論の第3の段階が成り立ったことになる。生体を自動制御のシステムとする見方はサイバネティックスなどにあらわれ,また前記のベルタランフィは,生命現象を含めての一般システム理論を樹立した。分子生物学の成立と発展により,生命を物質現象として追究する道はますます広く開けかつ深く進んでいるが,それにともない科学的成果と論者の思想的立場との交錯から,各種の生命観的議論がまた新たに生じている。そのなかでJ.モノの著作《偶然と必然》(1970)は著者独自の機械論的見解を述べたものとしてとくに議論の対象になった。
現代生物学(医学などを含め)では生物一般および人間の生命がすでに広範に操作の対象になっており,生命操作の倫理の確立が重要な課題として提起されている。また,実際的に人間の生命の中心的概念である意識に関しては,大脳生理学の面からの議論が盛んになされるようになった。
執筆者:八杉 龍一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「生命」の意味・わかりやすい解説
生命
せいめい
life
生命の本質に関する考察は,歴史的に生気論と機械論的概念との間で分かれてきた。生気論では,生物を非生物から区別し生命の根底にある本質を形成するなんらかの「生命力」の存在を認める。機械論では,生命が特質としてもつあらゆる現象は基本的な化学と物理学の法則に従う処理過程と変換現象で説明できるとし,究極的に生物は原子と分子で構成されたものであってそれ以上のものではないと主張する。
原核生物である細菌類や藍藻類は地球上でもっとも古い生命形態と考えられている。南アフリカ共和国北東部トランスバール地方のフィグツリー層から発見されたこれらの化石は,年代測定により 35億年前のものとされた。地球自体の年齢は約 46億年と考えられているので,この化石は,生物が地球の誕生から数億年以内に出現したことを示している。神による無生物からの生命の創造という宗教的なものから,一連の化学反応によって生命が初期の地球上に誕生したという科学的な理論まで,生命の起源に関する仮説は数多くある。近年の実験結果からの仮説によれば,初期地球上で豊富だったメタン,アンモニア,水蒸気といった無機化合物が,大気中の放電と紫外線放射をエネルギー源としてアミノ酸などの単純な有機分子へと形づくられていったとされる。こうして生じた単純なアミノ酸がどのようにして複雑に組織化された自己複製システムしての生命となったのかという問題は,まだ完全には解明されていない。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「生命」の意味・わかりやすい解説
生命【せいめい】
→関連項目コアセルベート
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
普及版 字通 「生命」の読み・字形・画数・意味
【生命】せいめい
 物を
物を 理し、
理し、 物各
物各 其の
其の を得、生命壽長にして、其の年を
を得、生命壽長にして、其の年を へて夭傷(えうしやう)せず。天下其の統を繼ぎ、~之れを無窮に傳へ、~天地と
へて夭傷(えうしやう)せず。天下其の統を繼ぎ、~之れを無窮に傳へ、~天地と 始す。
始す。字通「生」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...