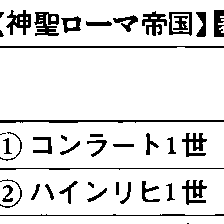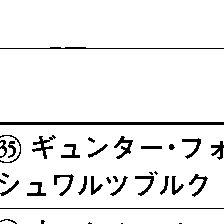神聖ローマ帝国(読み)シンセイローマテイコク(その他表記)Heiliges Römisches Reich
精選版 日本国語大辞典 「神聖ローマ帝国」の意味・読み・例文・類語
しんせいローマ‐ていこく【神聖ローマ帝国】
- ( [ドイツ語] Heiliges Römisches Reich の訳語 ) 中世から一九世紀初頭に至るドイツ国家の称。正称は「ドイツ国民の神聖ローマ帝国」。ドイツ王オットー一世の戴冠(九六二)以降歴代のドイツ王がローマ教皇から帝冠をうけて即位し、ヨーロッパ世界における俗権の最高君主となったが、もっぱらイタリア政策に努力を集中してドイツの分裂を招いた。一三世紀の大空位時代以後、皇帝の選挙権は七選帝侯に固定したが、一四三八年以後はハプスブルク家が帝位を独占。宗教改革期以後、領邦国家体制が確立するにつれて帝国は名目だけのものとなり、一八〇六年、ナポレオン支配下のライン同盟一六邦が脱退するに及んで、フランツ二世は帝位を辞し、消滅した。第一帝国。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「神聖ローマ帝国」の意味・わかりやすい解説
神聖ローマ帝国
しんせいろーまていこく
Heiliges Römisches Reich ドイツ語
Sacrum Romanum Imperium ラテン語
962年のオットー1世の神聖ローマ皇帝戴冠(たいかん)に始まり、1806年まで続いたドイツ国家の名称。
[平城照介]
名称
神聖ローマ帝国の正式の名称は「ドイツ民族の神聖ローマ帝国」Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation(ドイツ語)、Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae(ラテン語)であるが、この帝国が最初からそうよばれていたわけではない。帝国の先駆形態であるカロリング帝国はもとより、オットー1世の時代でも特別の名称はなく、単に「帝国」Imperiumとよばれていた。「ローマ」という形容詞が加わったのはオットー2世(在位967~983)の時代からで、とりわけ、ローマ帝国の復興を政治目的に掲げた次のオットー3世(在位996~1002)の時代に一般化する。さらに「神聖」なる形容詞が加わるのは、シュタウフェン朝のフリードリヒ1世(赤髯(あかひげ)王)の時代である。もともと神聖ローマ帝国は皇帝権と教皇権の2本の柱に支えられた一種の神聖政体であるが、聖職叙任権闘争の結果、教皇権=聖権と皇帝権=俗権の分離・対立が表面化し、皇帝権の世俗化が著しくなり、事態は聖・俗両権の分化という単純な形をとらず、皇帝権も教皇権もともに聖・俗両面を有するという主張を譲らなかった。皇帝側は、皇帝位は教皇によって授けられるものでなく、直接に神の恩寵(おんちょう)と諸侯の選挙によって決定されると主張し、「聖なる教会」Sancta Ecclesiaに「神聖な帝国」Sacrum Imperiumを対置した。その結果、大空位時代の皇帝、ウィルヘルム・フォン・ホラントWilhelm von Holland(在位1247~56)の時代に、初めて「神聖ローマ帝国」という名称が出現してくる。中世末、皇帝はイタリア支配を維持してゆく実力を失い、国王に選挙されたのち、ローマ遠征を行って教皇より皇帝として戴冠する慣行も、1452年のフリードリヒ3世を最後に後を絶った。神聖ローマ帝国の版図はドイツに限られたわけで、それに対応して、15世紀末より、「ドイツ民族の」という限定詞が付加されることとなった。
[平城照介]
帝国の変遷
神聖ローマ帝国の歴史的先蹤(せんしょう)は、800年のカール(大帝)の戴冠に始まる、いわゆるカロリング帝国であるが、この帝国もまた、476年に滅亡した西ローマ帝国の復活とみなされるものであった。ルートウィヒ(ルイ)1世(敬虔(けいけん)王)の死後、カロリング帝国は三分され、中部フランクと皇帝位は長男のロタールが、東フランクと西フランクはそれぞれルートウィヒとカールが継承し、東フランクはドイツ王国へ、西フランクはフランス王国へと発展するわけであるが、中部フランクはロタールの死後さらに、ロートリンゲン、ブルグント、イタリアに分割され、やがてカロリング家の王統も断絶した。ロートリンゲンはメルセン条約(870)、リベモン条約(880)により東西フランクに分割されたが、ブルグント、イタリアでは、在地の大豪族たちがそれぞれ王を自称し、対立・抗争を続けていた。
ザクセン朝第2代の国王オットー1世は、このブルグントとイタリアを征服、併合し、この地に残っていた皇帝権の伝統を手に入れることにより神聖ローマ皇帝となるわけであるが、ちょうどカール大帝がローマ教皇レオ3世の手により戴冠されたように、2回にわたるイタリア遠征を行い、962年、教皇ヨハネス12世の手により皇帝として戴冠された。以後歴代ドイツ国王は、即位後ローマ遠征を行い、教皇から皇帝として加冠されることが伝統となった。皇帝独自の権限というようなものはほとんどなく、名目的称号にすぎないが、教皇権の保護者であるという機能により、理念的には西欧キリスト教世界に一種の優越性を有したわけである。この優越性は、ザクセン、ザリエル、シュタウフェン3王朝を通じて若干の変動はあったとはいえ維持されたといえるが、同時に、のちに顕在化する教権と俗権との対立の契機をも含んでいた。
ザクセン朝時代のドイツ王国は、シュワーベン、ザクセン、バイエルン、フランケンなど、いくつかの部族大公領の合成体であったが、これは、部族大公の権力が強まり、在地の部族民との結合が強固になると、絶えず王国を分裂に導く危険を秘めていた。オットー1世はこれに対抗すべく、国家統一の支柱を、国内の教会勢力との結び付きに求める、いわゆる「帝国教会政策」なるものを採用した。大司教、司教、帝国修道院長などの高級聖職者に所領を寄進ないし封土として与え、種々の特権と保護を与えると同時に、彼らを国内統治上の枢要の地位につけるという政策である。この政策はザクセン朝の諸帝および初期ザリエル朝の皇帝によって継承され、かなりの成功を収めた。とりわけハインリヒ3世(在位1039~56)は、当時盛んになりつつあった教会改革運動の主導権を握り、教皇庁の改革をも助けて教皇権の権威の確立に貢献するところが大きく、神聖ローマ帝国の最盛期を実現した。だが、教会改革と教皇権の強化は、帝国教会政策にとっていわば両刃の剣であった。この政策は皇帝の聖職者に対する叙任権を前提としており、高位聖職者は大司教、司教、帝国修道院長に叙任されると同時に皇帝の封臣となり、皇帝に対し封臣としての奉仕の義務を負うが、これが教会改革の一つの攻撃目標であった聖職売買の一種とみなされ、ひいては俗権による聖職者叙任そのものまで否定される結果を生んだからである。とくに、教皇の至上権の確立を意図した教皇グレゴリウス7世と、教皇の警告を無視してミラノ司教の叙任を強行したハインリヒ4世との争いは、皇帝の王権強化政策と、それに反発する国内諸侯との対立というドイツ国内の政治状況と結び付いて、全国的内乱、いわゆる聖職叙任権闘争にまで発展したのである。
内乱はウォルムス協約(1122)によって収束したが、その間にドイツの封建化は急速に進み、聖俗の諸侯はそれぞれの領邦の樹立と領邦支配権の確立への道を踏み出す。これに対抗すべく、シュタウフェン朝のフリードリヒ1世は、西南ドイツを中心に皇帝自身も自己の領国の形成に努め(帝国領国政策)、皇帝であると同時に、一個の領邦君主でもあるという性格を帯びるに至り、中世後期、帝位が選挙により転々とするいわゆる「跳躍選挙」Springender Wahlの時代には帝国の運命に重大な影響を与えることになる。フリードリヒ1世は、諸侯中最大のハインリヒ獅子(しし)公Heinrich der Löwe(ザクセン公在位1139~80、バイエルン公在位1156~80)を失脚させるのにいちおう成功したが、諸侯から授封強制の原則(没収した封は1年と1日以内に再授封しなければならない)を承認させられ、神聖ローマ帝国は決定的に封建国家に転化した。孫フリードリヒ2世も再度にわたり国内諸侯に大幅に譲歩し、諸邦支配権確立の道をいっそう進めた。
シュタウフェン朝の断絶、大空位時代を経て、ハプスブルク家のルードルフ1世(在位1273~91)が皇帝に選挙されるが、以後帝国では選挙王制の原理が支配的となり、帝位は選帝諸侯の利害によって、ハプスブルク家、ルクセンブルク家、ウィッテルスバハ家などの間を転々とし(跳躍選挙の時代)、皇帝は帝国全体の利害よりも、一個の領邦君主として自家の利害を重視するようになり、帝国の弱体化を招いた。中世末、帝位はハプスブルク家に固定し、帝国の滅亡まで続くが、三十年戦争(1618~48)を終結させたウェストファリア条約により、領邦君主にほぼ独立国家の国家主権に近い自立性が承認された結果、帝国の領邦国家への分裂は決定的となり、近世の皇帝権はまったく名目だけと化し、ハプスブルク家は家領のオーストリアと西南ドイツの一部のみを実質的に支配するにすぎない状態となった。1806年、ナポレオン1世の保護下に結成されたライン同盟加盟の南ドイツ16領邦が神聖ローマ帝国からの脱退を宣言するに及んで、最後の皇帝フランツ2世は帝冠を辞退し、ここに帝国はおよそ840年の歴史に終止符を打った。
[平城照介]
帝国の機構
帝国の領域は時代によって変化したが、中核を形成したのはドイツ、ブルグント、イタリア(中部以北)である。デンマーク、ポーランド、ボヘミア、モラビア、また一時はハンガリーにもある程度の主権を行使し、シュタウフェン朝時代にはシチリア島も帝国に含まれた。
皇帝は、ドイツ国王が兼ねたのであるから、国王選出の原則が同時に皇帝選出の原則でもあった。国王は即位後ローマ遠征を行い、教皇から帝冠を受けるのが慣行であったが、1338年のレンゼ選帝侯会議およびフランクフルト帝国会議の決定により、選帝侯会議によって選出されたドイツ国王は、教皇の加冠を待たず、ただちに神聖ローマ皇帝でもあるという原則が確立し、ローマ遠征の慣行自体も中世末のマクシミリアン1世以後行われなくなった。ドイツ王制は選挙王制と世襲王制との二つの原理が結合したもので、王朝が安定している限り、形式的に選挙が行われても、実質上は世襲制の原理が支配的であったが、王朝が断絶すると、選挙制の原理が前面に出てくる。選挙は全会一致が原則であったので、事前に選挙人の意見の調整に成功しなかった場合には、それぞれが別な場所で選挙会議を開き対立皇帝を選出する(二重選挙)という事態がしばしば生じた。この欠陥を是正するため、カール4世は金印勅書を発布し(1356)、多数決原理の導入を図るとともに、選帝侯の数を7人に限定し、選挙手続も確定した。
7人の選帝侯は、マインツ、トリール、ケルンの大司教、ライン宮廷伯、ベーメン王、ザクセン大公、ブランデンブルク辺境伯であるが、17世紀以降その数に増減があった。
中世のドイツ国家は基本的に封建国家であり、皇帝の全国統治は皇帝と封臣間の封建的主従関係を介して行われたので、帝国直轄領を除き、いうに足る地方行政組織は存在しない。中央の行政機構も、その主要部分は文書行政であったので、聖職者が任ぜられる帝国書記局Reichskanzleiが主体であった。その最高官職は帝国書記官長Reichserzkanzenで、マインツ大司教が任命された。その職権はドイツに限られ、イタリアおよびブルグントに関しては別個の書記官長が置かれ、前者にはケルン大司教、後者にはトリール大司教があてられた。中央行政機構には、そのほかに訴訟処理を担当する宮廷裁判所Hofgericht、宮廷顧問会議Hofratおよびそれが発展した帝国会議Reichstagがあった。皇帝の封臣には、大侯、辺境伯、伯などの称号を帯びる世俗諸侯と、大司教、司教、帝国修道院長などの高位聖職者、および称号をもたないフライヘルFreiherrがあった。シュタウフェン朝時代における帝国諸侯身分の成立と領邦支配権の強化の結果、伯やフライヘルの多くは皇帝に対し陪臣化していった。帝国直属領には皇帝の代官として帝国代官Reichsvogtが置かれた。帝国都市が成立するにつれて、帝国代官は地方代官Landvogtと都市代官Stadtvogtとに分かれた。中世末期ごろより帝国都市(の代表者)も帝国会議に出席する慣行が成立し、ウェストファリア条約(1648)により、帝国都市の帝国会議出席資格が確認された。
[平城照介]
『今野国雄著『西洋中世世界の発展』(1979・岩波書店)』▽『G・バラクラフ著、前川貞次郎・兼岩正夫訳『転換期の歴史』(1964・社会思想社)』▽『M・パコー著、坂口昂吉・鷲見誠一訳『テオクラシー』(1985・創文社)』▽『平城照介著「神聖ローマ帝国」(『新版ドイツ史』所収・1977・山川出版社)』
改訂新版 世界大百科事典 「神聖ローマ帝国」の意味・わかりやすい解説
神聖ローマ帝国 (しんせいローマていこく)
Sacrum Romanum Imperium[ラテン]
Heiliges Römisches Reich[ドイツ]
中世西ヨーロッパのキリスト教世界は,教皇と皇帝という二つの中心をもつ楕円のような世界であった。そこでは,ローマ教皇を頂点とする教会が〈キリストの神秘体〉と考えられ,組織全体として〈聖なるローマ教会sancta Romana ecclesia〉とよばれたのに対応して,かかる教会の防衛を任務とする皇帝によって支配される超国家的領域は,〈ローマ帝国〉〈神聖帝国〉ないし中世中期以降は〈神聖ローマ帝国〉とよばれた。この名称は,皇帝の中世的超民族支配が国民国家の台頭の前に消滅したのちにもなお残存し,近世ドイツ帝国の呼称として1806年まで用いられた。
神聖ローマ帝国という名称が初めて現れるのは,皇帝フリードリヒ2世の対立王ウィルヘルム・フォン・ホラントWilhelm von Holland(在位1247-56)の晩年の証書においてである。その後,この名称は国王リチャード・オブ・コーンウォルの公文書を経て,ハプスブルク家のルドルフ1世(在位1273-91)の国王文書に継承され,爾来,ドイツ国王官房の公式用語として定着する。しかし,この場合,名称の初出は決して実体の誕生を意味するものではなかった。むしろ,この名称は,多少ともそれにふさわしい実体がすでに過去のものとなろうとしている時期に,いわばその理念的定式化としてうちだされたものであった。したがって,〈神聖ローマ帝国〉の理念に対応する現実を歴史に求めるとすれば,まだその名称の存在しない時代にそれを探らなければならず,また逆に,中世後期以降の神聖ローマ帝国なるものには,はじめからその名とは無縁な現実を予想しなければならない。
中世の諸皇帝がいずれもカロリング朝のカール大帝を範と仰ぎ,みずからを彼の事業の復興者ないし継承者として位置づけたことはよく知られている。800年にローマで戴冠したカール大帝は,その公文書のなかで〈フランク人とランゴバルド人の王〉という伝統的王称号を維持すると同時に,〈ローマ帝国を統(す)べる皇帝imperator Romanum qubernans imperium〉の皇帝称号をつけ加えた。これをもって,彼はコンスタンティノープルの皇帝(ビザンティン皇帝)の普遍的支配を拒否し,ローマ教会を基盤とする西方が彼の皇帝権のもとにたつ独自の宗教的・政治的世界であることを宣言したのである。カール大帝の〈ローマ帝国〉とは,ガリア,ゲルマニア,イタリアを含む大フランク帝国にほかならないが,フランク族による周辺諸部族の軍事征服を通じて形成されたこの大帝国は,通常の意味での国家として存立していたのではない。この帝国の統一性はむしろ一義的にローマ的キリスト教会の統一性に対応していたのであり,〈神の恩寵により〉その〈皇帝〉たるものの任務は,まず〈教会〉という形で組織された〈キリスト教徒共同体〉を内外に向かって守護することにほかならなかった。
カール大帝の直後にはじまったカロリング朝の解体と,ノルマン,マジャール,イスラム教徒による侵入のなかで事実上の機能停止に陥っていた皇帝権は,10世紀後半以降,ザクセン朝,ザリエル朝のドイツ諸王のもとに再び有力な担い手を見いだした。962年にローマ教皇から皇帝の冠を受けたオットー1世は,公式には後期フランク時代以来の官房用語の伝統にならって〈尊厳なる皇帝imperator augustus〉とのみ称したが,オットー3世は996年の戴冠直後に〈尊厳なるローマ人の皇帝Romanorum imperator augustus〉なる称号を採用した。これは決して偶然のことではなく,地中海的ローマ帝国の建設をさえ夢みたこの皇帝の熱烈なローマ理念は,皇帝印璽に刻まれた〈ローマ帝国の復興renovatio Romani imperii〉の標語にもはっきり表明されている。これ以来,ローマ皇帝の称号は確立された伝統として後継者たちに伝えられ,また,これに関連して,ハインリヒ3世(在位1039-56)以降のドイツ諸王は,ローマでの皇帝戴冠以前に〈ローマ人の王Romanorum rex〉という称号を用いるようになった。
このように,〈帝国〉はオットー1世以来ドイツ国王によって担われることになり,ドイツ王権とローマ的皇帝権との結びつきは,これ以降不動の原則となってしまうのである。ひとえにそれは,この時期のヨーロッパにカール大帝の帝国伝統を引き受けるに足る力を備えた他の王権がなかったゆえであり,また逆に,ドイツ王権がローマ教皇とキリスト教会全体を守護するという皇帝的課題の遂行を通じて,国内での権力基盤の確立と西ヨーロッパに対する指導的な地位の樹立とに成功したからにほかならない。すなわち,皇帝は神の意志を地上に実現すべき神権的統治者として,帝国教会に対する支配権をもっていたが,ザクセン朝,ザリエル朝の諸皇帝は,それに基づいて帝国司教教会と帝国修道院とを全面的に帝国の統治機関と化さしめ,それらがもつ,当時としては抜群の知的,経済的,軍事的能力をあげて皇帝の支配目的のために動員した(帝国教会政策)。その結果,11世紀中葉の帝国領域(ドイツ,イタリア,ブルグント3王国を含む)では,司教や修道院長の諸侯化傾向が著しく進行したが,この世俗化した高位聖職者こそ皇帝の支配基盤であると同時に,教会改革者たちの最大の攻撃目標だったのである。
グレゴリウス改革が皇帝の神権的統治に鋭い批判を加え,〈教会の自由〉をスローガンとして世俗権力の教会支配を排除しようとしたことは,ザリエル的帝国支配体制の土台をゆさぶるものであった(叙任権闘争)。ハインリヒ5世はウォルムス協約(1122)において,帝国教会の皇帝への世俗奉仕義務を一応確保することに成功したが,皇帝権はその本来的存立根拠であった宗教的基礎を基本的に失った。それに代わって,シュタウフェン朝の皇帝は,新たな皇帝権の根拠づけとしてローマ法を積極的に継受するとともに(ローマ法の継受),カール大帝の列聖を推進して皇帝の超越的権威の強化につとめた。そして,フリードリヒ1世のもとでこの帝国がはじめて〈神聖帝国sacrum imperium〉なる正式呼称をもってよばれたが(1157),これは,皇帝に対する封主的地位を主張するローマ教皇に対し,皇帝権の神への直属性を表明したイデオロギー的反動の所産であった。しかし,こうしたイデオロギー的神聖化の努力にもかかわらず,12~13世紀ヨーロッパの政治現実のなかでは,この皇帝権にザリエル朝期のような権威を再びよみがえらせることは不可能であった。英仏をはじめとする形成期の国民国家は,〈ドイツ王〉の優越的権威を端的に否認し,また〈帝国〉内では,急速に成長した領邦的諸権力(領邦国家)が皇帝の国家的支配を空洞化していった。その結果,シュタウフェン朝の没落とともに皇帝権の最後の担い手が存在しなくなった後には,帝国には,もはや時代おくれの壮大な理念(13世紀後半以降用いられた〈神聖ローマ帝国〉という呼称)と,ドイツ諸領邦に対するゆるやかな支配だけしか残されていなかった。
皇帝フリードリヒ3世(在位1452-93)の時代になると,この帝国の名称には,しばしば〈ドイツ国民のdeutscher Nation〉という付加語が結びつけられるようになり,1486年には帝国ラント平和令がはじめて公式の制定法の中で〈ドイツ国民のローマ帝国das römische Reich deutscher Nation〉なる呼称を用いた。17世紀の政論家たちは,この付加語の意味を,帝国の支配権がドイツ国民に帰属することの表現だと解し,また,19世紀ドイツの歴史家たちによってもこの解釈が主張されたが,その後の研究はそれが明瞭に限定的な意味で使われており,帝国のドイツ国民的部分を表現するための付加語であることを明らかにした。そこに含まれる領域は,ほぼ,西はネーデルラント,ロートリンゲン,フランシュ・コンテまで,東はオーストリア,ブランデンブルク,ポンメルンまで,南はスイス諸州を除いてチロルからトリエントまでであった。それ以上の権利要求,たとえばミラノその他のイタリア諸領域に対する封主権のごときは,実際上なんの意味ももたなかった。
15世紀末から16世紀にかけて,いろいろな帝国改革の試みがなされた。それは,中世後期以来王権の犠牲において自立化を強めた領邦的諸権力を,何らかの形で自己の国制の中へ組みいれようとする試みであったが,それは皇帝権の無力と領邦の一致した抵抗の前にことごとく失敗した。その結果,帝国国制の独特な二元主義的構造が定着したが,それは帝国全体を表すのに使われてきた〈皇帝と帝国〉なる定式の意味変化によく示されている。すなわち,もともと両概念は同じことで,皇帝の支配が帝国を意味していたのに対し,いまや両者は完全に分離して,〈帝国〉とは皇帝ぬきの等族(シュテンデStände)の全体を表し,家門勢力を背景とするにすぎない皇帝は,国制上,帝国住民との直接的関係をすべて失うことになった。住民と皇帝との間には領邦が割り込み,その全体がいまや〈帝国〉として皇帝と相対することになったのである。したがって,このような帝国に,同時代の西ヨーロッパ諸国家のような方向への発展可能性はなく,その国制的諸機関,たとえば帝国議会Reichstag(身分制議会),帝国宮内法院Reichshofgericht,帝国統治院Reichsregimentなどはほとんど実質的意味をもたなかった。ただ,帝国最高法院Reichskammergerichtだけは事実上,等族の手に握られた最高裁判所として帝国の解体にいたるまで活動をつづけ,帝国全体の伝統的身分制的諸権利を維持するのに役だった(身分制国家)。1648年のウェストファリア条約は帝国等族の主権的領邦支配権を承認し,対外的同盟権をも認めることにより,それを自主独立たらしめた。みずから国家化する道を最終的にとざされた〈ドイツ国民のローマ帝国〉は,近代国家形成への課題をすべて諸領邦に託しつつ,1806年8月6日,ナポレオン戦争の動乱のなかでフランツ2世が皇帝を辞し,その歴史を閉じた。
→ローマ理念
執筆者:山田 欣吾
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「神聖ローマ帝国」の意味・わかりやすい解説
神聖ローマ帝国【しんせいローマていこく】
→関連項目イタリア|オーストリア|シュパイヤー国会|スイス|ドイツ|西ローマ帝国|プレスブルクの和約|リヒテンシュタイン|レーゲンスブルク|ロストク|ローマ[古代]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「神聖ローマ帝国」の解説
神聖ローマ帝国(しんせいローマていこく)
Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation[ドイツ],Holy Roman Empire of the German Nation[英]
中世より19世紀初頭に至るまでドイツを中心にその周辺に広がった帝国の呼称(第一帝国)。世界帝国としてのローマ帝国の理念を受け継ぎ,元来はドイツ王国,イタリア王国,ブルグント王国を包摂する「超地域的」国家だが,皇帝の支配権がドイツに限定されるに従って,15世紀末より「ドイツ国民の神聖ローマ帝国」と呼ばれるようになった。起源は,原理上カール大帝の戴冠で,実質上は962年ローマでのザクセン朝のオットー1世の戴冠と考えられる。皇帝は血統権も考慮した選挙制で選出され,本来ローマ教皇による戴冠を必要とした。国制は台頭する諸侯権力を抑制するため,皇帝に直属する教会,修道院をその支柱とし(「帝国教会政策」),11世紀ザリエル朝期にこの体制は最高の発展をとげた。しかし叙任権闘争は教会との結合を弱め,聖俗諸領邦の自立化を促した。ホーエンシュタウフェン朝のフリードリヒ1世は再び帝権を強化したが,フリードリヒ2世のイタリア経略への専念は領邦分立を助長し,その死後まもなくの大空位時代をへて,この趨勢(すうせい)は決定的となった。14世紀以後皇帝選挙制の原理が確立し,金印勅書がこれを確認した。1438年以後帝位は事実上ハプスブルク家に定着したが,宗教改革と三十年戦争,ウェストファリア条約をへて皇帝の統制力は弱まり,帝国は300余の諸領邦の集合体として形骸化した。ナポレオン支配時代の1806年,帝国諸侯のライン同盟が帝国よりの脱退を宣言したために,最後の皇帝フランツ2世は帝冠を辞し,ここに帝国は完全に崩壊した。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「神聖ローマ帝国」の意味・わかりやすい解説
神聖ローマ帝国
しんせいローマていこく
Heiliges Römisches Reich; Holy Roman Empire
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「神聖ローマ帝国」の解説
神聖ローマ帝国
しんせいローマていこく
Heiliges Römisches Reich (Deutscher Nation)
ドイツ人の手による古代ローマ帝国の復活を意味し,ローマ−カトリック教会との結合によって「神聖」という意味をもつ。ただし,この呼称が出現したのは13世紀である。962年,ドイツ王ザクセン朝のオットー1世が北イタリアに遠征して,ローマ教皇ヨハネス12世から帝冠を受けて以来,フランケン朝・シュタウフェン朝が帝位についたが,歴代皇帝がイタリア政策に熱中し,ドイツの分裂を招いた。大空位時代(13世紀)以後は,選帝侯が皇帝を選んだが,1438年以後は代々ハプスブルク家が帝位についた。のち,ウェストファリア条約で領邦主権が確立すると帝国は有名無実化し,さらにナポレオン1世の勢力下にあったライン同盟が脱退を宣言すると,1806年フランツ2世が帝位を辞退し,ここに最終的に解体した。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の神聖ローマ帝国の言及
【ドイツ】より
… たしかに,歴史的にみても,ドイツをある定まった民族や国家とみることはできない。たとえば,中世のドイツ王国(神聖ローマ帝国)は,現在のオーストリア,スイス,さらにはイタリアまでをも含んでいた。したがってこの項目では,ドイツとは何かという定義を初めから下すのではなく,ドイツと呼ばれてきた地域や人々の社会のあり方を歴史的にたどることによって,ドイツとは何を意味し,それがヨーロッパないし世界史のなかでもってきた意味を考えたい。…
※「神聖ローマ帝国」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...