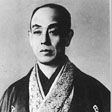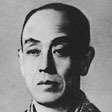精選版 日本国語大辞典 「市川左団次」の意味・読み・例文・類語
いちかわ‐さだんじ【市川左団次】
- 歌舞伎俳優。屋号高島屋。
- [ 一 ] 初世。俳名莚升(えんしょう)、松蔦(しょうちょう)。四世市川小団次の養子。大阪の人。明治時代の代表的名優で、団十郎、菊五郎とともに「団菊左」と呼ばれた。明治座を創設。当たり役は「慶安太平記」の丸橋忠彌など。天保一三~明治三七年(一八四二‐一九〇四)
- [ 二 ] 二世。初世の長男。本名栄次郎。俳名杏花。小山内薫と提携して自由劇場を結成し、岡本綺堂と結んで新歌舞伎を樹立するなど、演劇革新運動に貢献した。明治一三~昭和一五年(一八八〇‐一九四〇)
- [ 三 ] 三世。六世市川門之助の子。昭和二七年(一九五二)三世を襲名。芸域が広く、戦後の歌舞伎界において、後進の指導に尽くした。明治三一~昭和四四年(一八九八‐一九六九)
新撰 芸能人物事典 明治~平成 「市川左団次」の解説
市川 左団次(2代目)
イチカワ サダンジ
- 職業
- 歌舞伎俳優
- 本名
- 高橋 栄次郎
- 別名
- 前名=市川 ぼたん,市川 小米,市川 莚升,俳名=杏花
- 屋号
- 高島屋
- 生年月日
- 明治13年 10月19日
- 出生地
- 東京市 京橋区築地(東京都 中央区)
- 経歴
- 初代市川左団次の長男。明治17年4歳の時に市川ぼたんの名で「助六由縁江戸桜」に出演し、初舞台。その後、たびたび9代目市川団十郎の子役を務め、28年小米を経て、33年莚升と改名し、名題に昇進。37年父が亡くなったため高島屋一門を率いるようになり、39年2代目左団次を襲名。その直後に渡欧し、各地の劇場や西欧の芝居の実際を学んで帰国した。41年明治座の興行制度改革を断行し、茶屋制度の廃止や女優の起用など思い切った劇界の近代化を図るが、周囲の反対により断念。42年には小山内薫と組んで会員制の自由劇場を創設、有楽座で試演したイプセン作・森鴎外訳の「ジョン・ガブリエル・ボルグマン」が好評を博した。以後、ゴーリキー「どん底」、チェーホフ「犬」、ブリュー「信仰」などといった西洋の劇や、鴎外、秋田雨雀ら日本人作家の新作を次々と上演し、新劇運動のはしりとなった。歌舞伎では、42年歌舞伎十八番の中でも長らく演じられていなかった「毛抜」を岡鬼太郎の脚色で約100年ぶりに上演したのをはじめ、「鳴神」や鶴屋南北作品を次々と復活・上演し、古典劇の再興と定着に尽力。また、松居松葉、岡本綺堂、真山青果ら現代作家による新脚本(新歌舞伎)も積極的に上演した。大正元年明治座を手放し、松竹と専属契約を結ぶ。昭和3年には一座を率いてソ連を訪問し、海外ではじめて歌舞伎を上演。演出家のスタニスラフスキー、映画監督のエイゼンシュタインら、ソ連の演劇人とも交流を持った。雑俳もたしなみ、鶯亭金升の門下で小山内とは同門であった。当たり役は「名高慶安太平記」の丸橋忠弥(父の当たり役でもあった)、「仮名手本忠臣蔵」の大星由良之助、「修禅寺物語」の夜叉王、「鳥辺山心中」の半九郎など。著書に「左団次芸談」「左団次自伝」などがある。
- 没年月日
- 昭和15年 2月23日 (1940年)
- 家族
- 父=市川 左団次(初代)
- 伝記
- 荷風と左団次―交情蜜のごとし団菊以後歌舞伎百年百話人と芸談―先駆けた俳優たち 近藤 富枝 著伊原 青々園 著上村 以和於 著馬場 順 著(発行元 河出書房新社青蛙房河出書房新社演劇出版社 ’09’09’07’99発行)
市川 左団次(3代目)
イチカワ サダンジ
- 職業
- 歌舞伎俳優
- 肩書
- 日本俳優協会会長 日本芸術院会員〔昭和38年〕,重要無形文化財保持者(歌舞伎立役)〔昭和39年〕
- 本名
- 荒川 清(アラカワ キヨシ)
- 別名
- 前名=市川 男寅(4代目),市川 男女蔵(4代目)
- 屋号
- 高島屋
- 生年月日
- 明治31年 8月26日
- 出生地
- 東京市 日本橋区浜町(東京都 中央区)
- 経歴
- 明治35年、9代目市川団十郎の門下で、4代目市川男寅の名で初舞台。大正6年市村座で4代目市川男女蔵を襲名。15年6代目尾上菊五郎とともに松竹に移る。市村座時代から6代目菊五郎の女房役をつとめ菊五郎亡き後、昭和24年から菊五郎劇団の理事として劇団の経営に当たった。27年3代目市川左団次を襲名。立女役、二枚目、老け役など脇役に徹することが多かったが、33年の東横ホールでの「左団次舞台生活五十年記念」公演で「二人道成寺」を踊り、「弁天娘女男白浪」の主役・弁天小僧を演じた。他の当り芸に「妹背山婦女庭訓」の求女、定高、「本朝廿四孝」の勝頼、「髪結新三」の忠七、「紅葉狩」の平維盛、「仮名手本忠臣蔵」の早野勘平など。35年には「シラノ・ド・ベルジュラック」でラグノオを演じた。38年日本俳優協会会長、同年日本芸術院会員。39年人間国宝、40年文化功労者。北条誠著「市川左団次芸談きき書」がある。
- 受賞
- 日本芸術院賞(昭30年度)〔昭和31年〕,文化功労者〔昭和40年〕 毎日演劇賞〔昭和30年〕
- 没年月日
- 昭和44年 10月3日 (1969年)
- 家族
- 養父=市川 門之助(6代目),長男=市川 左団次(4代目)
- 伝記
- 木米と永翁 宮崎 市定 著(発行元 中央公論社 ’88発行)
市川 左団次(初代)
イチカワ サダンジ
- 職業
- 歌舞伎俳優
- 本名
- 高橋 栄三
- 別名
- 前名=市川 小米,市川 升若,俳名=莚升,松蔦
- 屋号
- 高島屋
- 生年月日
- 天保13年 10月28日
- 出生地
- 大坂・島の内(大阪府)
- 経歴
- 13歳の時4代目市川小団次に入門し、元治元年(1864年)養子となり左団次と名乗った。養父の死後、河竹黙阿弥の後援を受け、明治3年黙阿弥作の「慶安太平記」で丸橋忠弥を演じ人気を得た。以後、黙阿弥の新作史劇で活躍し、9代目団十郎、5代目菊五郎とともに、明治三大名優の一人に数えられた。26年には日本橋浜町の千歳座を買収して明治座を新築し座頭となり、32年新歌舞伎の嚆天といわれる松居松葉作「悪源太」を上演した。
- 没年月日
- 明治37年 8月7日 (1904年)
- 家族
- 長男=市川 左団次(2代目)
- 伝記
- 芝居随想 作者部屋から団菊以後 食満 南北 著伊原 青々園 著(発行元 ウェッジ青蛙房 ’09’09発行)
出典 日外アソシエーツ「新撰 芸能人物事典 明治~平成」(2010年刊)新撰 芸能人物事典 明治~平成について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「市川左団次」の意味・わかりやすい解説
市川左団次
いちかわさだんじ
歌舞伎(かぶき)俳優。屋号高島屋。現在4世まである。
初世
(1842―1904)本名高橋栄三。大坂生まれ。江戸へ出て幕末の名優4世市川小団次(こだんじ)に入門。のち師の養子となり1864年(元治1)左団次を名のる。養父の没後その提携者であった河竹黙阿弥(もくあみ)、12世守田勘弥(かんや)(1846―1897)、養母の庇護(ひご)を得て発奮し、黙阿弥作『慶安太平記(けいあんたいへいき)』の丸橋忠弥で認められた。のちに明治の名優9世市川団十郎、尾上(おのえ)菊五郎とともに「団・菊・左」と称せられた。1893年(明治26)明治座を建てて座主となった。
2世
(1880―1940)本名高橋栄次郎。初世の長男。1906年(明治39)襲名。同年末から翌年8月にかけて歌舞伎俳優として初めて欧米に渡り、帰国後小山内薫(おさないかおる)とともに自由劇場を結成。文芸協会の『人形の家』よりも2年早い1909年11月、イプセンの『ジョン・ガブリエル・ボルクマン』を第1回に、西欧の戯曲を試演し近代劇運動の旗手となる。歌舞伎でも岡本綺堂(きどう)や真山青果(まやませいか)と組んで多くの作品を上演し、新歌舞伎というジャンルを定着させた。その一方で、歌舞伎十八番の『毛抜(けぬき)』『鳴神(なるかみ)』や、4世鶴屋南北(なんぼく)の生世話物(きぜわもの)など演出の伝承がとだえていた古劇の復活にも尽力した。1928年(昭和3)ソ連を訪問し、歌舞伎の第1回海外公演を行った。
3世
(1898―1969)本名荒川清。6世市川門之助(もんのすけ)(1862―1914)の子。6代目菊五郎の一座にあって、4世市川男女蔵(おめぞう)の名で二枚目の立役(たちやく)および女方(おんながた)を勤め、菊五郎没後は菊五郎劇団の長老として二枚目役にも老役(ふけやく)にも洗練された演技をみせた。1952年(昭和27)3世を襲名、1962年芸術院会員、1964年に重要無形文化財保持者となる。
4世
(1940―2023)本名荒川欣也(きんや)。3世の子。菊五郎劇団の立役。敵役(かたきやく)としても活躍した。2016年度(平成28)日本芸術院賞を受賞。
[古井戸秀夫]
百科事典マイペディア 「市川左団次」の意味・わかりやすい解説
市川左団次【いちかわさだんじ】
→関連項目岡鬼太郎|河原崎長十郎|近代劇|修禅寺物語|高島屋|鳥辺山
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
改訂新版 世界大百科事典 「市川左団次」の意味・わかりやすい解説
市川左団次 (いちかわさだんじ)
歌舞伎俳優。4世まである。屋号は高島屋。(1)初世(1842-1904・天保13-明治37) 本名高橋栄三。俳名は莚升,松蔦。大坂生れ。床山中村清吉の次男,幼名辰蔵。子供芝居で初舞台,13歳で4世市川小団次の門に入り小米(こよね),升若を経て,1864年(元治1)小団次の養子となって左団次を名のり江戸の各座に出勤。66年(慶応2)養父没後一時廃業していたが,作者河竹黙阿弥の後援で復帰,70年(明治3)黙阿弥の書きおろし《慶安太平記》の丸橋忠弥の好演で人気役者の仲間入りをし,93年明治座を新築,座元・座頭として活躍,9世市川団十郎,5世尾上菊五郎ら名優と〈団菊左〉と並び称された。容姿とせりふに恵まれ,堅実な芸風で明治史劇に本領を発揮した。(2)2世(1880-1940・明治13-昭和15) 本名高橋栄次郎。東京生れ。初世の嫡男,俳名杏花。4歳のとき市川ぼたんの芸名で初舞台,小米,莚升を経て1906年左団次を襲名。新旧を問わず線の太い役柄をよくし,独特な芸風,輪郭の大きさ,ハイカラさから〈大統領〉の愛称があった。団菊没後劇界刷新の先頭に立ち,小山内薫と提携しての自由劇場や,文芸家をブレーンとしての古劇《鳴神》などや4世鶴屋南北の作品の復活,岡本綺堂,真山青果らとの新歌舞伎の開拓,劇場内外での旧弊の改革等々近代演劇史に残した足跡は高く評価されている。(3)3世(1898-1969・明治31-昭和44) 本名荒川清。東京生れ。6世市川門之助の子。4歳のとき4世男寅(おとら)の芸名で初舞台,4世市川男女蔵(おめぞう)を経て52年左団次を襲名した。女方ややわらかみのある立役と芸域が広く,6世尾上菊五郎の没後は菊五郎劇団のまとめ役として重きをなした。62年芸術院会員に推された。(4)4世(1940(昭和15)- )本名荒川欣也。東京生れ。3世の長男。7歳のとき5世男寅の芸名で初舞台,5世男女蔵を経て79年左団次を襲名,おおらかな芸格,線の太い芸質で敵役も演ずる。
執筆者:野口 達二
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
20世紀日本人名事典 「市川左団次」の解説
市川 左団次(2代目)
イチカワ サダンジ
明治〜昭和期の歌舞伎俳優
- 生年
- 明治13(1880)年10月19日
- 没年
- 昭和15(1940)年2月23日
- 出生地
- 東京市京橋区築地(現・東京都中央区)
- 本名
- 高橋 栄次郎
- 別名
- 前名=市川 ぼたん,市川 小米,市川 莚升,俳名=杏花
- 屋号
- 高島屋
- 経歴
- 明治17年市川ぼたんの名で初舞台。その後、小米、莚升と改名、39年2代目左団次を襲名。その直後、渡欧、各地の劇場、西欧の芝居の実際を学んで帰国。41年明治座で興行、茶屋制度の廃止や女優を起用、思い切った興行の近代化を図った。42年には小山内薫と組んで自由劇場を創設、イプセンの「ボルグマン」やゴーリキーの「どん底」など新劇を初演。さらに松居松葉、岡本綺堂らの新脚本(新歌舞伎)を上演、真山青果の諸作品も演じた。一方、「毛抜」「鳴神」など歌舞伎十八番の復活、南北作品を発掘、古典劇の定着にも力を尽くした。また一座を率いてソ連を訪問、海外公演の先鞭をつけた。当たり役は「丸橋忠弥」「修禅寺物語」の夜叉王、「鳥辺山心中」の半九郎など。
市川 左団次(3代目)
イチカワ サダンジ
明治〜昭和期の歌舞伎俳優 日本俳優協会会長。
- 生年
- 明治31(1898)年8月26日
- 没年
- 昭和44(1969)年10月3日
- 出生地
- 東京市日本橋区浜町(現・東京都中央区)
- 本名
- 荒川 清
- 別名
- 前名=市川 男寅,市川 男女蔵(4代目)
- 屋号
- 高島屋
- 主な受賞名〔年〕
- 日本芸術院賞〔昭和30年〕,毎日演劇賞〔昭和30年〕,文化功労者〔昭和40年〕
- 経歴
- 9代目団十郎の門下で、明治35年市川男寅の名で初舞台。大正6年市村座で4代目市川男女蔵を襲名。市村座時代から6代目菊五郎の女房役をつとめ菊五郎亡き後、昭和24年から菊五郎劇団の理事として劇団の経営に当たった。27年3代目市川左団次を襲名。立女役、2枚目、老け役など脇役に徹した。当り芸に「妹背山」の求女、定高、「廿四孝」の勝頼、「髪結新三」の忠七など。38年日本俳優協会会長。同年人間国宝、40年文化功労者。
出典 日外アソシエーツ「20世紀日本人名事典」(2004年刊)20世紀日本人名事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「市川左団次」の意味・わかりやすい解説
市川左団次(4世)
いちかわさだんじ[よんせい]
[没]2023.4.15. 東京
歌舞伎俳優。屋号高島屋。本名荒川欣也。荒事から老け役までこなし,持ち前の愛嬌と色気,奔放な発言で知られ,数多くのテレビ番組に出演した。
3世市川左団次の長男として東京市に生まれる。1947年『寺子屋』で 5代目市川男寅(いちかわおとら)を名のって初舞台。1962年,5代目市川男女蔵(いちかわおめぞう)を襲名。1979年,4代目市川左団次を襲名。特に『仮名手本忠臣蔵』の高師直(こうのもろなお),『助六由縁江戸桜』の「髭の意休」,『俊寛』の瀬尾などの敵役の演技に定評があった。このほか,『熊谷陣屋』の弥陀六(みだろく)の老け役,『身替座禅』の奥方玉の井の女方も評判を呼んだ。1997年松尾芸能賞優秀賞,1998年眞山青果賞特別賞。2011年旭日双光章。2017年日本芸術院賞。著書に『俺が噂の左團次だ』(1994),『夢を見ない、悩まない』(2014)など。
市川左団次(1世)
いちかわさだんじ[いっせい]
[没]1904.8.7. 大阪
歌舞伎俳優。屋号高島屋。4世市川小団次の養子。本名高橋栄三。明治3 (1870) 年河竹黙阿弥の指導で『慶安太平記』の丸橋忠弥で一躍人気役者となり,新作物の立役を得意とした明治期の代表的名優。9世市川団十郎,5世尾上菊五郎とともに「団菊左」と称された。
市川左団次(2世)
いちかわさだんじ[にせい]
[没]1940.2.23.
歌舞伎俳優。屋号高島屋。1世市川左団次の長男。本名高橋栄次郎。音声にすぐれ,線の太い独特の芸格がある。常に演劇革新の意志をもち続け,1909年には小山内薫とともに自由劇場を創設して新劇運動を推進。以後岡本綺堂,真山青果などの作品を上演し,新歌舞伎に新生面を開くと同時に,歌舞伎十八番『毛抜』『鳴神』など古劇も復活した。
市川左団次(3世)
いちかわさだんじ[さんせい]
[没]1969.10.3.
歌舞伎俳優。屋号高島屋。6世市川門之助の子。本名荒川清。6世尾上菊五郎の門弟となり,市川男女蔵より襲名。芸域が広く,ことに二枚目役に精彩を放った。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「市川左団次」の解説
市川左団次
いちかわさだんじ
歌舞伎俳優。幕末期から4世を数える。屋号は高島屋。初世(1842~1904)は大坂生れ。本名高橋栄三。俳名莚升・松蔦(しょうちょう)。4世市川小団次の養子。男性的な芸風で明治期の東京を代表する名優。9世市川団十郎・5世尾上菊五郎とともに「団菊左」と並び称され,明治中期の歌舞伎全盛期を築いた。晩年は明治座の座主にもなった。2世(1880~1940)は初世の子。東京都出身。本名高橋栄次郎。俳名杏花(きょうか)・松莚。小山内薫と提携して自由劇場を創立。またすぐれた新歌舞伎の初演,歌舞伎十八番や鶴屋南北作品の復活上演など,革新的な仕事で近代の演劇界に独自の足跡を残した。3世(1898~1969)は東京都出身。本名荒川清。6世市川門之助の養子で6世尾上菊五郎門下。本領は古風な二枚目や女方で,第2次大戦後は長老として重きをなした。人間国宝。芸術院会員・文化功労者。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「市川左団次」の解説
市川左団次(2代) いちかわ-さだんじ
明治13年10月19日生まれ。初代市川左団次の長男。明治17年初舞台。39年明治座で2代を襲名。42年小山内薫と自由劇場を創立する。とだえていた歌舞伎十八番の「毛抜」などを復活上演。岡本綺堂(きどう)らの新作を初演した。昭和15年2月23日死去。61歳。東京出身。本名は高橋栄次郎。初名は市川ぼたん。前名は市川小米,莚升。俳名は杏花。屋号は高島屋。
【格言など】今できないことは十年たってもできまい。思いついたことはすぐやろうじゃないか(むずかしい演技を実行にうつすときに)
市川左団次(3代) いちかわ-さだんじ
明治31年8月26日生まれ。6代市川門之助の養子。明治35年初舞台。6代尾上菊五郎に師事,昭和24年菊五郎劇団の理事。27年3代を襲名。立役(たちやく),女方,老役(ふけやく)を演じた。31年芸術院賞。38年芸術院会員。39年人間国宝。40年文化功労者。昭和44年10月3日死去。71歳。東京出身。本名は荒川清。初名は市川男寅(おとら)(4代)。前名は市川男女蔵(おめぞう)(4代)。屋号は高島屋。
市川左団次(初代) いちかわ-さだんじ
天保(てんぽう)13年10月28日生まれ。大坂の床山(とこやま)の子。4代市川小団次の養子。河竹黙阿弥(もくあみ)の後援をうけ明治3年「慶安太平記」の丸橋忠弥(ちゅうや)から人気を得,9代市川団十郎,5代尾上菊五郎とともに「団菊左」とならび称された。26年明治座を発足させ座元。明治37年8月7日死去。63歳。本名は高橋栄三。前名は市川小米,升若。俳名は莚升,松蔦。屋号は高島屋。
市川左団次(4代) いちかわ-さだんじ
昭和15年11月12日生まれ。3代市川左団次の長男。昭和22年初舞台。54年4代市川左団次を襲名。老役(ふけやく),敵役として活躍。東京出身。暁星高卒。本名は荒川欣也。初名は市川男寅(2代)。前名は市川男女蔵(おめぞう)(5代)。屋号は高島屋。
市川左団次 いちかわ-さだんじ
享保(きょうほう)11年(1726)以後に名をあらわし,江戸で若女方として出演。寛保(かんぽう)2年2代市川海老蔵(えびぞう)の門にはいり,市川左団次を名のった。初名は袖岡菊太郎。前名は袖崎菊太郎。俳名は春耕。
旺文社日本史事典 三訂版 「市川左団次」の解説
市川左団次
いちかわさだんじ
〔初代(1842〜1904)〕 立役を得意とし,市川団十郎(9代目)・尾上菊五郎(5代目)と団菊左時代を現出。明治座を創設,経営した。〔2代目(1880〜1940)〕 初代の実子。小山内薫らと自由劇場を始め,新劇運動を推進。のち新劇を離れ歌舞伎に専念した。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
367日誕生日大事典 「市川左団次」の解説
市川 左団次(2代目) (いちかわ さだんじ)
明治時代-昭和時代の歌舞伎役者
1940年没
市川 左団次(3代目) (いちかわ さだんじ)
明治時代-昭和時代の歌舞伎役者
1969年没
出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の市川左団次の言及
【岡本綺堂】より
…処女作《紫宸殿》(1896)の後,1902年1月岡鬼太郎と合作の《金鯱噂高浪(こがねのしやちうわさのたかなみ)》が歌舞伎座に上演された。その後文士劇若葉会に自作を上演したが,08年9月2世市川左団次に《維新前後》を書き,11年5月の《修禅寺物語》の好評によって,両者の提携になる〈新歌舞伎〉の路線が定着した。13年以後作家活動に専念,左団次主演の多くの名脚本とともに,14編の新聞小説があり,16年からは《半七捕物帳》を起稿した。…
【歌舞伎】より
…こうして生まれたのが〈新歌舞伎〉と呼ぶ一連の作品である。大正期になり,外遊から帰った2世市川左団次は,新しい演劇創造の熱意に燃え,小山内薫,岡本綺堂,岡鬼太郎,山崎紫紅,永井荷風,池田大伍という文学者たちをブレーンとし,毎月1作の新作を上演しつづけた。とくに岡本綺堂との提携で生み出した《鳥辺山心中》《修禅寺物語》などは名作で,新歌舞伎の中でも古典的作品となった。…
【自由劇場】より
…現実の人生と舞台上の虚構の人生とを混同する行過ぎもあったが,世紀末の大劇場で当たっていたスター中心のだまし絵的なウェルメード・プレーの虚偽と誇張を暴露して,現代劇への道を開いた。1894年にはアントアーヌの手をはなれ,96年には経営難で解散したが,演出家リュニェ・ポーや名優F.ジェミエもここから巣立ち,ベルリンの〈自由舞台〉や市川左団次と小山内薫の〈自由劇場〉など世界的な影響を残した。【安堂 信也】
[ブラームの自由舞台Freie Bühne]
1889年にパリの自由劇場に倣ってベルリンに設立された協会で,検閲で上演できぬ戯曲を会員だけに見せることを主たるねらいとしていた。…
【修禅寺物語】より
…1911年5月,東京明治座初演。配役は伊豆の夜叉王を2世市川左団次,姉娘かつらを市川寿美蔵(のちの3世寿海),妹娘かへでを市川莚若(のちの3世市川松蔦),源頼家を15世市村羽左衛門ほか。作者が伊豆の修善寺温泉に源頼家の面なるものがあると聞き,作劇の動機とした。…
【新歌舞伎】より
…これらの作品の特徴は,明治の団菊左や黙阿弥らが辛酸をなめつつ歌舞伎を変革改良しようとした方向ではなく,近代的思想もしくは人間像を歌舞伎の伝統的劇術を借りて表現しようとしたもので,その傾向は現在まで続いている。 俳優では2世市川左団次が注目される。父の死後明治座を背負って苦闘した左団次は,新作に活路を求め,08年山崎紫紅の《歌舞伎物語》や,それに次いでの《真田幸村》などの成功で自信を強め,さらに綺堂との仕事,とりわけ11年の《修禅寺物語》で新作の位置を決定づけた。…
【新劇】より
…逍遥はシェークスピア劇の移植と歌舞伎の改革を目ざし,また西欧近代を呼吸して帰国した弟子の島村抱月は,イプセンの《人形の家》など,逍遥以上に西欧近代劇の移入に熱心であった。 一方,歌舞伎俳優として初の渡欧体験を持ち,しかし帰国後の革新興行には失敗した2代目市川左団次と,1906年に〈新派〉を失望裡に離れた小山内薫は,共同して09年に自由劇場を創設,試演活動を開始した。これは〈日本の劇壇に脚本・演技の両面で真の(西洋近代劇の)翻訳時代を興す〉意図で行われ,以後14年にかけて意欲的な活動を展開した。…
【鳥辺山心中】より
…1915年9月東京本郷座初演。配役は菊地半九郎を2世市川左団次,遊女お染を3世市川松蔦,坂田源三郎を市川寿美蔵(のちの3世寿海)。地唄《鳥辺山》からの着想による。…
【雷神不動北山桜】より
…うち三段目の《毛抜》,四段目の《鳴神》,五段目大切《不動》はのち分離独立して,7世市川団十郎により歌舞伎十八番に制定された。以後上演は絶えていたが,2世市川左団次が岡鬼太郎の脚色を得て,《毛抜》を1909年9月,《鳴神》を10年5月にそれぞれ復活上演した。また《不動》は脚本が伝わらなかったが,12年3月,山崎紫紅が補綴して,やはり2世左団次が復活した。…
【番町皿屋敷】より
…1916年2月東京本郷座初演。配役は青山播磨を2世市川左団次,腰元お菊を2世市川松蔦,柴田十太夫を市川左升,放駒四郎兵衛を6世市川寿美蔵(のちの3世寿海),権次を市川荒次郎。古来からの皿屋敷伝説をふまえながらも,お菊の亡霊を出さず,近代人にも共感される恋の悲劇として作られ,盛行する。…
※「市川左団次」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

 (初世)[1842~1904]大阪の生まれ。9世
(初世)[1842~1904]大阪の生まれ。9世 (2世)[1880~1940]初世の子。東京の生まれ。
(2世)[1880~1940]初世の子。東京の生まれ。