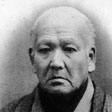改訂新版 世界大百科事典 「河竹黙阿弥」の意味・わかりやすい解説
河竹黙阿弥 (かわたけもくあみ)
生没年:1816-93(文化13-明治26)
歌舞伎作者。本名吉村芳三郎,俳号其水(きすい),現役名2世河竹新七,別号古河黙阿弥。江戸日本橋に湯屋の株の売買業越前屋勘兵衛の長男として生まれた。14歳のとき柳橋で遊興中を見つかって勘当され,貸本屋の手代となって乱読多読,芝居界にも縁を生じた。通人粋客と交わって狂歌,雑俳,三題噺,絵合せ,茶番などに才を発揮,芳々(よしよし)と号して点者もつとめた。後年の作の趣向の妙や世相人心の機微の把握と描写,音感に富むせりふの味などは,この遊蕩時代のたまものである。1835年(天保6)20歳のとき5世鶴屋南北に入門し,勝諺蔵(げんぞう)を名のった。以後病気や家庭の事情で何度か劇界を離れたが,41年江戸河原崎座へ出勤,柴(後に斯波)晋輔と改め,家督も弟にゆずって翌々年立作者となり,2世河竹新七を襲名。その後は50余年一筋に作者道を貫く。このころ天保の改革のため江戸三座が浅草猿若町に移転したので,住居を芝から浅草寺子院の正智院境内に移した。40歳ごろからは名実ともに劇界の第一人者となり,明治に入ってもその地位は変わらなかった。1881年官憲・学者による急進的な演劇改良運動の重圧を避くべく,〈腸(はらわた)の無き愚かさに直(すぐ)な道 知らで幾年横に這ふ蟹〉という狂歌をのこし,散切物《島鵆月白浪(しまちどりつきのしらなみ)》を一世一代として引退を声明,黙阿弥と改めた。が,その真意は晩年の手記によると〈又出勤する事もあらば元のもくあみとならんとの心〉であった。事実引退後もすぐれた後継作者なく〈スケ〉として書きつづけ,1887年本所南二葉町に移住,93年1月脳溢血で没。
黙阿弥の作者生涯はおよそ4期に分けられる。第1期は20歳でこの道に入ってから1853年(嘉永6)38歳まで約20年間の習作時代。この間に師の口述筆記,台本筆写,書抜作り,道具帳や番付・絵看板の制作助手,柝(き)の打ち方や稽古のつけ方,舞台監督など座付作者としての基礎修業をおさめ,補綴・脚色などの習作で作劇術を学んだ。勤勉で記憶力がよく,25歳のとき台本なしで《勧進帳》の後見をつとめて7世市川団十郎にほめられたのが出世の糸口となった。独習だが画才もあり看板下絵が得意だった。この期には団十郎のための《難有御江戸景清(ありがたやめぐみのかげきよ)》(1850),柳下亭種員の合巻を脚色した《児雷也豪傑譚話》(1852)などがある。
第2期は54年(安政1)から66年(慶応2)までの10余年間で,名人といわれた幕末の代表的役者4世市川小団次と組み,生世話狂言とくに白浪物に本領を発揮,地位を確立した時代。その契機は《都鳥廓白浪》(1854)で,以下《蔦紅葉宇都谷峠》(1856),《網模様灯籠菊桐》(1857),《小袖曾我薊色縫(あざみのいろぬい)》(1859),《三人吉三廓初買》(1860),《八幡祭小望月賑(よみやのにぎわい)》(1860),《勧善懲悪覗機関(かんぜんちようあくのぞきがらくり)》(1862),《曾我綉俠御所染(そがもようたてしのごしよぞめ)》(1864),《船打込橋間白浪(ふねへうちこむはしまのしらなみ)》(1866)などを小団次のために書いた。江戸市井の下層社会を,写実味と三味線にのる音感の両面をもつ小団次の芸風に合わせて,活写した作品群である。ほかに13世市村羽左衛門(後の5世尾上菊五郎)に《青砥稿花紅彩画(あおとぞうしはなのにしきえ)》(1862),3世沢村田之助に《処女翫(むすめごのみ)浮名横櫛》(1864),《怪談月笠森》(1865)など。
第3期は66年の小団次死後から81年66歳で引退するまでの約15年間で,旧来の世話物のほか新時代に順応すべく,活歴劇(活歴物),散切物,松羽目物の舞踊劇などに新境地を開く時代である。72年(明治5)守田座の新富町進出を機に,歌舞伎は〈団菊左〉すなわち9世市川団十郎,5世尾上菊五郎,初世市川左団次の3名優を代表とする新富座時代に入り,黙阿弥はその座付作者に迎えられた。この期の作群の第1は明治新政府の教化方針と団十郎の写実趣味に合わせた史実尊重・忠孝鼓吹の活歴劇で《桃山譚》(地震加藤,1869),《新舞台巌楠(いわおのくすのき)》(楠正成,1874),《牡丹(なとりぐさ)平家譚》(重盛諫言,1876)など。しかし一般に用語がむずかしくて趣向に乏しく,成功しなかった。第2は菊五郎のための散切物すなわち文明開化の新世相・新風俗を描く新世話物で,《東京日(にちにち)新聞》(1873)以下《富士額男女繁山(ふじびたいつくばのしげやま)》(1877),《霜夜鐘十字辻筮(しもよのかねじゆうじのつじうら)》(1879),《島鵆月白浪》(1881)など。作劇術や人間把握などには新鮮味がなく,やがて新派の現代劇にとって代わられるが,新風物以外にも女子の立身や没落士族の貧窮など,社会の変化が浮彫りされている点に意義がある。が,真価はやはり《梅雨小袖昔八丈》(1873),《天衣紛(くもにまごう)上野初花》(1881)などの江戸風世話物にあった。ほかに西南戦争に取材した《西南雲晴朝東風(おきげのくもはろうあさごち)》(1878),現在も上演されるリットン原作の翻案劇《人間万事金世中》(1879)などあり,79年には《ハムレット》の翻案も企てるなど多彩をきわめた。
第4期は引退以後の10余年間で,今日復演される唯一の活歴劇《北条九代名家功》(1884)や,《水天宮利生深川(すいてんぐうめぐみのふかがわ)》(1885),《月梅薫朧夜(つきとうめかおるおぼろよ)》(花井お梅,1888)ほかの散切物,《茨木》(1883),《船弁慶》(1885),《紅葉狩》(1887)などの能取り所作事,《チャリネの曲馬》(1886),《スペンサーの風船乗》(1891)などの洋風所作事を書いた。しかしこの期の作でもいまなお復演に耐えるのはやはり《新皿屋舗月雨暈(しんさらやしきつきのあまがさ)》(1883),《四千両小判梅葉》(1885),《盲長屋梅加賀鳶》(1886)のような純江戸風世話物であった。絶筆は没したその月に上演された所作事《奴凧廓春風(やつこだこさとのはるかぜ)》(1893)。
作品総数約360。題材は稗史(はいし)小説,講談落語,能狂言から新聞雑報,西洋物におよぶ。近代への激動の中で,市井のリアルな描写と七五調や清元の音感により江戸歌舞伎を集大成,坪内逍遥に〈江戸歌舞伎の大問屋〉と評された。
執筆者:河竹 登志夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「河竹黙阿弥」の意味・わかりやすい解説
河竹黙阿弥
かわたけもくあみ
(1816―1893)
歌舞伎(かぶき)作者。本名吉村芳三郎。俳号其水(きすい)。江戸・日本橋の商家4世越前屋(えちぜんや)勘兵衛の長男に生まれる。14歳のとき柳橋で遊興中を発見され勘当される。下町の通人仲間と交わり茶番集を書いたり、貸本屋の手代となって諸書を乱読したのち、1835年(天保6)に5世鶴屋南北(つるやなんぼく)に入門して狂言作者となり勝諺蔵(かつげんぞう)を名のる。病気と家庭の事情で再三引退したのち、1841年に4世中村重助(じゅうすけ)の招きで再勤して二枚目格となって柴晋輔(斯波晋輔)(しばしんすけ)と名のり、1843年に2世河竹新七を襲名して立(たて)作者格となる。旧作の補綴(ほてい)や小説の脚色、一幕物の世話物などで活躍したのち、1854年(安政1)の『都鳥廓白浪(みやこどりながれのしらなみ)』で4世市川小団次に認められ、以後1866年(慶応2)に小団次が没するまで、彼のために講釈種(だね)の白浪物(しらなみもの)など生世話(きぜわ)狂言の傑作を次々と書いて不動の地位を築く。その間、安政(あんせい)の大地震以後は市村座の立作者として重年し、3世桜田治助(じすけ)、3世瀬川如皐(じょこう)と三座体制を維持する一方で、中村・森田両座の重要な新作をも引き受け八面六臂(はちめんろっぴ)の活躍をした。
明治になってからも筆力は衰えず、小団次の遺児初世市川左団次をもり立てるとともに、新政府の方針をくむ若き興行師12世守田勘弥(もりたかんや)を助け、9世市川団十郎のためには史実に基づく「活歴劇(かつれきげき)」を、5世尾上菊五郎(おのえきくごろう)のためには明治の新風俗を写した「散切物(ざんぎりもの)」を書いて新境地を開拓した。1881年(明治14)に『島鵆月白浪(しまちどりつきのしらなみ)』を一世一代に引退して古河黙阿弥(ふるかわもくあみ)を名のるが、作者無人の劇界が黙阿弥の引退を許すはずがなく、死の直前まで新作を提供し続け、明治26年1月22日に78歳の生涯を終えた。門弟に3世新七、竹柴其水(たけしばきすい)、勝能進(かつのうしん)などがいる。
黙阿弥の作品は時代物、世話物、所作事あわせて約360にも及び、いずれにも力量を発揮したが、その真骨頂は講釈などに取材した生世話物にあった。代表的なものとして、小団次のために書いた『蔦紅葉宇都谷峠(つたもみじうつのやとうげ)』『鼠小紋東君新形(ねずみこもんはるのしんがた)』『網模様灯籠菊桐(あみもようとうろのきくきり)』『黒手組曲輪達引(くろてぐみくるわのたてひき)』『小袖曽我薊色縫(こそでそがあざみのいろぬい)』『三人吉三廓初買(さんにんきちさくるわのはつがい)』『八幡祭小望月賑(はちまんまつりよみやのにぎわい)』『勧善懲悪覗機関(かんぜんちょうあくのぞきからくり)』『曽我綉侠御所染(そがもようたてしのごしょぞめ)』『船打込橋間白浪(ふねへうちこむはしまのしらなみ)』のほか、5世菊五郎には『青砥稿花紅彩画(あおとぞうしはなのにしきえ)』『梅雨小袖昔八丈(つゆこそでむかしはちじょう)』『新皿屋敷月雨暈(しんさらやしきつきのあまがさ)』『水天宮利生深川(すいてんぐうめぐみのふかがわ)』『四千両小判梅葉(しせんりょうこばんのうめのは)』『盲長屋梅加賀鳶(めくらながやうめがかがとび)』、9世団十郎・5世菊五郎には『天衣紛上野初花(くもにまごううえののはつはな)』、3世沢村田之助には『処女翫浮名横櫛(むすめごのみうきなのよこぐし)』(切られお富)などを書いた。なお、舞踊劇には『土蜘(つちぐも)』『茨木(いばらき)』『船弁慶』『紅葉狩(もみじがり)』などの代表作がある。
坪内逍遙(しょうよう)はこのような黙阿弥の業績全般を評して「真に江戸演劇の大問屋なり」と称賛している。その作風は、化政(かせい)期(1804~30)の4世鶴屋南北が完成した生世話をさらに洗練、古典化し、時代物の世界から完全に独立した講談、実録調の筋立てのなかに、勧善懲悪、因果応報の理が強調されている。ことに小団次と提携した白浪物の諸作には幕末の逼塞(ひっそく)した世相が反映されている。そして逃げ道のない袋小路に入ってしまった小悪党の心情をうたった、七五調の「厄払(やくはらい)」とよばれる感傷的で音楽的な台詞(せりふ)は近代人にも共感され、今日でも歌舞伎のもっとも上演頻度の高いレパートリーとなっている。
[古井戸秀夫]
『『黙阿弥全集』全20巻(1924~26・春陽堂)』▽『河竹登志夫解説『名作歌舞伎全集10~12 河竹黙阿弥集 1~3』(1968~70・東京創元社)』▽『河竹繁俊著『河竹黙阿弥』(1961・吉川弘文館)』
百科事典マイペディア 「河竹黙阿弥」の意味・わかりやすい解説
河竹黙阿弥【かわたけもくあみ】
→関連項目十六夜清心|市川左団次|茨木|河竹繁俊|河竹登志夫|生世話|清元延寿太夫|児雷也|筑摩川|土蜘/土蜘蛛(演劇)|釣狐|鼠小僧次郎吉|三千歳
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「河竹黙阿弥」の意味・わかりやすい解説
河竹黙阿弥
かわたけもくあみ
[没]1893.1.22. 東京
歌舞伎狂言作者。本姓吉村,幼名芳三郎。5世鶴屋南北に入門。2世河竹新七を襲名し,幕末にはおもに4世市川小団次に世話物を,明治には9世市川団十郎,5世尾上菊五郎,1世市川左団次らに世話物,時代物のほか活歴物,散切物,松羽目物などの新傾向の作品を書いた。 1881年黙阿弥と改名後も執筆を続け,その作品は『三人吉三廓初買 (さんにんきちさくるわのはつがい) 』 (1860) ,『青砥稿花紅彩画 (あおとぞうしはなのにしきえ) 』 (通称『白浪五人男』) (62) ,『勧善懲悪覗機関 (かんぜんちょうあくのぞきからくり) 』 (通称『村井長庵』) (62) ,『梅雨小袖昔八丈』 (通称『髪結新三』) (73) ,『天衣紛上野初花 (くもにまごううえののはつはな) 』 (81) ,『島鵆 (しまちどり) 月白浪』 (81) ,『高時』 (84) など約 360編に及ぶ。本領は幕末市井を描写した生世話,特に白浪物で,江戸演劇の集大成者とされる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「河竹黙阿弥」の解説
河竹黙阿弥
かわたけもくあみ
1816.2.3~93.1.22
幕末~明治期を代表する歌舞伎作者。江戸日本橋生れ。本名吉村芳三郎。俳名其水(きすい)。別号古河黙阿弥。1835年(天保6)5世鶴屋南北に入門。勝諺蔵(げんぞう)・柴晋輔(しんすけ)をへて43年2世河竹新七を襲名し,立作者となる。安政~慶応期には4世市川小団次と提携して生世話物(きぜわもの),ことに白浪物の名作をうみ,一方では歌舞伎の音楽演出を進展させた。明治期には唯一の大作者として活歴物・散切物(ざんぎりもの)・松羽目(まつばめ)物なども手がけ,81年(明治14)引退を表明,「もとのもくあみ」になる意味で黙阿弥と改名したが,実際は最晩年まで執筆を続けた。「最後の狂言作者」「江戸歌舞伎の大問屋」とよばれ,作品数360余編。「黙阿弥全集」全28巻。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「河竹黙阿弥」の解説
河竹黙阿弥 かわたけ-もくあみ
文化13年2月3日生まれ。5代鶴屋南北に入門。天保(てんぽう)14年2代河竹新七を襲名後,4代市川小団次のために生世話(きぜわ)物をかく。維新後は9代市川団十郎のために活歴(かつれき)物,5代尾上菊五郎のために散切(ざんぎり)物などの作品を提供。明治14年引退して黙阿弥を名のる。時代物,世話物,所作事と幅ひろかったが,本領は生世話物にあった。明治26年1月22日死去。78歳。江戸出身。本名は吉村新七。幼名は芳三郎。俳名は其水。別名は古河黙阿弥。作品に「蔦紅葉宇都谷峠(つたもみじうつのやとうげ)」「青砥稿花紅彩画(あおとぞうしはなのにしきえ)」など。
【格言など】地獄の沙汰も,金次第だ
旺文社日本史事典 三訂版 「河竹黙阿弥」の解説
河竹黙阿弥
かわたけもくあみ
幕末・明治前期の歌舞伎脚本作者
本名吉村新七。江戸の生まれ。世話物・白浪物に特にすぐれたが,そのほか時代物・散切 (ざんぎり) 物・活歴物など,作品は360編にも及ぶ。代表作に『三人吉三廓初買 (さんにんきちさくるわのはつがい) 』『天衣紛 (くもにまごう) 上野初花』など。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の河竹黙阿弥の言及
【青砥稿花紅彩画】より
…通称《弁天小僧》《白浪五人男》。河竹黙阿弥作。1862年(文久2)3月江戸市村座で,弁天小僧を13世市村羽左衛門(後の5世尾上菊五郎),日本駄右衛門を3世関三十郎,南郷力丸を4世中村芝翫(しかん)らが初演。…
【網模様灯籠菊桐】より
…通称《小猿七之助》。河竹黙阿弥作。1857年(安政4)7月江戸市村座初演。…
【扇音々大岡政談】より
…世話物。河竹黙阿弥作。1875年(明治8)1月28日から東京新富座で,大岡越前守を5世坂東彦三郎,天一坊を5世尾上菊五郎,山内伊賀亮を初世市川左団次によって初演。…
【加賀見山再岩藤】より
…7幕。河竹黙阿弥作。別名題《梅柳桜幸染(うめやなぎさくらのかがぞめ)》。…
【活歴物】より
…明治10年代以降9世市川団十郎を中心に行われた歌舞伎の革新運動のなかで,旧来の荒唐無稽な時代物でなく,史実によって脚色し時代考証による扮装・演出に重きをおいた時代物の作品群をいう。団十郎のこの運動には1872年(明治5)に新劇場を新富町に建設して旧制度の打破を試みた興行師の12世守田勘弥,作者界の第一人者河竹黙阿弥らが協力した。〈活歴〉の語は,78年10月黙阿弥作の《二張弓千種重藤》が上演された際,〈時代物は活きたる歴史〉でなくてはならぬと依田学海らが述べたのに対し,《かなよみ新聞》で仮名垣魯文が〈活歴史〉と評したのにはじまるという。…
【勧善懲悪覗機関】より
…8幕11場。河竹黙阿弥作。1862年(文久2)閏8月江戸森田座初演。…
【生世話】より
…南北以前,上方の初世並木五瓶が,1794年(寛政6)に江戸へ下り,合理的作風をみせたこと,また,1792年11月江戸河原崎座の《大船盛鰕顔見世(おおふなもりえびのかおみせ)》で,4世岩井半四郎が切見世女郎の三日月おせんを演じたことなどは,南北の生世話を生み出す準備段階として注目される。南北以後,3世瀬川如皐(じよこう)から河竹黙阿弥へと至るうちに,市井の生活描写や演技・演出の写実化という面が継承され発展していくことになる。しかし,写実的傾向の拡大といっても,歌舞伎では下座音楽を使い,せりふのリズムや舞台の動きにおいても美化された様式は生きている。…
【吉様参由縁音信】より
…通称《湯灌場吉三(ゆかんばきちさ)》《小堀政談》《天人香》。河竹黙阿弥作。1869年(明治2)7月東京中村座初演。…
【極付幡随長兵衛】より
…通称《湯殿の長兵衛》。河竹黙阿弥作。1881年(明治14)10月東京春木座初演。…
【樟紀流花見幕張】より
…6幕。河竹黙阿弥作。別名題《花菖蒲慶安実記(はなしようぶけいあんじつき)》《慶安太平記》。…
【天衣紛上野初花】より
…7幕。河竹黙阿弥作。1881年3月東京新富座初演。…
【黒手組曲輪達引】より
…4幕。河竹黙阿弥作。通称《黒手組の助六》。…
【小袖曾我薊色縫】より
…通称《十六夜清心(いざよいせいしん)》。河竹黙阿弥作。1859年(安政6)2月江戸の市村座初演。…
【三人吉三廓初買】より
…別名題《三人吉三巴白浪(ともえのしらなみ)》,通称《三人吉三》。河竹黙阿弥作。1860年(万延1)1月江戸市村座で,和尚吉三を4世市川小団次,お嬢吉三を3世岩井粂三郎(のちの8世岩井半四郎),お坊吉三を初世河原崎権十郎(のちの9世市川団十郎),土左衛門伝吉を3世関三十郎らが初演。…
【実録物】より
…その方法は,時代物だけではなく,世話物でも採用されて《実録の助六》《実録伊勢音頭》などが生まれた。1874年3月東京村山座初演の《夜討曾我狩場曙》をはじめとして河竹黙阿弥は次々に実録物を書いた。76年6月東京新富座初演の《実録先代萩》すなわち《早苗鳥伊達聞書(ほととぎすだてのききがき)》は《伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)》の実録化であり,83年10月新富座初演の《千種花音頭新唄(ちぐさのはなおんどのしんうた)》は《伊勢音頭恋寝刃》の実録化であった。…
【島鵆月白浪】より
…5幕。河竹黙阿弥作。通称《島鵆》《千太と島蔵》。…
【児雷也豪傑譚話】より
…4幕。河竹黙阿弥作。通称《児雷也》。…
【新皿屋舗月雨暈】より
…3幕。河竹黙阿弥作。通称《魚屋宗五郎》《新皿屋敷》。…
【水天宮利生深川】より
…3幕。河竹黙阿弥作。通称《筆屋幸兵衛》。…
【曾我綉俠御所染】より
…6幕。河竹黙阿弥作。通称《御所五郎蔵(ごしよのごろぞう)》。…
【太鼓音智勇三略】より
…通称《酒井の太鼓》。河竹黙阿弥作。1873年3月東京村山座初演。…
【蔦紅葉宇都谷峠】より
…通称《文弥殺し》。河竹黙阿弥作。1856年(安政3)9月江戸市村座で,按摩文弥・提婆(だいば)の仁三を4世市川小団次,伊丹屋十兵衛を初世坂東亀蔵により初演。…
【梅雨小袖昔八丈】より
…4幕11場。河竹黙阿弥作。通称《髪結新三》。…
【鼠小紋東君新形】より
…通称《鼠小僧》。河竹黙阿弥作。1857年(安政4)1月江戸市村座初演。…
【八幡祭小望月賑】より
…通称《縮屋新助》《美代吉殺し》。河竹黙阿弥作。1860年(万延1)7月江戸市村座初演。…
【船打込橋間白浪】より
…通称《鋳掛松(いかけまつ)》。河竹黙阿弥作。1866年(慶応2)2月江戸守田座初演。…
【北条九代名家功】より
…通称《高時》。河竹黙阿弥作。1884年11月東京猿若座初演。…
【都鳥廓白浪】より
…通称《忍ぶの惣太》。河竹黙阿弥作。1854年(嘉永7)3月江戸河原崎座初演。…
【処女翫浮名横櫛】より
…通称《切られお富》。河竹黙阿弥作。1864年(元治1)4月江戸守田座で《若葉梅(わかばのうめ)浮名横櫛》として初演,同芝居が初日の翌日類焼したため,同年7月再開場に際して《処女翫浮名横櫛》と改題続演した。…
【盲長屋梅加賀鳶】より
…通称《加賀鳶》。河竹黙阿弥作。1886年3月東京千歳座初演。…
【夜討曾我狩場曙】より
…通称《夜討曾我》《敷皮の五郎》。河竹黙阿弥作。1881年6月東京新富座初演。…
※「河竹黙阿弥」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...