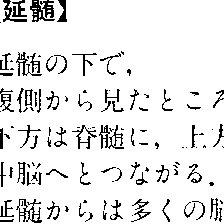精選版 日本国語大辞典 「延髄」の意味・読み・例文・類語
えん‐ずい【延髄】
改訂新版 世界大百科事典 「延髄」の意味・わかりやすい解説
延髄 (えんずい)
medulla oblongata[ラテン]
延髄は脳幹の最も下方の部分にあたり,生命の維持に不可欠な呼吸や循環の調節を行う場所であり,下は脊髄に,上は橋(きよう)に続く。延髄という名称は本来,脊髄の延長を意味するところからきている。また延髄は球根のように膨らんでいるところから球という名称が用いられることがある。延髄の下方は脊髄最上端(第1頸神経の上縁)を境とする。上方の橋との境は下面では明りょうであるが,上面には境界はなく,第四脳室という脳脊髄液を入れる空間の底面となっている。下等哺乳類からヒトに至るまで,延髄の構造は基本的には同じである。古くガレノスやビユサンスRaymond Vieussens(1641-1716)により観察されていたが,延髄の傷害で呼吸の止まることを見いだしたのはロリーA.C.Lorry(1760)とルガロアJ.J.C.Legallois(1812)である。その後,フルーランスM.J.P.Flourensは延髄の呼吸中枢の場所を明確にし(1837),生命結節と名づけた。
外部構造
延髄の表面には,脊髄から続いてきた3本の縦に走る溝により上面から下面にかけて左右対称的に三つの高まりができている。それらは延髄後索,延髄側索,延髄前索と呼ばれる。これらには,延髄内部にある構造により生じたいくつかの高まりがみられる。延髄後索は内側と外側の二つの高まりからできている。内側は脊髄の薄束(はくそく)の続きとそれが終わる薄束核により生じた薄束結節で,外側は楔状束(けつじようそく)とそれの終わる楔状束核でできた楔状結節とである。延髄側索にも二つの高まりがある。一つは灰白結節で中にある三叉神経脊髄路核に相当し,他の一つはオリーブの形をしているところからオリーブと呼ばれるものである。その内部にはオリーブ核がある。延髄前索は延髄錐体と呼び,錐体路という神経路でできている。
内部構造
延髄内部には,いろいろの働きをする神経核(神経細胞またはニューロンの集団)と延髄を通過し,あるいは神経核に結合する神経路とがある。神経核には,迷走・舌咽・副・舌下神経の四つの脳神経の核がある。迷走神経は大きく分けて,頸部,胸部,腹部の内臓に分布する。頸部では,喉頭の筋を動かして行う発声運動と咽頭の筋を収縮させて行う嚥下(えんげ)運動(食物を飲み込む働き)との二つの働きをする。胸部では心臓の運動を抑制し,腹部では食道,胃,小腸,大腸の運動を促進する。迷走神経はまた,これらの内臓からの感覚を延髄に伝えたり,大動脈(弓)に加わる血圧の状態を延髄に伝え,それに応じて心臓の運動を調節する。舌咽神経は,舌と咽頭に分布し,知覚,運動,分泌をつかさどる。副神経は頸と肩にある二つの筋(胸鎖乳突筋と僧帽筋)を動かす。舌下神経は舌の筋に行き舌を動かす。これらの脳神経核以外に,三叉神経脊髄路核や後索核のように身体の感覚を上位の中枢に伝える中継核がある。そのほか,網様体の核,オリーブ核などがあり,脊髄や上位の中枢からの入力を小脳に伝え運動の調節に大切な働きをしている。神経路は大きく分けて,運動系,感覚系,自律系の経路に分けられる。(1)運動系の経路として最も重要なものに錐体路がある。これは,大脳皮質の運動の領域から始まり,延髄の錐体を通って延髄の運動性脳神経核に接続し,迷走神経による発声と嚥下,舌下神経による舌の運動,副神経による頸と肩の運動などの随意運動を行う。錐体路はさらに下行し,大部分は左右のものが互いに交差したのち,脊髄の側索を下り,脊髄の運動性前角細胞に接続する。このようにして,頸部,上肢,体幹,下肢の随意運動を行う。その他の運動の経路としては,赤核脊髄路,網体脊髄路,前庭脊髄路がある。これらはいずれも,随意運動の際の微妙な筋の緊張状態の調節や反射運動の調節を無意識のうちに行うのに役立っている。(2)感覚系の経路には,後索-内側毛帯系,三叉神経中枢路,脊髄視床路の三つがある。後索-内側毛帯系は,脊髄の後索(薄束と楔状束とからなる)が延髄の後索核(薄束核と楔状束核とからなる)で接続し,そこから交差して視床の腹側核に終わる経路である。この経路は,触覚,圧覚,運動覚,位置覚,振動覚,二点弁別閾(いき)などを伝える。三叉神経中枢路は,三叉神経脊髄路核から起こり交差して,脊髄視床路とともに反対側を上行して視床に至る経路である。これは,顔面の皮膚に加えられた温度,痛み,触覚,圧を伝える。脊髄視床路は,脊髄から起こり交差して,延髄の網様体中を上行して視床に至る経路である。顔面以外の身体の各部からの温覚,痛覚,触覚,圧覚を伝える。(3)自律系の経路として重要なものに視床下部下行路がある。これは,自律系の上位中枢である視床下部から下行して脊髄に至り,交感神経や仙髄副交感神経の核に作用する経路である。途中延髄では迷走神経や舌咽神経の核に枝を出し,内臓運動や耳下腺からの唾液の分泌などを調節しているものと考えられる。
延髄の障害
以上のように,延髄には重要な働きをする神経核,神経路,脳神経が集中して存在するので,血管障害(出血,閉塞),腫瘍,変性疾患などにより種々の症状が出る。また障害が広く,両側にわたるようなときは生命が危険となる。(1)脳神経の障害 迷走神経の障害では,嚥下困難(食物をうまく飲み込むことができない),嗄声(させい)(しわがれ声),失声(声がかすれて出ない)などが起こる。舌咽神経の障害では,唾液の分泌の減少,味覚障害,咽頭の感覚障害が起こる。舌下神経の障害では舌の運動が障害される。両側が障害されると,言葉を話したり,食物の咀嚼(そしやく)ができにくくなる。副神経の障害では,肩を上げたり,頸を回したりすることができにくくなる。(2)運動の経路の障害 錐体路の障害がその代表である。障害された側と反対側の上肢や下肢の随意運動ができなくなる(片麻痺(へんまひ)と呼ぶ)。延髄の高さで錐体路が障害されると,しばしば脳神経の麻痺がいっしょに起こる。その場合,片麻痺と脳神経の麻痺とは互いに反対側に出る。このような麻痺を交代麻痺と呼ぶ。(3)感覚の経路の障害 後索-内側毛帯系の障害では,障害と反対側の身体の触覚,圧覚,振動覚,運動覚,位置覚がなくなる(手や足,またその指がどの方向に動いているか,あるいはどのような位置をとっているかを知ることができない)。三叉神経脊髄路やその中枢路が障害されると,顔面の温覚,痛覚がなくなる。脊髄視床路の障害では,障害と反対側の顔面以外の身体の温覚,痛覚がなくなる。以上のような症状は延髄での障害の大きさによって,いろいろ組み合わさって出てくる。
執筆者:松下 松雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「延髄」の意味・わかりやすい解説
延髄
えんずい
髄脳(ずいのう)ともいう。中枢神経系は脊髄(せきずい)と脳とからなっているが、その脳の最下部が延髄で、脳の延びた部分という意味である。延髄の上方は、哺乳(ほにゅう)動物の場合では後脳(橋(きょう)と小脳)へと続き、鳥類以下では橋がなく、小脳だけに続く。延髄の下方は脊髄につながるが、その境は明確ではない。一般には、脊髄の第1頸(けい)神経が出る部分までを延髄下端とするのが適当であろう。延髄長軸の長さは約2.5センチメートルで脊髄より膨らみ、やや横に押し延ばされたような円柱形をして、後頭骨の斜めになった後下部「斜台」にのっている。こうした全体の形から脳球という呼び方もある。延髄の下半部は脊髄と外形もよく似ており、横断面の中心部には脊髄からの中心管がそのまま続き、上半部は延髄全体が左右方向に扁平(へんぺい)となり、細い中心管が急に第四脳室へと開いている。つまりこの部分では、延髄の背側部は外側に割れるような感じで移動し、天井が開放されたようになる。天井の覆いとなるのは小脳の後半部である。延髄の表面には脊髄と同じ溝と索状隆起がみられるが、腹側面では正中線に前正中裂という溝があり、脊髄の前正中裂に続いている。とくにこの溝の左右に、内側から錐体(すいたい)およびオリーブとよばれる膨らみがあるが、ともに外観の形からつけられた名称である。錐体の内部には横紋筋の随意運動を支配する神経線維束(皮質脊髄路または錐体路)が縦走している。これはもっとも重要な運動支配路であり、系統発生的にみても、哺乳動物に特有な新しい仕組みである。オリーブ内部にはオリーブ核という神経細胞群が存在しており、この神経核は体の平衡、直立前行などに関係して、不随意運動の調節に重要な役割を果たしている。延髄下半部の背側部には、頭部を除く全身の皮膚感覚(とくに触覚)や筋肉覚、腱(けん)覚などの感覚線維がある。
延髄内部の構造は、下半部では脊髄とほとんど同じであるが、上半部に移ると変化が著しくなり、神経核の配置も複雑になる。脳神経に関係しては、内耳神経の中の前庭神経が関係する前庭神経核の一部、三叉(さんさ)神経が関係する三叉神経脊髄路核、舌下神経を出す舌下神経核、舌咽神経・迷走神経に関与する迷走神経背側核、疑核、孤束核、下唾液(だえき)核などが存在している。舌咽神経、迷走神経に関係するこれらの神経細胞群は、気管、食道、咽頭(いんとう)、喉頭(こうとう)あるいは心臓の運動、味覚や唾液分泌など、内臓諸器官の自律反射の働きに関係し、生命の維持にも重要な役割をもっている。そのほか、嘔吐(おうと)反射、咳嗽(がいそう)(咳(せき))反射、くしゃみ反射、そしゃく反射などに関係ある神経細胞群、嚥下(えんげ)反射、唾液分泌に関する中枢、呼吸中枢、血管運動中枢などが、延髄と関係していることが、種々の実験結果から考えられている。
[嶋井和世]
百科事典マイペディア 「延髄」の意味・わかりやすい解説
延髄【えんずい】
→関連項目球麻痺|くしゃみ|鎮咳薬|脳|脳幹
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「延髄」の意味・わかりやすい解説
延髄
えんずい
medulla oblongata
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
栄養・生化学辞典 「延髄」の解説
延髄
世界大百科事典(旧版)内の延髄の言及
【脳】より
…側脳室を囲む部分を終脳(正確には,左右の大脳半球と終脳の不対部),第三脳室を囲む部分を間脳,中脳水道を囲む部分を中脳,第四脳室を囲む部分を菱脳とする。さらに菱脳の前半部(後脳)からは小脳と橋(きよう)が分化し,菱脳の後半部は延髄(髄脳)として脊髄に連続する。 成人の脊髄は身長の28~29%の長さがあるが(日本人では40~47cm),脳と脊髄の重量比は約55対1であり,中枢神経系において脳の占める割合がいかに大きいかがわかる。…
※「延髄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...