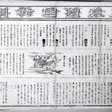精選版 日本国語大辞典 「東京日日新聞」の意味・読み・例文・類語
とうきょう‐にちにちしんぶんトウキャウ‥【東京日日新聞】
- 東京最初の日刊新聞。明治五年(一八七二)創刊。岸田吟香の雑報、福地源一郎(桜痴)の論説で声価が高かった。同四四年大阪毎日新聞に吸収された。
百科事典マイペディア 「東京日日新聞」の意味・わかりやすい解説
東京日日新聞【とうきょうにちにちしんぶん】
→関連項目阿部真之助|時事新報|末松謙澄|丹下左膳|千葉亀雄|郵便報知新聞
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
改訂新版 世界大百科事典 「東京日日新聞」の意味・わかりやすい解説
東京日日新聞 (とうきょうにちにちしんぶん)
東京における最初の日刊新聞で,現在の《毎日新聞》東京本社の前身にあたる。1872年(明治5)2月に条野伝平らによって設立された日報社より創刊された。74年末に入社した福地桜痴(おうち)が社説欄を創設,政府御用新聞としての立場を鮮明に打ち出し,自由民権派の政論新聞に対抗して健筆をふるった。明治前期には岸田吟香,末松謙澄らも活躍した。80年前後からの政府批判の高まりとともに御用新聞批判が強まり,しだいに勢力を弱め,88年福地は社長の座を関直彦(1857-1934)に譲り,退社した。関はそれまでの御用新聞主義から中立主義に切りかえ,紙面を刷新して,大幅に部数を伸ばしたが,内外の策動で91年に退任し,伊東巳代治が社長となった。同年朝比奈知泉が入社,論説を担当するようになってからは長州閥の機関紙と化し,伊藤博文,井上馨,三井資本などの支援もあったが,1904年三菱が買収し,加藤高明が社長となって以後,次々と社長が変わるが,経営不振は打開できず,ついに11年に《大阪毎日新聞》によって買収され,題字は存続させたまま《毎日電報》と合併した。以後同紙は,《大阪毎日新聞》とともに不偏不党の全国紙の方向へと発展した。42年新聞事業令による整理統合においてもそのまま存続したが,43年に題字が《毎日新聞》に統一されて,伝統ある題字は消滅した。
→毎日新聞
執筆者:山本 武利
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「東京日日新聞」の意味・わかりやすい解説
東京日日新聞
とうきょうにちにちしんぶん
1872年(明治5)2月21日に創刊された東京初の日刊紙。条野採菊(じょうのさいぎく)(戯作(げさく)者)、落合芳幾(よしいく)(浮世絵師)、西田伝助(本屋の番頭)が発刊した新聞だが、翌73年甫喜山(ほきやま)景雄、岸田吟香(ぎんこう)が入社、岸田は74年5月台湾出兵に初めて従軍、紙上をにぎわわせた。ついで福地桜痴(おうち)が入社、12月2日から社説を掲載するとともに「太政官(だじょうかん)記事印行御用」を掲げて権威を高め、代表的大(おお)新聞としての性格と地位を固めた。以後、福地の論説は政府ならびに各界に影響を及ぼすとともに、政府の官報の役割を果たした。
しかし、自由民権運動が盛んになるとともに、福地の主権在君論や漸進主義は、しだいに「御用記者」との批判を強め、82年、福地が政府支持の帝政党を組織したころから『東京日日新聞』の勢力は失墜し始めた。85年には勢力挽回(ばんかい)のため、わが国で初めて朝夕刊発行を1年間試みたりしたが形勢は変わらず、88年7月福地は退社、以後、関直彦(せきなおひこ)、伊東巳代治(みよじ)、朝比奈知泉(ちせん)が主宰し、伊藤博文(ひろぶみ)、井上馨(かおる)、山県有朋(やまがたありとも)らの長州閥系紙となる。日露開戦のときは、伊藤の政策を支持、最後まで対露外交交渉を説いた。1904年(明治37)三菱(みつびし)の手に渡るが欠損が続き、11年3月『大阪毎日新聞』の経営下に入り、全国紙へと発展(題号はそのまま)、43年(昭和18)1月『毎日新聞』に題号を統一した。
[春原昭彦]
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「東京日日新聞」の意味・わかりやすい解説
東京日日新聞
とうきょうにちにちしんぶん
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「東京日日新聞」の解説
東京日日新聞
とうきょうにちにちしんぶん
1872年(明治5)2月11日に条野伝平・西田伝助・落合芳幾(よしいく)によって創刊された新聞。74年福地源一郎(桜痴(おうち))が主筆として入社,のちに社長に就任して国会開設漸進を主張し,政府の御用新聞と目された。この頃が最盛期で発行部数は82年頃約7000部であったが,自由民権運動が衰退すると社勢も衰え,87年には福地の手を離れた。91年伊東巳代治の所有に移り,朝比奈知泉(ちせん)が主筆となった。1904年に加藤高明に売却されたが経営は苦しく,08年加藤は実質的に手を引き,11年大阪毎日新聞社に売却され,題字はそのままだが同社の経営となった。43年(昭和18)1月1日,東京・大阪の題字を「毎日新聞」に統一して紙名は消えた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
デジタル大辞泉プラス 「東京日日新聞」の解説
東京日日新聞
旺文社日本史事典 三訂版 「東京日日新聞」の解説
東京日日新聞
とうきょうにちにちしんぶん
1872年条野伝平らが創刊。'74年福地源一郎が主筆となり,日本の新聞で最初に社説を掲載した。終始政府の御用的立場をとる。1911年大阪毎日新聞社に併合され,'43年には新聞統合政策により,紙名も『毎日新聞』に統一された。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の東京日日新聞の言及
【大新聞・小新聞】より
…さらに大新聞の記者が旧幕臣を中心とした士族出身であるのに対し,小新聞の記者は戯作者を中心とした庶民出身であった。読者層でも両者の識別は鮮明で,〈日々新聞ノ如キ紙幅大ニシテ,且ツ勿論其議論高尚ナルヲ以テ,中等以上ノ人民之レヲ読ミ,又夫ノ仮名付小新聞ノ如キハ,平均セバ下等社会ノ読ム所ナルベケレ〉(《東京日日新聞》1878年2月13日)といわれるように,大新聞は中・上流社会に,小新聞は下流社会に,主として読まれていた。 大新聞は政論新聞ともいわれた。…
【御用新聞】より
…御用新聞であることが,官尊民卑の風潮のなかで民衆からの信用と尊敬をえるのに大きく役だった。1874年に《東京日日新聞》が太政官記事御用達を掲げだすと,部数は急増し,社長兼主筆の福地桜痴の名声も高まった。しかし自由民権運動の高まりとともに,政府批判と御用新聞批判が連動し,御用新聞の代表格である《東京日日新聞》への批判が高まってきた。…
【新聞】より
…
【日本の新聞の特徴】
(1)日本の新聞は,一般紙の多くが朝・夕刊を一組として発行する〈ワンセット制〉を採用している。これは1885年《東京日日新聞》,岡山の《山陽新報》が始めたのが最初だが,時期尚早で永続せず,年内に朝刊のみに復した。しかし1906年《報知新聞》が日露戦争後,ニュース量が増えたことに伴いワンセット制とし,さらに15年《大阪朝日新聞》《大阪毎日新聞》が,第1次大戦の速報と大正天皇即位式典に伴うニュース量の増大に対処するために朝・夕刊発行に移行して以後,ワンセット制が各紙に採用されることとなった。…
【報道写真】より
… 画像による伝達と言語による伝達は互いに機能特性が異なり,そのため古くから言語を補う意味で,新聞などの印刷媒体には挿絵(イラストレーション)が利用されていた。1872年(明治5)に発刊した日刊紙《東京日日新聞》でも錦絵が使われていたという。この時点ではすでに写真は実用化していたのだから,その新聞への利用も当然考えられることであったが,写真が大量印刷で使用されるようになるのはずっと遅れて,20世紀初頭になってからである。…
【毎日新聞】より
…日本の代表的新聞の一つ。《大阪毎日新聞(《大毎》)》と《東京日日新聞(《東日》)》がその前身。《大毎》は1876年2月,西川甫(はじめ)(1831‐1904)を社主に《大阪日報》として創刊,82年筆禍対策の〈身代り紙〉として興された《日本立憲政党新聞》に事実上受け継がれた(号数もこれから継承している)。…
※「東京日日新聞」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...