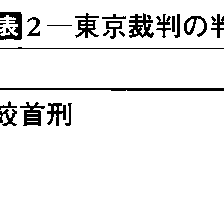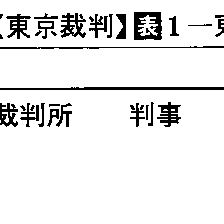共同通信ニュース用語解説 「東京裁判」の解説
東京裁判
第2次大戦に勝利した連合国が日本の指導者の戦争責任を裁いた極東国際軍事裁判の通称。1946年5月~48年11月に行われた。28人がA級戦犯として起訴され、途中死亡者ら3人を除く25人全員が有罪を言い渡され、
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
精選版 日本国語大辞典 「東京裁判」の意味・読み・例文・類語
とうきょう‐さいばんトウキャウ‥【東京裁判】
- 極東国際軍事裁判のこと。
改訂新版 世界大百科事典 「東京裁判」の意味・わかりやすい解説
東京裁判 (とうきょうさいばん)
正式の名称は極東国際軍事裁判International Military Tribunal for the Far East。日本の戦前・戦中の指導者28名の被告を〈主要戦争犯罪人〉(A級戦犯)として,彼らの戦争犯罪を審理した国際軍事裁判である。
前史
第2次大戦中の連合国の戦争目的には,日独伊など枢軸国による侵略と残虐行為に対する自衛と制裁の方針が一貫して掲げられており,戦争終結後に枢軸国の戦争指導者と戦争犯罪を処罰することは,連合国の共通目標だった。しかし連合国内には,枢軸国の戦争犯罪をどのような根拠と名目(戦争犯罪概念)で,どのような方法(戦争犯罪処罰方式)で誰(戦争犯罪人)を裁くかについてさまざまな意見があった。結局,連合国の戦犯政策はドイツ敗北後の大戦末期に決着した。米英ソ3国首脳によるポツダム会談に並行して,1945年6月からロンドンで戦争犯罪人に関する米英仏ソ4国代表によるロンドン会議が開催され,4国代表は8月8日〈欧州枢軸諸国の主要戦争犯罪人の訴追及び処罰に関する件〉(ロンドン協定)を締結した。ロンドン協定により第2次大戦後の戦争犯罪処罰のあり方は画期的に変化した。同協定に付属した国際軍事裁判所憲章(条例)によりニュルンベルク裁判が開廷され,のちに同憲章に準拠して東京裁判が開かれるのである。この変化の特色は,第1に,連合国の一部の指導者が唱えた枢軸国指導者の即決処刑という方式が排されて,国際裁判方式が採択されたこと,第2に,従来の戦時国際法に規定された〈通例の戦争犯罪〉に加えて,侵略戦争の計画・準備・開始・遂行等を犯罪とする〈平和に対する罪〉,戦前または戦時中になされた殺害・虐待などの非人道的行為を犯罪とする〈人道に対する罪〉が新たに国際法上の犯罪と規定され,それらの犯罪についての戦争指導者と目された個人の刑事責任を認めた点にあった。しかし他方で,ロンドン協定採択にいたる過程には,四大国の国家的利益や政治的要請が色濃く反映していた。とくに会議では,採択さるべき憲章が自己の行動を拘束する足かせとならないよう,妥当範囲が普遍的で国家の行動を厳格に拘束する一般規定をつくらないとの意見がしばしば表明された。そして四大国は,裁判で連合国の所業は問題とされてはならず,あくまでも枢軸国の過去の事件を審判する点でようやく一致したのであった。こうして45年11月よりニュルンベルク裁判が開廷する。
日本敗戦後,連合国最高司令官(SCAP)のマッカーサーは,アメリカ本国の指令をうけて,対日占領政策の第一弾として,日本の戦犯容疑者の逮捕を行い,1945年9月11日の東条英機らの逮捕令を皮切りに,12月6日まで100名を超える日本の戦争指導者を逮捕・拘禁した。他方,日本の敗戦前後から連合国間では対日戦争犯罪処罰政策をめぐって活発な論議がなされたが,日本の場合もニュルンベルク裁判と同じく,〈通例の戦争犯罪〉に加え,〈平和に対する罪〉〈人道に対する罪〉という戦争犯罪概念を用い,国際軍事裁判方式をとることでは基本的に一致していた。連合国間の摩擦は,この裁判所の憲章(条例)の公布,判・検事の任命など裁判所の設置・運営について,アメリカが決定的ともいえる主導権を握ったことから生じた。アメリカは日本の敗戦直後から,すでに準備がなされていたニュルンベルク裁判の経験から,日本の裁判もドイツの場合に準拠することが望ましいが,裁判所の設置と施行規則,戦争犯罪概念の規定は,連合国間の協定によるよりは,SCAPのマッカーサーが決定すべきだとの方針を固めていた。これに対し連合国,とくにオーストラリア,ソ連は強く反発したが,アメリカは戦犯容疑者の逮捕など既成事実を積み重ね,結局,日本占領におけるアメリカの圧倒的優位性からもその意図は基本的に貫徹された。なおこの間,マッカーサーは,この国際裁判とは別に,真珠湾奇襲攻撃の責任者として日米開戦時の東条内閣閣僚だけはアメリカ単独の軍事裁判にかけるべきだとアメリカ本国に執拗に要請したが,これは実現しなかった。45年12月6日に来日したキーナンJoseph Berry Keenan首席検事をキャップとするGHQの国際検察局(IPS)のメンバーによって準備され,IPSが起草した極東国際軍事裁判所憲章(条例)が46年1月19日,マッカーサーによって布告されて,東京裁判の基本的枠組みが設定された。同憲章は4月26日に一部分が改正されるが,ニュルンベルク裁判に比べ,東京裁判の構成の特色は表1のとおりになる。東京裁判がアメリカ・SCAPの決定的権限のもとにあったことが確認できる。裁判はアメリカの占領政策の一環という色彩を強めたのである。とりわけただ一人のアメリカ人の首席検察官の指令にもとづく統一的検察団の設置は,アメリカがオーストラリアの反対を押し切って,天皇の不訴追を決定する際に強力な武器となった。
被告の選定
国際検察局は,マッカーサーの戦犯逮捕令ののち独自に7名の逮捕指令を発し,被告選定作業にあたった。被告選定の準備として,当初,〈A.1930~36年1月〉〈B.1936年2月~39年7月〉〈C.1939年8月~42年1月〉〈D.財閥〉〈E.膨張主義的超国家主義団体〉〈F.陸軍軍閥〉〈G.官僚閥〉の7作業グループによって,戦犯容疑者の分類,尋問,事実調査がなされた。主要な作業グループはA~Cで,〈平和に対する罪〉を主眼点に被告の選定がなされたのである。検察局で被告選定を実質的に担当したのは,1946年3月2日に設置された執行委員会(議長はコミンズ・カー・イギリス検事)であった。そして4月5日,重光葵(まもる)と梅津美治郎(よしじろう)以外の26名の被告が来日していた連合国検事全員による参与検察官会議で決定され,マッカーサーに報告された。しかしこの後,来日したソ連の検察陣の要求で4月17日の参与検察官会議で,多数決で,重光と梅津の2名が追加され,28名の被告が決定された。被告選定で,最大の問題は天皇訴追問題であった。オーストラリアの検事は天皇訴追を正式に提議したが,占領政策の円滑な遂行のための高度な政治的配慮から天皇の免責を主張するキーナンがこれに反対し,天皇免責が決定した。なお被告確定後もA級戦犯容疑者の多くが拘禁されつづけたが,これは検察局が,当初は,第2,第3のA級裁判を予定していたからである。検察局は被告の選定とともに起訴状の作成にあたり,4月29日に公表した。起訴状は,訴追対象を1928年1月1日から45年9月2日までとし,28名の被告を〈平和に対する罪〉〈殺人〉〈通例の戦争犯罪及人道に対する罪〉に概括する55の訴因で起訴し,とくに訴因第1の1928年からの〈平和に対する罪〉の包括的共同謀議には全被告が該当するとした。
裁判の経過
公判は1946年5月3日開始し,法廷成立手続,起訴状朗読,被告の罪状認否の申立てがなされたが,清瀬一郎弁護人は裁判官忌避,裁判管轄権に対する異議申立ての動議を提出した。管轄権動議は〈平和に対する罪〉〈人道に対する罪〉が〈事後法〉(ある行動がなされたのちに,それを処罰する法を制定すること)に相当するものであり,〈罪刑法定主義〉に反するとの趣旨であったが,キーナン検事は裁判所憲章はパリ不戦条約などすでにある国際法を宣言しているものだと反駁(はんばく)し,裁判官も〈理由は将来において述べる〉として弁護側動議を却下した。ついで6月4日からキーナン首席検事の冒頭陳述を皮切りに検察側立証が開始され,戦争一般準備,満州事変,日中戦争,日独伊関係,ソ連邦,太平洋戦争,残虐行為,個人,の各段階にわたって論告・立証がなされた。これに対し弁護側は,47年2月24日の清瀬弁護人の冒頭陳述につづいて,検察側の各段階の立証について反証を展開した。この後48年1月13日から検察側反駁立証,弁護側再反駁立証,検察側最終論告,弁護側最終弁論がなされ,48年4月16日,裁判は結審となり,しばらく休廷となった。11月4日法廷は再開し,判決文の朗読が開始され,11月12日判決文朗読終了,被告への刑の宣告がなされた。こうして開廷から刑の宣告まで裁判は2年7ヵ月もの長期間続行し,この間,開廷日417日,開廷回数818回,証人419人,宣誓口供書779人,証拠4336件という膨大な数にのぼった。公判では,当時の国民が知りえなかった張作霖爆殺事件や満州事変以降,太平洋戦争にいたるまでの重大事件の真相が次々と暴露され,また南京事件など日本軍のおぞましい残虐事件のなまなましい証言が提出され,大きな衝撃を与えた。しかし他方で判事の法廷指揮は,勝者の敗者に対する一方的裁判であることを印象づけるものが少なくなかった。
判決
判決結果は表2のとおりであるが,28名被告中,公判中に死亡した松岡洋右,永野修身の2被告と精神異常と認定された大川周明は免訴となった。判決本文は,英文で1200ページに及ぶ膨大なものであったが,この多数派判事による本判決とは別に,インドのパル Radhabinod Pal判事,オランダのレーリングBert V.A.Röling判事,フランスのベルナールHenry Bernard判事の各少数意見と,オーストラリアのウェッブWilliam Flood Webb裁判長,フィリピンのヘラニラ判事による別個意見書も裁判所に提出された。判決は,裁判所憲章は裁判所にとって絶対であり法廷を拘束する,〈平和に対する罪〉〈人道に対する罪〉は〈事後法〉によるものではなく,現行国際法を明文化したものである,また訴因第1の侵略戦争の共同謀議は,その目的とする支配地域に制限を付したうえで立証されたと認定するとの判断を下した。これに対し少数意見で,パル判事は,被告の共同謀議は立証されないなどの理由で,被告全員の無罪を主張し,無差別殺人政策としてアメリカの原爆使用決定の重大さを強調した。レーリング判事は,共同謀議の認定に異論を呈するとともに,畑,広田,木戸,重光,東郷の無罪を主張した。ベルナール判事は,天皇の不起訴が公正な審理を不可能にしたとし,〈平和に対する罪〉の判定を否定し,量刑にも異議を唱えた。またウェッブ判事も有罪被告の量刑に天皇免責の事情を考慮すべきだとした。判決後,マッカーサーは対日理事会,極東委員会の意見を聴取して,判決を承認し,刑の執行を指令した。しかし11月29日,広田,土肥原ら7名の被告はアメリカ最高裁に人身保護令に対する訴願申立てを行ったが,同最高裁は,訴願を却下した。かくて12月23日,東条英機ら7名の絞首刑が執行された。しかし翌24日には岸信介,児玉誉士夫,笹川良一など最後まで拘禁されていた17名のA級戦犯容疑者の釈放がなされ,総司令部はA級裁判継続の意思がないことを示した。有期刑者のうち,梅津,白鳥,小磯,平沼,東郷の5名は服役中病死し,残りは仮出所制度により,50年11月の重光被告の仮釈放を最初として刑期前に全員が仮出所した。
問題点
東京裁判は訴追対象となった時期の日本の歴史と当該時期の戦争指導者を審判した試みとして重大な歴史的意義ももつが,問題点も多い。裁判手続では,判・検事とも中立国から選ばれず,すべて連合国の代表者であり,〈勝者の正義〉の色彩を強めたこと,原爆投下など連合国側の所業は問題にされなかったことが指摘できる。また,適用された国際法の是非についてはいまだに論議が多く,しかも裁いた側のアメリカ,ソ連をはじめとする大国が,以後の自国の対外行動で裁判の理念を裏切ったことが,裁判の信用をのちに低下させることになった。さらに問題の多い英米法特有の共同謀議論を適用して,日本の長期の侵略戦争の歴史を分析したのは相当無理があった。とくに政治的配慮から天皇を免責し,天皇制国家独特の国家意思発動の過程を正面から分析せず,極端な軍国主義による共同謀議による侵略戦争という歴史認識を判決が採用したことは,歴史の実態からみても問題が多い。なお,東京裁判の審判で欠落した日本軍の重大行為としては,関東軍防疫給水部(731部隊)などによる中国人捕虜など多人数へのペスト菌,コレラ菌など細菌の感染実験と生体解剖,中国戦線での細菌戦の実施,さらには中国大陸各地での毒ガス作戦の展開があり,近年,大きな問題となっている。
→戦犯 →ニュルンベルク裁判
執筆者:粟屋 憲太郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「東京裁判」の意味・わかりやすい解説
東京裁判【とうきょうさいばん】
→関連項目小野清一郎|木戸幸一|木村兵太郎|清瀬一郎|軍事裁判|第2次世界大戦|太平洋戦争(日本)|花岡事件|パル|松井石根
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「東京裁判」の解説
東京裁判
とうきょうさいばん
戦争指導者(A級)に対して,1946年5月〜48年11月に東京の市ケ谷法廷で行われ,東条英機ら7名は絞首死刑,18名は禁固刑(講和後釈放)となった。その他は未決で釈放された。なお,B・C級被告に対する裁判は青山・横浜で行われた。天皇の戦争責任を追及する立場に対し,キーナン首席検事(米)らの反対で,天皇免責が決定した。この裁判に対しては,戦勝国による復讐的なものである,また戦争犯罪の定義があいまいである,などの批判があるいっぽうで,日本軍の残虐行為について欠落したものがあるという問題点も指摘されている。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
デジタル大辞泉プラス 「東京裁判」の解説
東京裁判
山川 日本史小辞典 改訂新版 「東京裁判」の解説
東京裁判
とうきょうさいばん
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「東京裁判」の解説
東京裁判(とうきょうさいばん)
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「東京裁判」の意味・わかりやすい解説
東京裁判
とうきょうさいばん
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「東京裁判」の意味・わかりやすい解説
東京裁判
とうきょうさいばん
「極東国際軍事裁判」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の東京裁判の言及
【太平洋戦争】より
…ところが敗戦後の日本人は,みずからの手で戦争責任を厳しく追及することなく,今日に及んでいる。 連合国によって開廷された東京裁判(極東国際軍事裁判)(1946年5月3日~48年11月12日)は,(1)国際連盟,不戦条約,国際連合,日本国憲法第9条などに体現されてきた戦争を違法とする世界史の流れのなかで,〈共同謀議の罪〉という犯罪類型を導入し,初めて国家指導者の個人的な刑事責任を追及したこと,(2)〈平和に対する罪〉という新しい構成要件をつくりあげ,それを構成要件の筆頭にすえたこと,(3)〈文明の裁き〉というたてまえのもとに,〈殺人〉と〈通例の戦争犯罪および人道に対する罪〉を第2,第3の構成要件とし,十五年戦争の侵略的性格と日本軍の野蛮な残虐行為を具体的な証拠に基づいて白日のもとに暴露したこと,の3点において画期的な意義を有していた。しかし同時にこの軍事裁判は,(1)戦争の当事者である戦勝国が戦敗国を一方的に裁くという〈勝者の裁き〉であったばかりでなく,裁く側に過去4世紀に及ぶ過酷な植民地支配,アメリカによる原爆投下と都市無差別爆撃の戦時国際法違反,ソ連による日ソ中立条約侵犯と日本人捕虜のシベリア抑留問題などの汚点と弱点があったこと,(2)〈平和に対する罪〉は戦争違法観と指導者責任観とが結合されて第2次世界大戦末期に成立したが,これによって個人を重罰に処したことは法理上問題があり,また〈共同謀議〉という英米法でも問題の多い法概念で1928‐45年の事実を裁くことには無理があったこと,(3)裁判が事実上アメリカの日本占領政策の一環として行われたため,天皇の不起訴,真珠湾攻撃の観点が優越した被告人の選定,A級戦犯の責任追及の途中打切りなどの不十分な結果をもたらしたこと(戦犯),(4)日本の民衆の侵略戦争への荷担の責任がまったく問題にされなかったこと,などの弱さを有していた。…
【パル】より
…法律家。極東国際軍事裁判(東京裁判)判事。インドのベンガル州に生まれ,カルカッタ大で法学博士の学位をとり,1923‐36年カルカッタ大法科大教授。…
※「東京裁判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...


 稲垣俊原案、
稲垣俊原案、