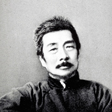共同通信ニュース用語解説 「魯迅」の解説
魯迅
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
精選版 日本国語大辞典 「魯迅」の意味・読み・例文・類語
ろじん【魯迅】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「魯迅」の意味・わかりやすい解説
魯迅
ろじん / ルーシュン
(1881―1936)
中国の文学者、思想家。9月25日浙江(せっこう)省紹興(しょうこう)に生まれる。本名は周樹人、字(あざな)は予才、ほかに迅行、唐俟、巴人など数十の筆名を用いた。家は祖父が知県も務める中地主だったが、祖父が科挙の不正事件で入獄、父も病死して、にわかに没落、彼は長子として生活の苦労も体験した。「世の中の人々の真の顔を見た」と自らいっている。1898年南京(ナンキン)の江南水師学堂に入学したが、内容に不満で退学、江南陸師学堂付設の鉱務鉄路学堂に入学、ここで厳復(げんふく)訳による西洋近代思想や変法派系の新聞、雑誌に触れた。
1902年(明治35)官費留学生として日本に派遣され、弘文(宏文)(こうぶん)学院を経て仙台医学専門学校に入学した。このころ思想的には革命派の立場にたち、清(しん)朝打倒を目ざす光復会にも加入した。仙台医専在学中、志を文学に転じて退学、東京に戻って企画した文学運動の雑誌『新生』は未成に終わったが、そこに発表するはずであった内容は、『河南』(1907年中国人留学生が東京で創刊した雑誌)に掲載した「文化偏至論」「マラ詩力説」「破悪声論」(いずれも1908)など一連の論文にみられる。強烈な個性と反逆精神をもつ詩人=精神界の戦士を顕彰して中国にもその誕生を促し、その叫びによって民衆の心を燃えたたせる、というのが当時の彼の描いた中国変革のイメージであった。民衆の問題を中心課題としているとはいいながら、具体的な運動論も組織論ももたぬ抽象的、観念的なものであった点で、当時の革命派の思想と、正負両面の特徴を共有していたといえる。これらの論文と並行して、弟の周作人(しゅうさくじん)とともにロシア、東欧の短編の翻訳『域外小説集』(1909)も出版したが、いずれもさしたる反響もないまま1909年帰国した。
帰国後、杭州(こうしゅう)、紹興で教師をするうちに辛亥(しんがい)革命(1911)を迎え、新政府に教育部員として参加、北京(ペキン)に移った。しかし辛亥革命後の現実は、彼の革命像を大きく裏切るもので、袁世凱(えんせいがい)の反動のもと、「寂寞(せきばく)」の時期を送る。やがて『新青年』を中心に起こった文学革命にも当初は消極的だったが、1918年、友人の勧めもあって『狂人日記』を発表、以後『阿Q正伝(あキューせいでん)』(1921~1922)等、のちに『吶喊(とっかん)』(1923)、『彷徨(ほうこう)』(1926)にまとめられた小説を発表した。これは文学革命に実質を与え、中国近代文学の成立を示すものであるとともに、彼にとっては、中国社会と民衆のあり方を振り返り、青年時代の革命像を再検討する意味をもったものでもあった。また一方鋭い社会・文化批評を込めた「雑文」を執筆した。雑文はやがて著作の大きな部分を占め、中国文学のなかでも独自の一ジャンルとなることになる。この時期には北京大学その他で『中国小説史略』(1923~1924刊)を講じた。これは小説史という新しい分野を開拓したもので、小説史研究の古典とされる。
1925年、北京女子師範大学の改革をめぐって新旧両派の衝突した「女師大事件」では、進歩派の学生・教員とともに軍閥政府に抵抗、そのためいったんは教育部員を罷免されたが、平政院に提訴して勝利を収めた。一方とくに自己の内面の矛盾に光をあてた散文詩集『野草(やそう)』(1927)を書いた。彼は留学中に一度帰国して朱安(しゅあん)(1878―1947)と古い型の結婚をしていたが、このころ女師大の学生だった許広平(きょこうへい)と出会い、しだいに愛が生じた。1926年夏、厦門(アモイ)大学に移ったが、その空気に不満で1927年初め、国民革命の根拠地だった広東(カントン)に移り、ここで四・一二事件(上海(シャンハイ)クーデター)を体験、思想的にも大きな転機となった。1927年秋上海に移り、このときから許広平と同居、1929年に1子海嬰(かいえい)(1929―2011)をもうけ、死まで上海に住んだ。
上海では国民革命の挫折(ざせつ)を機に、プロレタリアートの意識にたつ「革命文学」を唱える創造社、太陽社から、過去の暗黒しかみることのできぬ小ブル文学者と非難を受けたが、逆に、彼らが文学に対してのみならず革命に対しても安易であることをついて「革命文学論戦」を展開した。一方、自らマルクス主義芸術論やソビエト文学を精力的に翻訳した。やがて創造社等の側にも中国共産党の指導もあって態度に変化が生まれ、1930年左翼作家連盟の結成に至ると、その中心的人物となり、国民党政府の弾圧やその御用文人と非妥協的に論争した。一方、左翼内部の弱点も見逃さない彼の眼(め)とその発言は、若い党員文学者の一部には理解しがたいものもあったらしく、彼らとの間にはある種の摩擦もあった。1936年抗日統一戦線をめぐって周揚(しゅうよう)らとの間で展開した「国防文学論戦」などもその表れであった。
芸術にも早くから関心をもっていたが、1931年内山完造(うちやまかんぞう)の弟嘉吉(かきつ)(1900―1984)を招いて木版画講習会を開いたのをはじめとして若い木版作家を養成、中国現代版画の基礎を築いた。作品のおもなものにはほかに、回想録風の作品集『朝花夕拾』(1928)、神話・歴史に題材をとったユニークな短編集『故事新編』(1936)、許広平との往復書簡集『両地書』(1933)、雑文集多数がある。また翻訳にも力を注ぎ、全著作にほぼ匹敵する分量の翻訳がある。翻訳は、日本文学、ロシア文学ほか多岐にわたり、日本文学では森鴎外(もりおうがい)、夏目漱石(なつめそうせき)、芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)などのほか、厨川白村(くりやがわはくそん)、片上伸(かたかみのぶる)などのものが多い。1936年10月19日没。
[丸山 昇 2016年3月18日]
『竹内好訳『魯迅文集』全6巻(1976~1978・筑摩書房/ちくま文庫)』▽『竹内好著『魯迅』(1944・日本評論社/新版・1961・未来社/講談社文芸文庫)』▽『増田渉著『魯迅の印象』(1948・講談社/新版・1970・角川書店)』▽『飯倉照平著『人類の知的遺産69 魯迅』(1980・講談社)』▽『丸山昇著『魯迅――その文学と革命』(平凡社・東洋文庫)』
改訂新版 世界大百科事典 「魯迅」の意味・わかりやすい解説
魯迅 (ろじん)
Lǔ Xùn
生没年:1881-1936
中国の文学者,思想家。本名周樹人,字は予才。その弟に周作人がいる。浙江省紹興の裕福な官僚地主の家に生まれたが,少年期に家が没落して辛酸をなめたことが,最初の現実覚醒の契機となった。やがて,清末に流入した進化論をはじめとする西欧啓蒙思潮の影響を受けつつ日本に留学,はじめ民族救済の道を医学に求め仙台医学専門学校に籍をおくが,弱小民族として差別される経験を重ねるうち文学に傾斜し,東欧被抑圧民族の文学を訳出する。帰国後,郷里での教員生活中に迎えた辛亥革命(1911)に大きな期待を寄せるが,革命は挫折し,深い絶望を味わう。やがて教育部の一役人として北京に出た魯迅は,数年におよぶ絶望の沈黙のはてに最初の小説《狂人日記》(1918)を発表する。狂人の心理を借りて〈人が人を食う〉半封建・半植民地の現実を鋭く暴いたこの小説は,従来なかったまったく新しい近代文学の形式と内容を中国文学の世界に切り開いた。これにつづけて,《孔乙己》《故郷》《祝福》などの佳作をつぎつぎに発表した。なかでも唯一の中編《阿Q正伝》は,一人のルンペン農民の形象を民族の典型にまで高め,〈阿Q精神〉なることばを生んだ。また,彼の詩人的資質の結晶として,散文詩集《野草》が書かれた。
1920年以降は,北京女子師範その他で教鞭をとったが,その講義録は《中国小説史略》として出版され,これ以後古典文学の研究もその仕事の重要な一部となった。26年,三・一八事件(不平等条約の撤廃を要求してたちあがった民衆運動に対する段祺瑞政府の弾圧事件)で北京を脱出した魯迅は,厦門(アモイ),広東をへて上海に落ち着くが,北伐革命の挫折とそれにつづく国民党による白色テロを目撃したことで思想的に深い衝撃を受け,マルクス主義に接近し,独特のしかたでそこから栄養を吸収した。この間,自分を攻撃する論敵との論戦を通じて,〈雑感〉とよばれる鋭い匕首(あいくち)のような独自のエッセーのスタイルを創出した。30年に中国左翼作家聯盟が成立すると,実質的にその指導者となったが,これ以後その死までの6年間,芸術至上主義や民族主義の仮面をかぶった正面の敵のみならず,セクト主義や極〈左〉主義など革命陣営内部の敵とも不寛容に闘いつづけた。さらに数多くの雑誌や叢書を編んで新人の養成につとめるかたわら,木刻(版画)の振興に情熱を燃やし,その基礎をすえた。このほか,多数の翻訳の仕事がある。これらは,国民党の白色テロルの脅威と重い結核という悪条件の下でなされた。
その死は全国の各階層の人々から哀悼され,その葬儀は〈最初の民族葬〉と呼ばれた。その死後,〈魯迅精神〉は中華民族を励ます合言葉として,現在も生きている。作品集は,《魯迅全集》20巻が38年に出版されたが,新中国になって詳細な注釈つきの《魯迅全集》10巻が出版され(1958),さらにそれを全面的に改訂した《魯迅全集》16巻が生誕100周年を記念して81年に出版された。
日本における魯迅の翻訳紹介では,《大魯迅全集》(全7巻。1937)が最初のまとまった画期的なものであった。研究書としては,竹内好《魯迅》(1944)が,アジアの被抑圧民族の悲哀と苦悩を象徴する知識人としての魯迅の像を,アジアの中の日本に生きる竹内自身の苦悩に重ね合わせて描き,その後の魯迅研究に大きな影響を与えた。戦後は,《魯迅選集》(全12巻。1956)をはじめ,各種の選集が出版され,研究者の数も増えて研究は精緻になり,研究の中心はしだいに実証面にむかいつつある。81年に出版された16巻本の《魯迅全集》の全訳が刊行中だが,その完成によって,日本における魯迅の紹介も一区切りがつくであろう。
執筆者:吉田 富夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「魯迅」の意味・わかりやすい解説
魯迅【ろじん】
→関連項目内山完造|エロシェンコ|許広平|瞿秋白|胡適|胡風|鄒韜奮|宋慶齢|天演論|白話|北京大学|木刻画|野夫|林語堂
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「魯迅」の意味・わかりやすい解説
魯迅
ろじん
Lu-xun
[没]1936.10.19. 上海
中国の文学者,思想家。本名,周樹人。字,予才。ほかに多くの筆名がある。少年の頃祖父の失脚で貧窮を体験。光緒 28 (1902) 年日本に留学,医学を志したが文学の重要性を痛感し,帰国後,1918年短編小説『狂人日記』で作家として出発,以後代表作『阿Q正伝』をはじめ,多くの小説,随筆,評論を発表,外国文学の翻訳,紹介にも努め,中国近代文学の祖となった。その作品に一貫しているのは,民族の将来を憂い,民族精神の改革を説く姿勢である。反動政府を逃れ,27年からは上海に妻の許広平と定住,30年左翼作家連盟発足後はその指導者となり,民族統一戦線のため不屈の論陣を張ったが,過労で倒れた。短編小説集『吶喊 (とっかん) 』『彷徨』。 38年に全集が編まれている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「魯迅」の解説
魯迅(ろじん)
Lu Xun
1881~1936
中国の文学者。浙江(せっこう)省紹興の人。本名は周樹人(しゅうじゅじん),魯迅は筆名。日本留学中,医学を捨てて文学に転じた。北京に住んで『新青年』に「狂人日記」を寄稿し,白話(はくわ)文学の先鞭をつけた。1921年の「阿Q正伝」(あキュウせいでん)は名高い。反動的な北京を逃れて厦門(アモイ),広州へと移り,ついで上海に永住した。その間,独自の雑文形式を創出して左右両翼の非人民的立場と戦い,民族統一戦線の結成をめぐる論戦中に没した。夫人は許広平,弟に周作人,周建人がいる。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「魯迅」の解説
魯迅 ろじん
光緒7年8月3日生まれ。周作人の兄。明治35年(1902)日本に留学し仙台医専にはいるが中退し,文学に転向。42年(1909)帰国し,辛亥(しんがい)革命後は臨時政府の教育部員となる。1918年小説「狂人日記」を発表。ついで代表作「阿Q正伝」や社会,政治,文化を批判した小説・評論を多数執筆。1927年上海にうつり,左翼作家連盟の中心として論陣をはった。1936年10月19日死去。56歳。浙江省出身。本名は周樹人。字(あざな)は予才。中国語読みはル-シュン。
【格言など】青年時代には,不満はあっても悲観してはならない。つねに抗戦し,かつ自衛せよ
旺文社世界史事典 三訂版 「魯迅」の解説
魯迅
ろじん
中国の文学者
本名は周樹人。1902年日本に留学し,仙台で医学を学んだが中退。厳復・梁啓超らの啓蒙思想の影響を受け,東欧の被圧迫民族の文学にひかれ,ニーチェに心酔。1909年帰国。辛亥革命後,新政府教育部につとめたが,新国家への期待は裏切られ,文学革命のさなか,中国の暗黒な現実への絶望の中で,18年「新青年」誌に『狂人日記』を発表。以後,『阿Q正伝』ほか,詩・評論・小説を発表して,社会悪の根源を鋭くえぐる。1926年反動支配下の北京を逃れ,上海に定住。1930年左翼作家連盟を結成して,国民党の進歩派弾圧に抵抗の姿勢を示した。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「魯迅」の解説
魯迅
ろじん
Lu Xun
1881.9.25~1936.10.19
中国の作家・思想家。本名は周樹人(しゅうじゅじん)。字は予才。浙江省出身。1902年(明治35)日本に留学。進化論に関心をもち,仙台医学専門学校に入学。06年文学に転じ,東京で文芸雑誌「新生」を計画したが失敗。09年帰国。辛亥(しんがい)革命後,南京臨時政府・北京政府教育部部員となる。旧体制下の中国を痛烈に批判した「狂人日記」「阿Q正伝」などの口語体小説は,中国近代文学の黎明を告げる代表作。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
367日誕生日大事典 「魯迅」の解説
魯迅 (ろじん)
中国の作家;思想家;文学史家
1936年没
出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の魯迅の言及
【内山完造】より
…上海の店は,日本の中国侵略の進行しつつあった時代にもかかわらず,日中文化人の交流の場として著名になった。27年以来,10年におよぶ魯迅との交流は名高い。29年以来,北四川路にあった内山書店は魯迅の住居に近く,魯迅は内山書店を応接室がわりに利用していたほどであった。…
【エロシェンコ】より
…19年再来日,早大聴講生となり,第2次《種蒔く人》の同人となり,次々と童話を発表した。思想的に危険な人物として日本から21年に追放され,中国に行き,魯迅らの知遇を得て北京大学でロシア文学についての講義をした。23年祖国に帰り,極東勤労者共産主義大学(クートベ)の日本語通訳,マルクス主義文献の日本語訳などの仕事に従事した。…
【許広平】より
…魯迅夫人。広東省出身。…
【孔子批判】より
…〈民主と科学〉を旗じるしとする雑誌《新青年》を中心に,中国の社会と文化を改革するためには,中国の封建体制の基礎となっている家族制度とそれを支えてきた孔子の教え(儒教)を否定せねばならぬ,という認識が進歩的知識人の共通のものとなった。陳独秀は〈孔子の道と現代生活〉など多くの文章で,孔子の思想が封建的なものであって民主主義とは両立しえないと主張し,呉虞は〈儒教の害毒は洪水猛獣〉のごとくはなはだしいものだと痛烈に批判し,魯迅は,儒教は〈人が人を食う〉教えであるとのべて《狂人日記》のなかで,人を食ったことのない(儒教に毒されぬ)子供を救え,と書いた。このほか,胡適,李大釗(りたいしよう),周作人,銭玄同,易白沙,高一涵など多くの人々が儒教の打倒を論じた。…
【国防文学】より
…運動推進の母体として1936年に中国文芸家協会を結成したが,それに先だって,従来の文芸界における統一戦線組織である中国左翼作家聯盟(〈左聯〉)を,ソ連にいた王明(陳紹禹)の指示で解散した。このとき〈左聯〉の実質的な指導者である魯迅との意思の疎通を欠き,そのため魯迅は,胡風や中共党中央から派遣されて上海へ来たばかりの馮雪峰と相談,また茅盾にもはかって〈民族革命戦争の大衆文学〉というスローガンを提起,〈中国文芸工作者宣言〉を発した。その結果,36年の上海文化界は〈二つのスローガン〉をめぐっての論戦が激しくなり,一時的に混乱したが,両者は同年10月に〈文芸界同人の団結御侮と言論の自由のための宣言〉を出して,日本の侵略に一致して対応することとなった。…
【五・四運動】より
…前者は辛亥革命後の軍閥支配に抗して中国の出路をもとめていたインテリたちである。もっとも有名なのは,《新青年》に拠って新文化運動を展開した陳独秀,李大釗(りたいしよう),胡適,魯迅らのグループである。彼らは,民主と科学の旗をかかげ,中国の封建倫理の中核である孔子の教えを根底から否定しようとした(打倒孔家店)。…
【児童文学】より
…しかし,子どものための文学の意識的な創造は,第1次世界大戦後,中国に反帝反封建の運動がもりあがり,文学革命が進んでからのことである。葉紹鈞(ようしようきん)の《稲草人(かかし)》(1922)は,中国ではじめての近代童話であり,魯迅(ろじん)はこの作品を〈中国の童話のために一すじの創作の道をひらいてくれた〉と高く評価した。魯迅も,中国の児童文学の発展のために外国の作品を翻訳し,また民話・古典など民族の文化遺産の生かし方に指導的な役割を果たした。…
【中国文学】より
…ついで,陳独秀が〈文学革命論〉を発表してこれに呼応し,〈国民文学〉〈写実文学〉〈社会文学〉を提唱するにおよんで,〈文学革命〉は時代の合言葉となった。文学革命に最初の実体を与えたのは,魯迅の短編《狂人日記》(1918)であった。魯迅はその作品で,強靱でひきしまった口語体の文体を創出し,〈人が人を食う〉封建的儒教秩序の欺瞞(ぎまん)性を鋭く暴き,人間解放の悲痛な叫びをあげた。…
【二十四孝】より
…日本でもお伽草子の《二十四孝》や仮名草子の《大倭(やまと)二十四孝》が生まれた。魯迅は《二十四孝図》の一文で,人情にはずれた封建倫理に強く反発しているが,母のために雪中に笋(たけのこ)をもとめる孟宗の故事を〈一子寒し親孝行の袖の月,どこにあらうぞ雪の笋〉と皮肉った井原西鶴は,二十四孝物語を逆用して《本朝二十不孝》を著した。孝【吉川 忠夫】。…
【年画】より
…年画は約1000年の歴史をもち,宋代は比較的高い水準に達し,明代は印刷技術の発達で量産され,清代は天津や蘇州で多種多様な年画が生産された。民国時代は魯迅によって再興され,現代は広く農村にまで普及している。【遠藤 光一】。…
【百喩経】より
…〈愚人が塩を食べる喩〉をはじめとする各編は,まず寓話を述べ,次にその寓話が示す仏教訓話で締めくくっている。本経は,魯迅が南京の金陵刻経処に寄付して出版させたことでも知られる。【礪波 護】。…
【北京大学】より
…1912年,北京大学と改称したが,当時はまだ官吏養成機関としての性格が強かった。17年,蔡元培が学長に就任して,陳独秀を文科科長に据え,李大釗(りたいしよう),魯迅などを招聘し,アカデミックな大学に改革して以来,名実ともに学問の殿堂としての陣容を整えた。19年の五・四運動の先頭に立ったのは北京大学の学生であった。…
【木刻】より
…また蘇州の木刻画は日本の浮世絵にも影響をおよぼしている。 中華民国時代の木刻画は中国近代版画の父魯迅によって指導された。人間を変革すべき美術は正しくリアリズム芸術であるとして,白と黒だけの単純化された表現法と量産可能な複製とをもって,中国の近代化と独立を標榜した革命美術の創造と普及,啓蒙に貢献した。…
※「魯迅」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

 [1881~1936]中国の文学者・思想家。
[1881~1936]中国の文学者・思想家。