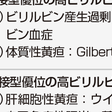黄疸(読み)オウダン(その他表記)jaundice
精選版 日本国語大辞典 「黄疸」の意味・読み・例文・類語
おう‐だんワウ‥【黄疸】
- 〘 名詞 〙 胆汁に含まれている胆汁色素が、多量に血液中に現われ、皮膚や粘膜などが黄色になる病気。体内で赤血球が一度に多量にこわれた時におこる溶血性黄疸、肝臓自体の病気でおこる肝性黄疸、胆汁を運ぶ胆道が閉塞されたためにおこる閉塞性黄疸がある。黄病。〔十巻本和名抄(934頃)〕
改訂新版 世界大百科事典 「黄疸」の意味・わかりやすい解説
黄疸 (おうだん)
jaundice
icterus
胆汁色素(ビリルビン)が血液および組織中に増加した状態を意味し,臨床的には血清,皮膚,粘膜が黄色に染まる状態をいう。jaundice,icterus(ラテン語由来)はもともと黄色を意味する言葉であったが,現在は黄疸を指す言葉として用いられている。正常者の血液では血清ビリルビンは1mg/dl以下であり,血清ビリルビンが3mg/dl前後以上の場合に黄疸として認識できる。一般に黄疸は単にビリルビンの増加する場合と,同時に胆汁成分,たとえば胆汁酸の増加を伴う場合とに分けられるが,前者は高ビリルビン血症hyperbilirubinemia,後者は胆汁鬱滞(うつたい)cholestasisと呼ばれている。
黄疸の研究史
黄疸はすでにヒッポクラテスによって記載されており,東洋医学においても古くから黄疸あるいは黄胆という言葉が用いられてきた。しかし黄疸の研究が化学的に展開したのは19世紀半ばで,R.フィルヒョーはビリルビンとヘモグロビン(血色素)の関係について述べ(1847),その後J.W.L.アショフ,ウィップルG.H.Whippleらはビリルビンはヘモグロビンから生成されることを明らかにした。ベルヒHijmans van den Berghらは,P.エールリヒのジアゾ試薬を用いて,ビリルビンには直接型反応を呈するものと間接型反応を呈する2種類があることを報告した(1916)。1950年前後からビリルビン研究の飛躍的な進歩に伴い,黄疸の病態生理は漸次解明されてきたが,いまだ不明な点も多い。
黄疸の症状
黄疸が最も早く現れるのは眼球結膜で,次いで顔面,手のひらに現れる。眼球結膜で黄疸がみられるのは,血清ビリルビンが3mg/dl以上のときが多く,1~3mg/dl程度では亜黄色調を呈する。皮膚,粘膜の黄染は,太陽光線によって比較的明るい場所で確かめる。ビリルビン以外の物質によって皮膚黄染を起こすものに,ミカン,ニンジン,トマトなどを大量摂取したときの柑皮症,あるいはカロチン血症があり,またルチン,アテブリンなどの色素によっても手のひら,足のうらが黄染することがある。したがって,黄疸の診断を確定するためには,血清ビリルビンを測定して,その増加を確かめる必要がある。黄疸時にはしばしば皮膚のかゆみを訴えることがある。かゆみの原因として血液および皮膚の胆汁酸の増加が考えられている。尿は黄疸発現の直前からしだいに暗褐色となる。ただし,溶血性黄疸では尿の色は正常で変わらない。糞便は黄疸の増強とともに固有の色調を失い,閉塞性黄疸では灰白色の粘土様になる。
黄疸の原因と発生のしくみ
正常人では1日300mg前後のビリルビンが生成されるが,このうち80%は老廃赤血球由来で,主として肝臓,脾臓の網内系細胞で生成される。残りの20%は,肝臓,腎臓のヘムタンパク質由来の早期ビリルビン非造血成分と,骨髄の無効造血由来の造血成分から成り立っている。血清ビリルビンには,ジアゾ試薬によりただちに呈色する抱合ビリルビン(直接型)と,メチルアルコール,安息香酸ナトリウムなどで処理後に,ジアゾ試薬で呈色する非抱合ビリルビン(間接型)とがある。抱合ビリルビンは肝細胞の小胞体でグルクロン酸抱合を受けたもので,水溶性で容易に胆汁へ排出されるが,非抱合ビリルビンは肝臓でのグルクロン酸抱合を受けない遊離型で,脂溶性を有する。実際にビリルビン量を測定するときには,総ビリルビンと直接ビリルビンを測定し,総ビリルビンから直接ビリルビンを差し引いて間接ビリルビンを求める。血清ビリルビンの正常値は,総ビリルビン0.2~0.8mg/dl,直接ビリルビン0.2mg/dl以下で,間接ビリルビンが優位を占める。
黄疸を考える場合に,肝前性黄疸,体質性黄疸,肝性黄疸,肝後性黄疸に分類すると,病態の理解が容易である。
(1)肝前性黄疸 ビリルビンの過剰生成によるもので,溶血性貧血とシャント高ビリルビン血症が代表的な疾患である。溶血性貧血は,種々の原因により溶血の亢進が起こって,肝臓が処理できる限度以上にビリルビンが産生されるもので,非抱合ビリルビン血症,赤血球半減期の短縮,糞便および尿中ウロビリン体増加を伴う。詳しくは〈貧血〉の項を参照されたい。シャント高ビリルビン血症は,原発性と続発性に分類され,前者は骨髄の新生赤血球の一部が末梢血に出現しない(無効造血),病因不明のきわめてまれな疾患である。続発性シャント高ビリルビン血症は,悪性貧血,ポルフィリア,サラセミア,慢性骨髄性白血病,再生不良性貧血,脱血などで出現する。
(2)体質性黄疸 先天性の高ビリルビン血症を総称する。そのうち,クライグラー=ナジャール症候群は,新生児にみられる高度の非抱合ビリルビン血症で,核黄疸を起こし早期に死亡する。病因は肝臓のビリルビン-グルクロン酸抱合にあずかる酵素(UDP-グルコニルトランスフェラーゼ)の欠損による。体質性黄疸の成人型として,ギルバート症候群(肝細胞のビリルビン摂取障害と抱合障害),ズビン=ジョンソン症候群(ビリルビンの排出障害で肝臓が肉眼的に黒褐色を呈する),ローター症候群(肝細胞のビリルビンの摂取障害と排出障害)があげられるが,いずれも先天性の予後良好な疾患である。
(3)肝性黄疸 肝性黄疸は肝細胞性によるもので,黄疸のもっとも多い原因である。ウイルス肝炎,アルコール性肝炎,薬剤性肝障害,肝硬変,肝臓癌などがあげられる。肝性黄疸では,ビリルビンの肝細胞摂取,運搬,抱合,排出などの諸機能が障害されるが,血清ビリルビンが抱合型を示すところから,ビリルビンがいったん抱合後血中に逆流する胆汁鬱滞の機序が加わっている可能性が強い。肝内胆汁鬱滞は広義の肝性黄疸にはいり,種々の原因により肝細胞の胆汁分泌機能が障害されたために,ビリルビン,胆汁酸などの胆汁成分が肝組織内と血中に停滞した状態である。肝内胆汁鬱滞の範囲にはいる疾患として,ウイルス性および薬剤性肝内胆汁鬱滞,妊娠性反復性肝内胆汁鬱滞,原発性胆汁性肝硬変,原発性硬化性胆管炎などがあげられる。原発性胆汁性肝硬変は,中年以後の女性に好発し,症状は皮膚搔痒(そうよう)感で始まり,しばしば免疫異常を伴う。
(4)肝後性黄疸 肝門部または肝外胆管の閉塞によって起こる肝外胆汁鬱滞で,肝臓から胆管,腸管への胆汁排出が障害されるために,胆汁が肝臓から血中へ逆流して胆汁鬱滞が起こる。したがって,肝外胆汁鬱滞は閉塞性黄疸あるいは外科的黄疸とも呼ばれる。具体的な疾患として,胆囊胆管系の結石,胆囊炎,膵炎,胆囊癌,胆管癌,膵癌,ファーター乳頭部癌,原発性および転移性肝臓癌,術後良性胆道狭窄症,先天性胆道閉鎖症などがあげられる。
黄疸の診断
黄疸の診断には,既往歴,家族歴が重要な情報を提供するので,問診を詳細に行う。粘膜,皮膚の黄疸がみられれば,診断は問題がない。ごく軽度の黄疸で,皮膚・粘膜の着色がはっきり現れないときには,血清ビリルビンを測定する。血清ビリルビンが非抱合型優位のときは,溶血性貧血あるいはギルバート症候群の可能性が強い。理学的検査では,皮膚症状,肝腫,脾腫などに注意し,意識障害や腹水の有無を確かめる。黄疸があって胆囊が触れられる場合(クールボアジエ症候群),胆管系の結石または癌,膵癌などの存在が示唆される。黄疸の診断や鑑別診断の場合,血清ビリルビンのほかに,GOT,GPTをはじめとする血液生化学検査を行う。引き続いて超音波検査を行って,黄疸の成因が肝臓内か肝臓外かの診断をつける。黄疸の閉塞部位と質的診断を得るために,内視鏡的逆行性胆管膵管造影,経皮経肝胆道造影,CTスキャン,肝胆道シンチグラフィーなどを組み合わせて診断をすすめる。
→肝機能検査 →胆囊造影
黄疸の治療
黄疸の治療にあたって最も重要なことは,黄疸を起こす原因疾患の診断を早期につけることで,病因の明らかな場合,その原因を取り除くことが基本的な治療になる。肝性黄疸では,入院安静をすすめ,食事療法は高タンパク質,高カロリーでビタミン類の豊富な食事を与える。閉塞性黄疸は外科手術によってその病因を除去する。黄疸で全身倦怠,食欲不振が強く経口摂取が不十分なときは輸液療法を行う。
執筆者:川崎 寛中
小児の黄疸
子どもには以下のように成人と違った原因による黄疸がみられる。
(1)新生児生理的黄疸 新生児のほとんどは生後2,3日に黄疸が現れ,1週間か10日で消える。黄疸以外に何の異常もない。出生後に多数の赤血球がこわれることと,肝臓が未熟であることが原因である。(2)新生児重症黄疸 新生児期に黄疸が非常に強い状態をいう。原因はいろいろあるが,多いのは母子間の血液型不適合(母親がRh-で胎児がRh+の場合,ABO血液型では,母親がO型で胎児がA型かB型のとき,強い黄疸が現れる)による新生児溶血性疾患である。そのほか,未熟児,皮下出血や大きい頭血腫のある子ども,敗血症などは黄疸が強くなりやすい。血液型不適合による黄疸は生まれた日にすでに出現し,3~4日に最高に達する。Rh血液型不適合では貧血,肝脾腫,心不全がみられることがある。新生児重症黄疸は核黄疸を起こすことがあるので,血液中のビリルビンを測定し,必要なら核黄疸の予防のために光線療法や交換輸血が行われる。(3)母乳黄疸 母乳栄養児が生後1週ころから黄疸が強くなり,1~2ヵ月も消えないことがある。母乳中に含まれるある種のホルモンや脂質のためである。母乳黄疸は核黄疸を起こす心配はないので,母乳をやめる必要はまったくない。以上の(1)(2)(3)は肝前性黄疸で,血液中に増加するのは非抱合ビリルビン(間接型)である。次の(4)(5)で血液中に増加するのは抱合ビリルビン(直接型)である。(4)新生児肝炎 新生児期を過ぎても黄疸がとれず,皮膚は緑色を帯びた黄色になり,便は灰白色で,尿は濃い黄色になる。原因は不明である。多くは生後6ヵ月ころまでに黄疸は消失し,正常になる。(5)先天性胆道閉鎖 肝臓と十二指腸をつなぐ胆道が先天的に閉鎖している病気である。症状は新生児肝炎と同様であるが,黄疸はしだいに強くなり,肝臓は大きく,かたくなり,腹水がたまってくる。治療は手術によって胆道と腸をつなぐことである。生後2ヵ月以内に手術しないと,肝硬変を起こし,治りにくくなる。
執筆者:奥山 和男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
内科学 第10版 「黄疸」の解説
黄疸(症候学)
血中で上昇したビリルビンが皮膚や粘膜に沈着して黄染した状態を黄疸という.血清総ビリルビン値が2.5 mg/dL程度となると黄疸が認められるようになる(顕性黄疸).皮膚の色は溶血性黄疸ではレモン色調,肝細胞性黄疸ではオレンジ色調であり,胆汁うっ滞が長期に持続すると緑色調を呈する.
病態生理
【⇨9-1-3)】
鑑別診断
高ビリルビン血症は表2-3-1のような疾患で起こるが,まず直接型,間接型ビリルビンのどちらが優位かで分類すると,病態生理上,理解しやすい.黄疸を主訴に来院する患者のほとんどは直接型ビリルビン優位の黄疸であり,肝細胞性黄疸と閉塞性黄疸,なかでも急性ウイルス肝炎,薬物性肝障害,悪性腫瘍による胆道閉塞が多いことを考慮する.
1)問診:
問診上,尿と便の色の確認が重要である.頻度の高い肝細胞性黄疸および閉塞性黄疸では,抱合ビリルビンは腸管への排泄障害が高度になると血中に逆流して増加し,この結果,尿が濃染し便の色が薄くなる.
ついで,倦怠感,食欲不振などの急性肝細胞障害に伴う症状の有無を確認する.これらを認めなければ,肝内胆汁うっ滞および閉塞性黄疸を念頭において,薬物の服用(前者では薬物性が多い)や閉塞性黄疸の鑑別に必要な腹痛の有無,体重減少を確認する.
急性肝細胞障害の症状があれば,急性ウイルス肝炎,アルコール性肝炎,薬物性肝障害などの肝細胞障害型を念頭において,鑑別に必要な最近の海外渡航歴,不特定多数との性行為の有無,生ものの摂取,飲酒および薬物服用,肝疾患の家族歴などを聴取する.このほかにも必要な問診はあるが,診断の方向性のついた時点であらためて聴取する.
2)診察:
皮膚の黄染の程度から血清ビリルビン値はある程度,類推可能である.肝脾腫の有無,腹部腫瘤の触知,圧痛など,肝胆膵疾患に対する診察を行う.
3)血液検査:
総ビリルビン,直接ビリルビン,AST,ALT,LDH,ALP,γ-GTPが鑑別上,重要である.血液検査の結果が判明すれば,血清ビリルビン上昇が直接型,間接型どちらが優位かわかり,間接型優位であれば疾患はかなり限られる.直接型優位では,トランスアミナーゼ優位の上昇であれば肝細胞性黄疸を,胆道系酵素(ALPとγ-GTP)優位の上昇であれば肝内胆汁うっ滞と閉塞性黄疸を考え,鑑別診断を行う.肝酵素がすべて正常の場合は体質性黄疸を疑う.
4)画像診断:
閉塞性黄疸の有無の確認と鑑別診断に有用である.すぐ実施可能であれば,腹部超音波検査もしくは腹部造影CTを血液検査のための採血の前後に行うのがよい.黄疸以外の症状がみられない場合は閉塞性黄疸か肝内胆汁うっ滞の可能性が高く,画像診断は両者の鑑別に有用である.
5)各疾患の鑑別のポイント:
以下,各疾患の鑑別のポイントを表2-3-1の順序に従って説明する.
a)間接ビリルビン優位の黄疸:間接型優位では,血清LDH上昇があれば溶血性黄疸を疑い,網状赤血球の増加,尿中ウロビリノーゲンの強陽性,血清ハプトグロビン値の低下を確認する.溶血が否定されれば体質性黄疸が考えられる.
Gilbert症候群とCrigler-Najjar症候群は,ともにビリルビンUDP-グルクロン酸転位酵素(UGT1A1)の遺伝子異常で起こり,非溶血性遺伝性間接ビリルビン血症とでもよぶべき疾患である.臨床的には,総ビリルビン値6 mg/dL未満と以上で両者を区別する.【⇨9-10】
b)肝細胞性黄疸:急性ウイルス肝炎の頻度が高く,肝細胞障害型の薬物性肝障害がこれにつぐ.各種ウイルスマーカー,IgG,抗核抗体を調べる.これらの結果から,急性ウイルス肝炎(B型慢性肝炎の急性増悪も含めて),アルコール性肝炎,自己免疫性肝炎が否定されると,薬物性肝障害の可能性が高くなるので,健康食品も含めた薬物服用歴を詳細に聴取する.
黄疸のある肝硬変は非代償期や進行肝細胞癌合併例であり,画像診断が容易である. c)肝内胆汁うっ滞:急性は薬物による場合が多い.
反復性の肝内胆汁うっ滞はわが国ではまれな疾患である.良性反復性は黄疸の既往歴の確認と原因遺伝子FIC1
の遺伝子分析を行う.妊娠性のものは,他疾患の除外と出産後,速やかに軽快することから診断する. d)閉塞性黄疸:高度の黄疸は腫瘍(胆道癌,膵頭部癌,十二指腸乳頭部癌)によることが多く,胆石や胆道感染症では,黄疸の程度は概して軽度である.超音波検査に加えて造影CTを行う.MRCP(magnetic resonance cholangiopancreatography)も有用である.必要があれば治療もかねてERC(endoscopic retrograde cholangiopancreatography)を行う. e)直接ビリルビン優位の体質性黄疸:Dubin-Johnson症候群,Rotor症候群ともまれな疾患である.ICG試験が両者の鑑別に有用で,前者ではほぼ正常であるが,後者では高度に遅延する.Dubin-Johnson症候群については,尿中コプロポルフィリン分画を調べ,興味があれば原因遺伝子MRP2の分析を行う.[滝川 一]
出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「黄疸」の意味・わかりやすい解説
黄疸
おうだん
jaundice
icterus
血液中のビリルビン(胆汁色素)が異常に増加し、皮膚、粘膜、その他の組織が黄染された状態をいう。最初に眼球結膜の黄染を観るが、それは、その成分のなかのエラスチンがビリルビンに染まりやすく、白いために黄染を発見しやすいことによる。ビリルビンは赤血球内のヘモグロビン(血色素)の代謝産物で、細網内皮系細胞と肝細胞のなかでつくられ、胆汁中に含まれて排泄(はいせつ)される赤黄色の色素である。健常人での血清ビリルビン値は1デシリットル中に平均0.6ミリグラムで、1.0ミリグラムを超えることはない。したがって、血清ビリルビン値が1.0ミリグラム以上に増えることが黄疸(高ビリルビン血症)であるが、この値が2~3ミリグラム以上にならないと肉眼で見える黄疸(顕性黄疸)にはならない。1.0~2.0ミリグラムの間は潜在性黄疸である。ビリルビンは、肝細胞内でグルクロン酸抱合を受けた抱合型ビリルビンと、抱合を受けていない非抱合型ビリルビンとに分けられる。抱合型ビリルビンの多くはジアゾ試薬(スルファニル酸、塩酸、亜硝酸ナトリウム)を加えると、ただちに赤紫色を呈するので直接型ビリルビンとよばれ、一方、一部の抱合型ビリルビンと非抱合型ビリルビンはアルコール処理後に初めてジアゾ試薬で呈色するため間接型ビリルビンとよばれる。この直接型と間接型のビリルビンの血中での増え方を調べることにより、黄疸の原因を診断することができる。
(1)閉塞(へいそく)性黄疸 胆石や腫瘍(しゅよう)などで胆管の閉塞がおこり、胆管から腸管への胆汁の流出障害をおこす場合で、直接型ビリルビンが増える。
(2)肝細胞性黄疸 肝細胞の機能障害により胆汁分泌障害をおこす場合で、急性肝炎がその代表で、直接型と間接型ビリルビンの両方とも増える。
(3)溶血性黄疸 過剰の赤血球破壊によっておこる黄疸で、間接型ビリルビンが増加する。
(4)体質性黄疸 遺伝的素因によっておこる黄疸で、直接型ビリルビンが増えるデュビン‐ジョンソンDubin-Johnson症候群とローターRotor症候群、間接型ビリルビンが増えるジルベールGilbert症候群、クリグラー‐ナジャーCrigler-Najaar症候群などがある。
[太田康幸・恩地森一]
症状
皮膚や粘膜の黄染以外に、皮膚のかゆみ、徐脈、倦怠感(けんたいかん)、右季肋(きろく)部(右側の最下方にある肋骨(ろっこつ)部)の疼痛(とうつう)、発熱などである。診断は、肝機能検査、十二指腸ゾンデによる胆汁の検査、腹部超音波診断、CT、MRCP(Magnetic Resonance Cholangio Pancreatographyの略称で、MRIを用いた胆管膵管撮影のこと)、内視鏡的膵(すい)胆管造影、経皮経肝胆道造影法などで行われる。なお、柑橘(かんきつ)類をたくさん食べるとカロチンが血中に増え、とくに手のひらが橙黄(とうこう)色を呈するので、黄疸と鑑別する必要がある。
[太田康幸・恩地森一]
治療
原因・原病の除去と肝庇護(ひご)療法が行われる。肝庇護療法は安静、栄養、薬物療法からなる。安静は肝細胞性黄疸でとくに重視される。栄養は炭水化物とタンパク質を十分に与え、脂肪を制限し、アルコール性飲料は禁止する。高度の肝細胞性黄疸や頑固な肝内閉塞性黄疸に対しては、副腎(ふくじん)皮質ホルモンが奏効することがある。経過は原病によって差がある。
[太田康幸・恩地森一]
百科事典マイペディア 「黄疸」の意味・わかりやすい解説
黄疸【おうだん】
→関連項目肝不全|γ-GTP|交換輸血|高コレステロール血症|サイトメガロウイルス|新生児|新生児黄疸|胆汁色素|胆石症|胆道癌|バンチ病|ビタミン過剰症|未熟児|溶血性貧血|ワイル病
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
妊娠・子育て用語辞典 「黄疸」の解説
おうだん【黄疸】
出典 母子衛生研究会「赤ちゃん&子育てインフォ」指導/妊娠編:中林正雄(母子愛育会総合母子保健センター所長)、子育て編:渡辺博(帝京大学医学部附属溝口病院小児科科長)妊娠・子育て用語辞典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「黄疸」の意味・わかりやすい解説
黄疸
おうだん
jaundice; icterus
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
栄養・生化学辞典 「黄疸」の解説
黄疸
普及版 字通 「黄疸」の読み・字形・画数・意味
【黄疸】こうたん
字通「黄」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典(旧版)内の黄疸の言及
【核多角体病】より
…感染末期には組織が崩壊し,多角体が血液中に遊離する結果,血液は乳白色の膿汁状になる。このためカイコでは昔から膿病jaundiceと俗称されている。カイコ幼虫の病徴としては,まず体色が汚れたように変色し,つぎに体節間膜の部分が膨れ,落着きなくはい回る。…
【痒み】より
…ある種の全身疾患では皮膚に病変がなくてもかゆみがおこる。たとえば,肝臓から分泌された胆汁を十二指腸へ送る胆管が障害されておこる閉塞性黄疸の患者は激しいかゆみに悩まされる。このときのかゆみは胆汁の主要成分である胆汁酸が血液の中にたまったためのもので,イオン交換樹脂を内服して血液の胆汁酸濃度を下げてやると楽になる。…
【肝炎】より
…肝炎と名がつく肝臓の疾患には,ウイルス性肝炎(急性肝炎),劇症肝炎,慢性肝炎,ルポイド肝炎,アルコール性肝炎や薬物性肝炎などがある。肝炎は,(1)肝細胞の変性,壊死(肝細胞の破壊),(2)肝細胞の機能障害,(3)間葉系反応(細胞浸潤や繊維増生),(4)胆汁鬱滞(うつたい)(胆汁の排出障害,黄疸)などの組織変化の組合せで起こる。 ウイルス性肝炎は肝炎全体の約90%を占め,肝細胞の変性・壊死がおもな病変で,胆汁鬱滞は副次的な病変である。…
【肝機能検査】より
…この代謝路あるいは排出路の途中に障害が生じると,これらの物質が血中にたまってくる。黄疸はこのような状態の代表的なものである。ビリルビンの大部分は,寿命のつきた赤血球のヘモグロビンからつくられ,肝臓に送られてグルクロン酸と抱合され(これを抱合型または直接型ビリルビンといい,抱合前のビリルビンを非抱合型あるいは間接型ビリルビンという),水溶性となって胆汁とともに排出される。…
【肝腫大】より
…アルコール性脂肪肝とアルコール性肝硬変では,ほとんど肝腫大を伴うが,禁酒によって急速に正常の大きさに戻る。黄疸,腹水を伴う重症な非代償性肝硬変では,肝臓が触れられなくなり,肝臓の萎縮の程度は肝臓疾患の重症度にほぼ並行する。一般に肝臓疾患で黄疸を呈するとき,肝臓は腫大し,黄疸の軽減とともに肝臓は漸次正常の大きさに戻る。…
【肝臓】より
…原因としては,慢性肝炎からの移行が最も多いが,ほかにアルコールの過飲,高度の栄養障害,日本住血吸虫症,心臓病による長期の肝鬱血(うつけつ),原因不明のものなどがある。肝硬変(4)胆汁流出障害 肝臓内に胆汁の鬱滞を生じ,肝機能を障害するとともに,血液中のビリルビン量を高め,黄疸を発現させる。この病態は,毛細胆管から肝外胆道系に至る部位の種々の病気が原因となる。…
【肝不全】より
…後者は,進行した肝硬変や肝臓癌,肝臓内に長期間持続して胆汁が鬱滞(うつたい)することなどによって生じ,高度の肝臓萎縮と繊維化,およびその結果生じる肝血流障害,腫瘍性変化などが直接の原因となる。ともに症状として,全身消耗,皮膚や性器の異常,感染に対する抵抗力の低下,循環障害などを伴うが,黄疸の増強,腹水,出血傾向,肝性脳症と,高度の栄養障害が臨床的には重大な問題となる。
[肝臓の機能低下による種々の症状]
(1)黄疸 黄色色素のビリルビンが体内に蓄積して皮膚などを黄色に染める現象を黄疸という。…
【膵癌】より
…膵癌による死亡は,全癌中,男は第7位,女は第8位(1995)で,年々増加している。
[膵癌の症状]
膵頭部では,膵臓が肝臓内で作られた胆汁を導く胆管と接していることから,癌発生当初より胆管が閉塞されて黄疸(閉塞性黄疸)を起こす。膵体尾部癌では,黄疸が出現するのはかなり腫瘍が発育してからのことであり,随伴する膵炎や神経への浸潤などによる上腹部不快感ないしは腹痛~背部痛が初めの症状であることが多い。…
【胆石】より
…これは,〈しゃく〉〈さしこみ〉といわれる激痛で,苦悶状の顔貌で冷や汗をかき,前屈姿勢でうずくまるが,ときに苦痛のため七転八倒する。同時に軽度の黄疸がみられる場合もある。しかし一方,まったく痛痒を感じずに一生を過ごすこと(無症状胆石)もまれではない。…
※「黄疸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...