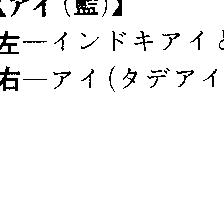アイ(その他表記)Chinese indigo
精選版 日本国語大辞典 「アイ」の意味・読み・例文・類語
あい
- 〘 感動詞 〙
- ① 呼ばれたときに返事をしたり、同意を表わしたりすることば。
- [初出の実例]「呉三桂(ごさんけい)、呉三桂(ごさんけい)とめさるる御声おとなしく、雪のみやまにうぐひすのはつねを聞きし思ひにて、あひ、あひ、あひ、とかうべをさげ」(出典:浄瑠璃・国性爺合戦(1715)四)
- ② 何か行動に移ろうとするときなどに、相手に注意を促したり、挨拶のことばの上に軽く添えたりして用いる語。
- [初出の実例]「アイとさし出す火入を取て」(出典:洒落本・弁蒙通人講釈(1780))
アイ
- 〘 名詞 〙 ( [英語] I, i ) 英語のアルファベットの第九字。
- ① ( I ) 化学で、ヨウ素を表わす記号。
- ② ( I ) 電流の強さを表わす記号。
- ③ ( i ) 数学で、二乗してマイナス1になる数、すなわちマイナス1の平方根の一つのこと。√-1とも書き、虚数単位とも呼ぶ。
- ④ ( I ) 英語で、島(Island)の略。
あい
- 〘 終助詞 〙 文末について、注意をうながしたり、念を押したりするのに用いる。
- [初出の実例]「タソ イルカ ai(アイ)」(出典:ロドリゲス日本大文典(1604‐08))
あいの補助注記
「ロドリゲス日本大文典」「コリャード日本文典」の説明では、「よ」「や」「やい」などと同類で、身分の高いものが低い者と話すときに用いるものとする。
あい
- 〘 名詞 〙 北北東の風。
- [初出の実例]「佐渡の方言に〈略〉北は正丑(まうし)より吹をあひ」(出典:随筆・烹雑の記(1811)前)
改訂新版 世界大百科事典 「アイ」の意味・わかりやすい解説
アイ (藍)
Chinese indigo
Polygonum tinctorium Lour.
濃青色,いわゆる藍色の染料を採るために栽培されるタデ科の一年草。インジゴと呼ばれる藍色の染料を採る植物には,アイのほかにリュウキュウアイStrobilanthes cusia O.Kuntze(キツネノマゴ科)やインドキアイ(コマツナギ属の数種,マメ科)などいくつかあるところから,とくにアイを区別してタデアイとも呼ぶ。東南アジア原産で,中国では古くから栽培された。日本へは飛鳥時代以前に中国から渡来したとされる。葉は先のとがった卵形で,柄は短く,全体が赤みを帯び黒ずんだ緑色となる。茎の高さは50~80cmほどになり,先端部が細かく枝分れをして,夏に紅または白色の小花を穂状に咲かせる。果実は長さ2mmほどの卵形で,黒褐色に熟す。葉の形や草丈などは品種により変異が大きい。栽培品種には小上粉(こじようこ),上粉百貫,百貫,小千本,縮藍(ちぢみあい)などがある。古くから日本各地で栽培されていたが,明治時代後半になるとインドキアイから採ったインジゴの輸入や,さらに合成インジゴの開発により栽培は激減した。しかし,色合いや木綿などでの色もちが比較的よいことなどから高級品を中心に需要は根強く,一部の地域で栽培が続けられてきた。主産地は徳島県である。2~3月に種子をまき,春に苗を畑に移す。徳島などでは前作物のムギの畝間に植える。開花直前の7月中ごろに茎葉を収穫する。さらに8月に再生した茎葉を収穫することもある。葉から染料を採る。収穫した葉を刻んで乾燥・堆積し,これに水をかけては切り返し,2~3ヵ月間発酵させると黒い腐葉土のようなものとなる。これを蒅(すくも)と呼び,臼に入れてつき固めて藍玉をつくる。この藍玉には2~10%の不溶性のインジゴが含まれ,これに木灰,石灰,ふすまを加えて発酵させると水溶性のインドキシルとなる。これが藍汁で,布を漬けて空気にさらすと酸化されてふたたびインジゴになり,染色される。またアイの葉や果実,藍玉は解熱・解毒などの薬用にもされた。
執筆者:星川 清親
染料としての藍
藍は人類が最も古く利用した青色染料である。古代エジプトの藍染布が残っており,古代ローマのindicum(顔料)の語源はIndia(インド)に由来するという。古代インドのサンスクリットで書かれた文献製法の記述がある。古代中国ではタデアイを栽培していたから独自に発達したと思われ,日本でもタデアイを用いるから,染色技術とともに大陸から渡来したとみなされる。古代日本ではタデアイの生葉をすりつぶして水を加え,かきまぜ,袋に入れて絞り,浸出液を染液として灰汁(あく)練りをした絹を染めた。《延喜式》に〈貲布(麻)一端,乾藍二斗,灰一斗,薪卅斤〉の記事があり,乾藍による藍建ても行われ,灰汁のアルカリによって日数をかけて発酵を助成し,麻布類を染めたことがわかる。平安の初期から中期にかけてはこの方法を続けたが,鎌倉期には木灰とともに石灰を用いてアルカリ性を強め藍菌の発酵を容易にするとともに,腐敗を防ぐことに成功した。藍建ては夏季の作業であったが,しだいに土間に藍壺を設置し,加熱によって四季を通じて藍建てを可能にし,室町期には紺屋(こうや)の発生をみた。近年では宮城県栗駒町(現,栗原市)の千葉アヤノ(1889-1980)が古来の藍建てを伝承し,その〈正藍染(しようあいぞめ)〉は1955年文化財に指定された。なお,緑染は藍と黄色染料との交染によって得られる。
→インジゴ
執筆者:新井 清
日本における栽培・流通の歴史
古代,中世
藍汁をもってする藍染は,染色のなかでも基本的なものとして,最も多く用いられたので,アイは百姓の屋敷地でよく栽培され,荘園によっては藍を年貢とする地もみられた。藍色には深藍,中藍,浅藍,白藍などの各種がみられ,《延喜式》にはすでに藍染のことがみえる。都市ではこの藍を供給するための座が結成され,なかでも藍生産地として著名であった京都の九条一帯には,15世紀半ば以降,九条寝藍座があって藍の売買を独占し,ときには付近の東寺を乾場としたため,寺と相論をひきおこした。なおこの藍汁をもって染色する業者を,藍屋・藍染屋・青屋・紺屋(こうや)などといった。
執筆者:川嶋 将生
近世
アイ(タデアイ)は江戸時代にはベニバナ・アサとともに〈三草〉の一つに数えられ,日本を代表する商品作物とされた。その栽培が本格化するのは,木綿生産が盛んとなる近世に入ってからである。江戸初期には山城,摂津,尾張,美濃などでの栽培が知られるが,その主産地は阿波であった。阿波ではすでに中世に藍作の存在が知られるが,とくに蜂須賀氏の入国後,藩の重要財源として蜂須賀氏の保護・奨励の下で発展した。1740年(元文5)の調査では藍作は〈北方(きたがた)〉(吉野川流域)全村に及び,吉野川中下流域の名東・名西・麻植・板野・阿波各郡を中心に藍作地帯を形成した。この地方は灌漑技術上の制約により稲作が半ば許容されず,かつ耕地の8割ちかくが藍作に好適な砂質土の畑地で占められていた関係もあって,農民生活のほとんどは藍作に依存していた。とくに18世紀以降,畿内の綿作の発展に対応して生産は急速に拡大し,1800年(寛政12)には作付け6500ha,藍玉生産高17.9万俵(約1.4万t)に達した。〈阿波藍〉は〈藍の種まき生えたら間引き,植えりゃ水取り土用刈り〉とうたわれたように,2月の播種(はしゆ)から7月の収穫まで除草,害虫駆除,施肥,炎天下の灌水作業と重労働の連続であった。収穫した〈葉藍〉は細刻して乾燥させ,〈藍粉成(あいこなし)〉といって連枷(からさお)で丹念に打ちほぐし,最後に葉と茎に分ける。こうして〈藍作人〉の手になる葉藍は,次に仲買人により〈藍師〉のもとに買い集められる。藍師は葉藍から染料の〈蒅(すくも)〉〈藍玉〉をつくる藍玉製造業者で,〈玉師〉ともいう。自宅に〈藍寝床〉と呼ぶ作業場をもつ。葉藍は9月ごろ藍寝床に仕込み,約3ヵ月間,前後20回にわたって給水とかくはん,保温を繰り返し,漸次発酵させて蒅に仕上げる。この作業工程では葉藍の発酵度合に応じた水加減がむずかしく,熟練技術を要した。そのため藍師はこの工程では〈水師〉と呼ばれる専門の職人を雇う場合が多かった。葉藍100貫目(約375kg)から50~60貫目(約188~225kg)の蒅が生成された。蒅はそのままでも売買されたが,たいていはさらに〈藍臼〉でつき固めて藍玉に加工(藍つき)された。できあがった藍玉は藍師・藍商により全国の売場先に積み出され,各地の〈紺屋〉に供給された。
こうして藍師は阿波藍の生産と流通を支配したが,1767年(明和4)には阿波の総藍師は1289人を数えた。なお藍師は在方では,藍作に欠くことのできない肥料(とくに干鰯(ほしか))や経営資金の前貸支配によって藍作人への経済的支配関係を強化し,質地地主として大土地を集積する藍師も出現した。他方,藍作人は藍作の展開に伴って,逆に商品経済の好餌となり経営が破綻し,貧窮化の様相を強めた。ところで徳島藩では阿波藍の利潤に注目し,1733年(享保18)には〈藍方御用場〉を新設し,葉藍取引税の徴収など葉藍専売制ともいうべき政策に着手した。しかし56年(宝暦6)の〈藍玉一揆〉(五社宮騒動。葉藍取引税,藍師株の撤廃を要求)により藩の支配は大きく後退し,藍方御用場も廃止された。その後66年藩主蜂須賀重喜は藩政改革の一環として〈藍方役場〉(翌年〈藍方代官所〉と改称)を再興,その監督下で城下市中に藍玉売場(のち〈藍大市〉として盛況)を開設した。また藍師層と提携して大坂市場の直接掌握を図るなど積極的な国益政策を展開し,さらに享和~天保期(1801-44)にかけて関東売場株,大坂ならびに畿内売場株の設定を皮切りにして31にのぼる全国売場株の成立をみた。全国の藍玉市場の独占支配をめざしたものであるが,他方この前後から関東の武州藍をはじめ尾張・美濃・山城・安芸・備前・因幡・長州・久留米・薩摩など各地でも〈地藍〉の生産が活発化した。広島・長州藩などでは〈藍座〉を設置し,他国藍の移入を禁じて自国藍の奨励と自給体制の確立を目ざしている。明治維新後も全国的な需要増により藍生産は拡大し,阿波藍は1903年に作付け1万5000ha,葉藍生産約2.2万tと史上最高を記録した。しかし,開国以来のインド藍の大量輸入や国内の染織業界の機械による工場生産への切替えは,しだいに阿波藍をはじめ国内藍の基盤をゆさぶった。これに対処して五代友厚の朝陽館による製藍法の改良事業などが興り,徳島でも五代友厚が1874年名東郡下に工場を設置し,精藍事業に着手した。さらに99年には長井長義の指導のもとに精藍伝習所が設置され,いわゆる長井製藍が始まった。しかし,この前後から人造藍(化学染料)がドイツから大量輸入されるに及び,国内藍・インド藍を駆逐して日本の市場を制圧した。ために阿波藍も明治30年代後半を境に以後急速に低落した。現在では郷土の伝統産業として,わずかな藍作農家が江戸時代以来の伝統的な藍作を継承し(1981年の栽培農家67戸,作付け14.1ha,葉藍生産42t),技術の保存発展と後継者の育成に努めている状況である。
執筆者:高橋 啓
アイ(間) (あい)
能一番のなかで狂言方の担当する役とその演技。間狂言(あいきようげん)とも,能間ともいう。もっとも一般的なかたちは,二場物の能で前ジテの退場後,後ジテの登場までのあいだをつなぐ役で,これに4種ある。〈語リ間〉(〈居語リ〉とも)は,シテの扮する役にまつわる物語を,ワキの問いに答えて語り聞かせるもので,能の梗概や主題を再説または補足・解説する効果をもつ。〈間語リ〉ともいい,《高砂》《八島》《井筒》《求塚》《熊坂》など多くの能にある。〈立シャベリ間〉は,名ノリ座で立ったまま,ワキと没交渉に独白で物語をする。《雷電》《春日竜神》など。〈末社間〉は,主として脇能で,末社の神が,シテの扮する神の徳をたたえたのち,三段ノ舞などを舞い,謡で留める。《嵐山》《賀茂》《竹生島》など。〈早打間〉は,事件の急を告げ知らせる役で,多く早鼓(はやつづみ)の囃子で登場する。《鉢木》《土蜘蛛》など。以上4種のほかに,一曲の最初に出て開演の糸口を与える〈口開(くちあけ)間〉が《鶴亀》《邯鄲》などに,ワキに名所を教える〈教エ間〉が《松風》《善知鳥(うとう)》などに,シテ・ワキ・ツレなどと交渉をもって筋の進展に加わる〈アシライ間〉が《安宅(あたか)》《道成寺》などにある。能の曲目によりアイの出ないものもあり,また,〈教エ間〉と〈語リ間〉というように一番の能に2種以上のアイが出るものもある。なお〈替(かえ)間〉といって,能に小書がつくなどして,ふだんとはちがう演出のアイを上演する場合がある。そのなかには《賀茂》のアイ《御田(おんだ)》,《嵐山》の《猿聟》,《輪蔵》の《鉢叩(はちたたき)》のように本狂言扱いするもの,《八島》の《那(奈)須》のように独立して語られるものもある。
→間狂言(あいのきょうげん)
執筆者:羽田 昶
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「アイ」の意味・わかりやすい解説
アイ(藍)
あい / 藍
Chinese indigo
[学] Persicaria tinctoria (Aiton) Spach
Polygonum tinctorium Lour.
タデ科(APG分類:タデ科)の一年草。東南アジア原産。日本には飛鳥(あすか)時代以前に中国から渡来したとされる。茎の高さは50~80センチメートル。夏に、枝先に紅色または白色の小花を穂状につける。種子は長さ2~3ミリメートル、熟すと黒色、卵形で3稜(りょう)がある。葉は先のとがった卵形で、全体が赤みを帯びて黒ずんだ緑色。葉から濃青色の染料インジゴをとるために栽培される。インジゴをとる植物にはリュウキュウアイ(キツネノマゴ科)、タイセイ(アブラナ科)、ナンバンコマツナギ(インドアイ)(マメ科)など数種あるところから本種をとくにタデアイとよぶこともある。日本には昔から「小上粉(こじょうこ)」「百貫(ひゃっかん)」「小千本(こせんぼん)」などの品種が栽培されたが、現在はおもに「小上粉」が栽培されている。これには赤花種と白花種があり、赤花種は早生で品質、収量がよく、白花種は晩生で耐病性が強く、葉の品質はもっとも優れている。
藍の産地として古くから京都、大阪の近郊が知られ、江戸時代中期以降は阿波(あわ)国(徳島県)が主産地となった。明治時代まではかなり広く栽培されていたが、インドアイからとったインジゴの輸入や、合成インジゴの開発で栽培は激減した。しかし、色合いや木綿などに染め付けて色もちがよいことなどから現在も高級品用に需要があり、徳島県など一部の地域で栽培が続いている。
漢方では果実・乾葉を解熱、解毒に用い、民間では藍実(らんじつ)の煎汁(せんじゅう)や、新鮮な藍葉をもんだ汁を毒虫の刺傷に外用した。
[星川清親 2020年12月11日]
百科事典マイペディア 「アイ」の意味・わかりやすい解説
アイ(藍)【アイ】
→関連項目草木染|紺絣|染色|染料|染料作物|徳島平野
アイ(間)【あい】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アイ」の意味・わかりやすい解説
アイ(藍)
アイ
Persicaria tinctoria (Polygonum tinctorium)
アイ
Ai
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル大辞泉プラス 「アイ」の解説
アイ〔洋楽〕
あい
アイ〔J-POP〕
世界大百科事典(旧版)内のアイの言及
【タイセイ(大青)】より
…中国原産の多年生のアブラナ科植物で,江南大青(こうなんたいせい)と呼ばれ,インジゴを含み,アイとともに染料に用いられたようである。江戸時代に中国から渡来して,幕府の薬園であった小石川植物園に植えられたという。タイセイ属Isatisはアジア,ヨーロッパ,アフリカから30種近くが報告されているが,分類のむずかしい仲間で,まだかなり混乱があるようである。 ホソバタイセイI.tinctoria L.(英名dyer’s‐woad)はヨーロッパや西南アジア原産の越年草で,タイセイと同様,染料に用いられた。…
【インジゴ】より
…マメ科のコマツナギ属Indigoferaの数種で,藍色の染料インジゴを採るために利用されていた植物の総称名,あるいは染料そのものの名称。小低木で,キアイ(木藍)とも呼ばれるが,それは藍染料をとる草本のアイ(タデアイ)と区別するためである。インドから東南アジア地域原産のナンバンアイI.tinctoria L.やI.sumatrana Gaertn.,I.arrecta Hochst.,熱帯アメリカ原産のナンバンコマツナギI.suffruticosa Mill.など10種近くある。…
【絵具】より
…一般的には顔料と展色剤を練り合わせて作った彩色材料をいう。広義には白墨,木炭などのように顔料を押し固めたり,そのまま使えるもろい単体をも含める。少なくとも化学工業製品が世にあふれる19世紀初頭までは,ごく少しの例外を除いて,いずれの時代にも絵具の顔料は共通している。天然鉱石粉,泥土,金属(銅,スズなど)のさび類,動・植物染料がそのおもなものである。絵具の種類,性質は展色剤の違いによる。展色剤は顔料を支持体の面に広くひろげるのを助けるとともに,両者の接着剤として作用する。…
【紺】より
…紺染を中心とする京都の染色は,代表的な名産としての地位を保ち続け,《田植草紙》にも〈そめてほされたこんや(紺屋)のかきのかたひら(柿帷子),(中略)かたやゑもんを京かうかき(紺搔)になろうた〉などと謡われて,その技術は諸国のものをはるかにしのぐものであった。アイ(藍)【川嶋 将生】。…
【染色】より
…染色は染料のもつ繊維材料への染着性を利用して,繊維等に染料を収・固着させる技術である。したがって繊維材料に顔料を固着材で固定する技術,たとえば顔料捺染(なつせん)などは染色には含めない。特別な例を除いて一般的には染料は水溶液として分子状に拡散したのち,染料の繊維に対してもつ特定の親和性(染着性)によって繊維上に収・固着される。染色は技術的には浸染と捺染に分けられるが,染色の原理として共通するのは,なんらかの形をとる水溶性(後述するように分散染料のような例外はある)と,染料分子またはイオンのもつ繊維高分子材料に対する親和性に基づく染着性である。…
【染料】より
…そのなかでとくに大きな意味をもつものは藍と茜(あかね)で,19世紀半ばまで天然染料の王座を占めていた。植物のアイの中に含まれる配糖体インジカンは,すりつぶすと酵素の作用により加水分解されインドキシルを生成する。これが空気酸化されて生成するインジゴをさらに発酵により還元させインジゴホワイト(白藍)とし,染色後,空気酸化して青い染色物を得るが,このような複雑な化学反応を含む技術を古代より人類がもっていたことは驚くべきことである。…
【タイセイ(大青)】より
…中国原産の多年生のアブラナ科植物で,江南大青(こうなんたいせい)と呼ばれ,インジゴを含み,アイとともに染料に用いられたようである。江戸時代に中国から渡来して,幕府の薬園であった小石川植物園に植えられたという。…
【徳島[市]】より
…城下町の建設は,軍事的には領内の要所阿波九城(一宮,岡崎,西条,川島,脇,大西,富岡,丹生(にう),鞆)に家老を配備する支城駐屯制と呼応してすすめられた。 領内経済の中核としての機能はアイ生産の発展につれて充足し,新町川沿いの船場には藍商の倉が並び,河口の津田は藍玉の積出しと大坂・堺からの物資の輸入港として繁栄した。城下町支配は仕置(家老)―町奉行(中老)―手代・同心―大年寄―町年寄―五人組―町人の系統で行われた。…
【徳島藩】より
…阿波国(徳島県)名東郡徳島に藩庁を置いた外様大藩。1585年(天正13)蜂須賀家政が豊臣秀吉によって阿波一国(17万6000石)に封ぜられたのに始まる。1600年(慶長5)関ヶ原の戦では家政の子至鎮(よししげ)が東軍に属し,戦後徳川家康からあらためて阿波一国を与えられた。03年板野郡の赤松則房旧領1万石と毛利兵橘旧領1000石を加え,大坂の陣後,15年(元和1)には淡路国7万石余が加増されて,25万7000石の藩領域が確定し,廃藩置県まで持続した。…
【難波】より
…江戸初期の難波村は,いまの西区の一部にもまたがる広い範囲であったが,市街の発展とともにしだいに南方に縮小され,現在は町名として中央区に難波・難波千日前,浪速区に難波中が残されているだけである。江戸時代にはアイ(藍)の栽培が盛んな農村地帯で,阿波藍の濃色用に対する薄色用の難波水藍として知られていた。また隣村木津のあたりまで5,6町の間に,難波市場と呼ばれる朝市が立ち,木津市場の延長をなした。…
【農業】より
…農業とは,土地を利用して作物の栽培または家畜の飼養を行い,人間にとって有用な生産物を生産する経済活動であり,そのような活動を行う産業である。人間に有用な農業生産物は食糧と一部の工業原料であるが,農業はそれらを,土,水,太陽エネルギーなどの自然力を利用して作物として生産し,また家畜を繁殖,肥育させることによってそれを生産する。このような農業の産業としての特質は,第1に,土地を基本的な生産手段とし,またその土地を商工業などの他産業と比較して,広い面積にわたって相対的に粗放に利用することであり,第2に,人間が長い年月をかけて育成し,または馴らしてきた高等動植物を対象(もしくは手段)とする,有機的生産であることである。…
【間狂言】より
…(1)能では,シテの中入のあと狂言方が出て演じる部分をいうが,能のアイ(間狂言)のみならず近世初頭の諸芸能では,たて物の芸能の間々に,種々の雑芸が併せて演じられた。それを〈アイの狂言〉または〈アイの物〉と呼ぶ。…
【能】より
…なお,ワキ方が1人も出ない能に《小袖曾我》などがあるが,シテ方が1人も出ない能というのは現行演目の中にはない。 狂言方は,元来狂言を演ずるのを専門とするが,能の中の人物でも,科白劇的な演技を必要とする役は狂言方が扮し,これをアイ(間狂言(あいきようげん)の意)と称する。現在能のアイには,《自然居士》や《船弁慶》のように筋の進行にかかわる重要な役もある。…
【アユ(鮎)】より
…1属1種(イラスト)。別名をアイ,年魚,香魚とも呼ばれる。おもに本州,四国,九州に分布するが,北海道南西部,朝鮮半島,台湾南部,中国南部にも分布する。…
※「アイ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...