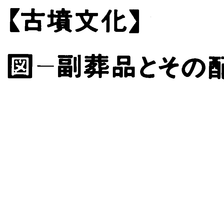改訂新版 世界大百科事典 「古墳文化」の意味・わかりやすい解説
古墳文化 (こふんぶんか)
古墳時代は弥生時代に継続する時代である。弥生時代に始まった農耕生活は,比較的はやく,日本の大部分の地域にひろがっていったが,さらに鍬,鎌などの農具に鉄の刃先を使用するようになるまでには,若干の年月が経過した。やがて鉄器の普及などによって耕地の拡張がさかんになり,生産量はしだいに増大していった。古墳時代は,こうした経済力の上昇が,ついにこの国土に国家としての統治形態の出現を導くにいたった時代である。また,国家的統一の進行にともなって,その統治機構のなかに組みこまれていった首長層と,一般の農民とのあいだにみる生活状態の差違が,大きくひらいてきた時代である。これを古墳時代と呼ぶのは,当時の首長層が,その墓として大規模な古墳を築く風習をもっていたからである。考古学の現状からいえば,この時代の文化の復原は,主として古墳の研究にもとづいていたので,それを時代の名称にも用いるようになった。しかし,その半面において,古墳のような大きな墓をもたなかった農民の生活については,まだ不明なままに残している点が多い。
日本において,古墳と総称する墳墓を作った期間は,少なくとも4世紀から7世紀にわたっている。したがって,古墳を作っていたという点からいえば,7世紀も古墳時代のうちにふくまれることになるが,このころになると,仏教文化が社会の上層部に強く浸透してくるので,古墳時代という観点から一面的にとらえることは不適当になる。
いろいろ問題はのこるのであるが,古墳時代をさらに細分して取り扱う場合には,前・中・後の3期に分けて,前期は4世紀代に,中期は5世紀代に,また後期は6世紀代に,それぞれその中心をおくものとみることができる。
古墳文化の発生
古墳時代という語を,厳密に古墳を作った時代という意味に限定すると,古墳時代は最初の古墳を作ったときから始まるといわねばならなくなる。しかし,そのときには,古墳を通じてみるような文化の状態は,すでに先行して発生していたはずである。はたしてそのような文化の状態は,どういう経過で発生したのであろうか。これには二つの考え方がある。その一つは,これをもっぱら古墳という墓制の発生の問題として説明しようとするもので,弥生時代の簡単な構造の墓が,しだいに複雑化し,規模を大きくしたことによって,古墳としての形式を備えるにいたったことを考える。たとえば,方形周溝墓や方形台状墓などのうちに,その過渡期の姿を見いだそうとするのであるが,ある墓制が古墳に先行し,かつ古墳の母体となったという証明には,なお困難が伴うのである。他の一つは,古墳が一般農民のものでなく,首長層のみの墓であるという観点から,首長層の発生の事情に原因を求めようとする。すなわち,共同体における司祭者としての任務をもっていた首長が,その地位の固定と権力の増大とによって,首長権の世襲に向かって一歩を踏み出したときに,古墳を作りうるような首長層が発生したと考えるのである。もちろん,古墳を作るためには,多数の労働力をその工事に動員できるような,首長層の存在のほかに,工事に必要な道具の用意があったことを考えねばならないが,これを可能にする鉄製の農工具は,古墳の発生期において,すでに広く普及していた。
日本が30の小国に分かれ,みなそのうちの一国である邪馬台の女王,卑弥呼の宗教的威力に服していたと,《魏志倭人伝》に伝える3世紀の状態は,おそらく古墳時代の直前の段階にあたるものであろう(邪馬台国)。当時の東アジアの大勢としては,漢以来の中国の圧力が強く朝鮮半島に及んでいて,朝鮮,日本における民族国家の発生を抑圧していた。魏の滅亡につづく中国勢力の北部朝鮮からの後退は,これらの地域に民族国家の生育を促進することになったが,古墳時代の日本もまた,同じ情勢のもとで進路を探求していたのである。少なくとも,古墳発生直前の日本は,東アジアにおける孤立した存在ではなく,中国のすすんだ文化に畏敬の念をもって対していた。その社会においては,弥生時代に輸入した漢の鏡が,神宝的な器物として,首長のあいだで伝世していたし,大量に将来した魏の鏡は,さらに大きな憧憬の的となった。しかし,国産品をもって新しい宝器を作る風習は,まだ顕著でなかった。
前期の古墳文化
古墳時代の前期においては,氏族の首長はまだ,かつての司祭者としての性格を,完全には脱却していなかったようである。古墳の副葬品から判断すると,彼らが所持していたもののなかには,実用的な武器や装身具のほかに,鏡や碧玉製腕飾や,特殊な形態の碧玉製品などの,宗教的・呪術的な用途をもったものを多くふくんでいる。鏡が宝器としての取扱いをうけていたことは,古く輸入した中国鏡を,数世紀にわたって伝世している事実からも推察できるが,中国鏡ばかりでなく,それを参考にして日本で作り始めた仿製鏡(ぼうせいきよう)も,新しく首長層の所有品のうちに加わるようになった。魏の時代に輸入した大量の三角縁神獣鏡は,畿内を中心として北九州から関東の一部にまで,広く国内に配布されるにいたった。仿製鏡の場合にも,とくに優秀な大型の製品の分布や,全体の分布の密度からみると,やはり畿内を中心として製作し,配布したものと考えることができる。
畿内を中心として配布されたもう一つの宝器として,鍬形石,石釧(いしくしろ),車輪石などの碧玉製腕飾がある。これらも,その原形はみな,弥生時代から使用していた貝輪にもとづいたものであるが,碧玉という新しい材料で作ることによって,特殊な発達の方向に向かい,ついには装身具として着装できないものにまで変形していったのである。この碧玉は,飾玉の材料としても大いに利用した。良質であるだけに入手の困難な硬玉のかわりに,碧玉で勾玉(まがたま)を作ることも始まったし,管玉(くだたま)にしても,しだいに大型のものを碧玉で作るようになった。そのほか,首長の威儀を整えるにふさわしい玉杖や,神秘な容器として用いたらしい合子(ごうす)なども,また同じ碧玉で作っていた。前期の宝器的な器物が,畿内を中心として分布していることは,古墳時代前期の文化が,畿内を中心として生育した事実を反映していることはいうまでもないが,それ以上に,畿内の政治権力が,その勢力下に加わった地方の首長に対する報償として,これらの器物を利用したことを想像したい。畿内の政権は,権威の象徴となりうるような,この種の宝器を自己の手で作る機構をすでにもち始めたわけである。《古事記》や《日本書紀》にみる鏡作部や玉作部が,はたして前期に成立していたか否かは確かでないが,少なくとも,この機構の実体は,それに近いものであったであろう。
畿内の政権が,鉄器の製作に対して,どのように優位な立場を占めていたかは,まだよくわからないが,全国的に鉄器生産量の急速な増加は注目すべきものがあった。とくに鉄器が,農工具のみでなく,武器として大いに発達している事実は,その原料になる鉄鉱が,国内で産出する砂鉄であっても,朝鮮南部などの外地から輸入した原鉱ないし鉄塊であっても,その配給機構が畿内政権による統治機構と一致しなければ,とうてい平和を保てなかったであろう。当時の鉄製武器には,刀,剣,槍,鏃などがあるが,1人の首長の死去に際して,大量の武器を惜しげもなく古墳に副葬している事実は,首長層の安全を守るために,よりおびただしい武器の蓄積を行っていたことを傍証する。攻撃武器のほかに,防御のための鉄製の甲(よろい)も,前期にすでに使用していたが,強いていえば,前期はまだ適当な甲の形式を選ぶ試作期の観があり,鉄製の冑(かぶと)はこの期の終りごろにその姿を現した。
農工具の方面では,鍬,鎌,なた,斧,鋸,やりがんな,のみ,錐,刀子など,種々の利器を鉄で作っていた。そのうち,鉄の刃先をつけた鍬が開墾や池溝の開掘に威力を発揮し,木の柄をつけた鉄鎌が稲の根刈りを可能にして,直播きから田植への道を開いたこと,鉄製木工具の完備が,角材の使用や枘(ほぞ)の活用を通じて,建築の形式を一変したことなどは,すでに前代に発足していたものがあるとしても,古墳時代前期の文化を理解するためには,見のがせないことである。ただし,このような一見農民的な道具が,古墳の副葬品のうちに加わっているのは,当時の首長も日常は農民的な生活を営んでいたという理由からではあるまい。これらの道具には,祭祀の実施に必要な建築用具としての用途を考えることができるからである。副葬品中に銛や釣針などの鉄製漁具をまじえた場合があるのも,祭祀の供物の調達に関連した理由があるかもしれない。
また技術の面からみると,前期の諸工芸は,すべて弥生時代以来の技術の,若干の向上にもとづいた製作であったといえる。かつて銅鐸を作りえた青銅の鋳造技術は,仿製鏡や銅鏃の製作にうけつがれて,ようやく白銅質の合金を使用する段階を迎えた。製品の繊細さを特色としていた攻玉技術は,大型の碧玉製品の製作に活用されて,石釧や合子の場合には,ろくろの応用にも成功するにいたった。各方面にわたる鉄器の製作は,すべて前代からの鍛造の方法により,鋳鉄の技術はまだ知られなかった。しかし,鍛鉄の技術の進歩は著しく,長大な直刀の製作に応じえたほか,複雑な曲面をもった鉄板を集めて,短甲を組み立てることもできたのである。ただ,短甲の鉄板のつづりあわせには,すべて革紐を用いていて,鋲留めの手法は前期には現れていない。
土器としては,赤色素焼(すやき)の土師器(はじき)を作っていたが,これも弥生土器の技術の継承である。別に,古墳の各部に飾りたてるために,土製品の一種として,埴輪を創案したのであるが,造形的な表現力には進歩をみるとしても,実質は土師器と同じ程度の窯業技術によるものであった。また,芸術的にすぐれた人馬の像などの埴輪は,前期にはまだ姿をみせず,家屋や器物をかたどったものにとどまっていた。
中期の古墳文化
古墳時代の中期においては,氏族の首長は政治的な支配者としての性格をはっきり示すようになった。副葬品に表れた変化をみると,いままでの宝器的な性格の器物にかわって,形式的な滑石製模造品が増加した。司祭者的首長が特定の宝器をもって神秘的な行事を主宰した段階から,衆人が模造の器物をささげて形式的な儀礼を繰り返す段階に進んだのである。そうして,首長自身の所有品としても,人びとの賛嘆の的となったにちがいない,装飾的な華麗なものが多くなった。金銀の使用の開始は,その最も顕著な一例である。またこうした儀礼の形式化は,その光景を人物埴輪の群像として再現する試みをも生むにいたった。
装身具に金を使うことは,冠帽,耳飾,帯金具および腰佩,履などの,一連の新しい服装の採用によって実現した。この文字どおり頭の上から足の先まで,金色燦然たる服装が,大陸の王族の風俗にならったものであることはいうまでもない。さらに威風を示す他の方法としては,甲冑にさえも金色うるわしく飾りたてたものを用いることが始まった。刀剣にも,環頭大刀という,金銀を使用する外装の形式が登場した。しかも各種の器物に金を飾りつける際に,金の使用量を少なくしながら,効果をかえない方法として,銅板の表面に鍍金を施したものを用いて,あたかも金製品であるかのようにみせる,金銅(こんどう)の技術も駆使するにいたった。ただし,こうした鍍金の技術のみでなく,金銀細工の製品のすべては,大陸の工人によって供給されたものであった。
4世紀末以来の,畿内政権を主導者とする南部朝鮮経営は,民族的勢力の結集のおくれた任那(加羅)をその影響下におくとともに,北方の高句麗に対抗しようとする百済や新羅に対しては,軍事的援助と政治的圧力とを与えていた。それらの地域からの貢物や工人の渡来は,日本に大陸系の新しい風俗や工芸を導入して,古墳時代の文化に大きな転換をもたらすことになったのである(帰化人)。南部朝鮮諸国から伝来したものは,たんなる華美な服装のみではなかった。たとえば乗馬の風習にしても,はじめは馬自身が輸入品であり,貴重なものであったから,特権者の乗用にあてるのみであり,馬具もまたそれにふさわしく金銅飾などの華美なものを選んだ。しかし朝鮮における戦闘は,騎兵をもつ軍隊を相手にすることが多かったので,たちまちにして乗馬は軍備の重要な一環となり,馬具もまた実戦に耐える堅牢なものを採用することになった。騎馬戦の完遂のためには,いままでの革綴じを鋲留めにあらためた短甲では,なお身体の自由を欠くことがわかった。そこでまた,大陸の武装にならって,短甲とは構成原理を異にする,鉄の小札(こざね)をつづりあわせた挂甲(けいこう)を採用することになった。それにつれて,攻撃武器としては弓矢の重要性が増大した。それも従来の,歩兵戦において傷口を大きくすることを目的とした,大型の鉄鏃にかわって,騎兵戦における刺貫の深さを目的とした,細身の鉄鏃を採用するようになった。
大陸から渡来した工人たちは,製陶術のうえにも著しい改革をもたらした。須恵器の製法の移入がそれである。ろくろを使用する量産的方法によって成形し,登窯(のぼりがま)を用いて1000℃以上の高火度で焼成した須恵器は,在来の土師器にくらべて,はるかに堅く吸水性の少ない,すぐれた土器であった。この新しい容器が,どの程度の範囲の人びとのあいだで,日常生活の需要を満たしたかは明らかでないが,中期末以後,古墳に納める供物の容器の大部分に,須恵器を用いるようになったことは事実である。機織や裁縫を特技とする工人の渡来も,記紀の伝えるところである。綾や錦の織成には,複雑な織機の操作を必要としたからであるが,呉服部(くれはとり)らが伝えた大陸風の衣服の形式が,人物埴輪の表現するところに一致するとすれば,その普及のはやさには驚くべきものがあった。
もっとも,大陸からの渡来人のすべてが,特殊な工芸技術の保持者であったわけではない。〈仁徳紀〉にみる茨田堤(まんたのつつみ)の築造にあたった新羅人などのなかには,土木技術者としての経験をかわれたものもあったであろう。支配者たる首長の絶大な権力をもってすれば,大量の人力を動員する大土木工事の実施も可能になったであろうが,さらに渡来人の技術的関与がその成功を助けたことを考えておきたい。応神陵,仁徳陵などの,驚くべき規模をもった人工の山陵を築造する風習も,同じ情勢のもとに出現したのである。地方の首長もまた,多少の時をおいて,この風習をまねるようになった。志幾(しき)の大県主が私宅の屋根に堅魚木(かつおぎ)をのせたのが,天皇の宮殿のほかには許されないことだとして,雄略天皇のとがめをうけたという物語は,中期における中央と地方との首長のあいだに生じた多くの抗争のうちでは,最も無邪気なエピソードである。
後期の古墳文化
古墳時代の後期になると,古墳に葬られる人びとの性格は,さらに一変した。後期の古墳が,近接した地域にきわめて数多く,群集して出現する傾向を示す点からいえば,もはやその被葬者を,従来のような,首長層などという,限定された人びとを意味する言葉で表すことは不適当であろう。それよりも,もっと広い範囲にわたった,官人層とでもいうべきグループであろう。
畿内政権が,約2世紀にわたって,南部朝鮮の政治に介入したことは,種々の副産物をのこした。その一つは,政府の機構と運営とが,大陸諸国にくらべておくれているのに気づいたことである。また内政外交のために文書を用いることが頻繁になってくると,文字を知っている人でなければできない仕事が増加してきた。こうして,律令国家にみるほどの整然とした官人制度はまだ実施できなかったとしても,官司における職務の分担はしだいに細分化し,記録の必要は文字に習熟した渡来人の進出を促した。これらの人びとのあいだに,新しく上下の秩序を立てるために,氏族の系譜を明らかにし,姓(かばね)の区別を整えることが必要になり,中国風の冠位の階制も採用するにいたった。官人による政治機構がしだいに成熟していったのである。これらの官人のあいだには,細かい身分の格差が成立しつつあったとしても,外部からみれば,一つの官人層を形成していたといえよう。その特権意識が古墳を作ることに表れたとすれば,規模が比較的小さくて,副葬品の豊かでない古墳が,きわめて多く出現する結果になったことも,おのずから理解できるであろう。
さらに,従来よりも広い範囲の人びとが古墳を作るには,古墳自身もまた,それに適したものに変化してくる必要があった。それを促したものは,横穴式石室という新しい墓室の構造の採用である。この大陸系統の墓室の形式は,すでに中期に北九州地方に伝来していたが,それが全国的な流行をみるためには,新しい土木技術の普及をまたねばならなかった。巨大な岩石を自由に運搬し,積み上げて,人びとがそのなかで葬儀を行えるような,広い空間をもった室を作る技術である。これには,〈てこ〉の原理のほかに,〈ろくろ〉などの機械を用いたものと考えられる。機械の利用によって,人力の浪費を節減しえたことと,横穴式石室の大きさから制約をうけて,墳丘の規模が小さくなってきたことは,いままでにくらべると,少なからず古墳を作りやすいものにかえたのである。同時に,一つの石室を家族墓として合葬の場所に用い始めたことが,いっそう古墳に葬られる人びとの範囲をひろげる結果になった。同じ横穴式石室を用いながら,それに階層の上位にあることを誇示しようと欲すれば,とくに巨石を選んで石室を構築するとか,加工の程度を高めた切石を使用するなど,方法はいくらも考えることができた。
しかし,いままでは,ごく限られた人びとが保持していた高い文化を,それよりも広い範囲の人びとも享受しうるものにするには,ある程度の妥協が必要であった。副葬品に表れた例でいえば,まず飾玉には,産地の限られた硬玉や碧玉よりも,瑪瑙(めのう)や水晶や,人工のガラスなどの,種々の材料を混用するようになった。これに金・銀を加えると,色彩の変化は著しく豊富になった。耳飾としては,細緻な技巧をこらした細金細工のかわりに,銅環に金・銀箔をかぶせて作る,実質的なものが普及した。腕輪にも,銀製品につぐものとして,銅製品を用いたり,それに5~6個の鈴をとりつける発案が人気を集めた。大刀(たち)の外装では,輸入品であった環頭大刀を国産化した変形様式をはじめとし,頭椎(かぶつち)大刀のような儀仗的な様式を生むとともに,鉄を多用した簡素で実用的な外装が多くなった。なお,倒卵形の〈つば〉の発生は,この両者を通じて,この時期にみる現象であった。乗馬の風習の普及に伴って,馬具にもいろいろの手法のものが現れた。鞍作部の家から仏師止利(鳥)が出たという伝えと一致するような,仏像などの金具と共通性をもった意匠も,馬具の一部に見いだすことができる。須恵器の使用もますます多くなったが,それは当初の朝鮮風の形態を失い,もはや純然たる国産工芸に転化している。一方では,おそらくは儀式的な食器と,一般の主食の調理に用いる鍋釜の類の製作を独占することによって,土師器も命脈を保っていた。
古墳に葬られる人びとの範囲はひろがっても,なお一般の農民には及ばなかったように,古墳時代を通じて,階級的な文化の偏差ははなはだしいものがあった。族長の邸宅をはじめ,倉庫などの特殊な建造物には,角材を用いた堅固な建築を作ったが,農民の住居は依然として竪穴式の賤(しず)の伏屋に終始した。牛馬の飼育は始まったとはいえ,まだ量においては十分でなかったし,これを農耕に使役するにはいたらなかった。新しい金銀珠玉も,はたして農民の装いを華やかに飾ることがあったであろうか。鍬や鎌をもっているところから,農夫を表したと考えてよい人物埴輪でも,金環を耳飾としてつけた姿に作っているのは,儀式に参列する人の仮装を写したものであろうか。
→飛鳥時代 →古墳 →弥生文化
執筆者:小林 行雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報