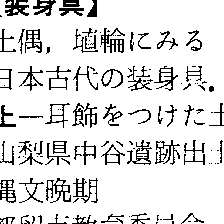精選版 日本国語大辞典 「装身具」の意味・読み・例文・類語
そうしん‐ぐサウシン‥【装身具】
- 〘 名詞 〙
- ① 飾りとして身体、衣服につける工芸品。櫛(くし)、簪(かんざし)、指輪、首飾り、腕輪、耳飾りなど。アクセサリー。
- [初出の実例]「タケ子が嫌疑をかけられた原因は、多くの衣裳や装身具を所持してゐたからであったのだと」(出典:女工哀史(1925)〈細井和喜蔵〉一三)
- ② 考古学で、身体を装飾する器具をいう。着装部位により頭飾り、耳飾り、腕飾りという。材料には石、骨、牙(きば)、貝、土、木などあらゆるものが使用された。旧石器時代に起源し、日本でも縄文時代以後多用された。呪的意義をもつものから始まったといわれる。
改訂新版 世界大百科事典 「装身具」の意味・わかりやすい解説
装身具 (そうしんぐ)
アクセサリーaccessory。広義の衣装に含まれ,一般には身体にまとう衣服以外のものをさす。首飾,耳飾,指輪,腕輪,ブローチ,アンクレット(足輪),髪飾などがあげられる。
呪術と装身
人間が装身具を身につける動機はさまざまであるが,地位・身分の表示と並んで最も強い動機は美的欲求の満足,美しく見せたいという装飾本能であろう。また装身具は,信仰や儀礼と分かちがたく結びついている。人々は神霊への畏敬の念を表し,神々と交流するために装身する。悪霊から身を守り,敵を威嚇する効果も同時にねらったのである。古代エジプトで,生命を奪う大気中の恐ろしい眼に魅入られないように,太陽神の聖眼やスカラベ(黄金虫)のペンダントを下げたことはよく知られている。いわゆる護符,魔よけとして身につけるもので,現代にも一部引き継がれている。未開社会ではとくに装身具の呪術性が高い。大形動物(ヒョウやライオン,イノシシなど)のきばや,タカラガイなどの貝類はとくに呪力が強いとされ,危険性の高い狩猟や戦争の際の衣服,また儀礼の衣服には欠かせないものとして,完全に衣服の一部になっている。ほとんど全裸に近い状態で暮らしている現存未開社会の原住民でも,首飾や腕輪その他の装身具を身につけているのが通例で,装身具が衣服以上のものになっていることがある。たとえばアフリカのマサイ族の既婚女性は,皮のスカート以外何も身にまとっていないが,既婚者の印であるシンチュウ製の耳飾をつけずに夫や他人の前に出ることはきわめて恥ずかしいこととされている。
装飾本能や宗教的動機は,装身具を身につけることによって,いわば〈変身〉をねらった自己異化行為といえる。代表的な装身である化粧は,いみじくも粧(よそお)って化けると書く。変身とは,古来俗なる状態から脱却してハレの場にのぞむための手段であった。入墨,身体変工,身体装飾,あるいは仮面をつけるといった行為は,すべて日常性からの離脱を目的とした行為であるといえる。
装身は変身願望を達成する,あるいは自己異化の行為である反面,自己同一化,すなわちアイデンティティの確立や保持を目的とした行為という側面をもつ。装身具は,入墨や化粧と同様,当該社会の全成員が直ちに理解しうる,性別,年齢,未既婚の別,帰属集団,身分や職業などを表示する社会的記号となっている。身分や権威のシンボルとしての装身具は,女性より男性において顕著であり,発達している。王冠や各種の勲章はそのよい例である。結婚指輪や婚約指輪は人生の段階を,各種のバッジ類は帰属集団を表す。また財産としての価値も高く,西アジアの遊牧民では,女性はしばしばすべてのもてる装身具を日常的に身につけ,また夫たちは収入があると,金や銀の装身具にかえて,娘や妻たちに与える。
執筆者:鍵谷 明子
装身具の歴史
身体や衣服を飾る習俗は,すでに後期旧石器時代に確認されている。ヨーロッパやシベリアで発見されているこの時期の埋葬例では,頭や首,手首,腕,腰,ひざ,足首のあたりから,動物の歯や骨や角,あるいは貝や石を加工,製作した装身具が発見されることがある。有機物を材料とした装身具もあったであろうが,腐朽してしまって残存していない。遺物として残存しているものには,海産の貝を加工したものが,海から500kmも離れた内陸で発見された例もある。装身具は,その起源がよく魔よけや招運のための呪具に求められるが,遠く運ばれた貝製の装身具からみて,特殊な色彩と形態とを身につけることによって,他のものからみずからを区別し,自己を顕示することが重要な機能であったと想像できる。これら旧石器時代の装身具では,男性のなかには女性と比較して,質量ともに優れたものをつけた例があることや,これまでに発見されている頭飾が,女性に限定されていることなどが注目されるが,一般に男女の性差はあまり顕著ではない。
日本の装身具
日本列島においても,多くの研究者が旧石器時代に相当するとみる先土器時代に属する墓から,石製の小玉(こだま)の出土が報告されており,縄文時代になると,耳飾,首飾,腕輪,腰飾,さらに実用品でもある櫛や簪(かんざし)などの髪飾がある。これら装身具をつける習俗は男女いずれにも認められるが,二枚貝腕輪や石製の玦状(けつじよう)耳飾(扁平な環状で下部に切れ目がある),あるいは骨製や土製の耳飾は女性着装例が圧倒的に多く,これらに対して,鹿角製腰飾は男性例が多いというように,男女による装身具の種類の差異が認められている。また,土製の耳飾は,多量に1ヵ所の遺跡から出土する事例もあって,女性用装身具として広く普及していたとみられるが,それ以外の装身具を着装したものは通常全被葬者のうちの10%以下ときわめて限定されている。したがって,獣類の犬歯に穿孔して製作した勾玉(まがたま)状装身具のように,獣のもつ力を付与することを願った呪具と解釈される例もあるが,着装者が10%以下という状況は,この時代の装身具の機能としては,彼らを他と一見して弁別させる社会的機能のほうが,より大きかったとみてよいであろう。
この機能は弥生時代の装身具でさらに強まる。青緑色の石材製の勾玉や管玉(くだたま)あるいは小玉には,新しくガラス製品が加わり,それまでの二枚貝製や木製の腕輪に代わって,青銅や鉄,ガラスの製品が出現する。これら特殊な新製品は,大陸から新しく渡来してきた技術によるものであり,着装者はそれを入手できた身分のものであったことを示している。あるいは,ゴホウラガイ(ゴホウラ)やイモガイなど,南海に産する美しい巻貝を加工した弥生時代の腕輪(釧(くしろ))は,古墳時代には碧玉などの美しい石材で模作され,その他の宝器類とあわせて,その保持者の権威を象徴するものであったと解釈されている。これら特殊な腕輪には,日常生活を送るには不自由であったかと思われるほど多数を着装した例があり,彼らが一般農民とはちがった,特殊な生活を送った人たちであったと想像されている。
特殊な身分を象徴する装身具は,5世紀大陸との交渉によってもたらされた事物の一部としても登場する。それらは,金や銀,あるいは金銅の製品で,頭を飾る冠から特殊な沓(くつ)形の履物まで,全身をきらびやかに飾りたてるものだった。ガラス製の玉類にも,従来みられなかった多様な色彩をもつものが出現する。これらの新式の装身具は,当時の朝鮮半島の墳墓の副葬品に共通するものが多く,その地域の支配者の権威を具現するものであった。この新しい波は,一部は農民にも及んでいる。農民を表現した埴輪には環状の耳飾を着装したものがあり,その実物である金環と呼ばれる耳飾が,後期の群集墳から出土することも少なくない。
日本の装身具の歴史は,古墳時代をもってひとまず終局する。高松塚古墳の壁画にみられる男女の群像は,装身具をつけていない。律令時代には,貴族官吏が官位に相当する衣服や帯をつけ,わずかにそれらを飾る程度にとどまる。以後,櫛や笄(こうがい),簪(かんざし),あるいは刀剣の拵(こしらえ)や印籠,さらにはタバコ入れなど,次章で見るように本来別の機能をもつ実用具に装飾を加えて身につけた。直接身につける装身具は,明治以降の新しいヨーロッパ文明の波及まで,日本では1000年以上にわたってほぼ欠如する時代が存続したのである。それは世界史上でもきわめて珍しい興味深い現象であったといえよう。
執筆者:田中 琢
日本的装身具の展開
飛鳥・奈良時代になると首飾,耳飾,腕輪など,直接身体につける装身具は姿を消し,衣服の付属品や髪飾が装身の主要な役割を担うようになったと思われる。その原因としては,上層階級の生活様式や服装が,大陸文化の影響を受けて大きく変化したことがあげられる。ことに仏教の伝来とともに,前代からの呪術性の強い装身具が少なくなり,階層や権威も服制・服飾によってシンボル化されるようになった。また染織技術の発達で豪華な衣服が作られ,装身具の必要を以前ほど感じさせなくしたであろう。新たに西域から中国を経てもたらされたものに佩飾(はいしよく)がある。腰に下げる飾で,真珠,玉,ガラスなどが用いられ,また飾りたてた刀子(とうす)なども下げられた。女性の礼装に際しては,中国の影響を受けた宝髻(ほうけい)と呼ばれる大きな髷(まげ)が結われ,そこに金属や玉類の簪をつけた。法隆寺献納宝物(東京国立博物館)には,奈良時代の銀製簪が伝えられている。
平安時代中期以降には,和風文化の隆盛に伴って衣服・装身具も和様化した。貴族の間では襲着(かさねぎ)の華美が競われ,装身具を用いる余地はさらに狭まる。女性は髷をやめて垂髪となり,髪飾も姿を消す。平安時代後期~末期の経塚から櫛が出土する例もあるが,もっぱら実用的な梳櫛(すきぐし)で,装飾を施したものは見られない。しかし服装の変化とともに各種の装身具や携帯品が用いられる。男性貴族は正装では石帯(せきたい)を着け,その垂飾に位を表す魚袋(ぎよたい)を下げた。またさまざまな装剣金具で飾られた飾太刀(かざたち)を帯び,緒も五彩の糸で刺繡した平緒などで華美を誇った。笏(しやく)や檜扇(ひおうぎ)なども正装の一部で,これらが貴族の装身具となる。女性ではことに懐紙をたたんだ畳紙(たとうがみ)や扇が装身具を兼ねた重要な必需品であった。このほか女性の外出・旅行に懸守(かけまもり)を首から下げることが流行した。神仏の護符を筒形の器に入れたもので,錦で包み金銀の飾も施された。大阪の四天王寺には平安末の懸守が七つ(ともに国宝)伝存している。この習慣はその後も長く受け継がれるが,しだいに簡素なものとなる。
鎌倉から室町にかけて武家中心の社会となると,服装も簡素化が求められ,小袖(こそで)が着用されるようになって装身具はほとんど使われなくなる。梳櫛,解櫛(ときぐし)など化粧道具も,まったくの実用品で装身具的な要素は見られない。ただ武士の間では,刀剣が太刀から打刀(うちがたな)へ変化し,鐔(つば)や鞘(さや)などの装飾がしだいに凝ったものとなる。江戸時代初期にはこうした刀装(拵)が,技術においても意匠においても頂点を迎える。
安土・桃山時代は,ポルトガル人をはじめ南蛮と呼ばれたヨーロッパ人が渡来し,服飾や甲冑にも南蛮趣味が流行した。その中で装身具として顕著なものはロザリオである。キリスト教徒でない者までが首にロザリオをかけ,腰に十字架を下げた。《松浦屛風》や《歌舞伎草紙》などの初期風俗画にこうした服飾が描かれている。江戸時代の武士の必携品となる印籠も,輸入された印章容器の模造にはじまる。やがて印籠のひもを締める付属品は水晶やサンゴ,象牙,ガラスなどで趣向が凝らされ,帯につる際の留具である根付(ねつけ)とともに,精巧な工芸品として発達した。また印籠そのものも,蒔絵(まきえ)や象嵌などさまざまな技巧で作られた。町人の間では印籠にかわるものとしてタバコ入れが流行する。これも革,金属,織物などで贅(ぜい)をつくして作られた。なお煙管(きせる)も桃山時代にタバコとともに伝来して,装身具の一つとなるが,ことに江戸時代の初期には大名の間で流行し,装飾の華美が競われた。
女性の髪は江戸時代初期から再び結び髪となり,中期以降は技巧を凝らした女髷が発達する。こうしたさまざまな髪形にあわせて,櫛,笄,簪などが作られ,なかでも蒔絵や象嵌,透彫などを施した飾櫛が重用された。笄も変わったものでは,俗に〈鶴の足〉と呼ばれる鳥の脛骨に蒔絵を施したものまで現れ,櫛と同じ意匠で統一した組物も作られるなど,豪華なものが用いられている。江戸時代末期にはいっそう派手な髷や鬢(びん)が結われ,櫛や笄も大型となり模様も多彩をきわめるようになった。簪は材質・種類ともに豊富で,歩くたびに揺れる〈びらびら簪〉には傑作が多い。なお江戸中期から後期の簪には,胴の先端に耳かきのついたものが多いのが特徴である。このほか江戸時代を通じて武家の女性が懐中に必ず携えたものに筥迫(はこせこ)がある。紙入れの一種であるが,鏡や簪などが入れられることもあった。
明治時代にも江戸時代以来の装身具は受け継がれたが,西洋の文物の流入と生活様式の欧風化によって,男女ともにさまざまな変化が起こった。洋髪がとり入れられるとともに,大きなリボンや,宝石類を使ったりモダンなデザインを施したものなど,髪飾も変化したが,洋髪・洋装だけでなく,従来の髪形にもこうした髪飾がとり入れられることがあった。またネックレスや指輪も普及し,これらも和装の中でも使用されるようになる。一方,着物では帯や襟などの部分にアクセントをおき,帯揚,帯締,半襟,羽織紐などが,装身具としてもくふうされ,ことに絽(ろ)や縮緬(ちりめん)地に刺繡を施した半襟は,明治から大正にかけて普及し,そのデザインが流行の指標とさえなった。男性では洋装化がすすみ,印籠やタバコ入れなどはすたれ,新たに時計,指輪,ステッキ,洋傘,帽子などが,装身具としての位置を占めるようになった。第2次世界大戦後になって,装身具はますます多様化し,また男女間の差異も見られなくなりつつあるが,現在用いられている装身具は,帽子,スカーフ,バッグなどのように実用性の強いものと,ネックレス,ブローチなどのように装飾性の強いものに大別することができる。
執筆者:橋本 澄子
ヨーロッパ
青銅器時代に入ると,青銅や金,銀の加工技術も発達し,アンクレットやブローチ,胸飾などが作られた。シュメールのウルでは,女王シュブ・アドの墓に多量に副葬された装身具が見られる。管状のビーズで覆われた胸飾,金,銀,瑪瑙(めのう),ラピスラズリの髪飾・首飾などで,女王の遺骸が飾られていた。一方,古代エジプト人は,金属に宝石をはめこんだ幅広のネックレス,七宝やビーズの腕輪などを愛用している。またスカラベのペンダントや耳飾も,王や貴族の聖性,権威を示す装身具として発達した。ラメセス2世像は耳朶に穴をあけて耳飾をつけており,ツタンカーメンの墓からは,黄金製の耳飾が出土している。ヨーロッパでも青銅器時代以降,金や銀を用いた精巧な装身具が作られたが,古代ギリシアではイアリングや腕輪のほか,ブローチが発達した。ブローチは上衣の留具であるピンから起こったとされ,貝を模した黄金製のものや,浮彫のカメオも用いられた。古代ローマに至ってさらにこの風は広がり,宝石,貴石,ガラス,貝製などのカメオが作られた。中世になると,衣服に金糸刺繡をしたり,宝石を縫いつける習慣が流行したが,これらは,城を奪われるような非常時に,軍資金に代えるためだったり,また勇敢な騎士に与えられた金の指輪や腕輪は,地金の価値と合わせて尊重されたり,装身具が単に身を飾るだけでなく,一方で財産として,貨幣としての価値も持つようになった。15~16世紀は男女ともに装身具の最盛期で,ペンダント時計や,イアリング,ネックレス,髪飾などが好まれ,サファイア,ルビー,真珠などの宝石も好んで用いられた。ルターは女性を〈装飾にあきることのない狂人〉と呼んだが,夜寝るときにも装飾用手袋を脱がなかったフランス王アンリ3世,また片時も手袋を放さなかったモンテーニュのような男性もいた。当時の貴婦人たちは,ドレスに宝石や装身具を飾りすぎて着用できないほどで,所持するだけで満足していた。また,袖にスリットを入れて対照色の裏地を見せる16~17世紀の流行から,宝石のボタンが装身具として登場し,18世紀に最盛期をむかえた。女性の髪形の変化とともに,リボンや造花の髪飾が流行し,レース,リボン,羽毛で飾りたてた帽子が,服飾の大きな要素となる。名画をミニアチュール風に飾り縫いしたボタンも登場した。18世紀のロココ時代の人々は,小箱,小道具,かぎタバコ入れ,裁縫箱,化粧品入れなどにもさまざまな装飾を施し,身の回りの装身具とした。金地に彫刻したペンダントのつまようじさえ現れている。このような装身具は,フランス革命以後男性の服装からは消え,女性のものも実用性を強めるようになった。1830年代ロマン主義が広まるようになって装飾性が強調されたあと,また間をおいて流行がよみがえっている。19世紀末からは,宝石の大きさや素材の価値よりも,その芸術性と趣味のよさが重んじられるようになった。
現代における装身具は,その基に18世紀ロココ時代の装飾性をおいており,1830年ごろに起こったロマンティック時代,1890年代からのギブソン・ガールgibson girlの時代,そして1947年のニュールックなどは,すべてロココ時代のリバイバルといえる。装身具の機能性と装飾性は,本来相矛盾するものではないが,両者をどう調和させるかは,現代美術における課題の一つとなっている。
→宝石
執筆者:飯塚 信雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「装身具」の意味・わかりやすい解説
装身具
そうしんぐ
装飾のために身体や衣服につける服飾付属品。英語のパーソナル・オーナメントpersonal ornament(または単にオーナメント)にあたり、こまごまとした小さい装身具はトリンケットtrinketとよばれる。通常、装身具の語はアクセサリーと同義に用いられることが多いが、厳密にはアクセサリーの一分類である。
一般に装身具は、実用よりも装飾を目的とし、服装の一部ではあるが不可欠なものではなく、それがあることによって服装をより効果的により完璧(かんぺき)にするものである。たとえばブローチ、ピン、ネックレス、ブレスレット、イヤリング、指輪、髪飾り、コサージなどの、装飾性の強い服飾付属品(服飾工芸品)をさす。広義のアクセサリーには、これら装身具のほかに、靴、手袋、ハンドバッグ、帽子、パラソルなどの実用を目的としている服飾付属品と、さらにリボン、ブレード、ビーズ、飾りボタンなどの手芸的なトリミングが含まれる。しかし一般にアクセサリーの語は、装身具のみを、あるいは装身具とファッション性の強い装飾的な服飾小物類(ベルト、スカーフ、眼鏡、キーホールダー、ライターなど)をさすのが習わしとなっている。原始的社会でしばしば用いられる足輪、首輪、鼻輪などは、その集団によっては装飾以外に特別の意味合いをもつものもあるが、一般にはこれらも装身具として考えられる。
[平野裕子]
ジュエリー
装身具のうち、宝石や貴金属製のものをとくにジュエリーjewel(le)ry、フランス語ではビジューbijou、ドイツ語ではエーデルシュタインEdelsteineとよんで、ほかのものと区別している。宝飾工芸品すなわち宝飾品の装身具である。また宝石を主体とした超高級な宝飾品の装身具はハイ・ジュエリーとよばれている。コスチューム・ジュエリーは模造装身具のことで、本物のジュエリーに対して、模造品のガラスや準宝石をはめ込んだ卑金属製の安価な装身具をさす。もともとこれは舞台衣装や歴史服などの特殊なコスチュームにあわせたイミテーションであった。第一次世界大戦後ジュエリーの価値感が大きく変化し、宝石や貴金属としての価値よりも、色や形などの外観の美しさが重視され、劇的な雰囲気、斬新(ざんしん)な感覚、奇抜な着想などの表現として、今日まで独特の用い方がされてきた。なお、コスチューム・ジュエリーをモードの世界に持ち込んだのは、1950年代のシャネルで、なんの変哲もないツィード地のスーツやジャージーのプルオーバーなどに、高価な宝石も模造宝石も安物のガラス玉も全部いっしょにした何連ものネックレスを用いたのが始まりである。
[平野裕子]
歴史
装身具の多くは衣服に先行するものとされ、原始宗教や呪術(じゅじゅつ)に始まって、しだいに身体装飾として発展したものと考えられる。今日的な装身具の基本の型は、すでにほとんどが先史時代に確立していた。初期の段階では、おそらく鳥獣、魚貝、植物など、身を飾るにふさわしい、ありとあらゆるものが装身具として役だっていたに違いない。ついで玉石が登場し、玉石と金属類の無機物による装身が行われ、工芸品としての装身具が誕生した。新石器時代から青銅器時代への移行は、ある意味で装身具の黄金期へ向かうものであり、装身具は急速な発展をみせるようになる。歴史時代に入ってからの装身具は、素材、技法の面でいちだんの発展を示す一方、複雑さや入念さが増してくる。長い歴史のなかで、それぞれの時代の服型の影響を受けながら、さまざまな装飾デザインが登場した。19世紀イギリスのビクトリア朝でその装飾は最高潮に達し、飽和状態ともいえる装飾過多の時代を迎える。繊細で凝ったデザインのジュエリーがもてはやされ、この傾向は20世紀のアール・デコの時代まで続く。第一次大戦後、価値の平等化はジュエリーにも及び、これまでの財産としての価値は軽視され、装身具はコスチューム・ジュエリーの時代に移行する。単純化された服型が確立すると、装身具はその従属的な価値がより重視されるようになり、素材、デザイン、技法はますます多様化し今日に至っている。
[平野裕子]
今日の装身具
個性の表現にもっとも重きを置き、自分の感覚にあったデザインや色を選ぶことが装身具の大きな魅力となっている。目的にあわせて変化をもたせることが一つの課題で、従来の装いにとらわれない新しい装い方が試みられている。クールな現代感覚の表現として、プラスチックや金属のシンプルなものをさりげなく用いたり、ポップ調のカラフルなものを楽しく、あるいは象牙(ぞうげ)やウッドなどの自然素材をしゃれた感じに用いたりする。新しい傾向としては、衣服とトータルなイメージでつくられたデザイナーズ・ブランドの装身具が売られている。一般に野性的でビッグなもの、繊細で凝ったデザインのロマンチックなもの、新しい素材の超モダンな装身具などが流行の主流となっている。
[平野裕子]
民族学からみた装身具
装身具の大半は、護身用呪具(じゅぐ)として衣服に先行して生まれた。すなわち、古代あるいは原始的社会では、病気、けが、死などの災禍は、悪霊が人体に侵入しておこすものと考え、その防止のため、侵入口とみなされる人体の穴の部分や通路に、侵入阻止の呪具をつけた。耳飾り、鼻飾り、首飾りがそれである。これは、今日的にいえば予防にあたる。次に、人体各部にはそこを管理する生霊がいるのだが、これら生霊たちは仕事を忘れ体外に遊びに出て、その留守中に悪霊が入り込み病禍をおこす、と考える。そこで、生霊を体内に閉じ込め身体管理に専念させようと、身体の主要部位を紐(ひも)で縛ったり輪をかけた。これが、鉢巻、胸飾り、腰飾り、腕紐または腕輪、指輪、足輪であり、今日的にいえば健康管理にあたる。超自然力に接するとき人体はねらわれやすく危険なので、このような呪具を、とくに祭礼の日には身体の各所につけた。こうして装身具の原型ができた。
しかし、それでも人間は、けが、病気、死を防ぎきれない。そこで護身の呪具の効力を強化することを考えた。すなわち、この世で貴重なものを材料にしたり、装飾化して目だつようにしたり、ライオンのたてがみや動物の角(つの)や鳥の羽などをつけ自分の戦闘力を強化しようとした。しかし、それらを十分にできる者たちは、その社会の支配層の人々に限られるので、高級で豪華な呪具はステータス・シンボルにもなっていく。すなわち、このように呪具は、財宝的なものを材料に使用したり豪華な装飾を施すことによって、装身具となる。呪具から装身具への転換でもある。
一方、単に実用品にすぎなかったものにも、材料を選び装飾を施すことによって装身具となったものがある。たとえば、櫛(くし)、かんざし、杖(つえ)、御守り入れケースなどである。
要するに、呪具あるいは実用品に財宝的あるいは装飾的要素が加わり、りっぱさや美しさが重視されることにより、装身具は生まれた。
[深作光貞]
諸民族の装身具
オセアニアでは、犬やブタの牙(きば)、イルカやコウモリの歯が珍重され、首飾りにする。貝殻からつくるビーズや美しい木の実も数珠(じゅず)つなぎにして、首に巻いたり胴を飾り巻いたりする。ニューギニアでは、ゴクラクチョウやヒクイドリの美しい羽根で頭を飾りたて、カンガルーのしっぽを胸に垂らし下げ、鼻には骨を棒状に差し渡したり、彫刻した貝を飾ったりする。胸には大きな貝をぶら下げる。
アフリカでは、タカラガイとビーズが多用される。ただし、オセアニアと違ってビーズはガラス製なので、青色のものもある。頭髪飾り、鉢巻、耳飾り、鼻飾り、首飾り、腕飾り、腰飾り、足飾り、襷(たすき)掛け式の胴飾りなど、木の実も混ぜて身体を飾りたてるが、なかでもマサイ人の女性の三段式円盤形の巨大な首飾りと、ドゴン人のタカラガイ製の仮面とがとくに圧巻である。蜻蛉玉(とんぼだま)も愛用される。
一方、文明の発祥地といわれるメソポタミアのウルク期の遺跡からは、紅玉髄(こうぎょくずい)、トルコ玉、水晶、めのう、真珠などの玉石類や、紀元前2000年のシエプ・アド王妃の墓から黄金の花冠などが発掘されている。古代エジプトになると、頭上に高く彫刻的装飾がそそり立つ冠と、金や陶器やビーズやカーネリアンなどの色石を豪華に使ったよだれ掛け状の大きな首飾りが印象的である。これらは、ツタンカーメン王の玉座背面の図柄で、われわれにもなじみ深い。
古代インドでは、ヒンドゥー教の女神たちの彫刻や絵画でもわかるように、頭も鼻も耳も首も胸も腰も腕も足も、やたらに黄金や玉石で飾りたてている。特異なのは、片方の鼻翼に穴をあけ黄金か玉石をはめ込むことであろう。中国では、3000年前の殷(いん)代に白玉や青玉製の首飾りがあるが、周代になると、めのうなどの玉石を使った腰飾り(佩玉(はいぎょく))が盛んになり、秦(しん)・漢代になると、銅に金銀、玉、ガラス、緑松石などをちりばめた豪華なバックル(帯鉤(たいこう))が、佩玉にかわって流行し、玉石・金銀を使用した髪飾り、耳飾り、腕輪、指輪などの装身具が愛用された。それ以後、中国では耳飾りは姿を消すが、満洲民族出身の清(しん)朝で復活することが注目される。
日本では、縄文時代に竹製や骨製の櫛、土製の小玉あるいは環状の耳飾り、貝製の腕輪、貝片や骨角や石に穴をあけて吊(つ)るす垂れ飾り(首飾りか腰飾りかは不明)などの装身具があった。弥生(やよい)時代になると、大陸との交通も進み、勾玉(まがたま)や管玉(くだたま)などの玉石製の首飾り、金銅の冠や耳飾りや金の指輪も現れる。佩飾や玉杖(ぎょくじょう)も現れる。古墳時代になると、翡翠(ひすい)、めのう、ガラスなどの美しい色彩の装身具が出現した。
以上、いわゆる未開社会や古代社会の装身具をみてきたが、文化の発達とともに装身具も変化していくことは、いうまでもない。鼻飾りのように廃れてしまったものもあるが、かつて呪具をつけたところにいまでも装身具をつけていることは興味深い。
[深作光貞]
『宮本悦也著『アクセサリーの流行学』(1981・流行学研究所)』▽『北山晴一著『おしゃれと権力』(1985・三省堂)』
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「装身具」の意味・わかりやすい解説
装身具
そうしんぐ
jewelry; ornament
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の装身具の言及
【装飾】より
…人体の装飾は膚に直接加工される〈入墨〉や〈つけほくろ〉のほかに,部分に取り付けられる髪飾(冠,鉢巻,櫛,簪(かんざし),笄(こうがい)),イアリング,首飾,腕輪,指輪などがあり,民族によっては鼻飾や足飾をつける風習をもつものがある。これらの装身具は帯留(おびどめ)やスカーフや各種のアクセサリーとともに〈服飾〉という語の中に含められている。広い空間の装飾としては住居内部や墓室の室内装飾,劇場内の舞台装飾,ショーウィンドーを含む店舗装飾,植込みや泉池の間に天然の石や人工品(灯籠(とうろう),彫像,腰掛の類)を配置する庭園装飾,街路を美化するための街頭装飾(広場の花壇,彫像,並木,モザイク舗装,広告塔)などが数えられる。…
※「装身具」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...