翻訳|fighter
精選版 日本国語大辞典 「戦闘機」の意味・読み・例文・類語
せんとう‐き【戦闘機】
- 〘 名詞 〙 軍用機の一種。敵機・敵艦への攻撃、味方の爆撃機、輸送機などの護衛、地上戦闘の援護および対地攻撃などの任務にあたる、比較的小型で高速の機種。
- [初出の実例]「戦闘機に同乗し」(出典:イタリアの歌(1936)〈川端康成〉)
改訂新版 世界大百科事典 「戦闘機」の意味・わかりやすい解説
戦闘機 (せんとうき)
fighter
敵の飛行機を撃墜することをおもな目的とする,比較的小型,高速で,運動性のよい軍用機。地上および海上の目標を攻撃する能力をあわせ持つ機種が多い。
分類
戦闘機はほぼ以下のように分類される。(1)要撃戦闘機fighter interceptor 自国の領域に侵入してくる敵機を迎え撃つことを目的とする戦闘機。上昇性能,速度,武装が重視される。局地戦闘機,防空戦闘機もほぼ同じものである。(2)戦闘爆撃機fighter bomber 地上および海上の目標を攻撃することを目的とする戦闘機。爆撃計算機を装備し,対地・対艦ミサイル,精密誘導兵器,爆弾等を外部に搭載,通常低空を高速で飛んで攻撃を行う。長い航続距離と大搭載量が要求される。(3)多用途戦闘機multirole fighter 敵戦闘機との戦闘,要撃,対地攻撃等多くの任務を一機種で遂行できるよう設計された戦闘機。それぞれの任務によって要求される性能,機能が若干違うので,ある妥協点で設計される。任務に応じ搭載電子機器を変えることもある。(4)制空戦闘機air superiority fighter 敵の戦闘機を撃墜して航空優勢を確保することをおもな目的とする戦闘機。高い運動性と,射撃管制装置の探知範囲内に入った敵機であれば,それが上下左右どこにあってもどの方向に飛んでいても攻撃できる能力が要求される。(5)全天候戦闘機all-weather fighter レーダーとコンピューターを組み合わせた射撃管制装置および航法装置を装備し,目視ができない夜間や悪天候下においても目標に接近し,これを発見,識別し,武器を発射する能力を持つ戦闘機。(6)艦上戦闘機carrier-based fighter 空母に積載される戦闘機。狭い格納庫に収納するため,大きさに制限を受け,主翼等を折り畳めるようにした機体が多い。着艦のためのフックを持つ。
変遷
戦闘機が出現したのは第1次大戦中である。軍用機は当初偵察などに使用されていたが,相手機の侵入を防ぐため,飛行機の搭乗員が機関銃を携行し射撃をするようになり,やがて機関銃を固定装備した専用の戦闘機が出現した。当時の典型的な戦闘機は,複葉,羽布張りのプロペラ機で,最高速度は200km/h程度であった。逃げ隠れのできない空中での戦闘では,戦闘機自身の性能,武装が勝敗を左右することが大きいため,各国は大戦中もそれ以後も競って高性能戦闘機の開発を進め,現代に至っている。
第2次大戦前には,ほとんどが単葉,全金属製となり,最高速度は570km/h程度まで向上した。他の軍用機の性能も向上し,陸上および海上の戦闘において,飛行機による攻撃力,ひいては航空優勢が勝利の鍵を握るようになった。第2次大戦中の発展は目覚ましく,末期には最高速度はプロペラ機の限界の700km/hに達した。プロペラにかわる原動機としてジェットエンジンが有望であることは第2次大戦前から認められており,大戦の後半にはドイツ,イギリスなどで若干のジェット戦闘機が作られたが,主流になるには至らず,大戦後1945年にアメリカのロッキードP80が,やや遅れてソ連のミコヤンMiG(ミグ)15が就役し,本格的なジェット戦闘機の時代となった。朝鮮戦争におけるこの両機種間の戦闘が,ジェット戦闘機どうしの初の戦闘である。この当時,最高速度は1100km/h程度で,武装は機関砲を主とし,目標との距離および自機の姿勢に応じ自動的に照準点を指示する照準器を持っていた。主として目視可能な状態での空対空戦闘に用いられたが,一部対地攻撃にも使用された。
1955年アメリカのノースアメリカンF100が実用機として初めて水平飛行で音速を突破し,超音速戦闘機の時代に入った。音速を超えるのは容易でなかったが,いったん超えると1950年代後半には,マッハ2クラスの戦闘機が続々と実用化された(マッハとは音速の倍数で示す速度の単位。外気温0℃の場合,マッハ1は1193km/hに相当する)。この時期は電子機器の発達も著しく,戦闘機にレーダーを装備することが一般化し,全天候戦闘機が実用化された。また1950年代からは空対空ミサイルが実用化され,攻撃力が著しく強化された。1950年代中期までは,核兵器を運搬するおもな手段は爆撃機であり,これを要撃するための全天候要撃戦闘機が各国で開発された。コンベアF106(米),ミコヤンMiG25(ソ)等がこの機種の例として挙げられるが,核運搬の主力が大陸間弾道ミサイル等にかわったため,全天候要撃戦闘機は少なくなりつつある。1950年代は地上レーダーや地対空ミサイルの発達も著しく,これを避けて対地・対艦攻撃をするには,低空を高速で進攻する必要が生じ,従来の攻撃機,軽爆撃機にかわり戦闘爆撃機が多用されるようになった。例としてリパブリックF105(米),スホーイSu24(ソ)が挙げられる。核爆弾の小型化,各種武器および爆撃計算機の進歩に加え,戦闘機が大推力を持ち多数の落下燃料タンクや武器を外部に搭載できるようになったことが,この用法を有効なものにした。
このように戦闘機の任務は拡大されてきたが,そのため別々の機種を持つことは,生産および整備補給上得策ではない。そこで生まれたのが多用途戦闘機で,1960年以降の多くの戦闘機がこれに属し,マクダネル・ダグラスF4(米),ダッソー・ミラージュⅢ(仏),パナビア200MRCAトーネイド(英・独・伊),サーブ37ビゲン(スウェーデン),ミコヤンMiG23(ソ)等が挙げられる。戦闘機は,高性能化し多用途性を追求するにしたがい大型化し,高価になる傾向がある。そこで搭載量や性能をある程度に抑え軽量小型を重視した,いわゆる軽戦闘機の流れもあり,ノースロップF5(米),ミコヤンMiG21(ソ),および最近のジェネラル・ダイナミックスF16(米)が挙げられる。特殊な戦闘機としては垂直離着陸機がある。この飛行機は滑走路が不要という利点があるものの,機構の複雑さと許容しうる搭載量が小さいことなどから,運用は限定され,現在実用機の種類は少ない。
戦闘機が対地・対艦攻撃を含め多用されるようになり,戦闘機どうしの戦闘が増加してきたため,1970年代に入り制空戦闘機と呼ばれる運動性の高い戦闘機が登場し,現代の主流になりつつある。敵味方入り乱れての空中戦では,目視で確実に敵と認めてからでないと武器は発射できず,このため必然的に近接戦となり,有利な位置に占位するための運動性が重視されることになる。また戦闘爆撃機等が低空進入してきた場合,これを上空から攻撃するのは難しいとされてきた。これは敵機が自機より下方にいる場合,地面または海面での電波の反射が邪魔して,敵機をレーダーで発見し難いからである。電子技術の進歩により下方の敵機をも発見し攻撃しうるルック・ダウン能力,シュート・ダウン能力が加わり,敵機を攻撃しうる相対位置が大幅に拡大された。マクダネル・ダグラスF15(米),ダッソー・ミラージュ2000(仏),スホーイSu27(ソ)が制空戦闘機の例として挙げられる。
日本の戦闘機
日本は航空に関して後進国であったが,第1次大戦前にすでに陸海軍は飛行機の重要性を認識し,欧米に人を派遣し,あるいは飛行機を輸入し研究を開始した。初期の欧米依存,模倣時代を経て,第2次大戦前にはゼロ戦などの世界レベルの戦闘機を自力で開発し生産する能力を持つに至った。しかし第2次大戦に敗れ,戦闘機の主流がプロペラ機からジェット機へ移行する重要な時期に,日本は航空に関する研究,製造等をすべて禁止され,約10年の空白期間を余儀なくされた。航空自衛隊では1954年発足以来,アメリカが開発したノースアメリカンF86,ロッキードF104,マクダネル・ダグラスF4EおよびF15をライセンス生産し,主力戦闘機として使用してきている。ようやく1970年代に三菱F1を開発し,国産の対艦ミサイルASM1等を搭載し,主として対艦・対地攻撃用に,一部要撃用に運用している。
戦闘機の戦闘
戦闘機の戦闘は空対空戦闘と対地・対艦攻撃に大別される。空対空戦闘は,敵の航空機および一部のミサイルを目標とするもので,航空優勢の獲得または維持のための敵戦闘機との戦闘(対戦闘機戦闘),自国の領域に侵入してくる敵の爆撃機,戦闘爆撃機等を迎え撃つ要撃,味方の爆撃機等の護衛,艦隊や船団の防空などがある。対地・対艦攻撃は,敵の陸上または海上部隊の進攻を阻み,またその補給路等を断つ航空阻止,味方陸上部隊を支援する近接支援に分けられる。要撃は戦闘機と地上の航空警戒管制組織の連係の下に行われる。航空警戒管制組織は地上のレーダー網および早期警戒機と連接された指令所からなり,この間の目標情報の伝達,敵味方の識別,戦闘機の誘導などは自動的に行われる。戦闘機は指令所の指示で発進し,誘導され,敵機の近くに達した後は自己のレーダーまたは目視により敵機を捕捉し,武器を発射し要撃を達成する。この戦闘は地上レーダー網等が整備されていない戦域で行われる場合は,レーダーを搭載し管制能力を持つ軍用機AWACS(エーワツクス)や移動用レーダー等がこれにかわって用いられる(防空)。対地・対艦攻撃の場合,通常,戦闘爆撃機は自機のレーダーで障害物を避け,慣性航法装置などで位置を確認しつつ低空を高速で目標に接近し,敵の対空ミサイル等に電子的妨害を加えてこれを回避しながら武器を発射する(電子戦)。
戦闘機の性能,機能
戦闘機は,それぞれ目的に応じ若干の差異はあるものの,一般的に最高速度,運動性,武器の発射能力が重視される。最高速度は発祥時から追求されてきた性能であり,時代を通じ飛行機の速度記録はほとんど戦闘機ないしはその改造機によって占められている。最高速度の向上には,推力の増大と抵抗の減少が重要である。推力の増大は,プロペラからターボジェットエンジンを経てターボファンエンジンへの移行,さらにその軽量小型化,アフターバーナーおよび効率の良い空気取入口の採用により達成され,抵抗の減少は工作法の進歩や空気力学の発達,なかでも後退翼や断面積の法則などの音速付近での抵抗減少方法の発見により達成され,超音速機が実現した。しかし高速の追求は運動性と相いれない面を持つ。高速のためには主翼を小さくしてでも抵抗を減らすほうが有利であるが,これは運動性の低下をもたらすからである。また機体の表面温度は空気力学的加熱(空力加熱)によりマッハ数の2乗に比例して上昇し,マッハ2.5では340℃に達し(外気温0℃の場合)機体の構造材料の強度を低下させるため,特殊な機種を除き実用機では約マッハ2.5を限界とし,むしろ現代の戦闘機では運動性の向上に重点が置かれている。
運動性とは,迅速に速度,高度,位置および姿勢が変えられる能力であり,加速・上昇・旋回性能と操縦性の良さと考えることができる。運動性の向上には,推力の増大と抵抗の減少に加え,重量の軽減と大きな揚力を発生する主翼が重要である。現代の戦闘機では重量軽減のため,従来のアルミニウム合金のほかにチタン合金や複合材料(炭素繊維等を合成樹脂で固めた材料)が使用され,推力と機体重量との比は1またはそれ以上になっている。飛行機が急激な運動をすると大きな遠心力が搭乗員にかかる。通常人間が耐えうる遠心力は,Gスーツやリクライニングシートを使用しても,重力加速度の8~9倍(8~9G)といわれ,これが有人機の運動性の限界となる。戦闘機にとっても大きな航続距離は望ましいが,そのためには細長い(アスペクト比の大きい)主翼と大きな燃料搭載量が必要となり,それが高速性と運動性とに相反するため,ある程度犠牲にせざるをえない。これを補うため落下燃料タンクまたは空中給油が用いられることがある。主翼を巡航時には横に延伸し高速時には後退させる可変後退翼により,航続距離と高速性を両立させる方法もあるが,機構が複雑となり利害得失がある。
現代の戦闘機は,射撃管制装置と連動したヘッドアップディスプレーを持ち,有効に武器が発射できるようになっている。ヘッドアップディスプレーは,操縦士の目前に斜めに置かれた半透明のガラスで,操縦士はそれを通して外部を見つつ,武器に応じて映し出される照準マークの中にレーダーまたは目視で捕捉した目標を入れるよう自機を操縦し,武器を発射すれば命中する機構になっている。このガラスにはそのほか自機の速度や姿勢等が映し出されるので,操縦士は目標から目を離すことなく操縦を続けることができる。一方,戦闘機はつねに敵から攻撃される危険性を持っており,防御能力も必要である。高速性や運動性は,それ自身が回避能力となる。敵からレーダーを照射されたときにそれを感知するレーダー警戒装置,敵のレーダーを妨害するECM装置などのほか,操縦士の射出脱出装置(射出座席)や防弾装置などがこのために装備されている。
将来の戦闘機
戦闘機はつねに新しい技術を取り入れ発展するが,将来適用される技術で最も注目されるのはCCVの技術であろう。飛行機は機体の空気力学的形状によって安定性を保っているが,元来安定性と操縦性は相反する特性である。そこでこのような安定性を捨て,コンピューターを通じて舵面を動かすことにより安定性を保ちつつ,操縦性をきわめて高くするよう設計された飛行機がCCVで,これにより従来不可能であった運動ができ,高い運動性を持つ戦闘機が実現されよう。また武器の発射,飛行状態,エンジン出力を統合して最適状態に制御することも行われよう。電子機器の高密度化,多様化が進み,計器にかわって必要な情報のみをブラウン管に表示する方式や,音声による制御が実現しよう。材料の面では,軽くて強く,かつレーダー波を反射しない複合材料の使用が増加し,電波吸収材と相まって,レーダーに映りがたいステルス性が付与されよう。エンジンはさらに軽量小型化するとともに,排気の方向が変えられる方式が出現するであろう。武器では各種ミサイル,特に近距離の機動目標に有効な空対空ミサイルが発達するであろう。
執筆者:鷹尾 洋保
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「戦闘機」の意味・わかりやすい解説
戦闘機
せんとうき
fighter
combat plane
敵の航空機と空中で戦い、撃墜するのを目的とする軍用機。第二次世界大戦以降は対地攻撃任務を兼ねるものが多くなり、対地攻撃を主として、空戦能力は敵戦闘機に襲われたときに自らを守る程度にとどめた戦闘機もある。
[藤田勝啓]
戦闘機の種類
現代の戦闘機を用途と性格によって大別すると、迎撃機、制空戦闘機、戦闘爆撃機の三つになる。迎撃機(防空戦闘機ともいい、航空自衛隊は昔の邀撃(ようげき)機という呼び方に音をあわせ要撃機とよんでいる)は、来襲する敵機(主として爆撃機)を迎え撃つための戦闘機で、速度、上昇力を重視し、レーダーと空対空ミサイルにより全天候戦闘能力を備えたものが多い。戦域の制空権確保を目ざす制空戦闘機は、敵の戦闘機と空戦を行うために軽快な運動性や優れた加速性能を追求し、ミサイルのほかに接近戦用の機関砲を装備するのが一般的である。空戦能力よりも対地攻撃に重点を置く戦闘爆撃機は、兵器搭載量が大きく、低空飛行性能や航続力に意を払った設計になっている。
しかし、これらの間に厳密な区分があるわけではなく、純粋な迎撃機のなかには対地攻撃能力をまったくもたないものが多かったが、そのほかの戦闘機は必要に応じて制空戦闘にも対地攻撃にも、また迎撃にも使えた。たとえば、アメリカ空軍が主力戦闘機として1970年代なかばから部隊配備しているF-15イーグルは、空戦能力を徹底的に追求した制空戦闘機として知られているが、対地攻撃能力も大きく、アメリカ本土の防空用にも使われている。また、空戦と対地攻撃の能力を両立させようという戦闘機も存在し、戦術戦闘機とよばれているが、これを広い意味で用いれば、一部の防空専用機を除いて、すべての戦闘機がこの範疇(はんちゅう)に入る。現在では戦闘爆撃機と攻撃機の侵攻能力が増したので、防空戦闘機といえども軽快な空戦能力が求められるようになり、昔のように爆撃機を主目標とする迎撃機は影が薄くなっている。また、戦闘機の価格が非常に高くなり、多種の戦闘機をそろえるのがむずかしくなったこともあるので、今では防空専用機はほとんど姿を消し、今後は広い意味で戦術戦闘機だけが使われることになろう。
[藤田勝啓]
戦闘機のスピード
戦闘機の歴史を振り返ると、まず気づくのがスピードの目覚ましい進歩である。戦闘機という機種は他の軍用機の多くと同様に第一次世界大戦中に誕生したが、この第一次世界大戦時の戦闘機は複葉機がほとんどで、装備エンジンは100~200馬力、最大速度は150~200キロメートル/時にすぎなかった。構造は木材あるいは鋼管を使った骨組に布を張ったものがほとんどである。これが第二次世界大戦の始まるころには、アルミ合金を主とする全金属製構造を用い、脚を引込み式にしたスマートな単葉機が主力となり、1000馬力前後のエンジンをつけて500~550キロメートル/時の高速を出すようになっていた。大戦末期には700キロメートル/時のプロペラ式戦闘機も登場したが、ドイツとイギリスが先陣をきったジェットエンジンの実用化により、速度は飛躍的に向上した。朝鮮戦争では最大速度が1000キロメートル/時に達するジェット戦闘機どうしが戦い、その後まもなく超音速戦闘機が実用になり、1960年代にはマッハ2級戦闘機が広く使われるようになったことをみれば、その進歩の速さがうなずけよう。
しかし、戦闘機の最大速度はその後さほど伸びず、現用機はだいたいマッハ1.8~2.5にとどまっている。それ以上の高速化が技術的に不可能なわけではなく、事実1960年代初めにアメリカではマッハ3を超えるロッキードYF-12が試作され、続いて旧ソ連でもマッハ3級のミグ25を完成させた。だが、マッハ3前後の速度になると空気摩擦による機体表面の温度上昇が著しく、従来のアルミ合金では耐えられないため、高価で加工に手間のかかるチタン合金や重量のかさむスチールを用いなければならない。そして機体は大型・高価になり、また戦闘機どうしの空戦においては、最大速度が大きいだけでは勝てないので、無理をしてまでマッハ3のような高速性能を求めないのである。自動車がカーブではスピードを落とさないと曲がりきれないように、マッハ2級の戦闘機といえども、空戦で機動する際はマッハ1.5~0.8程度の速度になり、もっと低い速度を使うことも珍しくない。そこで現在の戦闘機はこうした速度域における運動性や加速性に重点を置いた設計になっており、最大速度をマッハ2.5あたりまで高めうる余地がありながらも、簡易・軽量化のためマッハ2にとどめている戦闘機さえある。旧ソ連およびロシアだけがマッハ3級のミグ25を使ったのは、冷戦時代にアメリカの爆撃機やマッハ3級偵察機に対する迎撃を考えていたためで、他の戦闘機に比べると生産数はごく少ない。
[藤田勝啓]
現代の戦闘機
現代の戦闘機が第二次世界大戦時のものと大きく異なるのは、飛行性能の面だけではなく、レーダーなどの電子装置を備え、ミサイルを主兵器としていることである。レーダーは第二次世界大戦後半から爆撃機の夜間迎撃用戦闘機に積まれ始めたが、現在はコンピュータにより情報処理を行い、単に遠方から敵を発見するだけではなく、兵器の発射に最適な位置とタイミングまで指示するようになっており、戦闘機の戦闘力を決定づける大きな要素として考えられている。そのほか、爆撃照準システム、航法システム、敵味方識別システム、敵の電子装備に対する妨害システム、電子妨害に対する防御システムなど、戦闘力に関係する電子装置は多く、その充実が図られているが、装備品が増えると高価になるうえ、故障をおこす率も増加するので、全天候能力などを犠牲にし、可動率の高い機体を多数そろえようという考え方も存在する。
空対空ミサイルは1950年代から実用化され、戦闘機の主武装となったが、接近した格闘戦に備えて機関砲も標準装備兵器として使われ続けている。一時期はミサイル万能と考えられたこともあったが、爆撃機のような鈍重な相手ならともかく、機敏に動く戦闘機に対してはまだ命中率が低く(ベトナム戦争時には10%程度)、機関砲の必要性がふたたび認識されたのである。しかし、戦闘機が携行するミサイルの射程と追尾能力が空戦の局面を決定することは間違いなく、能力と精度向上が続けられている。対地攻撃用には、やはりミサイルも用いられるが、破壊力の大きな通常爆弾とそれに誘導装置を加えた誘導爆弾、ロケット弾、広域散布爆弾、火炎爆弾、機関砲など多様な兵器が目標に応じて選択され、核爆弾の携行能力をもつ戦闘機もある。また、レーダーに探知されにくいステルス技術を応用した戦闘機なども実用化されている。
[藤田勝啓]
『『世界の偉大な戦闘機』全8巻(1983・河出書房新社)』▽『マイク・スピック著、藤田勝啓訳『イラストレイテッド・ガイド10 現代の航空戦(戦闘機編)』(1989・ホビージャパン)』▽『ワールド・エアパワー・ジャーナル著、エアクラフト研究会訳、松崎豊一監訳『最新戦闘機図鑑』(1998・ソフトバンク)』▽『三野正洋・深川孝行著『戦闘機対戦闘機』『現代兵器事典』(1998・朝日ソノラマ)』▽『阿施光南著『最強戦闘機伝説!――戦闘機の誕生から最後まで』(2000・山海堂)』▽『野原茂編『写真集 日本の戦闘機』『写真集 ドイツの戦闘機』(2000)、『写真集 アメリカの戦闘機』(2001・以上光人社)』▽『日本兵器研究会編『世界の戦闘機・攻撃機カタログ』(2002・アリアドネ企画)』▽『青木謙知著『戦闘機年鑑』各年版(イカロス出版)』

戦闘機F-15

戦闘機F-2

戦闘機の構造
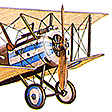
ソッピーズ・キャメル

カーティスP-6 ホーク

三菱A5M(九六式艦上戦闘機)

スーパーマリン・スピットファイア

フォッケ・ウルフFw190

メッサーシュミットMe262

ノースアメリカンP-51 ムスタング

ノースアメリカンF-86 セイバー

ロッキードF-104 スターファイター

ミコヤン ミグ21

グラマンF-14 トムキャット
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「戦闘機」の意味・わかりやすい解説
戦闘機
せんとうき
fighter plane
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「戦闘機」の意味・わかりやすい解説
戦闘機【せんとうき】
→関連項目F117Aステルス戦闘機|F/A18ホーネット戦闘攻撃機|FSX|F22ラプター戦闘機|AWACS|軍用機|スホイ27|兵器|ユーロファイター
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の戦闘機の言及
【軍用機】より
…これは,科学技術の進歩と戦略・戦術的要求の変化,年々膨大化する関連諸費用等に影響されて,各機種のもつ有効性や有利性が時とともに変化していくからである。
[軍用機の特徴]
例えば戦闘機は,強力なミサイルや機関砲と,それを正確に管制する装置を備え,さらに,これら武器の威力を十分に発揮するために必要な優れた速度と運動性をもつことが要求されるように,軍用機が第1に要求される条件は,運用目的を達成するために不可欠な優秀な兵器,器材を搭載し,かつその効力を十分に発揮させうる管制能力をもつことである。このために飛行性能(水平速度,上昇速度,上昇限度,航続距離,離着陸距離,操縦性,安定性,運動性),機体強度,有効搭載量,残存性または抗堪性(被弾や故障しにくく,被害を受けても堪えうる能力),耐環境性(天候,気象など各種環境条件の悪いときでも正確に機能する能力),信頼性(故障発生率の低さ),整備性(整備の容易さ)の諸性能が厳しく要求される。…
※「戦闘機」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...




