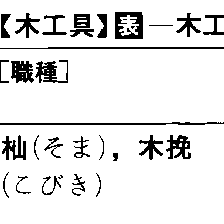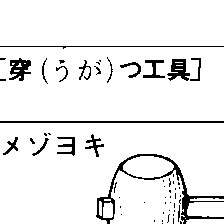改訂新版 世界大百科事典 「木工芸」の意味・わかりやすい解説
木工芸 (もっこうげい)
木を材料として美術的に価値ある製品をつくる技術,またその技術を用いてつくられた生産品のこと。家具や調度,建具なども含まれる。
西アジア,西欧
木の家具の歴史は古く,古代エジプトではファラオの玉座をはじめ寝台,椅子,腰掛,櫃(ひつ),テーブル,化粧箱,頭架などが作られている。それらの装飾には彫刻,象嵌,塗装,金箔付けなど木工芸にとって主要な装飾技法が使われていた。木材加工に使用した工具には鋸(のこぎり),鑿(のみ),ハンマー,斧,錐(きり),小刀,砥石(といし)などがあり,また部材の組手には枘接(ほぞつぎ)と蟻接(ありつぎ)などが使われていたことからみて,古代エジプトの木工技術はきわめて高い水準に達していたものとみられる。木材を平らに削る鉋(かんな)の出現は17世紀を待たねばならない。木工にとって重要なろくろ技術はメソポタミア地方の古代国家の家具に多くみられるため,この技術の発生地はメソポタミア地方とされている。イギリスの家具史研究家パーシー・マッコイドは家具の歴史を,使用された木材から〈オーク(ナラ,カシ)の時代 1400-1660年〉,〈ウォルナット(クルミ)の時代 1660-1720年〉,〈マホガニーの時代 1720-70年〉,〈サテンウッドの時代 1770年~19世紀初期〉と時代区分している。19世紀中期以後は主役をなす木材はなく,家具の使用目的に応じて多種多様な木材が使われるようになった。
木製家具の美的価値を高めるためには,古来からいろいろな装飾技法が採用されてきたが,そのおもな装飾技法は,彫刻,挽物,寄木細工,象嵌,化粧張り,塗装,金箔付けなどである。
(1)彫刻carving 〈切込彫chip carving〉〈浅浮彫bas-relief〉〈高浮彫high-relief〉〈透し彫〉などがある。ゴシック期初期の地方家具にはオークの表面に小刀で彫った素朴な切込彫の装飾がみられる。18世紀のアメリカ東部の収納家具にも切込彫の草花模様の飾りがみられる。切込彫が技術の低い地方家具に用いられたのに対して,ルネサンスからバロックにかけてウォルナットを用材とした高級家具には豪華な高浮彫や丸彫の装飾が流行した。17世紀のベネチアで活躍した木彫家ブルストロンAndrea Brustolon(1662-1732)の椅子や花台などには,家具というよりはまさに彫刻作品といってよいものがある。
(2)挽物turning ろくろ加工による挽物はすでにシュメール人やバビロニア人の椅子やテーブルの脚に用いられており,ヨーロッパでは古代ローマから中世を経て現代に継承されている。ロマネスク時代の椅子の多くは挽物部材から構成されている。イギリスではエリザベス朝のボビン・チェアbobbin chairや18世紀のウィンザー・チェアなどに挽物技術の特性が生かされている。
(3)寄木細工marquetrie(フランス語),intarsia(イタリア語) この技法も古く,エジプトでは家具の装飾に取り入れていた。ヨーロッパでは15世紀からイタリアのベネチアやフィレンツェで〈タルジアtarsia〉と名づけた寄木細工がカッソーネ(櫃)や衣装戸棚の装飾に用いられていた。浅く穴をあけて,そこに色の異なった木片をはめこんで模様をつくる技法である。ヨーロッパではバロックからロココにかけて,イギリスとフランスを中心に寄木細工の人気が高まった。この頃の寄木細工は色の異なる木片を組み合わせて1枚のパネルとする精巧なもので,イギリスではウィリアム3世時代に花文様,海藻文様,唐草文様などの精緻な寄木細工が簞笥やビューローの装飾に用いられた。フランスではポンパドゥール夫人からマリー・アントアネットの時代にかけて,華麗な花柄の寄木細工が上流婦人の家具に好んで採用された。アントアネットの宮廷家具師J.H.リーズナーの寄木細工は18世紀最高の技術水準を示した。
(4)象嵌marquetrie(フランス語),intarsia(イタリア語) シンチュウ,べっこう,象牙,大理石,金,銀などの小片を地板に組み込んでつくる技法である。ルイ14世の宮廷家具師A.C.ブールは黒檀の化粧張りにシンチュウ,べっこう,象牙などを組み込んだ〈ブール象嵌〉を完成した。
(5)化粧張りveneering この技術は17世紀にウォルナットの家具が流行した時代に始まった。ブナ材を下地とした家具に薄く切ったウォルナットの化粧板を接着して装飾効果を高める技法である。薄く切断したり,化粧板を家具に接着させる技術は職人にとってかなりの熟練を必要とする。黒檀,マホガニー,サテンウッド,ローズウッドなどの化粧張りは18世紀から19世紀にかけて流行した。
(6)塗装painting 古くからある装飾技法の一つであるが,とくに17世紀前期には中国からのちには日本から漆芸や蒔絵の技法が導入された。シノアズリー(中国趣味)と呼んで愛好された家具には,漆塗りと蒔絵の技法が使われている。
(7)金箔付けgilding 古くはエジプトの家具にみられるが,中世期に水性法と油性法の二つが完成した。前者は木材の平滑な表面に漆喰(しつくい)を塗り,その上に冷水を浸み込ませてから金箔をはり付け,焼き鏝(ごて)で金箔を固着させる技法,後者は木材表面に漆喰の下地をつくり,油性粘着剤をその上に塗ってから金箔をはり付け,乾いた布でこすりつける技法である。こういった技法は初めイタリアのゴシック期の家具に使われたが,後にフランスやイギリスなどに輸入され,とくにバロック,ロココ,帝政の各時代の王室や上流貴族の家具装飾に広く採用された。家具や調度品の特徴をより深く理解するためには,様式史だけでなく,このような木工芸に関する材料や装飾技法の理解も欠くことはできない。
執筆者:鍵和田 務
日本
日本には良質の各種有用材が豊富にあり,柾目(まさめ),板目の木理の美しさは本邦材の特色とされている。古来,こうした木材の特性を生かした生活用具をつくるために種々の技法が考案されてきた。板材を組み合わせて調度をつくる指物(さしもの),轆轤を用いて鉢や椀などをつくる挽物(ひきもの),檜(ひのき)や,杉などの薄板を曲げてつくる曲物(まげもの),鑿や小刀などで木を刳(く)り,彫って鉢などをつくる刳物,彫物などの技法がある。
すでに縄文時代に,椀や高杯(たかつき)などの容器,櫛や腕輪などの装身具,その他丸木舟,櫂(かい),弓など多くの木製品の出土をみている。弥生時代には漸次鉄製工具も普及し,各種の生活用具も豊かになった。椀や高杯には明らかに木工具としての轆轤の使用も認められ,その接合部には枘仕口(ほぞしぐち)の手法もうかがわれ木工技術に進展がみられる。古墳時代には鉄製木工具の急激な機能上の発達をみ,また多数の工人の渡来により,飛躍的な技術の進歩がもたらされた。これらの木器の用材には各種の針葉樹,広葉樹が適材適所に利用され,その木取りにも十分考慮が払われている。伝世最古の木工芸品に,法隆寺の玉虫厨子,橘夫人念持仏厨子,正倉院の文欟木厨子(ぶんかんぼくずし)などがある。玉虫厨子は宮殿と須弥壇とからなり,檜造黒漆塗りで,木工,漆工,金工,絵画の諸技法を総合した作品である。宮殿部は飛鳥様式の建築資料として,また密陀絵の意匠は絵画資料としても重要視される。文欟木厨子は《東大寺献物帳》によれば,文武天皇より孝謙天皇に至る歴代相伝の品である。奈良時代の木工芸は今日正倉院に幾多の優品を伝えており,大陸文化をよく消化したその高度な技術水準は驚嘆に値する。技法的にも意匠上からみても現在の木工に比してはるかに豊富であり,すでに一応の完成期を迎えていたことが指摘される。
平安時代に入ると木工品は多く塗漆され,これに蒔絵を配した調度が独自の発達を示す。中期ごろには公家調度としての〈しつらい〉の基本的な構成と形式とが整った(家具)。武家の調度もその典拠となったものはあくまでも公家調度であり,公家調度の二階厨子と二階棚とが組み合わされて,室町時代には武家調度としての厨子棚,黒棚が生まれた。江戸時代になるとこれに書棚が加わって三棚と呼ばれ,大名たちの嫁入り調度の中心的存在となった。桃山時代,千利休によって茶道が大成されると,日本の木竹工芸は再認識され,また本阿弥光悦は,平安朝の諸工芸を学び清新な時代感覚の作品を生み出した。江戸時代は各藩の殖産奨励により,各地に特色のある地域的産業が勃興した。明治時代以降いわゆる美術工芸としての木工芸と,産業工芸としての木工芸がそれぞれ分かれて進むこととなる。前者は木工技術の伝統を生かしながら生活に結びついた工芸を指向し,後者は産業振興政策に乗じて近代化をはかり,現代生活のうちに定着している。
→漆工芸 →唐木細工 →木材
執筆者:木内 武男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「木工芸」の意味・わかりやすい解説
木工芸
もっこうげい
木材を用いて工芸的に加工する技法、またはその製品。木製品には器具や道具類のほかに、建築用材、橋梁(きょうりょう)、木柵(もくさく)、輿車(よしゃ)、舟などがあるが、木工芸は主として器具・道具類を加工する技術をさす。材料は加工法によって適材が選ばれるが、針葉樹では檜(ひのき)、杉、松など、広葉樹では桐(きり)、朴(ほお)、桂(かつら)、欅(けやき)、橅(ぶな)、黄楊(つげ)、胡桃(くるみ)、楓(かえで)などがおもなもので、紫檀(したん)、黒檀(こくたん)、黒柿(くろがき)などの高級材なども用いられる。
[荒川浩和]
木工芸の技法
器物を成形する方法によって、刳物(くりもの)、挽(ひき)物、指(さし)物、曲(まげ)物に大別される。
[荒川浩和]
刳物
刀や鑿(のみ)を用いて削る方法で、古くは椀(わん)や鉢などの丸物の成形も行われたが、のちには脚、注口、把手(とって)、持送りなどの器物の部分をつくるのに主として用いられる。
[荒川浩和]
挽物
轆轤(ろくろ)を用いて、椀、盆、鉢などの丸物を成形する技法。おもに欅、樅(もみ)、栃(とち)、桂、橅などを用いる。
[荒川浩和]
指物
板(いた)物ともいい、板材を組み立てて成形する方法。各種の箱類、棚、たんすその他の調度類をつくる技法で、檜、杉、桐、樅、欅などをおもに用いる。
[荒川浩和]
曲物
檜や杉の薄板を曲げ、円形や楕円(だえん)形の胴部に底板をつける技法で、桜皮で留める。「わっぱ」とよばれ、蒸籠(せいろう)、ざる、篩(ふるい)、弁当箱、柄杓(ひしゃく)、炭櫃(すみびつ)などをつくるのに用いる。桶(おけ)は同一幅の薄板を円形または楕円形に並べ、底板をつけて箍(たが)で締めて成形するもので、曲物とは区別される。
木工芸の加飾法には、木画(もくが)、木地螺鈿(きじらでん)、玳瑁貼(たいまいばり)、金銀絵、彩絵、金箔(きんぱく)押し、刻彫(こくちょう)、漆(うるし)塗りなどがある。木画は、木、竹、牙(きば)、角(つの)などの細片を木地に象眼(ぞうがん)して幾何的模様や具象的模様を表す方法と、紫檀、黒柿、香木などの薄板を方形や菱(ひし)形に切って器物に貼り付けて幾何的模様を表す方法とがある。後世の木(もく)象眼や寄木細工はこの系統の技法である。木地螺鈿は紫檀地などに模様に切った厚貝を象眼する技法で、玉、石、サンゴなどを用いた木象眼も同系である。玳瑁貼は器物の表面または一部に玳瑁(べっこう)を貼る装飾法で、裏に彩絵を施したり金箔を押す方法を伏彩色という。金銀絵は金銀の細粉を膠(にかわ)で溶いて模様を描く技法で、顔料(がんりょう)を用いたものを彩絵という。金箔押しは、表面に金箔を押して飾る場合と、模様を表す方法とがある。模様を表す技法は箔絵ともいい、方形、短冊形、菱形などの切箔を用いて具象文や界線を表す方法もある。刻彫は器物に刀や鑿で模様を彫り表す方法で、浮彫りと透(すかし)彫りがあり、一般に「彫物(ほりもの)」とよばれる。漆塗りは透明塗りや各色の塗りを施す方法であるが、木工芸とは別種の技法として扱われることが多い。
[荒川浩和]
木工芸の歴史
木製品は腐食しやすく、発見される考古遺物は好適な条件に恵まれた例であり、木工芸の歴史がどこまでさかのぼるか明らかではない。日本で現在知られている木製品の出土例は、福井県鳥浜や千葉県加茂(かも)の縄文前期の遺跡から発見されたものが古い。盆状や皿状木器の断片、櫛(くし)、道具の柄(え)、櫂(かい)、弓その他があり、主として両刃や片刃の磨製石斧(せきふ)を用いたとみられる。縄文後期になると出土品も多く、なかでも青森県是川(これかわ)遺跡の弓、太刀(たち)、椀、高坏(たかつき)その他が知られている。弥生(やよい)時代には各種石斧を用いるとともに、一部鉄製の斧(おの)や手斧(ちょうな)が併用された。弥生中期以降は木工技術が発達し、斧、手斧、鉈(なた)、刀子(とうす)、鑿、錐(きり)などの工具が用いられ、また回転台(轆轤の系統)の使用や枘(ほぞ)組が行われた。中期の滋賀県近江八幡(おうみはちまん)市の大中の湖南(だいなかのこみなみ)遺跡、後期の静岡県山木遺跡からの出土品が知られ、奈良県唐古(からこ)遺跡や静岡県登呂(とろ)遺跡発見の高坏は回転台使用の好例である。
古墳時代になると大陸の技術が伝来して、技術が急速な発達をみせる。奈良時代には令(りょう)制では筥陶司(はこすえのつかさ)が宮内省に所属し、箱類や陶製食器類製作にあたった。正倉院宝物中には優れた木工技術や加飾法を示す遺例が多く、輪積法や印籠合口造その他の特殊な木地構成がみられる。
平安時代には内匠(たくみ)寮が調度の製作や装飾にあたり、これに属する職種のなかには、細工・漆塗工・木工・轆轤工・黒葛工・柳箱工などがある。また、禁中・幕府・社寺などに属す手工業の工房を細工所といい、鎌倉幕府直属の細工所には木工・檜皮(ひわだ)工その他があった。平安時代は貴族文化の爛熟(らんじゅく)期で、いわゆる和様の美が成立し、木工芸の遺例にも洗練された形態の作がみられる。鎌倉・室町時代の調度類は基本的には前代の形式の継承であるが、形態や意匠には時代による相違が現れる。中世の座は、商工業その他の同業者がその特権を保証された特殊な団体だが、応仁(おうにん)の乱(1467~77)以降はこれに属さない職人が徐々に活躍するようになった。
江戸幕府は西之丸に細工所を置き、細工頭のもとに諸職の世襲用達を管掌させ、各藩も産業奨励の政策もあって多くの工人を抱えた。そのため、この時代には木工芸が広く行われ、技術的にも非常に精巧になった。明治維新によって庇護(ひご)者を失った工人の多くは転業廃業せざるをえなかったが、明治の新政府は内外の博覧会への出品その他によって産業振興を計った。この結果、各地の木工芸も復活し、なかでも江戸指物象眼の系統や、石川県の木工が大いに盛んになった。江戸末期から明治に活躍した木工としては、小林如泥(じょでい)、木内喜八、木内半古(はんこ)、西村荘一郎、仰木(おうき)政斎、石川光明(みつあき)、堀田瑞松(ずいしょう)らが知られている。
1907年(明治40)には文展が開催されたが、工芸部門は1927年(昭和2)にようやく設置された。第二次世界大戦後の1951年(昭和26)には文化財保護法が制定され、それに基づいて1970年に黒田辰秋(たつあき)(1904―82)と氷見晃堂(ひみこうどう)(1906―75)が「木工芸」の重要無形文化財保持者に認定されたのを第1回に、大野昭和斎(しょうわさい)(1912―96)、中台瑞真(ずいしん)(1912―2002)、川北良造(1934― )、大坂弘道(ひろみち)(1937― )、中川清司(きよつぐ)(1942― )、村山明(1944― )が認定されている。
[荒川浩和]
『柳宗理・渋谷貞他編『木竹工芸の事典』(1985・朝倉書店)』
世界大百科事典(旧版)内の木工芸の言及
【イスラム美術】より
…工芸諸分野における一つの共通した特徴は,装飾面全体を種々の装飾モティーフですきまなく覆う,過剰とも思える装飾で,これによって,器物本来の性質,質感,機能性などが著しく損なわれる結果を招いている。イスラム工芸には,金属工芸,陶芸,染織,ガラス工芸,象牙細工,木工芸などの分野があり,とりわけ,金属工芸と陶芸が高度の発達を遂げて,東西両洋の美術に少なからず影響を与えている。
[金属工芸]
金工においても,ササン朝ペルシア,ビザンティン,コプトなどイスラム以前の伝統が継承された。…
※「木工芸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...