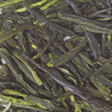精選版 日本国語大辞典 「煎茶」の意味・読み・例文・類語
せん‐ちゃ【煎茶】
- 〘 名詞 〙
- ① 葉茶を湯で煎じ出す喫茶の方式。団茶や抹茶に対して、風通しのよい所で陰干しをした葉茶に湯を注いで、香りや味をたのしむもの。また、その葉茶や、煎じ出された飲みものをもいう。せんじちゃ。〔撮壌集(1454)〕
- [初出の実例]「煎茶の釜をたぎらせて昔物語を聞はかうはしからずや」(出典:俳諧・類船集(1676)仁)
- [その他の文献]〔新唐書‐芸文志・小説家類〕
- ② 俗に、玉露や番茶に対して中級の茶をいう。
せんじ‐ちゃ【煎茶】
- 〘 名詞 〙 煎じて飲む茶。せんちゃ。煎じ。
- [初出の実例]「酒よりもせんじ茶でみよ姥桜〈重頼〉」(出典:俳諧・犬子集(1633)二)
改訂新版 世界大百科事典 「煎茶」の意味・わかりやすい解説
煎茶 (せんちゃ)
緑茶の一種で,玉露と番茶の中間の品質のもの。露地栽培で日光を遮蔽せずに,自然のままで育てた若芽でつくる。本来は茶葉を粉末にして湯でかきまぜて飲む抹茶に対して,茶葉に湯を注いで浸出させて飲む方式の茶を指した語で,煎じ茶,出茶(だしちや)とも呼ばれた。《煎茶仕用集》(1756)は近江信楽(しがらき)産の16種の銘柄を挙げ,〈日東煎茶此産第一とす〉と,煎茶は信楽産が最良であるとしている。その煎茶を玉露と煎茶に区分するようになったのは,幕末~明治初期に玉露という,新しく良質な煎茶が出現したことによるものであろう。いまの日本で茶といえば,ふつうこの煎茶を指し,生産量も緑茶全体の80%余を占めている。タンニン,カフェイン,ビタミン類,アミノ酸,葉緑素などを含み,とくにビタミンCの含有量は野菜や果実よりも多い。北海道と東北の一部を除いて日本全土でつくられており,産額は静岡県が最も多く,鹿児島,三重,埼玉の諸県がそれに続く。産地銘柄としては,静岡県の川根茶,本山茶,京都府では宇治田原や和束(わづか)の宇治茶,埼玉県の狭山(さやま)茶,三重県の伊勢茶,奈良県の大和茶などが知られている。品種としては,明治末に静岡県で育てられた藪北(やぶきた)が品質,収量ともにすぐれ,全国的に栽培されて茶樹の代表種とされている。
煎茶は玉露にくらべて温度の高い湯を使う。上級品の場合は,3人分として6~7gの茶葉をきゅうすに入れ,完全に沸騰させてから湯冷ましにかけて60~70℃にした湯を170mlほど注ぎ,2分ほど浸出させてから茶碗に注ぎ分ける。近年知られるようになった深蒸し茶の場合は,一般の煎茶よりも長く蒸してあるため,熱い湯でもおいしく飲むことができる。なお,茶道の流派の中には,抹茶ではなく煎茶を用いるものがあり,それらは煎茶または煎茶道と呼ばれている。
→緑茶
執筆者:松下 智
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「煎茶」の意味・わかりやすい解説
煎茶
せんちゃ
緑茶の一種。1738年(元文3)に山城(やましろ)(京都府)の永谷宗円(そうえん)が創案した茶で、日本人の嗜好(しこう)によくあって発展普及し今日に及んでいる。摘み取った茶の芽葉をまず蒸し、粗揉(そじゅう)→揉捻(じゅうねん)→中揉(ちゅうじゅう)→精揉(せいじゅう)→乾燥の工程を経て製品になる。摘採の季節によって一番茶、二番茶、三番茶に分けられるが、一番茶は芽葉も柔らかく形も整い香味も優れ、なかでも立春から数えて八十八夜前後に摘んでつくられた茶は、いわゆる新茶として味、香りともに優れ珍重される。中、下級茶は一番茶末期の硬化葉や二、三番茶を原料としたもので、アミノ酸は少なく、苦味成分のタンニンが多く、うま味は落ちる。
良品は形状が葉長方向に細く伸び、よりが固く締まっていて、全体に形がそろっていて、色は濃緑色でつやもある。茶をいれたときの水色(すいしょく)は濃黄淡緑色で沈殿の少ないもの、また香気は清らかな芳香で、青臭み、生臭みのないものがよい。味は苦味、渋味と甘味、うま味が調和して舌にまろやかな感じを与え、あとくち(飲んだあとに残るもの)の爽快(そうかい)なものが良品である。昔は産地により特徴があり、品質にも違いがあったが、現在では栽培、製造の方法も進歩し、品種も普及して品質の格差は縮まり、各地の特色もならされてきている。山間部などで生産規模の拡大がむずかしい所では、いまでもていねいに摘み取って製造しており、良品が多い。上級品を飲む場合、茶の量は3人分で約6グラム、湯は70℃ぐらいに冷まし、170~180ミリリットル注いで約2分浸出させる。
[桑原穆夫]
百科事典マイペディア 「煎茶」の意味・わかりやすい解説
煎茶【せんちゃ】
→関連項目緑茶
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「煎茶」の意味・わかりやすい解説
煎茶
せんちゃ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
飲み物がわかる辞典 「煎茶」の解説
栄養・生化学辞典 「煎茶」の解説
世界大百科事典(旧版)内の煎茶の言及
【チャ(茶)】より
…これ以後の操作は乾燥,揉捻(じゆうねん),整形であり,茶の保存性や商品価値を高めるとともに,使用時の茶葉成分の浸出を容易にするために行う。煎茶の製造は蒸熱,粗揉,揉捻,中揉,精揉,乾燥の6工程からなる。この工程は日本で発達した手もみ製茶法を基礎とするもので,現在でも生産家の間で伝統技術として伝承されている。…
【売茶翁】より
…僧号月海,諱(いみな)は元昭,晩年は還俗して高遊外と自称した。煎茶人として知られ,煎茶の中興といわれ,また本朝煎茶の茶神とまで称賛される。12歳のとき肥前竜津寺で同寺開山の化霖道竜につき出家,ついで化霖の師万福寺の独湛性瑩(しようけい)に師事し禅の修行に励んだ。…
※「煎茶」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...