精選版 日本国語大辞典 「山陽道」の意味・読み・例文・類語
さんよう‐どうサンヤウダウ【山陽道】
日本歴史地名大系 「山陽道」の解説
山陽道
さんようどう
- 兵庫県:総論
- 山陽道
律令制下に都を中心として放射状に設定された官道の一つ。のちにも畿内と山陽地方を結ぶ幹線道として機能した。
〔古代〕
大和、のちには山城から摂津・播磨・備前・備中・備後・安芸・周防・長門の諸国を結び、西海道(九州)の大宰府へと続いていた。律令制下では唯一の大路。発掘調査によると、最も広い例では幅一〇―二〇メートルの大道であった。「日本書紀」崇神天皇一〇年九月九日条のいわゆる四道将軍の派遣記事には、吉備津彦を西道に遣わしたことがみえ、「古事記」孝霊天皇段には、大吉備津日子・若建吉備津日子が
大宝律令施行直後の大宝三年(七〇三)一月の巡察使派遣時には、穂積朝臣老が山陽道の使者に任命された(「続日本紀」同年正月二日条)。山陽道の初見である。令制では大・中・小路のうち駅ごとに駅馬二〇匹を置く大路に位置づけられ(厩牧令義解)、天平元年(七二九)四月三日には山陽道諸国の駅家を改修するため、駅起稲五万束が充てられている(続日本紀)。山陽道は外国使節を送迎する道でもあり、駅家はとくに意を用いて整備されていたらしく、「日本後紀」大同元年(八〇六)五月一四日条によると、蕃客に備えて備後から長門までの駅館を瓦葺・粉壁にしていたが、今後、長門以外の駅館は農閑期に修理するよう命じている。摂津・播磨両国の駅家も同様の構造であり、しかもこれ以降も恒常的に維持管理が行われたことがうかがえよう。
駅家・駅馬の実数は、大同二年の時点で摂津国五駅、駅ごとに馬三五匹、播磨国は九駅で、駅ごとの馬数は二五匹であったと推定される。
山陽道
さんようどう
- 岡山県:総論
- 山陽道
古代には都京と筑紫大宰府(現福岡県太宰府市)を結ぶ官道として、国家にとって最も重要な道であった。中世には官道としての性格は失ったが、陸上交通路としての重要性に変りはなく、一部道筋を変えながらも近世に継承される。
〔古代〕
大宰府道・筑紫大道ともよばれた。大同元年(八〇六)五月一四日の勅(日本後紀)によると、備後・安芸・長門などの駅館は外国使節に備えて瓦葺粉壁の建物であったことが知られる。「延喜式」兵部省では全国の七官道のうち唯一の大路とされ、県内の駅家としては、備前国 (つさか・つさき)・
(つさか・つさき)・
播磨国を西進して
備中国に入ると津 駅(現倉敷市矢部に比定)から国分尼寺・国分寺(現総社市)の寺域の南辺を通って
駅(現倉敷市矢部に比定)から国分尼寺・国分寺(現総社市)の寺域の南辺を通って
山陽道
さんようどう
- 山口県:総論
- 山陽道
古代の令制による官道は、それぞれ設置する駅馬の数により大路・中路・小路の別があったが、大路は山陽道と 周防国大前駅家
周防国大前駅家 」とあるから、その一つは
」とあるから、その一つは
山陽道
さんようどう
- 大阪府:総論
- 山陽道
古代における中央の都京と西海道の大宰府(現福岡県太宰府市)を連絡した駅路。七道の一つで、諸道のうちただ一つの大路として古代国家がもっとも重視した官道である。
この和銅四年新設の山陽道は、平城京から千里丘陵北部までの路線しか示していないが、それ以前に奈良盆地南部の飛鳥京・藤原京から難波京を経由する山陽道が設けられていたと考えられる。
山陽道
さんようどう
- 広島県:総論
- 山陽道
山陽道は古代の行政区画である五畿七道の一つで、播磨・美作・備前・備中・備後・安芸・周防・長門の八ヵ国をさすが、一般にはこれら諸国を連ねて通じた駅路の意味で用いられることが多い。近世には西国街道・中国路などともよばれた。
令制では都と九州大宰府を結ぶ官道として重要視され、唯一の「大路」として駅馬二〇疋が置かれた。「延喜式」(兵部省)によると、備後・安芸に設けられた山陽道の駅は一六ある。東から
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
百科事典マイペディア 「山陽道」の意味・わかりやすい解説
山陽道【さんようどう】
→関連項目安芸国|駅・駅家|海田[町]|玖珂[町]|周防国|中国路|長門国|播磨国|備前国|備中国|備後国|船坂峠|美作国
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
改訂新版 世界大百科事典 「山陽道」の意味・わかりやすい解説
山陽道 (さんようどう)
古代の地方行政区画の七道(五畿七道)の一つ。《西宮記》では〈ソトモノミチ〉〈カケトモノミチ〉と読んでいるが,前者は山陰道の読みの錯入。中国山地の南斜面に位置し瀬戸内海に面する地域であったため,古くから内海交通の活発とあいまち大和朝廷にとって重要な地域となり,それは律令国家の行政下でも変りなかった。《延喜式》では播磨,美作,備前,備中,備後,安芸,周防,長門の8国が属するが,このうち美作は713年(和銅6)に備前より分立した。また備前,備中,備後,美作の4国は,古くは吉備と呼ばれ大和朝廷に対し一大勢力圏を形成していた。山陽道の成立時期は不明だが,685年(天武14)に佐味少麻呂が山陽使者として派遣されたことが知られるので,天武朝末年に成立したとみられる。なお駅制の大路(たいろ)は,平城京より山陽道の海岸沿いの各国を通り大宰府に至る道を指し,陸上交通路としての価値はきわめて大であった。
執筆者:亀田 隆之
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「山陽道」の意味・わかりやすい解説
山陽道
さんようどう
古代、律令(りつりょう)期における国の上部の地域単位である五畿(ごき)七道の一つ、およびそこに設定された官道の名称。中国地方の南側にあたり、734年(天平6)に安芸(あき)、周防(すおう)の国境が定められて、播磨(はりま)、美作(みまさか)、備前(びぜん)(『延喜式(えんぎしき)』では以上近国)、備中(びっちゅう)、備後(びんご)(以上中国)、安芸、周防、長門(ながと)(以上遠国)が確定した。美作以外の瀬戸内海側を京と大宰府(だざいふ)を結ぶ古代の最重要路山陽道が貫通し、原則として駅馬20~30疋(ぴき)が常備されていた。駅数は『延喜式』では合計54駅であった。同書「主税上」には山陽道諸国のすべてに海路の船賃を記載しており、陸路のみならず瀬戸内海を通じて淀(よど)川沿いの與等津(よどのつ)とも密接に結び付いていたことが知られる。近世には、山陽道は道路名としては西国街道あるいは西国路と称された。
[金田章裕]

歌川広重『六十余州名所図会 安芸 厳島…

歌川広重『六十余州名所図会 周防 岩国…

歌川広重『六十余州名所図会 播磨 舞子…

歌川広重『六十余州名所図会 美作 山伏…

歌川広重『六十余州名所図会 備前 田の…

歌川広重『六十余州名所図会 備中 豪渓…
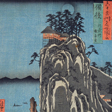
歌川広重『六十余州名所図会 備後 阿武…

歌川広重『六十余州名所図会 長門 下の…
山川 日本史小辞典 改訂新版 「山陽道」の解説
山陽道
さんようどう
(1)古代の七道の一つ。現在の近畿地方から中国地方の瀬戸内海側にそった地域で,播磨・美作・備前・備中・備後・安芸・周防・長門の各国が所属する行政区分。(2)これらの諸国を結ぶ交通路も山陽道と称し,「影面(かげとも)の道」ともよばれた。畿内から各国府を順に結ぶ陸路を基本に官道が整備され,ことに唐や新羅(しらぎ)からの外交使節の入京路にあたるため,瓦葺・白壁の駅館が建てられた。駅路としては大路で,各駅に20頭の駅馬がおかれる原則であり,「延喜式」では支路を含めて総計56駅に954頭の駅馬をおく規定であった。地方官として731年(天平3)に山陽道鎮撫使(ちんぶし),746年に山陽・西海両道鎮撫使を設置した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「山陽道」の意味・わかりやすい解説
山陽道
さんようどう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
防府市歴史用語集 「山陽道」の解説
旺文社日本史事典 三訂版 「山陽道」の解説
山陽道
さんようどう
現在の中国地方の瀬戸内海沿岸をいう。播磨 (はりま) ・美作 (みまさか) ・備前・備中・備後・安芸 (あき) ・周防 (すおう) ・長門の8カ国。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の山陽道の言及
【駅伝制】より
…大化改新後,7世紀後半の律令国家形成期には,駅鈴によって駅馬を利用しうる道を北九州との間だけでなく東国へも延ばしはじめたようであるが,8世紀初頭の大宝令では唐を模範とした駅制を全国に拡大することとした。すなわち朝廷は特別会計の駅起稲(えききとう)・駅起田(えききでん)(後の養老令では駅稲・駅田)を各国に設置させ,これを財源として畿内の都から放射状に各国の国府を連絡する東海・東山・北陸・山陰・山陽・南海・西海の7道をそのまま駅路とし,駅路には原則として30里(約16km)ごとに駅を置かせ,駅ごとに常備すべき駅馬は大路の山陽道で20匹,中路の東海・東山両道で10匹,他の4道の小路では5匹ずつとし,駅の周囲には駅長や駅丁を出す駅戸を指定して駅馬を飼わせ,駅家(うまや)には人馬の食料や休憩・宿泊の施設を整え,駅鈴を貸与されて出張する官人や公文書を伝送する駅使が駅家に到着すれば,乗りつぎの駅馬や案内の駅子を提供させることとした。その結果,もっとも速い飛駅(ひえき∥ひやく)という駅使は,大宰府から4~5日,蝦夷に備えた陸奥の多賀城からでも7~8日で都に到着することができた。…
【中国路】より
…江戸時代,瀬戸内海にそって設けられた街道で,西国路,山陽道,中国街道ともいう。1803年(享和3)の幕府大目付の訊問に対して,〈何国何之駅より何之駅![]() を中国路と相唱候哉,右体名目差極候ては難及挨拶候〉と答申しているように,その起点・終点も不明確で,起点を京都または大坂,終点を長門の大関・下関,豊前の大里などとする説がある。…
を中国路と相唱候哉,右体名目差極候ては難及挨拶候〉と答申しているように,その起点・終点も不明確で,起点を京都または大坂,終点を長門の大関・下関,豊前の大里などとする説がある。…
※「山陽道」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...




