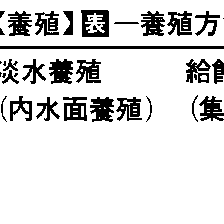翻訳|aquiculture
精選版 日本国語大辞典 「養殖」の意味・読み・例文・類語
よう‐しょくヤウ‥【養殖】
- 〘 名詞 〙
- ① 魚介、海藻などを人工的に飼養し繁殖させること。
- [初出の実例]「本法に於て漁業と称するは営利の目的を以て水産動植物の採捕又は養殖を業とするを謂ふ」(出典:漁業法(明治三四年)(1901)一条)
- ② 人工的に木を植えてふやし育てること。
- [初出の実例]「此沙地も亦拓て稚松を植え、森林を養殖せるは、森林官よりの注意と覚へたり」(出典:米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉四)
改訂新版 世界大百科事典 「養殖」の意味・わかりやすい解説
養殖 (ようしょく)
aquiculture
有用な水産生物を増やし,育てること。水産養殖ともいう。同じような意味で古くから使われてきたことばに〈増殖(水産増殖)〉があるが,養殖と増殖の概念は時代とともに変化しており,今日も統一されているわけではない。生物学的にみれば,養殖も増殖も人が労力を加えて対象生物種の繁殖率,成長率,生残率などを高め,収獲量を増やそうとする行為であるが,生産方式や経営の面から両者を区別する考え方が有力である。すなわち,養殖では対象生物種の生涯のすべてないしは大部分を人が管理し,その生産物および生産手段の所有者がつねに明らかであるのに対して,増殖では対象生物種の天然水域での繁殖と成長を助長することが目的であり,生産物は漁獲されて初めて所有者が決まる。また養殖が私企業として営まれるのに対し,増殖は公共的な事業として営まれることが多い。
→増殖
歴史
人の手で魚や貝を増やし,育てようとする試みは古くから行われていた。古代のエジプトなどでも行われていたと思われるが,そのはっきりした記録はなく,これらの魚がどのように管理されたかも明らかではない。しかし,前500年ころの中国の春秋戦国時代に,范蠡(はんれい)(陶朱公)が著した《養魚経》にはコイの養殖法が述べられており,最古の養魚書といえる。コイは日本でも大昔から飼われていたことが知られているが,これが産業化し始めたのは江戸時代の初期といわれ,やがて大和ゴイや信州ゴイなどの養殖品種ができ上がっていった。また,キンギョは1502年(文亀2)に初めて堺商人によって中国から移入され,江戸時代の中期ごろから養殖されるようになったという。
海ではカキの養殖が最も古い歴史をもち,紀元前にローマですでに養殖が行われており,カキ養殖場の争奪のために戦争になったこともあるという。日本のカキ養殖も300年以上の歴史があり,1673年(延宝1)小林五郎左衛門が広島湾で海中に竹ひびを建てて稚貝を付着させ,養殖を図ったのが始めと伝えられている。現在普及している貝殻を海中に垂下する採苗法は,大正末期に考案されたものであるが,そのヒントとなったのはアメリカに輸出された移殖用の親ガキの貝殻に付着していた稚貝が,親ガキは輸送中に死亡したにもかかわらず,生き残って成長したことであった。日本独特の水産物であるノリが天然採集からひび養殖に移行し始めたのは延宝年間(1673-81)以前といわれている。初めは大森付近の東京湾で独占的に行われていたが,文政年間(1818-30)以後,しだいに全国各地に伝えられていった。
魚の人工受精に初めて成功したのはオーストリアのヤコビーL.S.L.Jacobiで,1757年にマスを人工受精により孵化(ふか)させた。この成果はその後しばらく看過されていたが,19世紀後半に再認識され欧米各国に国立の孵化場が設立された。1877年,日本にアメリカ水産局からニジマスの受精卵1万粒が寄贈され,これを関沢明清が東京四谷の自宅の井戸水を用いて孵化させた。これが日本のニジマス養殖の始めである。明治になって始められたものにウナギの養殖がある。1879年に服部倉次郎が東京深川に2町歩(2ha)の池を造って経営を始めたという。ウナギ養殖が産業として確立し始めたのは明治末期から大正初期にかけてであり,静岡県,愛知県,三重県の3県が主産地となった。そして,昭和40年代の初めまではこの3県で全生産量の90%以上を占めていたが,その後,養殖法の進歩によって全国に産地が広がり,とくに温暖な気候と水利に恵まれた四国,九州さらには台湾での生産量が増大した。
琵琶湖や鹿児島県の池田湖には,河川のアユのようには大きくならないコアユが生息しており,古くは普通のアユとは別種と思われていた。しかし,石川千代松は両者は同種であり,コアユが大きくならないのは餌が足りないなど湖の環境条件のせいであると考え,これを証明するため,1909年に琵琶湖の西北岸にあった知内養魚場の池でコアユを人工飼料で飼育し,秋までに最大体長30cmに成長させることに成功した。これが現在広く行われているコアユを種苗とするアユの養殖や河川放流のもととなった。アユ養殖の種苗にはコアユのほかに,海岸で採捕された稚アユを人工的に淡水にならした海産稚アユも使われているが,これに着目したのは中野宗治で,1929年のことである。
海産魚類の短期蓄養はいろいろな魚種でかなり古くから行われていたが,長期にわたる養殖が行われるようになったのは比較的最近のことである。ブリ(ハマチ)養殖は1928年に野網佐吉が香川県で行ったのが最初とされているが,現在のように全国に広がったのは57年ころからである。ブリ養殖はモジャコと呼ばれる天然種苗を使って行われているが,天然種苗を大量に確保することの困難なタイ類の養殖が始まったのはブリ養殖よりさらに遅れ,人工種苗の生産技術の確立した65年以降である。
クルマエビは最も商品価値の高い水産生物であるが,養殖できるようになったのは藤永元作の研究に負うところが大きい。彼は第2次大戦前にすでに孵化幼生から成エビまでの飼育実験に成功していたが,1960年に事業規模での養殖を香川県下の廃止塩田を利用して始めた。クルマエビは海水養殖種のなかで人工種苗生産技術が最も早く確立したものであり,現在,タイ類やアワビなどとともに,養殖のみならず放流のための種苗も大量に生産されている。
分類
養殖の最も進んだ形態は,育成された親から人工的に採卵,孵化を行って種苗を生産し,その種苗を施設に収容し,人工飼料を与えて市場サイズまで育成するとともに,一部を親として利用するものである。このように養殖対象生物の生活史のすべてを管理するものを完全養殖といい,その段階まで達していないものを不完全養殖という。前者の例としてはコイ,ニジマス,マダイ,クルマエビ,後者の例としてはウナギ,アユ,ブリ,カキ,ホタテガイがあげられる。なお,アユ養殖では人工種苗による完全養殖も行われている。また,カキのように技術的には完全養殖が可能であっても,採苗の容易さや,採算面から天然種苗に依存しているものもある。餌料を与えているものを給餌養殖,与えないものを無給餌養殖という。無給餌の場合も,施肥を行って天然餌料の増加をはかる場合は施肥養殖と呼ばれている。普通,無給餌の場合は単位面積当りの収容量(放養密度)が低い粗放的養殖となる。粗放的養殖に対し,放養密度が高く,生産性の高いものを集約的養殖という。
河川湖沼の水や地下水を利用するものを淡水養殖あるいは内水面養殖といい,海水を利用するものを海水養殖(鹹水(かんすい)養殖)あるいは海面養殖という。淡水養殖はさらに人工池による池中養殖,農業用のため池や水田を利用するため池養殖や水田養殖(稲田養殖),湖などに網いけすを設置して行う網いけす養殖(小割養殖)などに類別される。池中養殖には新しい水をつねに給水する流水式,時間を限って給水する半流水式,水位を保つため以外には給水しない止水式,排水を処理して再利用する循環(ろ過)式などの別がある。海水養殖には陸上の人工池に海水をくみ上げて行う池中養殖,海面を堤で区画する築堤式養殖,網で区画する網仕切り式養殖,網いけすを設置する網いけす養殖(小割養殖),いかだや,はえなわから養殖かごなどを海中につるす垂下式養殖,杭からつるす簡易垂下式養殖,竹やそだ(細い木の枝)を浅海底に建てたり,網やすだれを海面に水平に張るひび養殖,網ひびやすだれひびを干出させないでつねに水面を浮動させる浮流し養殖(ベタ流し養殖),稚貝を浅海底に散布する地まき式養殖などがある(表)。
方法
養殖技術は種苗生産技術と育成技術とに大別され,養殖業でも種苗生産と育成は別々に営まれることが多い。
養殖に用いる種苗には天然種苗と人工種苗とがある。天然種苗は自然に生まれ育った稚仔を天然水域で採捕するもので,人工種苗をつくることが難しいものや,天然種苗のほうが経済的なものに利用される。例えば,ウナギ養殖に用いられる種苗は,12月~5月ごろ河川にのぼるため海岸近くに集まってきたシラスウナギをすくい採って,餌付けしたものである。餌付けは昔は露天の池で行われたが,現在は加温装置のついた池で行われている。初めイトミミズを与え,しだいに配合飼料に置き換えていく。給餌時間も,夜中から明け方へ徐々にずらし,最終的には夜明け後に餌をとるようにならす。ブリ養殖では5~6月ごろ,黒潮にのって北上する流れ藻についているモジャコと呼ばれる2~130gのブリ幼魚を採捕して種苗とする。カキ養殖,ホタテガイ養殖,アコヤガイ養殖(真珠養殖)では,これらの貝の産卵期である晩春から夏,浮遊幼生が付着幼生に変態するころあいを見計らって採苗器を海中に入れる。採苗器としては,カキではホタテガイやイタヤガイなどの貝殻をひもや針金で連ねたもの,ホタテガイではタマネギ出荷用の網袋に杉葉やハイゼックス縄を詰めたもの,アコヤガイでは杉葉を束ねたものが多くの場合使われている。人工種苗は人間の管理下で産卵,孵化させ,一定の大きさまで育てたものである。人工種苗生産においては,まず,よく成熟した親を確保しなければならない。親として天然産のもの(サケ,クルマエビなど)を使う場合と,養殖されたもの(コイ,キンギョ,ニジマス,マダイなど)を使う場合とがあるが,いずれにしても,産卵日を予測したり,人工採卵の日程を組むために,事前に成熟度を鑑別しなければならない。ときにはホルモン剤を投与して成熟を促進させたり,水温や日長時間を調節して成熟度を制御することも行われる(アユ,マス類)。
採卵は自然産卵の場合と人工採卵の場合とがあるが,だいたい生物種によって決まっている。自然産卵させるもののうち,コイやキンギョの場合はシュロなどで作られた魚巣を親魚池に入れ,これに産みつけさせ,タイ類では水面に浮き上がってきた卵をネットで採集する。アワビやクルマエビでは卵を水といっしょにくみとって静置し,沈んだ卵を集める。また,アワビなどの貝類では事前に水温変化,干出,紫外線照射した海水の注入など物理的あるいは化学的な方法で産卵を誘発させる。人工採卵には搾出法と切開法があり,前者はニジマスのように多回産卵するものに,後者はサケのように産卵後死んでしまうものに使われている。人工採卵された卵には人工受精が施される。人工受精法には水の中で卵と精子を混ぜ合わせる湿導法と,卵と精子だけを混ぜ合わせる乾導法とがあり,現在は受精率の高い乾導法が主に使われている。
受精卵は一定時間を経て孵化するが,その間の環境条件に十分留意する必要がある。とくに水温,溶存酸素量,塩分を適正に保つことや,紫外線,有害物質,振動などを防ぐことがたいせつである。孵化後しばらくは卵黄を吸収して栄養としているが,やがて餌を必要とするようになる。サケ・マス類は初めから配合飼料を食べるが,コイ,アユ,タイ類,クルマエビなどでは初期には生物餌料を与えなければならない。初期餌料となる生物は稚仔にとって食べやすく,消化されやすく,栄養のバランスがとれており,大量かつ確実にできるだけ安価に入手できるものでなければならない。このような条件を満たすものとして,コイやキンギョにはミジンコ類,アユやタイ類にはシオミズツボワムシ,クルマエビやアワビにはケイ藻がそれぞれ不可欠の初期餌料として使われている。これらの生物餌料はやがて魚貝肉ミンチや配合飼料に置きかえられ,種苗生産の段階から市場サイズへの育成に目標が移っていく。
養殖業は営利企業であり,生産効率を高めるために,高い放養(収容)密度で,短期間に育成する技術を志向する。しかし,放養密度には一定の限界があり,まず第1に溶存酸素量によって規定される。淡水養殖の場合,止水式と流水式では水中溶存酸素の供給に大きな違いがある。止水式では大気からの溶解と植物プランクトンの光合成によって供給され,養殖生物やその他の共存生物,有機物の分解,大気への拡散などによって減少する。普通,止水池の溶存酸素量は植物プランクトンの影響で夜間とくに夜明けごろに最低となるため,放養密度は夜間の溶存酸素量によって制約される。しかし,この間に曝気(ばつき)をしたり,新鮮な水を補ったりすれば放養密度を高めることができる。一方,流水式では放養密度は単純に流水量に比例する。一般に,流水式における放養密度は止水式に比べて数倍高い。海水養殖の場合は,海水の交流を妨げないような施設の設計や配置が決め手となる。
餌料の栄養,形状,保存性,価格,入手方法なども効率的な育成の重要な要因である。また,これらの条件を満たす餌料であっても,給餌方法,給餌時間,給餌回数,給餌量など,給餌技術もそれに加えて重要である。魚の場合,決まった時間と場所で魚群全体が飽食する量を与えることが多い。給餌回数は初めは多く,成長するにつれて減らしていくのが普通であるが,コイなどの無胃魚では成魚でも1日数回給餌したほうがよいとされている。体重当りの摂餌量は幼若なものほど大きく,成長するにつれて小さくなる。また,変温動物は適温範囲では高温ほど摂餌量が増加するので,高水温を維持することにより,育成期間を短縮することができる。一方,養殖の集約化が進むにつれ,養殖生物の排出物や残餌が増え,水質などの養殖環境が悪くなる。また,病害,とくに伝染病(魚病)が発生しやすくなる。水質の悪化や病害の増大は現在,いろいろな養殖生物において深刻な問題となっており,これらに対処するため,放養密度や給餌量の抑制,飼料添加物の使用,環境管理の強化などの方策がとられている。
養殖業によって利益をあげるためには,生産費を安くするとともに,販売を有利に進めることもたいせつである。出荷サイズはほぼ決まっており,必要時に必要量の出荷ができるように成長が調整される。出荷する場合,普通,取り上げの1~2日前から餌止めをし,取り上げた後もさらに2~3日間流水中で絶食させる。この作業を活(い)けしめといい,活魚輸送中の死亡を防ぐ効果がある。さらに,臭みを抜いたり,肉質を向上させる目的でも行われる。養殖は単価の高い中・高級種を対象とするので,生産物の品質の維持,向上はときには生産効率以上に重要な課題となっている。
執筆者:若林 久嗣
日本の養殖業
養殖の本質は,水産物を種苗との対比の歩留りにおいて高率であるように,対象水族の成長過程を人間の掌握下におき,栽培ないしは飼育の手を加えるなど,成長環境の制御を行うことである。産業としての養殖業は,需要が旺盛であるか,高級水産物とされているのに,その成長過程の歩留りが天然の水界内では低いために漁労的方法では需要に対応できず,したがって養殖の費用をかけても成長過程を農業に準じた管理のもとにおいたほうが利益があるような場合に成り立つ。
養殖は日本では江戸時代にまでさかのぼることができるが,第1次産業のなかの一つの有力な部門となったのは第2次大戦後で,養殖が経済的に成り立つ条件がようやく整ってきたからである。まず第1段階として,外貨獲得と漁業制度改革が絡まって真珠養殖の発展が,それにカキとマス養殖の発展が顕著であった。高度経済成長の進展は,一方で所得の上昇と食生活の向上によって高級水産物に対する需要を大きくし,他方で養殖設備,資材の価格を割安にし性能を高めた。また養殖対象の生物学的研究が進んで,種苗生産や養殖方法の技術に大きな進歩があった。また肉食魚を養殖する場合に必要なイワシ,サバなどの餌料用多獲性魚の漁労方法が発達する反面,それらの食用需要が減退し,それだけ養殖用餌料が安く大量に確保できた。そのうえ多くの漁家を抱えた沿岸漁村では,養殖業の導入によって自立漁民層を定着させようとし,旧網元層や水産会社も養殖に関心をもった。このように高度成長期を通じて全体として順調に伸びてきた養殖業も,1970年代の後半から,その成長にかげりが出始めた。過剰生産,価格の低迷の一方で,石油危機以後の資材費の上昇が採算を悪化させているためである。また経営効率を高めるための過密養殖が漁場の水質を悪化させ,工場排水や赤潮,油濁などの外部からの被害とともに問題となってきている。
94年における日本の漁業・養殖業の総生産高は810万t,うち海面養殖が134万4000t,内水面養殖が7万7000tである。金額でみると総生産額2兆3730億円,うち海面養殖は6270億円,内水面養殖は920億円となっている。すなわち,養殖業は生産量では総生産量の17.5%にすぎないが,金額では30.3%を占めており,養殖生産物は漁業生産物に比べて単価が高いことがわかる。とくに内水面では養殖業が金額でみて56%を占めている。生産の多い品目は海面養殖ではブリ類(14.9万t),タイ類(7.7万t),クルマエビ(0.2万t),カキ(22万t),ホタテガイ(20万t),ノリ類(48万t),ワカメ(8.8万t),内水面養殖ではウナギ(2.9万t),コイ(1.3万t),マス類(1.8万t),アユ(1.2万t)などである(養殖真珠については〈真珠〉の項を参照されたい)。1980年と比較すると,94年の養殖業の規模は生産量で1.3倍,金額で1.2倍に伸びており,漁業全体の減少(生産量で0.73倍,金額で0.86倍)と対照的である。
執筆者:浦城 晋一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「養殖」の意味・わかりやすい解説
養殖【ようしょく】
→関連項目漁業|水産業|マリノフォーラム21
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「養殖」の意味・わかりやすい解説
養殖
ようしょく
有用水産生物の育成に関することばで、一般的には水産養殖の略称。生物の生活史の全部、あるいは一部を人間が管理して育て、数・量の増収を図ることを目的とする。これらの事業を総括して、「養う」という概念より「増やす」という概念を強調して増殖(水産増殖)のことばが用いられることもあり、養殖と増殖とのことばの使い方は明確に区別されているわけではない。対象生物を育成する場合、たとえばウナギの養殖、ハマチの養殖、カキの養殖などとよばれ、また育成場所によって池中養殖、河川養殖、海面養殖などとよばれている。
なお、養殖の語は有用陸生動物の育成事業でも、ミンクの養殖などのように使われることがあるが、多くは養豚(ようとん)とか養鶏(ようけい)などのことばが定着している。
[出口吉昭]
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「養殖」の意味・わかりやすい解説
養殖
ようしょく
raising culture
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の養殖の言及
【生簀】より
…なお船のいけすのことを活間(いけま)とかかめ(甕)とか呼ぶことも多い。 従来はいけすというと比較的短期間飼っておく小規模のものが想起されたが,近年は養殖に用いられる大規模ないけすもある。内水面ではコイ,ウナギ,海面ではハマチ,マダイなどの養殖に用いられる。…
※「養殖」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...