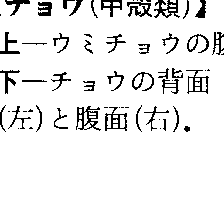翻訳|butterfly
精選版 日本国語大辞典 「ちょう」の意味・読み・例文・類語
日本大百科全書(ニッポニカ) 「ちょう」の意味・わかりやすい解説
チョウ(蝶)
ちょう / 蝶
butterfly
昆虫綱鱗翅(りんし)類(目)Lepidopteraに属する昆虫の一部(一群ではない)の呼び名。世界に産する種は約1万5000種、日本産は約260種。高等植物のまったく生えていない極地や砂漠を除いて全世界に広く分布するが、一般に植物相の豊富な地域ほどその種類は多い。
[白水 隆]
チョウとガの区別
一般に鱗翅目をチョウとガの二つに大別するが、この両者は対立する自然群ではなく、この用法は慣例的なものである。したがって、両者を厳密に区別する特徴を指摘できないのは、むしろ当然である。外国ではチョウとガをとくに区別しないことが多い。たとえば、フランス語のpapillon、ドイツ語のSchmetterlinge、イタリア語のfanfala、スペイン語のmariposaなどは、チョウとガを含めたことばである。
[白水 隆]
鱗翅目の分類
鱗翅目は分類学的には同脈亜目と異脈亜目に大別される。ここでその特徴とそれに含まれる上科の名称を示すと次のようになる。
〔1〕同脈亜目Homoneura 原始的な群で、前ばねと後ろばねはほぼ同形、後ろばねの脈(翅脈)は10~12本。前ばねの後縁の基部に小さな翅垂があって後ろばねを挟む。この亜目のなかでもっとも原始的なコバネガ上科では口器は大あごがあってそしゃく型。コバネガ上科Micropterygoidea、スイコバネガ上科Eriocranioidea、コウモリガ上科Hepialoideaの3上科が同脈亜目に含まれる。種類数は少ない。
〔2〕異脈亜目Heteroneura 同脈亜目より高等なもので、後ろばねの脈は8本以下。翅垂はなく、そのかわりに鉤(かぎ)形の密毛(翅刺)が後ろばねの前縁の基部にあるか、あるいはこれを欠く。口器は吸収型。種類数は多く鱗翅目の99%以上の種がこの亜目に入る。ムグリチビガ上科Nepticuloidea (Stigmelloidea)、マガリガ上科Incurvarioidea、ボクトウガ上科Cossoidea、ヒロズコガ上科Tineoidea、ハマキガ上科Tortricoidea、マダラガ上科Zygaenoidea、カストニア上科Castonoidea、メイガ上科Pyralidoidea、シャクガ上科Geometroidea、ヤガ上科Noctuoidea、カイコガ上科Bombycoidea、スズメガ上科Sphingoidea、イカリモンガ上科Calliduloidea、セセリチョウ上科Hesperoidea、アゲハチョウ上科Papilionoideaの15の上科がこの亜目に含まれ、これらの上科の大部分はさらに多くの科に分類される。
以上のうち、異脈亜目に属するセセリチョウ上科とアゲハチョウ上科の2群をあわせてチョウとよび、それ以外のすべての鱗翅目をガとよぶ。したがって、チョウとガは対立する二つの自然群ではないが、一般にいわれている次の特徴は両者を区別する目安となる。
(1)チョウでは触角の形は先端に向かって徐々に、あるいは急激に膨らんだ棍棒(こんぼう)状かばち形、または先端部近くに膨らんだ部分があり、それより徐々に細まる。ガでは糸状または種々の程度の櫛歯(くしば)状。
(2)止まるときにチョウははねを立てるが、ガは水平に開く。
(3)チョウは昼間、ガは夜間に活動する。
(2)(3)は日本産のものでも例外が多く、判断の基準にはならないが、(1)の特徴は日本産のものに限っては例外がないので(外国にはある)、この特徴で区別は可能である。
[白水 隆]
形態
鱗翅目はすべて完全変態を行うので、チョウには成虫、卵、幼虫、蛹(さなぎ)の四つのステージがある。
[白水 隆]
成虫
成虫の体は、頭部、胸部、腹部の3部に分かれ、頭部には1対の触角、1対の複眼および口器、胸部には2対のはね、3対の脚(あし)がある。触角は多数の環節からなり、有鱗あるいは無鱗、感覚器を備えている。複眼はきわめて大きくて頭部の過半を占め、単眼はない。口器は小あごの変形した吸収管となり、下唇鬚(かしんしゅ)は3節で前方に突出する。胸部は、前胸、中胸、後胸の3節からなり、各節に1対の脚があるが、特定の群では種々の程度に前脚の退化がみられる。脚は基部より、基節、転節、腿節(たいせつ)、脛節(けいせつ)、跗節(ふせつ)の5節よりなり、その先端につめがある。中胸、後胸にはそれぞれ1対の膜状のはねがあり、これを支える中空の脈がその中を走っており、これを翅脈といい、その様相を脈相とよぶ。脈相はチョウの分類上の特徴として多く使用される。はねの表裏には屋根瓦(がわら)のような状態で鱗粉(鱗片)および鱗毛が生えており、これらは毛の変形したものである。種によっては雄にだけみられる特別の形の発香鱗があるが、これははねの正常鱗の中に散らばっていることもあり、ある部分に集まっていることもある。
腹部は10節よりなり、外見的には特別の構造はないが、末端の9~10節あるいは8~10節は、雄では変形して交尾器をつくり、雌にもそれに相応する変形がおこっている。交尾器の形態は、雌雄ともに分類上の重要な特徴としてきわめて多く使用される。
[白水 隆]
卵
卵は、球形、半球形、まんじゅう形、砲弾形、ビヤ樽(だる)形などさまざまな形があって、卵殻の表面に稜(りょう)や突起、彫刻などをもつものが多く、卵の形態で種、属、科などの判定のできる場合が多い。
[白水 隆]
幼虫
幼虫は普通細長くて円筒形、ときにワラジムシ形。頭部1節、胸部3節、腹部10節の計14節からなるが、腹部末端部の分節はかならずしもつねに明瞭(めいりょう)ではない。胸部には成虫と同じく3対の胸脚、腹部には第3~第6節および第10節に5対の腹脚があり、第10節のものはとくに尾脚とよぶ。頭部の形態、胴部(胸部+腹部)の形態はさまざまで、特異な突起や棘(とげ)をもつものなどがあり、その形態、色彩によって、種、属、科の判定ができる場合も多い。
[白水 隆]
蛹
蛹はすべての付属物(触角、口器、はねなど)がキチン質の鞘(さや)に収まって胴部に密着しており、被蛹(ひよう)とよばれ、原始的な鱗翅目にみられる裸蛹(らよう)(付属物が胴部から遊離)は存在しない。チョウ類の蛹は、尾端と吐糸による負ぶい紐(ひも)で体を固定している帯蛹(たいよう)(アゲハチョウ科、シロチョウ科、シジミチョウ科、セセリチョウ科)と、尾端を固定して頭を下にして垂下する垂蛹(すいよう)(タテハチョウ科、マダラチョウ科、ジャノメチョウ科、テングチョウ科)の2形式が本質的なもので、地表で薄い繭をつくってその中で蛹となるウスバシロチョウ類や、地表のくぼみや石の下などに横たわって蛹化するタカネヒカゲ属、ベニヒカゲ属は例外で、前記の基本型から二次的に変化したものである。
[白水 隆]
生態
チョウの幼虫は一般に特定の植物の特定の部分を食物とするので、卵は、孵化(ふか)した幼虫が容易にその部分に到達できるような場所に産み付けられる。したがって、食草の新芽、花芽などに産卵されることがもっとも多い。アゲハチョウはその幼虫の食草であるミカン科の植物に産卵し、その場合に堅い古葉を避け、新芽、若葉を選ぶが、その結果、孵化した幼虫は適当な食物上に産まれ落ちることになる。生まれたばかりの幼虫は堅い葉を食べることができないので、古葉に生まれた幼虫は新芽を探して長距離をさまよい歩かねばならず、新芽にたどり着くまでに天敵に襲われたり、また新芽にたどり着くことができず餓死するものが多い。母チョウが幼虫の食草を感知するのは、その植物から発散するにおい(化学成分)によるものである。アゲハチョウがきわめて合理的に古葉を避けて新芽、若葉に産卵するのは、新芽、若葉からのにおいの発散が古葉よりも強いので、本能的にそれに誘引されているにすぎない。
[白水 隆]
幼虫の習性
孵化した幼虫は卵殻の一部または全部を食べることが多いが、その真の意味はまだよくわかっていない。幼虫は多くは食草の葉表または葉裏、あるいは枝上、幹上、ときに食草近傍の他物に静止し(その場所は種によってほぼ一定している)、若干の時間的間隔を置いて1日に数回の摂食を行うが、葉の食べ方にはそれぞれ特徴があって、葉につけられた食痕(しょくこん)によってその存在が容易にわかることもある。セセリチョウ科および特定の一部の種では幼虫は葉を折り返したり、つづったりして巣をつくり、その中に隠れる。また、タテハチョウ科の一部の種では、幼虫の若齢時代に葉の一部をかみ切ってカーテン状に垂らしてその奥に隠れたり、食べ残した葉の中脈の先端に糞(ふん)を吐糸でくっつけてそこに身を潜めて天敵の目をくらませたりして身を守るものがある。幼虫は数回の脱皮後、老熟して蛹となるが、幼虫の齢数(脱皮回数)は種によって一定しており、たとえばシジミチョウ科では4齢、アゲハチョウ科、シロチョウ科では5齢が原則、タテハチョウ科では5、6齢である。しかし、この齢数は種により絶対的に決まっているのではなく、5齢を経過すべきアゲハ属Papilioの幼虫が4齢で蛹化したり、6齢で蛹化したりすることもある。アゲハ属の場合の齢数の増加は、不良な栄養条件によって引き起こされるものと考えられる。
[白水 隆]
蛹化
老熟した幼虫は一般に蛹化場所を求めて移動し、垂蛹となるものは蛹化場所に吐糸して糸株をつくり、それに尾脚の鉤をかけて垂下するが、帯蛹となるものは糸株に尾脚の鉤をかけ、さらに吐糸で負ぶい紐をつくり、それを後胸部にかけて体を固定する。このときには幼虫の体は縮んで、その色彩はやや透き通った感じとなるが、この状態を前蛹とよぶ。前蛹はおよそ1、2日で脱皮して蛹となる。
このように卵、幼虫、蛹の期間の長さは温度によって左右され、高温で短く、低温で長くなるのが一般である。もっとも休眠状態にあるものでは、温度の高低はその期間の長さに関係しない。
[白水 隆]
季節型の成因
チョウは種類によって著しい季節的変異を現すものがある。すなわち、発生する季節によってはねの色彩や模様が違うのである。日本産でもっとも顕著な例はアカマダラやサカハチチョウで、春型と夏型は一見すると別種のようにみえる。タテハモドキの季節型も同様で、夏型は翅形が丸みを帯び、はねの裏面には明瞭な目玉模様が現れるが、秋型ははねがとがり、裏面は枯れ葉模様となって目玉模様は消失する。このような季節的な成虫の変異は、幼虫時代の日長(一日中の昼の長さ)と温度で決まるが、おもな要因は日長である。タテハモドキの場合、その幼虫を25℃という一定条件の温度のもとで、長日(13時間以上)で飼育すると夏型になり、短日(12時間以下)で飼育すると秋型になる。高温は夏型化を促進し、低温は秋型化を促進する。このことは、キチョウ、ツマグロキチョウの同様な実験からも明らかである。日長は6月下旬でもっとも長く、12月下旬がもっとも短い。秋になって短日に向かい、温度が下がってくると秋型が発生してくるわけはこれで理解できる。成虫で冬を越す秋型は生理的には休眠型であり、低温に耐えて越冬できるが、夏型にはその能力がなく、これは不良な環境に対する適応である。夏型と秋型、春型と夏型を分ける日長(これを臨界日長という)は種によって多少は違っているが、それはおよそ12時間と13時間の間にある。
[白水 隆]
雌雄間の認知
チョウの雄が同じ種の雌をどうして認知するか(またはその逆の場合)という問題はまだよくわかっていない。モンシロチョウは人間の目には雄も雌も白く見えるが、紫外線写真を撮ってみると、雄は黒く、雌は白い。昆虫の視覚は人間の可視域よりかなり紫外線(短波長)のほうに偏っており、モンシロチョウの見えている世界は人間とはかなり違っているらしい。ナミアゲハの雄は、ある大きさの範囲の黄と黒の縞(しま)模様に引き付けられる。黄と黒の縞模様は、すなわち雌のはねの模様であるが、その模様は色紙でつくった人造物でもその効果は同様である。ガの場合は、雌がそれぞれの種に特有のフェロモンという一種の化学物質を出し、雄はそのフェロモンに誘われて雌のところに集まってくる。チョウの場合はガと違い、まず視覚によって雌の存在を探知する。
[白水 隆]
日本産チョウの分類
日本産のチョウは、普通次の2上科、9科に分類される。
〔1〕セセリチョウ上科Hesperoidea セセリチョウ科Hesperiidaeの1科のみが含まれる。
〔2〕アゲハチョウ上科Papilionoidea アゲハチョウ科Papilionidae、シロチョウ科Pieridae、シジミチョウ科Lycaenidae、ウラギンシジミ科Curetidae、テングチョウ科Libytheidae、マダラチョウ科Danaidae、タテハチョウ科Nymphalidae、ジャノメチョウ科Satyridaeの8科が含まれる。
以上のうち、ウラギンシジミ科を分けずに、これをシジミチョウ科に入れる場合も多い。また、マダラチョウ科、ジャノメチョウ科をタテハチョウ科のなかに含め、それぞれをタテハチョウ科のなかの亜科とすることもある。しかし、前記の8科に含まれる種はそれぞれ一つの自然群となっていることは疑いなく、それを科とするか亜科とするかはほかとの比較の問題であって、本質的にとくに重要なことではない。
[白水 隆]
人間生活との関係
チョウは花とともに自然界でもっとも美しいものの一つとして、古くから人間に親しまれてきた。したがって文学、芸術上に取り上げられている例が多い。日本では郵便切手の図案となったものは、現在のところ国蝶のオオムラサキのほか、ミカドアゲハ、ギフチョウ、モンシロチョウ、ウスバキチョウ、キリシマミドリシジミの6種にすぎないが、外国ではチョウの切手はきわめて多く発行されている。明治時代以降、チョウのはねを装飾用に利用することが考えられ、コップの受け皿、盆、しおり、テーブルクロスなどにチョウのはねがはめ込まれて商品として販売されている。近年、展翅標本を額縁や標本箱に収めたものが装飾用として市販されるようになった。
農業上の害虫としては、日本では、幼虫がイネを害するイチモンジセセリ(ハマクリムシ、ツトムシ)、キャベツにつくモンシロチョウ(アオムシ)、栽培豆類の実を食害するシジミチョウの仲間(ウラナミシジミ、オジロシジミなど)、ミカンの苗木について害を与えるナミアゲハ、最近、沖縄本島に侵入してバナナの葉を食害するバナナセセリなどがあるが、とくに著しい害を与えるようなものはない。衛生害虫となるものは皆無である。全般的にはチョウは人間に対しては害より益のほうが大きいと判断される。
[白水 隆]
民俗
不気味なチョウの飛び舞うさまは、死者の魂の行き交うさまと結び付けられている。『和漢三才図会(わかんさんさいずえ)』68には、越中(えっちゅう)立山(たてやま)の地獄道の地蔵堂について、「毎歳七月十五日ノ夜、胡蝶(こちょう)数多(あまた)出テ此(こ)ノ原ニ遊舞ス、呼(よび)テ生霊市(しょうりょういち)ト曰(い)フ」と記されている。そのほかの地方でも、盆のころの黒いチョウは仏様の乗り物とされ、夜のチョウはその使いなどと伝えられる。
一般に、チョウが家に入ると盗人(ぬすっと)がくる、病人が死ぬなどというように、よくないことのしるしと考えられているが、土地によっては、チョウが家に入ると金が集まる、縁談がくるなどといって、逆にめでたいことのしるしとも考えられている。このほか、オコリチョウをとらえると、「瘧(おこり)」という病を患うとか、ミヤジマチョウを殺すと、宮島参りの舟が沈むなどと戒められており、チョウが家に入ると、雨が降るなどというような、天気の予知に関する伝えも少なくない。チョウのさなぎは種油につけて傷薬に用いるなど、民間療法に属することも知られている。
[大島建彦]
ビルマ語では肉体を離れやすいと信じられている霊魂のことを「蝶霊」とよぶという。チョウがはねをばたつかせるような音をたてて飛ぶからだといい、「蝶霊」が身体から抜け出ると、その人物は病気になり、それが永久に戻らなければ死を意味すると考えられていた。このような肉体からの離脱が可能な霊魂の観念は、全世界的に存在し、もっとも多くは鳥と結び付けられるが、チョウとの結合も、鳥の場合と同様、その飛ぶという属性が大きく関与していると考えられる。『荘子(そうじ)』のなかには夢で蝴蝶(こちょう)になるという有名な逸話がある。また、北アメリカの先住民であるピマの神話では、創造主がチョウの姿になって人々に適したよい土地をみつけるために飛び続けるという。南アメリカのデサナの人々が恐れる精霊は、背中を美しい南アメリカ特有の青いチョウで覆われているが、この場合のチョウは彼らにとっては凶兆である。一方、チョウが吉兆となることもあり、ドイツではチョウは子供を連れてくるといわれ、アメリカではチョウが家に迷い込むのは近く結婚がある知らせだともいわれる。
[横山廣子]
文学
早く『懐風藻(かいふうそう)』に「柳絮(りうじょ)も未(いま)だ飛ばねば蝶先(てふま)づ舞ひ」(紀古麻呂(きのふるまろ))とあり、漢詩文からの風物らしい。『荘子』の「蝶の夢」の故事はとくによく知られ、和歌にも詠まれている。和歌の例はあまり多くはないが、「散りぬれば後はあくたになる花を思ひ知らずもまどふてふかな」(『古今集』物名(もののな)・遍昭(へんじょう))には「蝶」が懸けて詠まれているといわれ、『古今六帖(ろくじょう)』6にも2首が収められ、『うつほ物語』「藤原の君」にも蝶の歌がみえる。『枕草子(まくらのそうし)』「虫は」の段に名を連ね、「三条の宮におはします頃(ころ)」の段の「みな人の花や蝶やといそぐ日も我が心をば君は知りける」という皇后定子(ていし)の歌に詠まれている。『源氏物語』には「蝶」「胡蝶(こちょう)」として4例みえる。『堤中納言(つつみちゅうなごん)物語』「虫めづる姫君」には、「人々の花や蝶やめづるこそはかなくあやしけれ」といって、毛虫をかわいがる風変わりな姫君が登場する。季題は春。「蝶の飛ぶばかり野中の日影かな」(芭蕉(ばしょう))。
[小町谷照彦]
『井上寛・白水隆他著『原色昆虫大図鑑Ⅰ 蝶蛾篇』(1959・北隆館)』▽『朝比奈正二郎他著『動物系統分類学 第7巻 上中下』(1970~1972・中山書店)』▽『安松京三・朝比奈正二郎他著『現代生物学大系 第2巻』(1973・中山書店)』▽『P・スマート著、白水隆監修『世界蝶の百科 日本語版』(1978・秀潤社)』▽『福田晴夫他著『原色日本蝶類生態図鑑Ⅰ~Ⅳ』(1982~1984・保育社)』

チョウの体制模式図(成虫、蛹、幼虫)

チョウの体制模式図(はね、頭部、脚部)

世界のチョウ(1)〔標本写真〕

世界のチョウ(2)〔標本写真〕

世界のチョウ(3)〔標本写真〕

世界のチョウ(4)〔標本写真〕

アゲハチョウ

アゲハチョウの生活史(1)卵

アゲハチョウの生活史(2)孵化

アゲハチョウの生活史(3)若齢幼虫

アゲハチョウの生活史(4)終齢幼虫

アゲハチョウの生活史(5)蛹

アゲハチョウの生活史(6)羽化

アオバセセリ

アオバセセリの幼虫

アカタテハ

アサギマダラ

ウスバアゲハ

オオムラサキ

キアゲハ

キアゲハの幼虫

キタテハ

キタテハの幼虫

キチョウ

ギフチョウ

ギフチョウの幼虫

ゴイシシジミ

ジャコウアゲハ

ジャコウアゲハの幼虫

スジグロシロチョウ

ツマキチョウ

ツマグロヒョウモン

テングチョウ

ベニシジミ

モンシロチョウ

ヤマトシジミ
チョウ(寄生虫)
ちょう
carp louse
[学] Argulus japonicus
節足動物門甲殻綱鰓尾(さいび)目チョウ科に属す、淡水魚類の寄生虫。日本からヨーロッパ、アメリカに広く分布する。キンギョ、コイ、フナなどの体表に付着するが、宿主から離れて泳ぐこともできる。体長5ミリメートル前後が普通であるが、大きいものは約1センチメートルに達する。背腹に扁平(へんぺい)で、円に近い楕円(だえん)形。甲の側葉の発達には変異があり、短い場合は第3遊泳脚をわずかに覆う程度、長い場合は第4胸脚を完全に覆う。腹面にある第1小顎(しょうがく)の変形した吸盤と触角の変形した鉤(かぎ)で魚の体表に密接し、左右の吸盤の間にある刺針で毒液を注入し、吻(ふん)で宿主の体液を吸収する。このため多数の個体が寄生すれば魚は衰弱死する。卵は水草などに産み付けられるが、15~30日、体長0.7~0.9ミリメートルで孵化(ふか)し、7回の脱皮を経て成体になる。孵化した幼生は吸盤をもたず、第1小顎は強い鉤になっているが、宿主に出会うとすぐ付着する。3、4日で第1回の脱皮を行うが、第4回目の脱皮で吸盤ができる。駆除は、ピンセットで取り除くのが確実であるが、殺虫剤ディプテレックスなどの薬浴も有効である。
チョウ類は3属約100種知られているが、海産のウミチョウA. scutiformisが最大で、体長3センチメートルに達する。この種はフグ、マンボウなどの体表につき、淡青色の地に紫褐色の斑点(はんてん)が多数ある。
[武田正倫]
改訂新版 世界大百科事典 「ちょう」の意味・わかりやすい解説
チョウ (蝶)
butterfly
全体から受ける印象でチョウは多くの人に花と同じようにうけ入れられ,美しいものの代名詞の一つでもある。翅のあざやかな色彩と花に舞う姿は陽性で,古くから美術工芸品のデザインとしてとり上げられ,文学作品にもしばしば登場するなど一般の関心も高く,昆虫の中ではもっとも親しまれているグループといえよう。こうした背景に支えられて研究の対象として興味をもつ人も多く,アマチュア研究家による新事実の紹介も今なお少なくない。それだけ情報量が多く多角的な分析も試みられていて,他の昆虫とは比較にならぬほど細かいデータが整いつつある。
チョウとガ
一般的には今でもこの両者についての比較や区別点があげられ,とくに児童図書などには詳しく紹介されていることがあるが,その差異はすべて便宜的なものであって画然と区別することはできない。たとえば翅を開いてとまるチョウも少なくないし,昼間飛び回り花のみつを吸いにくるガも多い。両者を区別しようとする傾向は国民性による思考の差で,英語には別々の単語があるが,ドイツ語やフランス語には共通の単語(ドイツ語はFalter,フランス語はpapillon)に〈昼の〉または〈夜の〉という形容詞がつくだけで固有の単語はない。元来鱗翅目として共通する形質をもつ一元的な系統の中に昼間にだけ活動する一群(チョウ)が生じたが,他の多くの系統(ガ)と本質的に違うまでにはなっていないのが両者の関係である。
系統進化
チョウの起源や系統に関する資料はきわめて少なく化石の数もごくわずかであるから,そのほとんどは推定による仮説の域をでない。現在知られている最古のチョウの化石は新生代古第三紀の漸新世から見つかっている。地史的にはウマの定向進化が始まって大型化し,ゾウの祖先とされるパレオマストドンが現れた時代でもある。つまり古生代のデボン紀に出現した昆虫類の一員としてトビケラ目に近い群から分化したと考えられる鱗翅目は,中生代ジュラ紀に特徴をそなえた一群として発展しはじめたと推定される。しかも白亜紀に入って被子植物の多様な分化が起こり,それに従って植物に依存する鱗翅目もこれに適応する形で発展したと考えられる。ただそのほとんどの種が夜行性か薄暮に活動するいわゆるガであって,チョウ(昼行性で口吻(こうふん)が長く訪花習性があると推定される)の仲間は新生代になってから昼間咲く花の増加とともに出現したと思われ,現存する科のほとんどが漸新世に存在している。
これは植物との共進化が爆発的に起きたことを示すもので第四紀洪積世の化石は現存するチョウとほぼ一致している。したがってチョウは昆虫類の中では出現がもっとも新しく,鱗翅目の特殊化した一群であることは明白である。ただすでに多くの鱗翅類によって種ごとに特定の植物を食物として占められているために,後から分化したチョウ類はいやなにおいや味のする植物またはアルカロイドやキノンなどの有毒成分を含む植物を食べなければ生き残れない状態であったろう。その結果,特有の体臭をもつものが多く,捕食者にきらわれて生残率が高くなり,同時に昼間活動できるようになったものと思われる。
現在知られている鱗翅目は約14万種であるが,このうちチョウ類は約1万8000種である。これはチョウに限ったことではないが,植物に依存する昆虫はその植物の生育する環境や気象条件に適応した結果独自の特徴をもち,科や属のレベルの分化が起こったと考えられる。
分類
体のどの特徴で分類するかは学者の考えで異なるが,鱗翅目Lepidopteraの場合は前翅と後翅の翅脈の相違で区分する方法があり,前・後翅の形と翅脈がほぼ同じのものを同脈亜目Homoneura,そうでないものを異脈亜目Heteroneuraとし,おのおのをさらに細分化した。しかし現在用いられている方法は雌の生殖口が一つのものを単門類,二つに分かれているものを二門類とし,後者をさらに三つに分け計4亜目を細分するものである。4亜目は21上科に分けられ,このうちの2上科がチョウに当たる。アゲハチョウ上科Papilionoideaは11科に分けられ,セセリチョウ上科Hesperioideaにはセセリチョウ科Hesperiidaeが属している。アゲハチョウ上科に属する11の科の特徴は次のとおりである。
(1)アゲハチョウ科 大型種が多く熱帯アジアには美しいトリバネアゲハ属が分布している。一方,中央アジアや寒冷地にはウスバシロチョウ属が分布していて,幼虫は刺激をうけると頭と前胸部の間から臭角を出す。ミカン科,ウマノスズクサ科,ケシ科などをおもに食べ世界で約600種が知られている。
(2)シロチョウ科 中型種が大半を占め翅の色は白色や黄色が多いが熱帯産のものにはオレンジ色や赤い斑紋のある種もある。幼虫は緑色で,いわゆる青虫とよべるタイプが多く,アブラナ科,マメ科などの植物を好む傾向がある。全世界には約1000種が知られている。
(3)マダラチョウ科 中型から大型の種が多く細長い体に対して翅の面積が大きく飛び方はゆるやかである。幼虫は有毒植物を食べる種類が多いために成虫ともどもいやなにおいや味で,捕食者からきらわれ〈擬態〉のモデルになっているものが多い。全世界から約450種が知られている。
(4)ジャノメチョウ科 褐色を基調とする翅には眼状紋(目玉模様)のある種類が多く中型種が大半を占める。温帯から寒帯に分布するものは明るくひらけた場所を好み,温帯から熱帯に分布する種類には暗い林の中などを好むものが多い。幼虫は単子葉植物(主としてイネ科)を食べる。全世界に約2500種が知られている。
(5)フクロウチョウ科 中央および南アメリカに分布するチョウで,後翅裏面にある大きな眼状紋がフクロウの目を連想させるところからこう命名されたチョウとその近縁種約80種のグループ。ジャノメチョウ科と近縁で,幼虫は単子葉植物(たとえばバナナなど)を食べる。
(6)ワモンチョウ科 東洋区やオーストラリア区の熱帯に分布する大型または中型のチョウで,成虫は夜明けと夕方に活動し主として森林内にとどまる。系統的にはジャノメチョウに近く幼虫が単子葉植物を食べるのも共通している。全世界に約100種が知られている。
(7)モルフォチョウ科 金属光沢に輝く翅をもつ種類が多いが,なかにはまったく光沢のないものもある。系統的にはタテハチョウやワモンチョウに近く,むしろそれらの祖先型と考えられる。南アメリカの熱帯地域にのみ分布し約80種が知られている。
(8)タテハチョウ科 小型から大型まで多様なグループで熱帯に分布するものは色彩がはでなものが多い。科の特徴としては,成虫の前脚が退化変形して歩行には用いず感覚器官になっていることがある。幼虫は体じゅうにとげのはえている型とナメクジ型に二分される。全世界に約3500種が知られている。
(9)テングチョウ科 口吻を左右から包む下唇のひげが長くのびているところから日本ではテングと命名され,世界に約10種が知られていて分布はきわめて局地的である。第三紀の化石が2種発見されていて(北アメリカ),系統的には古いチョウである。幼虫がニレ科のエノキ類を食べることは共通している。
(10)シジミタテハ科 小型種が多く名まえのようにシジミチョウとタテハチョウの両方に似た形質をもっているが,よりシジミチョウに近いと考えられる。翅の形には変化が多く色彩も多様で美しいものが多い。中央および南アメリカの熱帯に分布し約1000種が知られている。
(11)シジミチョウ科 小型種の大きなグループで世界中に分布し,一部は極地で採集された例も報告されている。幼虫の食性は植物に依存するものが大部分であるが,アリと共生する種類やアブラムシを食べる肉食性のものもあって変化に富んでいる。全世界に約5500種が知られていてチョウの中では最大の科である。
次にセセリチョウ上科に属するセセリチョウ科は今まで述べたアゲハチョウ上科のものとは形態的にも次の点で異なる。(1)触角の先端がかぎ状かとがる。(2)体が翅の大きさに比べて太い。(3)後翅基部に翅棘(しきよく)があり前翅と連動できる種がある。しかし必ずしも系統的にはガに近いというわけではなく独特な方向に分化したグループと考えるべきである。幼虫は双子葉植物を食べるものもあるが単子葉植物に依存するものが多い。全世界に約3000種が知られているが約2000種は南アメリカに分布する。
日本のチョウ相
現在日本にはおよそ230種のチョウが分布している。しかしこれは領土内で明らかに生活が確認されている土着種の数で,これ以外に約40種の迷チョウが知られている。迷チョウとは外国から台風や前線に伴う風で運ばれて記録されたもの,もしくは一時的に国内で世代をくりかえしたが姿を消したもの,あるいは人為的に(無意識のうちに)もち込まれたものを指し,偶産チョウともいわれる。土着種だけで比較するとイギリス本国は約60種,台湾は約360種で日本の地理的な位置からはむしろ豊富なチョウ相といえる。
この理由は日本列島がアジア大陸の東の端に位置し,第三紀に大陸から分離しはじめたことと氷期と間氷期のくりかえしによる気象の変化で元来分布範囲の異なるチョウがこうした外因変化につれて渡来や孤立をくりかえした結果と推定されている。すなわち日本のチョウ相はいくつかの系統で構成され,これは現在の種ごとの国外分布によって五つのタイプに分けられる。ただしこの名称は必ずしもチョウの発祥地を示すものではない。
(1)シベリア型 ユーラシア大陸北部に分布するもので,亜寒帯から温帯にみられる種類で高山チョウやヒメシジミ,キアゲハなどに代表されるチョウで約50種。
(2)アムール型 日本海の周辺地域,すなわち朝鮮半島,ウスリー,アムールなどに分布する種類で,ヒメギフチョウ,キマダラモドキ,ジョウザンミドリシジミなどがこれに当たり約60種が知られる。
(3)日本型 サハリンを含む日本列島に分布する種類であるが南西諸島の特産種(アサヒナキマダラセセリなど)もここに入れる。ギフチョウ,フジミドリシジミなど局地的分布の結果特殊化が進んだと考えられるチョウで約17種が考えられる。
(4)ヒマラヤ型 ヒマラヤ,中国西部,台湾から日本にかけてベルト状に分布する種類で主として森林にすむものが多い。クロアゲハ,オオムラサキ,クロヒカゲなどが該当種である。五つに分けたタイプ中もっとも古くから分布していたと推定され,日本のチョウ相の根底をなす群で大陸との関係を知るうえでも重要な手がかりになる。約40種が該当すると思われる。
(5)マレー型 アジアの熱帯域に広く分布する種類で日本を分布の北限にするものが多い。国内では暖帯か亜熱帯に限定されている。なおヒマラヤ型との関係が深く,移行も考えられる。アオスジアゲハ,キチョウ,カバマダラなどが代表種で約50種が該当種と推定される。
こうしたタイプの設定には研究者による多少の差異があって,より多くのタイプを提唱する者もある。いずれにしても日本列島は大陸やアジア地域からの流入で現在のチョウ相は定着したが,分布はなお流動的と考えるべきであろう。
行動生態
近年の研究はめざましく新事実が続々と発表されつつある。
たとえばアサギマダラは雄が雌を見つけると追い越して前方で腹端からヘアペンシルを開く。雌がこの行動で飛び方をゆるめると雄はそのまわりを回りながら近くの葉にとまるように誘導する。葉に雌がとまると雄は横からはばたきながら交尾する。つまり一般的には雌の出すフェロモンを雄が探知し,次に視覚で相手を確かめて交尾するが,マダラチョウの仲間では雄が発香物質を出して雌を誘うパターンが認められる。
シジミチョウ科にはアリとの関係が段階的にみられる。多くのチョウと同様に特定の食草を幼虫が食べて育つのだが,植物によってはアブラムシが群れてついていることがあり,シジミチョウ科の幼虫は葉とともにアブラムシも食べる場合がある。つまり肉食化への第1段階である。そして次に葉を食べずアブラムシを主食とするゴイシシジミの幼虫のような肉食性の種類が登場する。またアブラムシを食べずその分泌物をのむ種類(クロシジミなど)もあらわれるが,これらの雌はアブラムシの近くに産卵する習性を獲得している。しかしアブラムシの分泌物を求めに通ってくるアリと共存するためにはみずからも背面から分泌物を出す腺を開き,それをアリに与え見返りとしてアリから餌をもらう関係に発展する。これが第2段階である。
ところが成長してアリからの餌を多く必要とすると,アリに運ばれて巣の中で蛹化(ようか)し羽化するまで過ごす。しかしこの段階はあくまで分泌物の授受であるが,ゴマシジミの幼虫の場合はじかに巣の中のアリの幼虫を捕食して成長する。この第3段階に至ると,アリにとってシジミチョウの幼虫が天敵としての性格をもったというべきである。ゴマシジミの場合はアリに会って巣に運ばれるために胸と第2腹節までの膜質部を出し,アリはここをくわえて巣に運ぶという形態的な適応まで完成している。恐らく今後も驚くべき事実が次々と明らかにされるだろう。
人間との関係
実生活上の関係としては農作物に害を与えることが問題になろう。モンシロチョウはキャベツなどの害虫であり,キアゲハの幼虫はニンジンやセリの葉を食べてしまう。アゲハやナガサキアゲハ,それにシロオビアゲハの幼虫はミカン科の害虫として有名であり,フジマメやソラマメの花や若い実をウラナミシジミの幼虫が食害する。しかし何といっても古くから人々を苦しめてきたのはイネツトムシとよばれているイチモンジセセリの幼虫で,イネの大害虫としてニカメイガなどとともに被害をもたらし,ときには飢饉の原因にもなった。最近こうした被害は各種の農薬の開発や作物の品種改良によって防御できるようになった。プラスの面としては吸みつ行動によってどんな種類でも花粉の媒介者としての役割は果たしているし,その美しさは情緒的に人をなぐさめている。とくに日本では世界でも例の少ない国蝶にオオムラサキを指定し,その保護に努めているし,特別天然記念物1種(ミカドアゲハ),天然記念物9種(ルーミスシジミ,ウスバキチョウなど)を国が指定しているほか県や市が指定しているチョウはたくさんあって,いずれも許可なく採集することはできない。
一方,近年になって東京都とその周辺で韓国産のホソオチョウが各地の丘陵で数多く見られるようになり,すでに定着したかにみえるが,これは人為的にもち込まれた帰化種でありウマノスズクサを食べるところから同じ食草を食べる在来のジャコウアゲハが圧迫されはじめている。植物を食べる昆虫は植物防疫法でかたく輸入が禁じられているにもかかわらず,ひそかに持ち込まれる例があってホソオチョウのように在来種に影響をもたらすことはきわめて遺憾である。チョウの保護については研究者のみならず一般の関心を高め,二度とこのような例を起こさぬよう注意しなければならない。
→ガ →鱗翅類
執筆者:矢島 稔
名称,伝承
漢字の蝶という字は,薄くてひらひらした虫を表している。その音はtāp→tepと変化し,日本ではそれを借りてテフ→テオ→チョウと読み,使用してきたし,またしばしばテフテフ,チョウチョウと同音節を二度繰り返して畳語的に使ってもきた。フランス語のパピヨン,イタリア語のファルファラ,ポルトガル語のボルボレータはいずれもラテン語のパピリオに由来し,その祖形はパルパル→パルパリオンであり,これもひらひら,ぱたぱたしたものを表す畳語法である。同じことがインドネシア語のクプクプ,フィリピン,タガログ語のパロパロにも見られる。
日本語では蝶と蛾を区別するが,欧米では英語で蝶をbutterfly(butter+fly,すなわちバターの色をした飛ぶ虫の意)とよび,蛾をmothとよぶという区別があるだけで,他のことばではたいてい両者を一つのことばで表している。そして区別がどうしても必要なときに,たとえばフランス語のpapillon de nuit,ドイツ語のNachtfalterのように,蛾を〈夜の蝶〉という。
蝶には花から花へと飛び,みつを吸ってまわる華やかなものというイメージがあり,フランス語ではパピヨンが移り気な,あるいは気まぐれな精神の持主を指すことがある。また蝶(蛾)は知らせをもたらすものでもあり,それが夕方窓から家に飛びこんでくると,待ちに待った知らせがまもなくくるといって喜ぶ。しかし黒い蝶(蛾)は不吉なものと考えられ,春に初めて見た蝶が黒い種であると本人が病気になるか,年内に家族に病人が出るという。
執筆者:奥本 大三郎 日本の古語はカハヒラコであるらしい(《新撰字鏡》)。《吾妻鏡》には,蝶が群飛するのを怪異として社寺に祈禱する記事が散見する。蝶類の大発生は環境条件によることが多いが,昔の人々にとっては精霊の化生して訪れたもののように感じられたのであろう。人の霊が死後蝶に化したという話もあり,中国で《荘子》に魂が蝶となって夢の中で遊んだ話があるのと類を同じくする。これらは,幼虫からさなぎとなり,さらに変じて羽化して飛びたつという姿をさまざまに変える現象と,人の生死を変身して他界にいくこととの連想があったかと思われる。
執筆者:千葉 徳爾
チョウ (金魚蝨)
fish lice
Argulus japonicus
キンギョ,フナ,コイなどの淡水魚の体表に一時的に着生して,血液を吸い大害を与える小型の鰓尾亜綱チョウ科の甲殻類。体長5mmくらい。体は扁平な円盤状をしており透明。魚の体表を離れて泳ぐときは,木の葉が落ちるときのように左右に揺れながら泳ぐ。元来,日本の固有種であるが,ヨーロッパやアメリカなどに移入され分布している。チョウに外部寄生されると,血液を吸われて魚が弱って死んだりするので,見つけしだいピンセットなどで取り除いてやるのがよい。
近縁のものに,アユ,マス,タナゴの体表から1cm前後のチョウモドキA.coregoniや,フグ,マンボウなどの体表にふつうに寄生している3cmくらいの大型のウミチョウA.scutiformisなどが知られている。
執筆者:蒲生 重男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
普及版 字通 「ちょう」の読み・字形・画数・意味

9画
[説文解字]


[字形] 象形
〔説文〕七上に「艸木の實、垂るること

 然たり。象形」とし、「讀みて
然たり。象形」とし、「讀みて (てう)の
(てう)の (ごと)くす」といい、「籀
(ごと)くす」といい、「籀 (ちゆうぶん)は三
(ちゆうぶん)は三 に從ふ」としてその字形を録する。しかし字はその声義を以て用いることがなく、〔古今韻会挙要〕に字を
に從ふ」としてその字形を録する。しかし字はその声義を以て用いることがなく、〔古今韻会挙要〕に字を (ゆう)の古文とし、〔段注〕にその説をとり、
(ゆう)の古文とし、〔段注〕にその説をとり、 の隷変(れいへん)を
の隷変(れいへん)を であるとする。〔群経正字〕にも、
であるとする。〔群経正字〕にも、 を由の初文とする説がある。〔説文〕には
を由の初文とする説がある。〔説文〕には ・由を収めないが、
・由を収めないが、 は
は と最も字形が近い。酒器として用いる
と最も字形が近い。酒器として用いる の卜文・金文の字形は、
の卜文・金文の字形は、 とほとんど異なるところがなく、その形は壺
とほとんど異なるところがなく、その形は壺 (こひよう)の実に近い。酒器の
(こひよう)の実に近い。酒器の はその形から出たもので、壺
はその形から出たもので、壺 の実が熟して油化したものが由、その外殻を存して器となったものが
の実が熟して油化したものが由、その外殻を存して器となったものが である。すなわち
である。すなわち ・
・ ・由はもと一系をなすものであり、声義ともに同系に属するものとみてよい。
・由はもと一系をなすものであり、声義ともに同系に属するものとみてよい。[訓義]
1. みのたれるかたち。
2. 壺
 などの実の形。
などの実の形。3.
 の初文。
の初文。[古辞書の訓]
〔字鏡集〕
 キノミ
キノミ[部首]
〔説文〕に栗・粟の二字、〔玉
 〕にその異文をも合わせて七字を属する。ただ壺
〕にその異文をも合わせて七字を属する。ただ壺 の実と栗・粟の類とは甚だ形も異なり、同系の字とはしがたい。
の実と栗・粟の類とは甚だ形も異なり、同系の字とはしがたい。[声系]
〔説文〕に
 声として、
声として、 (ゆう)など五字を収める。その音は
(ゆう)など五字を収める。その音は (ゆう)と同声で、
(ゆう)と同声で、 声に従うものとすべきである。
声に従うものとすべきである。[語系]
 ・
・ (調)・
(調)・ dy
dy は同声。
は同声。
 (ちようちよう)・調調は、そよ風に吹かれてものの揺れるさまを形容する語である。
(ちようちよう)・調調は、そよ風に吹かれてものの揺れるさまを形容する語である。 も壺
も壺 の類の揺れ動くさまで、調調とはおそらく
の類の揺れ動くさまで、調調とはおそらく
 の意であろう。
の意であろう。
8画
[字形] 形声
声符は召(しよう)。召に迢(ちよう)の声がある。山の高いさまをいう。また迢と通用する。
[訓義]
1. たかい、山の高いさま。
2. そばだつ、けわしい。
3. 迢(ちよう)と通じ、とおい。
[古辞書の訓]
〔字鏡集〕
 ヤマ
ヤマ[熟語]
 嶢▶・
嶢▶・
 ▶・
▶・ 直▶
直▶出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ちょう」の意味・わかりやすい解説
チョウ
Chhau
チョウ
Argulus japonicus; carp-louse
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「ちょう」の意味・わかりやすい解説
チョウ(蝶)(昆虫)【チョウ】
チョウ(甲殻)【チョウ】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内のちょうの言及
【インド舞踊】より
… インドの舞踊には,踊手が1人で物語の筋を演じ踊るもの(1人でいろいろな役になるもの)とそれぞれの役がらの踊手が登場する舞踊劇の形のものとがある。前者の代表的なものはバーラタ・ナティヤム,オリッシ,マニプリ,カタックなどで,後者はカタカリ,民俗舞踊劇のヤクシャガーナ,プルリア地方のチョウなどである。オリッシは,オリッサ地方の寺院に伝承されてきた舞踊で,バーラタ・ナティヤムと似た,女性のソロの舞踊である。…
【仮面劇】より
…インドから南アジアにかけて,ヒンドゥー文化に起源するさまざまな神格の行為,叙事詩《ラーマーヤナ》《マハーバーラタ》を基礎とする仮面が地域ごとに独自の様式によって洗練されて,また地域固有の要素と結びつけられ,固有の演劇の文脈に編みこまれているという事実は,この点から見て大変興味深い。南インドの〈チョウ〉(紙と粘土で成形した仮面を用いる,《ラーマーヤナ》等に基づく民衆劇)のさまざまな様式,スリランカの〈コーラム〉,ネパールの〈ナバ・トゥルガー〉,タイの〈コーン〉および〈ラコーン〉,インドネシアの〈ワヤン・トペン〉は,共通の基礎の上に,多様な仮面劇の世界を作り上げている。 アジアにはこのほかにもインドネシア,バリ島のバロン仮面舞踊劇,悪疫をもたらす魔女ランダ(チャロンアラン)と戦い調伏するチャロンアラン劇,朝鮮のさまざまな仮面劇(タールツィム)があり,日本にも祭礼と結びついた神楽が各地に伝承されている。…
【町組】より
…京都において鎌倉時代末期から形成され,応仁・文明の乱後に確立する住民の生活共同体は,〈まち〉ではなく〈ちょう〉であるから,本来〈ちょう〉の連合体も〈まちぐみ〉ではなく,〈ちょうぐみ〉である。町組は上京,下京を単位とし,1568年(永禄11)の織田信長の入洛以前にすでに確立している。…
【鰓尾類】より
…鰓尾亜綱鰓尾亜目Branchiuraの小型甲殻類の総称。チョウ科のみを含み,4属約150種が知られ,淡水魚に寄生するチョウ,海産魚のウミチョウなどがある。魚類,カエルなどの体表に一時寄生し,血液を吸う。…
【水泳】より
…女子100mはP.ヘインズ(南アフリカ)がアトランタ大会で出した1分07秒02,200mはR.ブラウン(オーストラリア)のもつ2分24秒76である。
[バタフライbutterfly]
チョウが飛ぶような動きの泳法。平泳の変化したもので,空中高く前方に運んだ両腕を一気に下ろして水をかき切る。…
【虫】より
…虫の字は虺の古文として用いられて〈キ〉と読み,元来はヘビ類の総称であるという。昆虫は蟲と書くのが正しく,蟲豸(ちゆうち)は肢のあるむしで,肢のないものが豸(ち)である。中国ではトラを大蟲といったように,〈虫〉は今の動物分類学上の昆虫のみではなく,虫偏のつく漢字の示すように動物の総称に用いられた。 日本ではもっぱら地表をはう種類に対してこの文字を用い,〈むし〉または〈はうむし〉と称した。大祓の詞に〈昆虫の災〉というのは作物の害虫や人体寄生虫に悩まされることが多かったからで,蛇もまた虫の一種であった。…
※「ちょう」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...