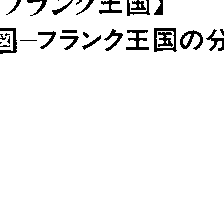精選版 日本国語大辞典 「フランク王国」の意味・読み・例文・類語
フランク‐おうこく‥ワウコク【フランク王国】
- ゲルマン民族の一部族フランク族が五世紀末に北部ガリアを中心に建てた王国。四八一年クロビスがメロビング朝を建てて全フランク族を統一したが、分裂・統一を繰り返し、七五一年宮宰ピピンがカロリング朝を建てた。その子カール大帝のときが最盛期で、西ヨーロッパ全域に版図を拡大したが、のち東フランク・西フランク・イタリアに分割。西欧文化圏形成の基礎となった。
改訂新版 世界大百科事典 「フランク王国」の意味・わかりやすい解説
フランク王国 (フランクおうこく)
中世ヨーロッパにおいてフランク族(フランケン)が建国した王国。486-987年。5世紀末に,クロービスがフランクFrankの全部族を統合し,北ガリアに部族王国を建てたのに始まり,他のゲルマン系諸部族・諸国家を次々と征服して,西ヨーロッパの大部分の政治的統一を達成し,カール大帝は800年,ついに皇帝の称号を帯びるにいたるが,ベルダン条約(843)で帝国は三つに分割され,さらにメルセン条約(870)により東フランク王国と西フランク王国が並立する。フランク王国の政治史的発展については〈メロビング朝〉〈カロリング朝〉の項に譲り,ここではフランク王国の政治構造,社会構成,経済状態,文化的貢献,さらにフランク王国をめぐる国際関係などを取り扱う。これら諸問題に関しては,19世紀後半から20世紀20年代まで学界を支配した通説に対し,フランク王国のみならず中世史全体にかかわる問題として30年代以降これを批判した新説が提起され,学界の現況でも,旧説の踏襲者と,新説の支持者との間の論争は,完全には決着をみていない。いきおい以下の叙述も,新旧両説の対比という色彩を帯びざるをえないが,両説の相違は基本的には,ゲルマン社会における階層分化の進展をめぐる問題にあるとみることができよう。
王権の性格
1~2世紀のローマの史家タキトゥスは古ゲルマン人の社会状態について《ゲルマニア》で詳述しているが,これによれば,その時代のゲルマン人はキウィタスと呼ばれる多数の小政治単位に分かれていた。タキトゥスは世襲的王(レクス)を頂くキウィタスと,全人民の構成する民会で選ばれる首長(プリンケプス)に統治されるものと,二つの政治形態を区別しているが,世襲王制は首長制に比べ,王の有する権力の強さによって特徴づけられるのではなく,王の家門が神に由来するという,王権の宗教的性格によって特徴づけられ,最近の研究はこれを神聖王権という概念で把握する。旧説によれば,フランク王権をはじめ中世初期の部族国家の王権は,キウィタス相互間の征服・統合の過程で,その世襲王権=神聖王権が部族全体の上に拡大されたものとみなされたのであるが,新説では神聖王権からの連続性の面より,新しい要素の加わった点を強調し,この新しい要素を軍隊王権という概念で説明する。タキトゥスは平時における王の権限と,戦時に置かれる軍事指揮官(ドゥクス)の権限とを対比し,前者が無制限の権限を有しなかったのに対し,後者には絶対服従を要求しうる命令権が与えられたことを指摘しているが,このドゥクスの権限が,民族移動の戦乱期に,戦争時のみでなく平和時にも拡大・恒常化された結果,軍隊王権が成立したと考え,フランク王国をはじめ,中世初期の諸部族王国の王権は,この軍隊王権を中核として形成されたとみなす。この新説はフランク族をはじめ民族移動期に登場する大部族(シュタム)の形成過程に関する新しい考え方と結びついている。旧説はタキトゥス時代の小部族(ゲンス)が統合されて大部族が形成されたと考えたのに対し,新説はシュタム形成の要因として,従士制的結合を重視し,軍隊王クロービスの下に北ガリアを征服し,フランク王国を樹立した軍隊(これは同時にフランク族民の主要部分を形成する)は,アントルスティオネスと呼ばれる国王側近の従士と,レウデスと呼ばれる一般の従士という,広狭二つの従士団によって形成されていたのだと考える。
社会構造
フランク王国はフランク族民のみでなく,征服・拡大の結果,多数のローマ系住民をはじめ,ブルグント族その他ゲルマン系の諸部族民をも含んでおり,社会構造も地域によって大きな相違を示す。メロビング時代にフランク王国の重心が置かれていたガリアにおいても,ロアール川以北の北ガリアと,それ以南の南ガリアでは,かなり対照的な社会構造が認められる。南ガリアでは,大土地所有者であるセナトル(元老院)貴族層,ポセッソレスと呼ばれる中・小土地所有者,前者の隷属的小作人であるコロヌスという,3階層よりなる古代末期の社会構造がそのまま存続し,中心都市と周辺農村とが一体となり,貴族層の指導の下に都市民の自治によって運営されるローマ末期の行政単位=キウィタス(ゲルマンのキウィタスと異なる点に注意)の制度も維持された。他方北ガリアではフランク族の定住,セナトル貴族層の南方への撤収によって,社会構成は大きく変わった。フランクの部族法典サリカ法典はフランク族の自由人(インゲヌウス)とリトゥス,ローマ系のポセッソレスの三つを主要階層として挙げており,前者の人命金が200ソリドゥスであるのに対し,後の2者の人命金をその半分と規定している。旧説はここから,メロビング時代のフランク王国には貴族は存在しなかったと結論したが,新説はゲルマン時代から中世初期にかけて,貴族制的政治体制を強調する一環として,フランク王国にも貴族が存在したことを立証しようとする。ただ貴族概念を厳密に法的身分と規定する限り,新説の立証は必ずしも説得的ではない。他方これを社会階層,すなわち豪族層ととらえるなら,フランク王国においてもかかる階層が存在したことは十分推定できるのであり,豪族層とそれ以外の自由民階層とは,従士団の二つのタイプ,アントルスティオネスとレウデスに,ほぼ対応すると考えられる。リトゥスの性格に関しても,新・旧の見解は分かれ,必ずしも実態が明らかでないが,その多くが主人をもっている事実からみて,被解放民を含め,国王や豪族層の保護・支配下にある,自由人より低い階層であったと考えられる。
行政組織
ここでも南北ガリアは対照的である。フランク王国の行政組織の根幹は,伯(グラーフ)制度であるが,南部ではキウィタス制度が存続していたので,フランク王国の代官としての伯(南部ではコメスと呼ばれ,多く在地のセナトル貴族層が任命された)が,キウィタスの行政,司法,軍事の大幅な権限をゆだねられたが,市民の自治組織も機能しつづけた。7世紀末以降,伯制度は崩れ,コメスは消滅するが,存続した場合にも都市司教の支配下に入るようになって,王権に対しキウィタスの独立性が強化された。これに対し北部では,キウィタスの制度は,都市司教座を中心とする教会組織に変形して残存した場合を除き,多くの場合解体して,より小さなパグスに分解した。初期メロビング朝時代では,国王の代官としてパグスの軍事,行政をつかさどるグラフィオと並んで,パグスの裁判集会を主宰するテュンギヌスが存在した。後者は国王によって任命される役人ではなく,おそらくタキトゥス時代のプリンケプスの後裔であったと推定される。6世紀の過程で,グラフィオもテュンギヌスも史料から姿を消し,代わってコメスの呼称が一般化する。これはかつてのグラフィオがテュンギヌスの権限をも吸収して,南ガリアのコメスとほとんど同じ権限を獲得したことの反映とみなされる。他方クロタール2世のパリ勅令(614)は,以後在地の豪族層のなかから伯を任命することを規定している。これは南部と同様,北部ガリアでも国王に対するコメスの独立性が強くなっていく傾向を反映したものと解釈され,その傾向はメロビング朝時代末,王権の弱体化に伴い,いっそう著しくなった。
カロリング朝の諸王,とくにカール大帝のもとで,強力な中央権力の指導の下に,地方行政組織の再建が行われた。この中核をなすのは,従来グラーフが置かれていなかった,ライン以東の地域を含め,全国を一律にグラーフシャフトに組織していくことであり,カロリング家の地盤であるアウストラシア出身者が,グラーフとして全国各地に派遣された。この政策がどの程度貫徹したかについては,新旧の学説で評価が分かれるが,少なくともカール大帝の下では,かなりの成功を収めたことは疑いない。さらに大帝はグラーフの任務遂行を監督するため,国王巡察使制度を強化し,詳細な報告を要求した。だがこのような中央集権的統治も,カール大帝のような優れた統治能力をもつ人間の下でのみ可能であったので,王権の弱体化した後期カロリング朝時代には,グラーフの在地豪族化の傾向を抑えることはできなかった。
封建制度の成立
カロリング朝時代までの軍制は,自由人の軍役によって支えられていた。カロリング朝の諸王もこれを維持することに努め,当時の勅令は,すべての自由人の軍役義務を規定し,グラーフの重要な任務の一つは,必要な場合管区内の自由人を軍隊に動員することであった。しかし軍事力の重心が,召集された自由人の軍隊から,封土の授受を媒介として,国王と人的主従関係に入った家臣(ウァッサル)の騎士軍へ移行する傾向が強くなっていった。その原因は,後述するような農業の集約化により,一般の農民=自由人の召集が困難になったこと,歩兵の集団戦闘から,重装騎士の戦闘へと,戦争技術が変化したことなどに求められる。だが封建制度の進展という事態は,このような軍制の封建化にとどまらず,前節で指摘した,地方行政機構の解体とも結びついていた。カール大帝がグラーフとして全国に派遣したアウストラシア出身者は,もともと〈国王の従士〉の階層であった。この事実から読みとれるように,国王-グラーフという官職の委任関係に,主従制という人的関係を重ねることにより,グラーフの自立化を抑えるのが,カール大帝の意図であった。ところが,後期カロリング朝時代の王権の弱体化と並行して,大帝の意図とは逆に,グラーフの官職もまた一種の封(レーン)であるという観念が広まり,本来の封土に世襲化が貫徹していくのに影響されて,グラーフの官職にも世襲化の傾向が生まれた。このような傾向が支配的になるのは,カロリング朝の崩壊期であるが,その端緒はすでにカール大帝の時代に置かれていたのである。
経済状態
フランク王国の経済的基礎は農業であった。だがメロビング朝時代の農業は,カロリング朝時代のそれに比べ,かなり粗放であり,穀物耕作より牧畜の占める比重が高かった。またとくに南ガリアを中心に,古代以来の商品・貨幣経済がある程度残存していたことも否定できない。H.ピレンヌはこの点をとくに強調し,メロビング朝時代は経済的にみていまだ古代の延長であり,イスラムの地中海制覇による地中海貿易の途絶の結果,西ヨーロッパは自然経済に逆転し,カロリング朝時代から経済的な面での中世が始まるとする。彼はカール大帝による金貨から銀貨への幣制改革は,貨幣経済から自然経済への移行の象徴とみなす。ピレンヌのいうように,カロリング朝時代にフランク王国の経済的重心が地中海沿岸から,ライン川,ロアール川に挟まれた北ガリアに移るに伴い,農業の比重が決定的に大きくなったことは疑いないが,同時にこの地域で,農業技術のうえで多くの改良が行われた鉄製農具の普及,犂と役畜とを連結する新しい繫駕法の導入による重量有輪犂の一般化などにより,開放耕地制度・三圃制を伴う集村が出現した。この結果,穀物耕作の比重が圧倒的に高まり,農業生産力の飛躍的上昇が実現された。最近の研究者はこの現象を中世初期の農業革命と名づけている。古典荘園と呼ばれる大土地所有の経営形態が重要な意義をもってくるのも,このような背景に支えられたからである。10~11世紀以降の中世都市成立の要因として,従来はピレンヌ説に従って,遠隔地貿易の復活を重視してきたが,むしろカロリング朝時代における農業生産力の上昇が,都市成立の前提をなしたと考えなければならなくなっており,最近の研究は,都市の成立そのものも,従来より早い時期へずらせて考える傾向がある。
皇帝権をめぐる国際関係
800年のクリスマス,教皇とローマ貴族たちとの紛争を調停するためローマに滞在していたカール大帝が,サン・ピエトロ大聖堂のミサに参加したとき,ローマ教皇レオ3世によって皇帝として加冠され,集まっていたローマ市民から〈ローマ人の皇帝〉に推戴された。通例西ローマ帝国の復活と呼ばれる事件である。しかし,カール大帝の皇帝権の意義についても,この事件の演出者であったレオ3世の意図に関しても,またこれに対するカール大帝の側の受け取り方についても,研究者の間にいろいろな議論がある。ここでは主としてビザンティン帝国という当時の国際関係のうえから,皇帝権の意味を考察する。
民族移動の混乱のなかで西ローマ帝国は滅亡し,その版図内にゲルマン系諸部族の王国が建国されるが,ビザンティン(東ローマ)皇帝は,西ローマの消滅によりローマ帝国は再び統一されたという立場をとり,ゲルマン系諸国王も,ビザンティン皇帝の宗主権を承認していた。彼らが,パトリキウスらの皇帝から与えられたローマ的官職を,ローマ系住民に対する支配権の法的根拠としていたという事実が,その事情を示している。しかしカール大帝の手で西ヨーロッパの政治的統一が達成され,ビザンティン帝国と優に対抗しうる政治勢力が出現した結果,このようなたてまえ上の関係は,遅かれ早かれ清算される必要があったのである。フランク王国側は,790年代初頭,〈カールの書〉を公表して,ビザンティンの〈王〉に対し,フランクの〈王〉の対等性の主張を掲げていた。他方ビザンティン帝国では,コンスタンティノス6世の摂政として実権を握っていた母后イレネが,797年息子の皇帝を廃位して,自ら帝位に就くという異例の事態が発生していた。女帝支配の合法性についてはビザンティン帝国内部にも異論が多く,各地で反乱が生じつつあった。教皇レオ3世がカール大帝の戴冠を演出した背景には,カール大帝とイレネとの結婚を成立させることにより,自分のつくり出した皇帝権をビザンティン側にも承認させうるという計算があったと思われる。しかし802年イレネが失脚し,ニケフォロス1世が帝位に就いた結果,はからずも東・西2人の皇帝の対立という事態となり,カール大帝はこの問題の解決に追いこまれることになった。以後812年まで,紆余曲折の折衝のすえ,フランク王国側が占領していた,ベネチア,ダルマティアを返還する代償として,カール大帝は己の皇帝権をビザンティン側に承認させることに成功した。このような形で,西ヨーロッパの,ビザンティン帝国すなわち東ローマ帝国からの政治的自立化が,実現をみたのである。
文化的貢献
フランク王国が後世に残した最大の貢献として,古典文化,とりわけラテン文化の継承と,後代への伝達が挙げられる。メロビング朝時代にラテン文化を担ったのは,主としてローマ系のセナトル貴族層であったが,とりわけカール大帝は,アルクインその他の聖職者の力を借りて,教育制度の改革(宮廷学校や修道院学校の設置)を行い,ラテン文化の普及に努めたので,一般にカロリング・ルネサンスと呼ばれる。近代にいたるまで一般教育の中核となった教養七学科(自由七科)が教育内容として確立されたのもこの時代である。フランク王国のもう一つの文化的貢献は,西ヨーロッパのキリスト教化である。東ゴート族や西ゴート族などは,アリウス派の信仰を受け入れていたのに対し,フランク族はクロービスの下で,異教信仰からカトリックに改宗したため,ローマ教皇と友好関係を保つことができ,ピピン3世の王権獲得が教皇によって支持をうけた結果,カロリング朝諸王と教皇との結合は,いっそう緊密になった。フランク国王は,たえず教皇権の保護者として行動し,異教徒の征服にあたっても,キリスト教化を大義名分として掲げることができ,カール大帝の皇帝戴冠も,背景に教皇権の保護者として実績があったからである。
→カロリング朝 →ガロ・ロマン時代 →メロビング朝
執筆者:平城 照介
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「フランク王国」の意味・わかりやすい解説
フランク王国
ふらんくおうこく
古ゲルマン人のうち、西ゲルマン系のフランクFrank人の建てた王国(486~987)。部族国家から発展し、しだいに他のゲルマン諸部族を征服・統合し、ピレネー山脈からエルベ川に至る西ヨーロッパの大部分を含む大帝国となり、民族大移動後の混乱を収拾して、ヨーロッパの政治的・文化的統一を実現した。フランク王国は、西ヨーロッパ最初のキリスト教的ゲルマン統一国家として、キリスト教文化および中世の諸制度の母体となるとともに、ドイツ、フランス、イタリアなどの諸国家が、その分裂・崩壊の過程のなかで誕生した。
[平城照介]
王国の成立と推移
フランクという名称が史料に最初に現れるのは3世紀中ごろで、フランクは、おそらくカマビー、ブルクテール、カッティーなど、ライン川中・下流東岸の諸部族を中核とし、多くの小部族の混成によってできあがったと考えられる。4世紀初頭以来、サリ支族、リブアリ支族、上フランク支族の三大グループが形成されたが、そのうちサリ支族は、5世紀初頭西進して、シェルデ川流域にまで広がった。そのころパーグス(郡)の小王として台頭してきたのがメロビング家である。この家から出たクロービス王は、サリ支族を統一し、さらにリブアリ、上フランク両支族を併合して、5世紀末にフランク王国を樹立した。
クロービスの統一によって成立したメロビング朝フランク王国は、その後他のゲルマン系諸部族を次々と征服、統合して発展したが、7世紀後半、王国の実権は、宮宰職を務めるカロリング家によって握られ、751年同家のピピン(小)はカロリング朝を開始する。その子カール大帝(シャルルマーニュ)の治下に王国は最盛期を迎えるが、843年その広大な版図は3人の孫たちの間に分割され、事実上三王国に分裂するに至る。両朝支配による王国の政治史的変遷は、別項「メロビング朝」「カロリング朝」に譲り、以下には、王国の社会構成、行政組織、経済について述べる。
[平城照介]
王国の社会構成
フランク王国はフランク人のみでなく、征服・拡大の結果、旧ローマ系住民をはじめ、他のゲルマン系民族をも含んでおり、社会構成も地域によって大きな相違を示す。王国南部(南ガリア)では、大土地所有者であるセナトール(元老院議員)貴族層、ポセッソレスとよばれる中・小土地所有者、前者の隷属的小作人であるコロヌスという、三階層からなる古代末期の社会構造が存続した。中心都市と周辺農村が一体となり、貴族層の指導の下に市民の自治により運営されるローマ末期の行政単位=キーウィタース制度も維持された。またライン川以東の地域に関しては、基本的には貴族、自由人、非自由人の三階層からなっていた。王国北部(北ガリア)では、フランク人の定住、セナトール貴族層の南方への撤収により、社会構成は大きく変わった。フランク人の部族法典=サリカ法典は、フランク人の自由人とリトゥス(非自由人)、ローマ系のポセッソレスの三つを主要階層としてあげており、後二者について自由人の半額の人命金を規定している。このことから、メロビング朝時代のフランク王国には貴族は存在しなかったとする説もあるが、新説は、ゲルマン時代から中世初期へかけての貴族制的政治体制を強調する一環として、フランク王国にも貴族の存在したことを立証しようとする。貴族層の概念を豪族層ととらえるなら、かかる社会階層がフランク王国においても存在したことは種々の証拠から推定できる。
[平城照介]
王国の統治組織
フランク王国の行政組織の根幹は、伯=グラーフ制度である。王国南部ではキーウィタース制度が存続していたので、フランク国王は、彼の代官としての伯(コメスとよばれた)をそれぞれのキーウィタースに置き、行政、司法、軍事の大幅な権限をゆだねた。7世紀末以降コメス制度は崩れ、コメスの王権に対する独立性は強まった。これに対し、北部ではフランク人の進出に伴い、キーウィタース制度は崩壊し、より小さなパーグスが統治単位となった。初期メロビング朝時代では、国王の代官としてパーグスの軍事・行政をつかさどるグラフィオと並んで、パーグスの裁判集会を主宰するチュンギヌスが存在した。6世紀に、グラフィオもチュンギヌスも史料から姿を消し、これにかわってコメスの呼称が一般化するが、これは、かつてのグラフィオがチュンギヌスの権限をも吸収し、南部のコメスとほとんど同じ権限を獲得した反映とみなされる。他方、7世紀初頭より在地の豪族層から伯が任命されるようになり、南部と同様、北部でも王権に対する伯の自立性が強まり、メロビング朝末期にはこの傾向がいっそう著しくなった。
カロリング朝時代には、地方行政組織の再建が試みられた。全国を一率に伯=グラーフ制度のもとに組織し、おもにカロリング家の地盤であるアウストラシアの出身者が、伯として全国に派遣された。さらに伯の任務遂行を監督するため国王巡察使制度も恒常化されたが、王権の弱体化した後期カロリング朝時代には、伯の在地豪族化の傾向を抑えることはできなかった。
[平城照介]
王国の経済
フランク王国の経済的基礎は農業であった。だが、メロビング朝時代の農業は、カロリング朝時代に比べかなり粗放であり、穀物耕作よりも牧畜の占める比重が高かった。またとくに王国南部を中心に、古代以来の商品・貨幣経済がある程度残存していたことも否定できない。カロリング朝時代には、フランク王国の経済的重心が地中海沿岸から、ロアール川、ライン川に挟まれた北ガリア地方に移るに伴い、農業の比重が決定的に大きくなった。同時にこの地域で、農業技術のうえで多くの改良も行われた。鉄製農具の普及、犂(すき)と役畜とを連結する新しい繋駕(けいが)法の導入による重量有輪犂の一般化などにより、開放耕地制度と三圃(さんぽ)農法を伴う集村が出現した。この結果、穀物耕作の比重が圧倒的に高まり、農業生産力の飛躍的上昇が実現された。最近の研究はこれを中世初期農業革命と名づけている。古典荘園(しょうえん)という大土地所有の経営様式が確立するのも、このような背景に支えられたからである。また、ゲルマン系の自由人の階層の多くの部分が、従来の戦士的性格を払拭(ふっしょく)して農民化し、軍事力の重心が、自由民の動員から、専業的戦士の封建的軍役へ移行(封建制の成立)するのも、このような事態の反映である。
[平城照介]
王国の歴史的意義
フランク王国の後世に対する最大の貢献として、ゲルマン系諸民族を統合し、民族大移動後の西ヨーロッパの混乱を収拾して、彼らに共通の政治的秩序、共通の信仰=カトリック信仰、共通の文化的基盤を与えたことがあげられる。それらはかならずしもフランク王国が独自に生み出したものではない。カトリック信仰や、カロリング朝ルネサンスに象徴されるこの時代の文化が、古典古代の遺産の継承であるのはもとより、法や制度においても従来考えられた以上に古代の影響の強かったことを、最近の研究は明らかにしつつある。だが他方、この共通の政治秩序、共通の信仰、共通の文化的基盤から、中世以降の西ヨーロッパの諸国家、諸民族の文化が生まれたことも動かない事実である。その意味でフランク王国は、古典古代と中世以降の西ヨーロッパとの結節点をなしたといえるであろう。
[平城照介]
『ジョゼフ・カルメット著、川俣晃自訳『シャルルマーニュ』(白水社・文庫クセジュ)』▽『増田四郎著『西洋中世社会史研究』(1974・岩波書店)』▽『山中謙二著『西欧世界の形成』(1968・東海大学出版部)』▽『ジャック・ブウサール著、井上泰男訳『シャルルマーニュの時代』(1973・平凡社)』
百科事典マイペディア 「フランク王国」の意味・わかりやすい解説
フランク王国【フランクおうこく】
→関連項目アーヘン|アルクイン|カール[3世]|スロベニア|ドイツ|トゥール・ポアティエの戦|西フランク王国|東フランク王国|ピピン[1世]|ピピン[2世]|フランシュ・コンテ|フランス|ブルグント|ベルギー|民族大移動
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「フランク王国」の意味・わかりやすい解説
フランク王国
フランクおうこく
Regnum Francorum; Frankenreich
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「フランク王国」の解説
フランク王国
フランクおうこく
Frank
民族大移動期にライン川右岸の地から北ガリアにかけて建てられた。メロヴィング朝の創始者クローヴィスがローマ教会と提携してから急速に発展。のち実権は宮宰の手に移り,751年ピピンがメロヴィング朝を倒してカロリング朝を創設した。カール1世(大帝)のときが最盛期で,西ローマ皇帝の帝冠を受け,ローマ的・ゲルマン的・キリスト教的要素の結合による西欧世界の基礎をつくりだした。その後,ヴェルダン(843)・メルセン(870)両条約で帝国は3分されて,東フランク・西フランク・イタリアとなり,現在のドイツ・フランス・イタリアの起源となった。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内のフランク王国の言及
【オランダ】より
…3世紀以降のゲルマン民族大移動期において,フリーシー人は沿岸地域に居住し続け,ザクセン(サクソン)人は北東部からエイセル川の線まで進出し,またフランク人はライン川の南部地方に侵入し,徐々に勢力を拡大した。734年フランク王国カロリング家のカール・マルテルはフリーシー人を,さらに孫のカール大帝はザクセン人を征服し,ネーデルラントはフランク王国の支配下に入った。8世紀にはユトレヒトを中心にアングロ・サクソンの修道士ウィリブロードWillibrordやボニファティウスBonifatiusの布教によってキリスト教化が進んだ。…
【ヨーロッパ】より
…政治の現実はやがて封建国家の割拠に突入し,それ以来西ヨーロッパでは今に至るまで2度と世界帝国が実現しなかったわけで,近世における国民国家の根源は,すでにこの頃に定礎されていたのである。ただ西では,このようにローマ教皇庁と密接な関係をもつフランク王国が,名実ともに他の諸部族国家に優越した地位を得て,一応諸国家体制の秩序ができ上がり,これが東のビザンティン帝国と対比されるほどの姿を整えたところから,カールの戴冠をもって西ヨーロッパの政治的枠組みが成立した画期とみるのが定説である。しかしこの時期に,西ヨーロッパ社会の基礎ができたとか,ヨーロッパ人の共通の意識が成立したとみるのは誤りである。…
※「フランク王国」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...