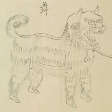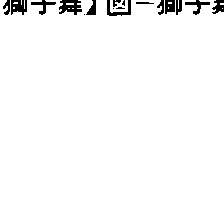精選版 日本国語大辞典 「獅子舞」の意味・読み・例文・類語
しし‐まい‥まひ【獅子舞】
- 〘 名詞 〙
- ① 獅子頭(ししがしら)をかぶって行なう舞。また、それを舞う人。唐から伝わり、多く一人、あるいは二人、また三人で舞う。伎楽、舞楽で用いられたが、のち太神楽(だいかぐら)などで行なわれる。五穀豊穰の祈祷や悪魔を払い清めるものとして、今日でも各地の祭礼行列に行なわれている。
 獅子舞①〈年中行事絵巻〉
獅子舞①〈年中行事絵巻〉- [初出の実例]「女院の御所に、しきしまと云雑仕と法師と二人かづきて師子舞(シシマイ)をして、御衣をもちて狂まゐりてけり」(出典:米沢本沙石集(1283)五末)
- ② 特に、新年の祝い事の一つとして、獅子頭をかぶり、笛・太鼓・鉦(かね)などではやして家々を舞い歩き、米や銭などを請うもの。《 季語・新年 》
- [初出の実例]「獅子舞や大口明て梅の花」(出典:俳諧・七番日記‐文化八年(1811)一月)
- 「東京の下町は獅子舞や恵方万歳の太鼓や鼓で正月の訪れが始まるのだった」(出典:湯葉(1960)〈芝木好子〉)
- ③ 能楽の囃子(はやし)による舞事(まいごと)の一つ。大鼓、小鼓、太鼓と笛の伴奏によって石橋(しゃっきょう)・望月・内外詣(うちともうで)にある舞で獅子の舞い狂うさまをかたどった豪華絢爛な急調子の舞。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「獅子舞」の意味・わかりやすい解説
獅子舞
ししまい
獅子頭(ししがしら)をかぶって舞う神事的な民俗芸能。獅子頭はおもに雄の獅子の頭をかたどった木製の作り物であるが、トラ、シカその他の場合もある。上古の日本人にとって獅子は現実の動物ではなかったが、空想上の威力ある聖獣であり、除魔招福の信仰の対象であった。獅子舞には渡来脈と固有脈があると考えられ、渡来脈を「二人立(ふたりだち)」、固有脈と目されるものを「一人立」という。二人立は6世紀なかばから7世紀にかけて、大陸から伎楽(ぎがく)とともに伝来したと推定される。752年(天平勝宝4)の東大寺大仏開眼供養に用いられた獅子頭が正倉院に伝存するが、今日の太神楽(だいかぐら)の獅子頭と形状的に大差がない。また7世紀なかばに伝来した舞楽(ぶがく)では、御願供養舞の一演目として演じられており、今日でも大阪四天王寺の聖霊会(しょうりょうえ)舞楽の四箇(しか)法要などにうかがえる。平安期以降は、祭礼の練り風流(ふりゅう)の一つとして、また田楽(でんがく)、神楽などに取り入れられて今日に至っている。
[西角井正大]
二人立の獅子舞
1人が頭部と前肢、もう1人が尻(しり)部と後肢を受け持って1頭をなす形式の獅子舞で、胴体は幌(ほろ)である。『教訓抄』には五色の毛があると記され、『年中行事絵巻』では幌に毛が列状に配してあり、『信西古楽(しんぜいこがく)図』では縫いぐるみである。今日、九州の一部や沖縄には中国風に縫いぐるみ式のものがあるが、そのほかは幌式である。
この形式は全国各地にみられるが、太神楽系がもっとも普及している。「伊勢太神楽(いせだいかぐら)」は、三重県桑名市太夫(たゆう)町に本拠を置く職能的な二人立獅子舞で、祈祷(きとう)の神事舞と奉納神楽、それに余興的な放下芸(曲芸)からなる。「江戸太神楽」は、寿(ことぶき)獅子という祈祷の舞のほかは曲芸で、以前は茶番も演じた。
幕末以降、中部地方には、余興芸として歌舞伎(かぶき)を取り込んだ「獅子芝居」(女主人公を獅子が演じ、「嫁芝居」ともいう)も生まれた。今日の獅子芝居は非職能であるが、一般に非職能の獅子舞は祈祷の神事舞あるいは奉納神楽的な舞しか演じない。雌雄2頭出るケースも少なくなく、また獅子と絡む獅子あやしが出ることもある。なお、成年式など村落民が参加することに意義があるとする場合には、1頭の幌の中に数人ないし数十人も入ることがある。山伏神楽として知られる岩手県の「早池峰(はやちね)神楽」は多様な芸能をもつが、獅子神楽に分類されるように、「権現舞(ごんげんまい)」とよばれる祈祷の獅子舞に中心がある。東北地方にはこの系譜のものが多く、権現さまとよぶ獅子頭は神である。なお、虎頭・虎胴の「虎舞」も若干ある。
[西角井正大]
一人立の獅子舞
1人で1頭をなし、多くの場合、腹に小型の太鼓をつけて打ちながら舞うが、3頭で1組をなすものと、おもに8頭で1組をなすものとがある。藩主の移封などによって西日本に伝わった例外はあるが、東日本にのみ存在する形態である。
3頭1組のものは、男(お)獅子、女(め)獅子、中(なか)獅子などとよばれる3頭で構成され、「三頭(匹)獅子舞」「風流(ふりゅう)獅子舞」という。道化の獅子あやしが出ることが多い。関東を中心に甲信越、また福島県など東北地方の一部に及ぶ。「ささら」とよぶ土地もあり、夏祈祷として舞われるケースが多い。『幣掛(へいかかり)』『弓掛』『剣掛』などのほか、『女獅子隠し』などという曲目がよく演じられる。普通、笛の伴奏がつき、獅子歌もある。頭は獅子だけでなく、竜、イノシシ、カモシカ、クマなど地域の特性によって一様ではない。
八頭式は東北地方固有である。「獅子踊」または「鹿踊」とも書くが、鹿(しし)はカノシシ(シカ)のシシである。8頭は中立(なかだち)と雌ジシのほか6頭の側(がわ)ジシからなる。岩手県奥州(おうしゅう)市の「梁川(やながわ)鹿踊」のように、大ぶりの締太鼓を下腹部につけて打ちながら踊る太鼓踊型と、同県遠野(とおの)市の「青笹(あおざさ)獅子踊」のように、身体の前面に大きな幕をかけてそれを翻して踊る幕踊型に大別される。後者では太鼓打ちを別に置く。頭は権現風にデフォルメされたものがほとんどで、角(つの)は太鼓踊型が本物の鹿の角を、幕踊型が板の作り物を用いる。円陣や方陣を形づくって踊り、シシ歌もあり、やはり『雌ジシ隠し』の曲がある。盆や年忌供養に踊られることが多い。
一人立は古い資料に乏しく、歴史を特定しにくい。『万葉集』巻16の「乞食人詠(ほかいびとのうた)」などにかすかな根拠が求められ、『北野天満宮御祭絵巻』によって室町期の存在が確認される程度であるが、今日の一人立との関連を論証するに至らない。有名な新潟県月潟(つきがた)村(現新潟市南区)の「角兵衛獅子」も、もともと二人立か一人立か不詳である。太神楽系の獅子舞は陰陽道(おんみょうどう)の、山伏神楽系の権現舞と一人立の獅子舞は修験道(しゅげんどう)の、俗聖(ぞくひじり)たちが唱導した可能性が強い。
なお、獅子舞(二人立)、あるいはこれに準ずる芸能は、中国、朝鮮をはじめ東アジアの各地に伝承している。
[西角井正大]
『「民俗芸術三ノ一・獅子舞号」(1930/民俗芸術の会復刻『民俗芸術5』所収・1973・国書刊行会)』▽『古野清人著『民俗民芸双書32 獅子の民俗』(1968・岩崎美術社)』▽『本田安次著『延年』(1974・木耳社)』
改訂新版 世界大百科事典 「獅子舞」の意味・わかりやすい解説
獅子舞 (ししまい)
獅子頭(ししがしら)(おもに木彫)をかぶって舞い,踊る民俗芸能。日本の芸能の中でもっとも古い歴史をもち,また様式や芸態の変化の少ないものである。猪(いのしし),鹿(かのしし)など獣類の頭をつける獅子舞は,《古事記》には弘計(おけ)王が鹿の角を捧げて舞ったこと,《万葉集》には鹿擬態を示唆する歌がある(後述)など,その来歴はきわめて古い。一方,獅子は古代の日本人にとって未見の動物であり,最強の獣との伝聞的認識と,仏教浄土の守護獣として悪霊を払う霊獣という信仰的認識により早くから広く国民的支持を得ていたと考えられる。獅子舞は広く全国的に分布するが芸態により〈二人立ち〉と〈一人立ち〉に大別される。獅子舞の系譜は図を参照。
二人立ち
二人立ちは頭と前脚をなす者と尻尾と後脚をなす者と2人で獅子1頭を形づくる。これは遅くとも7世紀初頭の推古朝までには伎楽の一部として朝鮮半島を経由して渡来したものと考えられ,伎楽獅子ともいう。伎楽より50年遅れて伝来した舞楽でも獅子舞は行われ,古典芸能においても種々の獅子の芸能を生んだ(《獅子》)。現存するもっとも古い獅子頭は正倉院御物の木彫128号で天平勝宝4年(752)の墨銘があり,今日のいかなる獅子頭より立派である。古い時代の二人立ち獅子の胴は五色の毛で飾られていた。それが縫いぐるみ式であったか,胴となる幌布に毛を配したものか不明である。《信西古楽図》には中国式の縫いぐるみ獅子が描かれ,《年中行事絵巻》には幌布にいささか毛を配したものが描かれている。今日もっとも多く用いられているのは幌布にまだら毛模様を配したものである。獅子のたてがみの図柄を配したものもある。
二人立ちの獅子舞は祭礼のお練りや田楽(でんがく)にも舞われるが,獅子神楽と呼ばれる太神楽(だいかぐら)や山伏神楽にもっとも定着した。太神楽は獅子舞による祈禱と余興としての曲芸(散楽(さんがく))からなるもので,三重県桑名市太夫町に本拠を置く伊勢太神楽と,もと尾張熱田に出て徳川家の江戸入府に伴い江戸太神楽となった丸一(まるいち)が代表的な存在である。全国の悪魔払いや豊年祈願などの二人立ちの獅子舞はたいてい太神楽の獅子舞に入る。このほか虎頭をつける虎舞などもある。沖縄の獅子舞は後代の伝来と思われるが縫いぐるみ式である。また数人から十数人という大獅子もある(静岡県掛川市)。東北の早池峰(はやちね)神楽などの山伏系神楽では独特の形の獅子頭を権現と崇(あが)め,祈年(としごい)や火伏せの祈禱として舞わせる。しかし尻尾役は胴幌の外に出て幌の端を持つにすぎず,時に太神楽の獅子舞に見られるような動物擬態的演技はない。
一人立ち
一人立ちの獅子舞は1人で1頭をなす。頭上に獅子頭をいただき,腹に羯鼓(かつこ)や腰鼓をつけた立ち姿勢のもので,基本的には東日本にのみ見られる。三匹(頭)獅子舞と鹿踊(ししおどり)があり,三匹獅子舞は関東地方や福島県,奥羽山脈の西側に若干散在し,3匹が1組を形成する。鹿踊は岩手県を中心に奥羽山脈の東側に分布し,8頭1組が多い。愛媛県の宇和島地方には同形式の八鹿(やつしか)踊がある。一人立ちの獅子は腹につけた太鼓を自身で打ちながら踊るが,歌方が,あるいは獅子自身が獅子歌として風流(ふりゆう)歌を歌うので風流獅子舞ともいわれる。一人立ちの獅子舞の来歴については二人立ちほど明らかではない。《万葉集》に鹿擬態を示唆する歌(3884~5番)があり,鹿踊式の何らかの芸能があったことが想像される。鹿踊は平安初期空也上人に始まる(岩手県花巻市の旧東和町落合)とか,慶長年間(1596-1615。宮城県栗原市の旧一迫(いちはざま)町金田)とかいい,三匹獅子舞では延喜年間(901-923。栃木県宇都宮市の旧上河内町関白)とか,天正年間(1573-92。埼玉県鴻巣市原馬室)とかの伝えがある。これらは念仏や修験や陰陽道(おんみようどう)の俗聖が唱導した形跡が伝書や口碑などによってうかがわれる。盆の供養,夏祈禱,雨乞いなどに踊られることが多く,三匹獅子舞では獅子頭のほか,地理的地域的条件により竜,猪,カモシカ(鹿),熊形などの頭がある。なお新潟県の角兵衛獅子は二人立ちと一人立ちが習合したものと思われる。
執筆者:西角井 正大
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「獅子舞」の意味・わかりやすい解説
獅子舞
ししまい
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「獅子舞」の意味・わかりやすい解説
獅子舞【ししまい】
→関連項目桶胴|門付|ささら(楽器)|獅子
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「獅子舞」の解説
獅子舞
ししまい
獅子の被り物をかぶって行う芸能の総称。悪霊払いの芸能だが,麒麟(きりん)・猪・鹿の被り物をつけるところも多い。正月,盆,春秋の例祭などに舞われる。日本の民俗芸能の約7割は獅子舞であるともいう。大別して,一つの獅子頭を1人がかぶって舞う1人立ち,2人以上が入って舞う2人立ちの2系統がある。1人立ちの獅子は神奈川県を境に東日本に,2人立ちの獅子は全国的に分布する。2人立ちは伎楽の系統をひくものといわれる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
日本文化いろは事典 「獅子舞」の解説
獅子舞
出典 シナジーマーティング(株)日本文化いろは事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の獅子舞の言及
【雨乞踊】より
…この種の芸態の踊りは,さまざまの飾り物を身につける風流(ふりゆう)系の踊りであり,〈太鼓踊〉〈鉦踊〉〈念仏踊〉などがこれにあてられる。また,竜神が雨を呼ぶという信仰から,獅子頭を竜頭に見たて獅子舞を雨乞踊として踊ったり,竜頭舞を演じたりするところも関東にはある。一般に地域全体で関与することが多く,その組織も大規模で氏神の境内のほか水辺や山頂で踊る。…
【沖縄[県]】より
…芸能化したものでは,八重山列島に多い弥勒踊があるが,これはニライから稲,アワをもたらす弥勒のおとずれを歌と踊りで示すものである。また全域的にさまざまの祭りに登場する獅子舞も,遠くから来訪して災厄を払い豊穣をもたらすと信じられた神の芸で,シュロなどの繊維で編んだぬいぐるみの中に2人の踊手が入ってデイゴの獅子頭を振りまわしつつ豪快に踊る。その他祭りをにぎわす芸能で全域的に行われるものに棒術,棒踊の類があるが,棒術は真棒(まあぼう),組棒などといって,2人1組の男が三尺棒,六尺棒などを激しく打ち合わせるもの,棒踊はそれの舞踊化で,土地によって赤毛をかぶって曲技を演じたりする。…
【行道面】より
…来迎会の形式によっては地蔵,竜樹という僧形の面や阿弥陀如来の面,持幡先導役の天童面なども使用する。なお,神社の祭礼において神幸の先導に獅子舞と王舞を伴う場合があり,これに使用する獅子頭と王舞面(鼻高,鼻ノ王,王ノ鼻)も法要の場合の師子の一群と同じ系統の仮面と考えられるので,この種類に含めたり,追儺(ついな)や鬼追い(鬼走り)などの会式に用いられる鬼面もこの呼称によってまとめられることが多い。その題材は仏教の神格が多いし,技法的には同じ時代の舞楽面に共通するもので,作者はふつう仏師と考えられ,表現の特色はその時代の仏教彫刻に通ずる。…
【獅子】より
…(1)伎楽・舞楽の曲名および役名とその演技 〈師子〉と記した例が多い。ともに伝承は絶えているが,民俗芸能の獅子舞や鹿踊(ししおどり),能の獅子舞,近世邦楽や歌舞伎舞踊の獅子物・石橋物など,日本芸能史における獅子の芸能の淵源を示すものと考えられる。伎楽の獅子は,行道の先導役,治道(ちどう)に続いて登場し,悪魔払いの役目をつとめたとみられる。…
【銅鑼】より
…歌舞伎で縁を打つときは細桴を用いる。盤の直径30cmくらいから大小あり,歌舞伎囃子,明清楽,民俗芸能,寄席などでも用いられるが,民俗芸能では長崎の唐子踊(からこおどり)(獅子舞),沖縄の打花鼓(たーふあーく)や獅子舞など中国的な芸能に使用することが多い。多数のいぼを打ち出した疣銅鑼(いぼどら)と呼ぶ小型のものもある。…
【虎舞】より
…民俗芸能。獅子舞の一種であるが,虎の頭(かしら)をつけ,1頭に2人入って舞う二人立ちである。岩手県陸前高田市広田町の〈梯子(はしご)虎舞〉は,虎が大小の太鼓と笛の囃子ではしごを駆けのぼり,サブと称するあやし2人も扇と造花を持ってはしごにのり,アクロバティックな振りを見せる。…
【梯子乗り】より
…これには〈大亀〉〈遠見〉〈邯鄲(かんたん)夢の手枕〉などの型がある。千葉県君津市の〈鹿野山梯子獅子舞〉や岩手県陸前高田市の〈梯子虎舞〉のように,はしごは二人立ち系の獅子舞にもとり入れられている。歌舞伎の《蘭平物狂》では殺陣(たて)の型の一つになっている。…
【風流】より
…室町時代後期の風流踊を支えた層と,当時の能・狂言を享受した層とは共通で,風流踊の趣向には能の曲が転用され,その入破(いりは)(キリ)が踊りの中で演じられたことも多い。
[民俗芸能の風流]
京都の祇園会の山鉾,日立市神峰神社の〈日立の風流物〉に代表される作り物の風流はもとより,風流踊の系譜を引く太鼓踊・羯鼓踊(かつこおどり)・花踊・雨乞踊,囃子物の伝統である鷺舞などの動物仮装風流,胸に羯鼓をつけた一人立ちの獅子舞・鹿踊(ししおどり)をはじめ,念仏踊(踊念仏)や盆踊など,全国の民俗芸能には風流の精神を受け継いだ芸能が多い。民俗芸能を分類する場合,それらを一括して〈風流系芸能〉と称するが,その芸態は一様ではない。…
※「獅子舞」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...