デジタル大辞泉 「蛇」の意味・読み・例文・類語
へび【蛇】
[類語]
じゃ【蛇】[漢字項目]
 〈ジャ〉
〈ジャ〉1 へび。「蛇身/大蛇・毒蛇」
2 へびの形に似たもの。「
 〈ダ〉へび。「
〈ダ〉へび。「 〈へび〉「海蛇・毒蛇・
〈へび〉「海蛇・毒蛇・[難読]
 〈ジャ〉
〈ジャ〉 〈ダ〉へび。「
〈ダ〉へび。「 〈へび〉「海蛇・毒蛇・
〈へび〉「海蛇・毒蛇・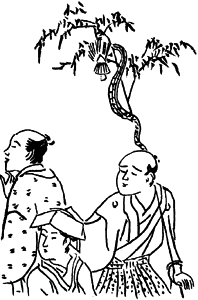
上代には「へみ」と呼ばれていたが、平安時代に「くちなは」が現われ、「へみ」と共存した。
平安時代には「へみ」とともに無毒の蛇の総称であった。「へみ」はすでに「仏足石歌」などの資料に見えるが、「くちなは」は平安以降の和文脈で用いられることが多い。


 、乎路知(をろち)〔名義抄〕委蛇 ウルハシ 〔字鏡集〕蛇 ヘビ・クチナハ・ハミ・ヲロチ
、乎路知(をろち)〔名義抄〕委蛇 ウルハシ 〔字鏡集〕蛇 ヘビ・クチナハ・ハミ・ヲロチ 〕に
〕に (ち)の異文として
(ち)の異文として を録している。
を録している。 )djyai、它thaiはもと同字であるが、区別して用いられるに及んで声にも少異を生じた。佗(駄)・駝daiは荷駄を負う意。蛇がまるく身を巻くことから、その形に類したものを它声を以てよぶ。
)djyai、它thaiはもと同字であるが、区別して用いられるに及んで声にも少異を生じた。佗(駄)・駝daiは荷駄を負う意。蛇がまるく身を巻くことから、その形に類したものを它声を以てよぶ。 ▶・蛇亀▶・蛇魚▶・蛇筋▶・蛇穴▶・蛇結▶・蛇交▶・蛇虹▶・蛇行▶・蛇豕▶・蛇師▶・蛇珠▶・蛇章▶・蛇蛻▶・蛇祖▶・蛇足▶・蛇頭▶・蛇年▶・蛇婆▶・蛇皮▶・蛇
▶・蛇亀▶・蛇魚▶・蛇筋▶・蛇穴▶・蛇結▶・蛇交▶・蛇虹▶・蛇行▶・蛇豕▶・蛇師▶・蛇珠▶・蛇章▶・蛇蛻▶・蛇祖▶・蛇足▶・蛇頭▶・蛇年▶・蛇婆▶・蛇皮▶・蛇 ▶・蛇腹▶・蛇蝮▶・蛇竜▶
▶・蛇腹▶・蛇蝮▶・蛇竜▶ 蛇・亀蛇・巨蛇・懸蛇・玄蛇・交蛇・黄蛇・蛟蛇・鉤蛇・斬蛇・珥蛇・修蛇・神蛇・青蛇・双蛇・走蛇・操蛇・戴蛇・大蛇・断蛇・蟄蛇・長蛇・
蛇・亀蛇・巨蛇・懸蛇・玄蛇・交蛇・黄蛇・蛟蛇・鉤蛇・斬蛇・珥蛇・修蛇・神蛇・青蛇・双蛇・走蛇・操蛇・戴蛇・大蛇・断蛇・蟄蛇・長蛇・ 蛇・闘蛇・毒蛇・巴蛇・白蛇・盤蛇・蝮蛇・文蛇・捕蛇・両蛇・竜蛇・弄蛇
蛇・闘蛇・毒蛇・巴蛇・白蛇・盤蛇・蝮蛇・文蛇・捕蛇・両蛇・竜蛇・弄蛇出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報
…ほかに阿形では天神,黒髭(くろひげ),顰(しかみ),獅子口など,吽形では熊坂(くまさか)がある。能面の鬼類では女性に属する蛇や般若,橋姫,山姥(やまんば)などのあることが特筆される。(3)は年齢や霊的な表現の濃淡で区別される。…
※「蛇」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...