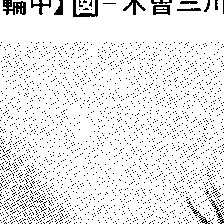精選版 日本国語大辞典 「輪中」の意味・読み・例文・類語
わ‐じゅう‥ヂュウ【輪中】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「輪中」の意味・わかりやすい解説
輪中
わじゅう
濃尾(のうび)平野南西部の木曽(きそ)、揖斐(いび)、長良(ながら)三川の下流の西濃(せいのう)から、伊勢(いせ)(三重県)北東端にかけた低湿な沖積地域にみられる、堤防によって囲まれた集落。囲堤(かこいづつみ)集落ともいう。この地域は古くから数多くの洪水にあい、激しい水害を受けてきた。近世中期の1754、55年(宝暦4、5)の御手伝普請(おてつだいふしん)による薩摩(さつま)藩の三川分流工事(宝暦(ほうれき)治水)や明治以後の三大川改修工事はその大規模対策事業としてよく知られる。この地域では洪水防止策として、集落や耕地(水田)の周りに水除堤(みずよけづつみ)を巡らしたが、その囲堤も「輪中」といっている。そして輪中内の居住者(集落民)は輪中を頼りに水防にあたってきたのみならず、広く輪中内での生産や経済・社会などの生活全般について、「輪中で生きる」との共同体意識のもとに生活し続けてきているのが特色である。輪中は、近世前期(1675=延宝3)の史料に「輪之内」「曲輪(くるわ)」とみえているのがおこりとされるが、この低湿性平野が輪中地域とされるように大規模になったのは近世も中期以後のこととされる。輪中は初めは農民自身の開拓意欲によって小規模ずつつくられていったが、のちには商人の資本投下による中・大規模のものもみられるようになった。
輪中を特色づける景観としては、周りの水除堤をはじめとして、集落の家は輪中内でも高みの地区に屋敷取りがなされている。さらにその一隅はとくに土盛りを高く築いて石垣で囲み、上に倉庫式の「水塚(みづか)」(水屋)が建てられ、洪水時の避難や食料の貯蔵、家財道具の保存にあてられるようにしている。ほかに「掘田(ほりた)」とよばれる特殊な土地利用もみられる。それは、輪中内でおこる内水氾濫(はんらん)による「水損(すいそん)不作」を防ぐために考え出されたもので、輪中内の低湿部を掘り上げて高くした「掘上げ田」と、その土(ど)取りのためにクリーク状に掘り下げられた「掘田」とが交互に配列されているものである。掘田は、第二次世界大戦後から始まる干拓土地改良事業および都市化の進展でほとんど消滅し、現在は見ることができない。隣り合う各輪中は水防上は対立し、近世の幕藩制下では徳川氏親藩の尾張(おわり)藩域と外様(とざま)大名の大垣藩域との間で、また同一藩域内でも上・下流域間やわずかの地盤の高低差によって対立抗争したことが、いまも語られる。しかし明治中後期以後の相次ぐ河川改修工事、ことに第二次世界大戦後の連続堤による治水工法の導入によって洪水が減少し、それに伴って輪中居住者の水防意識が低下し、さらには輪中堤の取り壊しが行われたりして輪中軽視観が漂い始めつつあった。しかし1976年(昭和51)の長良川の洪水に伴う輪中災害ののちに水害危険意識が高くなって、輪中の見直し論がおこり、輪中堤の防災効果、さらに心理的・社会的な輪中堤の有効性が再認識されている。それでも、かつて共同で行っていた水防活動への参加意識は低下している。
輪中に似た防水堤施設は、利根(とね)川下流の水郷、有明(ありあけ)海の干拓地、西ヨーロッパのポルダーをはじめ、ヨーロッパ(イギリス、ドイツ)の干拓地、そしてガンジス(インド)、ブラマプトラ(中国チベット自治区からベンガル湾に注ぐ)およびイラワディ(ミャンマー)、ソンコイ(ベトナム)の各河川流域にもみられる。
[浅香幸雄・菅野峰明]
『伊藤安男・青木伸好著『輪中』(1979・学生社)』▽『伊藤重信著『輪中と高潮』(1982・三重県資料刊行会)』▽『安藤万寿男著『輪中(わじゅう)――その形成と推移』(1988・大明堂)』▽『伊藤安男編著『変容する輪中』(1996・古今書院)』
百科事典マイペディア 「輪中」の意味・わかりやすい解説
輪中【わじゅう】
→関連項目安八[町]|大垣[市]|海津[町]|木曾川|木曾岬[町]|岐阜[県]|墨俣[町]|長島[町]|長島一揆|長良川|濃尾平野|初倉荘|平田[町]|穂積[町]|弥富[町]|養老[町]|輪中堤|輪之内[町]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
改訂新版 世界大百科事典 「輪中」の意味・わかりやすい解説
輪中 (わじゅう)
木曾川,長良(ながら)川,揖斐(いび)川の木曾三川の合流する濃尾平野南西部は古来より洪水常襲地域であった。そのためたび重なる洪水への対応として,集落や耕地を堤防でめぐらした。この囲堤(かこいづつみ)のことを輪中と称した。輪中とはこの囲堤のことだけを意味するのではなく,輪中を単位としてそのなかで生活する人々の水防共同体をも含めた特異な地域社会をも包括して定義されるべきである。この輪中は明治初年には約80を数え,その規模も大垣輪中や高須輪中のような大きなものから,1村だけの小さな十六輪中までさまざまである。分布地域は岐阜県大垣市を中心に南は三重県桑名市の旧長島町,東は愛知県愛西市の旧立田村にまで及び地形的には等高線10mが北限となる。この特異な輪中の発達は洪水多発と結びつくが,その原因は濃尾平野造盆地運動という地殻変動により,木曾川,長良川,揖斐川の木曾三川がこの地域で合流するようになったことと,尾張藩を洪水から防御するため慶長年間(1596-1615)に木曾川左岸に強固な連続堤である御囲堤(おかこいづつみ)を築造したことなどがあげられる。輪中が文献にみられるのは江戸時代前期であり,その大規模な発達をみるのは江戸時代中期のことである。輪中地域を代表する景観として,洪水時の避難場所をも兼ねて高く石積みされた倉,水屋建築がある。土地利用では内水氾濫による水損不作を防止するため,田面を盛土する掘上田(ほりあげた)などがある。また輪中は運命共同体であり隣接する輪中とは利害が相反するため対立抗争することが多く,この水論の熟談和解策として特殊な約定の慣行があった。頻発する洪水に対し人々は治水策を建言するが,それは三川の分流であり,史上名高いのが薩摩藩による御手伝普請宝暦治水であり,完全な分流工事はオランダ人技師ヨハネス・デリーケJohannes Derijkeによる明治の木曾川下流改修工事であった。この結果水害は急減し,一方,明治後半よりの排水機の設置などにより輪中は近代化されていくが,画期的なのは第2次大戦後の干拓土地改良事業による圃場整備と架橋による都市化の進行であった。この変容は輪中無用論となり,輪中堤を取り壊した所も多かった。しかし,1976年9月の長良川決壊により輪中は再認識された。
執筆者:伊藤 安男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「輪中」の意味・わかりやすい解説
輪中
わじゅう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「輪中」の解説
輪中
わじゅう
有名なのは濃尾平野の木曽・長良・揖斐 (いび) 3川合流地点に発達したもので,ふつう「輪中」といえばこの地域をさす。起源は古代末期にさかのぼるが,文書にみえるのは江戸初期からである。農民は輪中単位に強固な共同体を構成。織田信長をしばしば脅かした伊勢長島の一向一揆はきわめて強固だった。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の輪中の言及
【治水】より
…この頃には土豪,農民が地域の治水事業に積極的に参加しはじめた。池の築造に名を残しているのはもとより,山城国西岡の十一郷に灌漑する今井溝の管理・運営は著名であるし,淀川の氾濫から水田を守るため築かれた摂津国島上郡内の犬の縄手(畷),千間縄手(畷),また木曾,長良,揖斐の3河川の乱流から集落と耕地を守ろうとする輪中の形成も,中世に始まっている。さらに大和に多い環濠集落には,堤や井手板を設けて水防を企てているものもある。…
【長良川】より
…上流の山地は多雨地帯で,梅雨期,台風期にはしばしば大洪水をもたらし,たびたび流路も変わり水害を受けた。そのため三角州地帯では洪水の自衛手段として集落や田畑を囲む輪中堤が発達したことで知られる。明治以降も洪水と内水排除の闘いの連続であるが,明治20年代の木曾三川の分流工事完成後は輪中堤もしだいに姿を消しつつある。…
【美濃国】より
…1703年(元禄16)に続く05年(宝永2)の三川をはじめとする美濃諸河川の河道整理(大取払)の国役普請,54年(宝暦4)にはじまる油島締切と大榑川洗堰(あらいぜき)築堤による三川分流の薩摩藩御手伝普請――40万両の出費と藩士その他の犠牲者80余名(宝暦治水事件)――などは,大規模な工事の一つとして有名だが,これらの工事を余儀なくさせた水害多発の原因に,河床の上昇や遊水池の減少,排水の困難さなどがあり,それがおもに新田開発の進行によるものであったということが注目される。
[輪中]
美濃南,西部の水場地帯に特有な治水対策である輪中(わじゆう)は,中世末からはじまり,近世前期には福束(現,輪之内町),墨俣輪中などの形成をみるが,本格的な形成は近世中期以降である。低湿地や遊水池の開拓それ自体が輪中の形成として行われ,そしてそのことが河道の固定化,狭隘化をもたらして水位を上昇させ,ために自然堤防上にあった村々も新たなる築堤や堤防のかさあげを余儀なくされる,ということがより大きな輪中形成の一因と考えられている。…
※「輪中」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...